建設DXでペーパーレス化は可能?メリットや成功のステップを解説
建設

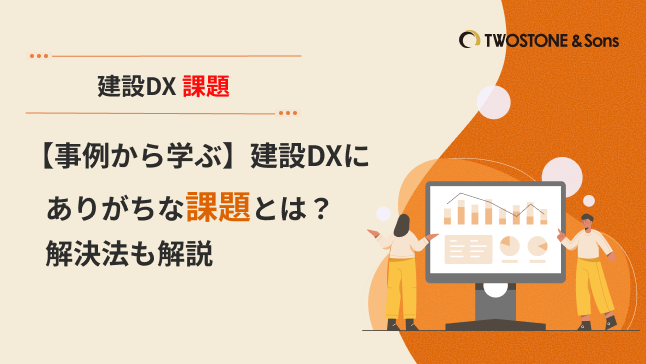
建設DXの推進に成功した企業の具体的な事例を通じて、導入時に直面しやすい課題の乗り越え方や効果的な取り組み方をわかりやすくご紹介します。業務改善や現場の効率化を目指す方にとって、有益な情報が満載です。
建設業界では、慢性的な人手不足や熟練職人の高齢化・非効率な業務フローなどさまざまな課題が積み重なっています。こうした現場の悩みに対する有効な手段として注目されているのが、建設DXです。
DX(デジタル・トランスフォーメーション)の推進によって、施工現場の業務効率を向上させるなど生産性や安全性を高める取り組みが進んでいます。ただし、導入すればすぐに成果が出るわけではありません。現実には、DX推進の過程で多くの企業が壁に直面しているのではないでしょうか。
この記事では、建設DXの基本的な効果と実際に企業がつまずきやすい課題、課題を乗り越えるための考え方を紹介します。今後DXに取り組もうとしている方にとって、失敗を避けるためのヒントを得られる内容です。

デジタル技術を活用する建設DXは、現場作業の最適化や業務の省力化など業界に新しい価値をもたらしています。一方で、導入がスムーズに進まない事例も少なくありません。
ここでは、建設DXの基本的な考え方と課題が生まれやすい背景について整理します。
建設DXは、建設業界における業務や工程・設計・管理などのプロセスにデジタル技術を導入し、効率化と品質向上を図る取り組みを指します。この取り組みによって以下の多様な技術が現場で実用化されました。
実際に従来は紙の図面を使っていた設計や工程管理をクラウドで共有する仕組みに変えることで関係者間のコミュニケーションがスムーズになり、情報伝達の遅延やミスを減らせます。さらに、IoTを活用することで作業員の安全状態をリアルタイムで監視でき、事故の未然防止に役立つといった安全管理面の改善も期待できます。
また建設DXは、単なる技術導入ではなく現場の働き方や管理手法の見直しも促すため、業務の生産性向上やコスト削減に寄与します。総合的な改革が、業界全体の競争力強化につながる点も注目されています。
建設DXが期待されている一方で、導入時に課題が多く発生するのはなぜでしょうか。主な要因は、現場とデジタルのギャップ・組織内の理解不足・IT人材の不足です。
実際にいまの現場では紙ベースの業務に慣れている職人が多く、いきなりデジタルツールを導入すると戸惑いや抵抗が生じることがあります。操作説明や目的の共有が不十分だとせっかくの技術が現場で活用されず、逆に業務の非効率を招くかもしれません。
また、経営層と現場担当者の間でDXに対する意識に差があるとプロジェクト全体が機能しなくなることもあります。DXを進めるためには、単なるツール導入ではなく社内の文化や体制の見直しが必要になります。
さらに、建設業界では専門のIT人材が不足しているケースが多く、外部のパートナー企業と連携しながら進める体制を整えることが重要です。専門知識と現場理解を兼ね備えた外部支援を活用することで、DXの定着がスムーズになります。
建設業界においてDXを推進することは、生産性の向上や安全性の強化・働き方改革の実現などさまざまな側面で大きな意義を持ちます。しかしながら、実際の現場では理想どおりに進まない場面も多く、特有の課題が浮き彫りになりました。
ここでは、建設DX推進時に起こりやすい7つの課題を整理し、その背景や対策のヒントを紹介します。
DX推進において、大きな壁の1つが現場と本部の温度差です。本部側では最新技術を導入しようとする意識が高くても、現場では「実務に役立つのか」「操作が難しいのでは」といった不安が根強く残っています。
実際に、クラウド型の進捗管理ツールを導入しても現場担当者が日々の作業に追われて活用が定着しないケースがあります。このギャップを埋めるには、現場の声を丁寧に拾って現場目線での改善提案を反映したDXにすることが欠かせません。
建設業界では、デジタルツールの使用経験に大きなばらつきがあります。ITに精通した若手と、紙の図面や口頭指示に慣れたベテランとの間でITリテラシーに差が生まれやすいのが現実です。
実際にタブレット端末を支給しても、操作に不慣れな社員が使用を避けてしまう場合があります。このような課題に対応するためには、ツールの導入だけでなく操作説明会やマニュアルの整備・ITサポートの体制づくりを並行して行うことが求められます。
DXを推進するには、現場で使用するネットワークやデバイスの整備が前提となります。しかし、多くの現場では通信環境が不安定だったり古い機器を使っていたりするため、スムーズな運用が困難になるケースがあるので注意しましょう。
例えば、山間部など電波が届きにくい場所ではクラウドツールの活用に支障が出ます。このような問題を回避するためには、モバイルWi-Fiの導入やオフラインでも利用できるアプリの選定など現場環境に合わせたインフラ整備が必要です。
DX推進において見られるもう1つの課題が、断片的なデジタル化です。例えば、一部の工程ではデジタルツールを導入しているのに他の工程では従来どおりの紙運用が残っているなど、全体がつながっていないケースも少なくありません。
この状態ではせっかくのデジタルデータが一貫して活用されず、情報の断絶が発生します。業務全体の流れを俯瞰し、データが一元化される仕組みを整えることではじめてDXの本来の効果が発揮されます。
現場が常に忙しくトラブル対応や納期厳守に追われる中では、DX推進が後回しにされやすい傾向があります。短期的な業務遂行を優先するあまり、長期的な改善が見送られてしまいます。
実際に日常業務が手一杯で、研修や新ツールのテスト導入に割く時間が取れないという声は少なくありません。このような状況に対応するには、DX推進を業務改善の一部として組み込み、既存の業務と並行して進める工夫が重要です。
DXを進める上で、導入すること自体がゴールになってしまうケースも見られます。しかし本来の目的は業務効率や品質向上にあり、データを収集して活用するプロセスこそが重要です。
例えば、現場のセンサーが取得した情報が蓄積されているにも関わらず、それが現場管理や予測分析に活かされていない状況ではDXの価値が半減してしまいます。DX推進後の活用計画と、それを支える人材や体制の整備がカギになります。
建設業界はプロジェクトごとに関係する企業や人材が変わるため、業務の標準化が難しいのが特徴です。現場ごとに使っているツールやフォーマットが異なれば、情報の連携やデータの活用にも支障が出ます。
例えば、ある現場ではBIMを導入していても他の現場では未導入であれば、データのやり取りに手間がかかるだけでなくツールの教育コストも増加します。こうした課題に対しては、一定の業界標準を意識した導入設計や横断的な情報共有の仕組みづくりが必要です。

建設DXを推進する中で、多くの企業が共通して直面する課題があります。しかし、それぞれの課題には具体的な解決策が存在します。
ここでは、建設DXをより効果的に進めるために有効な7つの方法をチェックしましょう。課題に直面している方は、自社の現場や体制に合わせて柔軟に取り入れていくことが重要です。
DXは経営層のトップダウンで進めるだけでは現場に定着しません。現場で実際に働くメンバーが主体的に関与する「ボトムアップ型のアプローチ」が、より実効性のあるDXを可能にします。
例えば、現場作業者が日々の不便や非効率を共有する仕組みを設ければ、現場に即したDX施策が自然に根づくでしょう。現場目線を尊重する姿勢が、社内全体の納得感と推進力につながります。
また、現場主導の取り組みは従業員のモチベーションアップにもつながり、DX推進の継続的な取り組みを支える基盤となります。現場が主体となることで、リアルなニーズに応じた柔軟な対応も可能です。
社内でのITリテラシーのばらつきを解消するには、教育体制と操作のしやすさがカギになります。ツールの導入と同時に、現場で使う人材が自信を持って操作できるような教育機会を設けることが大切です。
例えば、操作マニュアルを動画でわかりやすく解説したりデジタルツールの社内講習会を定期的に開催したりすることで、利用率を高めやすくなります。また、複雑な多機能型ツールよりも、現場のニーズに合ったシンプルなツールの方が定着しやすくなる傾向があります。
加えて、学習ペースに差がある社員にも配慮した個別指導やフォローアップの仕組みを整えることで全体のスキルアップが可能です。継続的なサポートがDX成功のカギとなります。
DX推進には初期投資がかかるため、資金面のハードルを下げる工夫も重要です。国や地方自治体では建設業向けのDX推進補助金やIT導入補助金を用意している場合があり、これらを活用することでコスト負担を抑えられます。
例えば「中小企業デジタル化応援事業」や「ものづくり補助金」などは、機器導入や業務改善のためのシステム開発費用を一部補助する制度として活用可能です。補助金の対象や申請条件は定期的に見直されるため、最新の情報を収集しながら柔軟に対応することが求められます。
また、補助金申請にあたっては専門家の支援を得ることで、スムーズに手続きを進められるケースも多いです。資金面の負担軽減は、より積極的なDX推進を後押しします。
断片的なデジタル化では情報の分断が発生しやすく、かえって業務効率を下げてしまうこともあります。そのため、業務全体の流れを俯瞰して一元管理できる統合型のDXツールを導入することが効果的です。
例えば、工程管理・進捗報告・図面共有・勤怠管理を1つのプラットフォームで完結できるようなクラウドシステムであれば、部署間や現場間の連携がスムーズになります。情報の一元化は、意思決定の迅速化や品質管理の精度向上にも直結します。
さらに、統合システムはデータ分析やAI活用にも対応しやすく、未来の業務効率化や安全管理の高度化につながる可能性が高い点も重要です。
現場の理解を得るためには、まず「負担が減った」と感じてもらう施策を優先的に実行することがポイントです。現場で即効性のある効果を実感できれば、DXへの前向きな姿勢が醸成されます。
例えば報告書の手書き作業をアプリ入力に切り替えるだけでも、日々の負担が軽減されます。写真を撮影するだけで進捗記録が残るようなツールなども現場で好評です。作業の効率化につながるDXから始めることで、無理なく導入を加速できるでしょう。
また現場社員が効果を実感すると、他の業務や機能のデジタル化にも積極的になる傾向があります。負担軽減の成果は、全社的なDX推進の原動力になります。
DX推進に社内の理解と協力を得るためには、ROI(Return on Investment:投資対効果)を具体的に示すことが重要です。単なるコスト増ではなく、将来的な収益性や業務効率の向上が見込めるという説明が必要になります。
例えば、「作業時間を30%削減できるため年間500時間の工数を省略できる」「ミスの再発率が50%減ることで手直しコストが下がる」など、定量的なメリットを数値で示すと説得力が増します。経営層や現場の納得感を得るには、こうした客観的な指標が不可欠です。
ROIをわかりやすく可視化した資料を作成して社内説明会で共有することで、より多くの関係者の共感を呼び、協力体制を強化できます。
すべてを一気にデジタル化しようとすると、混乱や抵抗が起こりやすくなります。そのため、小さな成功体験を積み重ねるスモールステップの進め方が効果的です。
例えば、まずは1つの現場や工程に絞って試験導入を行い、改善点を抽出しながら徐々に全体へ展開していく形が理想です。段階的なアプローチ現場の理解を得やすく、運用面のリスクも最小限に抑えられます。また成功事例を社内で共有することで、他部署への波及効果も期待できます。
加えて、スモールステップを積み重ねることで組織内のDX成熟度が徐々に高まり、最終的には全社一体となったデジタル変革が可能です。継続的な成長が見込める推進方法となります。
建設DXは業務の効率化や人手不足の解消に大きな効果を発揮しますが、導入の仕方によってはかえって混乱を招いたり、現場の負担を増やしたりすることもあります。そのため、DX推進では「いかに新たな課題を生み出さずに進められるか」が重要な視点となります。
ここでは、実行性が高く、現場にも定着しやすい建設DX推進の6つのステップを確認していきましょう。
DX推進の第一歩は、現場が抱える具体的な業務課題を正確に把握することです。経営陣の視点だけでなく、実際に日々の作業に従事する現場の声を丁寧に拾い上げる姿勢が不可欠です。
例えば、「写真付きの報告書作成に時間がかかる」「紙の図面を毎回確認しに戻るのが非効率」といった声が上がれば、業務のどこにボトルネックがあるのかが明確になります。ヒアリングを通じて課題を可視化し、DXの対象範囲を定義することで無駄なツール導入を避けられます。
さらに、現場社員の意見を尊重し反映することでDX推進への抵抗感を減らし、スムーズな推進が可能です。現場の実情に即した課題把握は、全社的な理解促進にも役立ちます。
課題を洗い出した後は、すべての業務に一斉導入するのではなく効果の出やすい部分から小さくスタートすることが成功の鍵です。短期間で成果が見込める業務に限定し、現場の混乱を最小限に抑える配慮が必要です。
例えば、「写真の自動保存・整理」や「作業進捗の簡単入力」など、導入後すぐに現場の負担が軽くなる機能は現場にとっても導入のハードルが低くなります。初期段階での成功体験が現場の信頼を得る基盤となり、次のステップへの意欲も高まるでしょう。
加えて、小さな成功を積み重ねることで社内のDX推進への理解が深まり、より複雑な業務への展開も円滑になります。効果が実感できる部分からの着手が、組織全体のモチベーション向上につながります。
スモールスタートを実施した後は、その効果を定量的に測定し、成果が出たら別の現場や業務に展開する「小さく始めて広げる」アプローチが有効です。このサイクルを繰り返すことで、全社的な定着へとつなげやすくなります。
例えば、ある現場で導入したクラウド図面共有システムが「図面確認の手間を30%削減できた」となれば、その数値と事例を社内で共有し、他現場でも同じ手法を展開できます。成功例を積み上げることで、現場内外の納得感も増すでしょう。
さらに展開にあたっては、各現場の特性や規模に合わせたカスタマイズも重要です。柔軟な対応により導入効果を最大化し、各部署のニーズに即したDX推進が可能となります。
ツール導入と同時に、人材育成とルール整備を並行して進めることも重要です。システムやツールだけを入れても、それを使いこなす人とルールがなければ形骸化してしまうリスクが高まります。
例えば新しい進捗管理アプリを導入する際は、使用方法の研修を行い、どのタイミングで誰がどのように入力するかといった運用ルールを明確に定めましょう。また、定期的な振り返りの場を設けることでツールの活用度合いや運用上の課題をリアルタイムで把握しやすくなります。
加えて、DX推進担当者の育成も欠かせません。専門知識と現場経験を併せ持つ人材が橋渡し役を担い、組織全体のDX理解を深める役割を果たします。
一定の範囲でDXが定着したら、次は個別のツールをバラバラに運用するのではなく、統合的に管理しつつデータを活用するフェーズへと進めることが大切です。情報を一元化し、部署や現場を横断して活かす仕組みが整えば業務効率はさらに高まります。
例えば、進捗管理・勤怠記録・安全点検をそれぞれ別ツールで管理するのではなく、共通プラットフォームに統合することでデータの連携が容易になります。その結果現場の実態把握が速くなり、トラブル発生前の予兆を察知するような予測型の管理も可能です。
また、統合プラットフォームの活用により分析データを活かした経営判断がスピーディになり、全体最適を実現しやすくなる点も見逃せません。
DXは一度推進して終わりではなく、効果検証と改善の繰り返しが欠かせません。運用してみて初めてわかる問題も多く、新たな課題に柔軟に対応する姿勢が継続的な成功を導きます。
例えば、「ツールの操作性が思ったより難しい」「記録の形式が現場に合っていない」といったフィードバックが得られた場合、それを速やかに改良しながら現場に最適化していくことが必要です。また、改善プロセスを通じて次のDX候補となる業務の課題が見えてくるケースもあります。
さらに、改善を積み重ねることで組織のDX成熟度が高まり、社員のITリテラシーも向上します。こうした継続的なPDCAが、建設DXの長期的な成功を支える要素です。
現場と本部の温度差や人材育成・既存業務との整合など、多くの障壁をクリアして建設DXを成功させた企業がいくつも存在します。
ここでは、それぞれがどのように課題を乗り越え、独自の工夫で効果を出したのかをご紹介します。
先進的な施工技術導入で知られる清水建設は、高精度の溶接作業を担う7軸ロボットアーム「Robo‑Welder」を採用しました。これによって波形鋼板などの複雑な曲面部材の加工を人手に頼らず自動化できるようになり、熟練者不足と作業品質の課題解決に貢献しています。ロボットによって安定した溶接品質が維持されるだけでなく、安全性も向上して作業負担が軽減される成果が報告されています。
また、導入前に現場担当者への教育を丁寧に実施して機器に対する拒否反応を最小限に抑え、実際の運用段階では技能伝承の機会とするなど、現場の巻き込みに成功している点が特徴です。現場の意見を取り入れた計画的な導入は、ロボット技術への信頼獲得とともに作業者のスキル向上にもつながっています。
参考:清水建設株式会社
鹿島建設は、段階的なDX推進により既存の事業基盤と整合した形で改善を進めています。例えば、施工データや進捗情報を蓄積し分析に活用する基盤を整え、まずは品質管理の省力化につなげました。そこから安全管理へ展開し、最終的に経営層が使えるダッシュボードへ進化させた流れです。
小さな成果を重ねながら体系化するプロセスは、DXを目的とせず事業強化の手段として位置付ける戦略に他なりません。現場担当者や関係部署との協働体制も整備し、全社的に変革を受け入れやすい環境が構築されました。段階的な実践により業務の混乱を防ぎつつ、着実にDX効果を積み上げています。
参考:鹿島建設株式会社
竹中工務店は、BIM構築とクラウドを連動させた先進的なデジタル活用を推進しています。設計段階から3Dモデルに音響やコスト情報を統合した「Archiphilia Engine」といった独自プラットフォームを実現し、施工前の精度と関係者間の協調性を向上させました。
この成果は、DX企画段階で現場だけでなく設計・調達・管理といった複数部門が共同で試行錯誤したからこそ実現したものです。横断的なチーム編成と現場視点の導入が鍵となり、設計から施工・維持管理に至るサイクルが一貫してスムーズに進むようになりました。
参考:株式会社竹中工務店
参考:株式会社竹中工務店
大成建設の「ロボストップシステム」は、AIとIoT技術の融合によりリアルタイムで危険を察知し、即座に機械や重機を停止できる先進的な安全装置です。現場での人的ミスや不慮の事故を未然に防ぐ役割を果たすため、作業環境の安全性が向上しました。
例えば、作業員が誤って危険区域に近づいた場合でもシステムが迅速に反応して機械を止めるため、重大事故のリスクを軽減します。加えて、操作性や誤検知の軽減に向けた継続的な改善が行われており、現場の作業効率と安全管理のバランスを保ちながら導入することも可能です。
このシステムは単なる安全装置にとどまらず、現場全体の安全意識向上にもつながっている点も評価されています。従来の安全対策では対応しきれなかった瞬時の判断をAIが補完し、働く人々の命を守る重要な役割を果たしています。
参考:大成建設株式会社
大林組のPLMシステムは、設計・施工・維持管理のすべてのデータを一元的に管理することでプロジェクトの全工程を見える化しています。作業の進捗状況や品質管理をリアルタイムで把握でき、問題発生時の迅速な対応が可能となりました。
このシステムでは設計段階での変更内容が即座に施工チームへ共有されるため、現場での手戻りや誤解を減少させています。また、維持管理部門とも情報が連携しているため、建物の長期的な保守計画も効率的に策定可能です。
この統合的なデータ管理は関係者間のコミュニケーションを円滑にし、責任の所在を明確化することで品質向上とコスト削減に大きく寄与しています。全体最適化を目指したデジタル基盤構築の成功例として注目されています。
参考:株式会社大林組

建設DX推進においては、技術そのものよりも「どう進めるか」が成果を分けます。ここで紹介した企業事例に共通するのは、課題を正確に見極め、小さく始めて成果を積み上げ、徐々に規模を拡大していった点です。技術の導入ではなく、現場に定着する仕組みと文化の醸成こそが実効性を生み出すカギを握っています。
DX推進は単なる課題解決ではなく、建設業界の未来をつくる行動でもあります。技術と現場を統合し、現実的な改善を積み重ねていくことで企業価値と競争力の源泉となっていくでしょう。まずは現場を巻き込みながら課題解決の実現性のある施策を講じて、次なる改革へとつなげるのがポイントです。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
