建設DXでペーパーレス化は可能?メリットや成功のステップを解説
建設

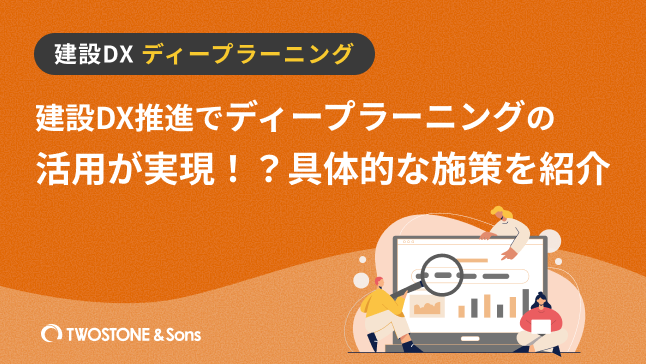
建設DXにおけるディープラーニングの活用方法や注意点について、導入を検討する企業向けにわかりやすく解説します。現場改善や業務効率化に役立つ視点が得られるでしょう。導入時のリスク対策や実践的な活用例も紹介しています。
建設業界は、変革の時を迎えています。人手不足・現場の非効率性・安全管理の高度化といった複合的な課題に直面している中、テクノロジーの活用が急務となっています。特に、AIの中でも高い学習能力をもつディープラーニングの導入は現場に新しい価値をもたらしました。
これまで人の経験や勘に頼っていた業務が、データとアルゴリズムに基づく精緻な分析に置き換わりつつあります。そこで本記事では、建設業界におけるディープラーニングの概要から活用される代表的な2つのアルゴリズムまで詳しく解説します。業務の効率化や精度向上を図りたいと考えている企業担当者の方にとって、実践的なヒントが得られる内容です。

ディープラーニングとは、多層構造の人工ニューラルネットワークを用いて大量のデータからパターンを学習し、高度な判断を行う技術です。建設業界においては、画像解析や音声認識・進捗予測・異常検知など幅広い領域で活用が進んでいます。
例えば、現場写真を自動で解析し、進捗状況や安全違反の有無を検出する仕組みは監督者の負担を軽減しながら精度の高い管理を実現します。また、過去の施工データから遅延やコスト超過の傾向を学習し、プロジェクトのリスク管理にも役立つのがポイントです。
従来のルールベースのシステムとは異なり、ディープラーニングはデータの中に潜む複雑な関連性を自動で見出せます。そのため、建設業のように多変量な要素が絡む環境でも高い精度で意思決定を支援するツールとして注目されています。
この技術を活かすためには、学習に用いるデータの質と量、そして適切なアルゴリズムの選定が欠かせません。
建設業界では視覚情報や時系列データを扱う機会が多いため、特定のアルゴリズムが効果的に機能します。
ここでは、CNNとRNNという2つの主要なアルゴリズムについて、その特徴と活用方法を解説します。
CNNは主に画像データの解析に特化したアルゴリズムです。特徴抽出の精度が高く、対象物の形やパターンを的確に認識できるのが強みです。
例えば、建設現場で撮影された写真からヘルメット未着用や資材の不適切配置などを自動検出するシステムにCNNが利用されています。人間の目では見落としがちな部分も、膨大な画像データを学習したCNNが高い精度で抽出できるため安全管理の質が向上します。
さらに、ひび割れ検出や構造物の劣化診断にも応用されており、点検業務の効率化になるのも特徴です。物理的な目視検査の手間や時間を削減し、より多くの資源を有効に活用できるようになります。
しかし導入時には、現場に合った学習モデルの構築と継続的なデータ更新が求められます。そのため、AI技術に精通した外部のパートナーと連携することでよりスムーズな運用が可能です。
RNNは、時間の流れを含むデータ、つまり時系列データの処理に特化したアルゴリズムです。過去の情報を保持しながら現在のデータを判断材料として活用できるため、動的な現場に適しています。
例えば、施工工程の進捗データや天候・資材搬入の履歴などを基に今後の工程の遅延リスクを予測するシステムに、RNNが利用されています。従来は経験に頼っていた判断も、データに基づいた客観的な予測が可能です。
また、建設機械のセンサーから得られる稼働情報や振動データをリアルタイムで解析し、異常の兆候を察知する仕組みにも応用されています。これにより故障による作業停止を未然に防ぎ、作業の継続性を確保できます。
ただし、RNNは学習が複雑であるため実装には高度な設計力と運用体制が必要です。継続的な精度向上のためには、モデルのチューニングやデータ環境の整備が欠かせません。
ディープラーニングは、建設現場のさまざまな課題に対して多角的な解決策を提供する技術です。現場の可視化や安全性の向上・業務の省力化など、具体的な用途に合わせて活用することで効果が高まります。
ここでは、建設DXにおいてディープラーニングが実際に活用されている代表的な方法を8つ紹介します。
建設現場では、作業員の安全確保が最優先されます。ディープラーニングを活用することで、画像認識によるリアルタイムの安全管理が可能です。
例えば、作業員がヘルメットや安全ベストを正しく着用しているかどうかをカメラ映像から自動判別するシステムが活用されています。異常が検出された場合にはアラートを発信し、迅速な対応を促す仕組みです。これにより、人的ミスによるリスクを減らして管理者の負担を軽減する効果が期待できます。
また、危険エリアへの立ち入りをAIが監視し、ルール違反を即座に検知できる環境づくりも進んでいます。
日々大量に発生する現場写真や設計図面を手作業で整理するのは、大きな負担です。そこでディープラーニングを使えば、こうした情報の自動仕分けと分類が可能です。
例えば、工事区画ごとに写真を分類したり図面から工種別に自動でタグを付けたりする機能が実装されています。視覚的な特徴を学習したAIが画像の内容を正確に識別できるため、ミスの少ない分類が実現します。
これにより後工程での検索性や共有効率が高まり、関係者間の情報連携がスムーズになるのがポイントです。業務効率の向上だけでなく、記録の正確性も担保されます。
老朽化が進むインフラの維持管理において、ディープラーニングを活用した異常検出の仕組みが注目されました。特に、橋梁やトンネル・建物の外壁などの点検作業に大きな変化をもたらします。
例えば、ドローンで撮影した画像をAIが解析し、ひび割れや腐食などの劣化箇所を自動で抽出する手法があります。人の目による検査と比べてより広範囲を短時間で点検でき、異常の見落としも防げるでしょう。
また、過去の検査記録と比較して変化量を自動で算出する機能により、劣化の進行度合いも把握しやすくなります。これにより、予防的な保全計画の立案にも役立ちます。
工事の進捗状況を正確に把握することは、工程管理の質を左右する重要な要素です。ディープラーニングを使うことで、現場の画像や動画から施工の進み具合を自動で認識することが可能になります。
例えば、一定間隔で撮影された写真を基に壁面の立ち上がりや仕上げ工事の進行度を解析し、予定との差異を数値で可視化する機能があります。従来の目視確認や口頭報告に頼る方法よりも、客観性とスピードが向上するのがポイントです。
このような仕組みは、工事全体の見える化を実現してプロジェクト管理の質を底上げします。複数現場を同時に管理する場合にも有効です。
建設現場では、重機や資材の管理が煩雑になりがちです。位置の特定や稼働状況を正確に把握することで、無駄な待機時間や手配ミスを削減できます。
例えば、カメラ映像やセンサー情報を基にAIが重機や資材の種類を認識し、その移動履歴をリアルタイムで追跡するシステムは、その一例です。トラッキング情報はクラウド上で共有され、現場と本社間の認識ギャップを解消します。
また、搬入された資材の数量や配置状況を自動で記録することで、在庫管理や発注業務の最適化にもつながります。
人手不足の解消策として、AIを活用した建設機械の自動運転が注目されています。高精度の制御と安定した動作により、作業効率と安全性の両立が可能です。
例えば、地面の整地作業や掘削作業をAIが自律的に行う建機が開発されています。センサーやカメラで周囲の状況を把握し、マッピングと自動制御により目標の形状を再現します。
現場の特性に応じた学習モデルを構築すれば、複雑な地形でも柔軟に対応可能です。オペレーターの負担を減らしながら、精度の高い施工が実現されます。
設計図面には多くの情報が詰め込まれており、人が読むには時間と労力を要します。ディープラーニングは、図面の自動読解と誤りの検出にも活用可能です。
例えば、設計ミスや規格外の表記をAIが自動でチェックし、担当者にアラートを出すシステムがあります。これにより、設計段階でのヒューマンエラーを最小限に抑えられます。
さらに、構造計算の自動化や法規制との照合など、設計段階での確認作業を効率化する機能も実装可能です。結果として、手戻りの削減と品質向上につながります。
建設現場では複数の作業が並行して進むため、全体をリアルタイムで把握するのは困難です。そこで、AIを活用した施工監視システムが導入されつつあります。
このシステムを導入すると、各作業エリアに設置されたカメラの映像をAIが常時分析し、作業の進行状況や異常の有無を監視できます。事故やトラブルが起きた際には即時通知が行われるため、初動対応が迅速になります。
また作業者の動きや重機の動線も解析することで、作業効率やレイアウトの改善に役立つデータも得られます。現場運営の最適化と、働く環境の安全性向上が両立されます。

ディープラーニングは、建設現場における業務の効率化やリスク管理の高度化に大きく貢献しています。実際に国内の大手建設会社もこの技術を積極的に取り入れ、現場の変革を実現しているのでチェックしてみましょう。
ここでは、ディープラーニングを活用した具体的な企業事例を紹介します。それぞれの取り組みから導入のヒントを得られるはずです。
竹中工務店は、東京大学と共同で空間制御システム「Archiphilia Engine(アーキフィリアエンジン)」を開発し、建築空間の自動生成・評価を行う研究を推進しています。空間設計においてディープラーニングを活用し、人間の感性やニーズに沿った設計案を自動生成するシステムです。
このシステムでは建物内の動線や光の入り方・人の心理的な快適性といった要素を学習データとして取り入れ、それらを反映した最適な空間をAIが提案します。この仕組みにより、建築デザインの初期段階における試行錯誤の負担を軽減し、設計の質とスピードを高めることが可能になりました。
さらに、このシステムは従来のCADソフトとは違って建築家の意図やコンセプトを深く理解し、提案に反映する点が特徴です。感性工学とデータ科学の融合によって、創造性を損なわずに効率化を実現しています。
参考:株式会社竹中工務店
清水建設は、ディープラーニングを活用して建物の電力需要を予測するAIシステムを開発しています。このシステムは、過去の気象データ・建物の使用状況・時間帯別の電力消費量などを基に、将来的な電力の使用傾向を正確に予測するものです。
このシステムを利用することで、猛暑日や使用頻度が高まる週末にどれだけ電力が消費されるかをAIが事前に把握し、最適な電力配分や空調制御を行うことで省エネ効果と快適性の両立を図れます。これにより、エネルギー管理の高度化とともに運用コストの削減にもつながるのがポイントです。
また、この予測データはBEMS(ビルエネルギーマネジメントシステム)と連携し、自動で空調や照明を制御する仕組みとしても活用されています。建物全体のエネルギー効率を最大化しながら、持続可能な施設運営を支援しています。
参考:清水建設株式会社
鹿島建設は、港湾工事や海洋構造物の設計・施工においてCNN(畳み込みニューラルネットワーク)を用いた波浪予測技術の開発に取り組んでいます。この技術は、気象データや海面変動データを基に、海上の波の動きを高精度で予測します。
作業船の運航計画や海上クレーンの作業可否判断において、波浪の影響は大きなリスク要因となります。そこでAIがリアルタイムで波の状態を予測することで作業の可否を的確に判断でき、工期の短縮と安全性向上に直結します。
従来の物理モデルに頼った波浪予測は多くの専門的知識と計算時間を必要としましたが、ディープラーニングによって処理が高速化され、より現実的な対応が可能になりました。実際の現場でも、突発的な天候変化への柔軟な対応がしやすくなっています。
参考:鹿島建設株式会社
ディープラーニングは建設DXにおいて多くの可能性を秘めていますが、導入には慎重な姿勢が求められます。技術の特性や現場との相性を十分に理解し、適切な準備と運用体制を整えることが成功のカギです。
ここでは、導入時に注意すべき5つのポイントについて解説します。
ディープラーニングの精度は、学習に用いるデータの質と量に大きく左右されます。十分な量の多様なデータがなければ、AIの予測や判定に偏りが生じて認識が発生しやすくなります。
例えばひび割れ検出AIを開発する場合、さまざまな照明条件・角度・劣化の度合いを網羅した画像データが必要です。特定の条件に偏ったデータだけでは、実際の現場で正確な判定が難しくなります。
そのため、導入前にはどのような学習データを収集すべきかを明確にし、社内外のリソースを活用してデータ基盤を整備する準備が欠かせません。
ディープラーニングは高い精度を誇りますが、あくまで確率的な判断を行う技術であり、完全無欠ではありません。誤認識が起きた際の影響を最小限に抑える設計が必要です。
例えば、安全管理AIが作業員の保護具未着用を誤って検出し続けると、現場の作業が無駄に中断される可能性があります。逆に、未着用状態を見落とすと重大な事故につながるおそれもあるので注意しましょう。
このようなリスクに備え、AIの出力結果に対して人の目で最終確認を行うなど多重的なチェック体制を構築することが望まれます。システムの信頼性を過信せず、補完的に人の判断を取り入れることが安全性の確保につながります。
建設現場は天候・照度・騒音・振動・粉塵など外的要因が多く、機器の性能や精度に影響を与えることがあります。そのため、導入予定のディープラーニングシステムが現場環境に適応できるかを事前に検証することが重要です。
例えば、画像解析AIが明るい屋外では正常に機能していても、トンネル内や夜間工事では誤動作を起こすケースがあります。照度不足によりカメラ映像の品質が低下すれば、AIの判断にも支障が出てしまいます。
したがって、現場での試験導入やパイロット運用を通じて機器やアルゴリズムの動作状況を入念に確認する段階を踏むべきです。机上での設計だけでなく、実環境での検証を怠らないことが重要です。
ディープラーニングの導入が現場の混乱を招かないよう、現場従事者への丁寧な説明と教育が不可欠です。特に、これまでアナログな作業に慣れてきた職人にとって、新たな技術の導入は心理的な抵抗を生みやすくなります。
実際に「AIに仕事を奪われるのではないか」といった不安を抱える社員も少なくありません。そうした声に寄り添いながら、AIはあくまで作業支援ツールであることを、丁寧に伝えた上で信頼関係を構築する姿勢が求められます。
いきなり全現場に導入するのではなく、まずは一部の作業や拠点で試験的に導入して効果を実証した上で段階的に広げるアプローチが効果的です。小さな成功体験を積み重ねることで、現場全体の理解と協力を得やすくなります。
ディープラーニングでは映像や画像などのデータを大量に扱うため、個人情報やプライバシーへの配慮が求められます。これを怠ると、法的リスクや従業員との信頼関係の毀損につながりかねません。
例えば、作業員の顔が記録された映像データを無断で収集・保存している場合、個人情報保護法の観点から問題となります。データ収集時には目的を明確にし、必要に応じて同意を得ることが基本です。
加えて、取得したデータの取り扱いには厳重なアクセス制限と管理体制が求められます。クラウドに保存する場合でも、通信の暗号化やIP制限などを講じて外部からの不正アクセスを防ぐ体制を構築することが不可欠です。

ディープラーニングは、建設DXを推進する上で極めて有効な技術です。安全性の向上・業務効率の改善・予防的な保全の実現など、さまざまな面で実践的な効果が期待できます。一方で導入には適切な設計と現場理解が必要不可欠であり、慎重に段階を踏んだ展開が求められます。
企業ごとに抱える課題や現場の状況は異なります。そのため、まずは本記事を参考に自社の業務にディープラーニングがどのように貢献できるかを具体的に検討することから始めましょう。そして、パートナー企業と連携しながら安全性と実用性を両立させた導入を目指すことが、持続可能な建設DXの実現につながります。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
