プロトタイプ開発によってプロダクトが生み出された3つの事例を紹介
開発手法
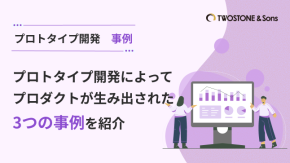

小売業の人手不足や非効率な業務にお悩みの方必見!DXによる業務効率化の進め方を、成功事例を交えて具体的に解説します。在庫管理やバックヤード業務を効率化するツール、導入の4ステップ、費用対効果の考え方までを徹底解説します。


・6万名以上のエンジニアネットワークを活用して課題を解決※
・貴社のDX戦略立案から実行・開発までワンストップで支援可能
※エンジニア数は2026年8月期 第1四半期決算説明資料に基づきます。
「人手不足で日々の業務がなかなか回らない」「在庫管理や発注といった作業に、多くの時間がかかりすぎている」
小売業の現場では、こうした業務効率の悩みが深刻です。この状況を打開する鍵が、小売DXによる業務効率化です。DXと聞くと難しく感じるかもしれませんが、まずは日々の非効率な作業をデジタルで楽にすることから始まります。
この記事では、小売DXを通じてどのように業務効率化を実現できるのか、具体的な成功事例や導入のステップ、課題解決に役立つツールなどを交えながら、分かりやすく解説します。
あなたの会社やお店に合ったDXの第一歩を踏み出すためのヒントがきっと見つかるはずです。ぜひ参考にしてください。
そもそも、なぜ今、多くの小売業でDXがこれほど重要だといわれているのでしょうか。その背景には、業界全体が向き合わなければならない、3つの大きな環境の変化があります。
日本では少子高齢化が進み、働く人の数が減り続けています。特に、多くのスタッフの力でお店を運営している小売業にとって、人手不足は経営の根幹に関わる深刻な問題です。
このような状況で、これまでと同じように人手に頼ったお店の運営を続けるのは、だんだん難しくなっています。採用コストが上がるだけでなく、今いる従業員一人ひとりへの負担が大きくなり、サービスの質が下がったり、やりがいを感じられずに辞めてしまったりする、という悪循環にも陥りかねません。
DXで単純作業を自動化できれば、限られたスタッフの力をより重要な業務に振り向けられます。お客様への丁寧な接客や魅力的な売り場づくりなど、人にしかできない仕事に集中させることができるのです。
スマートフォンの普及は、お客様の情報収集や購買行動を大きく変えました。
いつでもどこでもSNSや比較サイトで情報を得て、最適な商品を選べます。例えば、店舗で実物を見てネットで買う「ショールーミング」や、その逆の「ウェブルーミング」は、今や当たり前の光景です。
また、お客様が求める価値も「安さ」や「機能」だけでなく、自分のライフスタイルに合った提案や、「ここで買ってよかった」と思える特別な体験など、情緒的な満足度へとシフトしています。
このように複雑で個別化されたニーズに応えるには、経験や勘だけでは限界があります。お客様のデータを分析して一人ひとりを深く理解し、その人に合った情報をお届けすることが長く良い関係を築く上で不可欠です。
ECサイトの拡大は、小売業界の競争環境を一変させました。ECサイトは膨大な品揃えと価格競争力を武器に存在感を強めており、経済産業省の調査でも市場規模の拡大傾向は明らかです。
このような状況で、実店舗が価格や品揃えだけでECサイトと勝負するのは得策とはいえません。お客様に選ばれ続けるためには、ECサイトにはない独自の価値提供が不可欠です。
例えば、専門知識を持つスタッフによる親身なアドバイス、商品を実際に試せる安心感、店舗空間を活かしたイベントなどが挙げられます。
さらに、ネットと店舗を連携させ、新しい買い物体験を創出するOMO(Online Merges with Offline)戦略も重要です。DXは、こうした実店舗ならではの強みを最大化し、競争優位性を築くための強力な土台となります。
出典参照:令和5年度デジタル取引環境整備事業(電子商取引に関する市場調査)|経済産業省

DXを導入することで、具体的にどのような仕事が楽になり、効率的になるのでしょうか。このセクションでは、特に効率化の効果が期待できる代表的な5つの業務について、分かりやすく解説します。
在庫の管理は、小売業の利益に直接つながるとても重要な仕事です。
これまでは発注を経験と勘に頼ることが多く、需要の変化にうまく対応できないという課題がありました。その結果、在庫が足りなければ販売チャンスを逃し、多すぎれば廃棄ロスが発生するといった問題にもつながっていたのです。
こうした課題を解決するには、在庫管理システムやAI(人工知能)による需要予測ツールの導入が効果的です。POSレジの売上データや天気などの情報をもとにAIが需要を予測し、最適な発注数を自動で算出してくれます。
これにより担当者の負担が減り、人為的なミスも防げます。さらに、RFIDという電子タグを使えば、検品や棚卸し作業も一瞬で完了し、在庫管理の正確性と効率を飛躍的に高めることができます。
お店の運営において、お客様からは見えないバックヤードでの仕事は、多くの時間と人手がかかる領域です。商品の検品、伝票処理、品出し、売上報告など、その仕事内容は様々です。
これらの裏方仕事が非効率なままだと、従業員は本来力を入れるべき接客や売り場づくりに十分な時間を割くことができなくなってしまいます。
DXは、こうしたバックヤード業務を自動化し、効率化する上で大きな助けとなります。例えば、ハンディスキャナやRFIDを使えば検品作業の時間を大幅に短縮できます。報告書や日報の作成・提出は、専用アプリでデジタル化でき、ペーパーレス化と情報伝達の迅速化が図れます。
また、シフト管理システムを導入すれば、複雑なシフト作成を自動化し、管理者の負担を軽くすることができます。
レジの行列は、お客様の満足度を大きく下げてしまう原因になります。特に、お店が混み合う時間帯のレジ待ちは、お客様にとって大きなストレスとなり、購買意欲を削いでしまうことにもなりかねません。
この課題を解決する方法として、お客様自身が会計を行う「セルフレジ」や「セミセルフレジ」の導入が進んでいます。これにより、レジ業務に必要なスタッフを減らし、お客様の待ち時間を短縮することができます。
さらに進んだ形として、お客様が自身のスマートフォンで商品をスキャンしながら買い物をする「スキャン&ゴー」型のシステムも登場しています。これはレジに並ぶ行為そのものをなくし、ストレスフリーな買い物体験を提供します。多様なキャッシュレス決済への対応も、会計の迅速化に効果的です。
お客様一人ひとりに合ったサービスを提供するには、データ活用が欠かせません。しかし、情報が店舗やオンラインでバラバラに管理されていると、顧客の全体像を掴むのは困難です。
そこで役立つのがCRM(顧客関係管理)ツールです。これは、お客様の購入履歴や問い合わせ履歴などの情報を一元管理し、良好な関係を築くために必要なツールといえます。
蓄積したデータを分析すれば、顧客ごとの購買傾向などが把握できます。さらに、マーケティング活動を自動化するMA(マーケティングオートメーション)ツールと連携させることで、より効果的なアプローチが可能になります。
例えば「特定商品を買ったお客様に、1ヶ月後に関連商品のクーポンを自動配信する」といった施策を効率的に実行し、お客様に長くファンでいてもらうこと、つまりLTV(顧客生涯価値)向上を目指せます。
チェーン展開する小売業では、本部と店舗間の円滑な情報共有が不可欠です。本部からの指示が全スタッフに正確かつ迅速に伝わらなければ、施策の効果は大きく損なわれます。しかし、電話やFAX、メールでは伝達漏れや解釈のズレが生じがちでした。
そこで有効なのが、ビジネスチャットツールなどの情報共有プラットフォームです。重要な通達を一斉配信し、既読状況を確認することで、確実な情報伝達が実現します。
また、写真や動画も簡単に共有できるため、商品の陳列方法や接客ノウハウといった成功事例を分かりやすく横展開でき、組織全体のスキルアップにつながります。
双方向のコミュニケーションが活発になれば、現場からの改善提案などを迅速に吸い上げ、経営に活かす良い循環も生まれます。
日本国内でも多くの小売企業がDXを進め、素晴らしい成果を上げています。このセクションでは、異なるタイプのお店における3つの特徴的な成功事例を取り上げ、その取り組みと効果を詳しく見ていきましょう。
ドラッグストアチェーンを展開する株式会社ココカラファインでは、全国の店舗から本部への問い合わせ対応業務の効率化を目的に、AIを活用した社内向けチャットボット「ココカラボット」を導入しました。
このチャットボットには、社内マニュアルや過去のQ&Aデータが学習されており、店舗スタッフが質問を入力するとAIがその意図を理解して、関連情報をすぐに回答してくれます。
これにより、店舗スタッフは時間や場所を気にせず必要な情報を自分で見つけられるようになり、問い合わせ対応業務の効率化が実現しました。
出典参照:AIを活用した社内Q&Aシステムの稼働開始~社内の問合せ業務を迅速化~|株式会社マツキヨココカラ&カンパニー
百貨店業界をリードする株式会社三越伊勢丹は、スマートフォンアプリ「三越伊勢丹リモートショッピング」を開発し、2021年3月から提供を開始しました。このアプリを使うことで、お客様は自宅などからチャットやビデオ通話を通じて販売員による一対一の接客を受けられます。
販売員は店頭同様にお客様の要望を聞きながら商品を提案し、気に入ればそのままオンラインで支払いまで済ませることができます。来店が難しい状況でも、店舗と変わらない接客体験を提供することで、顧客満足度の向上につなげています。
出典参照:三越伊勢丹ITグループ会社とGxPが共同で三越伊勢丹リモートショッピングアプリを開発支援|株式会社三越伊勢丹ホールディングス
総合スーパーマーケットを展開するイオンリテール株式会社では、レジ待ち時間の短縮や会計の利便性向上を目的に、お客様自身がスマートフォンなどで商品バーコードをスキャンする「レジゴー(RegiGo)」を導入しました。
お客様は商品のバーコードをスキャンし、買い物かごに入れていきます。最後に専用セルフレジでQRコードを読み取れば、会計がスムーズに完了する仕組みです。買い物中に合計金額を確認できるため、安心して買い物ができるという利便性も評価されています。
また、店舗ではレジ業務の効率化により、スタッフが接客や売り場づくりなど他の業務に注力できるようになりました。
出典参照:イオンリテールは3月より、“レジに並ばない”お買物スタイル「レジゴー」本格展開|イオン株式会社
自社でDXを進めたいと思っても、「何から手をつければいいか分からない」という方も多いかもしれません。DXを成功させるためには、ただ流行りのツールを導入するのではなく、自社の課題に合わせた計画的で段階的な進め方がとても大切です。
このセクションでは、DX導入を進めるための標準的な4つのステップについて解説します。
DXを進める最初のステップは、「現状を正しく知る」ことから始まります。自社の仕事の流れ全体を見渡し、どこに非効率な点や問題があるのかを客観的に洗い出す「業務の可視化」が重要です。
実際、経済産業省が公開している「DX推進指標」でも、DXの出発点は業務プロセスの現状把握と課題特定にあるとされています。
具体的には、従業員に「どんな仕事に時間がかかっていますか?」「どんなことで困っていますか?」とヒアリングやアンケートを行い、現場が感じているリアルな課題を具体的に引き出す作業です。
この段階で一番大切なのは、経営層の視点だけでなく、実際に日々の仕事をしている現場スタッフの声を丁寧に聞くことです。生の情報を集めることで、本当に解決すべき課題の優先順位がはっきりします。
このプロセスを通じて、会社全体で問題意識を共有することが、後のステップをスムーズに進めるための大切な土台になります。
出典参照:DX推進指標(P.2)|経済産業省
現状の課題がはっきりしたら、次に「DXによって、何を、どう良くしたいのか」という具体的な目的とゴールを設定します。
この目的は、できるだけ数字で測れる目標、いわゆるKPIとして設定することが望ましいです。「目標がどれだけ達成できたかを測るための具体的な数値目標」のことだと考えてください。
例えば、「在庫の廃棄ロスを、今の半分にする」「バックヤード業務にかかる時間を、1日あたり1人1時間減らす」といった具体的な目標です。
設定した目的とゴールは、組織のメンバー全員で共有する必要があります。「なぜ私たちはDXに取り組むのか」という未来のイメージを共有することで、DX推進に対する従業員の理解と協力を得やすくなります。
設定した目的を達成するための手段として、最適なデジタルツールやシステムを選びます。世の中には様々なツールがあるため、「自社の課題解決に本当に役立つか」「現場のスタッフが直感的に使えるか」といった視点から、慎重に比較検討することが大切です。
そして、本格的に全社で導入する前にまず一つの店舗や特定の部署に限定して、試験的に導入する「スモールスタート」を実施することを強くおすすめします。
スモールスタートには、思いがけない問題点を早く見つけられる、導入効果を小さな範囲で確かめられる、現場の不安や抵抗感を和らげることができる、といった多くのメリットがあります。
この段階で得られた小さな成功体験や運用のノウハウは、その後の全社展開をスムーズに進めるための貴重な財産になります。
スモールスタートで導入したツールの効果を、ステップ2で設定した目標(KPI)に基づいて客観的に測定・評価します。導入する前と後のデータを比べて、目標をどれくらい達成できたか、かけた費用に見合う効果があったかを分析します。
もし期待した効果が出ていない場合は、その原因を探り、ツールの設定や使い方を見直すといった改善策を考えます。効果がきちんと確認でき、運用上の課題も解決できたら、いよいよ全社へと展開していきます。
全社に広げる際には、スモールスタートで得た知識を活かして、誰にでも分かるような詳しい導入マニュアルを作ったり、従業員向けの使い方研修会を開いたりすることが成功の鍵となります。

小売業の様々な課題に対応するため、色々な種類のDXツールが提供されています。このセクションでは、日々の業務効率化に役立つ代表的なツールのカテゴリーについて、その役割と機能を紹介します。
在庫管理システムは、商品の入荷や出荷、在庫の数、保管場所といった情報をまとめて管理し、在庫を最適な状態に保つ手助けをするツールです。
特に、商品を販売した時点の情報を管理するPOSレジと連携させることで、その効果は最大限に発揮されます。商品が一つ売れるたびに、その情報がリアルタイムで在庫データに反映されるため、いつでも正確な在庫状況を把握できます。
これにより、品切れによる販売チャンスのロスや、在庫の持ちすぎによるコスト増加のリスクを減らすことができます。
最近では、AIが需要を予測する機能を持ち、発注業務そのものを自動化する高度なシステムも登場しています。
シフト・勤怠管理システムは、従業員のシフト作成や出退勤の記録、給与計算といった労務管理の仕事を効率化するためのツールです。小売業のように、多くのパート・アルバイト従業員がいて、働き方が複雑になりがちな業種では、その導入効果は特に大きいといえます。
従業員の希望の休みや働ける時間、必要なスキルといった条件を考えながら、最適なシフトを自動で作成する機能は、店長のシフト作成にかかる膨大な時間を削減します。
また、ICカードや指紋認証、スマートフォンアプリで出退勤を記録する機能は、間違いや不正を防ぎ、正確な労働時間の管理を可能にします。
CRM(顧客関係管理)は、お客様の情報や購入履歴、問い合わせ内容などを統合的に管理し、お客様と良好な関係を築き、維持していくための考え方、およびそれを支援するツールを指します。お客様のデータを分析することで、一人ひとりのニーズや好みを深く理解し、その人に合わせたアプローチを実現します。
一方、MA(マーケティングオートメーション)ツールは、メール配信やキャンペーンの実施といったマーケティング活動の一部を自動化します。
これら二つのツールを連携させることで、「優良顧客のグループに対して、誕生月に特別なクーポンを自動で送る」といった、効果的で効率的なマーケティング施策を実行することが可能になり、お客様のロイヤルティ向上に貢献します。
ビジネスチャットや情報共有ツールは、組織の中での円滑なコミュニケーションを促し、情報伝達のスピードと正確さを高めるためのプラットフォームです。本部から全店舗への一斉連絡や、特定のプロジェクトチーム内での情報共有、店舗スタッフ間の業務連絡など、様々な場面で活用されます。
従来のメールや電話と比べて、リアルタイム性が高く、グループでの議論も簡単に行えます。また、文書ファイルや写真、動画などの資料も手軽に共有できるため、業務マニュアルをデジタル化したり、成功事例を他の店舗に広めたりするのにも役立ちます。
これにより、組織全体の知識レベルの底上げと、迅速な意思決定をサポートします。
DXの推進を考える上で、費用の問題は避けて通れません。ツールの導入には初期費用や継続的な運用費用がかかりますが、その価格はツールの種類や機能によっても大きく異なります。
多くの小売DXツールは、SaaS(Software as a Service)と呼ばれるインターネット経由のサービスとして提供されており、サブスクリプション(月額または年額)で利用するのが一般的です。
課金モデルにはいくつかの種類があります。代表的なものとしては、利用するユーザー数に応じて料金が決まる「ユーザー課金」、サービスの利用量に応じて課金される「従量課金」、機能や規模ごとにプランを分けた「プラン課金」などがあります。
また、小売業では業態に応じて、利用店舗数に応じた課金やID管理を軸にした課金体系が採用されることもあります。ただし、これらの料金体系はツールや業種によって異なるため、導入前にしっかりと確認しておくことが大切です。
DXツールの費用は、機能の専門性や対象とする企業の規模によって幅があります。
例えば、勤怠管理システムやビジネスチャットツールなどは、比較的低コストで導入できるケースが多く見られます。月額費用も1ユーザーあたり数百円から数千円程度と導入しやすい価格帯です。
一方、在庫管理システムやCRM(顧客関係管理)ツールなど、基幹システムと連携したり、多くのデータを扱ったりする高度なツールは、価格帯が上がります。
機能やサポート体制によって様々ですが、月額数万円からが一般的です。さらに、大規模なカスタマイズやコンサルティングが必要な場合は、費用も数十万円以上になることが珍しくありません。
導入を検討する際は、複数社から見積もりを取り、自社の課題解決に必要な機能とコストのバランスを慎重に見極めることが成功の鍵となります。
DXツールの導入を検討する際には、単に金額が高いか安いかで判断するのではなく、その投資によってどれだけの効果(リターン)が見込めるかという「費用対効果」の視点を持つことが非常に重要です。
これはROI(Return on Investment)とも呼ばれ、「かけた費用に対してどれだけの利益が返ってきたか」を示す指標です。ここでいう「利益」には、廃棄ロスが減るといった直接的なコスト削減だけでなく、業務が効率化されて人件費が抑えられたり、品切れがなくなって売上が上がったり、お客様の満足度が向上してリピーターが増えたり、といった間接的な効果も含まれます。
導入前に、現状の課題によってどれくらいの損失が出ているかを試算し、ツール導入によってそれがどの程度改善されるのかを予測することで、その投資が妥当かどうかを客観的に評価することが可能になります。

DXは、ツールを導入すれば自動的に成功するものではありません。組織全体での取り組みとして、いくつかの重要なポイントを押さえることが、その成否を分けます。
DXプロジェクトを成功に導くための最も重要なのは、その導入目的が組織全体ではっきりと共有されていることです。
経営層が描く「こうなりたい」というビジョンと、現場が抱える「ここが大変」という課題意識が一致し、「なぜ今、私たちはこの変革に取り組む必要があるのか」という問いに対して、全員が同じ答えを持てなければプロジェクトは前に進む力を失ってしまいます。
この目的共有が不十分な場合、DXは単に「ツールを入れること」自体が目的になってしまい、「面倒なことをやらされる」と現場の抵抗を招いたり、せっかく導入したツールが十分に活用されなかったりする大きな原因になります。
「DX実践手引書」にもあるように、定期的な説明会を開くなど、粘り強く対話を重ねることが求められます。
出典参照:DX実践手引書(P.11)|独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
DXの本当の主役は、日々そのツールを使って仕事をする現場のスタッフです。したがって、プロジェクトの計画段階から現場の代表者を積極的に巻き込み、その意見や知恵を反映させることが不可欠です。
現場の仕事を誰よりも知っているスタッフの視点は、ツールの選定や導入プロセスの設計において、机の上だけでは見えてこない実践的な課題を発見し、解決策を見出す上で非常に役立ちます。
また、自分自身が「これ、いいですね!」と納得して選んだツールであれば、導入後も「自分たちが選んだのだから、うまく活用しよう」という当事者意識が生まれやすくなります。
トップダウンの指示だけでなく、現場からの意見を吸い上げる仕組みを作ることが、変化をスムーズに受け入れてもらうための鍵となります。
世の中には、たくさんの機能がついた高性能なDXツールが数多くありますが、自社の課題やお店の規模、従業員のITスキルに見合わない、いわゆる「オーバースペック」なツールを選んでしまうと、かえって現場を混乱させ、定着しないリスクがあります。
大切なのは、流行やブランドイメージに惑わされることなく、「自分たちが解決したい課題は何か」を明確にし、その課題解決に必要十分な機能を備えたツールを冷静に見極めることです。
まずは、特定の課題に特化したシンプルなツールから小さく始め、運用を通じて「これは便利だ」という効果を実感しながら、必要に応じて機能を追加したり、他のツールとの連携を考えたりするのが良いでしょう。段階的なアプローチが、結果的に失敗のリスクを減らすことにつながります。
DXの本当の価値は、ツール導入によって得られるようになった「データ」を活用し、継続的な業務改善や新しい価値創造につなげることにあります。
POSデータ、在庫データ、顧客データなど、DXによって蓄積されるようになったデジタルデータを定期的に分析し、そこから得られる「なるほど、そういうことか!」という気づき(インサイト)を、次のアクションプランに活かす。このサイクルを確立することが重要です。
例えば、データ分析によって「このパンと、この牛乳が一緒に買われることが多い」という傾向が明らかになれば、売り場のレイアウトを変更して隣に並べたり、セット割引を企画したり、といった具体的な施策につなげることができます。
DXは一度きりのプロジェクトではなく、データに基づいた仮説と検証(PDCA)を繰り返し、常に進化し続ける経営活動そのものであると考える必要があります。
この記事では、小売業が抱える様々な課題を「業務効率化」という切り口から解決する手段として、DXを解説してきました。
深刻な人手不足を乗り越え、スタッフがより働きやすい環境を作るためにも、デジタル技術を活用した業務効率化は、もはや避けては通れない道といえるでしょう。業務効率化によって生まれた時間や心の余裕は、お客様へのより良いサービス提供や、新しい価値の創造へとつながっていきます。
大切なのは、DXを「難しそう」「うちには関係ない」と捉えるのではなく、「日々の仕事を少しでも楽にするための身近な工夫」として考えることです。
まずは、あなたの会社の業務の中で「この作業に時間がかかりすぎている」「もっと簡単な方法はないか」と感じる点を見つけることから始めてみませんか。それが、業務効率化へ踏み出すための、最も重要で具体的な第一歩です。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
