金融DXの推進によって叶う勘定系システムの刷新|4つの取り組み例を紹介
金融

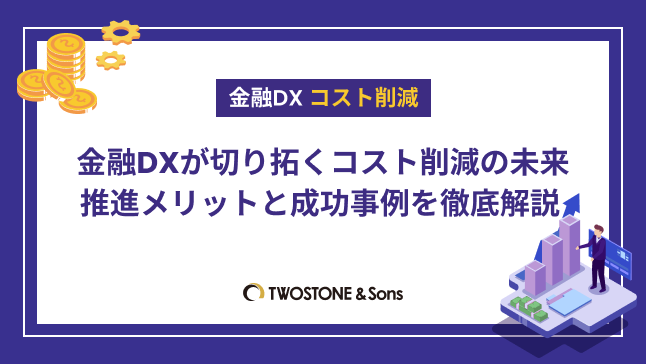
近年、金融業界では急速にデジタル化が進み、DX(デジタルトランスフォーメーション)の重要性が一層高まっています。中でも注目されているのは、業務効率の向上とコスト削減を同時に実現する「金融DX」の取り組みです。
この記事では、金融DXがもたらす5つの具体的なメリット、推進時に立ちはだかる課題と記事後半では、金融業界が実施すべきDX施策を具体例とともに紹介し、実際の成功事例からコスト削減につながる実践ポイントを解説します。
 金融業界では、人手不足や低金利の長期化といった構造的課題を背景に、業務の最適化を目的とした金融DXの必要性が高まっています。従来の業務フローに潜むムダや非効率を可視化し、デジタル技術を活用して再構築することで、人件費や運用コストの削減が可能です。限られた人材を有効に活用する手段としても、金融DXは企業の競争力強化に直結する施策として、今後さらに重要性を増していくでしょう。
金融業界では、人手不足や低金利の長期化といった構造的課題を背景に、業務の最適化を目的とした金融DXの必要性が高まっています。従来の業務フローに潜むムダや非効率を可視化し、デジタル技術を活用して再構築することで、人件費や運用コストの削減が可能です。限られた人材を有効に活用する手段としても、金融DXは企業の競争力強化に直結する施策として、今後さらに重要性を増していくでしょう。
金融DX(デジタルトランスフォーメーション)は、その取り組みによって得られるメリットの幅広さから、金融業界全体で今後さらに注目される取り組みです。従来の業務をデジタル技術で再構築することで、顧客体験の向上から業務効率化、コスト削減、さらには新たな価値創出まで、多方面にわたる成果が期待されています。
中でも、「コスト削減の実現」は経営の持続可能性を高める上で重要なテーマとなっており、金融DXがもたらす利点の1つです。
本章では、金融DXの推進によって得られる代表的な6つのメリットをご紹介します。それぞれ、1つずつ詳しく解説していきます。
金融DXの進展により、顧客との接点が多様化し、利便性の高いサービス提供が可能になっています。モバイルアプリやオンラインバンキングにより、時間や場所にとらわれずに金融サービスを利用できる環境が整いました。さらに、AIチャットボットなどの導入により、24時間対応のサポートも実現しています。加えて、取引履歴や行動データを活用したパーソナライズにより、顧客ごとのニーズに即した対応が可能となり、顧客満足度の向上に大きく寄与しています。
金融DXの主目的の1つは業務最適化を通じたコスト削減です。従来の紙ベース・手作業中心の業務から、クラウドシステム・AI・RPAを活用したデジタル環境への移行により、以下の効果が得られます。
金融DXはシステム更新にとどまらず、企業全体のコスト構造を根本から変革する重要な取り組みです。
金融業界では、人手不足や低金利の長期化といった構造的課題を背景に、業務の最適化を目的とした金融DXの必要性が高まっています。従来の業務フローに潜むムダや非効率を可視化し、デジタル技術を活用して再構築し、人件費や運用コストの削減をすることができます。限られた人材を有効に活用する手段としても、金融DXは企業の競争力強化に直結する施策として、今後より一層重要性を増すでしょう。
金融業界では、顧客の資産や情報を扱うため、セキュリティの確保が重要です。金融DXの推進により、新たな技術が活用されています。生体認証や多要素認証の導入で不正アクセスのリスクを低減し、AIによるリアルタイム検知やブロックチェーン技術で信頼性の高いサービス提供が可能になりました。金融DXは利便性向上にとどまらず、安全な金融環境の実現にも貢献しています。
金融DXは、分散していた顧客情報や取引データの一元管理を可能とし、AIやビッグデータ分析との連携によって多様な付加価値を生み出します。
具体的には、顧客の属性や取引履歴に基づくパーソナライズ提案の精度向上、データ主導の与信判断や信用スコアの高度化、新たな市場ニーズの予測による商品開発など「データを資産とする」発想は、金融機関の競争力強化に直結します。業務効率化にとどまらず、サービスの高度化やビジネスモデルの革新を実現する鍵として、データ活用は金融業界における中核的要素となるでしょう。
金融DXによって、データの即時取得と分析が可能になり、スピーディーな意思決定が実現されています。従来の紙業務や手作業に伴うタイムロスやヒューマンエラーは軽減されました。
たとえば、経営指標を可視化するダッシュボードやAIによる異常検知により、状況を素早く把握できるようになり、営業現場でもリアルタイム情報を活かした提案や判断が強化されました。
DXは意思決定の精度を高め、経営と現場の連携を一段と強固にしています。
金融DXには多くのメリットがある一方で、実際に現場レベルで推進していくにはいくつかの壁が存在します。
ここでは、金融DXを推進する上で立ちはだかる4つの主要な課題と、その対策について解説します。事前にこれらのポイントを把握しておくことで、スムーズかつ効果的なDXの実行が可能です。
それでは、これらの課題について詳しく見ていきましょう。
多くの金融機関では、長年にわたって運用されてきた基幹系システムが依然として稼働しており、新しいデジタル技術との互換性に課題を抱えています。これらのレガシーシステムは、保守にコストがかかるだけでなく、新しいサービスや外部ツールとの連携を阻む要因にもなりえます。
この課題に対しては、段階的なシステム移行やクラウド環境の活用が有効です。たとえば、まずは周辺業務からクラウド化を進め、段階的に基幹業務へと範囲を広げる「ハイブリッド型移行」が現実的なアプローチとされています。
DXを推進するには、ITスキルを持つ専門人材の存在が不可欠ですが、金融業界ではその人材確保が大きな課題です。特に地方銀行や中小金融機関では、社内にデジタル人材が乏しく、外部依存に頼らざるを得ないケースも多く見られます。
この問題への対応策としては、外部パートナーとの連携強化や、社内教育による「リスキリング(再教育)」の推進などがあり、兼業や副業による外部人材の活用といった柔軟な人材戦略を取り入れることで、人的資源の幅を広げる動きも加速しています。
システム開発や運用体制の構築に一定の初期投資が必要です。特に短期的な収益改善が求められる中で、コスト面の不安からDXの優先度を下げてしまう企業も少なくありません。
こうした懸念を払拭するためには、スモールスタートによる段階的導入が有効です。まずは一部業務に限定して試験導入を行い、投資対効果を可視化した上で全社展開を検討することで、経営層の理解と納得を得やすくなります。また、補助金や助成金制度を活用した初期負担を軽減する工夫も重要です。
DXは単なるツールの導入ではなく、業務の在り方や組織の意識そのものを変革する取り組みです。そのため、「前例がない」「変化に対する抵抗感が強い」といった文化的な壁が、DX推進を阻む要因となることもあります。
この課題に対しては、トップダウンとボトムアップの両面からのアプローチが欠かせません。経営層がDXの必要性を明確に発信しつつ、現場には「自分ごと化」してもらえるような仕組みやインセンティブを整えることが、組織全体の意識改革を促すポイントとなります。
 金融業界では、低金利や規制強化、競争激化といった外部環境の変化により、利益率の圧迫が続いています。その中で、デジタルトランスフォーメーション(DX)によるコスト削減は、多くの企業にとって早急に取り組むべき課題となっているでしょう。
金融業界では、低金利や規制強化、競争激化といった外部環境の変化により、利益率の圧迫が続いています。その中で、デジタルトランスフォーメーション(DX)によるコスト削減は、多くの企業にとって早急に取り組むべき課題となっているでしょう。
ここでは、金融業界における代表的なDX施策と、それによって実現できるコスト削減の具体例をご紹介します。業務効率化や顧客満足度の向上にもつながるこれらの施策は、今後の金融ビジネスの競争力強化に欠かせないものです。
チャットボットは、金融機関における顧客対応の自動化を支える重要な仕組みです。FAQの対応や口座情報の照会などを24時間体制で担うことで、オペレーターの負担を軽減しました。これにより、人件費の圧縮と業務の効率化が実現できます。
さらに、蓄積されたチャットログの分析から顧客ニーズを把握でき、サービス改善にもつなげられます。コスト削減だけでなく、顧客満足度の向上にも寄与する仕組みといえるでしょう。
金融業界では、口座開設や帳票作成など定型業務が多く、ミスや負担が大きな課題となってきました。
RPAは、こうした繰り返し作業を自動化し、入力・照合・レポート作成などを正確かつ高速で処理できます。
RPAの導入により、残業の削減や内部統制の強化にも寄与します。
さらに、社員が戦略的業務に専念できる環境が整い、組織全体の生産性向上にもつながるでしょう。
キャッシュレス化やデジタル通貨の台頭は、金融機関にとって業務改革の契機となりました。ATM運用や現金輸送コストの削減に加え、リアルタイムでの取引分析によって意思決定の精度も高まっています。
さらに、CBDCやステーブルコインといった新たな通貨への対応が求められ、非接触決済は顧客接点の拡充にも寄与しています。これらは、将来の金融基盤を支える重要な一歩といえるでしょう。
オンプレミス型の金融システムは、物理サーバーの保守や災害対策に多くのコストがかかり、柔軟性にも限界がありました。これに対し、クラウドは必要なリソースを必要な分だけ利用でき、初期投資の抑制と拡張性の両立が可能です。
さらに、自動スケーリングやセキュリティ更新などにより、運用負荷の軽減と安定性の向上が図れます。クラウド基盤は、金融機関にとってコスト最適化と将来の成長を支える中核インフラとなりつつあります。
これまで金融業界のマーケティングはテレビCMやチラシなどマス広告が主流でしたが、ターゲットの行動が多様化する中、費用対効果の最大化が難しくなっています。そこで注目されているのが、顧客データを活用した広告・販促の最適化です。
属性や取引履歴、Web行動などのデータを分析すれば、関心に合ったタイミングで最適なメッセージを届けられ、無駄な広告費を抑えつつ高い成果が期待できます。
さらに、A/BテストやLTV分析などデータドリブンな手法により、施策の継続的な改善が行いやすくなります。戦略的なデータを活用すれば費用対効果の向上だけでなく、顧客とのエンゲージメントを一層深められるでしょう。
金融DXは、コスト削減や業務効率化、顧客満足度の向上といった多くの効果をもたらす可能性があり、その効果を最大限に引き出すためには、単なるツール導入にとどまらず、全社的な取り組みとしての視点が欠かせません。
ここでは、DXによるコスト削減効果を最大化するために押さえておくべき5つの重要なポイントを、初期段階から意識することで、失敗リスクを抑えつつ、着実な成果につなげることが可能になります。
DXによるコスト削減効果を最大化するための5つのポイントについて、解説していきます。
DXによるコスト削減では、「既存業務の前提を問い直す」姿勢が欠かせません。デジタルツールの導入が目的化し、非効率な業務フローをそのままシステム化してしまうと、期待した効果が得られず運用負荷が増す恐れがあります。
失敗を避けるには、まず業務全体を可視化し、重複・無駄・属人化している部分を明らかにしてください。その上で、デジタル技術を活かして再設計すれば、DXの価値が発揮され、RPAやワークフロー管理ツールも、業務の流れを見直せるでしょう。業務改革とテクノロジー活用を一体で進めることが、柔軟で適応力のある組織づくりにつながり、単なる効率化ではなく「業務そのものを変える」という視点が不可欠です。
DXは初期投資や運用体制の構築を伴うため、取り組み前にROIを明確に試算し、経営判断の精度を高める必要があります。業務時間や人件費の削減、エラー率の低下などを定量化し、コストとのバランスを検証することで、施策の妥当性が判断可能になります。また、最悪・平均・最良の複数シナリオでシミュレーションを行えば、リスクの可視化と対策の準備にもつながり、こうした分析により、経営層や社内関係者の理解と納得を得ながら、着実なDX推進が可能となるでしょう。
DXの推進において、初期段階から大規模なシステム変更を行うことは、想定外のトラブルや進行の遅延を招く恐れがあり、こうしたリスクを回避するには、まず小規模な範囲から取り組みを開始する「スモールスタート」が有効です。
特定部門やプロセスを対象とした導入により、効果や課題を早期に把握し、次の段階に向けた改善を行えます。こうした検証を経て得られた知見を基に、段階的に導入範囲や機能を拡張することで、着実に成果を積み重ねつつ、全社的な浸透を図ることが可能です。
このように、段階的な進行はシステム運用の安定性を確保しながら、最終的なDXの成功と組織全体の最適化につなげる有効なアプローチとなります。
DX化を成功させるには、現場での運用定着が不可欠です。最新技術を導入しても、現場で使われなければ効果は得られません。そのため、まずは現場のニーズや課題を正確に把握し、フィードバックを取り入れながら、実務に適したツールへと最適化していきます。
導入初期にはトレーニングやサポート体制を整え、現場スタッフが安心して使える環境を作ります。さらに、システムの必要性やメリットを現場が理解し、主体的に活用し続けることで定着し、定期的なフォローアップで現場の声を反映し、継続的な改善につなげることが運用を根づかせるポイントです。
DXの成功には、経営層による強いコミットメントが不可欠です。現場の努力だけでは限界があり、経営層自らがDXの意義や目的を明確に示すことで、全社的な理解と協力が得られます。
経営層の積極的な関与は、DXを企業成長の中核戦略として位置づける姿勢を社内に示し、部門間の連携やリソース配分の調整を行い、プロジェクトの進捗を経営層が直接把握することで、現場の意欲向上にもつながります。
さらに、全社的な推進体制を構築するためには、専任チームの設置や部門ごとの役割分担が重要です。これにより、責任の明確化と進行管理の効率化が図られ、DXが組織全体に浸透し、企業の競争力強化に資する取り組みとなります。
金融業界におけるデジタルトランスフォーメーション(DX)は、業務効率化、顧客サービス向上、競争力強化を実現するために欠かせない取り組みとなっています。実際に、いくつかの金融機関はDXに取り組むことで顕著な成果を挙げており、これらの事例は他の企業にとっても参考となるものです。ここでは、代表的な3つの事例を紹介し、それぞれの成功の背景や実践ポイントを見ていきます。
金融業界でDXが進む中、ふくおかフィナンシャルグループ(FFG)はテクノロジーを活用した顧客中心のサービスで新たなビジネスモデルを推進しています。たとえば、2021年にはデジタルバンク「みんなの銀行」を設立し、銀行業務にとどまらない新しい価値を提供しています。
ふくおかフィナンシャルグループ(FFG)は、「お客さま本位」を徹底的に追求し、デジタル技術を活用して新しい価値体験の提供を目指しています。その一環として、FFGは2021年5月に「みんなの銀行」というデジタルバンクを立ち上げました。
この銀行は、全てのサービスがスマートフォン上で完結し、従来の銀行業務の枠を超えて、デジタルネイティブな思想に基づいて設計されています。銀行のサービスに加えて、日常の金銭管理やお金のやり取りが手軽に行える「デジタルウォレット」機能を提供し、従来の「金融仲介」から「価値のコネクティビティ」を高める新たなビジネスモデルを提案しています。
1.ゼロベースでの銀行設計
みんなの銀行は、既存のシステムや業務プロセスに縛られることなく、デジタル時代の顧客行動に即したサービスをゼロベースから設計しました。このアプローチにより、従来の銀行の枠にとらわれず、革新的なサービスを提供しています。
2.顧客に寄り添った価値の提供
みんなの銀行の理念は、単なる「お金のマッチング」ではなく、「価値のコネクティビティ」に基づいたサービスの提供です。これにより、顧客との関係性を深めるとともに、地域や社会全体に新たな価値をもたらしています。
デジタル技術が急速に進化する中、保険業界でも新しいアプローチが必要です。SBIインシュアランスグループは、FinTechやAIを活用し、業界の枠を超えた革新を実現しています。SBIグループの「顧客中心主義」を基盤に、最新のテクノロジーを駆使して、より効率的で精度の高いサービスの提供を目指しているのが特徴です。特に、SBI損害保険はAI技術の導入を進め、業務の効率化や顧客体験の向上を実現しています。
SBIインシュアランスグループは、FinTechやAIなどの先進技術を活用し、保険業界のビジネスモデル革新を進めています。SBIグループの「顧客中心主義」に基づき、「投資」「導入」「拡散」のサイクルで革新的なサービスを提供しています。
特にSBI損害保険ではAI技術を全社的に導入し、AIドリブンカンパニーへの変革を推進。具体的には、AIによる保険金不正請求の検知やコールセンターの受電予測などを実施し、業務効率化と精度向上、顧客体験の向上を実現しました。
さらに、AIを活用したデータ分析と業務改善を推進するため、「市民データサイエンティスト」育成を通じて社内の技術力向上を図っています。
1.業務のDX化とパートナー企業との連携強化
SBIグループは、パートナー企業と連携し、保険の販売プロセス全体をDX化しています。たとえば、団体信用生命保険や家財保険では、ペーパーレス化やAPI連携を進め、パートナー企業の業務効率化を支援して、販売側の負担を減らすことで、強固なパートナーシップを築く基盤となっています。
2.データドリブンな経営改革
AIを活用したデータ分析を通じて、顧客ニーズに基づいた迅速な意思決定が可能となり、経営改革を促進しました。また、社内でのAI技術活用を推進し、データサイエンティストの育成に注力することにより、技術的な能力が組織全体に浸透し、継続的なイノベーションを支える基盤が整っています。
多くの企業がDX(デジタルトランスフォーメーション)を進める中、東京センチュリー株式会社は、金融とサービス、事業領域を融合させた独自のビジネスモデルを展開しています。リースやファイナンスにとどまらず、サブスクリプション型ビジネスの共創やデジタル基盤の構築を通じて、持続可能な社会の実現に貢献しています。特に、パートナー企業との共創を通じて、新たなビジネスを創出する姿勢は今後も注目を集めるでしょう。
東京センチュリー株式会社は、「金融×サービス×事業」の強みを活かし、多様なパートナーと新たなビジネスを創出しています。リース事業に加え、サブスクリプション型ビジネスやデジタル基盤の整備を通じて、循環型経済の実現を目指す企業です。
オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社との協業においては、太陽光発電用パワーコンディショナの定額貸出サービスを展開しました。この協業において、東京センチュリーは金融・サービス機能と統合プラットフォームを提供し、双方の企業価値向上に貢献しているのが特徴です。
さらに、関係会社であるビープラッツ株式会社と連携し、SaaS型のデジタル共創基盤も整備しています。パートナーのサービスに金融機能を組み込む支援を通じて、デジタルトランスフォーメーション(DX)を推進しているのが特徴といえるでしょう。
1.サブスクリプションモデルによる持続可能なビジネスの構築
「売り切り」から「アップデート」への転換を目指すサブスクリプションモデルは、製造業のサービス化やIoTとの相性が良く、循環型社会にも貢献します。東京センチュリーは、これを単なる収益モデルではなく、社会課題解決の手段として積極的に採用しています。
2.基幹システム刷新によるDX強化
「新・基幹システム」の開発を進め、グループ会社との共同利用を視野に入れた柔軟な対応が可能なこのシステムは、経営ガバナンスの強化と運用効率化を同時に実現することを目指しています。
金融業界では、コスト削減が重要な経営課題となっています。『株式会社TWOSTONE&Sons』は、金融機関の業務効率化とDX推進をサポートし、システム運用・保守コストの最適化を支援しています。レガシーシステムのモダナイゼーションやマイグレーションにより、無駄なリソースを削減し、柔軟で拡張性の高いIT環境への移行を後押ししているのが特徴です。
経営効率を高めたい、運用コストを見直したいという課題をお持ちであれば、ぜひ『株式会社TWOSTONE&Sons』へご相談ください。
 金融業界におけるDX推進は、デジタル技術の導入だけでなく、業務効率化や顧客体験向上、コスト削減を実現する重要な経営戦略です。特に、限られた資源で競争力を強化するためには、DXによるコスト最適化が不可欠です。
金融業界におけるDX推進は、デジタル技術の導入だけでなく、業務効率化や顧客体験向上、コスト削減を実現する重要な経営戦略です。特に、限られた資源で競争力を強化するためには、DXによるコスト最適化が不可欠です。
本記事では、金融DXの6つのメリットと課題、コスト削減に効果的な施策や実践事例を紹介しました。重要なのは、ツール導入にとどまらず、業務プロセスの再設計や組織全体での意識改革を進めることです。
今後、複雑化する市場環境の中で、DX推進による柔軟な経営体制の構築が、持続可能な成長と収益性を確保するポイントとなります。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
