バックオフィスDXにセキュリティは必要?基本の対策やステップを解説
バックオフィス

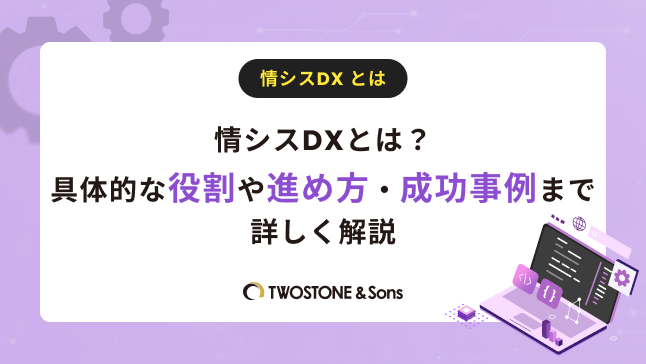
情シスDXの基本から役割の変化、具体的な進め方や成功事例、導入時の注意点まで網羅的に整理し、企業が競争力を強化するために役立つ実践的な情報をわかりやすく解説します。さらに、DX推進を支えるロードマップや人材育成の重要性にも触れ、実務に直結する視点を提供します。

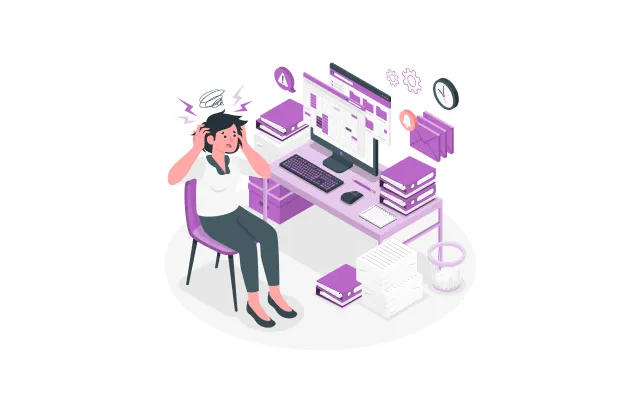
・6万名以上のエンジニアネットワークを活用して課題を解決※
・貴社のDX戦略立案から実行・開発までワンストップで支援可能
※エンジニア数は2026年8月期 第1四半期決算説明資料に基づきます。
近年、企業でのDX(デジタルトランスフォーメーション)への取り組みが加速しており、単なるIT化を超えて組織そのものの変革を模索する動きが広がっています。
特に情報システム部門、いわゆる情シスには、従来の保守・運用という「守り」の役割を超え、DX推進における中核的ポジションとして期待が高まっているといえます。
本記事では、まず「情シスDXとは何か」を明らかにしつつ、その具体的な役割や進め方を丁寧に整理します。
そして、実際の成功事例を通じて現場の実践的視点も紹介し、最後には推進にあたって押さえておきたい注意点をまとめます。こうした流れを理解することで、情シス部門が企業全体の競争力強化にどのように寄与できるのかが見えてくるでしょう。

情報システム部門におけるDXは、従来のシステム運用や保守を中心とした役割から大きな変化を迫られています。
単なるIT導入や業務効率化にとどまらず、経営全体の変革を支える存在としての重要性が増しているためです。ここでは、DXの定義やIT化との違いを整理しながら、企業競争力に直結する情シスの役割について詳しく解説し、実務における具体的な位置付けを明らかにしていきましょう。
DXとは「デジタルトランスフォーメーション」の略です。デジタル技術を活用して業務の効率化を進めるだけでなく、組織や事業モデルそのものを刷新し、顧客や社会に新しい価値を提供する取り組みを指します。
例えばデータ活用による意思決定の高度化や、AI・クラウドを活用したサービス開発などは、単なるシステム導入では得られない成果をもたらします。重要なのは、DXが単発の技術導入ではなく、企業全体の戦略と結びついた継続的な変革プロセスとして位置付けられている点であり、その推進には組織文化の変革も伴うでしょう。
IT化は既存業務を効率よく進めるためにデジタル技術を取り入れることを意味し、例として紙の帳票を電子化する取り組みが挙げられます。
一方、DXはその枠を超え、業務プロセスやビジネスの仕組みを根本から変えることが目的です。
例えば、単なる営業記録のシステム化ではなく、蓄積したデータを活用し新しい顧客体験を設計することがDXにあたります。つまり、IT化が「便利にする」取り組みだとすれば、DXは「新しい価値を創り出す」挑戦であり、この違いを理解することが情シスの役割変化を考えるうえで欠かせない視点です。
DXは企業の競争力を維持・強化するうえで重要な取り組みとなっています。データ活用による迅速な意思決定、新しい顧客接点の創出、柔軟な業務プロセスの構築などは、市場の変化に対応するためのポイントです。
その中心で役割を担うのが情シスであり、従来の「システムを安定稼働させる守りの役割」から、経営と現場を橋渡しする「変革の推進者」へと立場を広げています。IT戦略の立案や技術選定、導入後の効果検証までを支える情シスの取り組みが、結果として企業全体の持続的な成長につながっていくと考えられ、その存在は今後ますます重要視されるでしょう。
これまで情シスはシステム運用やインフラ整備、社員からの問い合わせ対応といった守りの業務を担ってきました。
しかし、DXの潮流を背景に、その役割は大きく変化しています。今後は従来の業務だけでなく、経営と連携した戦略立案やデジタル戦略の推進など、より能動的で戦略的な役割が期待されるようになってきており、情シスの立ち位置は確実に変わりつつあります。
ここでは、それぞれの役割を詳しく解説します。
従来、情シス部門は企業の基盤を支える存在として、ITインフラの構築・運用・保守が主な役割でした。
サーバーやネットワーク、パソコンなどの機器管理に加え、トラブルへの対応やユーザーからの問い合わせ処理、ヘルプデスク業務も重要な日常業務に含まれています。さらに、IT戦略やシステム企画にも関与しつつ、経営層が求める要件に合わせたシステムを設計・導入・維持してきました。
しかし、このような業務は「守り」に重心が置かれており、情シスのリソースの多くが運用やサポートに割かれてきたことが業務の固定化を招いていたといえます。
DX時代を迎えるなか、情シスにはより積極的な役割が求められている。単なる現場支援にとどまらず、経営層と協働してデジタル戦略を描き、企業価値の創出につなげる姿勢が必要です。
具体的には、RPAやAIといった先端技術の導入促進、データ活用による意思決定支援、クラウド移行やセキュリティ強化の計画立案などが挙げられます。さらにシステム導入後は効果を検証し、継続的な改善を進める役割も担うでしょう。
加えて、社内のICTリテラシー向上や変革への理解促進など文化的な側面への関与も求められ、情シスはDX推進の中心的存在へと移行しています。
ここでは、情シス部門がDXを実際に推進していく際に辿るべき主要なステップを示します。段階を踏んで進めることで、無駄のない変革を図っていけるでしょう。
まずは情報収集と現状分析から、次に要件定義や技術選定といった具体的なフェーズへと展開し、続いて導入と社内教育、最後に効果検証と改善へと至ります。それぞれの段階で情シスが果たすべき役割を整理するので、ぜひ参考にしてください。
情シスがDX推進の第一歩として担うべき役割は、現状を正しく理解することです。まずわかりやすさを追求した現状の可視化から始めることが重要です。
具体的には、各部署でどのような業務をしているのか、どこに属人化や非効率があるのかを明確にし、業務フローや利用システムの整理を行いましょう。システムのログや処理時間、問い合わせ件数といった定量データを収集し、客観的な分析材料とするのも有効です。
そのうえで、課題と改善ポイントを洗い出し、優先すべき領域を明確化し、次のフェーズの戦略的な基盤を整えます。これはDX推進の土台をしっかり固めるステップとして欠かせません。
現状分析に基づき、情シスはDXに向けた具体的な要件と導入すべき技術を定める役割を担います。
まずは「何を実現したいのか」を明確にし、経営目線や現場運用の視点を交えて要件を整理しましょう。その後、RPAやAI、クラウドなど技術候補の適性を評価し、目的に合致する手段を選定します。
選定後は、導入に伴うコスト、構築難易度、運用負荷なども考慮しながら実施計画を立てます。こうして情シスは、戦略的視点と現場の現実感覚の両方を融合させた、DX推進の基盤となる設計図を描く役割を果たしていけるでしょう。
要件と技術が確定したら、情シスには実際の導入と、組織内への展開支援を担うフェーズが求められます。
まずは選定したツールやシステムを構築または導入し、テストフェーズを経て本格運用を開始しましょう。同時に、社内ユーザーに向けた理解促進が欠かせません。そのために社内向け研修やマニュアル整備、ハンズオン形式のトレーニングを実施し、新しい仕組みを日常業務に定着させる狙いがあります。
このように情シスは、単に技術を届けるだけでなく、社内の活用力を底上げし、DXを現場に落とす役割も担います。
仕組みを導入したら、情シスには継続的な検証と改善を担う責任があります。導入後はROIやKPIなどの指標を用いて効果を定量的に評価し、結果に基づいて必要な調整や機能追加を検討します。
現場からのフィードバックを集め、UI/UXの改善や運用負荷の低減などを繰り返すことで、仕組みの精度を高めていきましょう。また、技術や事業環境の変化に応じた最適化やアップデートにも取り組むことで、DXは一過性の改良ではなく、永続的なプロセスとして強化されます。
こうして情シスが推進する改善サイクルは、持続的に価値を生む組織運営につながります。

情シスがDXを推進するには、段階を意識した取り組みが求められます。経営戦略と現場の改善をつなぐには短期・中期・長期のロードマップを描き、進捗を数値で評価する仕組みが重要です。
さらにスモールスタートや段階的拡大を進めることで現場の理解を得やすくなります。加えて、最新技術や業界トレンドを継続的に取り入れる姿勢がDXを持続させ、組織全体の成長へとつなげる要素となります。
DXは一度に完結するものではなく、段階を踏んで取り組む必要があります。そのため、短期・中期・長期の時間軸で計画を立てることが効果的です。
短期では既存業務の効率化を重視し、中期では全社的な最適化や部門横断的なシステム活用を進めます。そして長期では、新しい顧客価値やビジネスモデルの創出を視野に入れるべきです。
このように時間軸を分けることで計画の見通しが立ちやすくなり、経営層や現場双方の納得感を得ながら進められます。さらに、この計画があることで投資判断やリソース配分の精度も高まります。
DXを計画的に推進するためには、明確なKPIを設定し継続的に検証していく仕組みが欠かせません。例えば、業務工数の削減率、顧客満足度の改善度合い、導入システムの稼働率などを数値で把握すれば、進捗を客観的に評価できます。
設定した指標はSMARTの観点を意識して具体性を持たせると、現場にとっても理解しやすい基準となります。さらに、定期的なレビューを通じて改善点を洗い出し、施策の精度を高めることが持続的な成果につながるでしょう。こうした測定の積み重ねが、DXを一過性で終わらせないための基盤になります。
DXを全社的に一気に導入すると、コストや運用リスクが増え、現場の反発を招く可能性があります。そのため、小規模から始める「スモールスタート」が有効です。
例えば、改善意欲が高い部署や導入効果が出やすい業務を対象に試行導入し、成果を検証したうえで他部門へ横展開する方法です。このアプローチにより、現場での成功体験が積み重なり、社内全体の理解や協力が得られやすくなります。
段階的に範囲を広げることでリスクを抑え、確実に浸透させる基盤を築けます。最終的には全社規模での活用につなげることが理想的です。
DXは技術革新のスピードが速いため、継続的に情報を収集する姿勢が求められます。クラウドやAI、データ分析基盤など新しい技術の動向を把握し、適切に評価することが、将来の導入判断を支える根拠となります。
また、外部セミナーや業界コミュニティへの参加を通じて最新事例に触れ、社内に還元する取り組みも効果的です。こうした習慣を持つことで、単なるツール導入にとどまらず、組織の成長戦略と連動したDXを推進できる環境が整っていきます。
さらに、この姿勢が社員の学習意欲を刺激し、組織文化の変革にもつながります。
ここでは、実際に情シス部門がDXを通して改善を実現した事例を紹介します。現場で直面した課題を的確に把握し、技術とオペレーションの両面で解決した動きは、他の組織にも参考になる内容です。
特に、ネットワーク最適化や問い合わせ窓口の統合といった具体的な施策が、安定運用と業務効率化の両立にどう結びついたかを解説します。ぜひ、自社で活用するための参考にしてみてください。
ある中小製造業では、複数ベンダーが個別にネットワークを拡張してきた結果、障害が起こると対応先が曖昧になり、担当者に過度な負担がかかる状況にありました。
そこで、IT支援企業が介入し、現地調査を通じて配線や機器の配置を整理した構成図を作成し、属人化を回避する土台を整えました。そのうえで、最適経路での接続設定を含めたリプレイスを2カ月以内に実施し、問い合わせ先を一元化します。
結果として、構成が標準化されトラブルの初動対応が迅速になり、「何も起こらない」安定した運用が継続されています。これにより、問い合わせの混乱が解消され、心理的負担や業務負荷が軽減されました。
出典参照:問い合わせ先の一元化を実現し、ネットワークトラブル時の“たらい回し”を解消|アイチーム株式会社
中電技術コンサルタント株式会社では、情報システム部門に年間約5,000件もの問い合わせが集中し、本来の業務が圧迫される状況となっていました。
そこで導入されたのが、OfficeBotを活用した生成AIチャットボットです。社内規定や技術資料、問い合わせ記録など、約600件の情報をRAG技術でAIに学習させた結果、社員が必要な情報をいつでも取得できる環境が整えられました。
問い合わせ件数に大きな減少は見られなかったものの、回答精度の高さによりユーザーが自然な形で活用し続けられる状況が生まれ、問い合わせ対応の負担軽減を実現しています。また、AIとの対話体験を通じて、社内における生成AI活用への心理的障壁の低下にもつながりました。
出典参照:RAGを社員が気軽に活用!利用者維持で全社的なAI活用を促進!情報システム部門への年間約5000件の問い合わせ対応を効率化!|ネオス株式会社
株式会社ディー・エヌ・エー(DeNA)の社内ヘルプデスクは2018年に発足しましたが、問い合わせはメールベースで属人的に処理され、ナレッジも散在していました。
そこでZendeskを導入し、直感的なUIとナレッジベース構築のしやすさを活用しました。問い合わせ管理とFAQ整備を推進した結果、「困ったらまずヘルプセンター」が定着し、自己解決率が向上したようです。
週次250件あった問い合わせは約200件に減り、難易度の高い案件に集中できる体制が整いました。移転やシステム更新などで問い合わせが急増する場面も、事前のFAQ強化で混乱を回避しています。今後はSlack連携やナレッジ更新を進め、属人化に左右されないサポート体制を目指しています。
出典参照:効率化のカギは自己解決率アップ 情報収集力に左右されないナレッジ活用の実現へ|Zendesk
情シス部門が主体となってDXを進める際、技術の導入だけにとらわれてしまうと現場との乖離を生み、十分な成果につながらない恐れがあります。
DXは単発の施策ではなく継続的に価値を生み出す取り組みであるため、技術、人材、組織文化を総合的に考慮した推進が求められるでしょう。ここでは、特に注意しておきたい観点を取り上げ、企業がどのように取り組むべきかを詳しく解説していきます。
DX推進において、新しい技術を話題性だけで導入すると、現場での利用が定着せず失敗につながるリスクが高まります。システムの操作が直感的でない場合や、既存の業務フローと噛み合わない場合、従業員の負担が増し、期待していた効果が得られにくいです。
例えば入力作業が煩雑になったり、承認プロセスが複雑化したりするケースがあります。これを避けるには、導入前に利用部門の声を丁寧に吸い上げ、実際の業務で小規模に試験運用を行うことが重要です。
その結果を基に改善点を洗い出し、システムの改良や運用設計を繰り返すことで、組織に適した仕組みに近づけられます。
DXを進める際、最新のシステムを導入しても利用者が正しく使いこなせなければ成果は限定的になります。
現場が十分に理解できていない状態で運用を始めると、入力漏れや誤操作が増え、業務効率化どころか混乱を招くこともあるでしょう。解決策としては、導入初期から継続的な教育プログラムを用意し、段階的に習熟度を高める工夫が必要です。
例えば、社内マニュアルや操作動画を整備し、利用者が困ったときにすぐ確認できる仕組みを準備しておくと効果的です。加えて、導入直後だけでなく定期的にフォロー研修を行うことで、現場が安心して新しい仕組みを受け入れられます。
DX推進ではクラウドサービスや外部ツールの利用が増えるため、情報漏えいリスクも高まります。セキュリティ対策を後回しにすると、サイバー攻撃や内部不正による被害につながる恐れがあるでしょう。
具体的には多要素認証の導入、権限管理の明確化、ログ監視の仕組みが欠かせません。また、従業員に対するセキュリティ教育も並行して進めることで、意図しない情報漏えいを減らせるでしょう。
最新の攻撃手法や対策を定期的に見直す姿勢も重要です。技術面と教育面の両輪で強化することで、安全性を確保しながらDXを推進できます。
DXの成果が曖昧なままでは、現場に浸透せず効果検証も難しくなります。新しい仕組みを導入しただけで満足してしまうと、本来期待される生産性向上やコスト削減につながらない場合があります。
そこで導入前から「どの業務を、どの指標で測るか」を定義しておくことが大切です。例えば、問い合わせ対応時間の短縮率や入力作業の削減量など、現場の改善を具体的に数値化できるKPIを設定すると効果が見えやすくなります。
また、短期的な成果だけでなく長期的な視点で評価することも欠かせません。評価基準を共有しておけば、経営層から現場まで同じ目標に向かって進める環境が整います。

情シスDXは、従来の保守やサポート中心の役割から脱却し、データ活用や新技術の導入を戦略的に支える取り組みです。
クラウドや生成AIを導入すれば、業務効率化だけでなくナレッジ共有や意思決定の迅速化にも結びつきます。さらにロードマップやKPIを設ければ、成果を確認しながら改善できます。
一方で、現場に合わないツールや教育不足は失敗の要因となるため、セキュリティ対策や研修を含めた準備が欠かせません。まず課題を整理し、小さな範囲から検証を重ねることで、情シス部門は企業成長を支える存在へと変わります。情シスDXを正しく進めることが競争力強化につながるでしょう。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。
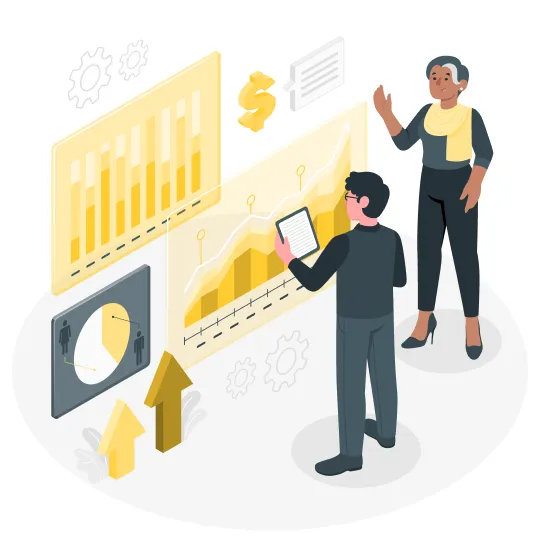
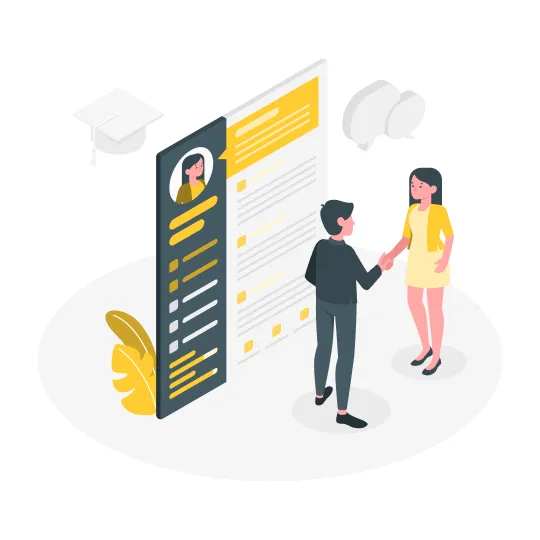
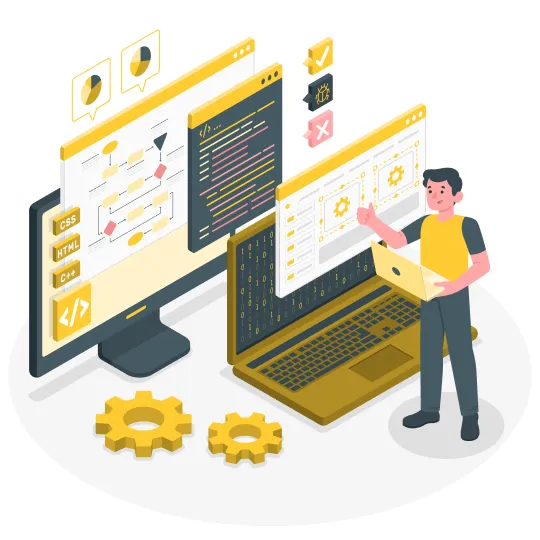
幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
