金融DXの推進によって叶う勘定系システムの刷新|4つの取り組み例を紹介
金融

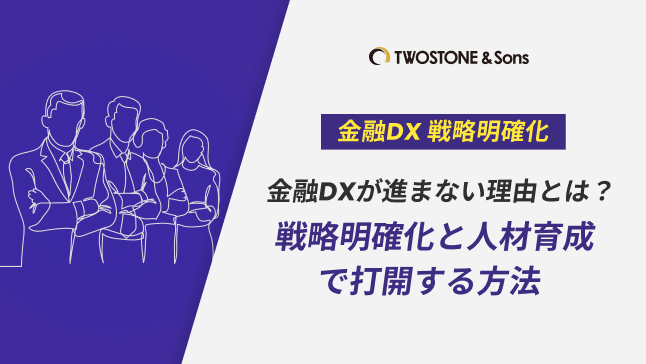
多くの金融機関がDXの必要性を感じながらも、形だけのデジタル化にとどまっています。本記事では、DXが進まない原因を整理し、戦略明確化と人材育成を軸に、顧客視点で本質的な変革を実現するための具体的なアプローチ方法を解説します。
「DXを進めなければならない」と多くの金融機関がこの危機感を抱いています。しかし現実には思うように進まず、形だけのデジタル化に終始しているケースも少なくありません。システムは最新化されたはずなのに業務の本質は変わらず顧客体験も改善されていない、このような課題に直面している企業に共通するのは、テクノロジーへの過度な依存と戦略・人材・組織文化といった本質的な視点の欠如です。
本記事では、金融業界でDXが求められる背景を押さえつつ、なぜDXが進まないのかという具体的な要因を整理します。その上で推進を加速するために不可欠な「戦略の明確化」と「人材育成」の重要性を解説し、課題を打破する実践的なヒントを提示します。読み進めることで、単なる技術導入ではなく顧客視点で本質的な変革を実現するための考え方とアプローチが見えてくるでしょう。

金融業界におけるデジタルトランスフォーメーション(DX)が加速している背景には、大きく3つの要因があります。第1に、顧客のニーズが急激に多様化し、オンラインやモバイル経由での金融サービス利用が主流となったことです。スマートフォン一台で完結する操作性やリアルタイム性が求められる中、従来の業務システムでは対応が難しくなっています。
第2に、競争環境の変化です。フィンテック企業の台頭によって金融サービスの提供形態が変わりつつあります。スピード感ある開発やユーザー視点で設計されたUI/UXによって、従来の金融機関との差別化が進んでいます。このままでは既存金融機関が取り残される可能性も否定できません。
第3に、規制緩和と政策的後押しです。政府が推進するデジタル庁の取り組みやAPI公開の義務化などにより、金融業界全体にデジタル対応が求められる環境が整ってきました。
このように、外部環境の変化に加え、顧客の期待に応えるためにも金融DXの推進はもはや避けて通れないテーマとなっています。
DXの必要性は理解されているものの、実際には多くの企業で推進が停滞しています。その原因を深掘りすることで、真の課題が浮き彫りになります。
ここでは、金融DXの推進が進まない理由を整理していきましょう。
多くの金融機関では、数十年前に構築された基幹システムが今なお運用されています。これらは高度にカスタマイズされており、新しい技術との互換性が低い傾向にあります。新たなサービスを導入しようとしても既存システムとの連携に多大なコストと時間がかかり、結果としてDXのスピードが鈍化しているのです。
さらにシステムを支えるエンジニアが定年を迎える中、内部にナレッジを引き継げる人材が不足している現状も深刻です。モダナイゼーション(近代化)の必要性は高いものの、業務リスクを避けたいがゆえに改革に踏み出せないジレンマが存在します。
DXの推進において重要なのは「目的の明確化」です。しかし、現場と経営層の間でビジョンの共有が不十分なケースが目立ちます。「何のためのDXか」が定まっていないため導入する技術やシステムも場当たり的になり、全体としての整合性を欠いてしまうのです。
ビジョンを共有するには、経営層から現場の従業員までが同じ方向を向いて取り組む必要があります。そのために定期的なワークショップや戦略共有の場を設け、コミュニケーションを活性化させる工夫が求められます。
DXを実現するには、デジタル技術を理解して実務に落とし込める人材が不可欠です。しかし金融業界ではIT系人材の採用競争に後れを取っており、自前での人材確保が難しい状況です。また、既存の従業員に対する再教育やリスキリングも十分に機能していません。
技術に強いだけでなく金融業務の知識を持ち合わせた「ハイブリッド人材」が求められていますが、そのような人材は市場に限られており、採用難易度が高くなっています。
自社で開発体制を持たない場合、外部ベンダーへの依存度が高くなります。この場合、スピード感を持った施策の実行が難しくなるだけでなくプロジェクトの進行や成果物の品質がベンダー任せになってしまいがちです。
またベンダーとの目的意識や期待値のズレが発生すると、DXプロジェクトの方向性がぶれる原因になります。理想的なのは、外部パートナーを活用しつつ将来的には自社での内製化にシフトできる体制を整えることです。
従来の金融機関では、縦割り型の組織構造が一般的です。この構造は業務効率に優れている反面、部門横断的な改革を進めにくいという弱点を抱えています。DXは営業・商品開発・IT・カスタマーサポートなど複数の部門にまたがる取り組みであるため、サイロ化された組織では調整に時間がかかり、スピード感が損なわれるのです。
また、階層的な意思決定プロセスも足かせとなります。迅速な判断と実行が求められるDX推進において、機動力のある組織設計が必要です。
現場の従業員がDXの本質を理解していないと導入された新システムやツールが活用されず、形だけの改革になりかねません。例えば、営業担当者が新しい顧客管理システムを使いこなせず、従来通りの紙ベースの管理に戻ってしまうようなケースです。
このような事態を避けるためには、現場への丁寧な説明やトレーニング、活用メリットの明示が欠かせません。現場からのフィードバックを反映させる体制も重要です。
金融機関では、四半期ごとの収益や業績が重視される傾向があります。そのため、DXのように長期的視点で取り組むべきテーマが軽視されがちです。結果として、すぐに成果が出る施策ばかりに注力し将来の競争力向上につながる本質的な改革が後回しになります。
金融DXの推進には、短期的な成果だけでなく中長期的な成長を見据えた戦略的投資を行う意識の醸成が求められます。そのためには、社内におけるDXの位置づけを再定義し、トップダウンでの強いメッセージを打ち出す必要があるのです。
金融DXを成功に導くためには、技術やツールの導入だけでは不十分です。経営層から現場まで一貫したビジョンと戦略、そして組織全体の変革が求められます。
ここでは、金融機関が取り組むべき6つの具体的なアクションを紹介します。
まず重要なのは、なぜDXを推進するのか、どこを目指すのかという目的とゴールの明確化です。DXを単なるデジタル化と捉えてしまうと、導入したツールが現場に浸透せずに形骸化してしまいます。
例えば顧客満足度の向上を目的とするならば、「応対時間を半減する」「問い合わせから解決までを自動化する」など具体的な成果を定める必要があります。曖昧な方向性では部門ごとに異なる解釈が生まれ、社内の足並みが揃いません。目的とゴールを数値目標やKPIで可視化することで、各チームの行動が一致しやすくなるでしょう。
目的が明確になったら、次に必要なのは全社的なDX戦略の策定です。部分的な改善ではなく組織全体を横断する改革として捉える必要があります。営業・企画・システム・カスタマーサポートなど各部門が個別に取り組むのではなく、経営層主導で一貫した戦略を打ち出すことが重要です。
特に、既存のビジネスモデルとどのように共存・進化させるかの観点が欠かせません。金融機関では規制対応やリスク管理といった複雑な要素があるため、各部門の専門性を活かしつつDXが全体最適につながるようなマネジメントが求められます。
DXの根幹を担うのは最終的には「人」です。外部ベンダーにすべてを依存するのではなく、将来的に内製化を見据えた人材育成が不可欠です。金融業界では特に、デジタル人材の確保が課題になっています。
まずは、自社にどのようなスキルセットが不足しているのかを棚卸しし、育成すべき職種とスキル領域を明確にします。例えば、データエンジニアやプロダクトマネージャー・UXデザイナー・セキュリティ専門家などそれぞれの役割に応じたトレーニングプログラムを設計する必要があります。
また、育成は単発の研修で終わらせず、OJTや実務経験を通じた継続的なスキルアップの機会を提供する必要があるのです。
育成だけでなく、外部からの人材採用も並行して進める必要があります。ただし、無計画に採用を進めてしまうと期待とのギャップや定着率の低下を招くリスクがあります。そこで、即戦力と育成対象を明確に区別した上で採用戦略を練ることが重要です。
例えば、新規サービスの立ち上げフェーズではプロダクト開発やアジャイル開発に精通した即戦力を確保する一方で、中長期的には社内人材を育てる体制を整える、といったバランスが求められます。また、職務内容やキャリアパスを明示することで候補者とのミスマッチを防ぎ、入社後の早期離職を減らす効果も期待できます。
従来の採用活動は学歴や業界経験を重視する傾向が強く、DX人材には必ずしもフィットしないケースがあります。そこで、DX視点で採用戦略そのものを再設計する必要があります。
具体的には、「どのような課題を解決できる人材なのか」「どのような価値を組織にもたらすか」といった、スキルベースや成果ベースの評価軸の導入がポイントです。また、選考フローにも工夫が求められます。例えば、技術課題への取り組みやロールプレイング、ケース面接などを通じて実践的なスキルや課題解決力を見極める仕組みを取り入れましょう。
さらに、金融業界特有の「堅い」企業文化がIT人材との相性に影響を与えることも少なくありません。柔軟な働き方やリモートワークの導入、心理的安全性の確保といった環境整備も並行して進める必要があります。
DX推進は経営層やIT部門だけの課題ではありません。現場の従業員一人ひとりがデジタルに対する理解を深め、自発的に活用する文化の醸成が成功のカギを握ります。
そのためには、初級者向けのIT基礎講座から業務システムの利活用トレーニングまで、職種やスキルレベルに応じた教育プログラムを段階的に整備することが効果的です。特に、業務上の「困りごと」をデジタルで解決できたという成功体験を重ねると、現場の意識は確実に変わります。
またITツールの導入時には、現場の業務プロセスや文化を丁寧にヒアリングし、ユーザーに寄り添ったサポート体制を整えることでツールの定着率が飛躍的に向上します。
ここまで述べたように、金融DXを成功に導くためには単なる技術導入にとどまらず、経営層のコミットメント・明確な戦略・組織構造の改革・人材育成・文化変革など複合的かつ体系的な取り組みが求められます。
特に重要なのがDX戦略の「明確化」です。曖昧なビジョンのままDXを始めてしまうとリソースが分散し、施策の優先順位が不明瞭になり、社内の理解や協力も得られにくくなります。逆に目指すべき姿が明確であれば、例え途中で困難があっても組織全体が同じ方向を向いて進めるでしょう。
また、戦略は一度立てたら終わりではありません。市場や技術の変化に柔軟に対応できるよう定期的な見直しとアップデートが不可欠です。デジタル施策が想定した成果に結びついていない場合、その原因を分析して戦略全体の再調整を行い、PDCAサイクルを回し続けることが重要です。
そのためにも、DX推進の専門家や伴走型の支援パートナーと連携しながら戦略のブラッシュアップを継続していく姿勢が求められます。戦略と実行のギャップを埋める存在として外部のノウハウを柔軟に活用することが、金融機関にとって今後さらに重要になるでしょう。

金融業界でDX(デジタルトランスフォーメーション)を成功に導くためには、単なるシステム導入や業務効率化にとどまらず全体戦略の明確化とそれにもとづく人材配置が不可欠です。特に既存の業務プロセスや組織体制が複雑な金融機関では、DXの方向性が曖昧なままだと部分最適に陥り、全社的な効果を得にくくなります。
ここでは、金融DX推進における戦略を明確にするための6つのステップを紹介します。
まず必要なのは、自社が抱える構造的な課題をテクノロジーの観点から捉え直すことです。現場の業務フローがどこで滞っているのか、顧客体験にどのような摩擦があるのかを具体的なデータやヒアリング結果をもとに可視化します。
例えば、紙ベースでの手続きが多い、情報システムの更新が属人的でブラックボックス化している、チャネルごとに顧客情報が分断されているなどアナログな運用のまま放置されている領域がDXによって改革対象となります。重要なのは、単なる業務効率化ではなく顧客接点の価値を高める視点を持つことです。
この段階で課題を洗い出す際にはIT部門だけでなく、営業・事務・企画など複数の部門からヒアリングを行い、現場の実態と意識のギャップを把握しましょう。
DXを推進するためには、従来の業務適性だけでなくデジタルリテラシーや課題解決力、部門横断でプロジェクトを進められるコミュニケーション能力が求められます。そのため、まずはDXに関わる職種の人材要件を見直す必要があります。
具体的には、「データ分析ができる営業職」「業務設計とRPA開発の両方を理解する企画職」「システム部門と現場の橋渡しができるプロジェクトマネージャー」など従来の枠を超えたハイブリッドなスキルを持つ人材です。
これに伴い、採用チャネルの見直しや選考プロセスの刷新も求められます。ポテンシャル採用を拡充して入社後に育成する前提で人物本位の採用を強化する、あるいは即戦力となるIT人材を外部から確保するなど複数の採用戦略を同時に展開する体制を整えると良いでしょう。
金融DXにおいて、すべてを自社で内製化することは非現実的です。しかし、重要な中核システムやデータ基盤、セキュリティ対応に関しては外部委託のみに頼ると自社にノウハウが蓄積されません。そこで、どこを内製化しどこを外部に委託するかの明確な線引きが重要です。
例えば、フロント業務に直結するアプリケーションや顧客接点のUX設計は自社主導で開発し、インフラや保守運用は外部のクラウドベンダーに任せるといった判断が求められます。ポイントは、パートナー企業との協業においても自社の視点で主導権を持つ体制を整えることです。
また、パートナーの選定基準も見直す必要があります。単に価格や技術力で選ぶのではなく、共に長期的なビジョンを共有できるか、文化的なフィット感があるかといった観点が重要になります。
DX人材は一朝一夕には育成できません。そのため、3〜5年単位の中長期で見た人材育成ロードマップを策定する必要があります。この設計においては、以下の3つの層に分けたアプローチが効果的です。
経営・管理層 | DX戦略の意義と自らの役割を理解し、部門間連携をリードできるスキルを習得 |
プロジェクト推進層 | アジャイル開発やデータ分析の実践的スキルを習得し、現場を牽引 |
現場スタッフ層 | 日常業務におけるツール活用や業務改善の意識を高め、デジタルシフトを定着させる |
このように、役割に応じて求められるスキルと教育施策を整理して社内外のリソースを活用した研修体系を構築することで、DX人材の継続的な育成が可能になります。
DXは単独部門では完結しません。したがって、複数部門が連携して取り組む横断的な体制が求められます。よく見られる失敗例としては、IT部門のみでプロジェクトが進行して現場の理解や協力が得られず定着しないケースです。
効果的な体制は、DX専任の「CoE(Center of Excellence)」を設置して各部門の代表者を巻き込んだ「DX推進委員会」を組成する方法です。これにより、現場の実情を反映しながら迅速な意思決定ができるでしょう。
またプロジェクト管理においては、ウォーターフォール型ではなくアジャイル型を採用することで、現場とのフィードバックループを回しながら柔軟に進められます。
DXの推進において重要なのが、経営層の強力なコミットメントです。現場がどれだけ変革に前向きでも、トップがデジタルの必要性を理解していなければ推進力にはなりません。
したがって、経営層と現場の間でDXに対するビジョンや目的を統一し、全社として一貫した方向性を持つことが不可欠です。社内向けのキックオフイベントやタウンホールミーティングで、経営層自らがDXの意義を語る機会をつくりましょう。
さらに、KPIやKGIといった目標指標を明示して進捗を可視化することで、組織全体のモチベーションと方向性を一致させる工夫も必要です。
DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進において、テクノロジーやシステム導入に注目が集まりがちですが、本質的な成功要因は「人」にあります。
特に金融業界では、厳格な法規制や複雑な業務プロセスが存在するため、単にITスキルを持つ人材を増やすだけでは変革は進みません。ビジネスとデジタルの橋渡しができる人材をいかに育成し、現場のDXマインドを醸成するかがカギを握ります。
ここでは、金融DX推進に必要な人材育成の具体的な方法について6つの観点から解説します。
まず全社的に取り組むべきは、従業員一人ひとりの「デジタルリテラシー」を向上させる施策です。デジタルリテラシーとは、ITツールやデジタル技術を業務に応用できる基礎的な理解力を指します。これが欠如しているとDX施策を導入しても現場での活用が進まず、改革のスピードが鈍化してしまいます。
リテラシー向上の第一歩として、全従業員を対象にしたeラーニングプログラムやオンライン講座の導入が効果的です。特に、クラウドサービスの基本知識やセキュリティ意識、業務改善に役立つデジタルツールの使い方など、実務に直結する内容を中心に構成すると現場での理解が深まります。
加えて、学んだ内容を現場でどう活かせるかを考える「実践型ワークショップ」を実施することで学習効果が定着しやすくなります。単なる知識の習得にとどめず、業務改善の視点を持った活用力まで育てましょう。
DXの現場では、システム部門と業務部門の間に立ち、相互の意図を正確に伝達・調整できる人材の存在が不可欠です。こうした役割を担う人材は「ビジネスアナリスト」や「テクノロジー・トランスレーター」と呼ばれ、業務知識とIT知識の双方を兼ね備えるハイブリッドなスキルが求められます。
これらの人材を育成するには、ローテーション研修やOJT(On-the-Job Training)を活用し、複数部門の業務を横断的に経験させる方法が効果的です。例えば、営業部門出身者を一時的にIT部門に配属してシステム要件定義や開発フローを体験させることで、部門間の共通言語を獲得できるでしょう。
また、業務プロセス改善やデータ分析の基礎を学ぶ外部研修を組み合わせることで、論理的思考や仮説検証能力といったビジネスに必要なスキルも磨けます。育成は短期的に完結するものではないため、数年単位の計画的な育成ロードマップが求められるのです。
既存従業員の中からDX推進人材を育てる手法として「リスキリング(再教育)」は有効です。これは、職種や業務の枠を超えて新たなスキルや知識を習得する取り組みを指します。急速に進化するテクノロジー環境に対応するためには、柔軟なキャリア形成を前提とした人材開発が欠かせません。
具体的には、金融業務経験の豊富な従業員に対してプログラミングやAI、データベース設計などの専門スキルを段階的に提供し、IT領域へのスムーズな転換を支援します。このとき重要なのは、学習意欲を高めるためのインセンティブ設計です。スキル取得に応じて役職や評価制度に反映する仕組みを整えることで、学習モチベーションの維持につながります。
さらにオンライン教育プラットフォームの活用によって、働きながら学べる環境を整えることもポイントです。従来の集合研修にとらわれず、個々のライフスタイルに応じた柔軟な学習設計が求められます。
DXの推進には、単なるスキルの習得以上に従業員一人ひとりの「マインドセット」の変革が必要です。変化を恐れず新しい挑戦をポジティブに捉える文化が根付いていない組織では、いかに優れたツールや人材が揃っていても改革は長続きしません。
このマインドセットを浸透させるためには、経営層自らが変革の必要性を繰り返し発信して現場の取り組みを積極的に可視化することが重要です。業務改善提案を表彰する制度や成功事例を社内SNSや社内報で共有する取り組みが効果的でしょう。
また、部門横断のワークショップやアイデアソンを開催し、異なる視点の従業員が協力して課題を解決する経験を積ませると、自然と「変革は自分ごと」という意識が芽生えます。文化づくりは短期で完了するものではありませんが、日々のコミュニケーションや評価制度の中で継続的に働きかけることで徐々に組織全体に定着するでしょう。
金融DXにおいては、すべてのリソースを内製化するのではなく外部のベンダーやスタートアップ企業と連携しながら進めるケースが多くなります。そのため、パートナーとの関係構築やプロジェクトマネジメントに長けた人材の育成が欠かせません。
このマネジメント力を高めるには、複数社と協業する中で発生するコンフリクト(利害対立)を整理して建設的に調整できるスキルが求められます。交渉力や契約理解、ガバナンスの知識も含め広範な視野でプロジェクト全体を俯瞰できる必要があるのです。
社内研修では、ケーススタディやロールプレイを通じて現実に近い状況を再現し、実践力を養うとよいでしょう。さらに、プロジェクトマネジメントに関する資格取得支援(例:PMPやITIL)を導入することで専門性を担保しつつ標準化を図れます。
最後に、実践的な研修プログラムの充実も忘れてはなりません。座学中心の研修だけでは習得した知識を現場で活かしきれないケースが多く見受けられます。そこで、実際の業務課題をベースにした「プロジェクト型研修」や「ジョブシャドウイング(業務観察)」を導入し、よりリアルな経験を積むことが重要です。
例えば、RPA導入をテーマに業務プロセスを洗い出して改善策を提案・実行する実習を行えば、業務理解と技術活用の両面からスキルを高められます。また、OJTの指導役となる従業員には「育成の技術」を事前に学ばせ、学習効果が高まる環境を整えましょう。
このように、実務に直結する研修を通じて即戦力を育てる体制を整えることで、研修後すぐに現場で成果を発揮できる人材が増えていきます。
金融DXを加速させるには、戦略や人材育成に加えて実行フェーズでの細かな配慮も不可欠です。特に現場との連携、長期的視点の確保、外部依存のバランスといった観点は失敗を避けるための重要なカギとなります。
金融DXの推進では、経営層と現場の間に認識のズレが生じやすくなります。このギャップを放置すると、現場の理解や納得感が得られず施策が形骸化する恐れがあります。
例えば、データドリブンな意思決定を目指すにもかかわらず現場に十分なデータ分析ツールや教育が提供されていない場合、導入効果は限定的になるでしょう。現場の声を拾い、業務に即した形で改善サイクルを組み込む体制が必要です。
経営層と現場の間に継続的な対話の場を設けることで、実効性あるDX施策が根付きやすくなります。
成果を早く求めるあまり、DXの目的が「見える化」や「業務の効率化」に限定されるケースがあります。しかし本来、DXの意義は顧客体験の革新や新たなビジネスモデルの創出です。
短期的な指標ばかりを重視すると、従業員のリスキリングやカルチャー変革といった長期的な投資が後回しになりがちです。目先のKPIだけではなく、5年後・10年後を見据えた視点での取り組みが求められます。
経営としては、中長期的なビジョンとロードマップを明示し、従業員の理解と共感を得る姿勢が重要です。
ITベンダーやコンサルティングファームとの協働は、専門知識の補完やスピードアップに有効です。ただし、依存度が高すぎると内製化が進まず、自社のデジタル成熟度が向上しないという課題が生じます。
例えば、すべてのデータ分析やシステム設計を外注している場合、自社内にノウハウが蓄積されず、次のフェーズでの判断に時間がかかることがあります。外部と連携しつつも、自走できるチームや体制の構築が求められるのです。
外注を戦略的に活用しながら社内人材の成長とナレッジ移転を計画的に進める姿勢がカギとなるのです。
DXの推進において、戦略の立案や人材育成、組織風土の変革など多くの課題に直面します。これらの悩みは、専門的な支援を求めましょう。
『株式会社TWOSTONE&Sons』は、戦略設計から人材育成プログラムの開発、現場への浸透支援まで金融業界に特化したDX支援を行っています。特に、経営と現場を橋渡しする人材の育成支援に強みがあります。
現場の課題を的確に把握して持続的に成果を生み出せる体制を整えるためにも、プロフェッショナルの力を借りることは助けになるでしょう。具体的な支援内容や導入事例については公式ホームページをご確認の上、ぜひお気軽にご相談ください。

金融DXを成功させるためには、戦略と実行の両輪を整える必要があります。特に重要なのは、「何を実現したいのか」を明確にし、それにふさわしい人材を育てることです。
さらに、現場との連携、長期的視点の維持、外部依存の抑制など実行フェーズでの注意点も押さえることで、組織全体が一体となってDXを推進できます。
今こそ、変革をリードできる金融機関を目指して戦略と人材の両面から本質的な変化を起こしましょう。その第一歩として、外部パートナーとの協働も視野に入れたアクションを始めてみてください。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
