『Dify×スプレッドシート』バッチ処理でビジネスアイデアを量産!AIによる自動考案・評価システム構築方法
自動化
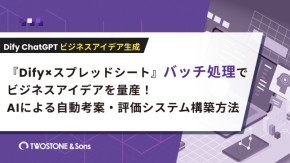
01-1.png)
金融DXを成功させるには戦略的な推進が不可欠です。本記事では、5つの実践ステップと成功事例、専門支援の重要性について詳しくご紹介します。DXの推進や加速をお考えの金融機関の皆さまはぜひご一読ください。
かつて「保守的」といわれていた金融業界に、今大きな変革の波が押し寄せています。銀行や証券会社、保険会社などの金融機関はデジタル技術の進展や顧客ニーズの変化に対応するため、従来のビジネスモデルを見直す動きを加速させています。
しかし、単なるITシステムの導入ではこの変化に対応しきれません。今求められているのは、デジタル技術を経営戦略の中核に据えて業務プロセスや企業文化までをも刷新する「金融DX(デジタルトランスフォーメーション)」です。
本記事では、金融DXとは何かを明確にし、その背景や導入によってもたらされる具体的なメリット、そして実際に成果を上げている5つの成功事例を紹介します。金融機関が今後も持続的に成長していくためには何が必要なのかを、具体的な視点から深掘りしていきましょう。

金融DXとは、デジタル技術を活用して金融サービスや業務プロセスを抜本的に変革する取り組みです。単なるデジタル化と異なり、既存のシステムやサービスの効率化にとどまらずデータの利活用やAI・クラウドといった先端技術を駆使し、新たな価値創造やビジネスモデルの構築を目指します。
例えばスマートフォンでの口座開設や資産運用アプリの活用、RPAによる事務作業の自動化、AIを活用したリスク評価などがその代表例です。これにより金融機関はより迅速かつ正確な意思決定を行い、顧客への提供価値を高められるのです。金融DXは、競争の激しい市場環境の中で業務の最適化と顧客満足度の両立を可能にする重要な戦略といえるでしょう。
金融機関がDXに取り組む理由は多岐にわたります。ここで紹介するような背景が重なり合うことで、デジタル変革の必要性が高まっています。
近年、フィンテック企業の台頭や大手IT企業の金融サービス参入など、業界構造そのものが変化しつつあります。これまで金融サービスを独占してきた既存の金融機関にとって、これらの新興勢力は強力な競合となっています。
さらに消費者の生活様式もデジタル中心へとシフトしており、金融サービスにもスピードや利便性、パーソナライズされた対応が求められるようになりました。こうした変化に迅速に対応しなければ、顧客離れを招くリスクが高まってしまうのです。
日本では少子高齢化が急速に進んでおり、金融機関の主要な顧客層も変化しています。高齢者には対面や電話を重視する層が多い一方で、若年層はスマートフォン1つで完結する金融サービスを好みます。
多様化するニーズに対応するには、チャネルの拡充とサービスの柔軟性が大切です。DXによって顧客データを分析し年齢やライフスタイルに応じた提案を自動で行う仕組みの導入は、こうした課題解決のカギとなるのです。
長引く低金利環境や市場の不確実性により、金融機関の収益構造は厳しい状況が続いています。預金業務や融資だけに依存したビジネスモデルはもはや限界であり、新たな収益源の開拓が急務です。
DXによって業務コストを削減する一方で、資産運用アドバイスやサブスクリプション型サービスなど新たな商品やサービスを創出する取り組みが求められています。こうした変革が収益の多角化につながり、企業の持続可能性を高めるのです。
金融DXは単なる業務効率化にとどまらず、企業全体に幅広い影響をもたらします。ここでは代表的な5つの効果を紹介します。
RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)やAIを活用することで、定型的な事務作業を自動化できるようになります。これにより、人的リソースをより高度な業務へと振り分けられ、結果として生産性が向上するでしょう。
また紙ベースの手続きや対面対応が減ることで、店舗運営費や人件費の削減にもつながります。金融機関全体のコスト構造が見直されると、収益性の高い組織体制へと転換できるのです。
デジタル化によって得られる膨大な顧客データを活用することで、より的確なマーケティングや商品設計が実現します。AIによる予測分析や機械学習モデルを導入すればリスク評価や貸出審査の精度も高まり、業務全体の信頼性が向上するでしょう。
過去の実績だけでなく、リアルタイムの行動データに基づく判断が可能になるため、変化の激しい市場にも柔軟に対応できる組織に生まれ変わります。
DXによって、これまでの枠組みにとらわれないビジネスモデルの構築が可能になります。実際に、APIを活用した他業種との連携により金融機能をさまざまなサービスに組み込む「Embedded Finance(埋め込み型金融)」が注目されています。
このような新たな価値提供により、既存の顧客層だけでなく新しい市場へのアクセスも可能になり、金融機関としての存在価値を再定義できるのです。
クラウド環境の整備や業務フローのデジタル化によって在宅勤務やフレックスタイム制度の導入が進み、従業員の働き方に柔軟性が生まれます。これによりワークライフバランスの改善だけでなく、従業員満足度の向上にもつながるでしょう。
また、属人化していた業務をシステムで標準化することでチーム全体の連携がスムーズになり、業務品質の均一化とミスの削減が実現します。
デジタル技術を積極的に活用する企業は、革新的で柔軟なイメージを持たれやすくなります。特に若年層やデジタルネイティブ世代からの支持を得やすくなり、優秀な人材の確保にも有利に働くことになるでしょう。
また、社会的なトレンドにも敏感に対応する姿勢は投資家やパートナー企業からの信頼にもつながります。DXは単なる技術導入ではなく、企業ブランドを形成する重要な要素の1つとなっているのです。

金融機関におけるDXの進展は、業務の効率化や収益構造の変化に留まりません。最大の受益者ともいえるのが、日々サービスを利用する顧客です。テクノロジーの導入によって提供されるサービスが進化し、顧客体験はかつてない水準へと引き上げられています。
ここでは、金融DXが具体的に顧客にもたらすメリットを5つの視点から解説します。
金融DXの最大の恩恵は、サービスの利便性向上です。従来、銀行の利用には窓口やATMに出向く必要があり、限られた営業時間や長い待ち時間が課題でした。現在ではスマートフォン一つで24時間365日、口座管理や送金、融資の申請まで完結できるようになっています。
また、オンラインバンキングの普及により外出先でも残高確認や振込が即座に可能になりました。加えて、アプリのUI(ユーザーインターフェース)が直感的に操作できる設計へと進化したことで、幅広い年齢層がストレスなく利用できるようになっています。
金融サービスの根幹である「手軽さ」を支えるこの利便性の向上は利用頻度の増加や離脱率の低下にも直結し、金融機関と顧客の関係性を強固なものにしています。
次に挙げられるのが、パーソナライズされたサービスの提供です。顧客データを高度に分析することで、一人ひとりのライフスタイルや資産状況に応じた金融商品を提案できるようになりました。
特に注目されているのが「レコメンドエンジン」の活用です。これは、過去の取引履歴や現在の資産構成、年齢や職業といった属性情報を基に適切な商品やキャンペーンを自動で提示する仕組みです。これにより、顧客は自分のニーズに合致した情報だけを効率的に受け取れます。
また、ライフプランに応じた資産形成シミュレーションや自動積立の提案なども行われており、「金融商品を自分で探す負担」から解放される環境が整いつつあります。
AIやRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)を活用した業務の自動化により、顧客対応のスピードが格段に改善されています。従来は数日かかっていた審査や手続きも、現在では数分〜数時間で完了するケースが増えてきました。
住宅ローンの仮審査を例に挙げると、従来は書類の提出から審査結果の通知までに数日を要していましたが、今ではオンラインで入力を行えば即座に結果が出るシステムも登場しています。
さらにAIチャットボットの導入により、24時間体制での問い合わせ対応が可能となりました。これにより夜間や休日でも疑問点を解消できるため、利便性の高さに加えて安心感も顧客満足につながっています。
パンデミック以降、非対面でのサービス利用への需要は急速に高まり、金融DXはこのニーズにも柔軟に対応する必要が出てきました。今ではモバイルアプリやウェブサービスを中心に、店舗に足を運ばずともほぼすべての金融手続きが完結するようになりつつあります。
特に地方に住む高齢者や多忙なビジネスパーソンにとって、オンラインで完結できるサービスは大きなメリットとなっています。加えて、ビデオ通話による相談サービスも拡充されており、専門的なアドバイスを自宅から受けられる環境も整ってきました。
こうしたチャネルの多様化は、従来の「金融サービス=店舗での対面対応」という固定観念を覆し、誰もが自由に、そして気軽にサービスへアクセスできる新しい時代を切り拓いています。
利便性とスピードが向上しても、セキュリティに不安があれば顧客は離れてしまいます。そこで金融DXを推進し、最新のセキュリティ技術の導入に積極的に取り組む企業が出てきました。具体的には・生体認証・二段階認証・ブロックチェーンなどの技術です。
生体認証は指紋や顔認証によって本人確認を行う仕組みで、従来のパスワードよりも高い安全性が確保されます。また、ブロックチェーン技術の活用によって取引履歴の改ざんが極めて困難になり、データの信頼性も向上しました。
これらの技術革新により、利用者は自分の資産や個人情報が守られているという安心感を得られます。さらに手続きや審査の透明性も高まり、不明瞭な手数料や説明不足といった課題も解消されつつあります。
安心して利用できる環境が整うことで顧客は積極的にサービスを活用するようになり、結果として金融機関との関係性もより良好なものへと発展していくのです。
金融DXが多くの金融機関にとって不可避の経営課題となる中、先進的な取り組みを行い、顧客体験の向上と業務改革の両立を果たしている事例が国内でも増えています。
ここでは、実際にDXを推進して顕著な成果を上げた金融機関を5つ紹介します。これらの事例からは、戦略の立て方や実行のポイント、そして顧客に対する影響まで多くの示唆を得られます。
三井住友フィナンシャルグループは、「デジタル×リアル」の融合を軸にしたDX戦略で注目を集めています。同社はグループ全体でDXを経営の中核に据え、「SMBC Digital Strategy」を策定し、ITだけにとどまらない全社変革を進めています。
具体的には、顧客接点の改革としてデジタルチャネルの強化や顧客行動の分析に力を入れています。AIを活用した顧客分析基盤を構築し、顧客一人ひとりのニーズに最適化されたサービス提供を実現しました。これによりサービスの提案精度が向上し、クロスセルや顧客定着率の改善につながっています。
また、社内業務の効率化にも力を入れており、RPAやAI-OCRを活用して紙業務の削減と人員配置の最適化を図っています。デジタル技術を通じた省力化は、従業員の付加価値業務へのシフトを促し、全体的な生産性向上を実現しました。
このようにSMFGは、顧客視点と業務効率の双方を見据えた総合的なDX推進によって、持続的な競争優位性を確立しつつあります。
りそなホールディングスは、地域金融機関として先進的にDXに取り組んでいる代表例の1つです。同行は「りそなグループアプリ」の提供を通じて、個人顧客向けにシームレスで直感的なサービス体験を実現しています。
アプリでは残高照会や取引履歴の確認に加え、資産管理ツールやローンの試算機能までワンストップで提供しています。特に評価されているのは、「りそなマイゲート」によるオンライン口座開設や各種手続きの非対面化です。
また、営業店ではタブレット端末を活用したペーパーレス化を進め、待ち時間の短縮と応対品質の均質化にも成功しています。こうした取り組みにより来店不要かつスムーズなサービス提供が可能になり、顧客満足度は向上しました。
さらに、同行は「デジタルと人の融合」をテーマに対面とデジタルを適切に組み合わせたハイブリッドな顧客対応を目指しています。このアプローチは、高齢層の利用者が多い地方銀行ならではのニーズに対応した戦略であり、今後の地域金融の在り方に一石を投じています。
ふくおかフィナンシャルグループ(FFG)は地域金融グループとして独自のDXビジョンを掲げ、顧客起点での業務革新を進めています。注目すべきは、社内に設置された「デジタル戦略部」と「デジタル人財育成制度」です。
FFGは地方銀行としては先駆的に「デジタルバンキングアプリ」を開発し、地域住民が気軽に利用できる金融サービス環境を整えています。このアプリでは、単なる残高確認に留まらず、公共料金の支払い・証券口座連携・家計簿機能など多機能な構成が特徴です。
また地域中小企業向けには、オンラインでの融資申し込みや経営相談に対応する「デジタルビジネスサポート」が導入されています。これにより、資金繰りの改善や事業拡大を目指す企業の支援がスピーディーに行える体制が整いました。
さらに注目すべきは、FFGのDX人材育成への取り組みです。社内でのデジタル研修やハッカソンなどを通じて、全従業員がDXに関与する文化を醸成しています。テクノロジーと地域密着の両立を図る姿勢は、多くの金融機関にとって参考になるでしょう。
東海東京フィナンシャル・ホールディングスは、証券業界におけるDXの先駆者として評価されています。デジタル戦略の中心には「Tochiya DXプロジェクト」があり、業界の常識を覆すような大胆な取り組みが特徴です。
同社は顧客の資産運用を支援するために「ロボアドバイザー」や「AIアナリスト」を活用し、個人投資家が安心して意思決定できる環境づくりに注力しています。これにより、初心者でも手軽に投資を始められるサービスが整備され、投資人口の裾野拡大につながっています。
また社内業務においては、業務プロセスのデジタル化を積極的に進めており、営業報告や顧客対応履歴のデータベース化により、情報の一元管理と分析の精度向上を実現しました。これが顧客対応の質を高め、クレーム削減やリピート率の向上につながっています。
「リアルとデジタルの融合」「顧客理解に基づく提案力の強化」という観点から、東海東京フィナンシャルの取り組みは証券会社におけるDXの理想的モデルといえるでしょう。
SBIインシュアランスグループは、保険業界におけるDXの先進事例として広く知られています。従来、保険商品は複雑でわかりづらいという課題がありましたが、同社は「見える化」と「自動化」によりその壁を取り払っています。
最大の特徴は、AIを活用した保険料シミュレーションとリスク分析です。これにより、契約者は自身のライフスタイルに合わせて最適な保険プランを自動で選定できるようになりました。また、加入から保険金請求までの一連のプロセスもオンライン上でスムーズに完結する設計となっています。
さらに、保険商品ごとの契約状況やカバー範囲、更新時期などをアプリで一括管理できるため、契約者は常に情報を把握しながら保険を活用できます。加えて、チャットボットによる問い合わせ対応も導入されており、迅速で的確なサポート体制が構築されているのです。
このように、SBIインシュアランスグループはテクノロジーの導入を通じて「わかりやすさ」と「使いやすさ」を追求し、保険のハードルを下げた点で高く評価されています。
金融DXを成功に導くには技術導入だけでなく、経営の視点から全社的に取り組むことが不可欠です。
ここでは、金融機関がデジタルトランスフォーメーションを効果的に推進するための5つのステップを紹介します。
最初に着手すべきは、DXの方向性を経営戦略と連動させることです。単なるIT導入ではなく、DXは業務の変革や顧客価値の創出を目的とした企業変革の手段です。
例えば地域密着型の金融機関であれば、地元企業や住民に対してどのように価値を提供するのかという視点が重要になります。経営陣がDXの必要性と目的を明確に認識し全社のビジョンと統一することで、現場の理解と協力を得やすくなります。トップダウンで戦略を落とし込むだけでなく、現場の実情に合った柔軟な方針も必要です。
次に行うべきは、現状業務の棚卸しと課題の可視化です。デジタル化によって業務効率化を図るには、何が非効率なのか、どの業務が重複しているのかを明確にする必要があります。
この際に有効なのが、業務フローの見える化とペインポイント(業務上の悩みや非効率なポイント)の抽出です。現場ヒアリングや業務データの分析を通じて属人化しているプロセスやシステム間の連携不足といった問題を整理していくと、改善余地の大きな領域が浮かび上がります。これにより、デジタル投資の優先順位を明確に設定できます。
DXを進める上で軽視してはならないのが、現場の声です。現場担当者の意見を無視して施策を進めてしまうと、システムが形骸化するリスクが高まります。
現場で働く従業員は、実際に日々の業務でどのような障壁や非効率があるかよく把握しています。彼らの視点を取り入れた上で施策を設計することで、実効性の高いDX推進が可能になります。また、現場との対話を重ねるとDXに対する理解と納得感が深まり、推進後の定着もスムーズになります。
DXを成功させるためには、技術やツールだけでなくそれを活用できる「人」の育成が欠かせません。外部ベンダーに任せきりにせず、自社内にDXを推進できる人材を育てる取り組みが求められます。
まずは、リスキリング(学び直し)を通じて既存従業員にデジタル知識を身につけさせる研修制度の整備が必要です。特にデータ分析や業務プロセス設計、プロジェクトマネジメントに関するスキルは重要視されています。
加えて、新卒や中途採用を通じてDX専門人材の獲得にも注力する必要があります。多様なバックグラウンドを持つ人材が加わることで社内の発想やアプローチにも幅が生まれ、変革を加速させる原動力となるでしょう。
DX推進は短期的なプロジェクトではなく、継続的な改善が求められる取り組みです。そのためには、あらかじめKPI(重要業績評価指標)を定めて施策の効果を定期的に評価する仕組みを構築する必要があります。
KPIの例としては、「顧客満足度の向上」「業務処理時間の短縮」「システム稼働率の改善」などが挙げられます。数値目標を設定し定期的なレビューを行うことで、達成度を把握しながら次のアクションを検討できるのです。
加えて、KPIの達成状況に応じて施策の方向性を柔軟に見直すようにしましょう。一度設定した方針に固執せず実績とフィードバックに基づいて最適化を図ることで、DXの成果を最大化できるでしょう。
これまで述べたように、金融DXの推進には戦略策定から業務改善・人材育成・成果検証までを一貫して実施する必要があります。しかし、これらすべてを自社だけで完結させるのは現実的に難しいという声も多く聞かれます。
そこで頼れるのが、DX支援の実績を持つ『株式会社 TWOSTONE&Sons』です。当社は金融業界に特化したDXコンサルティングを提供しており、業務課題の整理からシステム導入、プロジェクトマネジメントまで、ワンストップで支援しています。
単なるIT導入ではなく、「経営に資するDX」を目指す企業の皆さまにとって当社のノウハウと伴走型支援は大きな武器となるでしょう。ご相談は随時受け付けておりますので、金融DXをお考えの企業はぜひお気軽にお問い合わせください。

金融業界におけるデジタルトランスフォーメーションは、単なる一過性のブームではありません。少子高齢化や顧客ニーズの多様化、フィンテック企業の台頭など業界全体が抜本的な変革を求められている中、DXは持続可能な成長を実現するための中核的な戦略といえます。
本記事で紹介した「5つのステップ」は、DXを確実に推進するための実践的な手引きです。戦略と現場の融合、人材育成、そして定量的な評価を通じて、金融機関はより強固な経営基盤を築いていけるでしょう。
そしてその過程において、信頼できるパートナーを選ぶことが成功のカギを握ります。『株式会社 TWOSTONE&Sons』は、金融DXの未来をともに描き、ともに進める伴走者として皆さまをサポートいたします。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
