金融DXの推進によって叶う勘定系システムの刷新|4つの取り組み例を紹介
金融

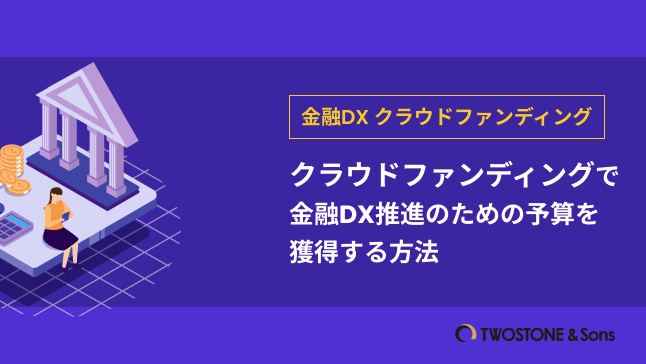
金融DXを推進するための資金確保の方法や、クラウドファンディングの活用メリット、顧客への説明ポイントを詳しく解説します。DX推進に悩む金融機関向けに、実践的な資金調達戦略をご紹介します。
「金融DXを進めたいけれど、予算が足りない」このような悩みを抱える中小規模の金融機関やベンチャー企業は少なくありません。DX(デジタルトランスフォーメーション)はもはや業務効率化のためだけの施策ではなく、顧客との関係を維持し競争優位を築くために不可欠な戦略になっています。
しかし、導入に必要な資金や専門人材の確保は容易ではなく、「最初の一歩」を踏み出すことに大きなハードルを感じている企業も多いのが実情です。そこで注目したいのが、クラウドファンディングという新たな資金調達手法です。
本記事では、金融DXの概要や必要性、推進の障壁を整理しながら、クラウドファンディングを活用して予算を確保する実践的な方法を解説します。あわせて、デジタル化の実現を支援するパートナー選びのポイントにも触れていきます。DX推進の足がかりを探している方にとって、有益なヒントが得られるでしょう。

金融DXとは、「デジタル技術を活用して金融サービスや業務の価値を抜本的に向上させる取り組み」を意味します。単なる業務のIT化ではなく、組織全体の体制やサービス設計、顧客体験までを包括的に変革することが求められます。
AIによる資産運用アドバイスの提供、チャットボットによる問い合わせ対応、クラウドベースのデータ分析による営業戦略の最適化などが、金融DXの具体的な例です。これらはすべて、顧客の利便性向上と企業の競争力強化を目的としたものです。
金融業界においてDXが進むことは、社会全体のデジタル化と連動してよりスマートで効率的な金融サービスの提供につながります。
金融DXは一過性のブームではなく、持続的な経営戦略として定着しつつあります。なぜ今、金融DXがこれほどまでに求められているのでしょうか。その背景には、顧客ニーズの変化、競争環境の激化、そして技術革新の進展があります。
ここでは、それぞれの観点から詳しく掘り下げていきます。
現代の消費者は、時間や場所を問わず利便性の高いサービスを求める傾向が強まっています。スマートフォン1つで口座開設から資産運用まで行える時代において、従来の対面営業や店舗中心のモデルだけでは、顧客の期待に応えきれなくなっています。
このような背景から、顧客接点のデジタル化が求められているのです。モバイルアプリの提供やオンラインチャネルの強化、パーソナライズされたデジタルマーケティングの活用によって、より密接な関係を築けます。金融DXは、こうした顧客接点の変化に対応するカギとなるのです。
金融業界は今や大手銀行や証券会社だけでなく、フィンテック企業や異業種からの参入によって、競争が激化しています。従来のサービス内容やブランド力だけでは差別化が難しくなっており、いかに先進的なテクノロジーを活用して新しい価値を提供できるかが問われています。
例えば、AIを活用したクレジットスコアリングや自動運用ツールによる投資提案などは、競合との差別化を図る有効な手段です。新しい視点でのサービス展開が顧客の支持を得るための重要な要素となります。
DXは顧客向けのサービス強化だけでなく、内部業務の効率化にも大きな影響をもたらします。事務手続きの自動化やAIによる審査業務の効率化、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)による定型業務の代替などは人的リソースの最適化につながります。
こうした取り組みにより、人件費の削減だけでなく、人的ミスの低減や業務品質の向上といった副次的なメリットも期待できるでしょう。リソースを戦略的な業務へ再配置するためにも、業務効率化の視点は欠かせません。
金融サービスの提供においては、システムの安全性と柔軟性がさらに重要になっています。旧来のオンプレミス型システムではスピード感のある開発や拡張が困難であり、時代の変化についていけなくなるリスクがあります。
一方、クラウドベースのインフラやAPI連携を活用することで、より迅速かつ柔軟なサービス展開ができるでしょう。サイバーセキュリティへの対応や障害発生時のレジリエンス向上といった観点からも、システムの高度化は避けて通れない課題です。
金融DXの必要性は広く認識されつつありますが、実際に推進しようとするとさまざまな障壁が立ちはだかります。中でも多くの企業が共通して直面するのが、組織体制や予算、技術人材といった現実的な問題です。
ここでは、特に金融業界で見られる5つの典型的な壁について解説します。
DXの推進には、全社的な取り組みと明確な意思決定が不可欠です。しかし、経営層がDXの意義や目的を十分に理解していないケースでは、必要な投資判断が後回しにされがちです。中長期的な視点に立ち、戦略的にDXを位置付けることが求められます。
現場でいくら意欲があっても、トップの理解と支援がなければ進捗は望めません。まずは経営層に対しDXがいかに経営課題を解決し、競争力を高めるかを可視化して伝える必要があります。例えば「業務効率が何%改善する」「顧客満足度がどの程度向上する」といった数値的根拠を交えながら説明することで、納得感が生まれるでしょう。
また、経営層が自らDXの旗振り役となることも重要です。社内のDX推進チームの設置や、定例の進捗確認会議への参加など、経営層が積極的に関与する姿勢を見せることで全社的な推進力が生まれます。DXは単なるIT投資ではなく、企業の変革と持続的成長のための経営戦略そのものであることを、まずは経営トップが深く理解する必要があります。
古い基幹システムがDX推進の足かせとなっているケースは多く見られます。部分的なカスタマイズが繰り返された結果、全体構造が複雑化して新たな技術との統合が困難になることがあります。このようなレガシーシステムは保守運用に過剰なコストがかかるだけでなく、柔軟な対応ができないため、市場環境の変化にも追随しづらくなるのです。
こうした状況では、段階的なシステム刷新やマイクロサービスの導入によって柔軟な構成への移行を図らなければなりません。まずは周辺システムからクラウド化し、徐々に基幹システムへと移行していく「ストラングラー・パターン」などのアプローチが効果的です。
また、技術的な壁を乗り越えるには、外部の専門的な知見を取り入れる判断も欠かせません。SIerやコンサルティングファームとの連携を通じて現行システムの課題を客観的に分析し、将来を見据えた最適なアーキテクチャを設計することが必要です。レガシーからの脱却は一朝一夕には進みませんが、計画的なロードマップを描きながら確実に一歩ずつ前進しましょう。
金融業界では、IT人材の確保が大きな課題です。特にAI・クラウド・データ分析など先端分野に強い人材は市場での争奪が激しく、内製化が困難な企業も少なくありません。その結果、DXを推進するためのプロジェクトが立ち上がってもリソース不足で思うように進まないケースが散見されます。
そのため、外部のパートナー企業や専門家との連携が現実的な選択肢になります。システム開発を担うだけでなく、戦略立案やPoC(概念実証)フェーズから支援してくれるパートナーを選定することが成功のカギとなるのです。
さらに、長期的な視点で見れば自社内における人材育成も欠かせません。OJTや専門研修、資格取得支援制度などを通じて、社内でDXを牽引できる人材を計画的に育成する必要があります。最近では、他業種からの人材転換や副業人材の活用といった多様な採用アプローチも注目されています。
また、IT部門に頼るだけでなく業務部門の社員もデジタル技術に関心を持ち、積極的に関与する文化を育てることがDXの浸透を後押しすることがあるでしょう。人材の質と量をどう確保し、どのようにプロジェクトに配置するかがDX推進の成否を左右するのです。
金融業界は、長年にわたって安定性と信頼性を重視してきた背景から変化に対して慎重な傾向があります。そのため、新しい技術やワークフローの導入に対して心理的な抵抗が強く働くケースが多いです。これにより、現場では「今のままで問題ない」「変えるリスクが大きい」といった消極的な意見が根付いてしまい、DX推進のスピードが鈍化する傾向があります。
このような文化を変えるには、一度にすべてを変えようとするのではなく小さな成功を積み上げることが効果的です。例えば、一部部署やプロジェクト単位で新しいツールや業務フローを導入して明確な成果を社内で共有することで、「DXは難しくない」「変化は利益を生む」という実感を醸成できます。
また、社内での情報共有やオープンな対話の場づくりも重要です。定例のミーティングでDX事例を紹介したり現場の声を吸い上げる仕組みを作ったりすることで、ボトムアップ型の変革が起きやすくなります。心理的な抵抗を和らげるためには、単に指示を出すのではなく、変化の「意義」と「具体的なメリット」を丁寧に伝え、共感を得る姿勢が不可欠です。
大きな障壁の1つが、資金調達の問題です。DX推進には、システム開発費・人材確保・研修などさまざまなコストがかかります。特に中小企業にとっては、初期投資を捻出することが大きな負担になるかもしれません。
ここで注目されているのが、クラウドファンディングという手法です。「クラウドファンディング」といわれてもどのように告知してどのように集めればよいのかわからない方もいるでしょう。次からは、このクラウドファンディングを活用して金融DXのための資金を集める方法について、具体的に解説していきます。
金融DXを実現するには、戦略立案からシステム開発、社内教育、外部パートナーとの連携に至るまで多くの資源が必要になります。中でも「予算の確保」はすべての施策の土台となる最重要課題です。限られたリソースをどのように活用し、どのように外部からの支援を得るかがDX推進の成否を左右します。
ここでは、金融DXを加速させるために効果的な3つの予算確保方法について解説します。
最も基本的かつ即効性のあるアプローチが、既存予算の見直しです。すでに社内で割り振られている各部門の予算を精査し、費用対効果が低い業務や非効率な運用が行われている領域からDX関連の施策に資源をシフトさせます。
例えば、紙ベースでの業務が多く残っている部門においてはデジタルツールの導入によって生産性を向上させられる可能性があります。その一方で従来型のマーケティング手法が十分な効果を発揮していない場合は、デジタルチャネルへの投資へと切り替えることが必要です。
予算再配分の過程では、部門ごとのKPI(重要業績評価指標)や業務プロセスの可視化が不可欠です。数字にもとづいた合理的な意思決定を行うことで社内の納得感を得やすくなり、DX推進に向けた風土の醸成にもつながるでしょう。
国や自治体が提供する助成金や補助金制度の活用も、DX予算を確保する有効な手段です。中小金融機関をはじめ、デジタル化に遅れを感じている事業者向けに国はさまざまな制度を設けています。
例えば「IT導入補助金」や「事業再構築補助金」は、DX関連の機器導入やシステム開発、外部人材の活用費用などが対象となっており、導入初期の負担を軽減できるでしょう。
ただし、申請には煩雑な書類作成と計画書の提出が求められます。公的支援制度に詳しい専門家や外部パートナーと連携しながら、制度の選定から申請、実施、報告に至るまで計画的に取り組むことが成功のカギです。これにより予算面での不安を解消しつつ、より戦略的なDX投資が可能になります。
近年注目されている手法が、クラウドファンディングによる資金調達です。従来はスタートアップ企業やクリエイター向けというイメージが強かったクラウドファンディングですが、現在では地方銀行や信用金庫などの金融機関でも活用事例が増えています。
クラウドファンディングは不特定多数の個人や企業から小口で資金を募る仕組みで、資金集めだけでなくマーケティングやブランディングにも効果があります。金融機関が地域の顧客や企業と共に新しいサービスを創出していく過程を「見える化」することで、共感を得やすくなり、支援者とのつながりも強まるでしょう。
資金調達だけでなくプロジェクトそのものを通じて顧客との信頼関係が構築されるため、単なる資金提供以上の価値が期待できます。

クラウドファンディングは単なる資金調達手段にとどまらず、顧客との共創やサービス改善、ブランド価値の向上といった複数の側面からDX推進を後押しする役割を果たします。ここでは、金融機関がクラウドファンディングを通じて得られる具体的な5つのメリットについて掘り下げていきます。
クラウドファンディングは、金融機関と顧客との共創を促進する手段として機能します。資金提供者である顧客は単なる「利用者」ではなく、プロジェクトの「共創者」として関わることになります。このような関係性は、従来の一方的なサービス提供とは異なり、双方向の価値創造を可能にするでしょう。
例えば、金融サービスのデジタル化に向けたアイデア募集やテスト版のユーザー体験などに支援者を巻き込むことで、ユーザー視点を取り入れたプロジェクト運営が実現します。これによりサービスの完成度が自然と高まり、実際の利用における満足度も向上しやすくなるでしょう。
クラウドファンディングでは、どのようなリターンが好まれるか、どのプロジェクトが支持を集めるかといったデータを通じて顧客の関心やニーズを定量的に把握できます。これは、マーケティングリサーチとしても有効です。
例えばある地域で高齢者向けのスマホアプリの導入が高い支援を集めたとすれば、そのニーズに即した展開を加速させる判断材料になります。このようにクラウドファンディングは、実際の顧客データにもとづいたPDCA(計画・実行・評価・改善)を支援するツールとして機能します。
金融機関にとって地域との結びつきは重要な価値です。クラウドファンディングを通じて地域住民や企業と連携すると、地域密着型のブランドイメージを強化できます。
プロジェクトの内容や進捗、結果を丁寧に発信することにより透明性や誠実さが伝わりやすくなり、地元メディアやSNSでの話題化を通じて、自然な広報効果も得られます。これは、若年層を含む新たな顧客層との接点が生まれるきっかけにもなるのです。
クラウドファンディングでは、支援者からのコメントやSNS上での意見などリアルタイムのフィードバックを受け取ることができます。こうした意見は、プロジェクトの方向性を見直す上で極めて貴重です。
特にDX施策においては、技術面での正解があってもユーザーの受容度や使用感が伴わなければ定着しません。支援者からのリアルな声を起点に柔軟な修正や改善を行うことで、現場のニーズに即したサービスが形になります。
クラウドファンディングは、支援者との新たな接点を生み出します。金融機関にとって、直接の取引がなかった個人や企業がプロジェクトを通じて興味を持ち、結果的に新規顧客となる可能性が高まります。
特に、地域や業界をまたいだ広がりを持つプロジェクトでは、普段アプローチできない層との接点が生まれる点が魅力です。また、支援者が自らのネットワークにプロジェクトを紹介することで、口コミによる拡散効果も期待できます。
クラウドファンディングで資金調達を行う際には、支援を募る顧客や地域住民に対して透明性の高い情報提供が不可欠です。金融DXという専門性の高いテーマを扱うからこそ、内容を丁寧に噛み砕き具体的かつ誠実に説明することが信頼の構築につながります。
支援者が安心して応援できるように、資金の用途を明確に示す必要があります。
例えば「オンラインバンキングのインターフェース刷新」「AIを活用した審査業務の自動化」「モバイルアプリのUX改善」など、資金が投じられる技術開発の詳細を説明します。また、導入予定のツールや外部ベンダーとの協業内容も併せて提示すると、より納得感を高められるでしょう。
抽象的な説明では支援のモチベーションは高まりません。どの技術にいくら投資し、どのような成果を期待しているかを数字や工程として具体化することで、支援者の信頼を獲得しましょう。
資金が投入されるプロジェクトの成果が、最終的にどのように顧客体験を向上させるのかを説明します。
例えば「24時間365日対応のチャットボットによる相談体制の構築」「スマートフォンひとつで完結する口座開設プロセス」など、利便性やスピード、安全性の向上に焦点を当てると共感を得やすくなるでしょう。
また、金融知識に不安があるユーザーにも伝わるよう、専門用語を避けながら「もっと簡単に」「もっと安全に」「もっと早く」といった日常の課題解決を軸に説明することが大切です。
プロジェクト開始後の進捗や成果を定期的に報告する体制を整えることは、信頼を維持する上で不可欠です。
定期的なメールマガジンやSNSでの活動報告、専用のウェブサイトやダッシュボードの設置など、可視化された情報提供は支援者の納得感と参加意識を高めます。加えて、開発中の裏話や従業員の声などを発信することで、プロジェクトへの共感を育めます。
透明性のある情報共有によって、支援者との長期的な関係構築が進められるでしょう。
支援者が安心して資金提供できるよう、目標金額やその達成基準を明示することが大切です。
目標金額は「必要最低限の機能を実装するためのミニマムライン」から「全機能を搭載するための最大ライン」まで段階的に設定すると、プロジェクトの規模感を具体的に伝えられます。また、資金の用途と金額の対応関係を説明すると、支援額の妥当性が理解されやすくなるでしょう。
このように明確な数値目標を設定することが、支援者の行動を促す大きな要因となります。
クラウドファンディングでは、金銭的な支援に対して何らかのリターンを設けることが一般的です。金融機関が取り組むDXプロジェクトにおいても、支援者への特典を工夫することで、参加意欲を高められるでしょう。
例えば「サービス先行体験の権利」「限定ウェビナーへの招待」「プロジェクトメンバーとの交流会への参加権」など、非金銭的な価値の提示が有効です。リターンは支援金額に応じて階層的に設けると、多様な層からの支援を集めやすくなります。
実際に支援すると得られる体験価値を明確に伝えれば、プロジェクトの魅力向上につながるでしょう。
金融機関がDXを推進する際には、単なるシステム導入にとどまらず、地域や顧客との信頼関係を深めながら変革を進めることが重要です。特にクラウドファンディングを活用した取り組みは資金調達手段としてだけでなく、その後の共創やブランド価値向上を実現する手段として注目されています。
『株式会社TWOSTONE&Sons』は、金融業界に特化したDX支援の経験を活かし、クラウドファンディング実施後の伴走支援に力を入れている会社です。資金調達後のシステム構築のサポートも可能です。
調達後のフェーズでは、いかに地域や顧客の期待に応え、透明性と共感を伴うプロジェクト運営を行えるかがカギとなります。私たちは、貴社のビジョンや戦略に寄り添いながら、持続的な成果へと導くための具体的な支援を行います。クラウドファンディングのその先を見据えたパートナーとして、貴社の変革をともに実現してまいります。
金融DXに本気で取り組みたいとお考えのご担当者様は、ぜひ一度ご相談ください。

金融機関にとってDXはもはや選択肢ではなく、時代の要請です。しかし、技術の導入や組織改革には少なからず資金が必要であり、そこをどう乗り越えるかが成功のカギを握ります。
今回紹介した「既存予算の再配分」「助成金の活用」「クラウドファンディングの導入」といった方法は、それぞれ異なるアプローチから金融DXの予算確保を支援する有効な手段です。中でもクラウドファンディングは、資金調達に加えて顧客との関係強化やブランド価値向上も期待できる、時代に合った手法といえます。
今後、より一層多様化・高度化する金融サービス市場において持続可能な経営と顧客価値の最大化を実現するには、戦略的な資金確保が不可欠です。自社に合った手段を選び、DXの取り組みを加速させましょう。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
