金融DXの推進によって叶う勘定系システムの刷新|4つの取り組み例を紹介
金融

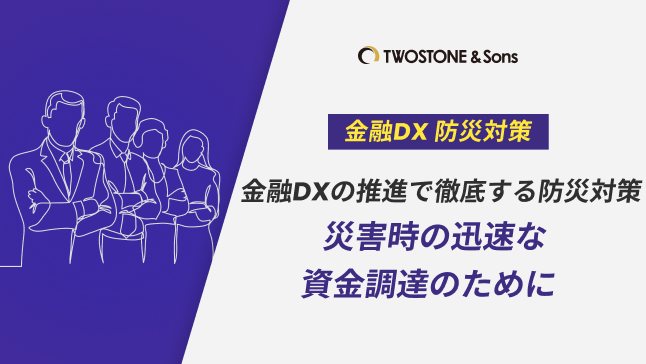
金融DXと防災対策の両立は、今後の業務継続に不可欠です。書類の電子化や顧客対応のデジタル化に加え、セキュリティ強化や従業員教育も重要な要素です。災害に強い体制づくりを進めるために、株式会社TWOSTONE&Sonsが金融機関のDX支援を行っています。
近年、世界中で自然災害が頻発し、企業にとってもその影響を無視できなくなっています。特に金融機関においては、災害時の迅速な資金調達が事業の継続性を保つために欠かせません。
しかし、災害時の対応力は単に備えをしておくだけでは不十分です。金融機関が今後の災害に備え、そして迅速に行動できるようにするためには、どのような対策が求められるのでしょうか。
ここで注目すべきなのが、「金融DX(デジタルトランスフォーメーション)」です。金融DXの推進は、従来の業務をデジタル化して効率化するだけでなく、災害時の迅速な対応を可能にする重要なカギです。
本記事では、金融DXがどのように防災対策と関連し、企業にどのようなメリットをもたらすのかを深掘りします。災害発生時に迅速かつ適切な資金調達を実現するために、金融機関がどのように備えを進めていけばよいのか、そしてそれをどのようにDXがサポートするのかについて解説します。
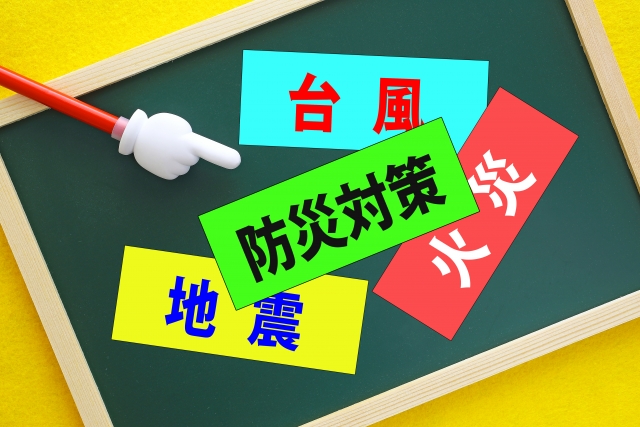
最近より注目され始めている「防災・減災」対策について、企業独自の取り組みが進められているだけでなく”国の施策”として動き出していることをご存じですか。
デジタル化が進む現代社会において、金融DXは単なる業務効率化の手段ではありません。防災という観点から見ても、顧客の命や生活を守るために不可欠な仕組みです。
ここでは、まず金融DXの基本的な意味を確認し、それがどのように防災対策と結びつくのかを紐解いていきます。
参考:内閣府
金融DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、デジタル技術を活用して金融業務を根本から再構築して顧客価値の向上や競争力の強化を目指す取り組みです。単に紙業務をデジタル化するだけでなく、データを中心に据えた意思決定やAI・クラウドなどの先端技術を活用した新たなサービスの創出まで含まれます。
例えばオンラインバンキングが普及すると、顧客は店舗に足を運ぶことなく手続きを完了できます。さらに、チャットボットによる24時間対応や不正検知AIによるセキュリティの強化も、金融DXの具体例です。
このような取り組みにより、金融機関は従来の業務を効率化しながら顧客へのサービス品質を高めています。
金融業界における防災対策とは、災害時においても業務を継続して利用者の資金ニーズに応えられる体制を整えることを意味します。具体的には、BCP(事業継続計画)の策定や遠隔地へのシステムバックアップ、代替拠点の確保などが挙げられます。
また災害時にはATMの稼働継続や現金の供給確保が求められるため、物理的なインフラとITの連携が重要です。さらに、通信障害時にも最低限のサービスを維持するためのオフライン対応や、緊急時専用の顧客サポート体制の整備も防災対策の一環とされています。
これらはすべて、金融機関が「社会インフラ」としての責務を果たす上で欠かせない要素です。
金融DXの推進が防災対策に直結する理由は、迅速な情報共有と業務復旧が可能になるためです。クラウド基盤を活用したシステム構築により、物理的な被害を受けても遠隔地から安全にアクセスし業務を再開できるようになります。
加えて、顧客情報や取引履歴のデジタル管理が進んでいれば、被災地においても本人確認や融資判断をスムーズに行えます。これによって緊急時の資金提供や支援金の振り込みなどを迅速に実施でき、顧客の生活再建を後押しできるでしょう。
このように、金融DXは単なる業務改革にとどまらず非常時の対応力を根本から底上げする力を持っています。特に近年の災害リスクを踏まえると、DXによる事前準備があるか否かで災害時の金融機関の信頼性は変わるといえるでしょう。
金融機関は社会基盤としての役割を担っており、災害時にも業務を止めるわけにはいきません。近年の自然災害の激甚化を受け、単なるリスク回避ではなく顧客資産の保護や社会的責任を果たす意味でも、防災対策は喫緊の課題となっています。
金融機関の業務はシステムへの依存度が高く、物理的拠点やネットワークの一部が停止するだけで全国的にサービス提供が困難になるケースがあります。例えば地震によってデータセンターが被災すれば、口座取引や送金業務がストップし利用者の生活に直結する混乱が発生します。
こうしたリスクに備えるには、被害を未然に防ぐだけでなく業務を迅速に再開する仕組みが不可欠です。クラウド基盤への移行や遠隔バックアップの導入など、ITを活用した柔軟な体制構築が求められます。金融DXはこうした技術的対応を支える土台となり、災害による業務停止リスクを最小限に抑える力を持っています。
金融機関の基本的な役割の1つは、顧客の資産を安全に管理することです。しかし、災害時には通帳やキャッシュカードの紛失、ATMやオンラインバンキングの停止などにより、預金の引き出しが困難になる可能性があります。このような状況下で、顧客資産へのアクセス性と安全性を確保することが、金融機関の信頼性を左右するのです。
日本銀行は災害時における金融機関の業務継続を支援するため、さまざまな対策を講じています。例えば、災害発生時には、金融機関に対して預金通帳や印鑑を紛失した顧客への便宜払戻しや損傷した日本銀行券の引換えなどの「金融上の措置」を要請しています。また、被災地の金融機関が早急に営業を再開できるよう、営業時間の延長や休日の臨時営業を行うよう要請することもあるのです。
デジタルトランスフォーメーション(DX)の活用も、災害時の金融サービスの継続に有効です。例えば、分散型台帳技術(ブロックチェーン)を活用することで、データの消失リスクを軽減できます。また、災害時専用の緊急支払いインターフェースを整備することで、最低限の金融サービスを提供し続ける体制を確保できます。
このように、日本銀行の防災対策やDXの活用により、災害時にも顧客への影響を最小限にとどめ、信頼の維持につながる具体的な備えを実現することが可能です。
参考:日本銀行
金融業は、エネルギーや通信と並んで社会インフラに位置づけられる産業です。被災地では現金の流通や公共料金の支払い、保険金の給付といった金融サービスが地域住民の生活再建に直結します。そのため、他の業界以上に迅速な復旧が求められるのです。
例えば、自治体が発行する災害見舞金の受け取りや被災企業が運転資金を確保するための融資手続きは、スピードが命となります。オンライン申請や電子契約、即時送金の仕組みが整っていれば、支援を一刻も早く届けられるようになります。
これらの機能を担保するためには、あらかじめ災害時を想定した業務プロセスの見直しが必要です。デジタル化を通じた仕組みの再構築は、復旧スピードを高めるカギとなります。
自然災害は物理的な被害をもたらすだけでなく、情報セキュリティにもリスクを及ぼします。浸水や火災によって紙の帳票やサーバーが損壊すれば、顧客情報や機密データの漏えいに直結するでしょう。また、金庫や現金を保管する設備が破損すれば、資産の喪失という深刻な被害も招きかねません。
こうした問題を防ぐためには、物理資産への依存を減らして情報や資産をデジタル上で安全に管理する体制が重要です。例えば、セキュリティ性の高いクラウドストレージの活用や生体認証による本人確認の導入が、データ保護の強化につながるでしょう。
また、紙の書類を必要としないワークフローへの転換も災害時のリスクを軽減する有効な手段です。DXによって情報の分散保存やアクセス権限の細分化が可能になれば、万が一の際にも情報漏えいを未然に防げるでしょう。
災害時に金融機関が果たすべき役割は年々重要性を増しており、その備えとしてBCP(Business Continuity Plan:事業継続計画)の存在が欠かせません。BCPは災害やシステム障害が発生した際に、どの業務をどの順序で復旧させるかを明確にする指針です。
近年では、BCPを単なるマニュアルとして残すのではなくDXと連携させる動きが活発になっています。実際に、リアルタイムで災害状況を把握して支店ごとの復旧優先度をAIが自動で判断するシステムの導入が進んでいます。さらにクラウドベースのツールを使えば、従業員が遠隔地からでも業務を継続できるようになり、人的リソースの柔軟な再配置が可能になるでしょう。
BCPの高度化は単なる危機対応力の向上にとどまらず、平時からの業務効率化や顧客サービスの品質向上にも直結します。結果的に企業の競争力そのものを高める取り組みへとつながっていくのです。
金融業界が災害に直面した際に迅速かつ的確に対応するためには、事前の備えだけでなく実際に起こった時にどう動くかが極めて重要です。業務継続と顧客保護、さらには地域社会の早期復旧に貢献するため、金融機関は多面的な対策を講じています。
ここでは、災害時に金融業界が実際に実施している主な施策を詳しく見ていきましょう。
金融機関がまず優先すべき対策の1つが、業務データの保全です。災害によって本店やセンターが被災した場合でも、重要な顧客情報や取引データを守るためには地理的に離れた場所へのバックアップが欠かせません。
例えば本店が東京にある場合、九州や北海道などの地震リスクが異なる地域にデータセンターを設け、リアルタイムでデータを複製しておくのが効果的です。これにより、いずれかの拠点が被災しても、もう一方で業務を再開できる体制が整います。
さらに、クラウドベースのバックアップも近年注目されています。物理的なインフラに依存せずインターネット経由でデータを保管・復旧できるため、災害時の対応スピードが向上するのです。このような仕組みは、金融機関にとってリスク分散の観点からも意義があります。
災害発生後、店舗への来店が困難になるケースは少なくありません。道路の寸断や交通機関の麻痺、さらには建物の損壊など、物理的な制約により対面での対応が著しく制限されます。
そのため、オンラインバンキングやモバイルアプリを活用した非対面取引環境の整備が急務です。これにより、預金の引き出しや振込、ローンの申し込みなどが顧客自身のスマートフォンやパソコンから安全に実行できます。
特に高齢者やITに不慣れな層にも配慮し、操作が簡単でわかりやすいインターフェースを提供することが重要です。災害時こそ、すべての利用者がストレスなく金融サービスを利用できる環境を整える必要があります。
金融機関には、地域経済の再建をサポートする社会的責任があります。災害時には被災した企業や個人に向けた特別融資や返済猶予措置などの支援策が展開されるため、事前に確認しておきましょう。
例えば中小企業向けには、無担保・無利子での緊急融資が提供されるケースが多くあります。これにより、事業の立て直しや資金繰りの改善が可能となり、地域全体の経済活動の再起が促進されるのです。
また個人に対しても、住宅ローンの返済猶予や新たな生活再建資金の貸付など、柔軟な対応が行われます。これらの支援は、迅速な告知と手続きの簡素化によって実効性を高める必要があります。
地震や台風などの自然災害では、特定の支店が物理的に使用不能になるリスクが常に存在します。そうした状況に備え、業務の分散化を事前に進めておくことが求められるのです。
一例としては、コールセンター業務や事務処理を複数の拠点に分ける取り組みが挙げられます。これにより、いずれかの施設が使用不能になっても他の拠点で代替業務が可能となり、業務の停滞を回避できます。
また災害時に一部の店舗が臨時閉鎖された場合、近隣の支店や提携ATMネットワークと連携して顧客サービスの継続を図る体制も重要です。現場単位ではなく全社的に柔軟な運用ができるよう、日頃からの訓練やマニュアル整備が不可欠です。
金融機関は多くの従業員を抱えており、その安全確保は最優先事項です。災害が発生した際には、迅速な安否確認と連絡体制の整備が業務継続にも直結します。
従業員の安否確認には、専用の安否確認システムや緊急連絡網を活用する方法が有効です。メールやアプリを通じて即座に安否状況を把握し、必要に応じて救助や代替勤務体制を調整できる環境を整えましょう。
さらに、役員・管理職から一般職員まで、災害時の行動指針をあらかじめ共有しておくことが重要です。「どこに集まるべきか」「誰に連絡するのか」「何を優先すべきか」などを明確にしておくことで、混乱を最小限に抑えられるでしょう。
金融機関が自然災害に対して迅速かつ的確に対応するためには、発生時の行動だけでなく平時からの備えが極めて重要です。特にシステムや人員の対応能力を高めておくことで業務継続性を確保して、利用者の信頼を維持できるのです。
ここでは、災害発生時に慌てず対応するために事前に整備・確認しておくべき取り組みについて解説します。
まず基盤となるのが、安定したデジタルインフラの整備です。近年、金融サービスの大半がオンライン化しており、サーバー・ネットワーク機器・通信回線といった情報インフラの停止は業務の停止に直結します。だからこそ、災害時にも機能する耐障害性の高いシステム設計が必要です。
具体的には、サーバーを冗長構成にするUPS(無停電電源装置)や自家発電設備を備える通信経路を多重化しておくといった対策が効果的です。さらに、これらのインフラは設置して終わりではありません。定期的に保守点検を行って老朽化や故障の兆候を早期に発見し、未然にトラブルを防ぎましょう。
また、クラウド環境との連携も災害対策に有効です。クラウドストレージにデータを二重保存することで、地震や水害で物理拠点が被害を受けてもサービス提供が継続できるでしょう。
万一の際に現場が混乱しないためには、緊急時にどう動くかを定めたマニュアルの存在が不可欠です。マニュアルには、対応の手順だけでなく誰がどのような役割を担うのかを具体的に明示しておくことが求められます。
例えば、「第一報を誰がどこに伝えるのか」「顧客対応チームはどう編成されるのか」「社内通報・報告ルートはどうなっているのか」などを細かく記載しておくと、緊張状態にあっても冷静に行動できます。
マニュアルの整備に加えて、普段からその内容を共有しておくことも重要です。全従業員が同じ情報を共有しているかどうかが初動の質に影響します。紙媒体だけでなく、クラウドや社内ポータルサイトなどでの閲覧性も確保しておきましょう。
災害時には本社や拠点の建物に出社できないケースも少なくありません。そのため、リモートで業務を継続できる環境の整備が不可欠です。ノートパソコン・モバイルWi-Fi・VPN(仮想プライベートネットワーク)接続などテレワークに必要な機器やインフラを平時から用意しておきましょう。
また、業務システムへのリモートアクセスが安全かつスムーズに行えるようセキュリティ対策と利便性のバランスを考慮した構成が求められます。加えて従業員ごとの自宅環境や通信状況もあらかじめ把握し、必要に応じてサポートできる体制を整えておきましょう。
いざという時に機器の不具合や接続トラブルで対応が遅れることを防ぐため、定期的な動作確認や接続テストも忘れずに実施しておきたいところです。
どれだけマニュアルを整備しても実際の現場で即座に実行できるとは限りません。そこで有効なのが、定期的な災害対応訓練やシミュレーションの実施です。これは座学だけではなく、実際に災害が発生した想定で行うロールプレイ方式の訓練が効果的です。
例えば「地震によってデータセンターの一部が停止した」「大雨で一部従業員が出社できない」といった状況を設定し、社内での連絡・業務の優先順位づけ・顧客対応などをシミュレーションすることで、問題点や改善点が明確になります。
さらに、訓練の成果を記録に残し、フィードバックを取り入れてマニュアルや運用体制を改善していくことも、災害対応力の底上げにつながります。形式的な訓練にとどまらず、実践的な内容を重視したプログラムを組むよう意識しましょう。
金融機関の業務は、システム会社や警備会社、ビル管理業者など多くの外部ベンダーに支えられています。そのため、災害時にこれらの外部パートナーとどのように連携するかをあらかじめ確認し、合意形成しておくことが不可欠です。
例えばシステム障害が発生した際に、どのタイミングで連絡を取り、どのようなサポートを受けられるのか、緊急時専用の連絡先や対応窓口はどこかといった点を事前に把握しておきましょう。契約書にBCP(事業継続計画)への対応を盛り込むと対応責任の所在を明確にできます。
また、ベンダー側の災害対策体制がどのようになっているかをヒアリングし、自社のBCPと整合性が取れているかを確認する作業も欠かせません。平時から信頼関係を築いておくことで、いざという時の対応力が変わってくるでしょう。

自然災害が頻発する現代社会において、金融機関は事業継続性の確保と利用者の信頼維持のために、DX(デジタルトランスフォーメーション)を通じた防災体制の強化が求められています。そのためには、単にITツールを導入するだけでなく組織全体で段階的に防災DXを推進することが重要です。
ここでは、金融DXを活用して防災対策を強化するための7つのステップを紹介します。
最初に行うべきは、自社の防災体制がどのような状態にあるかを正確に把握することです。なぜなら、現状認識が不十分なまま対策を講じても効果的な改善にはつながらないからです。
例えば災害発生時にどのような業務が止まるのか、復旧にどれくらいの時間がかかるのか、誰がどのような対応を行うのかといった点を明確にします。併せて、過去の災害時における問題点や社内で共有されていない情報の有無も洗い出しましょう。
この段階では部署横断的にヒアリングを行い、紙ベースで管理されているマニュアルや業務手順も見直すと実態に即した課題を明確にできます。現状を正確に把握することで、次のステップに向けた基盤が整います。
防災対策の効果を高めるには、全業務を一律に扱うのではなく重要性に応じて対応の優先順位を明確にする必要があります。
金融機関にとって、取引データの保全や資金決済、システムの稼働状況など停止によって甚大な影響を及ぼす業務が存在します。こうしたクリティカルな業務を特定し、復旧目標時間(RTO)や復旧目標時点(RPO)を設定することで現実的かつ効果的な防災戦略が立案できるでしょう。
この段階で業務ごとのリスク評価(Business Impact Analysis:BIA)を行い、被害想定と影響度を数値で見える化することは重要です。こうしたデータに基づいて優先順位をつけると、限られた資源を影響の大きい分野に集中させるという判断ができるのです。
災害発生時には、出社困難や人員不足などが生じやすくなります。そうした状況下でも業務を継続させるには、非対面で対応可能なITツールの導入が不可欠です。
具体的には、電子契約システム・ビデオ会議ツール・チャットボットによる顧客対応・ペーパーレスのワークフローシステムなどを活用することで、物理的な制約に左右されない業務体制を構築できます。
例えばオンライン上で口座開設手続きやローン申請が完結できる仕組みを整えれば、災害時でも顧客の利便性を確保できます。非対面での業務継続が可能になれば感染症など新たなリスクにも柔軟に対応できるため、防災だけでなく平時の業務効率化にもつながるでしょう。
業務のデジタル化を進める上で、データの安全性と可用性を担保することは重要です。災害時にサーバーやネットワークが停止した場合でも業務継続を実現するために、クラウド環境への移行が有効です。
クラウドサービスを利用すれば、地理的に分散されたデータセンターにバックアップを保持でき、災害による単一拠点の障害リスクを低減できるでしょう。またアクセス権限の管理や暗号化機能を活用することで、セキュリティ面でも安心です。
例えば、Amazon Web Services(AWS)やMicrosoft Azureなどの信頼性の高いクラウドサービスに基幹業務システムを移行すれば、災害発生後も迅速にサービスを再開できます。クラウド導入は、DX推進の柱としても位置づけられるのです。
いかに優れたITインフラを整えても、それを扱う従業員が適切に運用できなければ意味がありません。そのため、定期的な教育と誰でもすぐに対応できるマニュアルの整備が必要です。
教育内容には、災害発生時の初動対応・ITツールの操作方法・顧客への適切な対応方法などを含めると実用性が高まります。また、マニュアルは紙媒体とデジタル両方で管理し、災害時にもアクセス可能な状態を確保しておきましょう。
一例としてオンライン研修やeラーニングを活用すれば、全従業員が場所を問わず受講でき、知識の標準化を図ることが可能です。人材教育とマニュアル整備は、組織全体の対応力を底上げするための基盤といえるでしょう。
計画通りに対応できるかどうかを確かめるには、実地訓練による検証が不可欠です。訓練を通じて対応の不備や連携不足が可視化され、改善のヒントを得られるでしょう。
訓練内容は想定される災害シナリオに基づき、システム障害時の対応・顧客へのアナウンス方法・遠隔地勤務体制の構築など実際の業務に即した内容とします。定期的に実施することで、習熟度の向上も期待できるでしょう。
例えば「震度6強の地震で本社機能が麻痺した」という想定で、BCP(事業継続計画)に基づく行動をチーム単位で検証します。その結果をふまえて計画をブラッシュアップすることで、実効性の高い運用体制が築かれていくのです。
最後に重要なのが、実施した対策の効果を客観的に測定し、継続的に改善する姿勢です。PDCAサイクルを回すことで、防災体制の成熟度を高められるのです。
効果測定には、訓練後のアンケート・対応スピードの分析・復旧時間の短縮状況などを指標として活用します。数値に基づいた改善提案を行い、上層部を巻き込んだ意思決定プロセスを整備することがポイントです。
また、外部の専門家によるレビューを取り入れると、客観的な視点から改善点を見出せます。防災DXは一過性のプロジェクトではなく、組織文化として根付かせることが最終目標となります。
金融DX(デジタルトランスフォーメーション)は、将来的なシステムの刷新や大規模な予算を必要とするイメージを持たれがちですが、実は今日からでも取り組める小さなステップも数多く存在します。特に防災の観点では、「いざという時」に機能する柔軟な業務体制や情報の可視化が不可欠です。
ここでは、すぐに実行可能な金融DXの具体例を3つ紹介し、それぞれが防災対策にどう寄与するのかを詳しく解説します。
業務で扱う多くの書類を電子化することは、災害時においても情報の確保と業務継続に貢献します。
例えば契約書・申請書・報告書などが紙ベースで管理されている場合、それらがオフィス内に保存されていると地震や水害などで物理的に失われるリスクが高くなります。しかし電子化された書類はクラウド上で保管されていれば、どの場所からでも安全にアクセスでき、業務の再開も容易になるでしょう。
加えて、ペーパーレス化によって書類の検索・共有のスピードが上がるため、通常時の業務効率も向上します。業務フローを見直し、まずは使用頻度の高い帳票や申請書から電子化を始めるのが効果的です。電子署名ツールやワークフロー管理システムを導入することで、手続きの完全な非対面化も実現できるでしょう。
災害が発生すると、店舗や窓口の営業が難しくなるケースが多々あります。そのような時に役立つのがチャットボットやオンライン窓口、モバイルアプリなどを活用した非対面の顧客対応です。
例えば、LINEやメールによる定型通知を使うと、災害発生時の営業状況や避難情報を即時に共有できます。この機能によって顧客の不安を軽減し、信頼関係を維持できるのです。
また、ビデオ通話によるリモート相談や本人確認が可能な電子契約システムの整備によって、支店に足を運ばなくても手続きが完了する体制を整えられます。こうした取り組みは災害時に限らず、平常時にも利便性の向上という観点で価値を発揮します。
顧客の属性やニーズに合わせたチャネル選定と導入が求められますが、まずは既存のウェブサイトやアプリの機能拡張から取り組むのが現実的です。
デジタル化を進める上で避けて通れないのが、サイバーセキュリティの確保です。防災対策とセキュリティ対策は一見異なる分野のように見えますが、実は密接に関係しています。
例えば災害時に情報システムがダウンした場合、その復旧プロセスにおいてもセキュリティの確保は不可欠です。バックアップデータの保管場所が物理的に安全なだけでなく、第三者からの不正アクセスを防ぐための暗号化やアクセス制御が求められます。
また、サイバー攻撃と自然災害が同時に発生する「複合災害」のリスクも近年注目されています。こうしたリスクに備えるためにも、ゼロトラストモデル(すべてのアクセスを信頼せず常に検証するというセキュリティ方針)の考え方を取り入れたシステム設計が有効です。
小規模な金融機関であっても、クラウドセキュリティや多要素認証の導入など今すぐできる対策は多数あります。外部の専門業者と連携しながら、自社の業務特性に合ったセキュリティプランを段階的に整備していくことが重要です。
金融業界におけるDX(デジタルトランスフォーメーション)は、防災対策としても力を発揮します。しかし、その導入や運用には慎重な姿勢が求められます。特に、セキュリティや業務ルール、従業員教育など事前に整えておくべき事項を見落とすと、かえって混乱を招く恐れがあるのです。
ここでは、金融DXを推進する際に注意すべき4つの観点について詳しく紹介します。
デジタル化が進むほど、外部からの不正アクセスや内部からの情報漏えいといったサイバーリスクも高まります。特に金融業界では顧客の個人情報や口座情報などの機密データを多数扱うため、セキュリティ対策は最優先事項です。
例えばクラウドサービスを導入する場合、通信の暗号化やアクセス制限を適切に設定しなければ、外部攻撃の標的となる危険性があります。また、業務委託先との情報共有においても、契約上のセキュリティポリシーを明文化して遵守状況を定期的にチェックする必要があります。
社内全体で「情報資産を守る」という意識を高めると同時に、セキュリティ専門部署の設置や外部ベンダーとの連携強化も視野に入れましょう。
デジタルツールを導入しただけでは、期待される業務改善効果は得られません。運用ルールが整備されていないと現場での混乱や属人化が生じ、かえって非効率に陥る可能性があります。
例えば、チャットボットを導入したのに回答内容の管理責任が曖昧で顧客満足度が下がる、電子承認フローが複雑すぎて、業務スピードが落ちる、などがその典型例です。
このような事態を避けるには、業務フローに合わせたシステム設定と関係部署間での役割分担の明確化が不可欠です。あわせて、導入前には必ず業務プロセスを可視化し、DXによって何を改善するのかを全員が理解している状態をつくりましょう。
DXを進める上ではシステム依存度が高まる反面、そのシステムが停止した時の業務継続策も考慮しなければなりません。特に自然災害の発生時や通信障害が起きた場合、業務のすべてをデジタル上で完結させていると対応に窮する恐れがあります。
具体的には、システム障害時にも一部業務が遂行できるよう、紙ベースのマニュアルや代替手順を用意しておくことが有効です。また、重要なシステムについてはバックアップ環境や自動フェイルオーバー機能の構築も視野に入れましょう。
BCP(事業継続計画)の中にITの観点を組み込み、非常時のオペレーション体制を事前に整備しておくことで、万が一の事態にも冷静に対応できます。
いくら高度なデジタルツールを導入しても、それを正しく活用できる人材がいなければ本来の効果は発揮されません。特に防災対策と関わる場面では状況判断や適切なシステム操作が求められるため、従業員一人ひとりのITリテラシーが重要です。
ITリテラシーとは単にパソコンを使えるという意味ではなく、デジタルツールの仕組みを理解し、目的に応じて使い分けられる能力を指します。例えば、業務チャットの正しい使い方やファイルの安全な共有方法、個人情報の取扱いルールなど実務に即した教育が求められます。
定期的な研修やeラーニングを導入して全従業員のスキル底上げを図るとともに、新たなツールの導入時には操作ガイドやマニュアルの整備も徹底しましょう。
金融DXと防災対策の両立を目指す際には、専門的な知見と業務理解を併せ持ったパートナーの存在が不可欠です。『株式会社TWOSTONE&Sons』は、災害時の業務継続や情報インフラの整備に関して多方面からサポートを行っております。
特に、現場に即したDXの進め方やITツール選定、BCP支援に関して豊富なノウハウを有しており、お客様ごとに最適化された提案をいたします。
業務改善を目指しながらも、防災という観点を欠かさずDXを進めたいとお考えのご担当者様は、ぜひ一度ご相談ください。

金融機関が果たすべき最大の使命は、平時だけでなく有事においても社会基盤としての機能を維持し続けることです。災害時に混乱を最小限に抑えて速やかに業務を再開するためには、日頃からの備えと柔軟な体制づくりが求められます。
そのためには、金融DXを単なる業務効率化の手段と捉えるのではなく、防災・減災を視野に入れた包括的な戦略として位置づけることが重要です。今すぐ取り組める施策から始めて、段階的にシステム・人・ルールの整備を進めていきましょう。
『株式会社TWOSTONE&Sons』は、貴社の災害対策とDX推進を全面的にサポートいたします。不測の事態にも強い金融機関を目指すために、ぜひ私たちの専門知見をご活用ください。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
