AIエージェントとマルチエージェントの基本情報や活用例を徹底解説!
全般

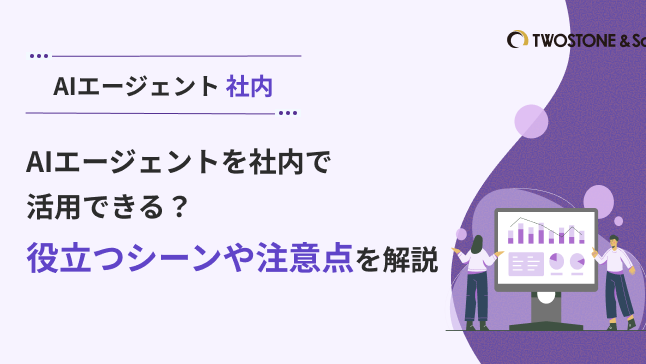
AIエージェントの活用は業務効率化やコミュニケーションの改善に役立つと考えられ、社内のさまざまな場面で注目されています。しかし、その効果を引き出すには適切な活用方法や運用ルールの整備が欠かせません。業務の自動化や情報共有の円滑化を目指す企業が増える中、AIエージェントを社内で活かす具体的なシーンや注意点を理解することが大切です。
本記事ではAIエージェントの社内活用例を5つ紹介し、導入時に気をつけたいポイントについても解説します。AIを取り入れる際には単に技術を導入するだけでなく、組織のニーズや現場の実情に合った使い方を模索しながら進めることが求められます。これにより従業員の負担軽減や業務の質の向上につながるでしょう。

AIエージェントは社内の多様な業務に役立つ可能性を持ち、効率的な運用を促進すると考えられます。具体的には、問い合わせ対応からスケジュール管理、タスク進捗の把握まで幅広い領域での活用が検討されているため、導入を検討する際にはどのような場面で使えるかを把握することが大切です。
ここでは、具体的な活用例や適用範囲についてわかりやすく解説しますので、参考にしてください。
社内ヘルプデスクは、従業員が日常業務で直面する多様な疑問や問題に対応する役割を担っています。AIエージェントがこの窓口を支援することで、頻繁に寄せられる基本的な質問に自動的に対応する体制が整うでしょう。
こうした対応をAIが担当すると人的リソースの節約につながるだけでなく、対応速度の向上も期待されます。また、AIが対応履歴を蓄積・分析することでどのような問い合わせが多いか把握でき、社内マニュアルの改善やFAQの充実に役立つかもしれません。ヘルプデスク業務の質を保ちつつ、従業員の満足度を高めるのがポイントです。
このようなハイブリッド体制により、AIと人間の強みを活かしながら効率的なサポートが促進されるでしょう。
社内で利用される業務マニュアルや規定、手順書は膨大であり、必要な情報を探し出す作業は時間や労力がかかりやすいです。AIエージェントは自然言語処理の技術を活用し、従業員からの問いかけを理解しながら関連資料を瞬時に検索し提示する支援が期待されます。
こうした検索支援はキーワードだけでなく文章の意図も考慮して検索結果を出すため、単純な検索ツールよりも利用しやすい環境にできるのがポイントです。また、ITに詳しくない従業員でも使いやすいインターフェースを提供することで、幅広い層の業務効率化に寄与します。
加えて、情報の更新があった場合にもAIが関連する社員に通知するなど、情報共有の円滑化に貢献しやすい点も特徴です。こうした即時検索支援により、社員の疑問解消や業務の迅速な遂行をサポートできる環境づくりが進むでしょう。
社内では会議の予定調整やスケジュール管理に時間が割かれがちですが、AIエージェントはこうした業務を効率的に支援します。従業員のカレンダー情報を把握しながら参加者の空き時間を照合し、最適な会議日時を提案できる点に注目しておきましょう。
さらに、会議室の予約状況も同時に管理し、予約の競合を避ける調整も含めて自動化が期待されます。通知機能により参加者へのリマインダー送信も行えるため、予定忘れや遅刻のリスク軽減に寄与します。
議題や参加メンバーに応じて必要な資料の共有を促す設定もでき、事前準備の手間を減らせるのがポイントです。こうした機能は管理職や事務担当者の負担軽減につながるだけでなく、スムーズな社内コミュニケーションの促進にもつながります。
タスク管理はチームの生産性を維持する上で欠かせない要素ですが、その進捗把握や期限管理は人手に頼ると漏れや遅延が発生しやすくなるので注意しましょう。
AIエージェントはタスクの登録や進捗状況を自動で追跡し、遅延の兆候があれば早期に知らせる仕組みを持つことが考えられます。これにより、タスクの抜けや遅れを未然に防げます。
また、期限が近いタスクにはリマインダーを送り、担当者が忘れずに業務に取り組める環境を整えましょう。こうした機能はプロジェクトマネジメントにおいても役立ち、チーム全体のスムーズな連携を促すことが期待されます。
AIを活用したタスク管理は人間の目では見落としがちな課題を早期発見する役割を担う可能性があるため、適切に取り入れることが望まれます。
従業員からの意見やフィードバックを集めるアンケートは組織の改善に欠かせませんが、実施や集計、分析には時間と労力を要することも少なくありません。
AIエージェントはアンケートの作成や配信、リマインダー送信まで一連の作業を自動化し、運用負担を軽減する役割を果たせます。集まった回答を自然言語処理で分類し、回答傾向や重要な意見を抽出しやすくする機能も活用できるのがポイントです。
単にデータを集めるだけでなく有効なインサイトを得て経営判断に反映しやすい環境を整えられます。回答率の向上を促すために、タイミングやリマインド頻度を調整する仕組みも取り入れましょう。
こうしたAIの活用により従業員の声を効果的に収集・分析することが可能となり、組織運営の質向上につながる期待が高まります。
AIエージェントを社内業務に取り入れることで、日々の業務フローにさまざまな前向きな変化が期待できます。業務効率の改善や情報共有の迅速化、属人化の抑制など部門や役職に関係なく組織全体に良い影響を与えるかもしれません。
ここでは、AIエージェントを活用することで得られる主なメリットについて、具体的に紹介します。各項目が相互に関連し合いながら、業務環境の整備にどう寄与するのかを考察していきましょう。
日々の業務において、確認作業や情報検索、定型業務の対応に時間を取られてしまうケースは少なくありません。AIエージェントを活用することで、こうした反復的な業務を自動化・簡素化する取り組みが進みやすくなります。例えば、過去の対応履歴を基に適切な回答を提示するサポートやスケジュール調整のような細かい作業の支援が挙げられます。
また、AIによる支援は時間帯に関係なく提供されるため、勤務時間外に情報を確認したいときにも役立つのがポイントです。これにより無駄な待機時間や手戻りが発生しにくくなり、全体的な業務の流れが滑らかになる傾向が見られます。結果として時間の使い方に対する意識が変化し、各従業員の業務パフォーマンス向上にも好影響をもたらします。
社内での問い合わせ業務は、担当者にとって見えにくい負荷となることが多いです。繰り返される類似の質問やマニュアルに記載されている内容への対応に時間を割くことで、本来の業務が滞ることも多いです。AIエージェントを取り入れることにより、よくある問い合わせに対する一次対応を任せる体制を築きましょう。
例えば、パスワードの再発行手順や勤怠管理システムの操作に関する基本的な質問など定型的な内容はAIが即時に回答し、担当者の対応工数を抑える形が想定されます。これにより人間による対応はより判断を要する問い合わせに集中できるため、全体の対応品質の維持・向上につながります。
部門やプロジェクトごとに異なる情報が蓄積されている場合、必要なデータへ迅速にアクセスすることが難しくなります。そうした状況を改善する手段として、AIエージェントによる情報共有支援が注目されました。AIが社内のドキュメントやナレッジベースを検索対象として扱うことで、必要な情報にすぐにたどり着きやすくなる仕組みが整います。
この情報探索の効率化は、特に新人や異動直後の従業員にとって有益です。業務に不慣れな段階でも自ら質問を入力すれば該当する資料や手順を参照できるため、早期の立ち上がりが期待されます。加えてメールやチャットでの情報共有にかかっていた時間を短縮できる可能性もあり、全体の業務スピードに良い影響を与えます。
特定の業務が一部の従業員に依存している状態では、急な退職や異動が業務全体に支障をきたすリスクが高くなります。こうした属人化を防ぐためには、業務手順やノウハウを可視化し、誰でも再現可能な体制を整える必要があります。AIエージェントは社内に散在する業務知識を一元的に管理し、必要なタイミングでそれを提供する役割を担うのがポイントです。
例えば、過去のプロジェクト進行における手順や注意点などをAIが学習し、新たに着任した社員に対して同様の進め方を提示するといった活用法が考えられます。これにより業務の再現性が高まり、標準化された業務フローの確立に寄与するかもしれません。
AIエージェントの活用は、業務そのものの効率化だけでなく職場環境の快適さや働きがいにも好影響をもたらします。煩雑なタスクやルーティン業務から解放されることで従業員はより創造性や戦略性を求められる業務に集中しやすくなるため、仕事への満足度やモチベーションが向上します。
さらに、疑問点や業務上の不明点がすぐに解消できる環境が整えば、心理的な不安やストレスを軽減する効果も期待されているので注目しておきましょう。特に在宅勤務やフレックスタイム制を取り入れている企業において、孤立感の解消にも役立ちます。AIがいつでも問い合わせに応じる体制があれば、業務の流れを中断せずに作業に集中できます。

AIエージェントは、業種や規模を問わずさまざまな企業で業務支援の手段として取り入れられています。多くの企業が情報共有の効率化や業務負荷の軽減、人材育成の側面など複合的な目的でAIエージェントの活用を進めています。その背景には、単なるツール導入にとどまらない、組織としてのDX推進に向けた意識の変化があるので注目しておきましょう。
ここでは、実際にAIエージェントを導入している国内企業の事例を5つ紹介します。それぞれの導入背景と得られた効果、活用の工夫に注目して見ていきましょう。
KDDIでは、2023年に従業員向けに開発されたAIエージェント「KDDI AI-Chat」を社内で試験的に運用し、本格展開が始まりました。この取り組みは、業務に直結する場面でAIが実用的に使える環境を整えることを目的に進められてきました。利用シーンとしては、資料作成支援や会議準備、社内規程の確認など多岐にわたっており、部門ごとに最適化された利用が模索されています。
導入当初から現場のニーズを丁寧に拾い上げながらAIの学習データを整備する体制が取られており、汎用的な生成AIとは異なる「業務に根差した応答」が期待されているのがポイントです。業務内での問い合わせ時間の短縮や自律的な情報探索の促進といった効果が確認されており、AIエージェントが社員の業務支援役として浸透し始めています。現在も継続的にフィードバックが取り入れられており、実務での有用性を高める仕組みづくりが進行中です。
出典参照:社員1万人が「KDDI AI-Chat」の利用を開始|KDDI株式会社
ベネッセホールディングスでは、生成AIをベースとした社内専用の対話型AI「Benesse GPT」を約1.5万人の従業員が活用しています。この取り組みは業務効率化と業務知識の社内共有を推進するための一環として行われており、全社的なDX推進の一部として位置付けられました。
AIの活用例としては、会議資料のたたき台作成や既存文書の要約、学習教材の草案づくりなど業務の初期段階を支援する用途が目立ちます。従業員がAIと自然に対話する中で業務アイデアを膨らませたり見落としやすい論点を補足したりするケースも見られており、補助的なツールとしての役割が強調されています。
出典参照:社内AIチャット「Benesse GPT」をグループ社員1.5万人に向けに提供開始|株式会社ベネッセホールディングス
KDDIが社内実験として展開しているもう1つのAIエージェントが「A-BOSS(本部長AI)」です。営業現場で蓄積された知見やノウハウをAIに反映させることによって、若手や新任の営業担当者が的確なアドバイスを得られる環境を構築することを目指して始まりました。
AIは営業支援の立場として、商談の進め方や提案書作成の参考情報を提供し、日々の業務における判断や検討を補助する役割を果たしています。あくまで最終判断は人間が行うものの、過去のケースや傾向に基づいた示唆を与えることで営業活動の質の安定につながっているとの見解が示されています。
出典参照:AIエージェントとは生成AIからの進化点や導入事例、注意点など解説|KDDI株式会社
トヨタ自動車では、エンジニア同士の知見の共有や技術継承を目的に生成AIをベースとした社内エージェント「O-Beya(オオベヤ)」の導入が進められています。このAIは社内ドキュメントや過去の設計履歴、技術会議の議事録などを学習データとして活用しており、ベテラン技術者が長年にわたって培ってきた暗黙知を若手従業員にも活用できる仕組みとなっています。
技術的な課題に直面した際、若手がO-Beyaに質問することで過去の対応策や設計上の留意点といった情報を即座に確認できる構造が構築されました。知識が属人化しやすいエンジニアリング領域においてAIがその橋渡しを担う形となっており、技術伝承の時間的・空間的な制約を緩和する効果が期待されています。
出典参照:トヨタ自動車、エンジニアの知見を AI エージェントで継承へ ー 競争力強化に向け革新的な取り組みを開始|マイクロソフト株式会社
日清食品ホールディングスでは、全従業員が利用可能な生成AIエージェント「NISSIN AI-chat」を社内で展開しています。同社が掲げるDX推進の柱の1つとして導入されたもので、部署や職種に関係なく誰もが日々の業務でAIのサポートを得られる体制を目指しています。
企画書作成時のアイデア出しや業務マニュアルの要約、他部署とのコミュニケーションなどを含む業務全体を支援できる点が特徴です。こうした業務の一部にAIを取り入れることで作業の起点を効率化し、創造的な思考や戦略的検討に時間を使いやすくする工夫がされています。
出典参照:「デジタルを武装せよ」をスローガンに全社でデジタル技術を活用した“業務改革”を推進|日清食品ホールディングス株式会社
AIエージェントを業務に取り入れる企業が増える中で、活用にあたっての課題も顕在化しています。効果的に運用するには、事前のルール設計や社内理解の醸成が欠かせません。特に利用目的の明確化・従業員のプライバシー保護・アクセス権限の適正管理は、長期的に活用するポイントです。
ここでは、社内にAIエージェントを取り入れる際に考慮すべき具体的なポイントについて詳しく解説します。
AIエージェントを業務に組み込むにあたっては、どのような目的でどの業務領域に対して利用するかを明確に定義しておくことが大切です。目的や対象があいまいなまま運用し始めると、情報の誤用や非効率な活用につながる可能性があるためです。例えば、社内マニュアルの検索支援やFAQ対応など用途を限定して試験的にスタートする方法が効果的でしょう。
また、導入初期はAIが人間の業務を完全に代替するものではないという前提を社内で共有しておくことが推奨されます。どの業務を支援するのか、どこまでの判断を任せるのかといった設計がなければ、誤解を招いたり運用負荷が増えたりする懸念があるので注意しましょう。あらかじめ目的と範囲を明示し、段階的な展開を進めることで安定的な活用が実現しやすくなります。
AIエージェントを社内に導入する場合、従業員が安心して利用できる環境を整えるためにはプライバシーへの配慮が欠かせません。AIが扱うデータの中には従業員の発言や個人に関わる情報が含まれる場合もあるため、情報の取り扱いに慎重な対応が求められます。
特に注意すべきなのが、チャットログや会話履歴の保存方法と管理体制です。これらの情報が分析対象となる際は、個人を特定できないような匿名化処理を施すことがおすすめです。
社員の信頼を得るためには運用ポリシーや目的を明文化し、必要に応じて本人の同意を得るフローを取り入れるなど透明性のある仕組みづくりが必要です。こうした配慮がAI活用に対する不安を和らげ、組織全体での活用を促進する下支えになります。
AIエージェントは社内のさまざまな情報にアクセスできることから、情報セキュリティの観点でアクセス権限の管理が大切です。すべての従業員が同じ情報にアクセスできるように設定されてしまうと、業務に関係のない情報への閲覧や不適切な情報利用につながる可能性があるため、業務内容に応じたアクセス制御が求められます。
例えば、人事部門が扱う評価情報や経理部門の予算資料などセンシティブな情報については、AIエージェントが自動的に参照しないよう制限を設ける必要があります。また、部署ごとに閲覧可能なデータを区分けし、管理者が権限設定を見直せる体制を用意しておくと運用上のトラブルを未然に防げます。

AIエージェントは情報共有の促進や業務負荷の軽減といった多面的な効果が期待される一方で、社内での運用においては慎重な姿勢も求められます。目的と範囲を明確にした上で、社員のプライバシー保護や適切なアクセス制御を講じることによって安全かつ継続的に活用される環境が整います。
また、国内での導入事例からは、企業の規模や業種に関わらず工夫次第でAIエージェントが業務支援の一端を担える可能性が示唆されています。社内における業務改善やナレッジの共有を目指すにあたり、本記事の内容を参考にして自社に合った取り組みを検討してみると良いでしょう。