AIエージェントとマルチエージェントの基本情報や活用例を徹底解説!
全般

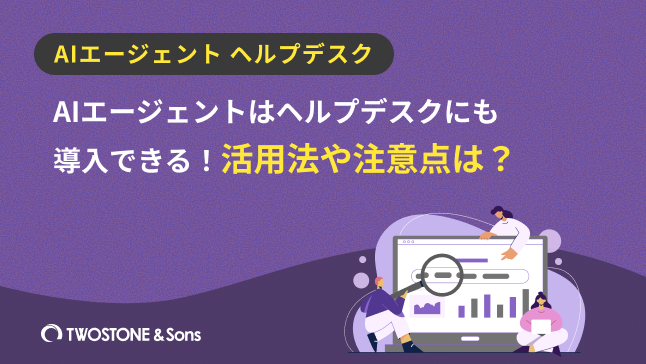
ヘルプデスクは企業の顧客対応や社内サポートの要として機能しますが、近年の業務量増加や問い合わせ内容の多様化によってその負担が増している傾向があります。こうした状況の中、AIエージェントの活用は業務効率化や対応品質の向上に期待が集まっています。
AIエージェントを活用すると24時間体制での問い合わせ対応や複雑な案件の振り分けが可能になり、人的リソースの節約にもつながりやすいのが特徴です。ただし単に技術を導入するだけでなく、運用の設計や適切な活用法の理解を求められるため注意が必要です。
本記事ではヘルプデスク業務で特に注目されるAIエージェントの具体的な活用法を5つの視点から詳しく解説し、業務改善に役立つポイントを紹介します。

ヘルプデスク業務におけるAIエージェントの活用は多様化しており、業務効率や対応品質向上に寄与しやすい施策がいくつも存在しています。中でもテキストチャットボットによる24時間対応のFAQ自動応答は、時間帯を問わず顧客の問い合わせに対応し続けられる点がメリットです。これらの技術は、互いに補完しながらヘルプデスクの質を高めることに寄与していくでしょう。
ここで紹介するのは代表的な活用方法を、5つです。
テキストチャットボットは事前に構築されたFAQやナレッジベースを活用し、ユーザーからの問い合わせに即時回答を提供します。これによって夜間や休日を含めた24時間対応が可能になり、顧客の疑問を迅速に解消できることが期待されるでしょう。
また定型的な質問に対するチャットボットの自動応答によってオペレーターの負担が軽減され、より複雑な案件に集中できる環境づくりに役立ちます。さらに利用者の反応や問い合わせ内容から学習し、応答の精度を高めていくため継続的にサービスの質が向上しやすい点も魅力的です。
ただしユーザー満足度の維持のためにはチャットボットで対応が難しい場合の、スムーズな人間への切り替え機能が不可欠となります。
問い合わせが多様化する中、AIによる自動分類と優先度判定はヘルプデスクの運営効率に寄与しやすいです。自然言語処理技術を用いて問い合わせの内容や緊急度を解析し、適切な部署や担当者に振り分けることで重要な案件が遅滞なく処理される体制を支えます。
こうした仕組みは担当者ごとの負荷を均等にし、迅速な対応を促進する効果も期待されます。とはいえ分類の精度を維持するには継続的なデータ収集とモデルの更新が求められるため、運用側の管理体制が欠かせません。また誤った分類を防ぐため、定期的な評価と改善作業を行う必要もあります。
音声認識技術を備えた音声エージェントは電話での問い合わせに対し、初期対応を自動化するケースが増えています。
顧客の話した内容をリアルタイムでテキスト化し、その情報を基にした案内や回答の提供により、単純な質問であれば人手を介さず解決が図れるようになります。これによってオペレーターの対応件数が減り、複雑な対応にリソースを割くことが可能になるため効率性が向上するでしょう。
近年の自然言語処理の進化によって人間に近い対話が実現し、利用者の満足度向上に寄与しやすいのも特徴です。ただし認識ミスや複雑な問い合わせには依然として人間の介入が必要なため、バランスの取れた運用が求められます。
AIエージェントは会話の内容をリアルタイムに解析し、自動で要約を生成してCRMシステムに連携する仕組みを支援しています。これによって対応履歴の共有がスムーズになり、担当者間の情報の重複や漏れを減らす効果が期待できるでしょう。
また手動でのデータ入力が不要となるため作業効率が上がり、入力ミスのリスクも軽減されます。これらの仕組みは業務の標準化にもつながりやすく、ヘルプデスクの全体的な品質向上に寄与し得ます。
ただし要約の正確さやCRM連携の整合性維持のためにシステムの継続的な点検や改善、運用体制の整備が必要とされる点に注意が必要です。
最近ではAIが顧客の言葉だけでなく声のトーンや話し方の変化を分析し、感情の動きを捉える技術も普及しつつあります。このリアルタイム感情分析によって不満や緊急度を早期に察知でき、オペレーターが適切なタイミングで介入しやすくなるため、応対品質の向上に役立つ可能性があります。
さらに蓄積されたデータは応対評価や教育にも活用され、ヘルプデスク全体のレベルアップにもつながりやすいです。ただし感情分析の精度には限界があり、誤検知や誤解を避けるための運用ルールやプライバシー保護の配慮も重要な要素となります。
ヘルプデスクにAIエージェントを導入する場合、事前に対応業務の範囲や目的の明確な設定が必要です。単に自動化を進めるだけでなくどのような業務に効果を期待し、ユーザーやオペレーターの負担軽減を図るかを具体的に定める必要があります。
また導入後の運用をスムーズに進めるためには、利用者のニーズや問い合わせの特徴を理解した上でシステム設計を行うことが必要でしょう。
ここでは導入時のポイントを、4つご紹介します。
AIエージェントの導入を成功させるためには、まず対応する業務の範囲と目的をはっきりさせておく必要があります。自動応答できる問い合わせの種類や範囲、対応レベルを具体的に決めておくことでシステムの設計や運用に無理が生じにくくなるでしょう。
例えばよくある質問への回答に限定するのか、複雑な問題の一次対応までカバーするのかで求められる機能やシステムの規模が変わります。またユーザー体験の向上やオペレーターの負荷軽減など、導入によって達成したい目的の共有も必要です。
これによって目標に合ったAIエージェントの性能や運用方法を検討しやすくなり、無駄な投資を抑えられる場合もあります。加えて目的や範囲が明確になることで関係者間の認識合わせがしやすく、導入後の混乱を防ぎやすくなります。
AIエージェントを効果的に運用するためには、ユーザーからの問い合わせパターンや過去の履歴データの詳細な事前分析が不可欠です。問い合わせ内容には傾向や頻度の高い質問が存在し、それらの把握によってAIの学習に適したデータを用意しやすくなります。
加えて利用者が用いる表現や言葉遣いを理解しておくと、応答精度の向上につながりやすいです。こうした分析を通じてよくある質問のカバー率を高め、誤解や対応漏れの軽減ができるでしょう。
また問い合わせの多様性や新たなトレンドにも対応できるよう、継続的なデータ更新やフィードバックの仕組みを設けておくことが望まれます。十分な準備により、AIエージェントが利用者の期待に応えられる確率が高まると考えられます。
AIエージェントが全問い合わせに対応するわけではないため、人間のオペレーターとの連携フローをあらかじめ設計しておくことが欠かせません。例えばAIが対応しきれない複雑な案件や感情的な対応が必要なケースでは、スムーズに人へ引き継ぐ仕組みが求められます。
この連携が滞ると利用者の不満につながりやすく、AI導入の効果が減じてしまう恐れがあります。具体的には引き継ぎのタイミングや方法、担当者の情報共有ルールの明確化によってシームレスな対応を実現する工夫が必要です。
またAIと人間の役割分担を明確にし、オペレーター側もAIの状況や対応履歴を確認しやすい環境を整えておくことも効果的です。このように連携フローの設計によって全体の対応品質を維持しつつ、効率化が進みやすくなります。
AIエージェントの効果を持続させるには、応答品質を継続的に改善するための運用体制の整備が欠かせません。AIは導入後も新しいデータを取り込み、ユーザーの問い合わせ傾向や表現の変化に合わせて精度を向上させる必要があります。そのため定期的なデータ更新や評価、フィードバックの仕組みが重要となります。
さらに誤った回答や対応漏れが発生した場合の原因分析や改善施策を迅速に行う体制も必要です。また担当者がAIの学習状況や性能を理解し、適切に調整できるスキルを持つことも望まれます。
こうした継続的なメンテナンスがあって初めて、AIエージェントが安定して高品質な応答を提供し続けることにつながります。長期的に見ればこの運用体制の充実が、導入効果を左右する重要なポイントとなるでしょう。

業務効率化やユーザー対応の質向上を目指して、AIエージェントをヘルプデスク業務に活用する取り組みが広がりを見せています。特に、多様なチャネルからの問い合わせ対応や、定型業務の自動化を求める企業にとって、AI技術の適用は有効とされる場面が増えています。
ここでは、ヘルプデスク領域で活用されている代表的なAIツールを取り上げ、それぞれの特徴と適用分野についてみていきましょう。
Zendesk AIは、顧客サポートに最適化されたAIエージェント機能を備えており、問い合わせ対応の効率化を図りたい企業の間で注目されているツールです。このツールの特徴として、自然言語処理技術による問い合わせ内容の自動分類や、過去のチケット履歴から導かれる推奨回答の提示などが挙げられます。
こうした機能により、サポート担当者は複雑なケースに集中しやすくなり、全体の応対品質を保ちやすくなります。また、Zendesk AIはナレッジベースとの連携機能も備えており、ユーザーが自己解決を試みやすい仕組みづくりにも活かされているようです。APIによる柔軟な拡張性にも配慮されており、既存システムとの統合もしやすい点が特徴です。
出典参照:Zendesk|株式会社Zendesk
Freshdeskは、電話・メール・チャット・SNSなど、複数のチャネルからの問い合わせを一元管理することを想定して設計されたAI対応のヘルプデスクツールです。
このプラットフォームにはAIアシスタントであるFreddy AIが搭載されており、ユーザーの質問意図を解析し、適切なナレッジ記事を提示する機能や、チケットの優先度判定を行う機能が組み込まれています。こうした機能は、担当者の判断負担を軽減し、対応スピードの改善に寄与しやすいとされています。
また、Freshdeskは、直感的なUI設計とグローバルな言語対応機能を備えており、多国籍チームでのサポート運用にも対応しやすい構成です。業務フローに応じた自動化ルールの設定もできるため、ヘルプデスクの運用に柔軟性を持たせたい場合に有用と考えられます。
出典参照:Freshdesk(フレッシュデスク)とは?|OrangeOne株式会社
IBM watsonx Orchestrateは、業務自動化における高度な連携性とワークフロー構築機能を備えたAIエージェントツールです。このツールでは、自然言語理解(NLU)とビジネスプロセス自動化(BPA)を融合させることで、業務担当者が個別の作業プロセスを可視化・最適化しやすい環境を構築しています。
特に、CRM・ERPなど既存の業務システムとAPI連携することで、問い合わせ内容に応じたデータ参照や処理の実行をスムーズに行える点が評価されています。また、複雑なワークフローをノーコードで設計できる点や、ユーザーのスキルに応じて自由に自動化範囲を設定できる柔軟性も、導入時の負担を軽減する要素です。技術部門と現場部門が連携しやすい設計であり、段階的なDX推進に取り組む企業に適していると考えられています。
出典参照:IBM watsonx Orchestrate|日本アイ・ビー・エム株式会社
AIエージェントは多様な業界のヘルプデスク業務で活用され、業務効率の向上やサービス品質の改善に寄与している例が増えています。各社が抱える課題や対応範囲に応じてシステムを最適化し、ユーザー対応の迅速化や運用コストの抑制を目指しているのが共通点です。これらの事例を参考に、自社に適した活用方法を検討するヒントが得られやすいでしょう。
ここで紹介するのはヘルプデスクへの導入を実現させた、企業3つです。
アサヒグループホールディングス株式会社では社内のITヘルプデスク業務の効率化を目的に、AIエージェントを活用しています。従業員からの問い合わせをチャットボットが一次対応し、よくある質問や手続き案内を自動化する仕組みが整えられました。
この導入によってヘルプデスク担当者の負担軽減が進み、複雑な問い合わせや特別なケースに集中できる環境づくりに寄与している様子が見受けられます。さらにチャットボットの回答履歴や利用状況の分析を通じて改善が続けられ、応答の精度やユーザー満足度の向上が期待されています。
これがAIエージェントの効果的な活用例として、注目されている運用です。
出典参照:社内のOAヘルプデスク業務に『AIヘルプデスク』導入|アサヒグループホールディングス株式会社
朝日生命保険相互会社では保険業務に関わる多種多様な社内照会に対応するため、AIチャットボットを導入しています。問い合わせ内容を自動で分類し、関連情報の検索や回答を速やかに行うことで従業員の作業効率を改善する狙いがあります。
照会回答システムの導入によって対応の均一化や迅速化が進み、ミスの減少や業務負担の軽減にも寄与しているといえるでしょう。さらにこのシステムは日々の利用データを学習し、継続的に応答の精度向上が進められている点も特徴的です。業務内容や規模に適合したAI活用が、社内ヘルプデスクの運営改善に役立っている事例といえるでしょう。
出典参照:生成 AI を活用した照会回答システムを導入|朝日生命保険相互会社
静岡銀行株式会社では社内手続きや問い合わせに対応するAIチャットボットを導入し、一次対応の自動化に取り組んでいます。従業員からの問い合わせに対し、よくある質問や手続きの流れの迅速な案内によって担当者の負担軽減が図られています。
さらにチャットボットの回答内容はCRMシステムと連携され、情報の一元管理が進められていることも運用効率化に貢献しているポイントです。導入後は利用状況や問い合わせ傾向の分析に基づいて応答内容の改善も行われており、AIエージェントの活用による社内ヘルプデスクの質的向上が期待される動きとなっています。
こうした取り組みは、同様の課題を抱える企業の参考になるでしょう。
出典参照:PKSHAと生成「AI」の活用に向けた共同研究等を開始|静岡銀行株式会社
AIエージェントはヘルプデスクの効率化や応答の迅速化に寄与する反面、運用上の課題や注意点も存在します。導入前にシステムの限界やユーザーの多様なニーズを見極めておくことが大切です。想定外の質問への対応や完全自動化の目標設定、適切なエスカレーション設計、そして学習データの質の確保などがAIエージェント活用の効果を左右しやすいポイントとなります。
ここで紹介するのは導入時の注意点、4つです。
AIエージェントは設計された範囲や学習したデータに基づいて応答するため、予期しない質問や複雑な問題には適切に対応できない場合があります。例えば曖昧な表現や専門的すぎる内容、ユーザー固有の事情に応じた質問では誤った回答や対応不能になるかもしれません。
こうした限界はAIの特性上避けがたいため、導入時にはその範囲を明確にしてユーザーにも理解を促すことが望まれます。また想定外の問い合わせが増えた場合に備え、改善のためのフィードバック体制や追加学習の仕組みの準備が効果的です。
AIの応答範囲と限界を見極めながら運用を進めることが、継続的な利用価値の維持につながるでしょう。
ヘルプデスクのAI化を進める際、すべての問い合わせ対応を自動化しようとする試みは慎重に検討する必要があります。全自動化が実現してもユーザーの期待やニーズに沿わない対応が増えることで、かえって満足度が低下しかねません。
特に感情的な対応や複雑な相談事に関しては、人間の柔軟な対応が不可欠でしょう。自動応答頼りではユーザーが求める、丁寧さや細やかな配慮が欠如するかもしれないためです。
したがってAIと有人対応のバランスを意識し、適切な役割分担を設けることが望まれます。段階的に自動化を進めつつ、利用者のフィードバックを反映しながら調整を加えることが満足度の維持につながりやすいと考えられます。
AIエージェントが対応できない問い合わせやクレーム発生時には、迅速かつ円滑に有人オペレーターへ引き継ぐフローの設計が必要です。エスカレーションのタイミングや方法が不明確であればユーザーに長時間の待ち時間や不十分な対応が発生し、結果としてサービス品質が損なわれるかもしれません。
そのためAIから人への受け渡しはスムーズで、必要な情報がオペレーターに確実に共有される仕組みが求められます。加えて担当者がエスカレーションを適切に判断できるよう、判断基準や操作手順の明確化も必要です。
こうした設計により、トラブルの早期解決とユーザー満足度の向上が期待されやすくなります。AIの強みを活かしつつ人間の判断や対応力を組み合わせることが、バランスの良い運用につながるでしょう。
AIエージェントの応答精度は学習に用いるデータの質や量に大きく依存するため、導入段階から適切なデータ整備が欠かせません。質の高いデータが揃っていなければ誤回答や不適切な案内が増え、ユーザーの信頼を損ねるリスクが生じます。
また学習データは多様かつ最新の問い合わせ傾向を反映する必要があり、継続的な更新と改善が求められます。さらに偏りのあるデータが学習されると一部の質問に対する応答が不適切になりやすく、全体の品質低下につながるかもしれません。
こうした問題を防ぐためには定期的な検証やチューニングを行い、データの品質を保ちつつ拡充していく体制が必要です。質の高い学習データを維持しながら運用を続けることが、安定した応答品質に寄与すると考えられます。

ヘルプデスクへのAIエージェントの導入により、問い合わせ対応の迅速化や業務負担の軽減が進みがちです。多くの企業事例に共通するのはAIが一次対応を担うことで、人的リソースをより専門的な対応に振り向けられる点です。
導入の際は自社の対応ニーズやユーザー特性に合ったシステム設計が重要視されやすく、応答品質の維持と向上を念頭に置いた運用体制の構築が求められるでしょう。記事を参考に、自社の業務改善の一助として検討してみてください。