AIエージェントとマルチエージェントの基本情報や活用例を徹底解説!
全般

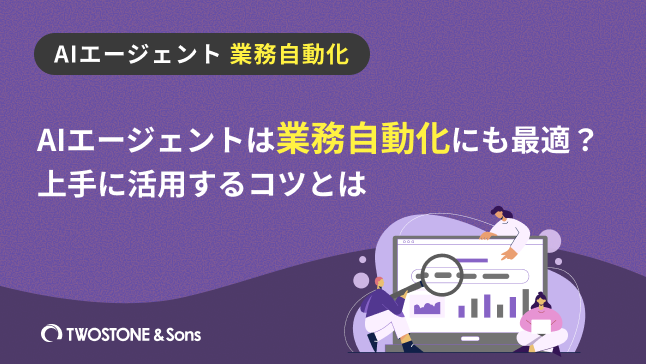
企業における業務効率化の手段として、AIエージェントの導入が注目を集めています。特に、定型的な事務処理やカスタマーサポート、データ処理など人間が手間と時間をかけていた業務をAIが代行することによって、業務全体の生産性向上が期待されています。
AIエージェントは、自然言語処理や機械学習、知識グラフといった複数の技術を組み合わせて人間のように判断し行動できるシステムであり、単なる自動化ツールとは一線を画す存在です。近年では、社内問合せ対応や人事手続き、受発注業務のサポートなどにも応用され、企業の働き方改革やDX推進を支える存在として広がりを見せています。
ただし、活用の幅が広い反面、設計や導入プロセス、運用フェーズにおいて注意すべき点もあるので事前に対策しておきましょう。
本記事では、AIエージェントが業務自動化に適している理由と、活用にあたっての重要な観点についてわかりやすく解説していきます。

AIエージェントが業務自動化の分野で支持を集める背景には、いくつかの明確な特性があります。中でも、定型作業の迅速な処理、24時間対応、コスト効率の良さ、複数タスクへの同時対応、継続的な学習と改善能力は多くの企業で求められている要素です。こうした特性をうまく活かすことで企業は限られたリソースの中でも業務全体を最適化し、従業員の負担軽減と価値創造業務への集中を実現しやすくなります。
ここでは、それぞれの特性について具体的に解説していきます。
企業の日常業務の中には、申請処理やデータ入力、報告書の作成といった定型作業が多く存在します。これらの業務は内容にばらつきが少なく、処理手順も明確であるため自動化による効率化の対象として最適です。AIエージェントはあらかじめルールやフローを学習し、それに基づいて一貫した処理を行うことで人的ミスのリスクを抑えながら正確なアウトプットを実現します。
さらに、事前に構築されたナレッジベースやデータベースを参照しながら業務を進めるため、対応スピードが速く処理の抜け漏れを減らす効果も期待できます。これにより、人手で対応していた頃と比べて業務の進捗が安定し、他の業務へリソースを割く余裕も生まれるでしょう。
人間の労働には限界がある一方で、AIエージェントは時間や曜日に関係なく常時稼働できます。この特性はカスタマーサポートや社内ヘルプデスクなど、即時対応が求められる部門にとって有効なメリットです。
例えば、深夜や休日に寄せられた問い合わせにもリアルタイム対応ができることで顧客や従業員の満足度の向上が期待できます。このように、24時間体制の業務運用を支える存在としてAIエージェントは働き方の多様化やサービスレベルの向上に貢献しています。
AIエージェントの導入によって人手に依存していた業務の一部を自動化することで、人的リソースを別の付加価値の高い業務へ再配分できます。これにより、同じ成果をより少ない労力で達成でき、運用コストの削減にもつながるのがポイントです。
特に、問い合わせ対応や業務処理の自動化によりこれまで複数人で対応していた業務を少人数でまかなえるようになり、外部委託や人件費の抑制にも効果があります。
業務量が増加する一方で人手を増やしにくい状況にある企業にとって、AIエージェントは効率的な体制構築をサポートする手段となり得ます。
AIエージェントの主な特長として、複数のタスクを同時に処理できるマルチタスク性能が挙げられます。人間の場合、同時に複数の問い合わせや作業を進めるには時間的・認知的な制約があり、集中力の低下や処理精度の低下につながりやすい側面があります。
一方で、AIエージェントは設定されたプロセスに基づいて同時に複数のユーザーに対応し、それぞれに適切な対応を返すことが可能です。
例えば、社内の異なる部署から寄せられる複数の申請や質問にも並行して対応できるため、業務の停滞を回避できます。こうした処理能力の高さは、業務のスピードアップやユーザー満足度の向上にもつながります。
AIエージェントは一度設定された内容を繰り返すだけでなく、実際の業務履歴を基に改善・最適化を続ける能力も持っています。これは機械学習や自然言語処理といった技術によって実現されており、ユーザーの反応や過去の対応履歴を分析することでより適切な回答やアクションを導き出せるようになります。
例えば、頻出する問い合わせに対しては優先的に解決策を提示したり、対応の流れを簡素化することで処理時間を短縮したりする工夫ができるでしょう。こうした継続的な最適化は単なる業務代替を超えて、業務品質の底上げに寄与する取り組みといえます。
AIエージェントは定型的な業務だけでなく、創造的思考が必要とされる業務の補助にも活用され始めています。特にビジネスの現場では、業務効率や生産性の向上を目指して多様なシーンでAIエージェントが活用されるようになりました。
ここでは、業務自動化におけるAIエージェントの具体的な利用例を5つ取り上げ、それぞれの効果や特徴についてわかりやすく紹介していきます。自社に導入できる方法を探ってみてください。
顧客からの問い合わせに対する対応は、企業の信頼性や満足度を左右する重要な業務です。一方で、質問内容が似通っていたり回答のテンプレートが用意されていたりする場合、人的対応では時間とリソースを要してしまいます。そこで注目されているのが、AIエージェントによる問い合わせ対応の自動化です。
AIエージェントは、チャットボットや音声認識技術と連携させることで定型的な質問に対して即座に応答できるよう設計されています。自然言語処理(NLP)によって文脈を理解し、適切な回答を導き出す仕組みが取り入れられているため、人手に頼らずとも円滑なやり取りが可能となります。
また、対応履歴を蓄積・分析することで回答精度を徐々に高められる点も見逃せません。対応の属人化を防ぎながら顧客体験の質を損なわずに効率化を図れることから、カスタマーサポート部門を中心に導入が進んでいます。
会議内容を正確に記録し、後から確認できる形で共有することはチーム間の情報共有や意思決定の迅速化にとって不可欠です。しかし、リアルタイムでの記録作成や終了後の要約には時間と集中力を必要とします。このような課題に対して、AIエージェントを活用した議事録作成の自動化が役立っています。
音声認識と自然言語処理を組み合わせることで、会議音声をテキストに変換し、発言者ごとに分類した上で文脈を保ちながら内容を整理できるのが特徴です。さらに要点抽出やハイライト表示によって、資料としての読みやすさも確保されます。
過去の会議データと照らし合わせて、同様の議題に関する結論や議論の傾向を提示する機能も開発が進められています。業務の記録にかかる手間を軽減し、会議後の迅速なアクションにつなげられる点で、チームの生産性向上に寄与する活用方法として注目されました。
日常業務において、メールの作成や返信は思いのほか時間を取られがちな作業のひとつです。内容の確認やトーンの調整、適切な言葉選びに配慮する必要があるため、単純に自動化するのは難しいとされてきました。しかし近年では、AIエージェントの精度向上により実用的なレベルでのメール支援が進んでいます。
AIは、受信したメールの文面や過去のやり取りを参照し、返信内容の草案を提案できます。業界用語やビジネスマナーに配慮した表現が採用されやすく、誤送信やトーンの不一致を防げることもポイントです。さらに、スケジュール調整や回答期限の提示など具体的なアクションも含めて提案されるケースが増えています。
送信前には人間による最終確認を前提とする設計が一般的であり、AIによる補助を受けつつも、業務の質を保つ形で活用されている点が特徴です。定型メールの迅速な作成や対応漏れの防止といった効果が期待され、営業部門や管理部門を中心に関心が高まっています。
日々蓄積される業務データの入力や整理、レポート作成は多くの部門にとって欠かせない業務ですが、同時に膨大な時間と労力を要する作業でもあります。このような繰り返し作業に対しては、AIエージェントの導入によって負担軽減が期待されました。
AIは、フォーマットに沿ったデータ入力を効率的に行うだけでなく、異常値の検知や不整合の修正提案といった補助的な機能も備えています。集計作業においても複数のデータソースを横断的に処理し、リアルタイムでの数値更新が可能となることで意思決定のスピードを上げる支援が可能です。
さらに、レポート作成ではテンプレートを基にグラフや文章を自動で生成し、視覚的に理解しやすい資料の作成が実現されています。特に定例業務として発生するレポーティングに対しては、人的リソースの削減だけでなく内容の一貫性や精度の向上にもつながるという評価が得られています。
プロジェクト管理やチーム運営において、関係者とのスケジュール調整は頻繁に発生する業務です。メールやメッセージを介して日程を擦り合わせる作業は煩雑で時間がかかる一方、ミスが生じることで業務全体の遅れにつながるリスクもあります。そこで活用が広がっているのが、AIエージェントによるスケジュール管理の自動化です。
AIはカレンダー情報や業務予定をリアルタイムで把握し、空き時間の提案や関係者間での調整を自動で行うことが可能です。また、会議室の予約やオンライン会議のリンク作成まで一貫して処理できるよう設計されているケースもあり、調整業務の負担が軽減されています。
さらに、変更が発生した場合にはリスケジュールの提案や関係者への通知も自動化されており、トラブルを未然に防ぐ体制を整えられます。こうした機能はマネジメント業務を円滑に進める上で効果的とされており、導入を検討する企業が増えている状況です。

AIエージェントを業務自動化に活用するには、事前準備と運用後の継続的な調整が重要になります。いきなり広範囲に導入を進めると現場の混乱や想定外のトラブルが起きやすくなるので注意しましょう。
そのため、まずは業務内容を見直し、AIエージェントが貢献しやすいタスクを選定した上で段階的に推進することが現実的なアプローチとなります。また、既存の業務フローとの整合性を重視し、ツールの運用状況を定期的に確認・改善する姿勢も求められます。
AIエージェントを効果的に活用するには、まず対象業務を明確にする必要があります。業務の中には、定型的で繰り返しが多く判断基準が明確なものと、人の介在が不可欠なものがあります。
自動化に適しているのは前者であり、問い合わせ対応、スケジュール調整、データ集計などが代表的な例です。これらはルールベースまたは生成AIの自然言語処理技術を活用することで、精度の高い処理が期待されます。
反対に、臨機応変な対応が求められる業務はAIによる代替よりも補助的な支援にとどめた方が良いでしょう。したがって、自社の業務の中で何を優先的にAIに任せるべきかを事前に分析し、業務ごとの特性に応じて適用範囲を決定することが重要です。
AIエージェントの導入初期においては、小規模なタスクからの試験運用が望まれます。初めから全社的な適用を目指すと、運用負荷やトラブル対応の負担が大きくなりやすいためです。
例えば、一部部署でのFAQ対応やレポート作成の補助機能など限定された業務領域において実施することで効果検証がしやすくなります。段階的に範囲を広げることで運用の中で見えてくる課題に柔軟に対応でき、全体最適化につながるでしょう。
こうした進め方により現場の理解と協力も得やすくなり、AIの定着にもつながります。導入を進める際には、業務の優先度や影響範囲を見極めながら段階ごとのロードマップを策定しておきましょう。
AIエージェントを活用する際には、単にツールを導入するだけでは成果につながりにくいです。現場で実際に働く人々の業務フローに自然に組み込まれるよう調整することが求められます。
例えば、問い合わせ対応をAIに任せる場合でも既存の顧客管理システムと連携しないと情報の断絶が発生しかねません。また、現場に負担をかけないUI設計や操作が簡単なチャットインターフェースの選定なども考慮すべきポイントです。
現場にとって使いづらい仕組みは活用されにくく、結果として形骸化することもあります。そのため、導入前のヒアリングや実際の業務に即した設計を通じて現場と連携しながら活用方法を調整していくことが重要になります。
AIエージェントは一度導入したら終わりというわけではなく、継続的なモニタリングと改善が不可欠です。現場の業務内容は時間とともに変化していくため、AIが対応しきれなくなるケースも想定されます。
例えば、問い合わせ内容が複雑化した場合、既存のAIモデルでは適切に対応できないこともあります。こうした課題に対処するには定期的に運用状況を点検し、問題点を洗い出した上でAIのチューニングやルールの見直しを行うことが必要です。
また、ユーザーからのフィードバックを活用することも効果的です。社内外の利用者から寄せられる意見を集約し、反映させることでより実用的なツールへと進化させることが期待されます。
AIエージェントによる業務自動化は近年関心が高まっており、さまざまな業種で導入への試行が進められています。特に、製造業や航空業界のように複雑かつ高い専門性が求められる分野では、従来の業務プロセスを効率化し、限られた人的リソースをより戦略的に活用するための手段としてAIエージェントが注目されました。
ここでは、具体的な企業事例を取り上げながら、その取り組みの特徴を見ていきます。
ダイキン工業株式会社は、日立製作所と連携し、空調設備に関する故障判断の支援にAIエージェントを活用する取り組みを始めています。このプロジェクトでは現場の点検業務における課題を抽出し、それに対応するAIエージェントの構築を進めてきました。
対象となるのは、空調機のセンサー情報やアラームログなどを基に設備の異常の有無やその要因を判断する業務です。従来は経験豊富な技術者の判断に頼っていた部分をAIが支援する形にすることで対応のばらつきを抑え、判断のスピード向上を目指しています。
現在は試験運用段階にあり、実際の業務に組み込むことで得られるデータを基にした制度や運用体制の整備が進められている状況です。
出典参照:ダイキンと日立が協創、工場の設備故障診断を支援するAIエージェントの実用化に向けた試験運用を開始|ダイキン工業株式会社
日本航空株式会社(JAL)は、社内業務の効率化とナレッジ活用を目的として、生成AIを活用した独自プラットフォーム「JAL-AI」を開発しました。
この取り組みではMicrosoft Azure OpenAI Serviceを基盤とし、社内情報を扱う範囲を明確に制限した上でセキュリティ対策を施しながら運用しています。活用領域は幅広く、旅客サービス、整備、企画などの部門で資料作成や業務マニュアルの検索、文書の要約といった業務支援を行っています。
また、社内での活用を進めるため、現場社員による実証的な利用と業務ごとの検証を通じて利便性と安全性の両立を目指しているのもポイントです。今後も適用範囲を段階的に広げる方針があり、既存業務との連携性を保ちながら継続的な改善が進められています。
出典参照:JALグループの社内業務を自動化、効率化する独自の生成AIツール「JAL-AI」の開発を支援|アバナード株式会社
AIエージェントを業務に取り入れて自動化を進める際には、事前の検討と導入後のフォローが重要になります。自動化の目的や対象業務の特性を十分に理解しないまま導入を進めてしまうと、かえって業務が煩雑になったり、トラブルの原因となったりするかもしれません。また、AIの判断に依存しすぎるとミスが起きたときのリスク対応が遅れる可能性もあるため、慎重な設計と運用体制が求められます。
ここでは、AIエージェントを活用して業務自動化を図る上で特に注意したいポイントについて詳しく解説します。
AIエージェントは特定のルールやパターンに基づいて処理する業務に強みを持ちますが、すべての業務に適しているわけではありません。
例えば、クリエイティブな判断が求められる企画業務や対人関係における感情的な配慮が必要な接客対応などは自動化にはあまり向かない業務と考えられます。そうした業務を無理にAI化しようとすると業務の質が低下したり、社員のストレスにつながったりすることもあります。
したがって、まずは業務の特性を分析し、明確な手順が定まっているタスクや繰り返し発生する処理業務を優先的に対象とすることが望ましいです。自動化の範囲を見極めることで、AIエージェントの導入効果を安定して発揮させやすくなります。
AIエージェントは大量のデータを処理する能力に優れており、一定の判断や分類も担えます。しかし、完全に人の判断を排除してしまうと想定外の状況や誤認識に対応できず、業務全体に影響を及ぼす恐れがあるので注意しましょう。
例えば、過去のデータからパターンを抽出して処理を行う場合でも、新しい条件が現れたときに誤った判断を下す可能性は常に存在します。そのため、AIエージェントに業務を委ねる場合でも、重要な意思決定や最終的な確認は人が行うような運用体制を残しておくことが望まれます。
AIが処理した結果をチェックする工程や、異常検知があった場合に即座に人が介入できる仕組みを構築しておくことで、リスクを抑えながら自動化を推進しましょう。
AIエージェントを活用する上では、業務の効率化だけでなくセキュリティと個人情報保護への配慮も欠かせません。特に顧客情報や取引データなど機密性の高い情報を扱う業務をAIに任せる場合、情報が外部に流出するリスクや不正アクセスの脅威に常に備える必要があります。
導入に際しては利用するAIプラットフォームのセキュリティ基準を確認し、自社の情報管理方針に適合するかを精査することが求められます。また、従業員による取り扱いミスを防ぐための教育も重要です。
例えば、アクセス権限の設定やログ管理体制を明確にすることで、万が一のトラブルに対するトレースや原因特定が行いやすくなります。信頼性の高い環境でAIエージェントを運用するためには、技術的・人的両面からの対策が求められます。

AIエージェントは、業務自動化を通じて生産性の向上や作業効率の最適化を支援する技術として、注目を集めています。ただし、導入にあたっては適切な対象業務の選定や、セキュリティ対策の徹底、人の介在によるリスク管理といった多角的な視点が欠かせません。
本記事で紹介した内容を基に、自社の業務プロセスを見直しながら、AIエージェントをどのように活用できるかを慎重に検討していくことが推奨されます。業務の特性に応じた段階的な導入を通じて、安定した自動化環境の構築を目指すことが現実的です。