AIエージェントとマルチエージェントの基本情報や活用例を徹底解説!
全般


企業活動の現場では、問い合わせ対応の負荷増大、業務ナレッジの属人化、情報の活用不足といった課題が長年存在してきました。
近年では業務の多様化・高度化が進むなかで、「正確かつ即時に対応できる業務支援」のニーズが高まっています。こうした背景で、今注目されているのがAIエージェントとRAG(Retrieval-Augmented Generation)と呼ばれる技術です。
本記事では、AIエージェントとRAGの基本概要から、それぞれのメリット、組み合わせた活用による効果、導入手順、さらには先進企業による活用事例までをわかりやすく解説します。これから業務のデジタル化を進めたい企業の担当者にとって、実践的なヒントを得られる内容となっていますので、ぜひ参考にしてください。

企業活動の現場では、顧客対応や社内問い合わせ対応、ナレッジ共有といった業務において、属人化や非効率性といった課題が慢性的に存在しています。加えて、近年は業務の複雑化やスピード化が進む中で、より高精度かつ柔軟な業務支援ツールのニーズが高まっています。
こうした背景のなかで注目されているのが、「AIエージェント」と「RAG(Retrieval-Augmented Generation)」という2つの技術です。
ここでは、それぞれの基本的な仕組みと特徴について解説し、なぜこれらの組み合わせが企業のDX(デジタルトランスフォーメーション)を加速させる手段として注目されているのかを整理します。
AIエージェントとは、自然言語でユーザーと対話しながら業務を支援する仮想アシスタントです。生成AI(Generative AI)の技術をベースにしており、チャット形式で質問に答えたりデータを検索・整理したり、定型業務を自動で実行したりするなど、さまざまな業務に対応しています。
例えば、社内のFAQ対応、営業資料の作成補助、カスタマーサポート対応など、多岐にわたるシーンで導入が進んでいます。これまで人手に頼っていた業務の一部を自動化できるため、業務効率化やコスト削減が大きなメリットです。
さらに、近年ではAPIやRPAとの連携により、業務プロセスを横断的にサポートする高度なAIエージェントも登場しています。
RAG(Retrieval-Augmented Generation)とは、「検索(Retrieval)」と「生成(Generation)を組み合わせた生成AIの高度化手法です。
通常の生成AIは、あらかじめ学習したモデルデータに基づいて回答を生成しますが、その情報は固定されており、最新の情報や社内限定の情報を扱うのが苦手という課題がありました。
RAGでは、生成AIが回答を出す前に、外部の知識ベース(社内ドキュメントやFAQデータなど)から関連情報を検索し、その情報を基に回答を生成します。これにより、最新かつ企業独自の情報に基づいた応答が期待できるでしょう。
具体的な例としては、社内の業務マニュアルから関連ページを自動で参照しながら回答するチャットボットや、過去の議事録を基に社内Q&Aを生成するAIツールなどが挙げられます。
AIエージェント単体でも業務支援は可能ですが、その性能をさらに実用レベルに高めるものがRAGとの組み合わせです。RAGを組み込むことで、AIエージェントは実務に耐えるナレッジ活用型のAIアシスタントへと進化します。
特に注目されているのが、社内限定のナレッジに基づいた応答が可能になる点です。これにより、一般的な情報だけでは対応できない、企業独自の業務や業界特有のルールにも柔軟に対応できるようになります。また、回答内容の一貫性や正確性が高まり、業務現場での信頼性が向上する点も大きなメリットです。
このように、RAGを活用したAIエージェントは、単なる業務効率化ツールにとどまらず、組織全体のナレッジマネジメントやDX推進の中核技術として期待されています。
AIエージェントの導入は、単なる業務支援にとどまらず、組織全体の業務効率化・対応品質の向上・ナレッジ共有の促進といった多方面にわたるメリットをもたらします。加えて、属人化の解消や情報の一元化、従業員の負担軽減といった効果も期待でき、働き方改革やDX推進の基盤整備にもつながるでしょう。
ここでは、AIエージェントの代表的な3つのメリットについて、具体例とともにわかりやすく解説します。
AIエージェントを導入することで、定型的な業務の自動化が可能となり、人的リソースの最適配分が実現できます。
例えば、社内の問い合わせ対応や業務マニュアルの参照対応といった「繰り返し業務」は、多くの従業員が時間を取られがちな作業です。AIエージェントは、これらの質問に即座に対応でき、担当者の工数を削減します。
また、営業日報の作成、会議議事録の要約、顧客情報の整理などもAIによって効率化され、人間が本来注力すべき企画や戦略業務に集中できる環境を整えられるのもメリットです。
このようにAIエージェントは、業務全体の流れをスムーズにし、生産性の底上げに貢献します。
AIエージェントは、時間や場所に縛られずに稼働できるのも大きな強みです。これにより、従来は人員確保が難しかった夜間・休日対応や、グローバル展開に伴うタイムゾーンの違いにも柔軟に対応できます。
例えば、カスタマーサポートの現場では、営業時間外の問い合わせに対してもAIエージェントが即座に回答することで、顧客満足度の向上が見込めます。必要に応じて有人対応へのエスカレーションも可能なため、サポート体制の品質を保ちながら対応スピードを向上可能です。
また、社内業務においても、24時間利用可能なAIエージェントが業務マニュアルやルールの問い合わせに対応することで、急なトラブルや確認作業に迅速に対応できる体制が整います。
業務ノウハウや問い合わせ対応の内容が、特定の担当者に依存している状態(属人化)は、多くの組織が抱える課題です。AIエージェントは、この「人に依存する業務知識」を可視化・構造化し、全社で共有可能にする仕組みを担います。
例えば、社内ヘルプデスクにおいて、ベテラン社員が蓄積してきた対応ノウハウをナレッジベースとしてAIに学習させることで、誰でもその知見を活用できる環境が整います。これにより、知識の継承や教育コストの削減にもつながるでしょう。
さらに、新入社員や異動者でもすぐに情報へアクセスできるため、スムーズなオンボーディングや業務立ち上がりの早期化が期待できます。
このようにAIエージェントは、組織内の知見を資産として活かし、業務の標準化・平準化を推進する役割も果たします。
RAG(Retrieval-Augmented Generation)は、近年急速に注目を集めている生成AIの応用技術のひとつです。生成AIの利便性を活かしつつ、企業ごとの業務課題や情報活用に最適化できる点が評価されています。
社内ドキュメントやナレッジベースと連携することで、より実務に即した形でAIを活用できるのが大きな特長です。
ここでは、RAGを導入することで得られる3つの主要なメリットを具体的に解説します。
従来の生成AIは、大量の学習データを基に自然な文章を出力できる反面、最新情報や特定領域の知識に対して正確さを欠くことが課題とされていました。
RAGは、回答を生成する前に関連する情報を外部データベースから「検索(Retrieval)」し、その情報を元に「生成(Generation)」を行うことで、より正確性の高い回答を得られやすくなります。
例えば、社内マニュアルやFAQをナレッジベースとして活用すれば、AIが常に信頼できる情報源に基づいて回答を出せます。これにより、利用者ごとに回答内容がばらつくといった不安も解消され、ユーザーエクスペリエンスの向上につながるでしょう。
生成AIにおける代表的な問題のひとつが「hallucination(幻覚)」と呼ばれる現象です。これは、AIが存在しない事実をあたかも真実のように生成してしまうことで、業務上のリスクにつながる恐れがあります。
RAGでは、情報の出典を検索プロセスで特定してから生成処理に進むため、AIが勝手に内容を想像する可能性が低下するでしょう。検索対象として設定するナレッジソースが信頼できるものであればあるほど、出力される回答の精度と正確性は向上可能です。
RAGの大きな魅力のひとつが、企業や組織が保有する独自のナレッジを活用できる点です。汎用型の生成AIでは難しかった、社内文書・技術資料・業務フローといった「個別性の高い情報」に基づいた回答が可能になります。
例えば、問い合わせ対応や社員教育の場面において、自社専用のQ&Aやマニュアルを検索対象にすれば、業務に応じた内容で回答できるRAG型AIエージェントを構築できます。これにより、他社との差別化を図りながら、効率的な業務運用が実現可能です。
さらに、ナレッジの更新もリアルタイムに反映できる設計にすれば、常に最新の情報をユーザーに提供できる体制を整えられるのもメリットの1つです。
RAG型AIエージェントを導入することで、業務効率化やナレッジ活用の高度化が実現できます。しかし、効果的に運用するためには、段階的なアプローチで導入を進めることが重要です。
導入目的や対象業務を明確にし、適切なデータ整備や検証プロセスを踏むことで、現場に定着しやすくなり、長期的な成果にもつながります。
ここでは、RAG型AIエージェントの導入における5つの基本ステップを解説します。
最初に行うべきは、AIエージェントを導入する目的と、対象とする業務範囲を明確にすることです。何を改善したいのか、どの業務にAIを適用したいのかを整理しないまま導入を進めると、現場とのギャップが生じて定着しづらくなります。
例えば、「社内問い合わせの負担軽減」「営業資料の作成支援」「FAQ対応の自動化」など、具体的な課題やユースケースを絞り込むことが成功への第一歩です。関係部署や現場担当者と早期にすり合わせを行い、目指すべきゴールを共有しておきましょう。
次に、AIエージェントが活用するナレッジデータ(例:社内FAQ、業務マニュアル、仕様書、議事録など)を収集・整理します。RAGでは、このナレッジデータを検索対象とするため、データの質と構造が回答精度に直結します。
データ整備の際には、以下のような前処理を丁寧に行うことが重要です。
このようにナレッジのクレンジングと構造化を適切に行うことで、AIエージェントが正確かつ一貫性のある回答を出せる状態を整えられます。
ナレッジベースの整備と並行して、自社に適したRAGプラットフォーム(技術基盤)を選定します。現在、国内外でさまざまなRAG対応の生成AIツールやAPIが提供されています。
選定時には、以下のような観点を比較検討するとよいでしょう。
必要であればベンダーや外部パートナーとの協業も視野に入れると、導入リスクを抑えられます。
RAG型AIエージェントを本格的に導入する前に、PoC(Proof of Concept:概念実証)を実施しましょう。限定的な業務範囲でAIを試験運用し、性能評価・課題抽出・利用者からのフィードバックを得ることで、精度と運用面の課題を洗い出せます。
PoCを通じて、以下のような検証が可能です。
この段階で得た知見は、ナレッジベースの修正やUI改善、社内ガイドライン整備などにも活かされます。
PoCで有効性が確認できたら、いよいよ本格導入と全社的な展開へと移行します。導入後は、単なるツール提供に留まらず、運用体制の整備と継続的な改善活動が欠かせません。
こうしたPDCAサイクルを回すことで、RAG型AIエージェントはより実務に根差した、高品質な業務支援ツールへと成長していきます。

RAGやAIエージェントは、さまざまな業界・業務で実用化が進んでいます。近年では、社内問い合わせ対応や業務マニュアル検索、オンボーディング支援など幅広い用途で導入が進められ、定型業務の効率化やナレッジ活用の高度化に貢献しているのが特長です。
ここでは、実際に導入して成果を上げている3社の事例を紹介します。各社がどのような目的でRAGやAIエージェントを活用し、どのような効果を得たのかを見ていきましょう。
西日本旅客鉄道株式会社(JR西日本)では、駅員の業務負荷軽減とサービス品質向上を目的に、生成AIとRAGを活用した「Copilot for 駅員」を開発しました。
本システムは、駅業務に関するマニュアルやFAQ、規則集などをナレッジベースとして構築し、AIが利用者からの質問に対して最適な回答を提示します。例えば、「車いす利用のお客様への案内方法」「天候による遅延対応の手順」など、状況に応じた業務対応をAIが案内してくれます。
その結果、新人駅員の業務習熟が早まり、ベテラン社員のサポート業務の負担も軽減可能です。RAGによる高精度な情報検索により、業務の標準化とサービス品質の平準化が進んでいます。
出典参照:JR西日本の生成AI「Copilot for 駅員」に対する開発支援を行っています – 株式会社ヘッドウォータース
LINEヤフー株式会社は、社内の業務効率化を目的に開発した生成AIツール「SeekAI(シークエーアイ)」に、RAG機能を本格的に導入しました。
同社では大量の社内文書、FAQ、議事録、仕様書などを検索可能なナレッジとして整備し、従業員が質問をするとAIが関連文書を検索したうえで適切な回答を生成する仕組みを構築しました。従来、情報検索に時間がかかっていた場面でも、数秒で正確な情報を取得できる環境が整っています。
結果として、業務時間の短縮や属人化の解消が進み、社内のナレッジ活用が加速しました。また、RAGを導入することで、従来の生成AIに見られがちだった誤答や曖昧な回答も大幅に減少しました。
出典参照:LINEヤフー、RAG技術を活用した独自業務効率化ツール「SeekAI」を全従業員に本格導入。膨大な社内文書データベースから部門ごとに最適な回答を表示し、確認・問い合わせ時間を大幅に削減
株式会社ゆめみでは、新入社員のオンボーディング支援にRAGを活用したAIエージェントを導入しています。
新入社員が業務中にわからないことがあれば、チャット形式でAIに質問できる仕組みを用意しました。社内ルールや就業規則、ツールの使い方などをナレッジとして登録しており、AIが即座に回答可能です。
この取り組みにより、新入社員が質問のたびに先輩社員に時間を割く必要がなくなり、自己解決力の向上につながっています。また、RAGの仕組みにより、社内情報に応じた正確な回答が可能で、教育コストの削減にもつながっています。
出典参照:ゆめみ、新入社員のオンボーディング支援にRAGを活用した生成AIを導入
RAGやAIエージェントは、業務効率化やナレッジ活用に大きな効果をもたらす一方で、導入・運用にあたってはいくつかの注意点も存在します。導入の目的が曖昧だったり、データ整備や従業員教育が不十分だったりすると、期待した成果が得られないこともあります。
こうしたリスクを回避するには、事前の準備と運用設計が欠かせません。ここでは、RAGやAIエージェントを導入する際に企業が意識すべき3つのポイントを解説します。
RAG型AIエージェントは高機能な分、いきなり全社展開や大規模導入を行うと、期待値と実用性にギャップが生まれ、現場に混乱を招く可能性があります。導入初期は、特定部門や業務に限定したスモールスタートから始めるのが効果的です。
例えば、「社内ヘルプデスク」「FAQ対応」「営業資料の検索支援」など、明確なユースケースがある領域から始めることで成果を出しやすく、現場からの信頼も得られやすくなります。
初期段階で得られたフィードバックを基にチューニングを重ね、徐々に他部署・全社展開へとスケールしていくのが理想的な進め方です。
RAGやAIエージェントは社内の重要データを扱うため、情報漏えいリスクやプライバシー保護の観点から、セキュリティ対策は不可欠です。
特にクラウド型サービスや外部APIを活用する場合、データの保管場所・アクセス権限・通信の暗号化といった基本的な対策は必ず確認しておかなければなりません。
また、ナレッジベースに個人情報や機密情報を含む場合は、アクセス制限やマスキング処理の徹底も求められます。企業ポリシーや法規制(例:個人情報保護法、GDPRなど)に適合しているかどうかも事前にチェックしておくことが重要です。
AIの利便性に頼りすぎず、技術面・運用面の双方でセキュリティリスクを最小限に抑える体制づくりが求められます。
どれほど優れたAIエージェントを導入しても、現場の従業員が使いこなせなければ効果は発揮されません。「AIに対する不安」や「使い方がわからない」といった心理的・技術的なハードルが、現場での活用を妨げる原因になることもあります。
そのため、導入と並行して社内での教育が重要です。操作方法のトレーニングだけでなく、「AIは業務を奪うものではなく支援する存在である」という理解を深める場も欠かせません。
さらに、日常的にAIと対話する文化を根づかせるためには、社内ポータルやチャットツールと連携した導線設計、ユーザーサポート窓口の整備なども有効です。現場の声を継続的に吸い上げ、AIの改善につなげる「フィードバックの循環」も意識しましょう。
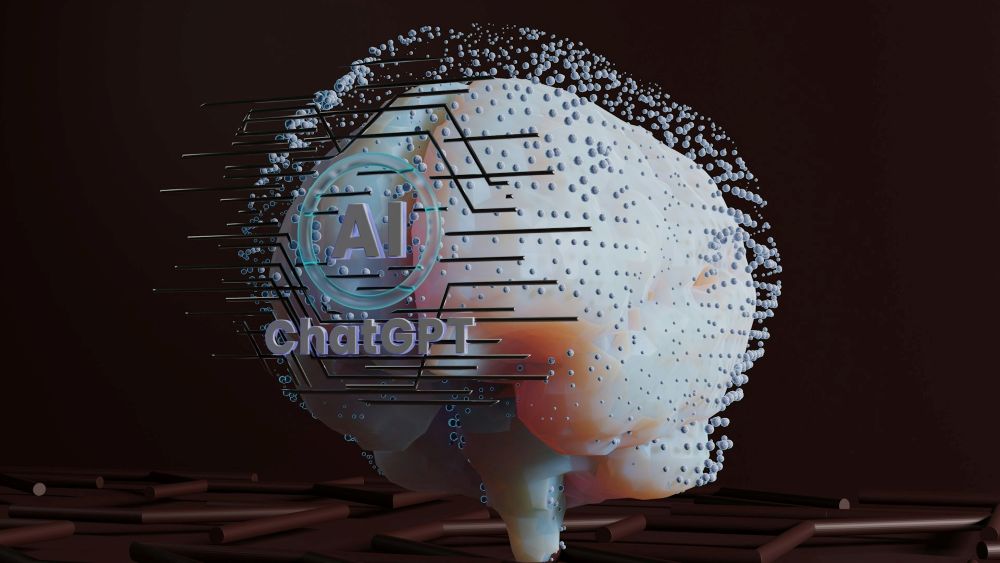
AIエージェントやRAG(Retrieval-Augmented Generation)は、企業の業務効率化やナレッジ共有の課題解決に貢献する先進技術です。AIエージェントは問い合わせ対応や定型業務を自動化し、RAGは社内ナレッジに基づいた正確で一貫性のある回答を生成できます。
両者を組み合わせたRAG型AIエージェントは、生産性の向上や意思決定の迅速化に直結し、企業のDX推進にも助けになるでしょう。
導入にあたっては、スモールスタートを基本に、セキュリティ対策や従業員教育などの準備を丁寧に行うことが重要です。まずは自社の課題を洗い出し、段階的に導入を進めていきましょう。