AIエージェントとマルチエージェントの基本情報や活用例を徹底解説!
全般

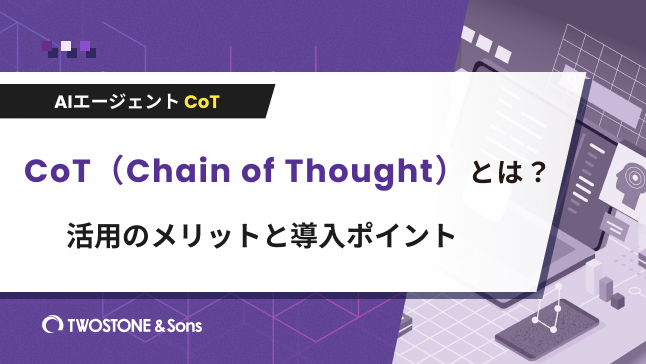
AIエージェントの進化により、業務の自動化や意思決定支援のあり方が大きく変わりつつあります。なかでも注目を集めているのが、AIに思考力を持たせる技術「Chain of Thought(CoT)」の活用です。
従来のAIは与えられた問いに対して即座に回答するものが一般的でしたが、CoTを用いることで「考えるプロセス」を持たせることが可能となり、より複雑で高度なタスクに対応できるようになっています。
本記事では、AIエージェントとChain of Thought(CoT)の基礎知識から、関連技術との違い、具体的な導入メリット、国内外の事例、導入時の注意点までをわかりやすく解説します。AIによる業務効率化や組織の意思決定支援を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

AI技術の進化に伴い、タスクの自動化や意思決定支援に活用される「AIエージェント」が注目されています。なかでも、AIが思考するように問題解決に取り組むための手法が「Chain of Thought(CoT)」です。
CoTは従来のAIと異なり、過程を重視する推論形式を導入することで、より複雑な業務への応用を可能にします。ここではCoTの基本概念から、詳しい仕組みまでを解説します。
Chain of Thought(CoT)とは、AIが答えを導き出す過程で「考えた順序」を言語化する手法であり、論理的な推論や判断が求められる問題に対して有効です。
従来のAIモデルは、入力に対して即座に出力を返す傾向があり、複雑な課題や理由を要する応答には不向きでした。しかし、CoTを導入すると、AIがステップ・バイ・ステップで問題を分析し、解答に至るまでの思考を自然言語で出力できます。
これにより、回答の透明性が高まり、説明可能なAIとしての価値も大きく向上します。CoTは近年、自然言語処理や自動応答システムなど、さまざまなAI応用分野で導入が進んでいるのが強みです。
CoTは、AIが一度に全体を処理するのではなく、問題を複数の段階に分けて思考し、それぞれの段階ごとに自然言語で推論結果を表現します。このプロセスにより、AIの思考が可視化されるだけでなく、誤りの特定や精度向上にもつながります。
人間のように段階的に考える力をAIに持たせることが、CoTの特長です。ここでは、CoTの仕組みをより詳しく解説します。
CoTの第一の核となる仕組みは、「問題の分割処理」です。AIが複雑な問いに答える際、一度に全体を理解・解決しようとするのではなく、複数のサブタスクに分けて一つずつ順番に処理していきます。
例えば「東京から大阪までの最適な移動方法は?」という問いに対して、AIはまず予算の上限を確認、次に移動手段の候補を挙げる、さらに所要時間を比較するといった具合に要素を細かく切り分けて判断します。
ステップ分解の考え方により、AIは誤解の少ない回答ができ、より論理的かつ柔軟なタスク遂行が実現可能です。
CoTでは、AIが途中で行う思考プロセスを、ユーザーにわかる自然言語で出力することが求められます。これが中間推論の可視化です。
例えば「8個のりんごを4人で分ける」という問題なら、「まず8÷4を計算する → 結果は2 → よって1人あたり2個」といったように、AIは計算過程や判断の背景を順序立てて説明します。
これにより、ユーザーはAIの出力結果が妥当であるかどうかを検証しやすくなります。また、誤った推論があった場合でも、途中の思考が見えるため修正可能であり、ブラックボックス化されがちなAIの透明性や信頼性の向上にもつながる重要なプロセスです。
AIエージェントにとって、CoTは単なる思考補助の技術ではなく、タスクの自律処理を実現する基盤技術です。
人間が問題に直面したときと同じように、AIも「何をすべきか」を段階的に判断できるようになるため、複雑な業務や変化の多い状況下でも柔軟に対応できます。
例えば、カスタマーサポートAIであれば、ユーザーの問い合わせを一度に判断するのではなく、「意図の把握→過去履歴の検索→適切な案内」といった形で論理的に処理できるようになります。
さらに、CoTによってエージェントの出力内容が説明可能になるため、ビジネスの現場における意思決定や自動化業務でも信頼性の高い活用が期待されるでしょう。
Chain of Thought(CoT)と並び、AIエージェントの性能を高める技術として注目されているのが「ReAct」「ToT」「Zero-shot」といった関連手法です。
これらは、すべてAIの判断精度や応用力を向上させるためのアプローチですが、それぞれに適した使い分けがあります。ここでは、各技術の特徴や違い、どのようなタスクに適しているのかを比較しながら解説します。
ReAct(Reason + Act)は、AIが「推論(Reason)」と「行動(Act)」を交互に繰り返しながら、タスクを解決するためのフレームワークです。
例えば、Web検索やツール操作といった外部アクションが必要な状況で、AIが一度に結論を出すのではなく「考えて→実行→再度考える」というプロセスを繰り返します。CoTが思考プロセスの明示に特化しているのに対し、ReActは行動と連動した推論が強みです。
特に外部ツールと連携するAIエージェントにおいては、状況判断と行動の柔軟な切り替えが求められるため、ReActの有効性が高まります。
ToT(Tree of Thoughts)は、AIの思考を「木構造」として展開・評価する高度な推論手法です。CoTが一本道の推論に基づくのに対し、ToTでは複数の仮説や中間結果を枝分かれさせながら展開し、各思考ルートを比較・評価しながら最適な結論を導きます。
これにより、より深い探索や複雑な意思決定が可能となり、創造的な問題解決や長期的な計画立案などに適しています。ToTは探索空間の拡大と最適経路の選別を可能にするため、AIエージェントがより柔軟かつ多面的に物事を考えることが可能です。特に戦略立案やマルチステップの意思決定に向いています。
Zero-shotとは、事前に具体的な例や文脈を提示せずにAIが初見のタスクに対応する推論手法です。例えば「この質問に答えて」とだけ指示された場合でも、AIが自ら課題を理解し、過去の学習知識を応用して応答するのが特徴です。
CoTやToTが多段階推論を前提としているのに対し、Zero-shotは簡潔な指示で即応可能な点が利点となります。一方で、タスクが複雑だったり前提が多い場合には、誤解や不十分な回答を招くリスクもあります。
ゼロからの柔軟な対応が求められる一方で、正確性や透明性には限界があるため、タスク内容に応じた使い分けが重要です。
AIエージェントにChain of Thought(CoT)を組み合わせることで、より人間に近い推論や意思決定が可能です。
これにより、従来のルールベースの処理では難しかった業務にも柔軟に対応でき、さまざまな業務へ活用していけます。ここでは、CoTを活用したAIエージェントがもたらす6つの主なメリットを具体的に紹介し、それぞれの導入効果についてわかりやすく解説していきます。
CoTによってAIはタスクを「理解→分解→実行」と段階的に処理できるようになり、複雑な業務への対応力が飛躍的に向上します。
例えば、これまで人間が判断していたマルチステップのタスク(例:問い合わせ対応、マーケティング戦略の立案、業務フロー設計など)も、AIが一人で完結できるようになります。これは、問題を細かくサブタスクに分割し、それぞれを順を追って処理するCoTの構造的な思考フレームがあってこそ実現可能です。
従来のAIは「最終的な答え」だけを出力する傾向がありましたが、CoTではプロセス重視のアプローチが可能です。結果として、人手に頼らずにタスク処理の自律化が進み、業務の自動化や24時間稼働といった恩恵をもたらします。
CoTの最大の強みの一つは、AIの思考の見える化です。つまり、AIがなぜその答えに至ったのか、どのような情報をどう解釈して判断したのかを、自然言語で順を追って説明できるようになります。
これは、説明責任が求められる業務(医療・法務・金融など)において、重要な機能です。従来のAIは「結論だけ提示」することが多く、ユーザーはその判断を鵜呑みにするしかありませんでした。
しかしCoTを活用すれば、「こう考えたから、この結果に至った」という透明性のある対話が可能になります。これにより、業務の信頼性が高まり、AIに対する心理的な不安も軽減されます。意思決定支援ツールとしてのAIの価値が、より実務的かつ実用的なものへと進化するでしょう。
AIの導入における大きな障壁の一つが、「ブラックボックス問題」です。これは、AIが出した結論に対して「なぜそうなったのか分からない」という不透明性に起因する問題です。
CoTはこの問題を構造的に解決するアプローチを提供します。AIは一連の思考ステップを自然言語で明示しながら結論に至るため、プロセスの可視化が可能です。例えば、推薦システムがユーザーに商品を勧める場合でも、「過去の購入履歴」「類似ユーザーの行動」「現在の季節やイベント」といった要因を明示できます。
これにより、判断の透明性が確保され、利用者や管理者が結果に納得しやすくなるでしょう。また、誤った判断が出た場合にも、どこでミスが起きたかを追跡・修正しやすくなるため、AIの精度改善にもつながります。
AIが高度な自律性を持つためには、「間違いを自分で見つけて直す」力が不可欠です。CoTはその基盤となる技術です。推論過程を段階的に出力することで、AI自身が途中の論理破綻や情報矛盾に気づき、再考を促すプロンプトを生成できます。
例えば、長文の文章を要約するタスクで、途中の内容と要約結果に齟齬がある場合、AIがその点を認識し、「再要約する必要がある」と判断できます。これはまさに人間の自己修正能力に近い思考パターンです。
業務システムにおいてこの自己修正機能を組み込めば、ヒューマンエラーの代替だけでなく、AI自体の信頼性とパフォーマンスが向上し、結果としてシステム全体の安定性も高まることになります。
CoTを活用することで、AIは複数の情報を組み合わせ、文脈を踏まえた高度な推論が可能になります。
例えば、営業活動で「顧客の過去の行動履歴」「現在の関心キーワード」「業界動向」「競合情報」などを統合しながら、最適なアプローチ方法を提案するような処理も可能です。単一情報に基づいた機械的な判断ではなく、関連性の高い情報を横断的に取り込みながら思考を進めることができる点が、CoTの強みです。
こうした統合的な処理能力は、データが膨大化・複雑化する現代において有用であり、人間にとっての「読み解く手間」や「整理する負荷」を軽減します。意思決定の質を高めると同時に、AIとの共同作業のシームレス化にも貢献します。
AIが思考過程を経て根拠のある結論を導き出すようになると、組織内の意思決定にかかる時間は劇的に短縮されます。CoTにより、AIは単なる情報提供者ではなく考えるパートナーとして機能するようになります。
例えば、経営層が複数の部門からの報告をもとに戦略判断を下す場面では、AIがそれらのデータを収集・要約・評価し、かつ根拠を示しながら提案することが可能です。そのため、会議の回数や意思統一にかかる時間が削減され、行動までのリードタイムが短縮されます。
さらに、AIが出力する思考ステップを各部門が共有することで、組織全体の認識統一が進み、連携の質も向上します。結果として、迅速で的確な経営判断を下せる「俊敏な組織」が実現するでしょう。

近年、AIエージェントにChain of Thought(CoT)を組み合わせることで、自律性と信頼性を高めた実用的なサービスが登場しています。
なかでもOpenAIの「Operator」は、CoTと高度な推論機能を組み合わせることで、Web上の実タスクを人の代わりに実行できる新時代のエージェントとして注目を集めています。
ここでは、Operatorをはじめとする先進事例を取り上げ、AIエージェント×CoTの実用性や可能性について紹介するので、ぜひ参考にしてください。
OpenAIが発表した「Operator」は、ユーザーの代わりにWebブラウザを操作してタスクを実行するAIエージェントです。GPT-4oと視覚認識・強化学習を組み合わせ、ボタンやメニューなどのGUIを理解し、入力やクリック、スクロールなどの操作を自律的に行えます。
例えば、食料品の注文や宿泊予約、フォーム入力など日常的なタスクを人手を介さずに処理可能です。Chain of Thoughtに基づく推論によって複雑なフローにも対応し、問題が発生した場合には自己修正も行います。
さらに、ユーザーとの対話を通じて重要操作時には制御を委ねる設計となっており、安全性と柔軟性の両立が図られているのが特徴です。現在は研究プレビュー版として提供されており、今後のChatGPT統合が期待されています。
Googleが提供する「Google Agentspace」は、生成AIと検索技術を組み合わせた企業向けAIエージェントです。
メールやドキュメント、社内ツールなどに散在する情報を一括で検索・統合し、従業員が自然言語で質問するだけで、業務に必要な情報を迅速に取得できます。Chain of Thought(CoT)を活用し、複雑な問いに対しても段階的に推論しながら正確に応答可能です。
JiraやSharePointなどとの連携にも対応し、職種や目的に応じた柔軟な活用ができます。加えて、ローコードで独自エージェントを作成できる機能も備え、社内のナレッジ活用を促進します。
出典参照:Google Agentspace と NotebookLM Plus で企業の生産性向上を支援|Google LLC
NECは2025年より、生成AI「cotomi」を活用した業務自動化型AIエージェントの提供を開始します。このエージェントは、ユーザーが依頼したい業務を自然言語で入力するだけで、タスクを自律的に分解・設計し、最適なAIやITサービスを選定して自動実行するのが特長です。
例えば「キャリア採用者の育成戦略を立てたい」と入力すると、社内外の情報を検索・分析し、育成計画書を自動作成する業務プロセスを構築します。Chain of Thought(CoT)的な段階的推論を活用し、複雑な専門業務にも柔軟に対応可能です。
高度な専門知識がなくても戦略立案や意思決定が可能なため、経営・人事・マーケティングなど幅広い領域で業務効率化が期待されるでしょう。今後は特化型エージェントの拡充も予定されており、企業のDX推進を支える存在となるでしょう。
出典参照:NEC、高度な専門業務の自動化により生産性向上を実現するAIエージェントを提供開始|日本電気株式会社
AIエージェントにChain of Thought(CoT)を活用すれば、高度な推論や複雑なタスク処理が可能になりますが、導入にはいくつかの注意点があります。
適切なプロンプト設計を怠ると誤解や誤動作を招く恐れがあり、またAIの出力を過信すれば重大な判断ミスにつながるリスクもあるでしょう。さらに、CoTによる処理は高精度な一方でコストや処理時間が増加しやすいため、導入時は全体最適を意識した設計と運用が求められます。
CoTを活用したAIエージェントでは、入力されたプロンプトに対して段階的な推論を行いますが、曖昧または過剰に複雑な指示を与えると、推論の方向性がずれてしまうリスクがあります。
例えば、複数の目的を1つのプロンプトに詰め込んでしまうと、AIが解釈を誤り、誤ったタスク分解を行ってしまう恐れがあるでしょう。また、指示の文脈が不明確な場合には、意図しない答えを導き出す可能性もあります。
適切なプロンプト設計のためには、「目的→前提→条件」の順に整理された構造で、具体的かつ明確な問いを与えることが重要です。運用前にはテスト・評価を重ね、想定外の挙動を抑えるプロンプト設計が不可欠です。
AIエージェントにCoTを組み合わせることで、思考過程を持つかのような高精度な応答が可能になりますが、その能力を過信すると業務上のリスクが高まります。
例えば、AIが出力した内容は一見正しく見えても、事実誤認や情報の文脈誤解が含まれている場合があり、特に医療・法務・金融などの分野では致命的な判断ミスにつながる可能性が高いです。
また、CoTによる推論は人間の思考に似せた表現ができる反面、その裏付けとなる根拠が曖昧になることもあります。AIはあくまで支援ツールであり、最終判断は人間が責任を持って行う体制が重要です。
定期的なファクトチェックやガバナンスの仕組みを整備することが、適切なAI運用につながります。
CoTを活用したAIエージェントは、ステップバイステップの推論処理を行うため、従来型の応答よりも計算量が増えやすく、それに伴う処理時間やAPIコストも上昇します。
例えば、1つの質問に対して複数の中間推論を行うと、トークン使用量が数倍に膨らむことがあり、システム全体のレスポンスが遅くなるケースもあります。また、複数のエージェントを同時に稼働させるような大規模運用では、コストが急増するリスクもあるでしょう。
導入にあたっては、タスクの重要度や頻度に応じてCoTを使い分けたり、低負荷の処理には簡易モデルを活用したりといった工夫が求められます。精度とスピード、コストのバランスを最適化する設計が重要です。
まとめ|AIエージェント×CoTを活用して業務効率化を図ろう
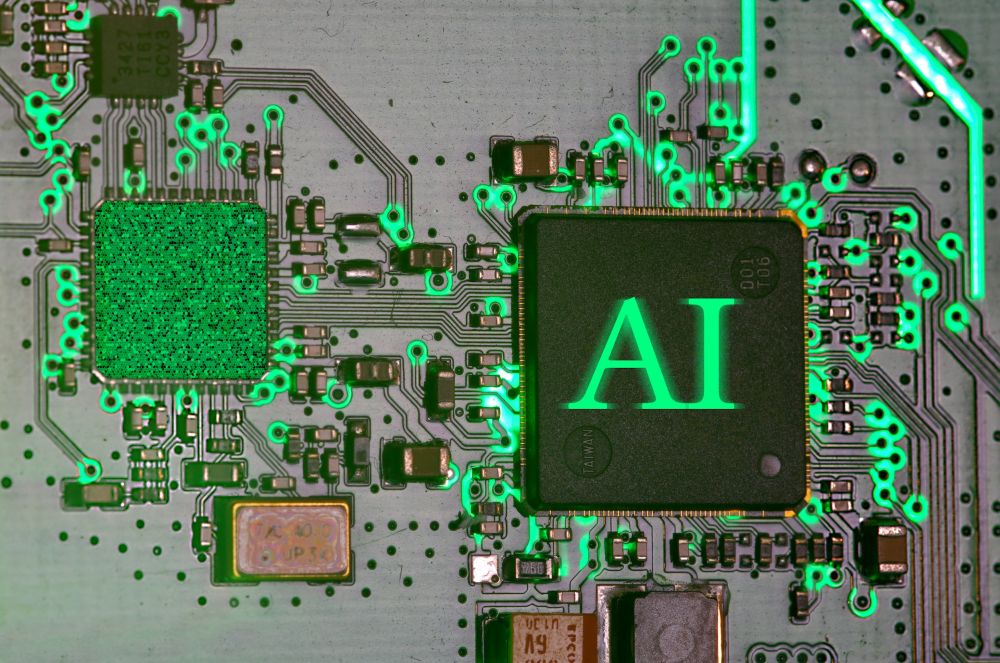
AIエージェントにChain of Thought(CoT)を組み合わせることで、複雑なタスクの自律処理や推論の透明化が可能になり、業務の効率化・高度化を同時に実現できます。
CoTは、従来のAIよりも柔軟かつ信頼性の高い応答を生み出し、情報統合や自己修正といった人間に近い思考プロセスを再現できる点が特長です。関連技術や事例も参考にしながら、自社の課題に合った活用方法を検討することで、組織全体の生産性と意思決定力を大きく向上させる可能性があります。
本記事を参考に、まずはスモールスタートでAIエージェント×CoTの導入を進めてみましょう。