今話題のAIエージェント×ToTとは?活用事例やメリットを紹介
全般
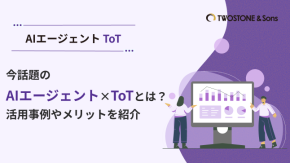

近年、多くの企業が業務効率化や人手不足の解消を目指してAIの導入を検討しています。中でも注目されているのが「AIエージェント」や「マルチエージェント」と呼ばれる仕組みです。これは複数のAIがそれぞれ役割を分担し、連携しながら課題解決を図るというものです。
特に製造・物流・接客など、複雑で多岐にわたる業務プロセスを抱える分野において、その柔軟性と高い適応力が評価されています。単純な作業の自動化にとどまらず、状況に応じた判断や例外対応にも活用できる点が大きな強みです。
本記事では、AIエージェントとマルチエージェントの関係や仕組み、導入メリット、活用事例、選定のポイント、導入時のリスクまで幅広く解説します。導入を検討している方は、ぜひ最後までご一読ください。
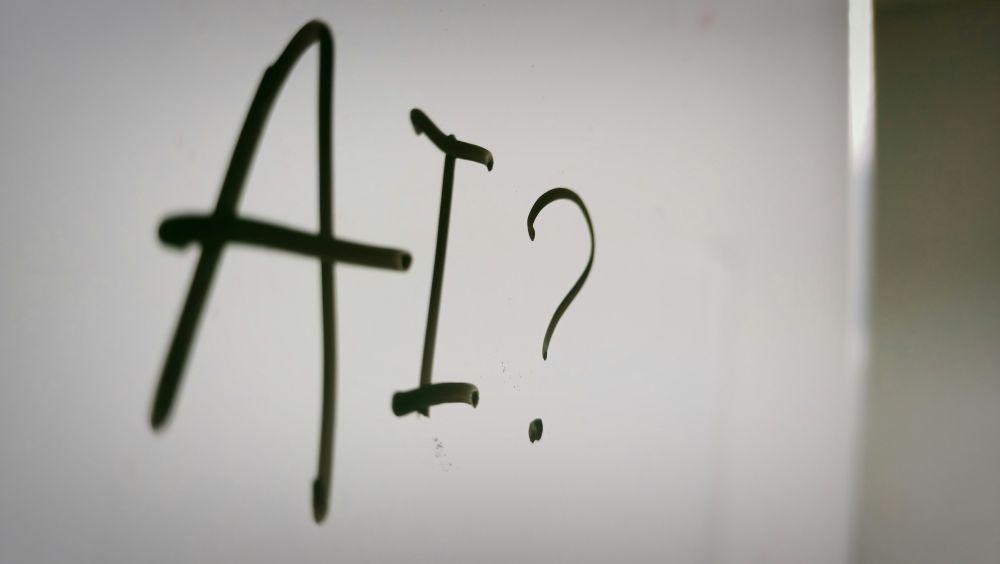
AIエージェントは単体で業務を遂行できる自律型AIですが、複雑な業務や部門横断的なタスク処理には限界があります。そこで注目されているのが「マルチエージェント」という構成です。
複数のAIエージェントが役割を分担しながら連携・協調することで、業務全体の最適化や変化への即応、さらには拡張性の高い業務基盤を構築できるでしょう。
ここでは、AIエージェントとマルチエージェントについて詳しく解説します。
AIエージェントとは、あらかじめ設定された目標やルールに基づき、自律的に判断し行動する人工知能の一形態です。
例えば、チャットボットは問い合わせに対応し、配送AIは交通状況に応じて最適なルートを選択、在庫管理AIは補充を自動で判断するなど、業務に特化したタスクを高精度かつ高速に処理します。
エージェントは、環境からの入力(センサー・ユーザー操作・外部データなど)をもとに、リアルタイムで状況を把握・分析し、能動的にアクションを起こせるのが特長です。
現在では、単体利用に加え、複数のAIを役割分担させた「マルチエージェント構成」も注目されており、DX推進の有力な手段として導入が進んでいます。
マルチエージェントとは、複数のAIエージェントがそれぞれ自律的に判断・行動しながら、相互に連携・協調してタスクを達成する仕組みです。各エージェントは明確な役割を持ち、リアルタイムに情報を交換し合いながら、全体の目的達成に向けて最適な処理を分担します。
例えば、製造業では品質検査AI・ライン制御AI・搬送ロボットAIが並行して動作し、1つの生産プロセスを自動で最適化します。物流業界では、在庫AIと配送AIが連携し、荷物の流れを調整・最短経路を自動選定するといった仕組みも活用できるでしょう。
この仕組みは処理の並列化による高速化、変化への即応性、将来の拡張性といった点で優れており、業務の複雑性が高い現場や複数部門にまたがる業務構築に最適なフレームワークといえるでしょう。
マルチエージェントは、複数のAIが異なる役割を担いながら連携・協調して動作する構成であり、業務の高度化や柔軟性の向上に優れています。
特に、人手不足や複雑な業務フローに直面する現場においては、処理の効率化や意思決定の迅速化が期待できるでしょう。さらに、予測困難な事象やリアルタイム対応が求められる環境にも強く、既存システムと連携することで全体最適な業務設計を活用できます。
ここでは、マルチエージェント導入で得られる代表的な3つのメリットを解説します。
マルチエージェントは、複数のAIが個別の機能に特化して動作し、業務全体を並列かつ自律的に処理できる仕組みです。
例えば、製造業では検査AI・搬送AI・生産管理AIがそれぞれのタイミングで動作することで、手作業による工程間の調整や待機が不要になります。その結果、処理速度が向上し、リードタイムの短縮や人的負荷の軽減にもつながります。
さらに、エージェント単位での改善が可能なため、業務ごとのボトルネックに個別対処しやすく、継続的な業務最適化も実現しやすいのが利点です。段階的な導入や拡張がしやすいため、いきなり全体を変えるリスクを取らずに、現場ニーズに合わせて導入できる点も魅力です。
マルチエージェントは、各AIが自律的に判断しながらリアルタイムで連携できるため、外部環境の変化に対しても迅速な対応が可能です。
例えば物流では、配送AIが渋滞や悪天候の情報を取得すると即座にルートを再計算し、同時に倉庫管理AIが出荷順や在庫の優先順位を調整します。これにより、配送の遅延リスクを最小限に抑えることができ、サービス品質を維持できるでしょう。
中央集権型システムでは対応が遅れがちな場面でも、分散型のマルチエージェントなら、現場ごとの判断をしやすくなり、各部門が連携しながらも自律的に動ける体制を構築できるでしょう。予測困難な事態への即応性は、BCP対策としても高く評価されます。
部門横断型の業務や複数ステークホルダーが関与するプロセスでは、単一AIだけでは対応しにくいケースが増えています。マルチエージェントなら、各AIが専門機能を分担し、必要なタイミングで連携・協力することが可能です。
例えば小売業では、接客AIが顧客との対話を担当し、レコメンドAIが購買履歴や嗜好データから最適な提案を生成、在庫AIがリアルタイムで在庫状況を確認し、購買判断に活用しやすくなります。
このように、それぞれのAIが得意分野で役割を果たすことで、システム全体の柔軟性・精度・応答速度が向上します。既存の部門間連携やレガシーシステムとの統合にも活用できる点が、現場運用における実用性の高さを示しているといえるでしょう。
マルチエージェントは、現場の自律性とシステム全体の統制を両立させる技術として注目されています。エージェント間の役割分担と連携によって、従来のシステムでは実現しにくかったリアルタイム最適化や業務全体の柔軟な制御が可能です。
ここでは、製造・物流・サービス分野における代表的な活用例を紹介します。実際の導入事例を知ることで、自社での適用イメージがつかめるでしょう。
マルチエージェントは、生産ラインにおける複数ロボットの協調作業を実現し、工程全体の柔軟な最適制御に貢献します。
例えば組立・検査・搬送などの工程に、それぞれ専用のエージェントを持つロボットを配置すれば、各ロボットが自律的に判断して役割を遂行しつつ、必要に応じて他ロボットと連携を取れます。
これにより、突発的なトラブルや設備の一時停止にも即時対応でき、生産ラインの停止リスクを最小限に抑えられるでしょう。また、作業負荷の分散や工程間の待ち時間の削減にも効果があり、人手不足への対応や生産性の向上を実現します。導入後も各ロボット単位での最適化が行えるため、拡張性と保守性にも優れた体制を構築できるでしょう。
広域な作業領域や動的な環境においては、空・陸・システムの3視点を統合した判断支援が不可欠です。
マルチエージェント構成を導入すれば、空撮を担うドローン、現地作業を担う地上ロボット、交通や移動経路の最適化を担うAIがそれぞれ独立しつつも連携しやすくなります。
例えば大規模施設の点検業務では、ドローンが施設全体をスキャンして異常を検出し、地上ロボットが該当箇所に移動して作業を実施、交通制御AIが作業車両の動線を最適化するといった連携もできるでしょう。
このような構成は、災害対応・施設保守・都市インフラ管理といったシーンで有効であり、迅速な判断と現場対応を高い次元で両立させられるでしょう。
小売・EC業界では、顧客ごとに最適な体験を提供することが競争優位性のポイントです。マルチエージェントの導入により、接客AI・在庫管理AI・レコメンドAIがそれぞれ専門機能を担いながら連携することで、リアルタイムな対応と高精度な提案がしやすいです。
例えば、接客AIがヒアリングした顧客の好みに基づき、レコメンドAIが類似顧客の傾向や購買履歴を解析し、即座に候補商品を提案してくれます。その後、在庫管理AIが現在の在庫状況と出荷可能日を確認し、購入判断に活かせるでしょう。
このような一連の流れを一体的に実現することで、スピード感ある接客と在庫連動型の提案が叶い、顧客満足度やリピート率の向上にもつながります。
物流業務におけるボトルネックの多くは、情報の断絶や現場の遅延に起因します。マルチエージェント構成により、配送AIと倉庫管理AIが連携することで、在庫引当・梱包ラインの負荷・配送経路・天候や交通状況までを考慮したリアルタイム最適化ができるでしょう。
例えば、注文受付と同時に倉庫AIが最適な出荷拠点とピッキング順を判断し、配送AIが効率的なルートと時間指定対応を調整します。突発的な道路渋滞が発生した場合でも、代替ルートを自動で再構築できるため、納期遵守率が向上します。
これにより、物流の安定性が高まり、繁忙期や緊急対応時でも高品質なサービスレベルを維持できるでしょう。
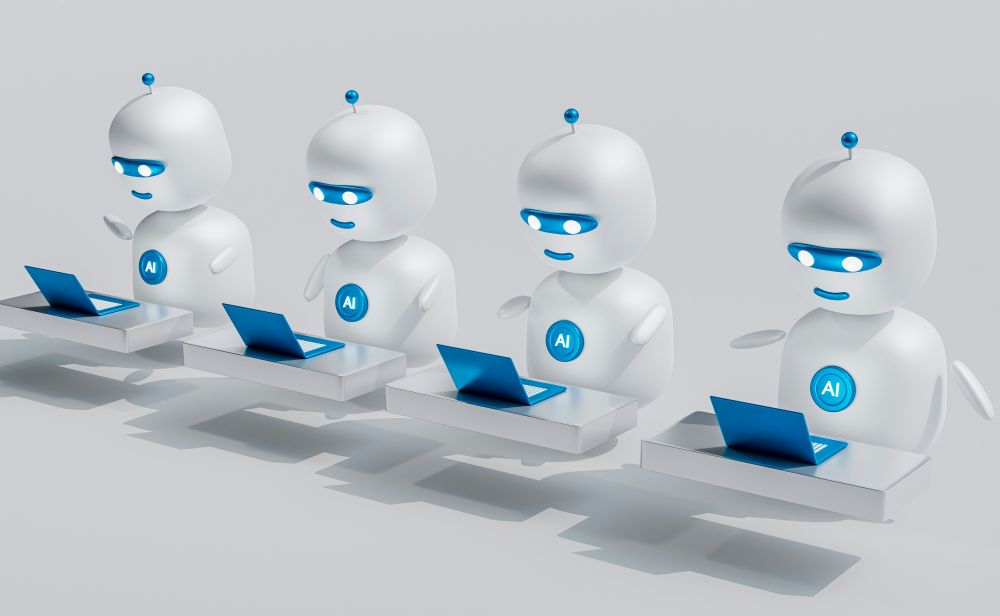
AIエージェントやマルチエージェントの導入においては、単に技術的に優れているだけでなく、自社の業務課題や将来的な運用体制に適合しているかを見極めることが重要です。
エージェント同士の連携方式・拡張性・導入実績・ログ管理の仕組みなど、複数の視点から事前に検討することで、実運用フェーズでの失敗を防げます。ここでは、導入判断にあたって押さえておきたい代表的な5つのポイントを解説します。
マルチエージェントの導入効果は、構成次第で大きく変わります。特に重要なのは、自社の業務課題や目的に合致したエージェント構成になっているかという視点です。
単なる技術導入ではなく、「何を解決したいのか」「どの工程がボトルネックなのか」を明確にした上で、それぞれの課題に対してどのような役割のエージェントが必要なのかを定義しなければなりません。
例えば製造業であれば、生産計画・機器制御・品質検査・保守など工程ごとの役割分担が重要です。汎用的なAIを並べただけでは効果は限定的で、業務フローに深く踏み込んだ構成設計が欠かせません。
上流工程からの要件を整理し、エージェント間の役割と関係性を整理した上で設計を進めることが、成功への近道です。
エージェント間で安定した連携を実現するには、通信プロトコルやデータ形式の標準化が不可欠です。導入初期には問題がなくても、他のシステムと統合したり拡張したりする段階で、独自仕様に依存していると柔軟性を損なう可能性があります。
例えば、エージェントがMQTTやAMQP、REST APIなどの業界標準プロトコルを用いて双方向通信を行えるか、JSONやXMLといった汎用フォーマットを採用しているかは重要な確認ポイントです。
標準化されていれば、将来的にベンダーを変更したり、異なるシステムやエージェントと連携したりする場合でも再設計や開発工数を最小限に抑えられるでしょう。また、セキュリティ認証や暗号化方式についても標準的な仕様に対応しているかあわせて確認が必要です。
PoCや限定的なスコープでマルチエージェントを導入する企業も増えていますが、本格運用を視野に入れるなら将来的な拡張性へ対応しておきたいところです。
例えば、初期は3~4種類のエージェントだけで構成されていたものの、業務領域の拡大に伴い新たなエージェントが必要になる可能性は十分にあります。その際、システム全体を作り直す必要があれば、導入効果が損なわれる可能性があるでしょう。
設計段階でエージェントの追加や入れ替え、通信負荷の増加に耐えられるアーキテクチャ(例:マイクロサービス構成やクラウドネイティブ設計)を採用しているかが重要です。また、データベースや通信基盤についてもスケールアップ・スケールアウトの対応力を持つ構成か確認しておくことで、将来的なトラブルや過負荷を回避できる可能性があります。
マルチエージェントは構成が複雑で、多数のAIやプロセスが絡むため、トラブル時の対応やノウハウ提供が大切です。そのため、製品やベンダーの選定においては「導入実績の豊富さ」と「技術サポートの充実度」を重視すべきです。
特に、自社と同じ業種・業態・規模での導入事例があるかを確認することで、実務に適した知見や支援体制を期待しやすくなります。加えて、トライアルから本番運用までを伴走できる体制が整っているか、PoC後の改善提案やトラブル発生時のリカバリー支援が受けられるかといった観点も欠かせません。
導入後の運用フェーズで発生する技術課題に迅速に対応できるかどうかは、業務継続性につながります。
エージェントの行動や通信履歴をログとして正確に取得・管理できる仕組みは、安定運用とリスク対策の両面において重要です。
業務で異常が発生した際に、どのエージェントがどのタイミングで何を判断・実行したのかを追跡できなければ、原因究明も改善も困難になります。さらに、行動ログはAIの判断根拠や信頼性の証明として、説明責任を果たすための重要な情報資産です。
ログは単に保存するだけでなく、リアルタイムに可視化できる仕組みがあるか、フィルタリングやアラート通知が可能であるかの確認が欠かせません。また、個人情報や機密情報を扱う場合は、暗号化・アクセス制御・ログ保管ポリシーの整備も必要です。
マルチエージェントは多様なAIが連携して機能するため、業務全体を効率化する可能性がありますが、その構成が複雑なぶん運用上の課題も発生しやすくなるでしょう。
本番運用を前提とした際には、連携構造・適合性・障害対応・セキュリティといった複数の観点から事前にチェックすべきポイントが存在します。ここでは、導入・運用時に想定される主な5つの課題と、それらに対する考慮点について整理します。
マルチエージェント構成では、各エージェントが独立して動作しつつ相互に連携するため、通信の複雑性が増します。
特にリアルタイム制御や動的判断が求められる業務では、タイミングのズレや競合によって予期しないトラブルが起こるケースもあります。また、導入時は正常に動作していても、システムの拡張や仕様変更が生じた際に連携エラーや非同期化が発生しやすくなるでしょう。
そのため、各エージェント間のインターフェースを明示し、通信フローを視覚化した上で、設計段階から冗長性や再送処理、状態管理の仕組みを取り入れておくことが重要です。フレームワークや統合基盤の選定時には、拡張時の連携管理機能も確認しておくと良いでしょう。
マルチエージェントの特性として、各エージェントがローカルな判断を最適化する一方で、システム全体としての整合性を損なってしまうことがあります。
例えば、営業部門向けAIが売上を最大化しようとする一方で、物流AIがコスト最小化を図ることで、処理能力を超えた注文が発生するような状況です。このような衝突を防ぐには、個別のエージェントに全体最適の指針を与える設計、あるいは統括的な意思決定エージェントの導入が効果的です。さらに、KPIの共有化や評価指標の一元管理も欠かせません。
初期設計時点で「部分最適の暴走」を想定し、調整ルールや優先順位の調整ロジックを用意することが、持続可能な連携運用につながります。
マルチエージェントの導入は理論上うまく設計できたとしても、実環境でスムーズに動作するとは限りません。特にPoC段階での現場検証は、導入後のトラブル防止や定着の鍵を握ります。
通信遅延、既存機器との非互換、センサーの誤作動など、現場固有の要因が業務パフォーマンスに大きく影響します。さらに、エージェント間の制御ロジックが現場フローに即していなければ、かえって作業が複雑化するリスクもあるでしょう。
そのため、単なる技術検証に留まらず、現場の作業員や管理者による運用テストを実施し、導入効果・改善余地・人的負担などを多角的に検証することが不可欠です。フィードバックループを確保する体制も整えておくと安心できるでしょう。
マルチエージェント環境では、1つのエージェント障害が他の複数プロセスに影響を及ぼす可能性があるため、障害時の影響範囲を可視化しづらいという課題があります。
特定エージェントの停止が連携業務のボトルネックとなり、連鎖的に全体システムの応答性や判断精度を低下させることも少なくありません。そのため、各エージェントのステータスをリアルタイムで監視し、異常検知・通知・自動フェールオーバーを行うための基盤構築が大切です。
また、設計段階で「単一障害点」を減らす構成にし、代替手段やバックアップエージェントを用意することが、安定稼働の前提となります。障害時の対応フローをドキュメント化し、属人化を防ぐ体制整備も求められます。
マルチエージェント環境では、複数のAIがネットワーク経由で連携・通信するため、セキュリティリスクが生まれます。特に外部APIとの接続やクラウド連携を伴う構成では、通信データの盗聴や改ざん、不正アクセスなどが発生しやすくなります。
各エージェントに対して認証・認可機能を個別に設定し、通信内容はTLS等で暗号化することが欠かせません。加えて、ログ管理・通信監査・アクセス履歴の可視化が可能な仕組みを構築しておくことで、異常の兆候を早期に察知しやすくなります。
現場端末の紛失や外部攻撃への備えとして、ゼロトラスト思想をベースにしたセキュリティ設計を採用する企業も増えています。システム全体のリスク評価を定期的に実施する体制も重要です。
AIエージェントの導入が進む中、マルチエージェント技術を活用して複数のタスクや業務プロセスを同時に処理・連携させるソリューションも増えてきました。
特に大手企業では、業務全体の自動化や判断の高度化を目指し、役割の異なる複数エージェントを協調させる構成が注目されています。ここでは、実際にマルチエージェントを活用したAIエージェントツールの代表的な事例を紹介し、それぞれの強みや活用シーン、導入メリットを詳しく解説します。
NTTデータが提供する「LITRON®」は、同社の先進AI技術を活用して業務改革を支援するブランドです。特徴は、「SmartAgent」と呼ばれる以下4種類のAIエージェントの組み合わせにより、多様な業務へ柔軟に対応できる点です。
例えば、営業やマーケティング、ファイナンスといった業界固有の業務に最適化されたLITRON SalesやLITRON Marketingなどを展開し、業務レベルの向上や付加価値創出、処理スピードの高速化を実現しています。
さらに、マルチエージェント構成により業務の連携と分担が効率化され、複雑な業務フローにも対応できるでしょう。コンサルから運用支援まで一貫して提供している点も安心材料といえます。
出典参照:LITRON®|NTTデータ
日立製作所が提供する「生成AI活用プロフェッショナルサービス powered by Lumada」は、生成AIの導入から運用、さらには人材育成までを一気通貫で支援する伴走型のサービスです。特に、製造・鉄道・エネルギーなどOT領域の豊富な知見と、IT技術の融合による高い実装力が大きな特長といえるでしょう。
本サービスでは、業務課題に即したユースケースの選定・実現性検証・RAG構築の支援をはじめ、生成AIアプリケーション開発や専門人材の育成支援まで幅広く対応しています。すでに社内外で約1,000件のユースケースを検証しており、回答精度や活用率の向上に関するナレッジも豊富です。
OT分野の複雑な業務プロセスにも対応可能なため、現場主導でのAI活用を進めたい企業にとって実効性の高い支援が期待できるでしょう。
出典参照:生成AI活用プロフェッショナルサービス|株式会社日立製作所
ソフトバンクが展開する「satto」は、社内業務の効率化に特化した法人向けAIエージェントサービスです。ドキュメント作成や情報検索、定型業務の自動化といったオフィスワークを支援する複数機能を提供しており、特に「satto workspace」はマルチエージェント型で構成され、用途に応じたAIが連携して業務を支えます。
例えば、資料作成用エージェントがコンテンツ生成を担い、検索エージェントが社内外の情報を収集・整理、タスク管理エージェントが業務フローを最適化するなど、それぞれが役割を分担して連携します。
また、直感的なUIと導入支援体制により、非IT部門でも使いやすく、企業全体の業務自動化を段階的に推進しやすいでしょう。サポート面でも評価が高く、PoC導入から本格展開までの流れが明確です。
出典参照:satto.me|ソフトバンク株式会社
まとめ|AIエージェントやマルチエージェントを活用して、業務最適化を図ろう

AIエージェントやマルチエージェントは、業務の自動化や省人化、スピード向上を実現する強力な手段です。
特に部署やシステムをまたぐ業務の最適化を検討する企業にとって、有効な選択肢となります。導入にあたっては、構成設計や拡張性、セキュリティ面まで考慮し、現場の業務課題と丁寧に擦り合わせていくことが重要です。
また、活用目的に応じたエージェント構成の検討やPoC段階での適合性評価も欠かせません。導入事例やユースケースを参考にしながら、自社のDX推進に最適な活用プランを立てていくことが、全体最適化と継続的な価値創出につながるでしょう。