建設DXでペーパーレス化は可能?メリットや成功のステップを解説
建設

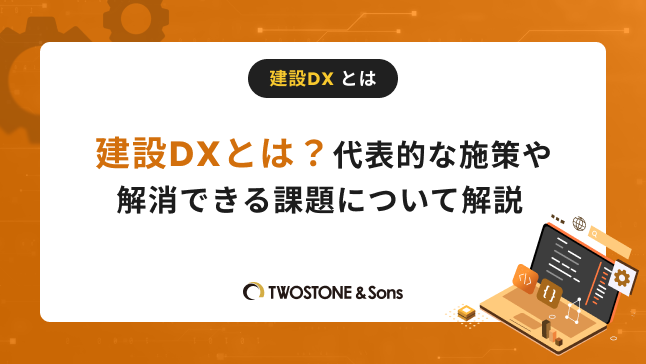
建設業界では人手不足や高齢化、作業の属人化、安全・品質管理の高度化など多くの課題が山積しています。本記事では建設DXの基本的な考え方や具体的な課題、代表的な施策を詳しく解説して今後の建設業の未来を切り開くヒントを提供します。
建設業界は今、転換点を迎えています。人手不足や高齢化といった慢性的な課題に加えて業務の属人化や現場の非効率性、さらには高度化する安全・品質管理への対応など多方面での変革が求められています。こうした状況を打破するカギとして注目されているのが、建設DX(デジタルトランスフォーメーション)です。
建設DXとはデジタル技術を活用して現場作業・設計・管理・業務フローなど、あらゆる領域を最適化して生産性と安全性を高める取り組みを指します。すでに一部の企業では、BIM/CIMやドローン、IoT、クラウドシステムなどを導入して現場業務の抜本的な改善を進めているのです。
本記事では建設DXの基本的な考え方から業界が直面する具体的な課題、そしてその解決策につながる代表的なDX施策について丁寧に解説します。建設業の未来を見据える方にとって、取り入れるべき戦略や視点が見つかるはずです。

建設DXとは建設分野における業務プロセスやサービス提供の在り方を、デジタル技術を活用して変革する取り組みを指します。DXは「デジタルトランスフォーメーション」の略称で、単にITを導入するのではなく業務全体を見直して価値提供の方法そのものを再構築することが目的です。
例えば設計工程にBIM(Building Information Modeling)を導入すると、建物の情報を3Dデータで一元管理できるでしょう。実際に現場では、ドローンを活用して施工状況をリアルタイムで可視化し、作業進捗を遠隔から確認する仕組みが広がっています。さらにクラウド型の施工管理ツールを使えば、現場と本社間の情報共有が迅速になり、報告・連絡・相談のスピードが向上します。
このように建設DXは業界全体の生産性や安全性、品質を高めるだけでなく働き方改革や若手人材の獲得にも直結する重要な取り組みです。
建設DXが求められる背景には、構造的かつ長年解消されていない業界課題の存在があります。ここでは特に深刻な、5つの問題を紹介します。
建設業界では若年層の入職者が減少しており、慢性的な人手不足が続いているのが現状です。公共事業や民間工事の需要が一定以上ある中、現場で作業できる人数が限られているため1人あたりの負担が増しています。
複数の現場を掛け持ちする職人が増えると、業務品質の低下や納期遅延のリスクも高まります。そのため人手不足は単なる労働力不足にとどまらず、企業の信用や事業継続にも影響する深刻な問題です。
加えて現場経験が浅い人材の増加により、教育やフォローの負担も増えています。これにより熟練者の負担がさらに増大し、疲労やモチベーション低下のリスクも無視できません。長期的な人材確保策が急務といえるでしょう。
建設現場を支える熟練職人の多くが50代後半〜60代を迎えており、高齢化が顕著になっています。一方でその技術を継承できる若手人材が不足しているため、技術の断絶が懸念されています。
例えば、ベテラン職人が担当してきた難易度の高い施工技術をマニュアルやデジタルデータで残さなければ、企業の技術資産として継続できません。高齢化は単なる年齢構成の問題ではなく、組織の知的財産の減少にもつながります。
高齢化が進む中で、職人の健康管理も課題です。現場作業は体力を要するため、無理が続くと事故やケガのリスクが高まります。若手育成と並行し、健康維持や働きやすさの改善も求められています。
建設現場では未だ、紙の図面や手書きの報告書に依存しているケースが多く見られます。工程の進捗管理や安全チェック、品質記録などがアナログで処理されていることが要因で作業に無駄が生まれやすい構造になっています。
例えば作業完了後に本社へ報告書を郵送するというフローでは、情報共有が数日遅れることも珍しくありません。こうした非効率な業務が、全体のスピードや意思決定に悪影響を与えています。
さらに現場の非効率は、コミュニケーション不足も引き起こします。関係者間での情報の遅延や誤解が生じることで、作業ミスや手戻りが発生しやすくなります。迅速で正確な情報共有の仕組みが不可欠です。
作業手順や判断基準が個人に依存している現場では、属人化が進行しやすくなります。担当者が変わると仕事の質が変わる、あるいは退職者が出ると業務が止まるなど組織としての安定性に欠ける状況が生まれます。
例えばある職人だけが施工手順を把握している場合、他のメンバーがカバーできずに作業全体が滞る可能性があります。属人化を解消するには、ノウハウの標準化と業務プロセスの見える化が不可欠です。
属人化の解消は、組織のリスクヘッジに直結します。そこで作業マニュアルや動画マニュアルの整備が進めば、誰でも一定水準の作業ができる環境が整うでしょう。こうした取り組みは人材育成の効率化にも貢献します。
労働災害や品質不良のリスクを最小限に抑えるため、安全管理と品質管理への取り組みがより強く求められています。社会からの信頼を得るためにも、可視性の高い仕組みづくりが重要になっています。
実際に、安全帯の着用確認や危険エリアの進入管理をIoTセンサーで実現する、といった事例が増えています。また品質チェックをデジタルで一元管理することで、トレーサビリティ(履歴追跡性)の強化にもつながるでしょう。
近年では、行政の規制強化や顧客からの要求水準も上昇し、安全文化の醸成が求められています。これに対応するには定期的な教育やトレーニングに加え、デジタル技術を活用した継続的なモニタリングが効果的です。
建設業界が抱える深刻な課題に対して、建設DX(デジタルトランスフォーメーション)は実効性の高い解決手段を提供します。デジタル技術を活用した具体的な施策は多岐にわたりますが、ここでは現場での活用が進む代表的な7つの施策を紹介します。
BIMは建築物の形状・構造・材料・工程・コストなど、あらゆる情報を3Dモデルで一元管理する仕組みです。従来の2D図面に比べて施工前の検討精度が向上し、手戻りの削減や関係者間の情報共有が円滑になります。
この仕組みを活用すると、施工段階で干渉部分を可視化し、設計変更を事前に行えるため現場でのトラブルを最小限に抑えられます。さらに保守段階でもデータを活用することで、建物のライフサイクル全体を通じた最適な管理が可能になります。
さらに、BIMの導入によって設計段階での関係者間の協働が強化され、情報の齟齬を減らせます。これにより工事中の変更対応もスムーズになり、結果として全体の工期短縮やコスト削減に寄与します。多様な専門家がリアルタイムにデータ共有できるのも利点です。
ドローンやレーザースキャナーを用いた測量技術は、現場の地形や構造物のデジタルデータ化を迅速に行えます。特に山間部や広大な敷地での作業効率が向上し、作業員の負担軽減にも寄与します。
実際に、上空からの高精度画像を基に三次元モデルを生成して施工前の準備や進捗管理に活用する、といった事例が増えています。これによって従来の手作業に比べて精度が向上し、スピードも改善されるでしょう。
ドローンやレーザースキャンは危険箇所の測量も安全に実施できるため、作業員の安全確保にも役立ちます。さらに取得したデータは即時クラウドへアップロードされるため、遠隔地にいる関係者ともリアルタイムで情報共有が可能となり、現場管理の効率化が促進されます。
IoT技術を活用して現場の温度・湿度・振動・作業者の位置情報などを、リアルタイムで取得・分析できます。これにより、安全管理や品質管理がより確実かつスピーディになります。
実際に、熱中症リスクが高まる夏季には作業員の体温や心拍をセンサーで監視し、リスクを事前に察知するシステムが導入され始めています。また振動センサーで構造物の変位を監視し、施工の安定性を可視化するケースもあります。
IoTの活用は安全管理だけでなく、作業効率の改善にもつながります。例えば機材の稼働状況をリアルタイムで把握できると、無駄な待機時間や故障による作業停止を減らせるでしょう。こうしたデータの蓄積は、将来的な現場運営の最適化に活用されます。
遠隔臨場は、現場に立ち会わずにビデオ通話やストリーミングを通じ、進捗や品質を確認する仕組みです。これによって監督者や設計者の移動負担を減らし、時間とコストの削減につながります。
この仕組みを活用すると複数の現場を1人の技術者が同時に管理できるため、人的リソースを効率的に活用できます。また撮影データが自動で保存されるため、監査証跡としても有効に機能するでしょう。
遠隔臨場は緊急時の迅速な状況確認にも有効です。例えば、自然災害などで現場への立ち入りが困難な際にもオンラインで詳細な進捗報告が可能となり、復旧計画の立案や関係者間の意思疎通が円滑に行えます。これにより対応速度が向上します。
施工ロボットや自動制御重機の活用は、危険作業の安全性向上と人手不足の解消に寄与します。ロボットは一定の精度と速度で作業を繰り返せるため、品質の均一化にも効果を発揮するのです。
実際にコンクリートの打設やタイルの貼り付けなど、繊細さと繰り返し作業が求められる工程でロボットが導入されています。重機の自動制御により、人の経験に依存せずに施工精度を確保する試みも進んでいます。
施工ロボットの導入は熟練者不足の解消だけでなく、作業の安全面にも好影響を与えています。危険な高所作業や重労働をロボットが担うことで労働災害のリスクが軽減され、現場の安全水準が向上、また品質の均一化も図れます。
紙やホワイトボードで行われてきた工程管理を、クラウドベースのツールで一元化する動きが加速しています。進捗のリアルタイム共有が可能になることで、遅れやトラブルへの迅速な対応が可能です。
タブレットやスマートフォンを使って現場で作業内容を入力し、それを本社の担当者が即座に確認できる仕組みは意思決定のスピードを変えます。また過去のデータを活用し、類似プロジェクトの工程予測も行えるようになります。
デジタル化された工程管理によって、作業の進捗だけでなく資材の手配や人員配置まで一元的に把握でき、無駄の削減につながります。加えて、過去のプロジェクトデータを分析してリスク予測や効率化策の立案にも役立てられ、現場の生産性向上を後押ししています。
AIを活用した設計・積算・見積ツールは、従来時間と労力がかかっていた作業を効率化します。大量のデータから最適解を導き出し、人手によるミスやばらつきを軽減できます。
例えば、過去の設計図面や見積データを学習させたAIが新しいプロジェクトに対して自動でレイアウト案や概算コストを提示できると、初期検討段階の時間短縮が実現するでしょう。設計者や積算担当者は、より創造的な業務に注力できるようになります。
AIの導入は初期段階の設計精度向上に加え、コスト見積もりの透明性も高めます。過去の膨大なデータを参照しながら最適解を提示するため、予算オーバーのリスクを抑制できます。結果として、プロジェクト全体の計画精度向上と信頼性の確保につながります。

建設業界ではデジタル技術を活用して業務効率や安全性を高める、建設DX(デジタルトランスフォーメーション)が注目されています。これによって従来の課題を克服し、持続可能な成長を実現するための一歩となります。
ここでは、建設DXを推進することによって得られる代表的なメリットについて詳しく解説します。
建設業界は多様な工程と複雑な作業が重なるため、生産性の向上が課題の1つです。建設DXではBIMやAI、IoTといった技術を活用して作業の無駄や手戻りを減らせます。
例えば、BIMによって建物の設計情報を3Dモデルで一元管理することで設計変更の影響範囲を事前に把握でき、現場でのトラブルを未然に防げます。さらに、AIが過去のデータを解析して作業工程の最適化を提案することで、作業スケジュールの精度が向上するでしょう。これによって計画通りの工期達成が可能となり、結果的にプロジェクト全体の効率が高まります。
生産性の向上は利益率の改善にも直結するため、企業経営にとって重要なメリットです。
深刻な人手不足は建設業界が抱える最大の課題といえるでしょう。高度な技能を要する職人の減少や新規就労者の不足が続く中、建設DXは人材不足を補う手段として注目されています。
例えばドローンによる測量や自動化重機の導入は、作業員の負担軽減と省力化を実現します。加えて作業の標準化や自動化は、未経験者でも比較的早期に戦力として活躍できる環境を整えるでしょう。これによって労働力の効率的な活用が可能となり、限られた人材で多様な作業をカバーできるようになります。
さらに建設DXは熟練技術者の技能伝承にも役立ち、業界全体の技術力の底上げに貢献します。
建設現場では安全管理と品質管理が、重要です。建設DXはこれらの課題に対し、先進的なソリューションを提供しています。
例えばIoTセンサーを活用すれば、作業環境の温湿度や振動をリアルタイム監視し、異常検知があれば即座に警告が出せるでしょう。またAIを用いた画像解析で作業の品質を自動チェックし、問題があれば早期に発見できるシステムも増えています。これによって人手による見落としや判断ミスを減らせるため、施工品質が安定します。
安全面でもリアルタイムデータに基づくリスク予測が可能となり、事故防止や迅速な対応が実現されます。
建設プロジェクトは多くの資材や労働力を必要とし、コスト管理が複雑になりがちです。建設DXを推進すれば工程管理や資材発注のデジタル化により、無駄な支出を削減できます。
例えばクラウドベースの進捗管理システムを活用すると、遅延や重複発注を減らして必要な資材を適切なタイミングで調達できます。加えて、AIによる見積もり精度向上や資材使用量の予測は過剰在庫を抑制し、資金繰りの効率化にも寄与します。これらによって資材の無駄遣いを防ぎながら必要な投資に資源を集中させられるため、全体のコスト構造を最適化できます。
結果として、競争力のある価格設定が可能となります。
建設現場では多くの関係者が連携しながら作業を進めるものですが、情報伝達の遅延やミスがトラブルの原因となります。建設DXのコミュニケーションツールは、これらの問題解消に役立つでしょう。
例えばクラウドを利用すれば、情報共有プラットフォームによって図面や工程表、報告書などをリアルタイムで全関係者に配信できます。さらに、モバイル端末を活用した現場報告や遠隔臨場機能により、現地とオフィス間の意思疎通が速くなるでしょう。これによって迅速な意思決定や問題解決が可能となり、無駄な待ち時間や誤解による作業遅延を減らせます。
円滑なコミュニケーションはプロジェクト全体の成功に不可欠です。
近年、建設業界には環境負荷低減や持続可能な社会づくりへの貢献が求められています。建設DXは省エネルギーや資源の有効活用を促進し、環境負荷軽減に寄与します。
例えばBIMを使った資材の適正配置や必要量の精密な算出を行うと、廃材を減らすことが可能です。また施工計画の最適化によって作業工程の短縮や重機の稼働時間削減が実現し、CO2排出量の低減につながります。さらに環境配慮型の建材選定やリサイクル技術をAIが支援し、サステナブルな施工を促進します。これらの取り組みは企業の社会的責任(CSR)を果たしつつ、長期的な経営安定にも貢献するのです。
建設業界の担い手不足を解消するには、若手や未経験者が早期に戦力として活躍できる仕組みづくりが不可欠です。建設DXは技能の属人化を排除し、標準化と効率化を推進します。
例えばAIによる作業支援ツールやVR・ARによる教育システムは、初心者が安全かつ正確に業務をこなせるようサポートできます。さらにシミュレーションや遠隔指導が可能になることで現場での学習機会が増え、経験を積みやすくなるでしょう。自動化技術と連携しながら作業を補助することで若手の負担も軽減し、離職率低下にもつながります。
このような環境整備は、将来的な業界の持続的発展を支える基盤となります。
建設業界においてDX(デジタルトランスフォーメーション)の重要性が高まる中、実際に先進的な取り組みを実践し、具体的な成果を上げている企業の事例が注目されています。
ここでは国内の代表的な建設企業5社によるDX施策を紹介し、それぞれの技術的特徴と実効性について掘り下げていきましょう。
青木あすなろ建設は山岳トンネル工事の現場において、自律飛行ドローンを活用した設備点検を実施しています。従来の手法では作業員が直接危険区域に立ち入って目視確認を行っていましたが、この取り組みにより安全性と効率性が向上しました。
同社では事前に設定したルートを自動で飛行することで、一定の品質で均質な点検が可能になります。取得した高精度映像はクラウド上で管理され、過去データとの比較や異常の早期発見に役立っています。このような無人化の進展は、人手不足への対応策としても期待されます。
参考:青木あすなろ建設株式会社
安藤・間では複雑な地盤条件への対応力を高めるために、AIとCIM(Construction Information Modeling)を統合した独自システム「GeOrchestra」を導入しています。このシステムは各種地盤データを収集・分析し、設計や施工方針の意思決定を支援するものです。
同社が開発したシステムは、ボーリングデータや地中レーダーの情報をAIが統合・解析することで地質リスクを視覚化できるものです。その結果として設計段階での柔軟な対応が可能となり、後工程でのトラブル回避に直結します。またCIMにより施工フローや資材配置も三次元で可視化され、関係者間の情報共有がスムーズに行われます。
参考:株式会社 安藤・間
大林組は建設現場を仮想空間に再現する「デジタルツイン」技術を活用し、災害対応力の向上に取り組んでいます。センサーやカメラで収集した現地データを基にリアルタイムで仮想モデルを構築し、状況の把握や予測を可能にします。
この技術を活用すると、地震や豪雨による地盤変動を即座に検知し、施工中断や作業員退避などの判断を迅速に行えます。さらに得られたデータは関係機関とリアルタイムで共有され、災害対応計画の精度向上にも寄与しています。現場における、リスクマネジメントの高度化が進んでいる好例といえるでしょう。
参考:株式会社大林組
奥村組ではDX(デジタルトランスフォーメーション)の実証・開発を推進するため、自社内にクロスイノベーションセンターを設置しています。この施設はAI・ロボット・センシング技術など、異分野の融合による建設技術の高度化を目的とした研究・開発の拠点です。
実際に同社では、現場作業を担うロボットの試験運用や施工計画自動化のためのアルゴリズム開発などが進められています。実証データは実際の現場にもフィードバックされ、現場起点での技術実装が可能となっています。このような施設の存在は、長期的な競争力の源泉になるといえるでしょう。
参考:株式会社奥村組
鹿島建設はロボットとIoT技術の融合による次世代施工管理を目指し、さまざまな技術連携を積極的に進めています。特にロボットの精度向上とデータ利活用を重視し、協力企業との共同開発も展開中です。
これらの技術を活用することで、同社はコンクリートの打設ロボットでは施工中にセンサーが圧力や温度を取得し、リアルタイムで施工条件を調整しています。これによって仕上がりの品質が安定し、作業時間も短縮されました。さらにIoTデバイスから得たデータを活用することで、現場全体の工程管理や安全管理の最適化も実現しています。
参考:鹿島建設株式会社
建設DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進は多くのメリットをもたらしますが、実現にはいくつかの注意点を踏まえた慎重な対応が必要です。特に現場とIT技術の融合は単なる技術導入にとどまらず、組織全体の意識改革や体制づくりを伴います。
ここでは建設DXに取り組む際に意識すべき、3つのポイントを解説します。
建設現場の作業者とIT部門、または技術ベンダーとの間にはしばしばコミュニケーションや理解のズレが生じるものです。
例えば現場では、実際の施工環境や慣習に即した対応が求められる一方、IT側は技術的な効率性や理論を重視することが多いです。このギャップが放置されると導入したシステムが使われなかったり、現場の負担が増えたりする原因になります。そのため双方の意見を尊重し、両者をつなぐ橋渡し役を置くことが重要です。
例えば現場経験のある人材をITチームに加える、もしくは逆にITリテラシーの高い現場担当者を育成するなどが効果的でしょう。加えて、現場で実際に使いやすいシステム設計や操作性の検証を繰り返し行い、段階的に導入を進めることでスムーズな定着を促せます。
建設DXでは大量のデータが生成され、設計情報や施工記録、工程データなどがクラウド上で管理されます。これに伴って情報漏えいやサイバー攻撃といったリスクが高まるため、セキュリティ対策が不可欠です。
例えばアクセス権限の厳格な管理や通信の暗号化、多層的な防御策を導入して情報資産の保護を強化しなければなりません。
またデータの正確性と可用性を確保するため、定期的なバックアップやシステム監査を実施することも求められます。加えてデータの活用において、プライバシー保護や個人情報の適切な取り扱いが重要です。これらの取り組みが不十分だと企業の信頼失墜や法的問題に発展する恐れがあるため、経営層の関与と継続的な見直し体制の構築が欠かせません。
建設DXは単に最新の技術を導入すればよいわけではありません。目的を明確に設定し、それに基づいて業務プロセスを再構築することが成功のカギです。
例えば生産性向上なのか安全性の強化なのか、あるいは人手不足対策なのかを具体的に定めてそれに応じたツールやシステムを選定しましょう。
さらに既存の業務プロセスを洗い出して無駄や非効率な部分を見直すことで、DX推進の効果が最大化されます。単にデジタル化しただけでは旧態依然としたやり方を継続することになるため、根本的な変革が必要です。プロジェクトチームを編成し、現場と管理部門が協力して改善案を検討しながら段階的に推進することが望まれます。

建設DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進には多くの可能性が秘められていますが、その実現には自社の課題を正確に把握して適切な技術と体制を選ぶことが不可欠です。
人手不足が深刻な企業では自動化技術を優先的に導入し、品質管理に課題がある場合はIoTやAIによる監視体制の強化など目的に沿った戦略的な取り組みが重要になります。
DXの推進は単なる技術革新ではなく、企業の働き方や文化を変えるきっかけです。無理に急ぐのではなく、現場の声を尊重しながら段階的に進めることが成功の秘訣となります。技術選定や導入計画の策定においては、専門知識を持つパートナーの支援を活用することも効果的です。
まずは本記事を参考に、自社の現状に合った効率的で安全なDX推進を目指してみてはいかがでしょうか。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
