建設DXでペーパーレス化は可能?メリットや成功のステップを解説
建設

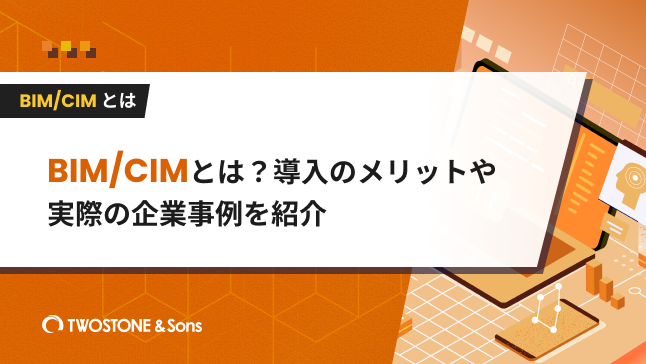
BIM/CIMを導入する際の注意点について詳しく解説します。関係者間のデータ共有体制を整え、初期コストを正確に把握し、従来の業務との整合性をしっかり確認することで、効果的な設計と安全な施工を実現するための重要なポイントを紹介します。
建設業界はデジタル技術の進展に伴い、大きな変革期を迎えています。その中でも特に注目されているのがBIM(ビルディング・インフォメーション・モデリング)とCIM(シビル・インフォメーション・モデリング)です。これらは従来の2D図面を超え、3Dモデルや情報を活用することで設計・施工・維持管理を効率化する手法です。これらの技術の導入により作業の質や効率が向上し、ミスの削減やコスト管理の精度アップが期待されます。
本記事ではBIM/CIMの基本的な概念から、導入が進む背景、そして具体的なメリットと実際に導入している企業の事例を詳しく解説していきます。建設DXを加速させたい方にとって必読の内容です。

建設業界で耳にするBIMとCIMは似ているようで異なる役割を持っています。正しく理解し使い分けることで、その効果を最大化できるでしょう。
ここではそれぞれの特徴と違いをわかりやすく説明します。
BIMとは、建築物の設計から施工、維持管理までのライフサイクルを3Dモデルと関連情報で一元管理する手法です。3Dモデルには構造や設備、内装、仕上げ材など建物のあらゆる要素が組み込まれ、設計変更や工事の進捗確認、維持管理に活用されます。設計図面だけでは把握しにくい空間の関係性や干渉部分が3Dモデルで可視化できるため、施工ミスや手戻りを削減します。
また、BIMは単なる3Dモデル作成に留まらず、スケジュール管理やコスト管理、資材調達の最適化にも役立つのがポイントです。設計段階でシミュレーションを行い、施工性や耐久性の検証も可能です。これにより、品質を確保しつつコストと工期の両方を管理しやすくなります。
一方、CIMは土木構造物に特化した情報モデリング技術で、BIMの考え方を応用しています。道路、橋梁、トンネル、ダムなどの社会インフラの設計・施工・維持管理に用いられています。例えば、トンネル掘削の計画を3Dモデルで作成し、掘削工程の安全性を事前に評価したり、施工中の進捗や安全を管理したりする際に活用可能です。
CIMは地形情報や環境データも取り込み、土木構造物の広範囲にわたる管理に適しています。従来の2D図面だけでは難しかった情報共有が進み、関係者間の連携強化や手戻り防止に寄与します。また、維持管理フェーズでも効果を発揮し、点検記録や補修計画をデジタルで一元管理できるのです。
BIMとCIMの大きな違いは対象物の種類です。BIMは主に建築物にフォーカスし、CIMは土木構造物に特化しています。技術的な基盤は共通しており、どちらも3Dモデルの活用と情報統合により業務効率化を図りますが、CIMは地形や環境の広域データ取り扱いが重要です。
例えば、都市開発のプロジェクトではBIMを用いて建築物の設計を進めつつ、CIMを使ってインフラ全体の設計や管理を行うケースがあります。このようにBIMとCIMは相互補完的な役割を担い、総合的な建設DX推進に欠かせない技術となっています。
近年、建設業界でBIM/CIMの注目度が急上昇していますが、その背景には大きく分けて2つの理由があります。1つは国の政策的な後押し、もう1つは従来手法の限界と課題の顕在化です。
国土交通省は建設DXの推進に向けて、令和5年度から公共工事におけるBIM/CIMの原則適用をスタートしました。これは公共工事の設計から施工、維持管理に至るまで情報のデジタル化と統合管理を義務化する動きです。この動きに倣って、道路や橋の設計段階でBIM/CIMを用いて3Dモデルを作成し、関係者間で共有しながらプロジェクトを進める必要が出てきました。
この政策によりBIM/CIMの導入が加速し、業界全体の技術レベル向上や作業効率化に寄与しています。また、デジタル技術を活用した施工管理や点検作業の効率化も促進され、公共インフラの維持管理コスト削減にもつながっています。
参考:国土交通省
従来は紙や2Dの図面が主な設計・施工資料でしたが、これらには情報共有の遅れやミスが多く存在しました。設計変更が現場に伝わらず施工ミスが生じたり、図面の不整合で手戻りが頻発したりするケースは少なくありません。
また、設計段階と施工段階、さらには維持管理の情報が断絶され、効率的な資産管理が困難でした。こうした非効率やリスクを軽減する手段として、BIM/CIMのような3Dモデルを中心とした情報統合手法が必要とされてきました。
さらに、技術者の高齢化や人手不足が進む中で、業務の効率化や省力化を図るにはデジタル化が欠かせません。BIM/CIMはこれらの課題に対応し、建設プロジェクトの生産性向上や品質確保、安全管理の強化に寄与しているといえます。

BIM/CIMは設計から施工、維持管理までの一連のプロセスに影響を及ぼします。各段階での課題解決に役立つため、現場の生産性や品質向上に貢献しています。
まず、BIM/CIMを導入すると設計精度が向上します。従来の2D図面では表現しきれなかった細かな要素まで3Dモデルで可視化できるため、設計ミスや干渉の発見が早まります。例えば、設備配管や構造体が重なる箇所を設計段階で発見できれば、施工時の手戻りを予防できます。
また、設計段階で複数のシミュレーションを実施可能です。耐震性やエネルギー効率の検証、施工手順の検討などがデジタル上でできるため、現実的かつ最適な設計案を作成できます。このため、品質を確保しながら無駄を省く設計が可能となり、プロジェクト全体の成功率を高めます。
さらに、設計変更時にもモデルの一括更新ができ、最新情報の共有が容易です。これにより、設計ミスのリスクを削減し、設計精度の向上につながります。
BIM/CIMはミスの予防と早期改善に貢献します。具体的には、3Dモデル上で施工手順や資材の配置を事前に確認できるため、施工段階での誤りや見落としを未然に防げるでしょう。従来の2D図面ではイメージしづらかった現場の実態を、立体的に把握できる点が大きな強みです。
さらに、工事の進捗や施工状況をリアルタイムで共有し、問題があれば即座に対応可能です。これは進捗遅延や施工不良が発生した際に、モデルを参照しながら関係者間で原因を分析し、迅速に修正指示を出すことにつながります。
このように、BIM/CIMは設計段階から施工、管理までミスの発見と解決を支え、工事全体の品質維持を実現します。また、過去のデータ蓄積によって将来のプロジェクトにおける同様の課題を予防することも可能です。
BIM/CIM導入で特に効果が高いのは、関係者間の情報共有の円滑化です。建設プロジェクトは多くの専門家や業者が関わるため、情報伝達の遅れや誤解がトラブルの原因となりやすいです。しかし、BIM/CIMを用いると、共通の3Dモデルをベースにコミュニケーションが可能になります。
例えば、設計者、施工者、発注者、管理者が同じモデルを参照しながら打ち合わせを行うことで、認識のズレを最小限にできます。これにより、意思決定の速度と正確性が向上し、プロジェクトのスムーズな進行に寄与します。
また、クラウドを活用すれば遠隔地の関係者もリアルタイムで最新の情報を閲覧・更新できるため、場所や時間を問わず効果的に情報共有が進みます。これにより、従来の紙ベースやメール中心のやり取りに比べて、作業効率が改善します。
施工計画や工程管理においても、BIM/CIMは大きなメリットをもたらします。3Dモデルにスケジュールや資材情報を連携させると、施工順序や資材搬入のタイミングを正確に把握可能になります。モデル上で工程の進捗を視覚化すればボトルネックや遅延の原因を素早く発見できるため、適切な対策が取りやすくなります。
さらに、施工段階での安全管理にも活用可能です。危険箇所や作業範囲を3D上で示し、リスクアセスメントを行うことで、安全対策の強化に役立てられます。これにより、事故防止や作業員の安全意識向上につながるでしょう。
またBIM/CIMは、資材の無駄遣いを減らしコスト管理にも貢献します。工程の最適化により余計な作業や手戻りが減少し、工期短縮にも効果的です。結果として、全体のプロジェクトコスト削減に寄与し、発注者と施工者双方の満足度を高められます。
BIMとCIMは似たコンセプトを持ちながらも対象が異なります。そのため、利用されるツールも建築向けと土木向けで特徴が違うので注意しましょう。
ここでは、各分野における代表的なソフトウェアを取り上げ、それぞれの特徴や強みを解説します。
BIMのツールは主に建築設計や施工管理で利用され、3Dモデリングだけでなくコラボレーション機能やシミュレーション機能が充実しています。設計の正確性を高め、関係者間の情報共有を円滑にする役割を担います。
Revitは世界的に広く使われているBIMソフトウェアで、建築設計・構造設計・設備設計に対応しています。多様な分野を1つのプラットフォームで統合できるのが大きな特徴です。例えば、建築士が設計した3Dモデルを構造技術者が解析し、その結果を設備設計者と共有するといった協働作業がスムーズに行えます。
さらにRevitはパラメトリックモデリングを採用しており、設計変更がモデル全体に自動的に反映されるため手作業での修正が減ります。クラウドとの連携も可能で、多拠点のチーム間でリアルタイムに情報を共有できる点が生産性向上につながっています。
ARCHICADは特に建築設計に特化したBIMソフトで、直感的な操作性が特徴です。例えば、初期段階のデザインから詳細設計まで幅広く対応しており、建築家や設計者の創造性を支援します。
ARCHICADはオープンBIMに対応して多様なフォーマットと連携できるため、他のソフトウェアとの互換性が高いです。施工管理ツールやコスト管理システムと連携して設計情報を効率的に活用することも可能なツールです。また、レンダリング機能も充実しており、リアルなビジュアライゼーションでクライアントとのコミュニケーションが円滑になります。
CIMは、土木分野の設計・施工・維持管理に特化したツール群が揃っています。地形データの取り込みや土量計算、施工シミュレーションなどに強みがあり、広範囲のインフラ整備プロジェクトを効率化します。
Civil 3Dは、土木設計分野で世界的に標準的に使われているCIM対応ソフトウェアです。このツールは道路・橋梁・排水設備など多様なインフラ設計に対応し、地形データや3Dモデルを統合して管理します。
Civil 3Dでは地形の起伏を正確に反映した3Dモデルを作成し、土工量の計算や施工工程の計画が容易になります。また、GISデータの連携機能が充実しているため、地域環境情報と統合した設計が可能です。さらに、設計変更が生じた場合もモデルが自動更新されて関係者間で常に最新情報を共有できるため、手戻りやミスを削減します。
TREND-COREは日本国内の土木・建設業界に特化したCIMソフトで、設計から施工・維持管理まで幅広く対応しています。国土交通省が推進するi-Construction対応に適しており、現場のデジタル化を強力にサポートします。
TREND-COREは3Dモデルと施工計画の連携が強化されており、重機の自動制御や施工進捗の可視化に活用されているツールです。また、クラウド上でのデータ共有で現場とオフィス間におけるリアルタイムな情報更新ができ、作業効率と安全性の向上につながっています。さらに、点検記録や補修履歴もデジタルで管理できるため、維持管理の効率化に寄与しています。
参考:福井コンピュータ株式会社
BIM/CIM導入は段階的に進めることでリスクを軽減し、社内の理解と協力を得やすくなります。ここでは3つの大きなフェーズに分けて解説します。
まず、BIM/CIMを導入する目的を社内で共有し、運用の基本方針を決定します。導入の目的は企業やプロジェクトごとに異なり、設計の効率化・施工ミスの削減・品質管理の強化などが挙げられます。目的が曖昧だと導入効果の評価や具体的な運用ルールの策定が困難になるため、関係者間で合意形成を行いましょう。
運用方針では、どの業務にBIM/CIMを活用するか、どのツールを使用するか、データの管理方法や情報共有のルールなどを明確にします。設計部門だけでなく施工部門や維持管理部門まで範囲を広げるか、あるいは限定的にスタートするかなど段階的な導入計画を策定しましょう。
また、社内のDX推進体制と連携してBIM/CIM導入を中長期的な経営戦略の一環として位置づけることで、経営層の理解と支援も得やすくなります。運用方針は文書化し、社内周知を徹底することで導入後の混乱を防げるでしょう。
導入目的と方針が決まったら、実際に運用を担うための環境整備に移ります。具体的には、BIM/CIM対応ソフトウェアやハードウェアを選定し、導入しましょう。ツール選定では、自社の業務に適した機能を持つものを選ぶことが重要です。例えば、設計段階での詳細なモデリングが必要な場合は高機能なBIMソフトを、施工管理を重視するなら施工支援ツールとの連携が強いものを選びましょう。
また、ツールの導入だけでなく、それを活用できる人材の確保と育成も不可欠です。BIM/CIMに精通した専門技術者を採用するほか、既存社員のスキルアップも並行して進めましょう。例えば、社内研修や外部セミナーを活用し、操作技術だけでなく運用ルールや活用メリットを理解させることが効果的です。
さらに、プロジェクトマネジメント能力を持つ人材を配置し、導入計画の進行管理や関係者調整を行うことがスムーズな運用につながります。人材育成は一過性のものではなく継続的な取り組みが求められるため、教育体制の整備と評価制度の構築も重要です。
初期段階では、全社一斉導入ではなく限定的なプロジェクトや部門で試行導入を実施します。試行導入を通じて、実際の業務にBIM/CIMがどのようにフィットするか操作上の課題や運用ルールの不備を把握しましょう。例えば、設計部門でのモデリング作業や施工計画での工程管理にBIM/CIMを活用し、効果検証を行う方法がその一例です。
試行導入で得られた課題や改善点を基に、運用ルールの見直しやツールのカスタマイズを進めて業務フローにBIM/CIMを自然に組み込んでいきます。こうした段階的な調整を怠ると現場の混乱や抵抗が生じやすく、導入効果を最大限に引き出せません。
また、試行導入では関係者の意見を積極的に収集し、導入に対する理解や協力を促進します。成功体験を共有し、社内の横展開や拡大導入へつなげることも重要です。最終的にはBIM/CIMの活用が業務プロセスの一部として定着することを目指しましょう。
ここでは、BIM/CIMを成功裏に導入した国内企業の具体的な事例を紹介します。これらのケーススタディからは、導入に際しての工夫や運用ノウハウ、得られた効果が具体的に見えてきます。自社の導入検討や運用改善に向けて参考にしてください。
株式会社エイト日本技術開発は、CIMの導入促進を目的に専門部署としてCIM推進室を設置しました。この部署は技術普及のための社内教育や外部への広報活動を担い、CIM活用の理解を深める役割を果たしています。
同社では、CIM導入初期段階で社内の抵抗感を減らし、各部署間の連携強化を図るために推進室が中心となり段階的な導入計画を立てました。実際に技術セミナーやハンズオン研修を定期開催するなど、実務担当者のスキル向上に注力しています。
この体制によりCIM技術の社内普及が加速し、工事の効率化や品質向上につながりました。また社外向けの発表や技術交流にも積極的で、業界全体のCIM活用促進にも貢献しています。推進室の設置は、組織全体の意識改革と技術浸透の大きなカギとなっています。
株式会社オリエンタルコンサルタンツは、設計段階で作成したBIM/CIMデータを施工段階に連携して効率的な工事を実現しています。設計図面と3Dモデルを融合させ、施工計画や資材管理に活用しています。
実際に施工前に3Dモデルを用いた工程シミュレーションを実施し、施工手順の最適化やリスクの早期発見に役立てました。これにより、工事の手戻りや遅延が減少しました。
また、現場ではBIM/CIMデータを基に進捗管理や品質チェックを行い、デジタルデータが一貫して運用されています。施工現場での意思決定が迅速かつ正確になり、コスト削減や安全対策の強化にもつながりました。
株式会社建設技術研究所は、ダムの放流設備の実施設計にBIM/CIMを導入しました。複雑な構造物の設計において、3Dモデルを活用することで設計の正確性と効率性を向上させています。
実際に多様な設備の配置検討や配管の干渉チェックをBIMモデル上で行い、設計変更を迅速に反映しました。設計の品質が向上し、施工段階でのトラブルを減らすことに成功しました。
また、維持管理段階でもBIM/CIMデータを活用し、設備の状態把握や保守計画の立案に役立てています。こうしたライフサイクル全体での活用は、長期的なコスト削減と施設の安全性確保につながっています。
参考:株式会社建設技術研究所
BIM/CIMの導入は建設業界のDXを前進させる一方で、スムーズな運用のためにはいくつかの注意点を押さえる必要があります。技術導入に伴う課題を未然に防ぐことで投資対効果を最大化し、現場の混乱を避けることが可能です。
ここでは、導入時に特に重要視すべき3つのポイントについて解説します。
BIM/CIMは、多様な関係者が同一のデジタルデータを共有しながら協働する仕組みです。関係者間でのデータ連携体制が適切に整っていないと、情報の錯綜や認識のズレが発生しかねません。これが原因で施工ミスや手戻りが発生すれば、導入効果が薄れてしまいます。
これを防ぐためには、設計者・施工業者・維持管理担当者といった異なる部署や企業間での情報共有ルールを明確に定める必要があります。ファイル形式の統一や更新頻度・アクセス権限の管理を徹底し、最新データを常に全員が参照できる環境を整備しましょう。
さらに、クラウドプラットフォームの活用によってリアルタイムにデータを同期させることが可能です。こうした環境構築により関係者間のコミュニケーションが円滑になり、意思決定のスピードも向上します。
BIM/CIMの導入には高性能なソフトウェアの購入や専用ハードウェアの整備が必要となる場合が多く、初期費用は決して小さくありません。また、技術習得のための社員教育や外部研修も欠かせず、これらの教育コストも計画に含める必要があります。
例えば、導入直後は操作ミスや運用ルールの不徹底による非効率が一時的に発生することがあり、これを見越したコスト管理が求められます。投資回収期間を現実的に設定し、短期的な成果に固執しすぎず中長期的な視点で効果を評価することが重要です。
また、教育体制を社内で整備して段階的なスキルアッププログラムを用意することで社員の理解度と活用意欲を高められます。例えば、操作研修だけでなくBIM/CIMの導入背景やメリットも併せて伝え、組織としての意識改革を促す取り組みも効果的です。
BIM/CIMの導入は従来の業務プロセスに大きな変革をもたらしますが、急激に既存業務と乖離すると現場混乱や反発が起きやすくなります。そのため、既存プロセスとの整合性を慎重に確認しながら移行計画を策定することが肝要です。
例えば、設計から施工・維持管理までのワークフローにBIM/CIMのプロセスをどの段階で組み込むのかを明確にし、段階的に切り替えていく方法が効果的です。既存の報告書や図面作成フローとデジタルデータの作成手順を比較し、重複や抜け漏れが生じないよう調整を進めましょう。
また、関係者の理解度に応じて部分的なプロセス変更を試験導入し、フィードバックを基に改善を繰り返すことでスムーズな定着が期待できます。こうした段階的な導入は抵抗感を減らし、BIM/CIMの価値を実感しやすくするポイントでもあります。

BIM/CIMの導入は、設計の精度向上や施工の効率化・安全性の強化に欠かせない施策です。導入に際しては、関係者間のデータ共有と連携体制をしっかり構築して初期コストや教育負担を現実的に捉え、既存の業務プロセスとの整合性を念入りに確認することが重要になります。
本記事で紹介した注意点を踏まえて段階的かつ計画的に導入を進めれば、現場でのミス削減や業務効率化が実現し、結果的に企業競争力の向上につながります。BIM/CIMは単なる技術導入ではなく建設業界全体の働き方改革を促進する強力なツールであることを認識し、効果的に活用しましょう。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
