建設DXでペーパーレス化は可能?メリットや成功のステップを解説
建設

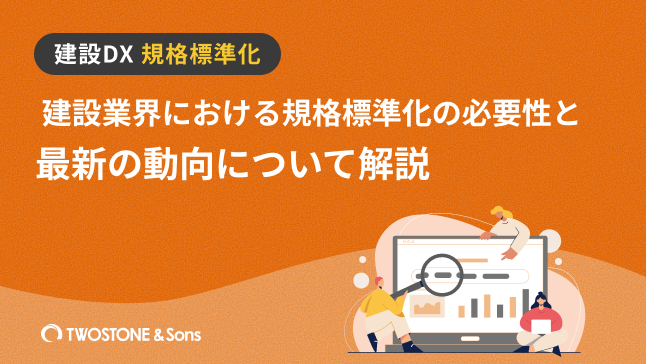
建設DXの推進には規格標準化が不可欠です。この記事では、最新の動向や実際の企業事例を通じて、規格標準化の重要性と具体的な取り組み方法を詳しく解説します。これにより、効率的なデジタル化の実現や業務改善につながるポイントを理解できます。
建設業界は、長年にわたり多様な業務形態と個別の現場対応に支えられてきました。しかし、近年の技術進展や労働環境の変化により、従来のやり方では対応しきれない課題が増えています。特に建設DX(デジタル・トランスフォーメーション)の推進に伴い、規格標準化の重要性が急速に高まっています。
本記事では、建設業界における規格標準化の必要な背景と、その遅れがもたらす問題点や最新の動向について詳しく解説します。この記事を読むことで、規格標準化が建設業の未来をどう変えるのか理解が深まり、自社のDX戦略に役立てられるでしょう。

建設DXの成功には、規格標準化が欠かせません。では、なぜ規格標準化が必要となったのか、その背景を紐解いていきましょう。複雑かつ多様な建設業界の実態を踏まえながら、3つの視点から解説します。
建設業では、案件ごとに仕様や条件が大きく異なります。単品受注生産は、製造業のような大量生産と違って規格化が難しい側面を持ちます。また設計・施工・管理といった業務プロセスも多様で、各社ごとに異なる手法やツールを用いるケースが多いです。例えば、設計段階で使用するCADデータの形式が異なるため、他の業者とのデータ連携がスムーズに進まないこともあります。
こうした背景からデータや情報の共有に標準的な規格が必要となり、業界全体で共通のルールを整備することが求められています。標準化が進めば異なる企業や部署間の連携が強化され、効率的なプロジェクト運営が可能になります。
建設業界は長年にわたり慢性的な人手不足に直面しています。加えて熟練技術者の高齢化が進み、技術継承が課題となりました。若手の人材確保や教育に多大な時間と労力を要する状況で、属人的なノウハウ依存は限界を迎えています。
このため、業務の標準化・規格化により誰でも一定の品質を保った作業が行える環境を整えることが急務です。例えば、作業手順書のデジタル化と標準化により経験が浅い作業員でも適切に作業を進めやすくなります。また技術情報を共通のフォーマットで管理すれば、熟練者のノウハウを効率的に次世代に伝える基盤を築けます。
このように、規格標準化は人材育成や技術継承の面でも効果を発揮し、現場の安全性や品質維持に寄与します。
グローバル化や市場の成熟により、建設業界の競争環境は一層厳しくなっています。同時に、原材料費の高騰や労務費の増加などコスト圧力も高まっています。こうした状況下で競争力を維持・強化するためには、作業効率や品質の向上が不可欠です。
規格標準化によって共通の作業基準やデータフォーマットが整備されると、無駄な手戻りや誤解が減り、作業の精度が向上します。例えば、設計情報と施工計画が統一された規格に基づいていれば、変更対応や現場調整の手間が減少するでしょう。結果として、全体のプロジェクトコスト削減や納期短縮にもつながります。
また、標準化は品質保証やトレーサビリティの向上にも寄与し、顧客満足度の向上や信頼獲得にも貢献するため、競争力強化の有効な手段となります。
規格標準化が十分に進まなければ、建設業界においてさまざまな弊害が生じます。
ここでは主に3つのリスクを取り上げ、具体的にどのような影響があるのか説明します。
規格が統一されていないと、異なる企業やシステム間でデータのやり取りが円滑に進みません。例えば設計データのファイル形式が統一されていない場合、変換作業や再作成が必要となり無駄な時間が発生します。さらに、複数のソフトウェア間で互換性がないと情報共有の遅れや誤解が生まれやすくなることも課題です。
このような非互換性は業務効率の低下を招き、プロジェクト全体の遅延やコスト増加の原因となります。業界全体で規格を揃えなければ、DXの本来の効果が得られず投資が無駄になる可能性も高まります。
建設DXが進むためには、業界全体のデジタル化が欠かせません。ところが規格標準化が遅れていると、各企業が独自のシステムやフォーマットを使い続けてデータの連携や共有が困難になります。結果として、建設業界全体の生産性向上やイノベーション創出が阻害されます。
そこで複数の企業が関わる大規模プロジェクトで情報が一元管理できなければ、進捗管理や品質管理に混乱が生じるでしょう。デジタル技術の恩恵を受けるためには、共通の基盤として規格標準化が必須です。
現場では、仕様や手順が標準化されていないと作業員や管理者の間で認識のずれが生じやすくなります。同じ工程でも業者ごとに異なるやり方があれば、安全基準の遵守が難しくなったり品質にばらつきが出たりすることも課題です。
こうした混乱は事故のリスク増加や再工事の発生につながり、結果的にコスト増加や顧客信頼の失墜を招きます。規格標準化によって作業手順や品質基準を統一し、現場の混乱を防ぐことが重要です。
建設業界における規格標準化の推進は、国土交通省が中心となり積極的に取り組まれています。特に公共工事を中心に、明確な基準の整備やデジタル技術活用の促進を目的とした施策が展開されました。
ここでは、国土交通省が実施している主要な標準化施策を3つのポイントで解説します。
国土交通省は公共建築工事の質と効率を高めるために標準仕様書を定期的に改定し、最新の技術動向や社会情勢を反映させています。この標準仕様書は設計から施工までの各工程で求められる基準や要件を具体的に示すもので、公共工事の品質均一化に大きく貢献しています。
この改定では最新の耐震基準や環境配慮の仕様が盛り込まれ、各発注機関や施工業者はこれを遵守しながら工事を進めることが欠かせません。規制の確実な遵守において、明確な基準があることは現場の混乱や誤解を防ぎ、無駄な手戻りを減らせる効果もあります。こうした整備により公共工事の透明性と信頼性が向上し、業界全体の品質向上につながっています。
参考:国土交通省
i-Constructionは建設現場の生産性革命を目指した国土交通省の施策で、ICT技術を活用した施工方法の普及を推進しています。これに伴ってICT活用のための標準的なガイドラインが整備され、多くの現場で適用されているので注目すべきでしょう。
このガイドラインでは、ドローン測量や3D設計モデルの活用・ICT施工機械の運用基準が示されており、これらを現場で統一的に実践することで作業効率の向上が期待されています。ガイドラインの整備は、技術活用のばらつきをなくして施工品質を一定水準に保つ上で重要です。また、適用にあたっての安全管理や労務管理の指針も含まれているため、現場でのリスク低減にも寄与します。
このように、i-Construction推進のためのガイドラインはデジタル技術を活用した標準的な施工プロセスの基盤整備として、建設DXの加速に不可欠な役割を果たしています。
参考:国土交通省
BIM(Building Information Modeling)とCIM(Construction Information Modeling)は、設計から施工・維持管理までの情報を3Dモデルで一元管理する手法です。国土交通省は令和5年度から公共工事においてBIM/CIMの原則適用を開始し、業界全体での導入を本格的に促進しています。
実際に、大規模な土木・建築工事ではBIM/CIMモデルを用いて関係者間の情報共有を円滑化し、設計変更や施工計画の調整をリアルタイムで行うことが可能です。これにより、手戻りの削減や工期短縮・コスト削減を実現しやすくなります。
BIM/CIMの原則適用は規格やデータフォーマットの統一も伴っており、標準化がさらに進むことで異なる企業間でも円滑な連携が期待されます。こうした政策は建設DXの基盤を形成し、持続可能なインフラ整備の実現に大きな影響を与えました。
参考:国土交通省

建設DXの現場では、具体的にどのような規格標準化が進んでいるのか理解しておくことが重要です。
ここからは、建設業界で特に注目されている3つの具体的な標準化例を紹介し、それぞれの効果と課題を説明します。
BIMやCIMは高度なデジタル技術ですが、業界全体で活用を広げるためにはデータの形式や属性を標準化する必要があります。これにより、異なるソフトウェアや企業間でのデータ連携がスムーズになります。
近年では、IFC(Industry Foundation Classes)と呼ばれる国際標準フォーマットが導入されており、これを活用することで3Dモデルのデータを共通化可能です。標準化されたBIM/CIMデータを利用すれば設計情報の一貫性が保たれ、工事段階での手戻りやミスが減ります。
標準化はデータの長期的な活用や維持管理フェーズにも効果的で、将来的な修繕計画や資産管理においても役立つため、建設プロジェクトのライフサイクル全体を支えています。
建設現場では設計図面や報告書・見積書など多種多様なフォーマットが利用されており、非効率や誤解の原因になっています。そのため、PDF・CAD・Excelなどのデジタルフォーマットの標準化が進められています。
例えばCADデータには各社独自のファイル形式が多く存在しますが、DX推進のためにはDWGやDXFといった共通のフォーマットで保存し、編集や共有をするのが望ましいでしょう。また、報告書やチェックリストはフォーマットを統一することで、内容の比較やデータ解析が容易になります。
こうしたフォーマットの統一は情報の精度を高めるだけでなく、作業時間の削減にもつながって全体の生産性向上を後押しします。
建設プロジェクトは複数の段階に分かれ、それぞれで異なる業務プロセスが存在します。これらのフローが統一されていないと、情報伝達の遅れやミスが起こりやすくなります。したがって、見積り・発注・施工・維持管理といった一連の業務フローを標準化することが重要です。
例えば、見積り作成から契約・資材調達・施工計画・現場管理・検査報告までを一連のデジタルプロセスとして標準化すれば各フェーズでの情報連携が円滑になり、無駄な重複作業を減らせるでしょう。これによりプロジェクト全体の透明性が高まり、品質管理も強化されます。
標準化された業務フローは異なる企業や職種が協力して働く環境を整え、建設業界のDX推進を加速させるカギとなるでしょう。
建設業界でのDX推進を成功させるには、規格標準化のプロセスを段階的に進めていくことが不可欠です。規格標準化は単なる技術的な作業ではなく、業務効率化や情報共有の基盤をつくる重要な施策です。そのため、手順ごとに適切な準備や取り組みを行う必要があります。
ここでは、規格標準化を進めるための具体的な手順を5つの段階に分けて解説します。
まずは現場や業務全体の現状を把握し、どのような課題があるのかを明確にしましょう。標準化は問題を解決するための手段であり、必要性を理解せずに進めると効果が薄れてしまいます。
例えばデータのやり取りでフォーマットの違いによるトラブルや設計と施工間の情報共有の遅延が発生している場合、その原因を具体的に洗い出します。ヒアリングや現場調査を通じて、業務の非効率部分や重複作業の存在、デジタルツールの活用度合いなどを把握しましょう。
こうして現状課題を整理すれば標準化の目的が明確になり、社内外の関係者を巻き込みやすくなります。課題が共有されることで標準化推進の動機付けが強まるため、初期段階での丁寧な調査は重要です。
現状の課題が整理できたら、次に標準化を進める範囲と具体的な目標を設定します。標準化は一度に全てを網羅するのは難しいため、段階的かつ重点的に対象を絞る戦略が有効です。
例えば、設計図面のデジタル化とフォーマット統一を最優先課題とし、次のフェーズで施工管理の業務フローを整備するなど段階的な計画を立てます。目標には「データ共有の時間を20%短縮」「設計ミスの発生率を30%減少」といった具体的な数値を設定しましょう。
明確な目標を掲げることでプロジェクトメンバー全員が方向性を理解しやすくなり、進捗評価も的確に行えます。目標は現場の実情や技術レベルを踏まえて現実的に設定し、達成感を得られる仕組みをつくることが大切です。
標準化の成功は、推進体制の構築に大きく依存します。社内の関係部署や外部パートナーを含めた体制を整え、役割分担や意思決定プロセスを明確にしましょう。
例えば、プロジェクトリーダーを設置し、設計・施工・IT部門から代表者を選出して協議会を形成します。こうした横断的なチームを組むことで、各部門間の意見調整や情報共有がスムーズになるのがポイントです。
また、外部の専門家やコンサルタントの活用も効果的です。規格の技術的な検討や最新動向の情報提供・ツール導入の支援などで推進力を高められます。全体の体制を整えた上で定期的な進捗報告や問題点の共有を行い、透明性の高い運営を心がけましょう。
体制が整ったら、実際に標準フォーマットや通信プロトコルの導入に着手します。これには既存システムの改修や新しいツールの導入が伴うため、現場作業との調整が必要です。
例えば、BIM/CIMモデルのデータ形式をIFC標準に合わせて変換し、社内の設計システムや施工管理ソフトと連携させる取り組みが挙げられます。CADやExcelファイルのフォーマット統一も同時に進めることで、データ共有の混乱を防げます。
システム改修は業務に影響を与えるため段階的に導入し、現場の負担を軽減しながら進めましょう。導入後は操作教育やサポート体制の充実も必要で、利用者が標準化された環境に慣れるまで継続的なフォローが欠かせません。
標準化は導入して終わりではなく、実際に運用しながら効果を評価し、改善を繰り返すプロセスです。実務での課題や新しい技術の登場に対応し、標準規格を適宜更新していく姿勢が求められます。
例えば、データ連携の不具合や業務フロー上のボトルネックが判明したら関係者で問題点を洗い出し、対策を検討します。標準化の効果指標を定期的にチェックし、目標の達成状況を確認することも重要です。
また、業界全体や行政が推進する新たな標準仕様が発表された際には、迅速に社内規格に反映させることが必要です。こうした継続的な改善により規格標準化が建設DXの強力な武器となり、競争力の向上につながっていきます。
建設業界における規格標準化は、単に作業効率を上げるだけでなくDX推進の基盤として欠かせません。
ここでは、実際に規格標準化を積極的に取り入れ、DX推進に成功している企業の具体例を紹介します。各社は先進的な技術を活用しつつ業務プロセスやデータ形式の統一を図ることで、現場の効率化や品質向上を実現しています。
鹿島建設は、BIM/CIMを活用した建設プロジェクトにおいてVR技術を導入し、データの標準化と共有体制の強化を図りました。具体的には、設計から施工までの各段階で生成されるBIM/CIMモデルをVR空間上でリアルタイムに確認できる仕組みを構築しています。
このシステムでは設計担当者や施工管理者が同一のデジタルデータを共有し、3Dモデルを視覚的に検証しながら意思決定が可能です。データのフォーマットを国際規格に準拠させることで、社内外の関係者間での情報交換をスムーズにしました。
こうした取り組みにより設計ミスの早期発見や工事現場での手戻りを減少させ、プロジェクト全体の生産性が向上しています。VRの活用は技術継承や人材育成にも効果を発揮しており、建設業界における規格標準化の重要性を示す好例となっています。
参考:鹿島建設株式会社
清水建設では、SLAM(Simultaneous Localization and Mapping)技術を活用して現場計測の効率化と資料の標準化に取り組みました。SLAMは、ドローンやモバイルロボットを使って現場の3D空間データを自動的に取得し、高精度な地形や構造物の情報をリアルタイムで生成します。
この技術を導入することで複数のフォーマットに分散していた図面や資料の統一が進み、関係者が一元的に情報を管理できる環境が整いました。デジタルデータの活用によって、測量作業の省力化や人為的ミスの軽減が期待できます。
また、SLAM技術による高精度な現場情報は設計変更や施工計画の迅速な対応を可能にし、工期短縮やコスト削減に寄与するのが特徴です。このように、デジタル技術を活用した規格標準化は現場の生産性向上に直結する重要な施策として注目されています。
参考:清水建設株式会社
大成建設は契約や承認業務の電子化を進めるためにAdobe Acrobat Signを導入し、業務フローの標準化に成功しました。紙ベースの書類管理から脱却し、電子署名とクラウド管理を活用することで業務効率が改善されました。
このシステム導入により契約書や申請書類のやり取りがデジタル上で完結し、社内外の承認プロセスが迅速化しました。さらに、電子署名の法的効力が認められているため、安心してペーパーレス化を推進できます。
また、業務フローの統一により各部署間の情報伝達がスムーズになり、ミスや遅延のリスクが軽減されました。建設プロジェクト全体の進捗管理が効率化し、コスト削減にもつながっています。こうした取り組みは規格標準化とDX推進の好循環を生み出している例として評価されています。
参考:大成建設株式会社

建設業界におけるDX推進には、規格標準化が欠かせません。業務プロセスやデータ形式を統一することで情報共有や業務効率が向上し、競争力の強化につながります。
今回紹介した企業の事例では、VRやSLAM技術の活用・電子署名システムの導入など多様なアプローチで規格標準化を実現して現場の課題解決や生産性向上に貢献しています。
これらの取り組みは単なる技術導入にとどまらず、組織の運用や管理体制の整備と連動しているので注目しておきましょう。建設DXを加速させるには規格標準化の必要性を理解し、自社の課題や目標に応じた具体的な施策を検討することが重要です。
規格標準化を進めることで、建設プロジェクトの品質向上やコスト削減・新技術のスムーズな導入が可能になります。まずは本記事で紹介した先進事例を参考にしながら、規格標準化を検討してみてはいかがでしょうか。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
