建設DXでペーパーレス化は可能?メリットや成功のステップを解説
建設

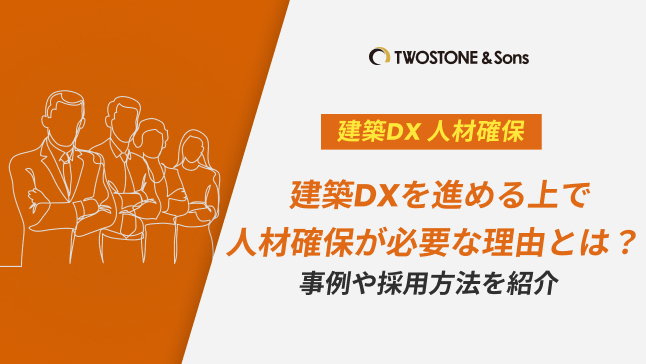
建築業界でDX(デジタル・トランスフォーメーション)推進が叫ばれる中、「人材が足りずになかなか進まない」と悩んでいませんか?実は、建築DXにおける人材確保は、単なる課題解決以上の価値をもたらします。
適切な人材確保により、業務効率化による働きやすい環境づくり、技術継承の仕組み化、安全性向上が実現し、若手人材にとって魅力的な職場を創出できるでしょう。
本記事では、建築DXに人材確保が必要な理由、人材確保がもたらすメリット、成功事例、具体的な採用・育成方法まで詳しく解説します。自社に最適な人材戦略を策定し、持続的な成長基盤を構築できるようになるでしょう。

建築業界では、DXの推進が企業の競争力を高めるための重要な経営課題となっています。一方で、推進を成功させるためには、戦略的な人材の確保が欠かせません。
令和4年の総務省の調査では、67.6%の企業がDX推進の障壁として『人材不足』を挙げています。この結果からも、人材の確保が成否を左右する重要なテーマであることが分かります。
以下より、建築業界で人材確保が重視される背景と要因を詳しく見ていきましょう。
参考:総務省|令和4年版 情報通信白書|デジタル・トランスフォーメーション(DX)
建築DXには、従来の建築知識に加えてデジタル技術への深い理解が求められます。BIM/CIMソフトウェアの操作、IoTセンサーの設置・管理、AIを活用したデータ分析、クラウドシステムの運用管理などの専門スキルが必要です。
しかし、現実的には必要な専門スキルを扱える人材が圧倒的に不足しています。建設業界の多くの企業では、既存社員がデジタル技術に習熟しておらず、新しいシステムを導入しても十分に活用できない状況です。
特に中小企業では、専門スキルを持った人材の確保が困難であり、DX推進を阻害する大きな要因となっています。人材育成にかかる時間とコストの負担も重く、外部からの専門人材の採用においても、大手企業との競争に苦戦しているのが現状です。
新しいデジタル技術の導入には、現場作業員への丁寧な教育と継続的なサポートが必要不可欠です。従来の紙や電話を使った業務に慣れ親しんだ現場では、デジタルツールへの移行に抵抗感を示すケースも少なくありません。
特に年配の作業員や、長年同じ作業手順で働いてきた職人にとって、新しい技術の習得は大きな負担となります。建築DX推進には、技術的な理解だけでなく、変化に対する意識改革も重要です。
現場の声を聞きながら、段階的にツールの改善や運用方法の見直しを行い、全社員がデジタル技術を受け入れられる環境作りが求められます。教育体制の構築と人材育成への投資が、DX推進の鍵を握っています。
建築業界では、設計から施工、維持管理まで複雑な業務プロセスが存在します。しかし、従来のアナログ手法では、プロジェクトの規模拡大や多様化する顧客ニーズに対応することが困難になってきています。
対応するには、3次元モデルを活用したBIM/CIMやドローンによる測量・点検作業など、新技術の活用には専門知識を持つ人材が不可欠です。
IoTやAIを活用したデータ分析により、従来では不可能だった予防保全や最適化も実現できますが、デジタル技術を理解し活用できる人材なしには効果を発揮できません。
業務プロセス全体の変革を実現するために、デジタル人材の確保は避けて通れない課題となっています。
建築業界ではDXを進めることで、人材の確保に良い効果が期待できます。業務の効率化や働き方の柔軟性が進むことで、若手や多様な人材が定着しやすくなるためです。デジタル技術の活用により、従来の建設業界のイメージを一新し、現代的で魅力的な職場環境を構築できます。
実際にDXに取り組む企業では、採用力や社員の満足度が高まる傾向が見られます。以下より、労働環境の改善から新しいキャリア形成の機会まで、建築DXを進めて人材を確保する5つのメリットを見ていきましょう。
建築DXの推進により、従来手作業で行っていた図面作成や資材管理などの業務が自動化され、作業時間の大幅な短縮が実現可能です。
RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)の活用をすれば、日報作成や資材発注などの単純作業が自動処理され、入力ミスや転記ミスの防止にもつながります。
また、クラウドサービスを活用することで、どこからでも同じ情報にアクセスできるようになり、現場とオフィス間での情報共有が円滑になります。残業時間の削減が実現し、働き方改革にも大きく貢献するでしょう。
労働環境が改善されることで、若手人材にとって魅力的な職場となり、優秀な人材の確保につながる好循環が生まれるでしょう。
建築業界では熟練技術者の高齢化が進み、貴重な技術やノウハウの継承が課題となっています。しかし、DXを進めることで、ベテラン技術者の経験や判断基準をデジタル化し、AIシステムに蓄積することが可能です。従来は口伝や実地指導に頼っていた技術伝承が、データベース化により体系的に管理できるようになります。
BIM/CIMモデルに属性情報を付与することで、設計や施工における判断根拠を明確化し、若手技術者でも高品質な成果物を作成可能です。
VR(バーチャルリアリティ)技術を活用した教育システムでは、危険な作業や複雑な工程を安全に学習できるようになります。DXによる技術継承の仕組み構築で、人材育成の効率化と品質向上が同時に実現できるでしょう。
デジタルネイティブ世代の若手人材にとって、最新技術を活用できる職場環境は大きな魅力です。建築DXの推進により、3次元CADやドローン操作、AIを活用したデータ分析など、先進的なスキルを身につける機会を提供可能です。これらの技術経験は、若手にとって将来のキャリア形成においても貴重な資産となります。
また、テレワークや遠隔監視システムの導入により、柔軟な働き方が実現し、ワークライフバランスの向上にもつながるでしょう。IoTセンサーやウェアラブルデバイスの活用により、作業員の安全管理が強化され、安心して働ける環境が整います。
DXでの現代的な職場環境の整備により、優秀な若手人材の獲得と定着率向上が期待できるでしょう。
建築現場では常に安全リスクが伴いますが、DXの推進により安全性の向上ができます。IoTセンサーを活用した作業員の位置情報の管理や心拍数モニタリングにより、危険な状況を早期に検知し、事故を未然に防ぐことが可能です。
ドローンを使用した高所点検により、作業員が危険な場所に立ち入る必要がなくなり、墜落事故のリスクを大幅に削減できます。AIを活用した画像解析では、重機との接触事故や不安全行動を自動検知し、即座に警告を発することも可能です。VRシミュレーションでは、実際の危険にさらされることなく安全教育を実施できます。
DX推進での安全対策の充実により、作業員の安心感が向上し、結果として離職率の低減と人材の定着につながるでしょう。
建築DXにより業務効率が向上すると、従業員はより創造的で価値の高い業務に集中できます。単純作業から解放された従業員は、設計の最適化や新技術の研究開発など、より専門性の高い分野にチャレンジすることが可能です。
また、デジタル技術に精通した人材は、社内での昇進機会が増えるだけでなく、業界全体での市場価値も高まります。BIM/CIMマネージャーやDX推進担当者など、新しい職種や役職の創設により、キャリアパスが多様化できます。
DX推進による成長機会の拡大により、モチベーションの高い人材の確保と育成が可能になり、組織全体の競争力向上につながるでしょう。

建築DXにより建築業界が抱えるさまざまな課題を解決し、同時に人材確保につなげるためには、適切なデジタル技術の選択と活用が重要です。
現在、建築現場で注目されているDXを推進する技術には、BIM/CIM、AI・IoT、ドローン、クラウドサービスなどがあります。それぞれの技術がどのように課題解決と人材確保に貢献するのか、具体的に見ていきましょう。
BIM/CIMは、建築・土木分野の設計・施工・維持管理を一貫してデジタル化できる3次元モデル技術です。従来の2次元図面では把握が難しかった構造や情報も、関係者全員が直感的に理解しやすくなります。
設計段階では干渉チェックや数量算出を自動化できるため、設計ミスや手戻りを大幅に削減できます。施工段階では4次元(時間軸)を加えた工程管理により、作業の効率化や工期短縮が可能です。
このように、BIM/CIMによって現場の負担が軽減され、限られた人材でも無理なく対応できる環境が整います。BIM/CIMに対応できる専門スキルを持った人材のニーズが高まっており、採用や育成を通じて組織の競争力強化にもつながるでしょう。
AIとIoTを組み合わせることで、建築現場の管理業務は飛躍的に進化しています。IoTセンサーが収集した大量の現場データをAIが分析し、判断の精度を高める仕組みが実現しつつあります。
例えば、コンクリートの養生状況をリアルタイムで把握し、適切なタイミングで工程を進めることで、品質の安定と工期短縮の両立が可能です。また、AIが作業員の動きや現場の傾向を学習することで、安全リスクの予測や事故防止の対策も自動化されます。
現場管理の高度化によって、業務の効率と安全性が向上し、過度な負担も軽減されます。結果、働きやすい職場環境が整い、人材の定着や新たな採用にも良い影響を与えるでしょう。
ドローン技術の導入により、測量や点検といった建設現場の作業が大きく変化しています。
高精度カメラや3Dスキャナーを搭載したドローンを活用することで、従来は人手と時間が必要だった工程も短時間で正確に実施できるようになりました。
例えば、従来数日を要していた測量業務が数時間で完了し、必要な人員を大幅に削減できます。また、高所や危険箇所の点検作業もドローンで代替することで、作業員の安全性を飛躍的に向上させることが可能です。
ドローン技術を導入すれば、効率化と安全性が向上し、現場の負担が軽減、作業環境も改善されるでしょう。結果として、肉体的・精神的な負担の少ない働き方が可能になり、人材の定着率向上や新たな人材確保にもつながっていきます。
クラウドサービスを導入することで、建築プロジェクトに関わる全ての関係者が円滑に連携できるようになります。情報がクラウド上で一元管理されているため、現場でもオフィスでも常に最新の情報にアクセス可能です。
従来の方法で発生していた伝達ミスや情報の遅延が大幅に改善され、プロジェクト全体の効率化につながります。あわせて、リモートワークの導入や現場間の移動削減といった柔軟な働き方の実現も可能です。
クラウドサービスの導入による働き方改革は従業員の負担を軽くし、ワークライフバランスの向上を図れるでしょう。結果、職場への定着率が高まり、求職者からも選ばれやすい環境づくりが進みます。
建築業界における人材不足の解決には、DX推進を通じた魅力的な職場環境の構築が重要です。先進的な取り組みを行う企業では、デジタル人材育成プログラムの充実などにより、優秀な人材の確保と定着を実現しています。
以下より、建設会社3社の具体的な取り組み事例を通じて、どのような方法で人材確保の課題を解決しているかを詳しく見ていきます。成功事例から、自社の人材確保に活かせるヒントを探っていきましょう。
清水建設株式会社は、2024年4月に『シミズ・デジタル・アカデミー』を開講しました。従業員のデジタルリテラシー向上とDX人材の育成に力を入れています。
プログラムでは、経済産業省の『DXリテラシー標準』に準拠したアセスメントとeラーニングを実施しています。特徴的なのは、結果に応じた最適な学習内容を個別に提案する仕組みです。
さらに、イノベーションと人材育成の拠点『温故創新の森NOVARE(ノヴァーレ)』内に『NOVARE DLZ(Digital Learning Zone)』を開設しました。XR(エクステンデッドリアリティ)やVR(バーチャルリアリティ)を活用した実践的な研修を行っています。
参考:デジタル人財育成プログラム「シミズ・デジタル・アカデミー」を開講 | 企業情報 | 清水建設
株式会社竹中工務店では、役員を含む全従業員約8,000人を対象に、エクサウィザーズの「exaBase DX アセスメント&ラーニング」を導入しました。この取り組みは大手建設業での全社導入として初の事例となり、業界最大規模の導入実績を誇ります。
同社では建設デジタルプラットフォームを核としたデジタル変革を推進しており、その取り組みを加速させるために全社員のデジタルリテラシー向上が不可欠と判断しました。
eラーニングでは、業務のデジタル化推進に必要な基本的コンテンツを必須コースとして設定し、その他のコンテンツも積極的に受講を推奨しています。デジタル室所属の約100人に対しては、より詳細なDXアセスメントを実施し、DX推進スキルレベルの可視化を図っています。
参考:「建設デジタルプラットフォーム」の構築によるデジタル変革の取組み|プレスリリース2021|情報一覧|株式会社 竹中工務店
株式会社大林組では、2022年2月にDX本部を設置し、「地に足のついたDX」を推進しています。同社の特徴は、BIM教育を中核とした人材育成です。出向・派遣社員を含む全従業員だけでなく、サプライチェーン全体を教育対象としている点が注目されます。
デジタル教育プログラムでは、世代や役割に応じたカスタマイズされた内容を提供し、各人の業務に紐付いたオリジナルプログラムを実施しています。マインドセット変革のためのオリジナルアニメーションを制作し、5分以下の短い動画で学習しやすい環境を整備しているそうです。
また、Di-Liteを導入するにあたり、3年間でITパスポート試験の新規合格者500人という具体的な目標を設定し、データ活用度の高い企画管理部門から段階的に展開しています。
参考:【事例紹介】大林組が進める「地に足のついたDX」、Di-Liteでデジタル教育に力を入れる理由とは | Di-Lite啓発プロジェクトサイト【公式】|デジタルリテラシー協議会
建築業界でDXを成功させるには、適切な人材確保が最重要課題です。しかし、DX人材の需要は急増している一方で、供給が追いついておらず、多くの企業が人材確保に苦戦しています。
DX人材の確保方法には主に3つのアプローチがあります。それぞれにメリットとデメリットがあるため、自社の状況や目的に応じて最適な方法を選択することが重要です。各手法の特徴を詳しく見ていきましょう。
外部委託(アウトソーシング)は、DXに必要な専門業務を外部の専門業者に委託する方法です。システム構築やBIM/CIMモデリング、データ分析などの高度な技術が必要な業務を、その分野に特化した企業に任せることができます。
最大のメリットは、すぐに専門性の高い業務を開始できることです。また、社内での人材育成にかかる時間やコストを削減でき、最新の技術やノウハウを手軽に活用できます。
一方でデメリットとして、ナレッジが社内に蓄積されにくく、外部業者への依存度が高まるリスクがあります。選定時は技術力だけでなく、建設業界への理解度も重視すべきです。
中途採用は、他社でDX経験を積んだ即戦力人材を獲得する方法です。建築業界での経験とデジタル技術の知識を併せ持つ人材なら、すぐに現場で活躍が期待できます。
即戦力として活躍できることが最大のメリットですが、人材獲得競争は激しく、採用コストや給与条件での負担が大きくなるでしょう。
特に建築DXに精通した人材は希少価値が高く、転職市場での競争も厳しくなっています。採用にあたっては技術力だけでなく、自社の企業文化や業界への適応力も重視する必要があります。
既存社員の育成は、現在在籍している社員にDXスキルを身につけてもらう方法です。建設業界の知識を持つ社員がデジタル技術を学ぶことで、現場のニーズを理解した実践的なDX推進が可能になります。
自社の内情に精通した人材が中心となることで、現場に即したDX推進が実現可能です。
また、中長期的には投資対効果が高く、組織全体のデジタルリテラシー向上にもつながります。
初期投資や育成期間は必要ですが、継続的なスキル蓄積により自社独自の競争力を構築できるのが大きな魅力です。

建築DX推進における人材確保は、企業成長への戦略的投資です。専門スキル不足や現場教育の課題に対し、外部委託、中途採用、既存社員育成を組み合わせることが成功の鍵となります。
清水建設や竹中工務店の事例が示すように、体系的な人材育成により業務効率化と働きやすい環境を実現可能です。BIM/CIMやAI・IoT技術活用は技術継承と安全性向上をもたらし、若手人材にとって魅力的な職場を創出します。
建築DXは人材確保と企業成長を両立する戦略です。本記事を参考に最適なDX戦略を策定し、持続可能な人材確保体制を構築しましょう。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
