建設DXでペーパーレス化は可能?メリットや成功のステップを解説
建設

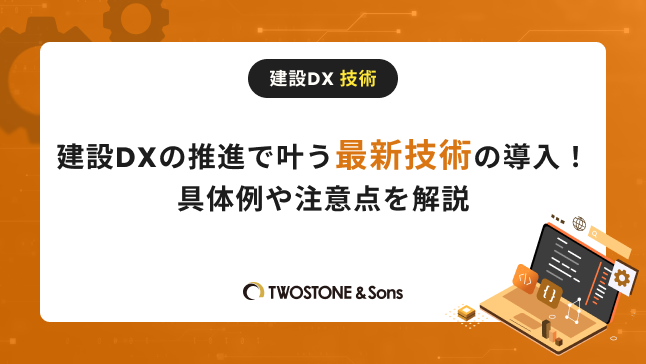
人手不足や高齢化が進む建設業界では、現場の負担が増す中で技術の継承や効率化が大きな課題となっています。多くの現場で「もっと効率よく仕事を進めたい」「属人的な作業から脱却したい」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
そのような中、注目されているのが建設DX(デジタル・トランスフォーメーション)の推進です。これは、建設業界におけるICTやAI、クラウド技術などを活用することで、作業効率や安全性、品質管理の精度を向上させる取り組みです。
この記事では、建設DXの必要性を技術面の課題から紐解きながら、最新技術の具体例と導入時に注意すべきポイントを解説します。実践的なヒントを得たい方は、ぜひ最後までご覧ください。

建設現場ではいまだに紙の図面や手作業での工程管理が日常的に使われており、業務全体の進行や生産性に支障が出ています。特に、工程ごとの情報共有の遅れや現場とオフィス間のデータの非連携は、作業ミスや工程の無駄を生む一因となりかねません。
また、ITツールの導入が進みにくい背景には、現場ごとに異なる作業環境や導入後の運用体制に対する不安が根強いことも挙げられます。こうした要因が、他産業と比較して技術革新の進度を鈍らせている構造的な問題といえます。
建設業界では長年現場を支えてきた熟練技術者の高齢化が進み、退職による人材流出が加速しています。その一方で若年層の入職者は減少傾向にあり、技術やノウハウの継承が難しくなっているのが現状です。
技術者の知見が属人化しやすく、現場ごとの判断や対応が個人の経験に依存している状況では、品質のばらつきやミスの発生リスクが高まります。また、ベテランが抜けた穴を埋めるために少ない人数で複数の工程を担うケースも増え、現場の負担はさらに増しています。
こうした状況を打破する手段として、ICTを活用した情報共有やデータ蓄積、施工フローの標準化を進めることが重要です。
建設現場では、クラウドベースの管理ツールやドローン、3D測量といった最新のICT技術が導入され始めていますが、まだまだ十分に活用されているとはいえません。その背景には、業界全体でのIT人材不足や、従来の作業フローから脱却できないという意識の壁があります。
新しい技術を導入するには、現場との連携だけでなく社内全体での理解と教育体制の整備が必要です。特に、複数の現場を同時に管理する場合や外注先とのやり取りが発生する場合には、クラウドツールによる一元管理が効果を発揮します。
ツールの導入によって進捗管理や工程の可視化が可能になるため、関係者全体での情報共有がスムーズになるでしょう。結果として、納期遵守やコスト削減、安全対策の徹底にもつながります。
多くの建設会社では、10年以上前に導入した機器やソフトウェアをいまだに使い続けているケースがあります。こうした老朽化した設備はトラブル発生時の対応が難しく、生産性低下の要因です。
また、古いシステムでは現代のソフトウェアと互換性がない場合が多く、新しい業務アプリや管理ツールと連携できないことがあります。結果として、現場と事務所とのデータ連携が断絶され、無駄な手作業が増えかねません。
そこで最新のデジタルプラットフォームを活用すると、こうした設備のギャップを解消できるでしょう。業務フロー全体を見直し、必要なデータを一元的に管理すると、設備の更新を最小限に抑えながら効率的な運用ができます。
建設DXとは、単にシステムやツールを導入するだけでなく、業務の在り方や意思決定のプロセスそのものを見直し、デジタル基盤と実務を融合させる取り組みです。DXを起点として業務フローが再構築されることで、従来の属人的な作業や勘に頼った判断から脱却し、最新技術の導入に対する障壁を下げる効果が期待できます。
これにより、ツール単体では発揮できない効果が全体最適の視点で実現され、長期的な業務改善にもつながっていきます。
第一に、建設DXの推進によって整備されるのがデジタル基盤です。紙の図面や口頭での伝達に依存していた情報のやり取りが、クラウドやアプリを活用することで即時共有できるようになるのがデジタル基盤整備の効果です。
デジタル基盤が整うことで、ドローンによる空撮や3Dスキャンデータを現場でリアルタイムに確認する体制が整います。また、IoT機器で収集した作業データもクラウド上で一元管理できるため、分析やフィードバックにかかる時間を短縮できるでしょう。
このように、土台となるデジタル環境を整備することで、新しい技術の導入・運用がスムーズになります。
DXの本質は、既存の業務をデジタル技術で補完するだけではなく、業務プロセスそのものを再構築する点にあります。従来の慣習や非効率な手順を見直すことで、技術導入のスペースが生まれます。
例えば、紙の工程表を毎日更新していた作業をプロジェクト管理ツールでの進捗共有に変えるだけでも、時間削減とミスの回避につながるでしょう。その分のリソースを新技術の習得や現場への試験導入に振り分けられるようになります。
現場ごとにバラバラだった作業フローを標準化することで、技術導入の影響範囲を明確にして段階的かつ計画的に進めることが可能になります。この再構築こそが、建設現場における技術進化を支える土台です。
新しい技術を導入する際、障壁となるのが現場の抵抗感です。特に、長年の経験に基づいたやり方に誇りを持つ職人が多い建設業界では、新しいものを拒む傾向も見られます。
そこで重要なのが、DX推進にあたって企業文化を変革することです。経営層が率先してデジタル技術の意義を共有し、現場スタッフが主体的に学び、実践できる風土を作る必要があります。
そこで継続的な研修やサポート体制を整えると、現場が安心して技術に触れられるようになるでしょう。技術導入の成功は企業文化の変革と深く結びついており、DXによる土壌づくりがその第一歩となります。
以下の建設DXの取り組みによって現場へ最新技術を導入する環境が整うことで、さまざまな利点が生まれます。
これらの複合的な効果が、事業継続性の向上につながる重要な要素となります。ここでは、この5つのメリットについて詳しく見ていきましょう。
最新技術を導入するメリットの1つは、施工の精度の向上です。例えば、ドローンを活用した測量や3Dモデルによる設計の可視化によって、誤差の少ない施工計画を立てることが可能になります。
また、BIM(Building Information Modeling)を活用することで、設計から施工、管理までの全工程を一貫してシミュレーションできます。BIM活用により、資材の過不足や設計ミスによる手戻りを事前に防げるでしょう。
その結果、品質が安定し、信頼性も向上することで、発注者や利用者からの評価も高まります。
クラウドベースの施工管理ツールやAIを活用した工程分析によって、日々の業務効率が劇的に向上します。例えば、帳票の自動作成や資材の在庫管理をデジタルで行えば、現場担当者の負担を軽減できるでしょう。
さらに現場と本社との情報連携もリアルタイムで可能になり、電話やFAXでのやり取りにかかっていた時間が削減されます。人為的なミスの減少にもつながるため、全体の生産性が底上げされるでしょう。
生産性向上は、労働時間の短縮やコスト削減にも直結し、働き方改革の実現にもつながります。
建設現場では、わずかな油断が重大な事故につながるリスクをはらんでいます。ここで活用されているのが、AIカメラやウェアラブルデバイスなどの安全管理技術
です。
AIによる映像解析により危険行動や異常を即時に検出してアラートを発信するシステムは、作業員の注意喚起に役立ちます。また、心拍や動作をモニタリングするウェアラブル機器を装着すれば体調異変を早期に把握でき、熱中症などの予防にも有効です。
安全性を数値化して管理できるようになることで従来の感覚的な管理から脱却でき、事故の発生率を下げることが可能です。
熟練者の減少が課題となる中で、DXの推進は技術継承の手段としても有効です。現場での作業手順や判断基準を動画やマニュアルとして記録することで、若手や未経験者が実践的な知識を吸収しやすくなります。
さらにAR(拡張現実)やVR(仮想現実)を使ったトレーニングは、現場に近い環境での疑似体験を可能にし、短期間でのスキルアップをサポートします。
人材の確保が困難な時代において、こうしたデジタル技術の活用は持続可能な人材育成体制を築く上で欠かせません。
建設業界では、資材の過剰使用や産業廃棄物の増加が課題となっています。ここに最新技術を導入することで、環境負荷の軽減にも貢献できるでしょう。
例えば、BIMを活用した正確な資材発注により無駄な在庫を減らせます。さらに、建機に取り付けたセンサーで燃料消費量を監視すればCO2排出量の削減にもつながります。
施工の最適化によって作業時間が短縮され、エネルギーの使用効率も高まるため、環境配慮が求められる今の時代、持続可能な建設の実現に向けて技術導入は重要なカギとなります。

最新技術を導入した企業の事例を見ると、建設DXが現場の生産性と品質の向上に直結している様子がうかがえます。実際に、MR技術を活用した施工管理アプリを独自開発した企業や、教育やマニュアル整備にVRを導入してベテランのノウハウを若手に伝承する体制を構築した企業が出てきました。
このような先進的な取り組みは、技術導入の成功事例として参考になります。業界全体での共有と実践が今後のカギを握ります。
建設の設計段階で不可欠となっているのがBIM(Building Information Modeling)です。その代表的なツールであるAutodesk Revitは、3D設計と構造、設備、施工情報を一元的に管理できます。
従来の2D図面では難しかった干渉チェックや資材数量の自動算出が可能になるため、設計ミスの早期発見と手戻りの防止に効果を発揮します。また、プロジェクト全体の見える化が進むことで、関係者間の意思疎通がスムーズになるでしょう。
さらに、Revitを導入することで設計と施工が連動し、現場の作業精度が向上します。工程全体の効率化と品質確保の両立を実現する上で、BIMは重要な基盤となります。
出典参照:Autodesk Revit|オートデスク株式会社
測量作業の効率化と精度向上を両立するツールとして注目されているのが、FLIGHTS SCAN HANDYです。これはレーザースキャナーを活用したハンディ型3D点群測量機器で、現場の状況を短時間で高精度にスキャンできます。
従来のトータルステーションやGPS測量に比べて地形や構造物の細部までデータとして取得できるため、設計や施工前の判断材料として有効です。3DデータはそのままBIMやCADソフトに取り込めるため、デジタルワークフローの構築に役立ちます。
屋内外問わず使用可能で、狭い場所や複雑な構造の現場でも活用しやすいのが特徴です。これにより、測量の手間を削減しながら精度の高い現場管理が可能になります。
出典参照:FLIGHTS SCAN HANDY|株式会社FLIGHTS
ドローンによる現場の記録と測量は、すでに多くの建設現場で活用されています。中でもDJI Phantom 4 RTKは高精度な位置情報を取得できるRTK(リアルタイムキネマティック)技術を搭載しており、数センチ単位での正確な空撮データを取得可能です。
このドローンを使えば広範囲の現場全体を上空から把握でき、工事の進捗や安全状況を短時間で確認できます。さらに定点観測による記録を残すことで、発注者との進捗共有やトラブル時の検証資料としても活用できます。
高所作業の回避にもつながるため、安全性の向上とコスト削減の両面で効果があるといえるでしょう。現場の状況を第三者にも説明しやすくなるため、透明性のあるプロジェクト運営が可能になります。
出典参照:Phantom 4 RTK|DJI JAPAN 株式会社
重機のメンテナンスと管理を効率化するためのツールとして注目されているのが、ConSite Oilです。これは建機の作動油の状態をリアルタイムで監視し、異常検知や劣化予測を行う機能を備えたシステムです。
通常、重機のトラブルは突然発生しがちですが、作動油のデータを継続的に取得することで部品の摩耗や劣化傾向を事前に把握できます。異常が予測されると自動でアラートが送信され、早期対応が可能になります。
これにより計画的なメンテナンスが実現し、突発的なダウンタイムや修理コストの削減が可能です。重機の安定稼働は工期の安定にもつながり、現場全体の信頼性が高まります。
出典参照:ConSite OIL|日立建機株式会社
AR(拡張現実)技術を活用し、現場と設計を重ねて表示できるのがTrimble SiteVisionです。このツールを使うことで、タブレットやスマートフォンを通じて実際の地形に対して設計情報を視覚的に重ねられます。
これにより図面だけでは把握しきれなかった施工位置や構造の高さを現地で確認でき、施工ミスや手戻りのリスクを減らせます。特に複雑な構造物や地下設備など、目に見えない要素が多い現場での活用が効果的です。
現場のスタッフにとっても、視覚的に分かりやすい情報提供が行えるため理解度が高まり、意思決定が迅速になります。設計と施工のギャップを最小限に抑えるために、有力なツールです。
出典参照:Trimble SiteVision|株式会社ニコン・トリンブル
現場管理の効率化において、多くの企業で導入が進んでいるのがANDPADです。クラウドベースで動作するこのツールは、主に以下の4つの情報を一括管理できます。
これまで紙やExcelで個別に管理していた情報を集約し、どこからでもリアルタイムで確認できるようになります。複数の現場を持つ企業にとっては、情報の統一と属人化の排除につながるでしょう。
また、現場とのコミュニケーションもアプリ上で完結できるため、電話やメールのやり取りにかかる時間を削減できます。結果として、現場と本社、発注者との連携が強化され、スムーズな施工管理が実現します。
出典参照:ANDPAD|株式会社アンドパッド
建設DXを推進する中で最新技術を導入した企業では、単なる機器の導入にとどまらず、現場への定着を重視した取り組みが行われています。ICT建機やクラウド連携システム、AR支援などの先端技術も、実務と結びつかなければ十分な効果を発揮できません。
また、実際の作業現場で得られたフィードバックを基にシステムの改善を継続することで、技術と現場のギャップを埋め、運用の安定化と成果の最大化を目指しています。このように、建設DXの推進を軸とした企業の先進的な取り組みは、他の現場にも参考になる実例といえるでしょう。
清水建設株式会社は、BIMを全面的に活用した施工プロジェクトを通じて設計と施工管理の一元化を実現しました。3Dモデルを用いて設計情報をデータ化することで施工前に干渉チェックを行い、設計ミスによる手戻りを回避しています。
この取り組みでは、現場の作業員もBIMモデルを活用して施工手順や仕上がりを確認しながら作業を進められる体制が整えられました。その結果、施工の精度が向上し、全体の工期短縮にもつながっています。
また、発注者との合意形成もスムーズになり、事前の説明や変更対応が効率的に行えるようになりました。BIMを通じて関係者全体の情報共有が進み、プロジェクト全体の統制力が高まった事例です。
出典参照:BIMをベースにした生産体制を構築へ|清水建設株式会社
株式会社大林組では、MR(複合現実)を使った施工支援に取り組んでいます。MRとは現実空間に3Dデータを重ね合わせて表示する技術で、施工前の確認や手順の共有に活用されています。
この事例では、現場において設計図面をそのまま可視化し、作業員が現実の構造物と設計とのズレをその場で確認できる仕組みを構築しました。これにより、施工ミスの早期発見と手戻りの防止が可能になりました。
特に、新人作業員や協力会社との情報共有において効果を発揮しています。言葉や紙の図面だけでは伝わりにくい施工意図も、MRを使えば一目で理解できます。現場教育やマニュアルの代替としても優れた成果を上げていることが評価すべき点です。
出典参照:建設現場における作業手順をMR(複合現実)で可視化し、工程管理での有効性を実証|株式会社大林組
進捗管理において効果的な技術の1つがドローンです。鹿島建設株式会社では、ドローンを用いて工事現場を定期的に空撮し、進捗や出来形の確認を行っています。
この手法によって全体の施工状況を俯瞰的に把握することが可能になり、工程管理や品質管理の精度が高まりました。特に大規模な土工事やインフラ工事では、地上からでは見えない部分も把握でき、全体最適の判断がしやすくなりました。
また、空撮データは定点で取得され、過去との比較も容易です。これによって報告資料の作成も効率化され、関係者とのコミュニケーションも迅速になっています。定期的な進捗チェックによって、トラブルの早期発見と対策が実現できるようになりました。
出典参照:ドローンを用いた写真測量の精度向上、大規模造成工事に初適用|鹿島建設株式会社
もう1つ注目すべき事例は、IoTを活用した現場の遠隔監視です。竹中工務店では現場に各種センサーを設置し、騒音・振動・温湿度などの環境情報をリアルタイムで本社に送信するシステムを構築しました。
この仕組みにより、現場の状況を遠隔で把握し、異常があればすぐに対応できる体制が整えられています。特に都市部や病院・学校などの施設周辺での工事では近隣への配慮が求められるため、これらのデータは貴重です。
また、施工中の重機の稼働状況や作業員の動線もモニタリングでき、安全対策や効率化のための分析にも活用されています。IoTを活用した現場管理は、今後の標準となる可能性を秘めています。
出典参照:IoT技術を活用した工事用機械におけるクラウド型遠隔監視システムの運用を開始|竹中工務店
建設DXを推進し最新技術を導入する際には多くの利点が期待されますが、現場に定着させるためには慎重な準備と段階的な導入が欠かせません。ツールやシステムそのものの性能だけでなく、導入に関わる人材の理解度や運用体制の整備が重要なカギを握ります。
また、導入直後にすぐ成果を求めすぎると現場の負担が増し、かえって非効率になる可能性も否定できません。
ここでは、建設現場において技術を効果的に活かし、日常業務に自然と根付かせるための基本的な考え方と実践的な工夫を紹介します。
技術導入の第一歩として、導入目的をはっきりさせることが欠かせません。漠然と新しい機器やシステムを導入しても、現場のニーズに合わず効果が薄れてしまいます。
具体的には、以下のような目的です。
目的が明確であれば必要な機能や性能を備えた技術を選定でき、無駄なコストや手間を減らせます。
また、目的を共有することで現場スタッフの理解も得やすくなり、導入後の協力体制が強化されるでしょう。計画段階で関係者全体が共通認識を持つことが、成功のカギを握ります。
最新技術の導入に失敗しやすい原因の1つが、現場の実情と導入システムの乖離です。設計部門や経営層の意向だけで決めると、実際に使う作業員や現場管理者の声が反映されずに不便なシステムになる場合があります。
導入にあたっては、現場の作業フローや負担、ITリテラシーのレベルを十分に把握し、現場担当者の意見を取り入れることが重要です。そうすることで、使いやすく、現場業務にマッチしたツール選びやカスタマイズが可能になります。
また、段階的に導入し小規模の現場や一部の工程で試験運用を行うことで、問題点や改善点を早期に発見できます。現場の声を反映した柔軟な対応が、導入成功の近道となるでしょう。
最新技術の導入には、初期費用だけでなくランニングコストも発生します。例えば、機器の保守費用やソフトウェアのライセンス料、アップデート費用などがその一例です。
導入前にコストを詳細に見積もり、長期的な収支計画を立てることが重要です。コスト面で無理があると、途中で運用を断念したりメンテナンスが疎かになったりして、せっかくの投資が無駄になる恐れがあります。
また、トータルコストだけでなくROI(投資対効果)をしっかりと評価し、導入後にどの程度の効果が見込めるかを具体的にイメージできるようにしましょう。費用対効果のバランスを考慮した計画が、持続可能な運用につながります。
新技術を導入しても、使いこなせなければ効果は発揮されません。特にIT機器やシステムの場合、操作方法や設定の理解が不十分なままだと誤操作やトラブルの原因になります。
導入後は、操作マニュアルやFAQの整備に加えて現場スタッフ向けの説明会や研修を定期的に開催することが効果的です。対面やオンラインでの質疑応答の場を設けることで、現場の疑問や不安を解消しやすくなります。
また、担当者が自信を持って使いこなせる環境を作ることが現場での活用度を高め、技術導入の成功につながります。継続的なフォローアップも視野に入れて体制を整えましょう。
建設業界では世代間でITリテラシーに差があるのが現状です。若手はスマートフォンやPCに慣れている一方、高齢の技術者は苦手意識を持つケースも少なくありません。
このギャップを放置すると、新技術の導入が現場の混乱を招く可能性があります。したがって、ITリテラシーの向上に向けた取り組みも同時に進める必要があります。
具体的には、段階的な教育プログラムの導入や分かりやすい操作ガイドの作成が効果的です。操作の簡略化や自動化機能を持つツールを選ぶことも重要です。
こうした配慮があることで、全従業員が安心して技術を活用できる環境を整備できます。結果として、現場全体のDX推進のスピードと効果が高まります。

建設DXは、業界が抱える熟練技術者の減少や業務の非効率、設備の老朽化といった課題に対して有効な解決策です。デジタル基盤の整備や業務プロセスの見直し、企業文化の変革によって最新技術の導入が現場の力となります。
施工精度の向上や生産性の強化、安全管理の充実、技術継承の促進、環境負荷の軽減といったメリットが期待できることから、DXは単なるIT導入ではなく、建設業の未来を支える重要な柱です。
この記事を参考に、自社の課題や目標に応じた建設DXの推進を検討し、現場に最新技術を取り入れる第一歩を踏み出してみてください。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
