建設DXでペーパーレス化は可能?メリットや成功のステップを解説
建設

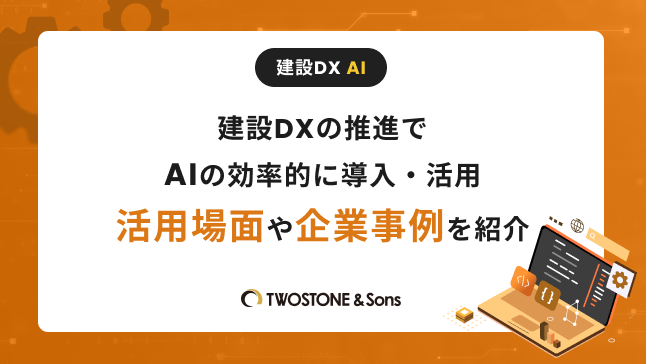
建設業界では今、深刻な人手不足や安全性の確保といった課題に直面しています。こうした背景から、AIをはじめとした先端技術の導入が求められる場面が増えてきました。中でもAIは、業務の効率化やリスクの軽減に役立つ手段として注目されており、建設DXを推進するうえで欠かせない存在になりつつあります。実際に、どのようにAIを導入すれば効果的なのかを理解しておくことは、これからの競争力を左右するポイントになるでしょう。
本記事では、建設業でAIの導入が必要とされる背景をわかりやすく整理し、具体的な活用シーンや導入事例を通じて実践に役立つヒントを紹介します。読み終えたときには、自社でのAI活用の可能性が具体的にイメージできるようになるでしょう。

建設DXを推進するにあたり、AI技術の活用は避けて通れないテーマとなっています。従来のIT化では対応が難しかった業務の効率化や安全管理、品質向上において、AIは実用的な解決策を提供できる段階に到達しつつあるといえるでしょう。
また、国土交通省をはじめとする政策機関が掲げるスマート建設の方針でも、AIを含む自動化技術の導入が強く推奨されています。技術的な進化と制度的な後押しが重なった今、AIの導入は建設DXにおいて不可欠な要素となりつつあります。
国土交通省は建設業の生産性向上、および働き方改革を目指す政策として「i-Construction 2.0」を推進しています。この施策は従来のICT活用に加え、AIやロボット技術の導入を加速させることで建設現場の自動化や高度化を図ることが目的です。
i-Construction 2.0では現場のデータをより高度に分析し、作業計画の最適化や安全管理の強化が求められています。大量のデータから有用な情報を抽出するAIの能力はこうしたニーズにマッチし、工期短縮やコスト削減、リスク低減を実現します。
この方針に基づき各企業は単なる機械の導入ではなく、AIを活用した現場の全体最適化を目指してDXを戦略的に進めているのが現状です。政策の後押しにより、AI技術の現場導入が急速に進む状況が生まれています。
出典参照:i-Construction 2.0~建設現場のオートメーション化~|国土交通省
建設分野ではBIM(Building Information Modeling)やCIM(Construction Information Modeling)が標準化されつつあります。これらは設計・施工・維持管理の全段階で建物やインフラの情報をデジタルモデルとして統合管理する技術です。
BIM/CIMの適用が原則化される中で、膨大なデータの効果的な活用が求められています。その中でAIが果たすのは複雑なデータ解析や予測、異常検知などを自動化し意思決定の精度を高める役割です。
例えば、施工現場の進捗管理においては3Dモデルと現場のセンサー情報をAIが解析して遅延のリスクを早期に検出したり、資材の最適配置を提案したりします。こうした高度なデータ活用が、BIM/CIMの本来の価値を引き出す上で不可欠です。
出典参照:令和5年度のBIM/CIM原則適⽤に向けた進め⽅ |国土交通省
建設業界にAIを導入することで得られる利点は、単なる業務の省力化にとどまりません。工程管理の精度向上や作業員の安全確保、資材の最適配置など、多角的な分野でAIは価値を発揮しています。
これまで熟練技術者の勘や経験に依存していた業務も、AIのアルゴリズムによって標準化され、再現性の高い業務プロセス構築が可能です。
ここでは、建設現場にAI導入を行うことによって実現できる、5つの代表的なメリットについて紹介します。
建設業界では高齢化や若年層の就業離れにより、慢性的な人手不足が続いています。AIの導入でこの人手不足を補完し、現場の負担を軽減する効果が期待されています。
例えばAIによる重機の自動操縦や画像認識による施工状況の自動チェックは、作業員の代替または補助としての機能が期待できるでしょう。これによって少人数でも作業が回る体制が整い、人手が足りない状況でも業務を止めずに進行させることが可能になります。
特に繰り返し作業や判断基準が明確な業務はAIと相性が良く、効率化の効果が顕著に表れます。労働力不足に悩む現場にとって、AIは有力な選択肢です。
建設現場では、長年の経験に基づく判断やノウハウが作業の質を支えてきました。しかしその知識は属人的で、文書化や共有が難しいケースも少なくありません。
AIは過去の施工記録や図面、工程管理データなどからパターンを学習して熟練者の判断を再現するアルゴリズムを構築できます。これによって暗黙知とされていた技術をデジタル上で再現し、若手人材や新規従業員への教育にも役立ちます。
さらに、引退が迫るベテラン技術者の知見のAIへの蓄積により、次世代への技術継承もスムーズに進められるでしょう。知識の属人化を防ぎ、組織全体の技術力を底上げする手段としてAIの活用が注目されています。
建設プロジェクトでは設計ミスや工程のズレが全体に影響を与えるため、初期段階からの精度が重要です。AIは設計段階から工程管理まで幅広く支援し、ミスの防止や計画の最適化に貢献します。
BIMデータと過去の施工情報をAIが解析すると、設計の妥当性や構造の干渉リスクを事前に検出できます。また工程管理では、センサーから取得した現場の進捗データをAIが分析し、作業の遅延やリスクをリアルタイムでの予測が可能です。
このようなデータ主導の計画と管理によって工程全体の見通しが立ちやすくなり、突発的なトラブルの回避にもつながります。予測精度の高い管理体制が、現場全体の安定運営に寄与します。
AIの導入により期待できるのが、品質管理と安全対策の水準向上です。これまで目視確認や手作業で行っていた検査や点検も、AIによる画像解析やセンサー分析によって自動化され、ヒューマンエラーのリスクが低減されます。
実際に、コンクリートのひび割れや鉄筋の配置ミスを画像認識AIが即座に検出、作業員の動線をモニタリングして危険な動きをアラートで知らせるなどの活用が進んでいます。
また、安全装備の着用チェックや重機と作業員の接近検知などもAIが担うことで、安全管理がリアルタイムに行えるようになりました。これにより事故の未然防止が強化され、現場の安全意識も自然と高まるでしょう。
AIの力を最大限に活用するには、蓄積された現場データの活用が不可欠です。建設業では日々の作業記録や品質検査、気象条件、機器の稼働状況など膨大なデータが生まれています。
これらをAIに分析させることで、作業の無駄を可視化したり、設備の最適な保守時期を予測したりといった継続的な業務改善が可能です。定量的な判断材料が得られるため、感覚ではなく根拠に基づいた意思決定が実現します。
また、現場ごとのパフォーマンス比較やコスト分析などもAIによって効率的に行えるため、全社的な改善活動のベースとして機能します。単に一度導入するだけでなく、継続的な活用によって効果を積み重ねられるのがAIの強みです。
建設業界におけるAIの活用は、突発的に始まったものではありません。その背景には、建設DXの推進により整備されつつあるデジタル基盤の存在があります。AI導入が現実的になり、効果を発揮できる環境が構築されているのはデータの収集や共有、業務の可視化といった土台が整ってきたからこそといえるでしょう。
ここでは建設DXによってAI活用が加速している理由について、5つの視点から掘り下げていきます。
AIを活用するには、学習用データが不可欠です。過去の施工記録や気象情報、品質管理データ、写真、センサー情報など多種多様な情報を大量に蓄積できる環境がなければ、AIは機能しません。
建設DXが進むことでこれらの情報が紙ベースからデジタルに移行し、クラウドやサーバー上で一元管理されるようになってきました。これによってAIが学習できるデータが継続的に集まり、より高度な予測や判断が可能になります。
実際に、過去の施工不良の傾向を学んだAIが似たようなリスクのある状況を早期に検知する、といった活用が現場で実現しつつあります。デジタル化は、AIの精度と実用性を支える土台です。
建設DXの中でも特に注目されるのが、現場のリアルタイム情報の可視化と共有です。センサーやドローン、ウェアラブルデバイスなどを活用して温度・湿度・振動・人の動きなどを常時モニタリングする仕組みが整いつつあります。
このようなリアルタイムデータは、AIにとって極めて価値の高い情報源です。施工の進捗や設備の状態、作業環境の変化などを即座に把握し異常の検知や改善策の提示が可能です。
また、現場の状況が即時に把握できることで管理者は迅速な意思決定を下せるようになります。これまでのように人間の勘や経験に頼るのではなく、データとAIによる合理的な判断が行えるようになります。
建設業界では、熟練の作業員が担ってきた業務が多く存在します。しかしそれらの作業は個人のスキルや判断に依存するため、標準化が困難でした。そこで建設DXにより作業プロセスが可視化されるようになると、こうした属人的な業務を再構築するきっかけが生まれます。
業務プロセスがデータとして記録・分析されることで、どの作業がどのような手順で行われ、どこに改善の余地があるかといった明確化が可能です。これにより、AIによる作業支援や自動化が現実的になります。
例えば、配筋検査や品質チェックなどの技術と判断を必要とする工程も、画像解析AIやパターン認識技術の導入により標準化と精度向上が可能です。作業の属人性排除は、人材育成の効率化にもつながります。
多拠点にまたがる現場や山間部・災害復旧などの特殊な環境では、現地に常駐する人員を最小限にしたいというニーズがあります。このような現場においては遠隔で状況を把握し、作業を支援する仕組みが求められます。
AIが果たす役割は、映像データの解析やセンサーデータの集約を通じた現地状況のリアルタイム把握、および離れた場所からの管理です。異常やトラブルの兆候を自動で検出し、関係者に通知するシステムもすでに実用化されています。
またAIによるナビゲーションや作業手順の提示により、現地の従業員への支援も可能です。人がいなくてもAIが状況を監視し、的確な対応を促す体制が実現しつつあります。
建設業界が抱える課題は、生産性の低さや安全性の確保です。これまではどちらか一方に注力すると、もう一方が犠牲になる場面も少なくありませんでした。ですが建設DXの進展によって、AIを使ってこの2つを同時に向上させる可能性が広がっています。
AIは現場の動線や作業手順を分析して作業効率を最適化するだけでなく、事故リスクの高い行動や配置を事前に予測する機能も備えています。作業の流れを変えずに安全性を高められるため、従来の管理とは異なる運用が可能になるでしょう。
こうした活用を可能にするのは、建設DXによって現場とシステムが密接に連携して情報がリアルタイムで共有される体制が整いつつあるからです。今後AIは単なる効率化ツールにとどまらず、建設業の基幹的な技術として位置づけられるでしょう。

AI技術は、建設現場の多岐にわたる課題に対応できる手段として注目されています。特に人材不足が深刻化する中で、AIによる業務の自動化やサポート機能が重要な役割を果たしています。
実際に工程管理、施工シミュレーション、安全予測、異常検知、進捗把握など、AIは実務レベルでの課題に直接対応できる技術として導入が加速してきました。
ここでは、建設業界における代表的な5つのAI活用場面を紹介し、それぞれの実用性と課題解決への貢献について解説します。
現場の進捗確認は、これまで担当者が目視で行うのが一般的でした。しかし現場が広範囲にわたる場合や複数現場を掛け持ちする場合、正確な確認が難しくなります。そこで注目されているのが、画像認識AIを用いた施工進捗の自動確認です。
現場に設置された定点カメラやドローンで撮影された画像をAIが解析し、図面や工程表との照合で施工がどこまで進んでいるかを自動で把握できます。作業の遅れや未着手箇所をリアルタイムで通知する機能も搭載されており、マネジメントの精度が向上します。
人の判断に頼らず客観的に進捗を評価できるため、スムーズな工程全体の見直しやリカバリープランの策定が可能です。
建設現場では、資材や機材の欠品や余剰が業務効率を左右します。AIの活用でこれらの在庫状況をリアルタイムで管理し、最適な発注タイミングを自動で判断可能です。
センサーやバーコードリーダーで収集した入出庫データをAIが解析し、使用傾向や過去の消費パターンから今後の需要を予測します。その結果、過剰在庫や納期遅延による作業の中断を防ぎ、資材ロスを最小限に抑えることが可能です。
また、現場ごとに異なる使用傾向にも柔軟に対応できるため、現場ごとの調整もスムーズに行えます。資材の最適化はコスト削減だけでなく、作業効率全体の改善にも直結します。
AIは大量の過去データの学習で今後の作業スケジュールや工期を高い精度で予測し、天候や作業人員、使用材料、施工方法などの要因を組み合わせて分析して最適な工程計画を提示可能です。
従来は経験則に頼っていた工程表の作成も、AIを活用すればデータに基づいた合理的な計画が立てられるようになります。作業の前倒しや遅延が発生しやすいタイミングも事前に把握できるため、リスク対策にもつながります。
また、複数の現場を同時に進行させる場合でもリソースの割り当てをAIが自動で調整できるため、全体の効率を向上させることが可能です。
建設現場における人員配置は、安全性や効率に直結します。無駄な動きが多ければ疲労が蓄積し、ヒューマンエラーのリスクも高まるでしょう。そこで、AIによる動線分析と作業量評価が活用されています。
AI活用の基盤が整うと、ウェアラブルデバイスや位置情報を活用した作業員の動きや作業内容をリアルタイムで取得し、その情報をAIが分析して動線の最適化や作業の偏りの是正を提案できます。負担の大きい作業が集中している作業員がいれば、AIが自動でタスク配分の再設計をすることが可能です。
また交差点や作業が重複するエリアではAIが接触リスクを検出し、注意喚起を行うこともまた可能です。適切な人員配置は安全性向上にもつながり、結果として全体のパフォーマンスを底上げします。
建設現場は常に危険と隣り合わせです。高所作業や重機の運転、気象の変化など、さまざまな要因が事故の引き金になります。異常検知AIはこうしたリスクをリアルタイムで把握し、迅速な対応を促すために活用されています。
AIはセンサーやカメラから得られるデータを分析し、通常と異なる動作や状況を検出可能です。例えば、作業員が立ち入り禁止区域に進入した場合や重機が異常な動作をした際には、即座にアラートを発する仕組みが代表例です。
気温や湿度の急激な変化による熱中症リスクも事前に察知し、作業中断や休憩の指示を自動で行えるようになります。こうした取り組みにより、重大な事故を未然に防ぐ体制が整ってきています。
AIを実装したシステムは、建設DXを進める上で実務的な価値を持つツールとして認識されています。特に、AIによる画像解析や進捗管理、音声指示による操作、設備の稼働予測など、目的に応じた機能を備えた専用システムが次々に現場に導入されています。導入には業務の性質に応じたシステム選定が欠かせません。
ここでは、現場での導入実績がある代表的なAI関連システムを6つ取り上げ、その特徴や活用のコツについて具体的に解説します。
SPIDERPLUSは建設現場における図面管理や写真撮影、帳票作成などをタブレットで一括して行えるアプリです。AIの活用によって写真に写る部材や設備を自動認識し、位置情報や図面との紐づけを自動化しています。
このシステムによって現場で撮影された画像は即座に整理・共有され、関係者間の情報伝達が迅速かつ正確になります。さらに作業内容や撮影箇所の抜け漏れもAIによるチェックで、ミスの防止も可能となりました。
図面と現場の情報をリアルタイムで連携させる機能は、施工管理や記録の正確性を高める上で有効です。
SiteBoxは、建設現場の帳票作成や工程管理をスマートフォンやタブレットから簡単に行えるアプリで、AI機能による写真整理や自動帳票生成が特徴です。
AIは撮影された画像を自動で分類し、関連する帳票の項目に割り当てることで日報や報告書の作成時間を短縮します。また、過去の帳票から学習したパターンを基に、記入ミスの防止や不足項目のアラートも行われます。
手作業で発生しがちな入力ミスや確認漏れを防げる点は、現場の実務にとって大きなメリットです。結果として現場での事務作業を軽減し、作業員が本来の施工業務に集中しやすくなります。
出典参照:SiteBox|株式会社建設システム
ANDPADの豆図AIキャプチャーは、建築図面における詳細な納まり図(豆図)を自動で認識・抽出する機能を持っています。これによって図面から必要な情報を瞬時に取得でき、現場作業の確認や準備の迅速な進行が可能です。
これまで手作業で行っていた図面の確認作業を自動化できるため、施工ミスの削減や確認作業の負担軽減が実現します。また、図面と現場の状況が一致しているかをAIが照合する機能もあり、設計通りに進んでいるかのチェックが容易になります。
特に複雑な設計を伴う住宅や集合建築の分野で、高い評価を受けているツールです。
出典参照:ANDPAD豆図AIキャプチャー|株式会社アンドパッド
Hikariは、建設業界に特化した対話型AIシステムです。施工方法や建材の種類、工程管理の知識など現場でよくある質問や調べ物にAIが即座に回答します。
スマートフォンやPCから簡単にアクセスでき、作業中にわからない点をすぐに確認できるため作業の中断を最小限に抑えられます。加えて、質問履歴を基に社内FAQとしての活用も可能です。
Hikariは単なる情報検索ツールではなく、社内のナレッジを蓄積・活用する役割も果たします。特に若手技術者や新人にとって、学習ツールとしての価値が大きいAIです。
出典参照:AIコンストシェルジュ「光/Hikari」|燈株式会社
AnyDataは、書類や画像などの非構造データをAIが自動で分類・分析するクラウド型データプラットフォームです。建設現場で日々発生する大量の資料や写真を一元管理し、必要な情報を即座に検索できます。
AIは文書の中からキーワードを抽出して関連する案件や図面と自動で紐づけ、類似案件との比較分析を通じて意思決定に必要な情報も可視化します。
情報管理にかかる時間と工数を削減でき、部門横断的なデータ活用を推進できるのが大きな特長です。過去の案件の傾向を活かしたリスク対策や、資料の再利用も効率的に行えます。
Kizukuは施工現場の進捗管理や連絡共有を一元化するアプリで、写真や工程表、書類、チャットなどを1つの画面で管理できる点が特徴です。AIは日々の進捗から遅延傾向を分析し、工程の見直しや対応策の提案を行います。
また写真に写る作業や部材を認識し、自動で紐づけやタグ付けを行う機能も搭載されています。現場からの報告内容をAIが整理し、管理者への通知や帳票作成までを一括で行う設計です。
特に複数の下請け業者が関わる大規模現場では情報の錯綜を防ぎ、統一された進行管理を実現するためのツールとして活躍しています。
出典参照:Kizuku|コムテックス株式会社
AIを取り入れた建設DXはもはや実験段階ではなく、実用フェーズに入りつつあります。現場での生産性向上、労働環境の改善、データ活用による戦略的な意思決定など、企業ごとに異なる課題に対してAIが活躍しています。導入事例を通じて、AIがどのように建設業務に統合され、具体的な成果を上げているのかを知ることは、今後導入を検討する上で非常に参考になるでしょう。
ここでは、AIを活用してDXを進めた建設企業3社の実例を紹介します。
清水建設ではChatGPTをベースとした業務用の社内AIシステムを構築し、全従業員に向けて展開しています。このAIは社内規定や技術資料、プロジェクト情報などと連携しており現場担当者や管理者が必要とする情報を迅速に取得できる仕組みです。
導入の背景には、業務ナレッジの属人化や情報検索にかかる時間の多さがありました。AIの導入によって社内文書の検索精度が向上し、業務の効率化とミスの削減が実現されています。また問い合わせ対応やマニュアル作成などにもAIが活用されており、全社的なデジタル化を後押ししています。
このように生成AIをうまく業務に組み込むことで、作業効率と判断スピードの両立が可能です。
出典参照:全従業員向けに生成AIサービスの提供を開始 |清水建設株式会社
竹中工務店では建物の構造設計業務に、AIを活用する取り組みを進めています。具体的には、構造解析や断面設計などの複雑な計算をAIが自動で実行し、設計案を瞬時に提示できる構造設計AIシステムを開発しました。
従来は構造設計者が図面や条件を基に試行錯誤しながら設計案を作成していましたが、このシステムの導入によって数時間かかっていた工程が短時間で完了するようになりました。その結果クライアントへの提案スピードが向上し、競争力の強化にもつながっています。
また設計条件に対して最適な案を複数提示できるため意思決定の幅も広がり、より質の高いプロジェクト運営が実現されています。
出典参照:構造設計をクリエイティブに 「構造設計AIシステム」を開発|竹中工務店株式会社
前田建設工業で導入されたのは、交通誘導員の配置が難しい大規模現場やトンネル工事においてのAIを活用した交通安全システムです。このシステムは監視カメラの映像をAIがリアルタイムで解析し、人や車両の異常な動きを検出します。
危険が迫った場合は現場担当者のスマートフォンにアラートが通知されるほか、現場の警告灯や音声で周囲にも注意を促します。従来は目視や巡回に頼っていた安全確認作業がAIによって常時監視可能になったことで、事故リスクの軽減と作業環境の改善が可能となりました。
現場の安全性確保はDXの重要な要素であり、AIの活用で人手不足の中でも高水準の安全管理が可能になります。
出典参照:人工知能(AI)による交通危険事象検知システムを開発(特許出願中)|前田建設工業株式会社

建設業界におけるAIの導入は、もはや一部の先進企業だけの取り組みにとどまりません。人手不足や現場の複雑化が進む中で、AIは生産性と安全性を両立させるための重要な選択肢となっています。
AIの導入によって作業効率の向上やミスの防止、工程の最適化、さらには従業員の知識継承など多くの課題解決が期待できます。特にDXを同時に進めることでAIが活用しやすい環境が整い、より実践的な成果につなげることが可能です。
今回紹介した企業の事例や活用シーンを参考に、自社の業務と照らし合わせながらAI導入の可能性を具体的に検討してみてください。身近な業務から段階的に取り入れることが、建設DX成功の第一歩となるでしょう。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
