建設DXでペーパーレス化は可能?メリットや成功のステップを解説
建設

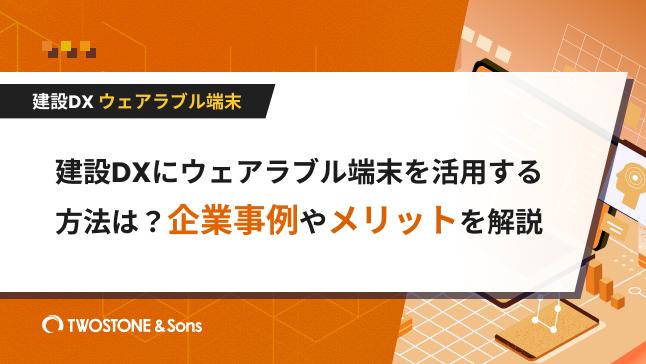
建設現場では天候や地形、重機の運用などにより、常に安全と効率の両立が求められています。こうした現場特有の課題に対して、最新技術の力で解決を目指す建設DXが注目されています。その中でも、作業員の安全確保と作業効率の向上を両立させる手段として注目されているのが、ウェアラブル端末の活用です。現場での体調管理や作業状況の可視化に役立つだけでなく、緊急時の対応を迅速にするなど、多面的に効果を発揮しています。
本記事では、建設業界でウェアラブル端末が果たす役割や、導入が加速している背景、さらに具体的な活用方法や企業事例を紹介します。建設現場におけるウェアラブル端末導入の可能性を知るきっかけとして、ぜひ参考にしてください。

建設DXの推進が進む中で、ウェアラブル端末はその中心的な役割を果たしています。その理由として挙げられるのが、現場で働く作業員の安全確保や作業効率の改善、労働環境の向上に貢献している点です。これらの端末は、装着者の健康状態や作業状況をリアルタイムで把握し、管理者や関係者に情報を共有できます。その結果、事故の未然防止や迅速な対応を可能にします。
ウェアラブル端末はセンサー技術の進歩により多様な機能を持ち、建設現場の複雑な状況に柔軟に対応可能です。具体的には心拍や体温、動作の異常を検知した際の警告発信、位置情報を活用した作業者の居場所の把握などです。このように安全管理の強化と作業の見える化が建設DXにおいて重要な役割を果たします。
建設業界では、人手不足や高齢化、安全管理の高度化といった課題が慢性化しています。これに対応する手段として、リアルタイムでの情報取得や現場の可視化、作業者の負担軽減を可能にするウェアラブル端末の需要が高まっています。これらの端末は、作業効率や安全性の向上を実現するだけでなく、デジタル化が進む中で蓄積されるデータを活用した現場管理や判断の支援にも寄与するためです。
ここでは、こうした技術が必要とされる3つの代表的な背景を解説します。
建設現場では高所作業や重機の稼働など危険を伴う作業が多く、事故や怪我のリスクが常に存在します。労働安全の強化は国や企業にとって重要な課題であり、ウェアラブル端末はこうしたリスク管理の強化に寄与しています。センサーが異常な心拍数や転倒を検知すると即座に警告が出され、速やかな対応が可能です。
またリアルタイムでの体調管理は熱中症や過労など、健康リスクの予防にもつながります。従来の目視や定期的なチェックではカバーしきれなかった異常の早期発見に貢献し、現場の安全度を高めます。こうした安全性向上の需要が、ウェアラブル端末の導入を促進している要因の1つです。
建設業界では工期の短縮やコスト削減が強く求められ、作業効率の改善は重要な課題です。ウェアラブル端末は作業員の動きをリアルタイムで把握し、動線の無駄や作業負荷の偏りを分析可能にします。これにより、効率的な人員配置や作業プロセスの最適化が実現します。
加えて、コミュニケーション機能を備えた端末は現場内の情報共有を円滑にし、迅速な指示伝達が可能です。作業者間の連携が強化されることで、作業ミスの減少や対応速度の向上が期待できます。こうした効率化ニーズの高まりが、ウェアラブル端末の導入を後押ししています。
建設業界では労働者の高齢化が進み、体力的な負担や健康リスクが増大しているのが現状です。若年層の人手不足と合わせ、高齢者も含めた全員が安全かつ効率的に働ける環境整備が求められています。ウェアラブル端末は健康状態のモニタリングを通じ、高齢作業者の安全管理を支援します。
具体的には、心拍や体温の異常を検知して早期警告を発信したり、作業負荷の偏りを把握して無理な作業を回避させたりといった役割です。これにより、高齢者の安全確保と現場全体の労働環境改善が同時に図れます。こうした社会的背景も、ウェアラブル端末普及の理由です。
建設DXにより現場のデジタル化が進展する中、ウェアラブル端末の価値はさらに高まっています。まず、現場作業の情報がリアルタイムでデジタル化されることで、収集したデータをAIやクラウドと連携させて分析できます。これにより、健康状態の把握や作業効率の見える化が可能です。
また導入コストの低下や端末の多機能化により、幅広い現場での活用が可能となっている点も普及を後押ししています。現場のニーズに応じた多様な製品が登場し、個別の課題に合わせた最適な導入が実現しやすくなりました。こうした環境変化が導入拡大を促進しています。
建設現場では、作業効率の向上と安全性の確保を両立するために、ウェアラブル端末の活用が進んでいます。これらの端末は、ヘルメットに装着するカメラやスマートグラス、バイタルセンサー付きの作業着など多岐にわたります。これらは映像や音声による情報共有だけでなく、作業員の位置情報や体調のモニタリングもリアルタイムで行えるため、緊急時の対応やリスクの早期発見にもつながる点が魅力です。
ここでは、建設DXの実現に貢献する代表的なウェアラブル機器を紹介します。
Xacti LIVEは、作業員が装着しその視点をリアルタイムで共有できるウェアラブルカメラです。現場の状況を遠隔地の管理者や技術者にライブ映像で伝えるため、指示の迅速化やトラブル対応がスムーズになります。映像はクラウドに保存され、後からの確認や報告書作成にも活用可能です。
このカメラの導入によって現場内のコミュニケーションが強化され、確認作業の無駄が減少します。現場経験が浅い作業員も専門家のアドバイスを受けながら作業を進められるため、品質の均一化にも寄与します。特に、広範囲に及ぶ現場や複数の現場を同時管理する際に効果的です。
出典参照:Xacti LIVE|株式会社ザクティ
スマートヘルメットは従来の保護帽に加えて、映像記録や音声通信機能を搭載した多機能デバイスです。その特徴として頭部に装着するため、両手を自由に使いながら情報を取得・発信でき作業の邪魔になりません。危険箇所の映像を撮影しつつ、管理者とリアルタイムで連絡を取り合えます。
さらに、ヘルメットに搭載されたセンサーが作業員の動きや姿勢を解析し、転倒や異常行動を検知して警告も可能です。安全管理の強化に加え事故発生時の状況把握に役立つため、迅速な対応につながります。現場のリスクを減らし、作業効率の向上に貢献しています。
出典参照:スマートヘルメット ||株式会社イプロス
BIM連携端末は、建築物の3Dモデルや設計データを現場で直接確認できるデバイスです。作業者は設計図面を持ち歩く代わりに、タブレットや専用ゴーグルを使って立体的な情報を閲覧しながら作業が可能です。これにより設計と施工のズレを防ぎ、手戻りの削減に役立ちます。
また、現場での状況とBIMデータを照合しながら作業できるため、変更や修正が必要な場合も速やかに対応できます。BMI対応デバイスの導入は建設DXの一環として設計情報のデジタル化と現場での活用を推進し、プロジェクトの効率化と品質向上の実現を可能にしてきました。複雑な構造物の施工においてもメリットがあります。
出典参照:施工BIMの活用ガイド|一般社団法人日本建設業連合会
バイタルセンサーは作業員の心拍数や体温、呼吸状態などの生体情報を常時監視できる装置です。ウェアラブル型センサーの装着で、熱中症や過労など健康リスクの早期発見が可能となります。異常が検知されると管理者に自動通知され、迅速な対応を促します。
健康状態のリアルタイム把握は、高温多湿の夏場や過酷な労働環境で特に有効です。作業者の安全を守るだけでなく休憩のタイミングを科学的に決定できるため、作業効率の向上にもつながります。こうした機能は、労働安全衛生の強化に欠かせない要素です。
出典参照:熱中対策ウォッチ カナリアPlus|Biodata Bank株式会社
Apple Watchは一般向けスマートウォッチの一例ですが、建設現場でも活用されています。作業員の心拍や活動量を測定し健康管理を支援できるほか、SOS機能を活用して緊急時の連絡手段として役立ちます。GPS機能により位置情報の把握も可能です。
また端末は、着信やメッセージの通知を手元で受け取れるため、現場での連絡がスムーズになります。作業効率の向上や安全管理に寄与しながら、使い慣れた操作感で導入しやすい点がメリットです。実際に、既存のスマートウォッチを活用しながら建設DXの一環として活用する企業も増えています。
出典参照:Apple Watch|Apple

建設現場での安全性や効率向上をめざして、ウェアラブル端末の導入が進んでいます。作業員の動きや健康状態をリアルタイムで把握し、現場の情報共有や安全管理を強化するツールとして注目を集めているのがこれらのデバイスです。
ここでは建設業におけるウェアラブル端末導入のメリットを、4つの視点から詳しく解説します。導入がもたらす効果を理解し、建設DX推進の参考にしてください。
ウェアラブル端末は作業員の現場状況を即時に収集し、管理者や他の作業員と共有できるため意思決定や指示がスムーズになります。例えば、ウェアラブルカメラを通じて現場の映像をリアルタイムで共有すれば、遠隔地にいる専門家からも迅速なアドバイスが受けられます。
また現場の状況変化を即時に把握できるため、トラブル発生時の早期対応やリスク回避につなげることも可能です。従来の報告や確認作業にかかっていた時間を削減できるため、作業効率全体の向上が期待されます。さらに作業員同士のコミュニケーションも円滑になるため、連携プレーが強化されます。
建設現場は常に危険と隣り合わせの環境です。ウェアラブル端末を活用すれば作業員の体調や動きを常時監視し、危険な状態を検知した際に即座の警告が可能です。例えば、バイタルセンサーが心拍数や体温の異常を察知すると、管理者にアラートを送信して熱中症や過労を未然に防ぐことにつながります。
また、転倒や衝撃を感知できる加速度センサー搭載の端末が役立つ場面として挙げられるのが、事故発生時の即時通報です。これによって迅速な救助活動が実現し、被害の拡大を防げるため作業員の安全確保に貢献します。さらに安全管理データの蓄積により、過去の事故傾向分析や対策の立案も可能です。
ウェアラブル端末は作業内容や工程の記録を自動で取得できるため、手動での報告書作成や作業日報の記入負担を減らせます。現場作業員は記録にかかる時間を削減し、本来の作業に集中できる環境が整います。
映像やセンサー情報がクラウドに保存されるため、後からの検証や進捗管理にも活用可能です。これにより作業の正確性が向上し、手戻りやミスを減らす効果も期待できます。加えて自動化されたデータは管理側の負担も軽減し、効率的な現場運営につながるでしょう。
緊急事態は現場で突然発生するものですが、ウェアラブル端末の導入で対応速度を高められます。異常を検知した場合には即時に管理者へ通知が届き、迅速な対応が可能になるため被害の拡大を防ぐことにつながります。
例えば転倒や心拍異常などの危険信号が送られた際、管理者は正確な位置情報と状況を把握した上で救助の手配が可能です。こうした迅速な対応は作業員の安全を守るだけでなく、現場の信頼性向上にもつながります。緊急時のスムーズな連携の実現は、建設DXの重要なメリットです。
先進的な建設企業の中には、ウェアラブルデバイスを実用レベルで取り入れ、生産性の向上と安全性の両立を図っている事例が増えています。これらの企業では、現場作業員の視点を共有できるスマートグラスや作業負担を軽減するアシストスーツ、リアルタイムのバイタル管理を行うウェアなどを導入し、現場全体の可視化とマネジメント強化を実現してきました。
ここでは実際に導入を行っている企業の取り組みを具体的に紹介し、導入による成果や特徴を明らかにします。
清水建設は現場の作業効率と安全管理を向上させるために、骨伝導通信デバイスとウェアラブルカメラを組み合わせたシステムを導入しています。骨伝導通信は耳を塞がずに音声を伝える技術であり、作業中でも周囲の音を聞き取りながら安全にコミュニケーションを取れます。
これによって現場作業員は、ヘルメットを装着したままハンズフリーで会話が可能になり、手を使う作業中でも指示や情報共有をスムーズに進めることが可能です。さらに、ウェアラブルカメラを通じた遠隔地の管理者との映像共有で、リアルタイムに現場の状況確認が行えます。
このシステムは安全性を高めるだけでなく、問題発生時の迅速な対応や現場全体の効率化にも寄与しています。こうした技術活用は建設現場の働き方改革につながり、今後も多くの現場で応用されるでしょう。
出典参照:その先の未来につながるIT活用。|清水建設株式会社
大林組は作業員の健康状態を常に監視するために、ウェアラブルリストバンドを導入しています。このデバイスは心拍数や体温、動きのデータをリアルタイムで計測して作業環境の過酷さや労働者の疲労度を把握します。
収集したデータはクラウドに送信され、管理者が複数の作業員の状態を一括管理可能です。これによって熱中症や過労による事故を未然に防止し、安全管理体制を強化しています。
また異常な数値が検出された場合は即座にアラートが発せられ、迅速な対応を促します。作業員個々の健康状態に基づいた安全対策は現場の信頼性向上に直結し、労働環境の改善が可能になるでしょう。
出典参照:心拍数や作業環境状況をリストバンドでリアルタイムに計測し作業員の体調を管理します|株式会社大林組
鹿島建設は、独自に開発した背負い型の「ウェアラブルバイブレータ」を導入し、作業者に安全面での新たな支援を提供しています。このデバイスは、危険箇所や接近禁止エリアに近づくと振動で警告を発し、視覚や聴覚に頼らない安全確保を可能にします。
作業員は、振動による直接的なフィードバックを受け取ることで危険回避の意識が高まり、事故発生リスクの軽減が可能です。さらにこのシステムは、長時間の使用でも疲労が少ない設計で、現場での継続的な活用に適しています。
こうしたウェアラブル技術は、現場作業の安全性向上と効率化に加え、労働者の心理的負担軽減にも寄与しています。現場環境の厳しさに対応した新たな安全対策として注目されている事例です。
出典参照:人間工学に基づいた軽量設計「ウェアラブルバイブレータ」を開発 |鹿島建設株式会社
ウェアラブル端末を建設現場で効果的に活用するためには、導入の準備段階から明確な目的設定と段階的な計画が求められます。
まずは現場の課題や改善ポイントを洗い出し、それに合ったデバイスの選定を行いましょう。次に、実証実験を通じて導入効果を検証し、運用ルールや教育体制を整備した上で本格導入に移行します。
この流れを踏むことで、機器の性能を最大限に活かし、現場にスムーズに定着させることが可能になります。ここではその基本手順を詳しく解説します。
まず現場で抱える課題や改善したいポイントを、具体的に洗い出すことが重要です。例えば、安全管理の強化が優先ならバイタルセンサー付き端末が有効であり、コミュニケーションの円滑化を図りたいならウェアラブルカメラや骨伝導デバイスが適しています。
また作業の種類や環境に応じて必要な機能の明確化で、導入する端末の性能や仕様が決まります。現場の声を反映させ、使いやすさや負担の少なさにも配慮しながら選定を進めることが成功のカギです。
選定したウェアラブル端末は、いきなり大規模な現場で導入するのではなく、小規模な試験運用から始めることが推奨されます。トライアル運用では実際の使用感や操作性、通信環境などの課題が明らかになります。
また作業員のフィードバックを集めて改善点を洗い出し、必要に応じて運用ルールや教育体制を整備しましょう。こうした段階的な運用によって導入後のトラブルや不具合を未然に防ぎ、本格運用時の円滑な展開につなげられます。
ウェアラブル端末は、初期投資や運用コストが課題になることもあります。そこで国や地方自治体が実施している補助金や助成制度の活用で、導入費用の負担を軽減可能です。
これらの制度は建設業の生産性向上や安全対策推進を目的としており、条件を満たせば一定割合の補助が受けられます。申請手続きは複雑な場合もあるため、専門家の支援を受けながら計画的に準備するとよいでしょう。
公的支援を上手に活用し、コスト面の不安を解消しながらウェアラブル端末の導入を進めることで現場のDX化を加速できます。
ウェアラブル端末の導入には多くのメリットがある一方で、現場に適応させるにはいくつかの注意点を押さえておく必要があります。
例えば、利用者の負担にならない装着性や操作性の確保、デバイスの耐久性やバッテリー性能、さらには扱うデータのセキュリティとプライバシー保護も重要な要素です。導入後の運用トラブルを防ぐためには、使用ルールの明確化と社員教育の実施が欠かせません。
ここでは、安全かつ持続的に活用するための留意点を解説します。
ウェアラブル端末は作業員の健康情報や位置情報など、個人に紐づく重要なデータを扱います。これらの情報が漏えいした場合、労働者のプライバシー侵害や企業の信頼失墜につながるリスクがあります。
したがって導入段階で通信の暗号化やアクセス権限の設定、端末管理の徹底などセキュリティ対策の強化が欠かせません。またクラウドサービスを利用する場合は、信頼できるプロバイダーを選び、データ保護のための法令遵守も確認しましょう。
総合的な対策で個人情報漏えいを防止し、安全なウェアラブル端末運用を実現しましょう。
ウェアラブル端末を現場全体に導入すると、端末の購入費用だけでなく管理システムの構築や通信環境の整備などのさまざまな初期投資が発生します。これらは中小規模の企業にとって大きな負担となる場合があります。
そのため、導入規模に応じたコスト計画を立てることが重要です。段階的に導入を進めて運用の効果を検証しながら、最適な機器選定や運用方法を検討するとよいでしょう。
また導入費用を抑えるためにレンタルサービスの活用や、前述の補助金・助成金制度の利用も有効です。初期費用に対して過度に慎重になりすぎず、長期的なコスト削減や作業効率向上による投資回収も視野に入れた計画を立てましょう。
ウェアラブル端末は単独で使うだけでなく、現場の他の管理システムやITインフラと連携させることで効果を発揮します。したがって、導入前に既存のシステムと相互運用できるかどうかを確認しましょう。
特に作業管理ソフトや安全管理ツールとスムーズにデータ連携できれば、情報の一元管理が可能となり現場の透明性と効率性が向上します。逆にシステム間の連携が不十分だと、二重入力やデータの不一致など、運用上の混乱を招く可能性を無視できません。
ベンダーや専門家と連携して技術的な検証を進めることが成功への近道です。

建設DXの推進において、ウェアラブル端末は現場の安全性と作業効率を支える重要なツールです。リアルタイムの健康管理やコミュニケーション強化、作業記録の自動化など多様なメリットをもたらします。
しかしながら導入時には個人情報の保護や初期コスト、既存システムとの連携といった課題を十分に検討し、計画的に進めることが求められます。こうしたポイントを踏まえながら段階的に活用範囲を広げていけば、DX効果をより大きくできるでしょう。
記事の内容を参考にしながら自社の現場に合ったウェアラブル端末の選定と運用方法を検討し、安全で効率的な建設現場の実現に役立ててください。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
