建設DXでペーパーレス化は可能?メリットや成功のステップを解説
建設

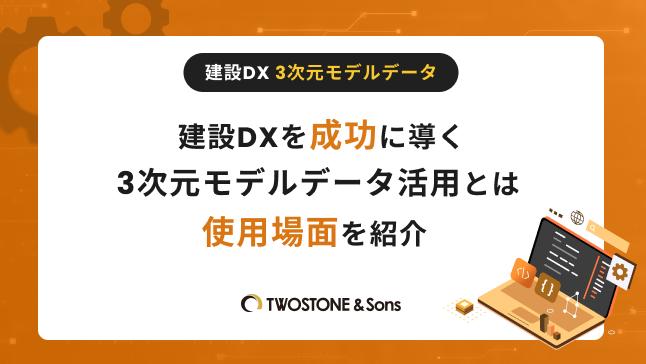
建設現場の状況が年々複雑化している中で、従来の2次元図面だけでは対応が難しくなってきています。図面上での情報伝達に限界があるため、現場での意思疎通が円滑に進まず、設計と施工のズレや確認不足によるミスが起きやすくなっています。特に工程管理においては、複数の業者や部署が関わる中で、タイミングや手順の食い違いが混乱を招くことも少なくありません。
このような現場課題の解決策として注目されているのが、3次元モデルデータの活用です。建物や設備を立体的に可視化することで、関係者全員が空間や構造の把握を直感的に行えるようになります。
本記事では、3次元モデルデータが建設DXにおいてどのような役割を果たすのかを詳しく解説します。

3次元モデルデータとは、建物や構造物の形状を3次元空間上で再現したデジタルデータを指します。これはBIMやCIMにおける中核的な要素であり設計や施工、維持管理の各フェーズで情報共有と意思決定を支える基盤です。
このデータは、図面では表現しきれない空間の奥行きや構造を立体的に把握できるため、関係者間の理解のギャップを埋めやすくなります。3次元モデル上には形状情報だけでなく材料や寸法、工期、コストなどの属性情報も付加できます。
建設DXの推進において、3次元モデルデータは単なる可視化ツールではなく、全体の工程管理や意思決定における精度向上、業務効率の底上げに貢献します。現場作業と設計情報の統合、関係者間の情報共有の円滑化など、幅広い領域で有効性を発揮しており、今や建設現場に欠かせない存在といえるでしょう。
ここでは、3次元モデルデータ導入によって得られる代表的な5つのメリットを詳しく解説します。
3次元モデルは、図面に慣れていない関係者にとっても理解しやすいのが特徴です。2次元の設計図では把握しにくかった構造や仕上がりを立体的に確認できるため、設計者と発注者、現場担当者との意思疎通が円滑になります。
合意形成に時間がかかると設計や施工の進行にも影響しますが、3次元モデルによって誤解や確認漏れを防ぎやすくなります。その結果、打ち合わせや調整にかかる時間が短縮され、スムーズなプロジェクト進行が可能です。
建設業では多様なステークホルダーが関わるため、共通認識を早い段階で持てることは重要です。
3次元モデルを用いることで、設計段階での干渉チェックや整合性確認がしやすくなります。配管や配線が構造体と干渉していないか、施工スペースが確保されているかを視覚的に確認できるため後工程でのトラブルを減らすことにつながります。
施工に入ってから設計ミスが発覚すると再設計、やり直し工事などが発生し工期やコストに影響を及ぼします。しかし3次元モデルで事前に問題点を洗い出すことで、こうしたリスクを最小限に抑えられるでしょう。
またモデル上でのシミュレーションによって安全性や施工性の検証も行いやすくなり、品質管理にもつながります。
3次元モデルデータは、ICT建機との連携によって施工の自動化にも活用できます。例えば重機への3次元データのインポートで、オペレーターの操作を補助しながら正確な施工を支援可能です。
地盤整地や掘削作業ではモデルを基に施工範囲や深さを指示できるため、作業精度の向上とともに時間短縮にもつながります。さらに、ドローンやスキャナーと組み合わせて現況との比較もできるため、進捗状況の確認や差分の分析も効率的に行えます。
こうしたデジタル化は省人化にも効果があり、現場の人手不足対策としても有効です。
3次元モデルは施工状況や工期に応じたモデル変化を視覚的に追えるため、進捗管理に強みを発揮します。工程ごとの作業内容を時系列で表示も可能となるため、関係者全員がスケジュールの理解を深めやすくなります。
また遅延リスクやボトルネックが生じた場合も、モデルと実際の状況との比較により原因の特定が容易です。これにより、的確な対策をタイムリーに講じることが可能です。
工事の全体像を可視化できるため、工程の精度と柔軟性が両立しやすくなり品質・納期の確保にもつながります。
3次元モデルは、竣工後の維持管理や改修計画においても活用されます。施設や設備の配置、材料の情報、修繕履歴などを一元管理できるためメンテナンスの効率が高まります。
特にインフラや大型施設では、長期間にわたる維持管理が必要です。その際モデルデータを参照し、点検対象の特定や補修計画の立案が容易になります。
加えて、将来的なリニューアルや用途変更の検討にも役立ちます。現況を正確に再現したモデルがあることで、計画の立案やコスト試算がスムーズに進行可能です。
3次元モデルデータは設計段階の図面確認にとどまらず、施工計画や進捗管理、さらには維持管理フェーズまで広範囲で活用されています。3次元モデルデータを活用することで、従来の2次元図面では捉えきれなかった構造や干渉箇所の確認が可能となり、現場での手戻りや調整工数を削減できるようになりました。
ここでは、3次元モデルデータの活用によって業務の質が大きく変わる5つの具体的な活用場面を紹介します。
土工の現場では、土地の形状や標高の把握が正確な設計と施工の前提となります。3次元モデルデータの活用で造成計画の段階から現況の地形を可視化し、必要な切土や盛土の量、排水計画の最適化などを高精度で検討できます。
さらにICT建機と連動させることで自動施工の指示ができ、作業の精度と効率を同時に高めることが可能です。これによって人的ミスや過剰な施工を防ぎ、資材や時間のロスを最小限に抑えられます。
複雑な地形や制約条件が多い現場でも、立体的なシミュレーションにより問題点の早期発見が可能となり、施工計画の質を向上させる効果が期待されます。
橋梁やトンネルの設計に求められるのは、高度な構造解析と正確な図面作成です。3次元モデルデータは構造物の各要素を立体的に表現して寸法や納まり、施工順序を確認するために有効です。
特に異なる構造体が交差する箇所や曲線部の設計では、2次元図面だけでは見落としが生じやすくなります。3次元モデルを用いることで干渉や矛盾点の検出がしやすくなり、設計品質の向上につながります。
また地盤条件や既存インフラとの取り合いもモデル上で検討できるため、実際の施工時に起きがちな手戻りリスクを減らす効果も期待できるでしょう。
建築設計の段階では、施主や関係者との合意形成が重要です。3次元モデルを用いることで完成後の建物イメージを視覚的に伝えやすくなり、図面だけでは伝わりにくい空間の広がりや採光、導線といった要素を共有できます。
また日照シミュレーションや内装材の比較などもモデル上で行えるため、施主の理解と納得を得やすくなります。設計者にとっても、プレゼンテーションの説得力を高めるツールとして有効です。
加えてモデルの一部を変更して異なる案の比較も可能であり、設計段階の柔軟性を保ちながら意思決定を迅速に進められます。
工事が始まった後も、3次元モデルデータは活用されます。進捗管理の場面ではモデルと現況との比較によりどこまで作業が進んでいるのか、どの部分に遅れが出ているのかを視覚的に把握することが可能です。
ドローンやレーザースキャナーによって取得した点群データと連携すれば、施工状況の定量的な把握も可能です。この情報は発注者への報告資料としても活用でき、信頼性の高い情報提供が実現します。
さらに工事記録としてモデルを保存し、将来的な工事履歴の確認やトラブル発生時の検証にも役立てることが可能です。
施設やインフラの維持管理においても、3次元モデルデータの価値は高まっています。モデル上に各部材の仕様や点検履歴を紐づけることで、管理業務の精度と効率を向上させられます。
従来の紙ベースの台帳管理では図面と写真、記録がバラバラになりやすく情報の把握や共有に時間がかかっていました。しかし3次元モデルへの情報の集約により、視覚的かつ直感的に状況を把握できます。
特に経年劣化や修繕履歴の可視化は今後の維持管理計画を立てる上での判断材料となり、無駄な修繕や点検の重複を防ぐことが可能です。

3次元モデルデータを効果的に運用するには、業務特性に適したツールを選定する必要があります。近年はBIMソフトをはじめとする建設向けの専用ツールが多様化しており、機能や対応範囲も異なります。目的に合ったツールを導入することで、設計・施工・管理の連携がスムーズに進むだけでなく、関係者の負担も軽減できるでしょう。
ここでは、現場で実際に使われている代表的な4種類のツールを紹介します。
Revitは建築設計に特化したBIM対応ソフトウェアです。建物の構造や設備、仕上げなどを1つのモデル上で統合管理できる点が特徴です。3次元モデルの作成に加えて建材や面積、数量といった属性情報も自動で付加されるため、設計の段階から施工や管理まで一貫して活用できます。
またRevitは、クラウド経由で複数の関係者とリアルタイムでデータを共有できるため、設計変更への迅速な対応や合意形成のスピードアップにもつながります。建築プロジェクトの初期段階から維持管理フェーズまで広く活用されており、設計業務の中心的な存在です。
出典参照:Autodesk Revit |Autodesk, Inc.
TREND-COREは土木分野に特化した3次元CADソフトで、特に日本国内で多くの導入実績を持つツールです。地形モデルや構造物の3Dモデルを作成し、視覚的にわかりやすい形で関係者に共有できる点が評価されています。備わっている機能は、公共工事や民間工事の設計段階においての住民説明会、合意形成と役立つ内容が豊富です。
また国土交通省が推進するCIM(Construction Information Modeling)にも対応しており、設計から施工までを一元管理するための機能が充実しています。日本の土木業界に適応したインターフェースと機能性が特長で、現場のニーズに応えやすい設計となっています。
出典参照:BIM/CIMコミュニケーションシステム|福井コンピュータ株式会
InfraWorksは、都市計画やインフラ設計に強みを持つ3次元モデリングツールです。GISデータや既存の地形情報との連携で広範囲にわたる土地や道路、橋梁などをリアルに再現できます。都市計画や交通インフラのシミュレーションを行う場面で特に活用されています。
このツールの特徴は、モデルのビジュアル性と操作の直感性に優れている点です。複雑な構造やエリア全体の整備計画を視覚化し、ステークホルダーと具体的な議論を進めるための材料として利用できます。環境影響評価や都市開発計画など、マクロなスケールの検討に適しています。
Civil 3Dは土木設計に対応した3次元CADソフトで道路や上下水道、造成設計などのインフラ整備に活用されます。特に断面や縦断の設計、数量計算、設計図の作成までを一元化できるため設計工程の手間を削減可能です。
またBIMやCIMに対応した設計プロセスを実現できるため、公共工事を中心に導入が進んでいます。3次元モデルと2次元図面の整合性を自動的に保ちつつ、修正がリアルタイムで反映される仕組みも備わっており作業効率の向上に貢献します。
これらのツールは単体で使用するだけでなく、プロジェクトの特性に応じて組み合わせて運用されるケースも少なくありません。設計や施工、維持管理といった各フェーズでの活用シーンを想定しながら、自社に最適なツールの選定が求められます。
出典参照:Civil 3D|オートデスク株式会社
建設DXの一環として3次元モデルデータを導入した企業では、単なる業務効率化を超えた変化が見られています。現場での作業判断や施工の精度向上、トラブルの予防策としての活用が進み、結果としてコストや工期の適正化にもつながっています。
導入当初は一部部署に限られていた取り組みが、成功事例を経て全社的に拡大していく傾向も確認されてきました。
ここでは、実際の導入効果が明確に見られた3社の事例を紹介します。
大和ハウス工業では建築設計に用いるBIMデータをベースに、建物や敷地全体を立体的に再現したメタバース空間を構築しました。この取り組みによって建物の完成イメージをリアルに体感できるようになり、施主との打ち合わせにおいて高い説得力を発揮しています。
特にVR対応のメタバース内では外観や内装、周囲の景観までも忠実に再現可能です。これによって、従来は口頭説明や2次元図面では伝わりにくかった空間の広がりや使い勝手を明確に伝えられ、顧客満足度の向上にもつながっています。
また設計段階での意匠検討や建材選定、家具配置などもシミュレーションできるため設計修正の精度とスピードも向上しています。
出典参照:「D’s BIM ROOM(ディーズビムルーム)」開発|大和ハウス工業株式会社
積水ハウスで活用しているのは、自由設計住宅のプランニングにおける最新のVR技術と3Dモデリング技術です。各施主の要望に応じた設計プランを3次元で立体化し、VRで歩き回れる状態を提示して完成前に詳細な確認が可能になっています。
この技術によって、顧客が実際に居住する際のイメージが掴みやすくなり照明や収納、動線といった細部まで納得した上でプランを選定できる環境が整います。設計者にとっても空間の使い方や家具の配置を検証しながらプランを練り直すことができ、より実用的な設計提案が可能です。
また邸別のモデル作成が自動化されており、従来よりも短期間でVRモデルを作成できるため設計から着工までのリードタイムを短縮する効果も生まれています。
出典参照:最新のVR(バーチャルリアリティ)技術を導入 邸別自由設計のオリジナルプランを360度3D空間体験|積水ハウス株式会社
鹿島建設では老朽化が進む道路橋の床版を効率的に更新するため、3次元モデルの自動生成システムを開発・運用しています。このシステムは点群データやCAD情報を基に、橋梁の床版や構造部材の3Dモデルを自動的に作成する仕組みです。
床版更新工事では既設の寸法と現場条件の正確な把握が求められますが、従来の手法では時間と手間がかかりやすい課題がありました。自動生成システムの導入で設計データの整合性確認や施工手順の検討が短期間で可能となり、計画段階から施工フェーズまでを効率よく進めることが可能です。
さらに3Dモデルには部材ごとの情報や施工履歴が付加されており、将来的な維持管理や点検にも役立つデータベースとしての機能を持たせることもまた可能です。これにより、インフラの長寿命化とメンテナンスの最適化にもつながっています。
出典参照:道路橋の床版更新における設計業務時間を10分の1に3Dモデル自動生成システムを開発|鹿島建設株式会社
建設DXに欠かせない技術である3次元モデルデータですが、導入すれば即座に効果が出るわけではありません。ツールの操作性や既存業務との整合性、人材のスキルレベルといった要素を踏まえ、段階的かつ計画的に導入を進める必要があります。また、データ運用体制の整備やセキュリティ対応も並行して考慮しなければなりません。
ここでは、導入の失敗を避けるために意識しておきたい3つの重要なポイントを紹介します。
3次元モデルは、用途に応じて求められる精度が異なります。施工の手順確認や進捗管理では概略的なモデルでも機能しますが、鉄筋配置や構造解析など設計精度を要する場面ではミリ単位での正確性が求められるのは当然のことです。
誤った判断で過剰に高精度なモデルを作成してしまうと作業コストやデータ容量が増大し、結果的に非効率につながるおそれがあります。まずは導入目的を明確にし、それに応じたモデリングレベル(LOD)の選定が重要です。
またモデリングの粒度をプロジェクト単位で統一しておくことで、データ活用時のトラブルを防ぎやすくなります。設計段階から精度の基準を定めておくと、後工程への影響も最小限に抑えられるでしょう。
3次元モデルデータの活用において、ツール間の互換性は重要です。使用しているCADやBIMソフト、解析ツールが異なるとデータがうまく連携せず、情報の欠落や意図しない変換が発生する場合があります。
例えば設計部門ではAutodesk製品を使用していても、施工管理側では別のプラットフォームを使っているケースがあります。このような状況でスムーズに情報連携を図るには、中間フォーマット(IFCなど)の仕様理解と整備が欠かせません。
さらに、データを受け取る側のツールやPC環境によっては容量オーバーや動作不良が生じる可能性もあるため、モデルを軽量化する工夫も求められます。事前に関係部門と仕様を共有し、互換性の検証を行うことが基本です。
3次元モデルは1つのデータに多様な情報を付与できる点が魅力ですが、その分取り扱いには明確なルールが求められます。データの更新頻度や変更履歴の管理、ファイル命名規則などをあらかじめ決めておかないと混乱の原因となります。
プロジェクトに関わる設計者や施工担当者、管理部門が共通の理解を持ち、誰がいつどの情報を追加・編集したのかを記録する体制が必要です。バージョン管理のルールを設け、共有フォルダやクラウドストレージでの運用ルールも整備しておきましょう。
情報が属人的になると、担当者の異動や業務委託の際にデータの価値が失われてしまいます。組織全体での共有ルールづくりが、3次元モデルの活用を長期的に成功させるカギです。

建設業界ではDXの進展に伴い、3次元モデルデータの役割が日々拡大しています。視覚的な共有性の高さやミスの削減、進捗管理や維持管理への応用など多くのメリットを持つこの技術は建設現場の生産性と品質の向上に寄与しています。
設計・施工・管理といった各工程で活用される場面も増え、メタバースやVRと組み合わせた提案手法やインフラ管理への応用などの先進的な取り組みも進んでいるのが現在の環境です。実際に導入している企業の事例からも、その有用性と将来性が明確に見て取れます。
建設DXを実現する上で、3次元モデルデータの活用は欠かせない要素となりつつあります。自社の業務にどのように取り入れられるかを検討し、今後の戦略に組み込む価値は十分にあるといえるでしょう。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
