建設DXでペーパーレス化は可能?メリットや成功のステップを解説
建設

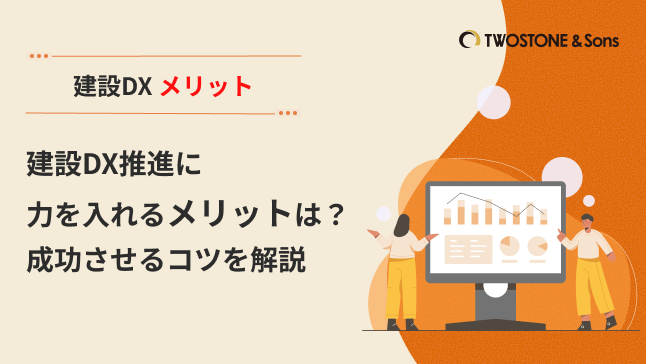
建設業界では、業務の属人化や人手不足、非効率な作業プロセスが深刻な課題となっています。現場ごとにルールや手順が異なり、紙ベースの管理が主流であるため、情報共有や業務の標準化が難しい状況です。こうした構造的な問題に対して注目されているのが、デジタル技術を活用した建設DXの推進です。
建設DXは、業務フローの可視化や自動化、情報の一元管理を通じて、効率性と生産性の向上を目指す取り組みです。
本記事では、建設DXの基本的な考え方に加え、推進によって得られる具体的なメリットや、業界全体でDXが必要とされている社会的背景についても詳しく解説します。さらに、DXを進めるにあたり最初に着手すべきポイントについても紹介します。どのように変革を始めればよいのか悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。

建設DXとは建設現場における業務や情報をデジタル技術で可視化・効率化し、業務プロセス全体を改善する取り組みを指します。ICTやIoT、AI、BIMといった先端技術を活用し、これまでアナログ中心だった作業工程をデジタルに置き換えていきます。
例えば、図面や工程表のデジタル化により設計ミスや情報伝達の遅れを防げるでしょう。またセンサーを用いた重機の稼働管理やドローンによる測量など、現場作業の生産性向上や安全性の強化にもつながります。
これらの取り組みは単なるIT導入にとどまらず、業務そのものの見直しや企業文化の変革にも直結するため、経営層を巻き込んだ全社的な取り組みが必要です。
建設業界では慢性的な人材不足や高齢化が進んでおり、従来のやり方では生産性の維持すら難しい状況です。特に若手人材の確保が難しく、技術の継承が進まないという課題は深刻化しています。
また、現場での情報共有が紙中心であることやシステムが部門ごとに分断されていることも作業の非効率化を引き起こしています。DXの推進が求められているのは、こうした問題を根本的に解決したいという背景があるためです。
さらに国土交通省が主導するi-Constructionの推進により、公共工事を中心にBIMやCIMの導入が加速しています。この動きは民間工事にも波及しており、今後はDX対応が標準的な取り組みになる可能性が高いです。
このような背景を踏まえると、建設DXへの対応を早期に進めることは競争力を維持するためにも必要不可欠といえるでしょう。
建設DXの推進は、業務の自動化や情報の可視化だけでなく、長期的に見て企業体質そのものを強くする施策です。現場の負担軽減や品質の安定、さらには人材の確保や育成にもつながります。単なる効率化にとどまらず、働き方改革や脱属人化、環境対応までカバーできる点が特長です。
ここでは、経営面・現場面の両方で得られる7つの具体的なメリットを取り上げ、建設DXを戦略的に活かすための視点を解説します。
建設業界が抱える深刻な課題の1つが人手不足です。高齢化の進行や若年層の業界離れにより、現場では常に人材が足りない状況が続いています。
そこで有効なのが、デジタル技術の活用です。例えば、ドローンによる測量や遠隔操作型の重機導入によって、現場作業の人数を最小限に抑えることが可能になります。また、ICTやAIを活用した自動化によって、従来は熟練者でなければ対応できなかった作業も少人数で対応できる体制が整います。
人材確保に苦労している企業にとって、DXは現場力を補完する有効な選択肢です。作業の効率化が進むことで限られた人員でより多くの仕事をこなせるようになり、経営面でもプラスに働きます。こうした技術導入は現場の安全性維持にも寄与し、長期的な業務継続に役立つでしょう。
業務が特定の社員に依存している状態、いわゆる属人化は建設業界に多く見られます。ベテランの経験や勘に頼る場面が多いため、退職や異動のたびに業務の質が低下するリスクがあります。そういった状況下でもDX推進により、業務の標準化・マニュアル化が可能です。
例えば、BIMデータを用いた設計・施工情報の可視化やクラウドを使った工程管理により、誰が見ても同じ情報にアクセスできる環境が整います。
属人性の排除により、チーム全体の再現性や作業品質の安定化が期待できます。加えて新人教育の負担軽減にもつながり、長期的な人材育成が効率よく進む環境が整備されることも利点です。こうした取り組みは組織全体の強化に寄与し、経営の安定化にも役立ちます。
建設現場では、安全管理と品質管理の徹底が求められます。DXを活用すればこれまで目視で確認していた情報やチェック項目を、センサーやAIによって自動的に記録・検知する仕組みを導入可能です。
例えば、ウェアラブル端末による作業員のバイタルチェックや現場カメラによるリアルタイム映像の共有により、危険予兆を早期に把握できるようになります。また設計段階での3次元モデルの活用により、設計ミスの削減や現場での修正回数も低減可能です。
安全と品質の両面で高いレベルを維持しやすくなる点は、DX推進の魅力といえます。リスク管理が強化されることで労働災害の減少につながり、保険料削減や社会的信用の向上にも寄与します。結果として生産性向上に直結する、安心して働ける職場環境の実現につながるでしょう。
建設DXは業務の無駄を省き、作業全体の生産性を向上させます。紙ベースの図面や資料を電子化するだけでも情報の検索や共有がスムーズになり、移動や確認にかかる時間を削減できます。
また、AIによる工程の最適化提案やBIMと連動した自動施工計画の作成により、プロジェクト全体の工期短縮が実現可能です。現場作業の効率だけでなく、設計・管理・発注などのバックオフィス業務も含めて広範囲にわたる業務改善が可能になります。こうした取り組みは、短期的な業績改善にもつながります。
さらにリアルタイムでの進捗把握や問題発見が可能になり、柔軟な対応がしやすくなるため納期遅延のリスク軽減も可能です。これによってコスト管理がしやすくなり、顧客満足度の向上にもつながるでしょう。
建設DX推進には初期投資が必要になるものの、中長期的にはコスト削減の効果が期待できます。
まず、資材の発注ミスや過剰在庫の発生を防ぐことで無駄な費用を抑えられます。資材管理をデジタル化すれば必要な分だけを正確に発注でき、過剰在庫や不足による再発注のリスク軽減が可能です。また作業員の配置計画や重機の稼働状況のリアルタイムでの把握により、人件費や機材使用料を効率的に調整可能です。
さらに施工ミスを減らし、手戻り工事を回避できるため無駄な作業にかかるコストを抑制します。正確なデータに基づく計画はリスクも最小限にし、全体の経費節減に寄与します。結果として、投資した費用以上の効果が得られることが多いです。
DXにより設計の意図や仕上がりを3次元モデルで視覚化できるため、顧客とのコミュニケーションが円滑になります。設計段階から立体的な完成予想図を示せることでイメージのズレが減り、手戻りの防止に役立ちます。
施工中の進捗や工程の変更点もリアルタイムに共有可能です。これにより施主が現場の状況を正確に把握でき、安心感が増します。透明性の高い情報共有は信頼関係の構築に寄与し、顧客満足度の向上につながるでしょう。
満足度が高まれば紹介案件やリピート受注が増加し、企業の安定的な成長に結びつきます。顧客の期待に応えられる体制づくりは、長期的な競争力の強化にとっても重要です。
積極的に建設DXを推進する企業は業界内外で評価が高まります。特に公共工事や大手ゼネコンの案件では、技術力やデジタル対応力が取引の選定基準になることが増加中です。
環境配慮や省人化への対応は社会的な要請に応えるものであり、サステナビリティやESGの視点からも注目されています。これらの取り組みは企業の社会的評価を高め、ブランドイメージ向上にもつながるでしょう。
さらに、DXの推進は社内の働き方改革や人材の定着にも効果を発揮します。効率的で働きやすい環境は社員の満足度を上げ、離職率の低減につながるため企業の持続的成長を支える重要な要素です。

建設DXは強力な変革手段ですが、導入初期には負担やリスクも存在します。例えば、高額な初期投資、人材の確保や育成が進まない問題、現場との意識のズレなどが挙げられます。また、既存の業務フローや文化との摩擦によって、定着までに時間がかかるケースも少なくありません。
ここでは、こうしたデメリットの具体例を挙げながら、それぞれがなぜ起こるのか、どのように乗り越えるべきかを整理して紹介します。
建設DXを推進するためには、まずICT機器や専用ソフトウェアの導入が必要です。これには数百万円から場合によっては数千万円規模の初期投資がかかるケースもあります。特に現場の規模が大きい場合や複数の現場で同時に導入する際、費用が膨らみやすいです。
こうした初期投資は設備購入やシステム構築に加え、通信インフラの整備やオペレーターや管理者の教育費用も含まれます。中小規模の企業にとっては負担が大きく、経営資源の割り振りが課題になるでしょう。
しかし、推進の規模や段階を調整しながら段階的に拡大する方法もあります。ROI(投資対効果)を正確に見極めることが、無理なく推進を進めるカギです。
デジタル技術を使いこなすためには、社員のスキル向上が欠かせません。しかし建設業界は従来の経験や勘を重視する文化が根強く、ITスキルを持つ人材が不足している場合も多いです。
また、新しいシステムや機器に対して抵抗感を示す社員も存在します。こうした状況では単に技術を導入するだけでなく、教育体制の整備や人材育成の計画が重要になります。
研修やOJTを通じてデジタルリテラシーを高めるとともに、社内での成功事例を積み重ねることで社員の理解や協力を得やすくなるでしょう。
DXはあくまで手段であり、単に最新技術を導入しただけでは期待される効果を得にくいのが現実です。業務プロセスの見直しや組織文化の改革を伴わなければ、現場の混乱や業務の非効率化を招く可能性があります。
例えば新しい管理システムが現場の作業フローに合わない場合、かえって業務が煩雑になったり、トラブルが増えたりします。導入前に現状分析を行い、課題を明確にした上で最適なソリューションを選択しなければなりません。
また関係者間の連携やコミュニケーションも重要であり、単独で技術だけに頼るのではなく現場運営全体の改善策を併せて検討しましょう。
建設現場は多様であり、場所や作業内容によってはデジタル化や自動化が難しいケースも存在します。例えば狭小地や急斜面、悪天候の多い地域では、ICT機器の設置や通信環境の確保が難しくなります。
また小規模な工事や短期間のプロジェクトでは、推進に伴うコストや労力に見合わない場合もあることでしょう。このような環境ではDXの効果を十分に活かしにくいため、推進の可否や範囲を慎重に判断する必要があります。
こうした場合は段階的な適用範囲の広域化や部分的なデジタル技術の活用など、柔軟な対応が求められます。
デジタル化が進むと、サイバー攻撃や情報漏えいのリスクの増加についても無視できない問題です。建設DXでは多くの情報がクラウドやネットワークを通じて共有されるため、適切なセキュリティ対策を講じなければ重大なトラブルに発展しかねません。
特に設計データや施工計画は企業の重要な資産であり、第三者に不正アクセスされた場合は工期遅延や信用失墜につながります。パスワード管理やアクセス権限の厳格化、通信の暗号化、定期的なセキュリティ教育が必要でしょう。
さらに、事故発生時の対応手順やバックアップ体制も事前に整えておく必要があります。
建設DXに関連する技術は日々進化しています。新しいソフトウェアや機器が短期間で登場し、導入したばかりの技術が数年後には陳腐化してしまうケースも珍しくありません。
このため過度なカスタマイズや特定技術への依存は避け、拡張性や互換性の高いシステムの選択が重要です。定期的な技術見直しや更新計画も欠かせません。
また最新技術を追いかけすぎて現場の混乱を招かないよう、実用性やコスト面を踏まえたバランスの良い導入戦略が求められます。
せっかく建設DXを推進しても、準備不足や推進体制の欠如により期待した成果が得られないことがあります。重要なのは、単にツールを導入するだけでなく、現場や経営層を巻き込みながら、段階的かつ計画的に進める姿勢です。
ここでは、DXの利点を本当に活かすために意識したい4つのヒントを解説します。組織の合意形成、効果測定、継続的な改善体制など、実務に役立つ視点から詳しくみていきましょう。
建設現場の作業とIT部門の技術支援は密接に関係しています。現場のニーズや課題を正確に把握し、それに合ったシステムやツールを開発・導入しなければ効果的なDX推進は難しいです。
現場担当者とIT担当者が連携してコミュニケーションを取り合うことで、実際の運用で発生する問題点を迅速に解消できます。加えて、双方の意見を取り入れることで現場にフィットしたシステム設計が可能になり、導入後の現場混乱を防止できるでしょう。
この連携強化には、定期的な打ち合わせやワークショップの開催、現場視察を取り入れることが効果的です。IT担当者による現場状況の直接理解によって、より実用的な改善策を提案できます。
このように、連携を強化するには定期的なミーティングや情報共有の場を設けることが効果的です。双方が理解を深め合うことで、現場に根ざしたDX推進が可能になります。
建設DXの推進は、一度に全体を変革するのではなく段階的に進める方法が効果的です。これをスモールスタートと呼び、小規模なプロジェクトや部分的な機能の導入から始めることでリスクを抑えつつ運用の感触を掴めます。
大規模な変革は現場の混乱や抵抗を招きやすく、失敗のリスクも高まります。スモールスタートで実証実験的に進めることで、現場の実態に即した課題発見や運用上の工夫の発見が可能です。
この段階的な推進では成果が確認できた段階で範囲の広域化、新たな機能の追加といった拡張も行いやすくなります。結果として無理なくDXを根付かせることができ、社内の理解も深まるでしょう。
こうした段階的な進め方の採用で、現場の声を反映しながら柔軟にDXを推進しやすくなり、結果的に成功率が高まります。
建設DXの効果を十分に引き出すためには技術的な導入だけでなく、社員の意識改革も欠かせません。新しいシステムやツールを使いこなすスキルの習得はもちろん、DXに対する前向きな姿勢や理解が必要です。
社員教育は単なる操作方法の研修にとどまらず、DXがもたらすメリットや業務効率化の意義を共有する場を設けることが大切です。目的や効果が明確になることで、社員のモチベーションが上がり推進後の活用度も高まります。
さらにマインドセットの変革には、トップマネジメントのリーダーシップも不可欠です。経営層がDXの必要性を強調し、全社的な方向性を示すことで現場の理解と協力が促されます。
変化に対して抵抗感を持つ社員も存在するため、現場の声を丁寧に聞き入れて不安を和らげるコミュニケーションも重要です。疑問や問題点が解消されれば、自然とDX推進への参加意欲が高まるでしょう。
建設DXでは大量のデータが生成されますが、それらを単に蓄積するだけでは価値を発揮しません。データ分析や活用を通じて業務改善や経営判断に結び付ける仕組みが必要です。
まず、データの収集・管理・分析の担当部署や専門人材を明確にし、責任の所在をはっきりさせます。次に、現場の意思決定に役立つ形で情報を提供するためにダッシュボードやBIツールの導入も検討しましょう。
データを活用したPDCAサイクルを回すことで、施工品質の向上やコスト削減、安全管理の強化が進みます。さらに長期的には、デジタルツインの構築やAI活用など高度な技術導入の土台にもつなげることが可能です。
建設DXの価値は、実際の推進事例に触れることでより明確になります。ある企業では、MR技術を用いた施工支援で作業時間の短縮を実現し、別の企業ではクラウド連携によって拠点間の情報共有を効率化しました。また、高齢作業員の負担を軽減する技術導入で、定着率向上に成功した例もあります。
こうした実践例から、DXを効果的に根づかせる戦略とそれがどのような成果につながったのかを具体的に紹介していきます。
鹿島建設はトンネル工事の現場で、3Dレーザスキャナを導入しました。トンネルの掘削面である切羽の状態を正確に把握するため3次元の点群データを取得し、その解析にAIを活用しています。
このシステムでは切羽の変形や亀裂の発生を自動的に検知し、従来は熟練作業者の経験に頼っていた判定を効率化しました。これにより安全管理の精度が向上し、危険箇所の早期発見や対策が可能になっています。
さらに切羽のデータをリアルタイムで共有できるため、現場のリスク情報が即座に関係者に伝わり迅速な対応が実現しています。この取り組みは建設DXによる現場の安全強化の代表例です。
出典参照:ブレーカに搭載した3Dレーザスキャナで切羽のアタリ判定を自動化 |鹿島建設株式会社
飯島建設はデジタル技術の活用範囲を広げるため、本社管理本部に「PRデジタルマーケティング室」を設置しました。従来の建設業務だけでなく、企業のブランディングや情報発信にもDXを推進しています。
この部署で行われているのは、SNSやWebサイトを活用した広報活動に加え、デジタルツールで顧客データの管理や分析です。これにより顧客ニーズをより正確に把握し、サービスの質向上につなげています。
また内部の情報共有や業務効率化にも寄与しており、DXを経営の全体戦略として取り入れる姿勢が評価されています。現場だけでなく、経営層でもDXのメリットを追求した好例といえるでしょう。
出典参照:期納め |飯島建設株式会社
大林組は工事現場の車両管理を効率化するため、「FUTRAL」というシステムを導入しました。このシステムはGPSやセンサーを利用して、車両の位置や稼働状況をリアルタイムで把握します。
「FUTRAL」により現場車両の運用効率が改善し、無駄な待機時間や燃料消費が削減されました。管理者は遠隔から複数の現場をモニターできるため、迅速な指示や調整が可能です。
加えて安全運転の促進や車両のメンテナンス計画にも役立てており、労働安全とコスト管理の両面でメリットを享受しています。この事例はIoT技術を活用した建設DXの先進的な取り組みです。

建設DXは単なる技術導入にとどまらず、現場の安全性向上や作業効率の改善、経営戦略の強化など多岐にわたるメリットをもたらします。鹿島建設の切羽判定自動化や大林組の車両管理システム、飯島建設のデジタルマーケティング活用など各社が独自の視点でDXを推進し成果を上げています。
これらの成功事例に共通するのは現場の具体的な課題に即した技術選定と運用体制の構築、そして現場と管理部門の連携を重視している点です。単に最新技術を取り入れるだけではなく、実際の業務フローに馴染ませ、継続的に改善を続けることが重要だとわかります。
建設DXのメリットを最大限に活かすにはこうした成功企業の取り組みを参考にし、自社の環境や目標に合わせた最適な戦略を模索しましょう。効果的なDX推進は企業の競争力強化につながり、未来の建設現場を支える力となります。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
