建設DXでペーパーレス化は可能?メリットや成功のステップを解説
建設

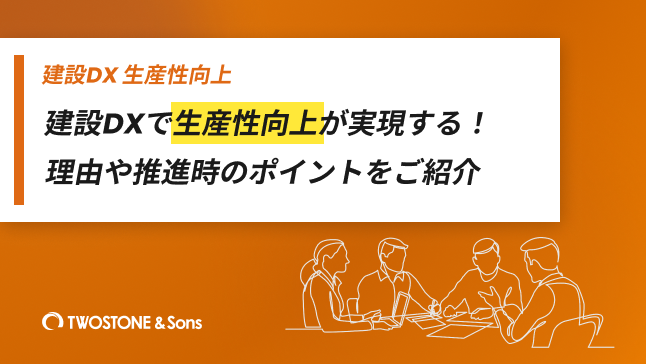
建設業界では長年にわたり、人手や経験に頼った現場作業が中心となっており、生産性の向上が大きな課題となっています。特に人手不足や工期短縮の要請が強まる中、建設業におけるDXの推進が急務となっている状況です。
建設DXとは、デジタル技術を活用して業務の流れを見直し、効率化や品質の向上を目指す取り組みです。これによって現場の生産性だけでなく、安全性も高めることができ、関係者間の情報共有や連携も円滑になります。
本記事では、建設DXが具体的にどのように生産性を改善するのかを詳しく解説し、その成功のポイントについても触れていきます。建設DXの推進に関心のある方は、ぜひ最後までお読みいただき、現場改革に役立ててください。

建設DXは、単なる業務のデジタル化にとどまりません。以下の複数の視点から、現場の働き方そのものを改革するアプローチです。
技術と運用のバランスを取りながら現場の課題を解決する仕組みを構築することで、従来の方法では得られなかった高い生産性が実現できます。ここでは、建設DXが生産性向上に寄与する5つの理由を取り上げ、具体的な効果を1つずつ紹介します。
建設現場での単純作業や繰り返し作業は、自動化によって効率化されます。例えば3次元レーザースキャナやドローンを使った測量では、従来の人力調査に比べて短時間で正確なデータ取得が可能です。
さらに、自動化技術は現場の安全性向上にも貢献します。人が入りづらい危険区域や高所作業でも、機械やロボットが代わりに作業を進めるため事故リスクの抑制が可能です。
また、ロボットや遠隔操作建機の導入も省人化に寄与します。これによって危険な作業の人員削減や疲労軽減が実現し、現場全体の作業効率が向上します。人手に頼らない作業が増えると人的ミスの減少や安全性の向上にもつながり、結果として生産性の上昇が可能です。
建設現場では設計図や工程表、作業指示書など多くの情報が飛び交います。これらがバラバラに管理されていると情報の食い違いや伝達漏れが発生し、トラブルや手戻りの原因になります。
こうした課題を解消するために、建設DXではクラウド技術を活用した情報の一元管理が可能です。現場の作業員から設計者、管理者までが同じデータにアクセスできる体制は意思疎通をスムーズにします。
全関係者がリアルタイムに同じデータを共有できるため、コミュニケーションの無駄を減らして誤解を防げるでしょう。この情報共有の透明性は現場だけでなく設計事務所や管理部門とも連携しやすくし、スムーズな意思決定と迅速な対応を促します。
工期の遅れや余剰作業は建設現場の生産性低下の原因の1つです。建設DXではセンサーや3次元モデルを用いて工程や進捗を可視化し、現場の状況をリアルタイムに把握します。
この「見える化」によって現場の全員が進捗状況を正確に理解しやすくなり、遅延が発生した場合も迅速に原因を分析し対処することが可能です。工程の遅れをいち早く察知できることが、作業の効率化につながります。
見える化によって遅延や手戻りを早期に発見し、対策を迅速に打てます。これにより工期の短縮とコスト削減が期待でき、効率的な作業計画の立案が可能です。また過去のデータ蓄積による分析で類似現場での問題点を事前に予測し、事前対応の精度も上がります。
建設現場での品質不良や安全事故は工程の遅延や修正作業を招くだけでなく、作業員の怪我や命に関わる重大な問題にもつながります。そのため、品質管理と安全対策は生産性向上の根幹を成す要素です。建設DXの推進によって最新の検査技術や監視システムを活用でき、これまで人の目や経験に頼っていた作業をデジタル化して効率化します。
例えば、AIによる画像解析は従来見落とされがちだった施工ミスや欠陥を高精度で検知し、早期対応を促します。またIoTセンサーによる安全ルールの監視では、作業者の動きや環境状況をリアルタイムで把握し、危険な行動を未然に防止することが可能です。
こうした技術の活用は、トラブルや事故の発生頻度を抑え、無駄な再作業や工期の延長を防ぐため生産性に直結するような成果を生み出します。
建設業界では慢性的な人手不足に加え、若手や女性の参入促進が求められています。こうした背景の中で建設DXは遠隔操作技術やVR・ARを用いた実践的な教育プログラムを提供し、多様な人材の育成を支援します。これによって、地理的制約や経験の有無に関わらず、スムーズな技術習得が可能です。
具体的には、VRを活用した仮想現場での訓練は初心者でも安全にさまざまな作業を体験できる環境を整え、リアルな現場に即した技術習得を促進します。遠隔操作機器の導入は身体的な負担やリスクの高い作業を支援し、特に女性や高齢者、身体にハンディキャップがある人でも活躍できる可能性を広げます。
建設DXの推進において重要なのは、単にクラウドやAIなどの先端技術を導入するだけで満足せず、自社の業務フローや人材構成、課題の所在を正しく捉えた上で最適な活用方法を設計する点にあります。成功している企業の多くは、現場作業員の声を丁寧に吸い上げ、段階的にツールを導入しながら、業務に定着させる工夫を重ねてきました。
ここでは、現場の理解を起点にした生産性向上のための実践的なポイントを解説します。
建設現場では、さまざまな問題や非効率が日々発生しています。こうした課題を明確に抽出し、優先順位をつけて対応する姿勢がまず重要です。
単純にITツールを導入しても現場が抱える具体的な課題を解決しなければ、効果は限定的です。例えば進捗遅延や情報共有不足、手戻り作業の頻発といった問題に対してDXの適用範囲と手法を決定する必要があります。
課題を起点に据えることで目的がはっきりし、現場の納得感も得やすくなります。結果として現場のモチベーションも維持しやすく、生産性改善の効果も現れやすくなるでしょう。
建設DXは大規模な改革に見えますが、それは初めから全社的な展開を想定しているためであり、実際にそのような適用はリスクを伴います。まずは小規模な現場や限定した工程からスタートし、実践的な運用を通じて改善点を見つけるのが効果的です。
スモールスタートのメリットは初期投資や人的リソースを抑えながら、失敗を小さく収められる点にあります。また現場のフィードバックを反映しながら柔軟に計画を修正し、最適化できるのも強みです。この方法は、中小建設企業やサブコンでも導入が可能です。
小さな成功体験を積み重ねることで社内の理解と協力を得やすくし、段階的にスケールアップを目指しましょう。
DXはIT部門だけの取り組みではありません。現場が主役となって主体的に推進し、改善活動に取り組む姿勢が不可欠です。現場の声や実務者の知見を反映しないDXは、形骸化しやすい傾向にあります。
現場主導の推進を実現するためには、現場担当者がDX施策の目的やメリットを理解し、自分ごととして捉える必要があります。現場管理者やリーダー層が積極的に関与し、現場作業者とのコミュニケーションも密に行いましょう。
こうした体制が構築されれば、現場で発生した課題をスピーディに改善し、DXを現場の日常業務に根付かせられます。
建設DX推進においてまず重要なのは、現状の業務フローを正確に把握し、デジタル対応へと見直すことです。多くの建設現場では、手作業や紙ベースの管理が根強く残っており、これが作業効率や情報共有の障壁となっています。業務プロセスを細かく分析し、どの部分をITツールやクラウドサービスで自動化・効率化できるかを検討しましょう。
例えば、図面管理や工程管理、資材発注などをデジタル化することで、ミスや情報の遅延を減らせます。さらに、デジタルツールの導入は単なるシステム変更ではなく、業務の流れ自体を変えるチャンスとして捉え、効果的な設計を行うことが求められます。これにより、全体の作業時間短縮や現場の透明性向上が期待でき、結果として生産性の向上につながるでしょう。
建設DXを成功させるためには、単にシステムを導入するだけでなく、人材教育とマインドセット改革を同時に進めることが不可欠です。従来のやり方に慣れている作業員や管理者にとって、新しい技術やツールは抵抗感を生む場合があります。そのため、デジタルツールの操作方法だけでなく、なぜ建設DXが必要なのか、どのようなメリットがあるのかを丁寧に説明し、現場全体の意識改革を促しましょう。
教育プログラムは段階的に進め、実務に即したトレーニングや成功事例の共有を通じて従業員の自信と理解を深めることが大切です。また現場の声を取り入れ、現場目線で改善を図る姿勢が、マインドセットの変化を促進します。こうした教育と意識改革の両輪が、持続的なDX推進と生産性向上の基盤になります。
建設DXの真価は、現場で発生する膨大なデータを効果的に活用する仕組みづくりです。現場からの進捗情報、資材使用状況、品質チェックの結果など多様なデータを一元的に収集して見える化することで、管理者はリアルタイムで状況把握が可能になります。これにより問題の早期発見や迅速な意思決定が実現し、工期遅延やコスト超過のリスクを低減できます。
データ活用のためには、データベースの構築や分析ツールの導入だけでなく、情報の標準化やフォーマット統一も必要です。また、現場のスタッフが簡単にデータ入力できる環境を整えることも重要です。こうした環境整備と運用ルールの策定により、蓄積されたデータが有効な資産となり、継続的な業務改善や未来予測にも役立つでしょう。
建設DXの推進は一過性のプロジェクトではなく、継続的な改善活動が不可欠です。そのためには、ITベンダーやコンサルタントなどのパートナー企業と強固な協力体制を築くことが重要になります。建設現場の専門知識とデジタル技術の両面からの支援を受けながら、自社の課題に合ったソリューションを継続的に検証・改善していきましょう。
パートナー企業との連携により、新たな技術の導入や運用上のトラブル対応、最新の業界動向の情報共有がスムーズになります。また、現場の声をパートナーにフィードバックし、システムのカスタマイズやアップデートを進めることで、現場に最適化されたDX推進が実現します。こうした協働を通じて、建設現場の効率化と安全性向上を持続的に図ることが可能です。

実際に建設DXを推進して生産性の向上に成功した企業は、現場ごとの課題を洗い出し、それに対応する形でDX施策を計画的に実施しています。例えば、現場管理をデジタルで一元化した結果、作業時間の短縮や無駄の削減に成功した企業もあれば、設計と施工のデータ連携により手戻りを減らした企業も存在します。
ここでは、そうした企業がどのようなDXツールや体制を用いて、どの程度の効果を上げたかを事例として紹介し、自社への推進を検討する上で参考になる視点を確認しましょう。
株式会社大林組は建設現場の資材搬送の効率化に注目し、自動搬送システムの開発に取り組みました。建設現場では資材の搬入や移動は多くの人手と時間を要するため、作業全体のボトルネックになりやすい工程です。
そこで大林組は、無人搬送車(AGV)や自律移動ロボットを活用したシステムを現場に導入しました。資材の移動ルートや作業状況をリアルタイムで管理し、搬送効率を高める仕組みを構築しました。
この自動搬送システムにより資材の搬送作業にかかる時間を削減すると同時に、搬送作業に伴う人員の安全リスクも低減できています。さらに現場の人手不足にも対応しやすくなり、現場全体の生産性アップに寄与しています。
出典参照:新築建物の工事現場における生産性向上に向けて自動搬送システムの開発に着手しました|株式会社大林組
鹿島建設は建設現場における生産プロセスの革新を目指し、「鹿島スマート生産」というプロジェクトを立ち上げました。この取り組みではBIM(ビルディングインフォメーションモデリング)を中心に据えて、設計から施工、維持管理までをデジタルで一貫して管理します。
特に3次元モデルデータを活用し、設計の段階で施工上の問題を早期発見する仕組みを整えました。施工現場ではロボット技術やドローンによる作業支援を導入し、精度の高い施工と安全性の向上を実現しました。
また作業員の動線管理や機械の稼働状況のリアルタイムな把握により、現場の無駄を排除しています。これにより作業効率の向上だけでなく、品質の安定化にも成功しています。鹿島建設の事例は、最新技術と現場力の融合が生産性向上に直結する好例といえるでしょう。
出典参照:変革を起こす鹿島 生産性向上に向けた最新技術の現在地 | 鹿島建設株式会社
戸田建設は複数の現場で発生する多様なデータの集約と連携を重視し、生産性向上を図っています。現場で扱われる図面や進捗情報、品質検査結果などのデータをクラウド上に集約し、関係者がリアルタイムで共有できる環境を整備しました。
この環境によって施工管理者や設計担当者が迅速に情報を確認できるようになり、コミュニケーションのロスや手戻り作業を減らすことができました。また蓄積されたデータを分析し、工程の最適化や労務管理の改善にもつなげています。
さらに戸田建設は、スマートデバイスやウェアラブル端末を活用し、現場作業者の安全管理や作業効率のモニタリングも強化しています。データを活用した総合的な現場管理により、品質と安全性の向上とともに生産性アップを実現しました。
出典参照:データ集約・連携・利活用による建設現場の生産性向上|戸田建設株式会社
建設DXを推進する際には、事前の準備と段階的な運用が重要です。現場に馴染まないままツールを導入してしまうと、かえって混乱を招き、かかる時間やコストが増える恐れがあります。また、操作方法が複雑なツールは現場担当者の負担となり、生産性の向上どころか定着すら困難になりかねません
ここでは、そうした事態を避けるために事前に確認すべきポイントや、導入後に起こりやすい問題とその対処法を詳しくみていきましょう。
建設現場は多様な業務が複雑に絡み合っているため、導入するツールやシステムは現場の実態に適合している必要があります。最新技術であっても現場の作業フローや環境に合わなければ使い勝手が悪く、浸透しにくくなるのは想像に難くないでしょう。
例えば土木工事現場と建築現場では、必要とされるデータの種類や利用頻度が異なります。また屋外での使用が多い現場では、耐久性や操作性も重要な選定基準です。したがって現場の担当者や作業員の声を取り入れながら、現場にマッチしたツールを選ぶことが大切です。
建設業界は高齢化が進み、デジタル技術に不慣れな作業員も少なくありません。こうしたデジタルリテラシーの格差が大きいと新しいツールの導入が現場の混乱を招き、逆に生産性を下げる場合もあります。
そのためDX推進にあたっては、利用者のレベルに応じた教育やサポートが不可欠です。研修やマニュアルの整備だけでなく、現場でのフォローアップ体制を充実させることが効果的でしょう。現場の声を吸い上げ、使いにくい点や改善要求を反映していく仕組みが重要となります。
建設DXは単に新技術を導入するだけでは成功しません。従来の業務フローやシステムとの連携を意識し、スムーズに移行できる計画が欠かせません。既存業務を無視した導入は、かえって混乱や二重作業を引き起こすリスクが高まります。
例えば紙の図面や帳票管理からデジタル化へ切り替える場合、段階的に移行するロードマップを作成します。移行期間中は旧システムとのデータ互換性を確保し、業務が滞らないように配慮する必要があるでしょう。
移行プロセスではトラブル対応や操作サポートの体制も整えておくことで、現場の混乱を最小限に抑えられます。こうした準備が結果としてDXの効果を最大化し、生産性向上を実現します。

建設DXは単なるデジタル化を超え、業務全体の効率化と安全性向上を実現する重要な手段です。しかし、生産性を高めるためには現場の実態に即したツール選びが不可欠であり、利用者のデジタルリテラシーにも十分な配慮が求められます。
さらに、既存の業務との統合やシステム移行のプロセスを計画的に進めることで、DXを現場にスムーズに浸透させられます。これらのポイントを押さえた上で、段階的かつ現場主導の取り組みを進めることが建設DXの真価を引き出す鍵です。こうした方法により、現場の作業効率はもちろん、安全管理も強化され、持続可能な現場運営が可能になるでしょう。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
