建設DXでペーパーレス化は可能?メリットや成功のステップを解説
建設

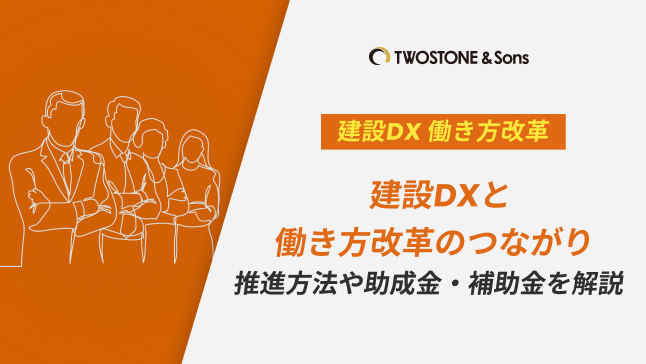
建設業界は長年にわたって、人手不足や長時間労働といった慢性的な課題を抱えてきました。特に現場作業の多くは属人化し、紙ベースのアナログ管理や複雑な報告体制が業務の非効率を生み出しています。これにより、若手の入職者が定着しにくくなり、高齢化が進む現場では業務負担が一層重くなっています。
近年、そうした課題に対処するための有効なアプローチとして注目を集めているのが、建設DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進です。建設DXは、ICTやIoT、BIMといった最新技術を活用して現場業務を効率化し、データの一元管理や遠隔操作、工程管理の見える化などを実現します。
本記事では建設DXと働き方改革の関係性を明らかにし、建設業界が直面する課題とその解決に向けたポイントを解説します。この記事を読むと、建設DXを活用した働き方改革のメリットや具体的な進め方が理解できるでしょう。

建設DXとは建設現場でのデジタル技術活用を通じ、業務プロセスの効率化や品質向上を図る取り組みです。これによって手作業の自動化や情報共有の最適化が可能になり、現場の負担を軽減します。
働き方改革では労働時間の短縮や柔軟な働き方、作業の安全性向上が求められています。建設DXはデジタル技術を活用して作業の効率化やミスの低減、安全管理強化の実現によってこれらの目標と直接つなげられるでしょう。
さらにDXは単なる効率化に留まらず、多様な人材の活躍を促す基盤ともなります。人材不足の解消や職場環境の改善に寄与し、持続可能な建設業界の形成に役立つのがこうした新しい働き方です。
建設業界は他の産業に比べて、長時間労働や人手不足、労働災害のリスクといった独自の課題を多く抱えています。これらの課題は現場の生産性や安全性、社員の健康に直結しており、社会全体の働き方改革の波に対応する必要が出てきました。さらに、労働力の高齢化が進み、持続可能な働き方を確立することが急務となっています。
これらの背景から、業界全体で働き方改革を進める意義が高まっています。
建設業界では深刻な人材不足が続いています。若い世代の建設業離れや高齢化が進み、労働力の確保が難しい状況です。このままでは現場の担い手が減り、生産性低下や工期遅延のリスクの増加が懸念されます。
働き方改革は、多様な人材が無理なく働ける環境づくりに注力します。例えば柔軟な勤務時間や安全配慮、スキルに応じた作業割り当てなどさまざまな工夫が必要です。建設DXの活用で遠隔作業や自動化を進めれば、限られた人員でも効率的に現場運営が可能となります。
そのため人材不足の解消には、技術と働き方改革の両面からアプローチを行う必要があります。
建設業界では労働時間の長さが大きな問題となっています。過酷な作業環境や突発的なトラブル対応が原因で、残業や休日出勤が常態化しやすい現場も多いです。
こうした長時間労働は労働者の健康リスクを高め、事故やミスの発生にもつながります。結果的に現場の安全性や品質にも悪影響を与え、生産性低下の負の連鎖を生んでしまいます。
働き方改革で整備されるのは労働時間管理の強化や適切な休息確保、効率的な作業の推進を通じた健康的な労働環境です。建設DXは工事の自動化や進捗管理の「見える化」で作業効率化に貢献し、長時間労働の削減に役立ちます。
建設業は激しい競争環境にあり、持続的な成長が求められています。新規案件の獲得やコスト管理、品質向上を実現しなければ企業の競争力の低下は避けられません。
働き方改革は働く環境の改善により従業員のモチベーションや定着率向上を促進し、企業全体のパフォーマンスを高めます。これと並行して建設DXを取り入れ、業務効率や品質の向上を図ることでより強固な競争力が構築できるでしょう。
デジタル技術は計画の精度向上やリスク管理の効率化も可能にし、長期的な事業運営の安定にも寄与します。両者の融合が、変化の激しい建設業界での成長を支えるカギとなるでしょう。
建設DXの推進は単なるIT導入だけでなく、業務プロセスの根本的な見直しを促進し、企業文化の変革に寄与します。特に働き方改革を目指す場合、技術の活用だけではなく、組織体制や作業手順の最適化が欠かせません。
ここで紹介する5つの施策は、多くの建設企業で効果を実証しており、現場の効率化や労働負荷の軽減、情報共有の促進に役立っています。これらの取り組みは働く環境を改善し、持続可能な成長にもつながります。
業務のデジタル化は建設DX推進の基本であり、働き方改革の第一歩です。従来の紙ベースや手作業による情報管理はミスや作業の重複が発生しやすく、効率が悪いだけでなくコミュニケーションロスの原因にもなります。
クラウドシステムを導入すれば、現場とオフィス間での情報共有がリアルタイムで可能になります。例えば図面や進捗データをクラウドに保存してどこからでもアクセスできる環境を整えれば、迅速な確認や承認作業につながるでしょう。
またモバイル端末を活用した現場での入力や報告は、データの正確性と即時性を高めます。これにより作業時間の短縮や移動の削減が期待でき、従業員の負担軽減にもつながるでしょう。
こうしたデジタル化は業務の透明性も向上させ、管理者が適切な指示や調整を行いやすくします。結果として作業の重複や遅延の削減に貢献し、現場全体の効率化と働き方改革を後押しします。
建設業界でその必要性の高まりを見せているのは熟練技術者の高齢化による、その技術や知識の若手への継承です。しかし従来の口頭伝達や現場依存の方法では技術の伝達にばらつきが生じやすく、継承が遅れる恐れがあります。
ここで役立つのがDX技術の活用です。例えば動画やVR技術で施工手順を記録し、遠隔地にいる若手社員が何度も学べる環境を構築できます。デジタルマニュアルやオンライン研修も、時間や場所に縛られずに技術継承を促進します。
ナレッジ共有のプラットフォームを整備すれば、成功事例や失敗事例の情報も全社で蓄積・活用でき、業務改善に役立てられるでしょう。こうした取り組みは属人化の解消と人材育成の効率化を実現し、現場の生産性向上と働き方改革に貢献します。
長時間労働の是正と人手不足の対策は建設業界の働き方改革において重要なテーマです。建設DXは作業の自動化や省力化を通じ、これらの課題解決に役立ちます。
具体的にはドローンや3Dレーザースキャナによる現場測量の自動化やロボットによる資材搬送、AIを活用した工程管理の効率化などが挙げられます。これらの技術によって人手を削減しつつ、正確かつ迅速な作業ができるでしょう。
またペーパーレス化や電子契約の導入も事務作業の短縮に効果的です。これにより現場の従業員は本来の作業に集中できるため、無駄な残業や休日出勤の削減に直結します。
このように時短・省人化の取り組みは、労働環境の改善にとどまらず、全体の生産性向上を支えるための重要な要素となります。
働き方改革を成功させるためには、評価制度の見直しも欠かせません。従来の時間や成果主義に偏った評価では、多様な働き方や新しい業務スタイルが評価されにくいことがあります。
建設DXの推進に伴いプロセス改善やチーム連携、デジタル技術の活用度合いなど成果以外の要素も評価に組み込む必要があります。これにより社員のモチベーションを向上させ、新しい働き方への適応を促進できるでしょう。
また柔軟な勤務形態やリモートワークを取り入れた場合の評価基準も整備し、制度の公平性と透明性を確保しましょう。こうした仕組みづくりは、従業員の定着率向上や多様な人材の活躍推進につながります。
評価制度の改善は組織文化の変革にも影響を与え、建設DXと働き方改革の根幹を支える役割を果たします。
働き方改革の最終目的は、従業員が仕事と私生活を両立できる環境の整備です。建設業界は長時間労働や突発的な作業対応が多いことから、ワークライフバランスの確保が難しい場合が多いです。
建設DXの推進によって作業効率が上がり、労働時間の削減が見込めますがこれだけでは不十分でしょう。勤務時間の柔軟化や有給取得の促進、育児・介護休暇の充実など制度面の整備も重要です。
またメンタルヘルスケアや健康管理の支援策を取り入れることで、従業員の心身の健康を守れます。これらの制度が整えば従業員満足度が向上し、結果的に職場の生産性や組織の持続性を高めることに役立ちます。
建設DXの技術的側面と制度面の両輪での働き方改革推進が、真の効果をもたらすポイントです。

働き方改革に取り組む際、国や地方自治体が提供する助成金や補助金は初期投資や運用コストの負担軽減に貢献します。これらの支援制度は、DX推進や労働環境改善のための設備導入や教育研修に活用でき、建設業界でも利用対象に含まれるものが多いです。制度ごとに利用条件や申請方法が異なるため、事前に詳細を把握することが成功のポイントとなります。
ここでは代表的な助成金や補助金を紹介し、活用のポイントも解説します。
厚生労働省が提供する働き方改革推進支援助成金は企業が労働時間の短縮や柔軟な働き方の導入など、働き方改革の取り組みを進める際の支援を目的としています。
建設業界では現場作業の効率化やITツールの導入に取り組む企業が増えており、これに伴う環境整備や社員教育の費用が助成対象になる場合があります。例えば現場作業のデジタル化やクラウド利用のため、システム導入費用を補助してもらえます。
申請には、事業計画書や取り組み内容の提出、および認定が必要です。助成金額は取り組みの規模や内容によって変わりますが、上限が設定されているため計画的な活用が求められます。
この助成金を活用すれば建設DXの推進による働き方改革の初期コストを抑えられ、スムーズに導入を進められるでしょう。
出典参照:働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)|厚生労働省
中小企業庁が提供するIT導入補助金は、中小企業・小規模事業者がITツールやソフトウェアを導入する際の費用を一部補助する制度です。建設業界でも業務管理や工程管理、情報共有システムの導入に活用できます。
この補助金はITツール導入による業務効率化や生産性向上を目的としており、申請時には導入計画書の提出が求められます。補助率は導入費用の一部で、ケースにより受けられる補助は最大数百万円までです。
例えばクラウドベースの建設管理ソフトやモバイル端末での現場報告システムの導入などが対象になります。これにより現場作業の効率化や情報共有の円滑化を図り、働き方改革の効果を高められます。計画的に補助金を利用し、段階的にデジタル化を進めることが重要といえます。
出典参照:IT導入補助金(複数社連携IT導入枠)|中小企業庁
中小企業省力化投資補助金は、中小企業が省力化や自動化に資する設備やシステムを導入する際に利用できる補助金です。建設業界の現場での省力化や安全管理の強化に役立つ機器やソフトウェアが対象となります。
この補助金は労働時間の削減や作業効率向上を促進するもので、例えばロボット搬送システムや自動測量機器、労務管理ソフトウェアの導入費用に利用可能です。
申請には導入計画書の作成や効果予測の提出が必要です。補助率は通常数割から半分程度で、機器やシステムの種類により補助金額が異なります。費用対効果を考慮して計画を立てることが重要です。
この制度を利用すれば現場の作業効率化に直結する設備投資が可能になり、省人化や安全対策を推進する上での経済的負担を軽減できます。結果として、建設DXの具体的な成果を引き出しやすくなります。
出典参照:中小企業省力化投資補助金|中小企業省力化投資補助事業
建設業における働き方改革は単純な労働時間の短縮だけではなく、生産性の向上や職場環境の改善を目的としています。最新技術を導入するだけでは成果が出にくいため、段階的かつ計画的な取り組みが求められます。
最初に現状把握を行い、課題の優先順位を設定し、現場に合った技術選定や教育を行うことが重要です。続いて試験導入を実施し、効果検証を重ねながら全社展開を目指す方法が成功のポイントです。
ここでは、働き方改革につながる建設DXの具体的な進め方を4つのステップに分けて解説します。
建設DXを推進する第一歩は、自社の現状業務における課題の正確な把握です。現場作業のどこに無駄や非効率があるか、労働時間が長くなる原因やコミュニケーションに支障をきたしているポイントを明確にしましょう。
例えば工程管理がアナログで複数の担当者間の情報共有に遅れが生じている、書類作成に多くの時間が割かれている、技能継承がうまく行われていないなどの問題が挙げられます。これらは労働時間の増加や作業ミスの温床となりやすいため、記録を細かく洗い出すことが重要です。
課題の把握には、現場の担当者や管理者からのヒアリングを活用しましょう。現場の声を反映した課題抽出が、実効性の高いDX推進に結びつきます。明確な課題の整理こそ、後続のステップでの技術選定やプロセス設計の基盤です。
課題が明らかになったら、それを解決するための適切なデジタル技術を選定します。建設業界向けには以下の選択肢があります。
重要なのは単に最新技術を採用するのではなく自社の課題に合致し、現場の実態にマッチしたシステムを選ぶことです。
選定後は、新たな業務プロセスを設計し直す段階に入ります。デジタルツール導入に合わせて作業手順や報告フローを見直し、効率化や情報共有の円滑化を目指します。この時点で現場担当者の意見を反映し、現実的で実行可能な仕組みの構築が肝要です。
業務プロセスの構築は単なるデジタルツールの導入に留まらず、組織全体の働き方に影響を与える可能性があるため計画的に進めましょう。
全社導入の前に一部の現場や部署でパイロット導入を行い、実際の運用効果を検証します。パイロット導入は、選定したデジタル技術や新業務プロセスが現場でスムーズに機能するか確認する重要なフェーズです。
導入後は作業効率や情報共有の改善状況、社員の使い勝手や反応を観察して課題や改善点を抽出しましょう。予想外の問題が発生した場合も早期に発見できるため、拡大前に手直しが可能です。
この段階では現場担当者からのフィードバックを積極的に集めることがポイントです。彼らの意見を取り入れて改善を重ねることで導入後の抵抗感を減らし、定着を促進します。
効果検証は具体的な数値や定性的な評価を組み合わせて実施し、成果や課題を明確化して次の展開へつなげます。
建設DXは一度推進して終わりではなく、真の成果を得るには継続的な改善を重ねていくことが肝要です。PDCA(Plan・Do・Check・Act)サイクルを活用して改善点を洗い出し、新たな対策を計画・実施・評価していく体制を整えましょう。
現場の状況や技術の変化に応じてプロセスやシステムを柔軟に見直すことで、より高い生産性や働きやすさを追求できます。例えば初期の導入後に発覚した使いにくさや操作ミスの改善、新機能の追加が考えられます。
継続的改善の文化を醸成するために、トップマネジメントの理解と支援も欠かせません。DX推進が長期的な経営戦略の一環であることを全社に浸透させましょう。
建設業界では、現場の効率化や生産性向上だけでなく、社員が働きやすい環境作りが重要な課題として認識されています。こうした背景から、多くの企業が建設DXを活用して業務改善に取り組み、実際に労働環境の改善や離職率の低下を実現しています。
ここで紹介するのは具体的に建設DXを推進し、働き方改革を実践している企業の事例です。その取り組みがどのように現場の環境や働き方を変えているか、見ていきましょう。
株式会社後藤組は、業務のデジタル化を積極的に進めている企業の1つです。特にクラウド型業務改善プラットフォームであるkintoneを導入し、現場の情報共有や報告作業を効率化しています。
従来は手書きの書類や電話連絡を中心としたアナログなコミュニケーションが多く、若手社員には業務の負担が重く感じられていました。kintoneの導入によって現場からの報告や工程管理がスマートフォンやタブレットから簡単に行えるようになり、作業の手間が軽減されました。
この変化は若手社員の働きやすさに直結しています。時間の節約だけでなく情報の透明化によってミスや伝達の遅れが減少しており、結果として若手社員が安心して働ける環境を整え、定着率の向上やモチベーションの維持に役立っています。
出典参照:後藤組 様の導入事例|株式会社後藤組
平山建設株式会社はこれまで現場作業で多用されてきた手書きの記録や電話での連絡を、デジタルツールに置き換えることで働き方改革を進めています。特にGoogle Workspaceを活用したコミュニケーションの効率化に注力しました。
電話での連絡ミスや情報の伝達遅延は建設現場の大きな課題でしたが、Google Workspaceの導入でチャットやドキュメントの共有、スケジュール管理が一元化されました。これによって現場と事務所間の情報共有がリアルタイムで行われ、作業の抜け漏れや確認の手間が大きく減少しています。
またデジタルツールの導入は働く場所を選ばない柔軟な働き方にもつながっています。現場作業員はスマートフォンやタブレットから進捗報告や指示確認が可能となり、無駄な移動時間が減り時間的な余裕が生まれました。
出典参照:DX推進による働き方改革の基本方針|平山建設株式会社
ヤンマーグリーンシステム株式会社では書類業務の効率化に焦点を当て、電子承認システム「X-point Cloud」を導入しました。これによって従来の紙の申請書や承認フローをデジタル化し、業務全体のスピードアップを図っています。
建設業界では多くの書類が発生し、その管理や確認に多くの時間を要していました。X-point Cloudは電子承認を実現し、どこからでも承認作業が可能となったため承認遅れや書類の紛失リスクを低減しています。
電子化はペーパーレス化による環境負荷軽減にもつながるため、企業の社会的責任の観点から見てもメリットがあるといえるでしょう。さらに業務の効率化は社員の負担軽減にも寄与し、精神的なストレスの軽減や働きやすい職場環境の実現に貢献しています。
出典参照:若手中心のDX推進チームがアナログな組織文化を変革、申請業務の電子化を起点に業務のデジタルシフトを加速|ヤンマーグリーンシステム株式会社

建設DXには多様なツールやシステムが登場しており、それぞれの現場や業務に適した選定が非常に重要です。単に最新の技術を導入するだけでは効果は限定的であり、自社の課題や目的に照らし合わせた上で、最適なソリューションを導入する姿勢が求められます。そのためには、現場の声を反映させた選定プロセスや、段階的な導入計画も欠かせません。
DX推進によって業務効率の向上や情報共有の促進が図れれば、結果として働き方改革の実現にもつながります。この取り組みが、変化する労働環境に柔軟に対応し、持続可能な成長を実現する基盤となるでしょう。この記事であげた施策や活用できる補助制度を参考に、自社でもDX推進を検討してみてください。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
