建設DXでペーパーレス化は可能?メリットや成功のステップを解説
建設

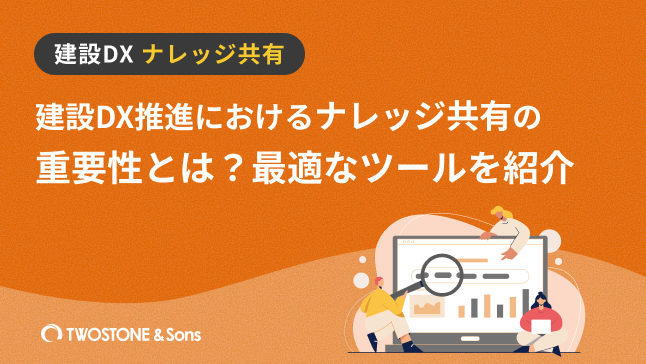
建設業界は長年にわたり職人の技術や経験に頼る場面が多く、作業の効率化や標準化に課題を抱えてきました。働き方改革の波が押し寄せる中で、業務効率の向上と社員の働きやすさを両立させる方法として注目されているのが「建設DX(デジタルトランスフォーメーション)」です。
建設DXの中心的な要素として、ナレッジ共有があります。これは職人の持つ技術や現場の知識・過去のノウハウをデジタルで蓄積し、関係者間で効率よく共有する仕組みです。
本記事では、建設DXにおけるナレッジ共有の役割やメリットを具体的に解説します。建設現場の働き方を改革したいと考える経営者や管理者にとって、実践的な視点と導入効果を理解できる内容です。これを参考に自社のDX推進を進め、持続的な成長と社員の働きやすい環境づくりにつなげましょう。

建設DX推進において、ナレッジ共有は欠かせません。ナレッジとは、現場で培われた技術・工程管理の方法やトラブル対応の知識などを指します。従来は個々の職人や管理者の頭の中や経験に依存しがちでしたが、デジタルツールを活用して体系的に蓄積・共有することで、業務の効率化や品質の安定に直結するのがポイントです。
ナレッジ共有の手法には、ドキュメント・写真・動画・3Dモデルなど多様な形式が含まれます。ICT(情報通信技術)を活用してクラウド上で情報の一元管理ができるため、どの現場でもリアルタイムで最新情報を確認可能です。
建設DXを推進するには、現場と本社、設計と施工など異なる部署や立場の間での情報連携が不可欠です。そこで重要になるのがナレッジの共有です。これにより、作業効率や品質の向上だけでなく、人的ミスの防止や技術の継承など多岐にわたる利点が期待されます。
また、業務の属人化を回避し、誰でも一定のレベルで対応できる環境づくりにもつながります。ここでは、特に重要な5つのメリットを詳しく紹介し、それぞれがどのように現場改善に寄与するのかを明らかにしていきましょう。
建設現場における作業や判断が特定の職人や担当者に依存していると、その人が不在のときに作業の停滞や品質の低下が起こりやすくなります。これは「属人化」と呼ばれ、多くの現場で慢性的な課題です。
ナレッジ共有を進めることで、各種ノウハウや判断基準が組織全体で可視化され、誰もが同じ情報を基に行動できるようになります。作業のばらつきが減り、トラブルやミスの防止にもつながります。特にベテランが培ってきた経験や判断基準を記録・展開する仕組みを整備すれば、世代交代が発生した際も安定した運用が可能になるでしょう。属人化を防ぎ、業務の継続性や再現性を確保することは、建設DX推進の土台となります。
建設業界では、マニュアル化が難しい熟練工の知識や勘といった「暗黙知」が数多く存在します。ベテランの感覚や経験は、見て学ぶしかないというのが従来の教育手法でした。
しかし、ナレッジ共有の仕組みを活用すれば、こうした感覚的な技術も形式知として残すことが可能になります。動画や3Dデータ、音声記録などを使って、ベテランの作業手順や判断のポイントを詳細に記録することで、視覚的・聴覚的に理解しやすくなるためです。
新人や若手社員は、現場での実地研修と並行して、事前に知識をインプットできるため、短期間で技術習得が可能になります。また、技術の継承が進むことで業務の質が維持され、属人化の回避にもつながります。これは企業全体の生産性向上にも直結するでしょう。
ナレッジを共有することで、現場の業務効率が高まり、無駄なコストを抑える効果が期待されます。例えば、設計ミスや施工ミスの再発を防ぐために過去の事例を活用すれば、手戻りややり直しの発生を減らせるでしょう。
また、情報が共有されていない場合に生じる確認作業や調整コスト、人的ミスによるトラブル対応の時間も削減できます。さらに、業務情報や進捗状況をクラウド上で一元管理すれば、関係者全員が最新の情報にアクセスできるため、意思決定のスピードが向上します。
これらの取り組みは、結果的に工期短縮・人件費削減につながり、企業の価格競争力を高める要因となるでしょう。リソースを有効に使い、収益性の高い体制を築くことが可能になります。
人材不足が続く建設業界において、新人教育の効率化は重要なテーマです。従来のOJTでは、教育内容が指導者ごとに異なったり、現場の忙しさで指導が後回しになったりすることも珍しくありません。
ナレッジを共有すれば、教育用コンテンツをデジタル化し、動画やマニュアル、チェックリストなどを通じて誰でも均一な教育を受けられる環境が整います。これにより教育の質のばらつきが抑えられ、短期間で業務を覚えられるでしょう。
さらに、遠隔地でも同じ教材を利用できるため、支店や現場ごとの教育格差も減少します。結果として、早期に実務で活躍できる人材が増え、企業全体の生産性が底上げされます。人材育成が戦略的に進む環境が整うのは大きな利点です。
建設業ではこれまで、紙ベースの図面、帳票、報告書などが業務の中心を占めてきました。しかし、こうした紙媒体の管理は非効率であり、情報の検索性も低いため、業務の足かせになることが多くあります。
ナレッジ共有をデジタルベースで行えば、こうした紙資料をクラウド上に集約し、電子化によるペーパーレス化を実現できます。ファイルの保管場所を問わず、検索や共有も容易になり、誤記入や紛失のリスクも軽減されるでしょう。
加えて、クラウドを活用すれば、遠隔地からのアクセスが可能となり、現場に出向かなくても必要な情報を確認できる環境が整います。これによりテレワークが可能になり、従業員の働き方の多様化やワークライフバランスの向上にも寄与します。

ナレッジの共有は、建設業界における生産性向上のカギを握る要素の一つです。しかし、共有を促進する過程では、さまざまな障壁に直面することがあります。例えば、情報が属人化していたり、現場ごとに文化やルールが異なっていたりすると、共有のハードルが上がりかねません。
また、ツールを導入しても活用が定着せず、形式だけの共有に終わるケースもあります。こうした課題を放置すれば、せっかくのDX施策が形骸化する恐れがあるでしょう。
ここでは、実務でよく見られる代表的な注意点を4つ取り上げ、それぞれに対応する現実的な対処法を解説します。
ナレッジを共有するためには情報の収集・整理・登録が必要です。現場から上がってくる情報は膨大で多様なため、これを体系的に管理するには相応の手間がかかります。
しかも、建設現場は変化が多く、新しいノウハウや作業手順が常に生まれます。古い情報が放置されると混乱を招くため、定期的な更新作業も不可欠です。したがってナレッジ管理の負荷が高まりやすく、担当者の負担増加や更新の遅れが問題になります。
対応策として、管理を効率化するためのツール活用が有効です。タグ付けや検索機能が充実したプラットフォームを導入することで、情報の登録や更新作業がスムーズになります。更新ルールを明確にし、責任者を設けることで定期的な見直しを促進しましょう。
ナレッジには重要な技術情報や契約書類・個人情報など機密性の高い情報も含まれます。これらを適切に保護し、許可された人だけがアクセスできるようにする権限管理は重要です。
しかし、多数の関係者が関わる建設現場では権限設定が複雑化しがちです。誰がどの情報にアクセスできるか明確にしないと、不必要な情報漏えいや情報過多による混乱を招きます。
適切なセキュリティ対策としては、多層的なアクセス制御やログ管理の導入が効果的です。アクセス権限を細かく設定し、情報の閲覧や編集を必要最小限に絞ることでリスクを低減します。定期的な権限見直しと従業員教育も欠かせません。
共有したナレッジはただ保存されているだけでは意味がありません。必要な情報を素早く見つけ出し、実際の業務で活用できる状態にすることが大切です。
しかし、ナレッジが体系化されていなかったり検索機能が不十分だったりすると、情報の活用率が下がります。特に多様な形式のデータが混在するとどこに何があるかわかりにくくなるため、現場の作業効率を妨げる原因にもなります。
これに対処するには、ナレッジの分類やキーワード検索などを活用して、使いやすい設計に整えることが欠かせません。また、利用頻度やユーザーのフィードバックを基に情報の整理を継続的に行い、検索性の改善を図りましょう。
ナレッジ共有の仕組みを構築する際に、管理部門だけの視点に偏って設計を進めると、実際の現場業務と乖離が生じてしまうことがあります。例えば、操作が煩雑だったり、必要な情報にアクセスしづらくなったりするシステムになると、現場では負担と感じてしまい、利用を避ける傾向が強まります。このような状態ではせっかく導入しても形だけの共有にとどまり、DXの効果を十分に発揮できません。
現場の作業員や監督者が日常的に何に困っているのか、どのような情報をリアルタイムで求めているのかを正しく理解する必要があります。その上で、現場の実態に即したシステム設計を行うことが重要です。現場からのフィードバックを受け、定期的に機能や表示項目を見直すなど、継続的な改善も欠かせません。
建設現場では、図面や工程表だけでなく、過去の施工実績や技術的なノウハウなど、多様な情報が日々蓄積されています。これらを有効に活用するには、適切なツールによるナレッジ共有が重要です。特に建設業界においては、現場作業の忙しさや通信環境の制限などを考慮し、使いやすく即時性のある仕組みが求められます。
音声や画像にも対応したプラットフォームや、スマートデバイスからアクセス可能なシステムの活用が有効です。
ここでは、建設業務に特化した特徴を持つナレッジ共有ツールを4つ紹介し、それぞれの活用シーンや導入のポイントについて具体的に解説します。
Knowledge Explorerは設計図面や仕様書など、多様な設計情報を一元管理できるプラットフォームです。建設プロジェクトで発生する膨大な設計データを集約し、キーワード検索やタグ管理を活用して必要な情報を素早く探し出せます。
設計変更の履歴管理機能が充実しており、誰がいつどのように設計を変更したかを明確に追跡可能です。現場での誤解や手戻りを減らし、プロジェクトの品質向上に寄与します。
また、設計チームだけでなく現場作業員も情報にアクセスできるため、関係者全員が最新の情報を共有できる環境が整います。建設業界特有の複雑な設計情報管理に対応した機能が多く、DX推進の基盤として有効です。
出典参照:Knowledge Explorer| 株式会社図研プリサイト
X-point Cloudは書類のワークフローを電子化するツールで、紙ベースの申請や承認プロセスをクラウド上で完結させられます。建設現場では多種多様な申請や報告書類が日々発生しますが、このツールを使うことで書類の紛失や記入ミスを減らし、業務の効率化を図れます。
操作は直感的で、ITに慣れていない現場従業員でも短期間で習得が可能でしょう。多様なテンプレートが用意されており、建設業界のニーズに合わせてカスタマイズしやすい点も魅力です。
さらに、ワークフローの進捗状況をリアルタイムで把握できるため、承認遅延の防止や業務管理の透明化につながります。書類管理の効率化を通じて、建設DXの推進に直結する効果を期待できるツールです。
NotePMは社内の知識や情報をまとめて管理し、誰でも簡単にアクセスできるナレッジマネジメントツールです。マニュアルや技術情報・会議の議事録などを整理し、キーワード検索やタグ付けで必要な情報を素早く取り出せます。
建設現場の属人化を防ぐために経験豊富な職人や管理者のノウハウを蓄積し、若手社員に共有する役割を果たします。編集履歴が保存されるため、情報の正確性や最新性も確保できるのがメリットです。
また、スマートフォンやタブレットからもアクセス可能なため、現場作業員が移動中や休憩時間に知識を参照できて学習効率を高められます。使いやすさと柔軟性を兼ね備えたNotePMは、ナレッジ共有の基盤整備に適したツールです。
AppSuiteは、専門的なプログラミング知識がなくてもノーコードで業務アプリを簡単に作成できるプラットフォームです。建設現場の独自業務やプロセスに合わせたカスタムアプリを素早く導入し、業務効率化に役立てられます。
例えば、作業報告書の入力フォームや資材管理のアプリなど現場のニーズに即したツールを現場担当者自ら作成し、運用可能です。これにより現場の細かな課題に対応しやすく、DX推進に柔軟性をもたらします。
さらに、AppSuiteは他のシステムやデータベースとの連携も可能なため、既存の業務システムと統合して情報の一元管理を図れるのがポイントです。現場主導の改善活動を支援し、変化に強い業務体制の構築に貢献します。
出典参照:AppSuite|株式会社ネオジャパン
建設業界でのDX推進において、ナレッジ共有ツールの導入は欠かせない要素となっています。現場や設計・管理といった多様な情報を効率よく共有し、業務の属人化を防ぐために多くの企業がさまざまなツールを活用するようになりました。
ここでは、実際にナレッジ共有ツールを導入して建設DXを推進している企業の事例を4つ紹介します。導入の背景や効果を理解し、自社のDX推進の参考にしましょう。
ライト工業株式会社は、建設プロジェクトに関わる多様な設計図面や仕様書・技術資料を一元管理するためにKnowledge Explorerを導入しています。以前は情報が複数のシステムやファイルに分散しており、必要な資料を探すのに時間がかかることが課題でした。
Knowledge Explorer導入後は、キーワード検索やタグ管理によって必要な情報を即座に見つけられるようになりました。設計変更や施工ミスを防ぐための最新情報へのアクセスが迅速化し、現場の判断スピードが上がっています。
さらに、設計情報の共有が徹底されたことで社内のナレッジ活用が進み、属人化の解消につながっているのもポイントです。情報の一元化が現場の生産性向上に直結し、DX推進の成功例として注目されています。
出典参照:建設事業会社のナレッジ活用事例| ライト工業株式会社
ヤンマーグリーンシステム株式会社は、日々発生する各種申請書や承認フローの管理に課題を抱えていました。紙ベースの申請は処理に時間がかかり、紛失や記入漏れのリスクもありました。
そこでX-point Cloudを導入し、全ての申請書類を電子化しワークフローをクラウド上で管理する仕組みを構築しています。結果として申請にかかる時間が約90%短縮され、承認の遅延も減少しました。
使いやすい操作性と現場への導入のしやすさから従業員の抵抗感も少なく、スムーズな運用開始が実現したのもポイントです。業務効率化だけでなく、ペーパーレス化によるコスト削減効果も得られています。
出典参照:クラウド型ワークフロー「X-point Cloud」導入により年間約600時間の業務削減やDX人材の育成を実現|ヤンマーグリーンシステム株式会社
株式会社横森製作所は、技術情報やノウハウの共有不足から属人化が進み、新人教育や作業ミスのリスクが高まっていました。これらの課題を解決するためにNotePMを導入しています。
NotePMでは、マニュアルや技術メモを体系的にまとめ、誰でも簡単に閲覧・編集が可能です。検索機能に優れており、必要な情報を速やかに見つけ出せるため作業効率が向上しました。
さらに、現場からのフィードバックや改善提案を反映しやすい運用体制を整備したことで、ナレッジの質が向上しています。教育の効率化やミス防止に寄与し、現場の働き方改革にもつながっています。
出典参照:【導入事例】文書管理システムを刷新!社内質問箱で問い合わせ業務も効率化|株式会社横森製作所
鹿島建設株式会社は、先端ICT技術を積極的に取り入れ、施工現場の自動化や効率化を推進しています。特にロボット技術やドローンを活用した現場計測のデータをKnowledge Explorerなどのシステムに集約し、施工ノウハウとして社内で共有しています。
これにより各現場で蓄積されたノウハウが中央管理され、異なる現場間での情報共有が円滑になりました。ロボットによる作業データもナレッジとして活用し、作業の標準化や品質向上に役立てています。
技術の活用とナレッジ共有の両輪で建設DXを推進し、競争力強化に結びつける先進的な取り組みが評価されています。
出典参照:特集 ICT x 発想力 ~新たなワークスタイルを創る~ |鹿島建設株式会社

建設DXの推進にはナレッジ共有が不可欠であり、業務の効率化や技術継承を実現するカギとなります。記事で紹介したツールや企業事例を参考に、自社に適した仕組みを整えることが重要です。
情報の一元管理や属人化防止は、生産性向上だけでなく品質と安全性の維持にもつながります。さらに、テレワークやペーパーレス化などの働き方改革の観点からもナレッジ共有は効果的です。
継続的な情報の管理や現場の意見反映を意識しながら、適切なツールを導入し運用することが建設DX成功のポイントです。自社の業務課題や人材育成の観点からナレッジ共有の活用を検討し、DX推進を着実に進めていきましょう。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
