建設DXでペーパーレス化は可能?メリットや成功のステップを解説
建設

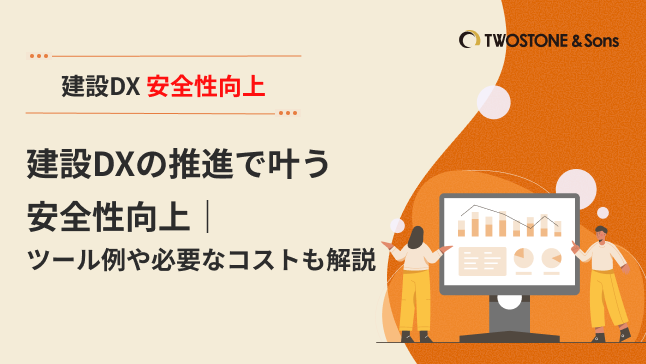
建設現場では、常に安全確保が最優先事項とされています。高所作業や重機の使用など、危険と隣り合わせの現場において事故・災害を防ぐ取り組みは欠かせません。一方で、深刻な人手不足や高齢化の進行により、従来の安全対策だけでは限界があるという現実もあります。
そこで注目されているのが建設DXです。デジタル技術を導入することで現場の見える化や自動化が進み、安全対策の精度と効率が同時に高まります。
この記事では、建設DXがなぜ安全性向上に有効なのか、その理由と具体的なアプローチを詳しく解説します。推進時に役立つツールや費用感についても紹介しているため、安全な現場づくりを目指す企業にとって有益な情報が得られるでしょう。

建設業界でのDX(デジタルトランスフォーメーション)は、業務の効率化や人手不足の解消だけでなく安全性向上にも密接に関係しています。紙や口頭で行われていた安全確認や指示は、ミスや漏れの原因になることがありました。しかし、デジタル技術を導入することで情報共有がリアルタイムかつ正確になり、危険予知や事故防止につながるケースが増えています。
また、AIやIoTを活用したモニタリングシステムの導入によって、従業員の行動や機器の稼働状況を常時把握することも可能です。こうした仕組みにより異常が発生した場合にはすぐに対処できる体制が整い、重大事故を未然に防げます。
現場の安全性を高めるためには、予防的な管理とリアルタイムの対応が不可欠です。その両方を支えるのが、建設DXの強みだといえるでしょう。
建設DXの推進によって、業界全体の安全対策がより実効性のあるものへと変化しています。デジタル技術を活用することで、これまで見落とされていた危険要因の把握や作業工程の可視化が可能となり、現場のリスク管理が体系化されます。
また、データの収集と分析により危険予兆を早期に察知できる仕組みも整備されてきました。こうした変化が、災害や事故の未然防止へとつながり、働く人々の安心感と現場全体の生産性を高める結果を生んでいます。
建設DXの進展により、危険性の高い作業を人が直接行わずに済む仕組みが整ってきました。特に、ドローンやロボットによる高所点検や遠隔操作による重機の運転などは代表的な例です。人が立ち入る必要のない作業エリアを増やすことで、接触事故や転落事故のリスクが軽減されます。
実際に、遠隔操作が可能な重機を導入した現場では、従来の作業手順を見直すと同時に安全基準の見直しも進みました。人が介在する機会を減らすことで、作業ミスや判断ミスによる事故も減少傾向にあります。
こうした自動化・遠隔化の技術は、現場の安全対策に新たな価値をもたらしています。
建設DXの推進は作業効率の向上にも貢献します。効率化が進めば余計な負荷が減り、従業員の疲労やストレスの蓄積を抑えられるのがメリットです。こうした状態が続くと、ヒューマンエラーの発生率も自然と低下していくでしょう。
例えば、現場での材料管理や作業工程の進捗をタブレットで一元管理する仕組みがあれば、情報の確認漏れや指示ミスを減らせます。従業員同士の連携もスムーズになり、混乱や誤解によるミスを防げるでしょう。
さらに、AIを活用したシミュレーション機能により、作業手順の最適化やリスク分析も容易です。作業前に危険箇所や注意点を共有する文化が根付き、事前準備の段階から安全対策が強化されます。
建設現場では多くの関係者が同時に作業を進めているため、情報の伝達ミスや共有漏れが安全リスクに直結します。そこで活躍するのが、クラウドやモバイルデバイスを活用したリアルタイムの情報共有です。
これにより、現場の状況や作業計画、緊急連絡などをその場で確認・更新可能です。急な天候変化による作業中止や、資材の搬入遅れといった変更にも柔軟に対応できます。
また、スマートフォンやタブレットを活用したチェックリスト機能や報告書の電子化により、紙媒体に依存しない管理が可能です。こうした環境が整うことで情報伝達のスピードと正確性が向上し、安全面の強化にもつながります。
建設現場では、高所作業や重機の使用など危険を伴う作業が日常的に行われており、従業員の安全を確保するためには従来の目視確認や紙による管理では限界があります。
そこで近年注目されているのが、ICTやセンサー技術、ウェアラブルデバイスなどを活用した安全管理ツールです。ここでは、現場の安全管理に役立つ代表的なツールを紹介し、それぞれの特徴や活用方法について詳しく説明します。
作業者安全モニタリングシステムは、従業員の動きや位置情報をリアルタイムで監視し、危険な行動や異常を検知します。具体的には、センサーやビーコンを装着した作業者の位置や動作を把握し、高所作業中の転落や接触事故のリスクを減らす仕組みです。
このシステムは、危険エリアへの侵入や一定時間の動作停止を検知すると、即座に警告を発信します。そのため、事故の早期発見と迅速な対応が可能となります。従業員一人ひとりの安全確保が強化され、管理者は現場全体の安全状況を可視化できるのがポイントです。
さらに、収集したデータを分析すれば、事故発生の傾向や危険要因を把握できます。予防策を講じるための有効な情報が得られるため、継続的な安全改善にもつながります。
出典参照:作業者安全モニタリングシステム |株式会社村田製作所
hitoe®ウェアラブルセンサは、衣服に取り付けるタイプのセンサーで、作業者の心拍数や呼吸数・体温といった生体情報を計測します。これにより、従業員の健康状態をリアルタイムで把握し、熱中症や過労などのリスクを早期に察知できるのが特徴です。
従来は定期的な健康チェックが中心でしたが、このウェアラブルセンサの導入により作業中の変化も即座に確認できるのがポイントです。異常値が検出されると管理者や作業者本人にアラートが届き、迅速な対応が促されます。
さらに、継続的なデータの蓄積は健康管理の質向上に寄与し、個々の従業員に合わせた安全対策の立案も可能になります。ウェアラブル技術は負担の少ない自然な装着感も評価されており、現場での実用性が高い点もメリットです。
リモートモニタリングシステムは、離れた場所からでも作業者の健康状態や作業進捗をリアルタイムで確認できる仕組みです。モバイル端末やパソコンを介して現場の状況を一括管理できるため、管理者は複数の現場を効率よく監督できます。
このシステムの活用により現場での緊急事態に即応できるほか、現場従業員の健康不調を早期発見して休憩や交代を指示するなどの対応も可能です。遠隔からの状況把握は、安全管理の負担を軽減してより正確な判断をサポートします。
また、過去のモニタリングデータは安全教育や作業改善に活かせるため、現場全体の安全レベル向上にも寄与するのがポイントです。遠隔監視技術の進化により、管理の効率化と安全対策の高度化が期待されます。
バイタルセンサーは、心拍数や血圧・体温などの生体情報をリアルタイム収集できる装置で、主に腕や胸部に装着します。建設現場では、従業員の体調変化を即座に検知して熱中症や心臓発作といった健康リスクの予防に役立てられています。
このセンサーは無線通信機能を持ち、取得したデータをクラウド上で一元管理できるのもポイントです。管理者は現場全体の作業者の健康状態を常に把握でき、必要に応じて迅速な医療措置を手配できます。
バイタルセンサーには、個人差を考慮しながら異常を検出しつつ、誤報を減らす高度なアルゴリズムが組み込まれている点も特徴です。安全対策のデジタル化において重要な役割を果たしており、現場のリスクマネジメントに欠かせないツールといえます。
出典参照:バイタルセンサー|センスウェイ株式会社
EXBeaconプラットフォームは、BLE(Bluetooth Low Energy)ビーコンを活用し、屋内での人や物の位置情報をリアルタイムかつ高精度に把握できるシステムです。建設現場ではGPSが遮断されやすく、建物内や地下での位置把握が困難でしたが、この技術により、従業員や重機、資材の動きを正確に可視化できます。
このプラットフォームは、危険区域への立ち入りを感知すると即座にアラートを発信し、関係者に通知を送る機能を備えています。例えば、立ち入り禁止エリアに作業員が侵入した場合、現場管理者に自動で警告が届くため、迅速な対応が可能です。
これにより、安全対策の強化に加え、作業工程の見直しや人員配置の最適化にも貢献します。EXBeaconプラットフォームは、現場のリスク低減と運用効率の向上を両立する重要なツールといえるでしょう。
出典参照:EXBeaconプラットフォーム|株式会社WHERE

安全性を高めるための建設DXは、一度にすべてを変えるのではなく段階的な進行が基本です。
まずは現場ごとのリスクを可視化し、危険箇所や課題を明確にするステップが必要です。次に、その課題に合ったツールやシステムを選定し、パイロット導入を実施します。現場の反応を確認しながら運用フローを見直し、少しずつ他の現場へと展開していく流れが理想です。並行して教育やマニュアルの整備も行い、現場全体が新たなシステムに馴染めるよう環境を整備することが重要です。
ここでは5つの手順について詳しく解説します。
建設現場には多種多様なリスクが存在します。高所作業・重機の操作・資材の移動など、どの作業も事故やケガの危険性をはらんでいます。これらのリスクを把握して適切な対策を講じるには、まず現場の状況をデジタル化して見える化することが重要です。
ドローンや3Dスキャン技術を用いると、現場全体のレイアウトや危険区域が正確にデジタルマップとして作成されます。さらに、IoTセンサーを設置すればリアルタイムで作業環境の温度や振動・ガス濃度なども計測可能です。
こうしたデジタルデータは管理者だけでなく従業員にも共有でき、リスクを共有しながら安全意識を高められます。リスクの可視化は事故予防の第一歩として重要な取り組みです。
リスクを明確にしたあとは、安全管理を支援する各種ツールの導入に進みます。これには作業者安全モニタリングシステムやウェアラブルセンサー・位置情報管理システムなどが含まれます。適切なツールを選定することで、安全リスクをリアルタイムに検知できるようになるのがポイントです。
導入時には現場の規模や作業内容・従業員のITリテラシーを考慮し、使いやすさを重視したツール選びが欠かせません。また、ツールの性能だけでなくデータ連携や管理の仕組みも構築する必要があります。
さらに運用体制を整えて定期的なメンテナンスやアップデートを実施することで、ツールの効果を持続可能にします。これにより、安全管理が現場の標準業務として根付いていくでしょう。
安全管理ツールの導入は、現場の事故リスクを下げる大きな一歩ですが、それだけで成果が出るわけではありません。肝心なのは、ツールを使用する従業員がその操作方法を理解し、日常業務で自然に活用できるようになることです。そのためには、初期導入時から継続的に教育と訓練の機会を設ける必要があります。
実際の研修では、機能説明だけでなく、実際の現場を想定した活用例を交えて説明することで、ツールの使用目的や重要性を理解しやすくなります。
また、現場で得た使い勝手や改善提案などのフィードバックを積極的に収集し、教育内容や運用方法に反映する姿勢も大切です。従業員の声を運営側がきちんと受け止めることで、ツールへの信頼感が生まれ、現場全体の安全文化の醸成にもつながります。
建設現場に導入された安全管理ツールは、従業員の動きや環境データなど、多様な情報をリアルタイムで収集します。しかし、それらのデータを蓄積するだけでは十分とはいえません。重要なのは、収集した情報を分析し、現場のリスク要因を明確にして、的確な安全対策へとつなげていくことです。
例えば、過去の作業記録や移動データをもとに、特定エリアで転倒や接触などのヒヤリハットが多発していると判明すれば、そのエリアの作業動線の変更や注意喚起の強化といった対策が講じられるでしょう。
データに基づいた改善策は、現場の安全対策を主観に頼らない合理的なものへと変える効果があります。こうした取り組みは、事故の抑制だけでなく、従業員の安心感やモチベーションの向上にも直結します。データを活用した安全対策は、これからの建設現場に欠かせない基盤といえるでしょう。
建設DXによる安全管理を真に根付かせるためには、現場単位での取り組みにとどまらず、企業全体として安全文化を構築する必要があります。経営層が率先して安全への姿勢を示すとともに、現場の最前線で働く従業員まで、その価値観を共有しなければ実効性は期待できません。
安全第一を共通認識とし、日常業務の中で自然に安全確認が行われる風土を醸成することが不可欠です。そのためには、定期的な安全ミーティングや教育研修の実施、表彰制度の導入、安全通報制度の整備など、組織的な仕組みづくりが求められます。
また、建設DXの推進と並行して、安全推進に関わる責任者やチームを明確化し、部署間の連携体制を整えることも重要です。こうした取り組みにより安全意識が習慣として根付き、労働災害の発生を抑えるだけでなく、従業員の安心感や信頼感の醸成、さらには業務全体の効率化にもつながります。
建設DXによる安全対策を導入する際には、初期費用・運用費用・教育費用といった複数のコスト要因があります。これらのコストは一見高く感じられるかもしれませんが、長期的に見ると事故の防止による損失回避や保険料の低減、現場の稼働停止リスクの低下といった面で十分なリターンが期待できます。
ここでは、建設DX推進にかかる主なコストを具体的に整理し、それぞれの対策を検討していきます。
建設DXを推進して安全性を高めるには、初期投資と継続的なランニングコストの両方を想定する必要があります。初期費用には、ソフトウェアの購入、機器の設置、ネットワーク環境の構築、従業員への研修などが含まれます。
一方、ランニングコストとして代表的なものは、以下の4つです。
これらの費用を過不足なく見積もり、現場規模や導入範囲に応じて調整することが、無理なくDXを進める上で重要な要素となります。
建設DX推進で大きな初期費用は、デジタル機器やシステムの購入および導入費用です。ウェアラブルセンサーや監視カメラ・IoTセンサーなどのハードウェアを購入するだけでなく、それらを統合・管理するソフトウェアの構築やカスタマイズにも費用がかかります。
新たな技術を導入する際は、導入前に複数社から見積もりを取り、機器の性能と価格を比較検討しましょう。安価な機器が必ずしも良いコストパフォーマンスであるとは限らず、現場の特性に適した機器選定が求められます。
また、導入時には現場のネットワーク環境の整備やシステムと既存設備の連携設計にも予算を割く必要があります。これらの費用も見逃さずに計画に含めておくことが重要です。
建設DXの効果を引き出すには、現場従業員や管理者への教育も不可欠です。新しいツールやシステムの操作方法・安全管理の意識向上に向けた研修を行うための費用が発生します。
研修には、講師の派遣費用や教材作成費用・受講者の業務調整に伴う間接的なコストも含まれます。研修内容や受講者数によって変動しますが、計画的に教育プログラムを組むことが無駄な支出を抑えるポイントです。
さらに、eラーニングやオンライン研修を活用すれば、移動時間や講師費用を削減しながら教育効果を維持できます。こうしたデジタルツールの活用は、教育費削減に有効な対策です。
導入する安全管理システムは多くの場合、クラウドサービスを利用して運用されます。クラウドサービスは初期費用が抑えられる反面、月額や年額の利用料が継続的に発生するので注意が必要です。
利用料はシステムの規模や機能・同時接続ユーザー数によって異なります。契約前には利用プランの詳細を確認し、無駄な機能や過剰な容量を避けることが必要です。
また、契約期間の見直しや複数サービスの統合によるコスト削減も検討すると良いでしょう。クラウドのメリットを活かしつつ、運用コストを抑える戦略が重要です。
建設DXで導入した機器やシステムは、継続的に正常稼働させるためにメンテナンスが必要です。センサーの故障対応やソフトウェアのアップデート、障害対応にかかる費用がランニングコストに含まれます。
特に現場の過酷な環境下では機器の劣化や故障リスクが高まるため、定期的な点検計画を立てることが欠かせません。故障時の迅速な対応を可能にする保守契約を締結する企業も増えています。
メンテナンス費用の削減には、耐久性の高い機器の選定や自動更新システムの導入も効果的です。加えて、現場の従業員による簡単なトラブルシューティング教育も運用コストの軽減に寄与します。
建設DXを推進する中で、安全性向上のための投資を行うにはコスト管理が不可欠です。限られた予算内で効果を最大化するには、国や自治体が提供する補助金や助成金の活用が有効です。
また、すべての現場に一斉推進するのではなく、最初は限定的にツールを導入して成果を検証し、段階的に展開する「スモールスタート」方式を採用するのも現実的な方法です。コストを抑えつつ、現場の安全をしっかり支えるための取り組みがカギとなります。
建設DX推進にかかる費用の軽減には、国や地方自治体が提供する補助金や助成金を活用すると良いでしょう。これらの公的支援制度は初期費用の負担を減らすだけでなく、継続的なDX推進のモチベーションにもなります。
補助金や助成金には多様な種類があり、建設現場の安全性向上に関わるデジタル機器やシステムの導入費用が対象になる場合もあります。申請には導入計画の提出や実績報告が必要ですが、正しく準備すれば多くの企業が利用可能です。
補助金を利用すると設備投資のリスクを減らしながら最新の安全管理ツールを導入できるため、建設現場の安全性を向上させる取り組みが加速します。
建設DXは現場や組織の規模、業務内容によって必要な機能や推進の難易度が異なります。すべてのシステムやツールを一度に導入するのではなく、段階的に進める方法が効果的です。
まずはリスクの高い作業や課題が顕在化している現場から、安全管理ツールを導入していきます。これにより初期投資を抑えつつ導入効果を早期に実感でき、次の導入計画の検討材料にすることも可能です。
段階的な推進は従業員の負担軽減にもつながります。これにより、急な変化を避けることで操作ミスや混乱を防ぎ、現場の理解や協力を得やすくなるのがメリットです。新たなツールやシステムに慣れる時間を十分に確保しながら、安全文化の浸透を進められます。
建設業界では、安全性の向上が継続的な課題となっており、その解決策としてDXの推進が注目されています。実際に多くの企業がデジタルツールやシステムを活用し、従来の現場管理方法を見直しています。
AIによる映像解析で危険動作を検知する取り組みや、IoTセンサーを使った高所作業者の転倒予防、リアルタイム位置情報を用いた避難誘導システムの整備などはその一例です。こうした先進的な事例は、安全性向上と業務効率の両立が可能であることを証明しており、他企業にも導入の参考となっています。
鹿島建設株式会社は、建設現場の安全性向上を目的に、IoT技術を活用したセンサーによる位置情報管理と機械稼働状況の監視システムを導入しました。このシステムでは、作業員に取り付けたセンサーからリアルタイムで位置情報が送信され、危険区域に近づくと即座に警告される仕組みが整備されています。
加えて、重機や建設機械の稼働状態も監視対象とされており、異常動作や長時間稼働などが検出された場合には即時対応が可能です。この仕組みにより、人と機械の接触事故を予防すると同時に、緊急時の初動対応も迅速になりました。管理者は現場全体の状況を俯瞰的に把握できるようになり、人的ミスによるリスクも抑制されます。
IoTセンサーの導入は、単なる見守り機能にとどまらず、データの蓄積と分析によって、安全対策の高度化や運用改善にも役立っています。
出典参照:建築業界の課題,溶接技術者の現状と解決策|鹿島建設株式会社
大成建設株式会社は、自社で開発した「T-iROBO」という人体検知システムを建設現場に導入しています。このシステムは、AIとカメラを活用して現場内の作業員の動きをリアルタイムに監視し、安全リスクが発生した際には警告を出す仕組みです。
具体的には、AIが画像解析を通じて危険な動作や接近行動を検出し、管理者や本人に通知を送信することで、事故の予防を図っています。人の動線や活動範囲を可視化することで、危険箇所の把握や安全対策の重点的な実施が可能になり、現場全体の安全性が向上しました。
また、作業内容の最適化や業務計画の見直しにも活用されており、管理体制の改善にも貢献しています。特に多数の作業員が同時に働く現場では、個別の目視確認が難しいため、このような自動検知システムの導入は大きな効果を発揮しています。
出典参照:自動運転クローラダンプ「T-iROBO® Crawler Carrier」の実用化に目途 |大成建設株式会社
清水建設株式会社は、独自開発した統合管理プラットフォーム「DX-Core」を中核とし、IoTデバイスと連携させた安全管理を展開しています。これは、建設現場から収集されるさまざまなデータをリアルタイムで可視化・分析し、安全リスクの早期発見と対応を行うシステムです。
例えば、作業員の体調に関する情報や周囲の温度・湿度などの環境データをモニタリングし、熱中症などのリスクを事前に警告する機能も備えています。さらに、作業進捗や品質データも一元的に管理できるため、安全と生産性の両面で効果が期待されています。
「DX-Core」は単なるデータ収集ツールではなく、現場と本社をつなぐ情報基盤として活用されており、業務の効率化や安全文化の醸成にも寄与しているといえるでしょう。従業員の安心感を高めると同時に、リスクの見える化による対応精度の向上にも貢献しています。
出典参照:建物を一括管理するデジタル化プラットフォーム「DX-Core」|清水建設株式会社
株式会社竹中土木は、3Dデータと工程情報を組み合わせたCDM-3D可視化システムを導入し、建設現場のリスク情報や作業工程を「見える化」しました。このシステムは、3Dモデル上に作業スケジュールや進捗を投影することで、現場全体の状況を一目で把握できるように設計されています。
結果として、危険エリアへの立ち入りや作業の重複による事故リスクを早期に発見でき、安全対策の即時実施が可能になりました。また、管理者だけでなく現場作業員自身も視覚的に情報を共有できるため、安全意識の向上にもつながっています。
システムの導入後は、作業計画の精度が向上し、業務全体の効率も改善されました。CDM-3Dは、単なる表示ツールにとどまらず、情報伝達の質を高める安全管理支援ツールとして、高く評価されています。
出典参照:地盤改良杭の施工品質可視化技術 |株式会社竹中土木
西松建設株式会社では、AI画像認識技術を用いた安全管理システムを開発し、建設現場におけるリスクの自動検知を実現しました。このシステムは、現場に設置されたカメラ映像をAIがリアルタイムで解析し、足場の崩れ、無防備な作業姿勢、不審な動きなどを検出します。異常を検知すると即時にアラートが発信され、管理者が迅速に対応できるよう支援します。
従来は人的確認に頼っていた安全管理に自動化と客観性を取り入れることで、見落としの削減や作業者の負担軽減を実現しました。また、蓄積された映像データは過去のリスク傾向の分析にも活用され、今後の予防対策の質を高める材料となっています。AIの活用により、より高度な安全対策が可能になり、現場全体のリスク対応力が底上げされています。
出典参照:AI切羽評価システム|西松建設株式会社

建設DXの推進は単なる効率化に留まらず、現場の安全性向上に直接寄与しています。鹿島建設のIoTセンサー、大成建設の人体検知システム、清水建設の統合管理プラットフォームなど多様な技術が活用され、労働災害の抑制に成功する企業がでてきました。
これらの事例からわかるように、デジタル技術を活用することでリアルタイムのリスク把握や危険箇所の早期検知が可能になり、従業員の安全を守る環境づくりが進みます。また、導入に際しては現場の実態やニーズを踏まえた選定・運用が重要です。
建設DXは安全文化の形成にもつながり、事故防止だけでなく持続可能な現場運営の基盤を作ります。現場の安全を守るために、今回紹介した企業事例を参考にしつつ自社の現場に適したデジタル技術の導入を検討してみてください。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
