建設DXでペーパーレス化は可能?メリットや成功のステップを解説
建設

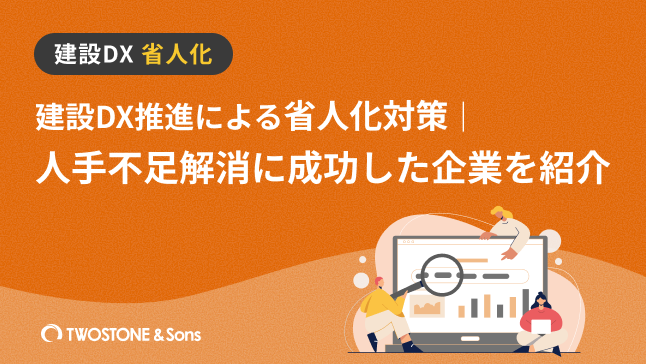
建設業界は深刻な人手不足に直面しており、現場の作業負担は増す一方です。若手の減少や熟練技術者の高齢化により、将来的な労働力不足が懸念されています。こうした状況を打開するために注目されているのが、建設DXの推進です。建設DXは、デジタル技術の活用によって現場の業務効率を高め、省人化を実現するためのカギとなります。
この記事では、建設DXと省人化の関係性を紐解きながら、なぜ建設DXの推進が省人化につながるのかを詳しく解説します。さらに、企業が実際にどのようにDXを取り入れて省人化に成功しているのかも紹介し、今後の建設業界に必要な視点を提供します。この記事を読むことで建設DXを推進した省人化のメリットと推進のポイントが理解でき、自社の課題解決に役立てられるでしょう。

建設DXとは、IoT・AI・クラウドなどのデジタル技術を活用し、建設業務全体の効率化と革新を目指す取り組みです。このDX推進は、省人化と密接な関係を持っています。省人化とは、作業に必要な人員を削減しながら効率や品質を維持・向上させる取り組みのことです。
建設業は技術や経験に基づく属人的な作業が多く、人手を減らすのが難しい業界とされてきました。しかし、最新のデジタル技術を取り入れることで作業の標準化や情報共有が促進され、業務の効率化が進みます。
建設DXの推進が省人化に結びつく背景には、業務の自動化・効率化を可能にするデジタル技術の活用があります。従来は人の手に依存していた作業や判断が、IoTやAI、クラウドシステムなどの導入によって機械的に処理できるようになってきました。こうした取り組みは単なる労働力削減ではなく、少人数でも現場を円滑に運営する仕組みづくりとして、持続可能な生産体制の構築に寄与します。
ここでは主なポイントを詳細に解説します。
建設業では、人件費が経営コストの大きな割合を占めています。人手を省くことで無駄な労働コストを減らせるため、経営効率が改善されます。デジタル技術の導入によって作業の自動化や遠隔監視が可能となり、同じ作業量をより少ない人数でこなすことが可能です。
また、省人化は単なるコストカットに留まらず、収益力の強化に寄与します。余剰資金を新しい技術導入や人材育成に再投資できるため、企業の持続的成長が期待されます。無理な労働力削減ではなく、効率的で質の高い生産体制を構築するための戦略的な投資です。
建設業界の人手不足は長年の課題であり、特に熟練者の減少が深刻です。労働環境の厳しさや若年層の業界離れも影響し、採用と定着の難しさが顕著になりました。こうした現状に対し、DX推進で業務効率を上げれば、少ない人員でも作業が回る体制を作り出せます。
例えば、ドローンによる現場の調査やロボットによる危険作業の自動化は、作業員の負担を軽減して事故のリスクも低減します。これにより現場の安全性も向上し、働きやすい環境づくりが進むでしょう。結果として、離職率の低減や人材確保に良い影響をもたらします。
建設業は労働安全衛生法や労働時間規制の厳格化により、作業管理の高度化が求められています。従来の手作業や紙ベースの管理では適切な労務管理が難しい場合もありますが、デジタル技術を活用すればリアルタイムで作業状況や勤怠を管理できます。
これにより法令遵守の体制を強化しつつ、過重労働の抑制にもつながるのがポイントです。また、労働環境の改善は社員の健康維持や生産性向上に寄与し、企業の社会的信用の向上にも貢献します。結果的に、法規制の変化にも柔軟に対応できる強い経営基盤が構築されます。
建設現場の技術継承は、高齢化と若手不足の中で大きな課題です。熟練技術者の暗黙知は書面化や口伝で伝わることが多く、属人的な状況から脱却しにくい傾向があります。しかし、DXの推進によって技術情報をデジタルで記録・共有できる環境が整います。
動画マニュアルや3Dシミュレーション、ナレッジ共有プラットフォームの導入により、後進が効率的に学べる仕組みが生まれるでしょう。これにより属人化が解消されて技術の均質化が可能になり、作業品質の安定にもつながります。技術継承が進むことで、長期的に現場の生産性を維持しやすくなります。
建設業界で慢性的な人手不足が深刻化する中、デジタル技術の活用による省人化が不可欠となっています。そこで多くの企業が建設DXを推進し、最新のツールやシステムを導入して省人化を実現しています。
ここでは具体的にどのような取り組みが行われているのか、先進企業の事例を通じて詳しく見ていきましょう。これらの事例はツール導入のヒントや成功のポイントを示しており、自社のDX推進に役立つきっかけを与えてくれます。
鹿島建設はICT建設機械の導入に積極的に取り組み、重機の自動化や遠隔操作技術を活用して省人化を推進しています。ICT建設機械とは、GPS・センサー・通信機能を備えた建設機械で、施工計画に基づき自動で精密な作業を行うことが可能です。これにより現場作業員の負担が軽減されるだけでなく、作業精度も高まります。
具体的には、土木工事の掘削・整地作業での遠隔操作や自動制御による施工を行いました。これにより人が危険な箇所に立ち入る必要が減り、安全性の向上にもつながっています。省人化効果としては、従来の作業に必要だった複数のオペレーターを削減し、少人数で効率的に現場を回せる体制を構築しています。
また、ICT建設機械の導入は、作業の均質化と工期短縮にも寄与するのが特徴です。鹿島建設の取り組みは、デジタル技術を用いた建設DX推進の模範例として注目されています。
出典参照:伐採作業無人化システム「キッタロー君®」|鹿島建設株式会社
大林組はBIM(Building Information Modeling)やCIM(Construction Information Modeling)を積極的に導入し、デジタルツイン技術を活用した現場の見える化を推進しています。BIM/CIMとは、建築物や土木構造物の設計・施工・管理の各段階で3Dモデルを活用し、情報を一元管理する手法です。
この技術により施工計画の精度が向上し、作業工程の効率化と省人化が可能になります。デジタルツインでは、現実の現場状況をリアルタイムで3Dモデルに反映させることで、現場の問題点を早期に発見し、迅速に対策を講じることが可能です。
大林組では、BIM/CIMによって設計変更の影響を即座に把握し、現場の混乱や手戻り作業を減らしています。これにより人員配置の最適化が図られ、省人化につながりました。
出典参照:建設現場のデジタルツインを構築できる「デジタルツインアプリ」を開発|株式会社大林組
大成建設は独自に情報収集WEBカメラシステムを開発し、建設現場の省人化を支えています。このシステムは、複数のWEBカメラを設置し、現場の作業状況や進捗をリアルタイムでモニタリングする仕組みです。映像はクラウドに保存されているためどこからでもアクセス可能で、遠隔地の管理者が効率よく現場を監督できます。
現場の状況を常に把握できるため、作業員の配置や工程管理を最適化できます。従来は現場監督が直接足を運び確認していた作業も、遠隔監視によって少人数で行えるようになりました。結果として管理業務の省人化が進み、現場全体の効率化に寄与しています。
大成建設のWEBカメラシステムは、省人化を図りながら安全性と品質管理の両立を目指す建設DXの一環として、今後も進化が期待される技術です。
出典参照:施工管理業務の飛躍的な効率化を実現する情報収集WEBカメラシステムを開発 |大成建設株式会社

建設業における省人化の実現には、業務工程ごとに適したデジタル技術を導入することが求められます。まず、設計段階ではBIMを用いて図面と施工計画を一体化し、関係者間での情報共有を円滑に進める体制を整える必要があるでしょう。施工現場では、スマート建機や遠隔操作システムを活用し、少人数でも安全かつ効率的に作業を進められるようにします。
ここでは、建設DXを活用した省人化における具体的な作業フローを順を追って解説します。
省人化の第一歩は設計・計画段階のデジタル化です。従来の手書き図面や紙ベースの設計書は、修正や情報共有に多くの手間と時間を要しました。BIM(Building Information Modeling)やCIM(Construction Information Modeling)といった3Dモデリング技術を活用すれば、建物や構造物の設計情報をデジタルデータとして一元管理できます。
これにより設計ミスや手戻り作業のリスクが低減し、設計変更の影響範囲も即座に把握することが可能です。さらに、関係者間でのリアルタイムな情報共有が促進されるため、意思決定のスピードも向上します。結果として、設計部門の作業負担が減り、必要な人員数を抑えながら質の高い設計成果を出せるようになります。
設計・計画の段階からデジタル化を進めたあとは、現場作業における自動化と遠隔化が次の課題です。ICT建設機械や自動化重機は掘削・整地などの土木作業を自動制御で行えるため、省人化に大きく貢献しています。これにより、重労働や危険を伴う作業を機械に任せ、人間は機械の監督や遠隔操作に注力できます。
遠隔化は人手不足解消だけでなく、安全性向上にも貢献するのがポイントです。危険区域における作業や高所作業を遠隔操作で行うと事故リスクが減少し、労働環境の改善が期待できます。
これらの自動化・遠隔化技術は、省人化に加えて作業の均質化や精度向上にも寄与します。熟練度に左右されない安定した作業品質を確保できるため、作業員の技術差を吸収しつつ、少人数体制でも効率的に現場を進められます。
建設現場では工程管理と進捗管理が複雑であり、従来は紙ベースや口頭での情報共有に依存していました。これが情報の遅延や誤伝達を引き起こし、結果的に無駄な作業や人手の過剰配置を招いていました。
DXの推進をしてクラウド型のプロジェクト管理ツールや専用アプリを活用して工程情報をデジタル化すると、関係者全員がリアルタイムで進捗状況を把握できます。これにより、現場の作業員や管理者は作業内容や優先順位を瞬時に共有し、無駄な待機時間や重複作業が減少します。
さらに、AIを活用した進捗分析や予測も活用されつつあり、工程の遅れや問題発生の兆候を早期に可視化できるのがポイントです。これにより、対策を迅速に講じて現場を円滑に進められるため、人手の効率的な配置につながります。
建設業界の省人化は現場作業だけでなく、事務作業やバックオフィス業務の効率化も欠かせません。従来は書類の作成や承認などの業務に多くの人員が割かれていましたが、これらもデジタルツールを活用して統合・自動化が進んでいます。
クラウド型の業務管理システム・電子契約・RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)を活用すれば、単純作業や繰り返し業務の自動化が可能です。これにより、担当者はより高度な業務や現場支援に集中できるため、組織全体の生産性が向上します。
また、情報の一元管理は情報漏えい防止やコンプライアンス遵守にも役立つのでチェックしてみましょう。データの整合性が保たれて必要なときにすぐアクセスできるため、意思決定の質も向上します。
近年のテレワーク普及の波は建設業界にも影響を与えています。DXの活用によって遠隔監督やリモートワークが可能となり、従来は現場に常駐しなければならなかった管理者の業務スタイルに変化が起きました。
例えば、現場の進捗状況や安全確認をクラウド上でリアルタイムに共有し、遠隔地から監督業務を行うケースが増えています。これにより管理者は複数の現場を効率的に管理でき、現場に直接出向く頻度を減らせます。
また、設計者や事務の従業員もリモートで業務を行いやすくなり、柔軟な働き方が実現することもポイントです。遠隔監督の導入は人員の柔軟配置を促し、省人化に貢献しながら働きやすい環境づくりにもつながります。
建設業界における省人化は重要な課題でありながら、かかるコスト面の負担を懸念する企業も少なくありません。そこで、低コストで建設DXを推進しながら省人化を実現する具体的な方法を理解することが重要です。
ここでは、費用対効果を意識した4つの具体策を詳しく解説します。これらを踏まえれば、コストを抑えながら生産性や安全性を向上できるため、現場の省人化を進める指針となるでしょう。
建設現場の管理業務は多岐にわたり、紙ベースの記録や情報共有では手間と時間がかかるなど人的ミスも起きやすい環境です。クラウド型の現場管理システムやスマホアプリを導入すると、施工記録・工程管理・作業報告などをリアルタイムで一元管理できます。
このようなシステムは初期導入費用が抑えられ、月額利用料のプランが多いので運用コストも予算に合わせやすいのが特徴です。また、現場の作業員や管理者はスマートフォンやタブレットで手軽に操作可能で、特別な専門知識がなくても扱えるものが多い点も魅力です。
クラウドを活用することで現場データが即時に共有され、作業の重複・遅延・報告漏れを防げます。データがクラウドに保存されるため災害や紛失のリスクも低減し、長期的な運用コストの削減にもつながります。
遠隔臨場とは、現場に直接赴かずとも映像やセンサーを通じて状況をリアルタイムに確認し、指示や検査を行う方法です。カメラやウェアラブル端末を活用することで、管理者や専門家が遠隔地から作業状況を把握できます。
ウェアラブル端末は作業者の動きやバイタルサインを計測できるため、安全管理や労務管理に役立ちます。これにより、現場の人数を減らしつつ安全を確保できるのがポイントです。
導入コストは機器の購入や通信環境の整備が必要ですが、クラウドサービスや既存インフラを活用すれば初期費用を抑えることも可能です。長期的に見れば作業時間短縮や事故防止による損失低減が大きく、省人化とコスト削減の両立が期待されます。
ドローンの普及により、測量や現場の進捗管理にかかる人手と時間を削減できるようになりました。ドローンは高所や広範囲の撮影が容易で、従来の測量作業の負担軽減につながるでしょう。
ドローンによる撮影データは3Dモデルの作成や進捗確認に活用でき、現場の「見える化」できます。これにより現場監督は現地に何度も赴く必要がなくなり、作業の効率化と省人化につながります。
ドローン自体の購入費用や操縦者の育成にコストはかかりますが、外注を活用したりレンタルサービスを利用したりすることで初期費用を抑えられます。また、測量の精度向上や作業時間の短縮により、トータルでコスト削減効果を得やすいのも特徴です。
近年ではスマートフォンにLiDAR(光検出と測距)センサーが搭載され、簡易な3D測量が可能になりました。専用の3D測量アプリを利用することで、高価な機器を導入しなくても現場で手軽に正確な測量データを取得できます。
この技術により測量作業の省力化が実現し、人手不足の現場でも効率的なデータ収集が可能となります。従来の測量技術と比べて操作がシンプルなため、専門の技術者が少なくても利用できる点もメリットです。
導入コストはスマートフォンの購入費用とアプリ利用料に限られ、既存の従業員が利用しやすいことから教育コストも抑えられます。小規模から中規模の現場において特に効果的な方法で、省人化に寄与しつつ測量精度の維持も期待できます。
建設DXの推進により、省人化を実現している企業は少なくありません。共通して見られるのは、単なるツールの導入にとどまらず、業務プロセス全体の見直しと現場の課題に即したシステム運用を行っている点です。こうした取り組みは、慢性的な人手不足に対応しながらも品質を確保する手法として注目されています。
ここでは省人化に成功した代表的な企業の事例を見ていきましょう。
鹿島建設は建設機械の自動化に積極的に取り組み、自動化施工システム「A4CSEL」を開発しました。このシステムは複数の建設機械を連携させて自動運転させる技術で、土工や整地などの重労働工程を人手を介さずに実施します。
この取り組みにより危険が伴う現場作業の安全性が向上した上、作業員の負担軽減と人手不足の解消につながりました。さらに施工の精度も均一化され、品質の安定に寄与しています。
導入の背景には高齢化や労働力不足があり、自動化技術の活用が生産性向上と省人化の両立に不可欠との判断がありました。鹿島建設の例は建設機械の自動化が人手不足対策の有効手段となることを示しています。
出典参照:A4CSEL 現場の工場化を実現|鹿島建設株式会社
中原建設は3次元CIM(Construction Information Modeling)統合モデルを積極的に導入し、測量・設計・計画から施工までの一連の工程をデジタル化・効率化しています。
このモデルにより現場の地形や構造物の情報を3次元で可視化し、従来の2次元図面に比べてミスや手戻りの削減が可能になりました。また、関係者間でリアルタイムに情報共有ができるため、意思決定の迅速化にも寄与します。
結果として作業工数の削減が実現し、省人化に直結しました。加えて計画段階での不具合検証や改善が容易となり、現場でのトラブルを未然に防ぐ効果も得ています。
出典参照:「3次元CIM統合モデル」の活用により自社の建設DXを推進することで建設業界全体のDXを牽引、その取組が「第1回埼玉DX大賞」において「奨励賞」を受賞!|中原建設株式会社
ハゼモト建設ではスマートフォンやクラウドシステムを駆使し、これまで複数人で行っていた現場作業を1人で完結できるよう改善しました。
現場での進捗管理・報告書作成・材料発注などをスマホアプリ上で連携させ、作業の省力化と情報共有を推進しています。これにより現場作業の無駄を排除し、少人数でも効率的に業務を遂行できる環境が整いました。
ハゼモト建設の事例は、手持ちのスマートフォンや既存システムを有効活用し、無理なく省人化を推進する方法として参考になるでしょう。
出典参照:職人さんのDX化 |ハゼモト建設株式会社

建設DXの推進は、人手不足に悩む建設現場にとって不可欠な施策です。鹿島建設の自動化施工システム・中原建設の3次元CIM活用・ハゼモト建設のスマートフォン活用など、各企業の成功事例に共通するのはデジタル技術を活かしながら現場の効率化と安全性を両立している点です。
今後も新たな技術やサービスが登場するため、最新情報をキャッチアップし、自社のDX推進計画に反映させることが省人化成功のカギとなるでしょう。こうした視点で建設DXを推進すれば、未来の建設現場で必要な人手を効率よく確保できる環境を築けます。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
