建設DXでペーパーレス化は可能?メリットや成功のステップを解説
建設

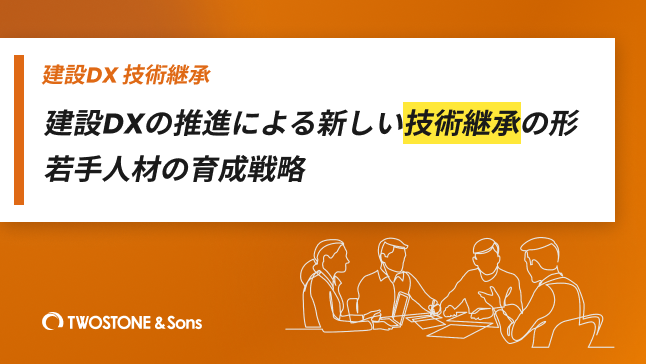
建設業界は長年にわたり、多くの熟練技術者が現場の経験や知識を蓄積し、技術を継承してきました。しかし、昨今では高齢化が進み、若手の技術者が減少している現状に直面しています。若手人材の育成や技術継承が遅れると、現場の品質や安全性に影響を与える可能性が高まります。そこで、建設DXの推進によって新しい技術継承の形を模索し、効果的な若手育成戦略を実現することが求められているのが現状です。
この記事では、建設DX推進による技術継承の必要性と、その背景を詳しく解説します。さらに、若手人材が技術を習得しやすい環境を作るための具体的な方法や戦略も示し、現場の持続的な成長に寄与する情報をお伝えします。この記事を読むことで、建設業の未来に向けた技術継承のあり方とDXを活用した若手育成のポイントを理解できるでしょう。

建設DXの推進は、単なる効率化やコスト削減の枠を超え、構造的な人材問題にも切り込む手段として注目されています。特に現場における熟練技術者の高齢化と若手不足という二重の課題が深刻化している中、技術継承の仕組みが不十分なままだと、企業の技術力や施工品質に悪影響を及ぼしかねません。
そこで、建設DXを通じて技術やノウハウをデジタルで記録・共有し、持続可能な形で次世代へ伝える取り組みが求められています。
建設業界は長年にわたり、熟練工の手作業や経験に基づく技術に依存してきました。しかし、その多くが定年を迎え、現場から離れていく傾向があります。若手の技術者は少なく、加えて経験を積む機会も限られているため技術力の低下が懸念されるようになりました。
こうした状況に対応するためには、建設DXの推進が重要です。デジタルツールを使って技術を見える化し、標準化することで技術の質を維持しながら若手に継承しやすくなります。熟練技術者の経験やノウハウをデジタル化することで、現場の高齢化による技術力低下をカバーできるようになります。
現場では、特定の技術やノウハウが一部の熟練者に集中しがちです。技術の属人化が進むと、その技術者が抜けると同時に技術が失われるリスクが高まります。属人化を防ぐには、技術やノウハウを組織的に管理し、共有する仕組みづくりが欠かせません。
建設DXの推進は、この課題を解決するカギとなります。クラウド・AI・デジタルツインといった技術を活用し、技術データ・施工マニュアル・作業プロセスを一元管理して誰でもアクセス可能な状態に保つことが大切です。これにより技術の継承が組織的に行われ、属人化を防止できます。
若手技術者の育成においては、伝統的な「現場でのOJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)」だけでは対応しきれない現状があります。現場での学びの機会が減少し、多忙なスケジュールや安全面の配慮から実践経験を積む機会が減るケースが増えました。
DX推進によりバーチャルリアリティ(VR)や拡張現実(AR)を使ったトレーニングが可能になれば、現場に近い形で技術を習得できる環境が整います。また、映像記録や遠隔指導の活用で、熟練者が離れた場所からも若手の指導に参加することが可能です。これにより若手は効率よく学習でき、技術継承が促進されます。
建設業界はこれまで属人的な技術伝承に頼ってきたため、技術継承を組織的に支援する仕組みが不十分なままです。個別の職人技術やノウハウが蓄積されていないケースも多く、体系的な教育プログラムも整備が遅れています。
建設DXの推進により、これらの技術継承の仕組みを構築できます。クラウドベースのナレッジ共有ツールやドキュメント管理システムを導入すれば、技術情報の蓄積と共有が進むでしょう。これに加え、教育プログラムのデジタル化やオンライン学習を活用すれば、継続的な技術研修も可能になります。
建設業界が持続的に発展するには、若手人材の育成と技術継承が不可欠です。熟練技術の消失は品質低下や安全リスクの増加に直結し、業界の競争力を弱めます。DX推進により生み出された新しい技術継承の仕組みは、この課題を克服する手段となるでしょう。
デジタル化により技術やノウハウの標準化が進み、誰もが効率的に学べる環境が整備されます。若手人材は実践的な知識や技能を早期に身につけることが可能になり、建設業の未来を支える基盤になるでしょう。持続性を確保しながら人材育成を行うことは、DX推進のメリットの1つです。
建設DXを活用して技術継承を行うことで、単に過去の知見を残すだけでなく、若手人材の即戦力化を促し、教育の効率も高まります。動画や3Dモデル、クラウドシステムを用いたナレッジ共有により、従来属人的だった技術の伝達が誰もがアクセス可能な形で可視化されるためです。
これにより組織の知的資産が強化され、品質の均一化や施工精度の安定といった波及効果が現場全体に広がります。
建設現場の技術は従来、個々の熟練者の経験や感覚に依存しがちでした。しかし、こうした属人的な技術は標準化が難しく、再現性に課題がありました。建設DXを推進すると、熟練者のノウハウや施工手順をデジタル化し、体系的に蓄積できるのがポイントです。
デジタル化された技術資産はいつでもアクセスできるため、過去の成功例や問題点を振り返りながら再現性の高い施工が可能です。設計データや施工マニュアル、映像記録なども一元管理できるため、現場ごとに異なる作業のばらつきを抑制して品質の均一化も実現します。
このように、技術資産の蓄積は施工品質の安定化だけでなく、工程短縮やコスト削減にもつながります。結果的に現場の効率化を促進し、企業競争力の維持につながるでしょう。
建設業界では若手技術者の確保と育成が大きな課題となっています。従来の現場教育は長期的で習得に時間を要し、離職率が高い傾向も見られました。しかし、DXを活用することで学習環境が変わり、育成スピードと定着率が向上します。
具体的には、VRやARを用いたシミュレーション教育を使って、若者に実践的な経験を与えることが可能です。デジタルマニュアルや動画解説はいつでも参照できるため、自主的な学習もできます。これにより、若手は効率的に技術を習得し、現場で即戦力となれるのがポイントです。
結果として職場環境の改善やモチベーション維持につながり、離職防止にも役立つでしょう。
技術の属人化は、建設業界の大きな問題です。一部の熟練技術者にノウハウが集中すると、その人材の退職や転職で技術が失われ、品質低下や作業の遅延が発生しやすくなります。建設DXを推進すると、こうしたリスクを抑制できます。
技術情報や作業手順をクラウドに集約して共有プラットフォームを整備すれば、複数人が同じ技術を学べる環境を構築できるのがポイントです。標準化された手順や検証データを基に作業を進めれば、誰が作業しても一定の品質を確保できます。
また、作業状況のリアルタイム監視やAIによるデータ分析も、ミスや異常検知に役立ちます。有効活用して、品質管理を効率化しつつ属人化によるトラブルを未然に防ぎましょう。属人化リスクの低減は、現場の安全確保や顧客満足度の向上に直結します。
若手人材の不足は、建設業界全体の課題です。業界のイメージ改善や働きやすさの向上が進まなければ、優秀な人材を確保し続けることは難しくなります。建設DXの推進は、こうした課題に対する有効な打開策です。
デジタル技術を活用した現場は、若手にとって魅力的な職場環境を生み出します。重労働や危険作業の軽減が進み、効率的かつ安全な働き方が実現可能になるからです。また、最新技術を取り入れた先進的な企業イメージは、求職者の関心を高めます。
こうしたメリットが積み重なり、業界全体の魅力向上と採用力強化を促進します。結果的に、建設業は持続可能な人材確保が可能となり、社会的な信頼も高まるでしょう。

建設業界における技術継承の難しさは、暗黙知が多く体系化されていない点にあります。
これを解決するには、建設DXによる情報のデジタル化だけでは不十分です。知識を誰でもアクセス・再利用できる形に整理し、OJTや研修など実践的な教育活動に活かせるように設計する必要があります。加えて、記録された技術情報を現場で活用しながら、日々の業務に自然に組み込むことが求められます。
技術継承の第一歩は、これまで蓄積された技術情報やノウハウを体系的に保存することです。デジタルアーカイブは、設計図・施工マニュアル・過去のプロジェクト記録など、多様な資料を電子化して一元管理できます。
こうしたアーカイブをクラウド上に構築すると、時間や場所を問わず必要な資料を参照できます。さらに、従来の紙媒体や属人的な情報管理と比較して、検索性や共有性が向上することもポイントです。デジタルアーカイブは単なる保管庫に留まらず、技術継承の基盤となる知識ベースとして機能します。
また、文書だけでなく施工時の写真・動画・検査データも一緒に管理できるため、現場の実態を把握しやすくなります。若手従業員が視覚的に学びやすくなり、理解度も得られるのがメリットです。
建設技術の多くは、言葉や図面だけでは十分に伝えきれない繊細な手作業や工程を含みます。そのため、映像教材を活用して技術の流れや細かなポイントを可視化し、再現性を高める取り組みが効果的です。
映像教材は熟練技術者の作業を高精細に撮影し、具体的な手順や注意点を詳細に解説します。若手は現場で直接教わるのが難しい部分を自習でき、習熟度を上げられます。
さらに、映像を使うことで技術の標準化も促進されるのもポイントです。熟練者の技術のばらつきや個人差を減らし、一定の品質で作業を行うための基準として機能します。映像教材はオンデマンドで視聴可能なため現場作業の合間に復習もでき、効率的な学習を実現します。
現場では突発的な疑問や不明点が生じやすく、熟練者がすぐに対応できない場合もあります。こうした状況に対応するため、チャットボットを活用して技術的な質問やマニュアル検索を支援する仕組みが注目されています。
チャットボットには、過去の技術情報・FAQ・マニュアルをあらかじめ登録し、自然言語での質問に対して的確な回答を自動的に提示できることが特徴です。これにより現場作業員や若手技術者は即座に必要な知識にアクセス可能になり、作業の遅延やミスを減らせるでしょう。
また、チャットボットは24時間稼働して複数のユーザーに同時対応できるため、現場の柔軟なサポート体制を強化できるのもメリットです。問い合わせの履歴は蓄積され、改善ポイントや頻出質問の把握にも役立ちます。技術継承の現場支援として有効なツールといえます。
建設技術の習得には実際の現場体験が欠かせません。しかし、現場の安全管理や人手不足の影響で、若手が多くの実地経験を積む機会が減少しています。ここでVR(仮想現実)技術が力を発揮します。
VRを活用すると、現場のリアルな環境や作業工程を仮想空間に再現し、安全に繰り返し体験することが可能です。これにより、危険を伴う作業もリスクなしに学習できるため、若手の技術習得を加速させられます。
また、VRは実際の施工状況をシミュレーションできるため、ミスを防ぐための判断力や対応力を養う訓練に最適です。複雑な施工手順も視覚的に理解できるため、技術の定着率を高める効果が期待されます。
職人技の多くは感覚や経験に基づくため、技術継承が難しいという課題があります。ここにAI(人工知能)を活用し、職人の作業をセンサーや映像で解析して数値化する取り組みが注目されています。
AI解析では、作業の動作パターン・力加減・速度などをデータとして抽出し、最適な施工方法や技術ポイントを科学的に示せるのがポイントです。これにより、属人的な技術が客観的に評価され、誰でも再現できる標準手順として整備されます。
数値化された技術は教育教材に組み込みやすく、若手は効率的に習得できるようになるでしょう。また、AIによる異常検知や品質評価も可能になり、施工品質の安定化に寄与します。
技術継承をスムーズに進めるには、データの記録や共有、検索性などに優れた専用ツールの導入が不可欠です。例えば、作業手順を動画で残せるアプリや、点群データ・BIMモデルを共有できるプラットフォーム、進捗をリアルタイムで確認できるダッシュボードなどが有効です。
これらを現場で活用することで、熟練者のノウハウが組織内に蓄積され、新人教育や業務の標準化にも活かされます。
Photoruction Buildは、建設現場の情報管理とコミュニケーションを支援するクラウド型プラットフォームです。写真・図面・進捗情報を一元管理し、関係者全員がリアルタイムで共有できる環境を提供します。
このツールの強みは、現場の状況を写真やコメントで直感的に記録しやすい点です。熟練者が持つノウハウを撮影した画像に添えて残せるため、技術の見える化が促進されます。
また、スマートフォンやタブレットからのアクセスが簡単で、現場での活用がスムーズに行えます。若手社員も使いやすいインターフェースが設計されており、情報共有の障壁を減らすのもメリットです。
さらに、進捗状況のタイムライン表示や報告書の自動生成機能があり、工事管理の負担を軽減しながら技術継承に必要な資料を効率的に蓄積できます。プロジェクト全体の透明性も向上し、トラブル予防にもつながります。
出典参照:Photoruction|株式会社フォトラクション
施工体制クラウドは施工管理に特化したクラウドサービスで、特に施工体制台帳のデジタル化に強みがあります。これにより、複雑な現場体制や作業内容をわかりやすく管理できます。
このサービスでは、作業指示・安全管理資料・技術継承に必要なマニュアルなどを一括管理し、現場関係者全員が情報にアクセス可能です。従来の紙ベースの管理から脱却し、効率的な情報伝達を実現します。
また、クラウド上のデータは常に最新の状態に保たれるため、変更や更新も即座に反映されるのがポイントです。若手技術者は最新の施工情報やノウハウにリアルタイムでアクセスでき、技術習得のスピードが高まります。
操作画面は直感的で、建設業界特有の専門用語や書式にも対応しています。これにより未経験者でも導入しやすく、幅広い人材が活用可能です。
出典参照:施工体制クラウド| 株式会社建設システム
技術継承を目的としたツールを導入する際は、ただ高機能であるかどうかではなく、現場で実際に使われるかどうかが重要です。操作のしやすさ、現場との連携性、今後のスケールアップへの柔軟性などを考慮しながら、将来的な保守性や継続運用のしやすさまで見通す必要があります。
また、導入後の教育体制やマニュアルの整備も忘れてはならず、現場が自主的に活用できる環境づくりが成功へのカギとなります。
まずは、熟練者の持つ知識やノウハウを漏れなく正確に記録できるかを重視しましょう。建設技術は細かな手順や注意点が多く、単なる文章や図面だけでなく写真や動画、コメントでの詳細な説明が求められます。
ツールが多様なデータ形式に対応し、現場の状況をリアルに反映できるかを確認しましょう。操作が複雑すぎると記録が疎かになるため、使い勝手の良さもツール選びの重要な基準です。
さらに、保存した情報を検索しやすく、後から参照しやすい構造であることもポイントです。知識が埋もれてしまわないために、データベース機能やタグ付け機能の有無もチェックしましょう。
技術継承の本質は、若手や未経験者が使いこなせて初めて意味を持ちます。そのため、ユーザーインターフェースは直感的で操作しやすいデザインであることが求められます。
初心者が迷わず利用できるように、画面構成やメニューの配置がわかりやすく、必要な操作が少ないツールを選ぶとよいでしょう。モバイル端末対応があると、現場での活用が一層進みます。
また、ヘルプ機能・マニュアルの充実度・サポート体制も確認してみましょう。導入後のトレーニングや疑問解消がスムーズに行える環境が整っていれば、定着率が高まります。
操作性の良いツールは現場の負担を軽減し、積極的な情報共有を促す効果があるのもポイントです。若手の技術習得を支援するための必須条件といえます。
導入したツールは単発の利用で終わらず、長期的に運用し続けることが必要です。そのためには、将来的な更新や改善に対応できる体制が整っているかを検討しましょう。
クラウドサービスであればベンダーが定期的に機能改善やセキュリティ対策を行う場合が多いですが、契約内容やサポート体制を事前に確認しておくことが望ましいです。
また、現場のニーズ変化に応じてカスタマイズ可能なツールは、より柔軟な運用につながります。ユーザーからのフィードバックを反映できる仕組みがあることも重要です。
さらに、社内での運用担当者を決め、適切な教育を実施することも欠かせません。継続的な利用促進と更新管理を通じて、技術継承の効果をより大きくしていきましょう。
建設DXの推進によって、技術継承の手法がより実践的で効果的なものへと変化しています。例えば、熟練者の作業工程を記録して若手に伝える仕組みや、施工履歴を3Dデータで可視化して教育に活用する方法など、各社の取り組みにはさまざまな工夫が見られます。成
功事例を通じて学ぶことで、自社の導入において参考になる要素を抽出しやすくなり、実効性の高い戦略を描く手がかりとなるでしょう。
清水建設株式会社では、AR(拡張現実)技術を用いた施工支援により、現場の理解度と安全性の向上を図っています。具体的には、設計図やマニュアルだけでは伝えきれなかった細かな配管ルートや作業手順を、3D映像として投影することで、作業員が直感的に理解しやすくなりました。若手や経験の浅い作業員にとっては、熟練者の技術や判断を現場で即時に再現できる手段となっており、技術継承の効率化にもつながっています。
また、AR上で表示される情報は現場の状況に応じて柔軟に切り替えることができるため、臨機応変な対応が可能です。施工ミスの削減や作業時間の短縮に寄与しているだけでなく、標準化された作業手順の共有にも貢献しており、全体の作業品質の安定化にもつながっています。この取り組みは、AR技術を単なる補助的ツールにとどめず、建設現場の中核的な支援ツールへと進化させている好例です。
三井住友建設株式会社は道路舗装などで必要な締固め作業の技能をAR技術で可視化し、技術継承の支援を進めています。熟練者の作業を3D映像で再現し、若手技術者がその動作を繰り返し学べる環境を整備しました。
この取り組みでは、締固め機械の操作や圧力のかけ方といった細かな技術を映像化することで、経験不足の若手でも標準的な技術を身に付けやすくなっています。映像教材としての活用により、現場にいない状況でも自主学習ができるようになりました。
結果として、属人化していた技術が共有され、作業の均質化や安全性の確保が実現しました。後継者育成の一助として、ARによる技術継承が注目されています。可視化によって技術の「ブラックボックス」を解消する取り組みは、他の分野にも応用可能な先進事例です。
出典参照:締固めの範囲と時間を見える化する「ARコンクリート締固め管理システム」を開発|三井住友建設株式会社
戸田建設株式会社は、施工に関する豊富なノウハウをデジタルデータベース(ナレッジDB)に蓄積し、必要な情報を検索して利用できるシステムを構築しています。熟練者の経験がデータベース化され、若手が現場で疑問を感じた際にすぐに参照できる環境が整いました。
ナレッジDBには施工手順の詳細・注意点・過去の事例分析など多岐にわたる情報が含まれており、これが技術の蓄積と継続的な改善につながっています。検索機能が充実しているため、現場のニーズに即した情報が迅速に手に入ることも大きなメリットです。検索性が高いため新人からベテランまで幅広い層が使いやすい仕組みとなっており、現場主導でPDCAサイクルを回しやすくなっています。
この仕組みは現場での即時対応力を高めるだけでなく、若手の自主的な学習意欲を引き出します。同社はナレッジ共有を通じて組織全体の技術レベルが底上げされ、安定した施工品質を保つ基盤が築かれました。
出典参照:戸田建設のDropbox活用が拡大、電帳法対応から建設現場のナレッジ蓄積まで|戸田建設株式会社
建設現場には言語化されにくい経験知が多く存在し、それらをいかにデジタル技術で記録し活用するかが重要です。
しかし、無理なシステム導入やツールの押し付けでは、現場からの反発を招くリスクもあります。そのため、若手が使いやすく、ベテランも納得できるツールや仕組みを丁寧に選定し、現場と一体となって推進する姿勢が求められます。継承を日々の業務に自然に溶け込ませる工夫が成果につながるでしょう。
建設現場で培われる熟練者の経験や技術は、しばしば言語化されていない暗黙知で構成されています。これは単なる手順書には表れない繊細な感覚や判断力を含みます。こうした知識を形式知に変換しない限り、DXツールでの活用は難しいでしょう。
このため、動画やARを活用した映像教材の作成や、熟練者へのインタビューで技術の背景・ポイントを具体的に記録することが必要です。また、作業現場での動作や判断の理由を言語化し、図解や写真と組み合わせてドキュメント化すると理解度が高まります。
形式知化が進むことで若手が体系的に学びやすくなるだけでなく、品質の均一化も期待できます。暗黙知を形式知へ変換する過程は時間や労力を要しますが、長期的な技術継承の基盤作りに欠かせません。
技術継承において、デジタルツールの使いやすさが重要です。デジタル社会で育ってきた若手が抵抗なく活用できる設計でないとせっかくの情報が活かされず、現場での実践につながりにくくなります。
スマートフォンやタブレットで簡単にアクセスできる操作性や、直感的に理解できるUI(ユーザーインターフェース)を備えたシステムを選定しましょう。また、通信環境が整っていない現場でも利用可能なオフライン機能があると利便性が増します。
こうした環境整備により、デジタル機器の扱いに慣れた若手は学習に前向きになり、技術継承がスムーズに進みます。DXはツールの導入にとどまらず、現場の文化や働き方を変えていく取り組みです。
技術継承の推進は単なるツールの導入だけでは成り立ちません。日々の業務の中に継承プロセスを組み込み、習慣として定着させる必要があります。
例えば、施工計画の段階で熟練者が動画やデジタルマニュアルを確認し、若手と共有する仕組みを作ることが挙げられます。現場作業後には振り返りミーティングを設け、実際の経験をデジタル記録に残す運用も効果的です。
また、定期的な技術講習やオンライン学習のスケジュールを組み込み、継続的な教育を保証する体制が欠かせません。こうした継承プロセスを業務フローに組み込むことで、自然な形で技術の蓄積と共有が進みます。

建設DXの推進は、従来の技術継承に新たな可能性をもたらしています。熟練者の暗黙知を形式知としてデジタル化し、若手技術者が使いやすい環境を整備しながら、継承プロセスを業務の中に組み込むことが成功のカギとなります。
この取り組みにより技術の属人化が減り、品質の安定化や若手の育成スピードの向上につながります。さらに、建設業界全体の競争力と魅力も高まるでしょう。記事で紹介したポイントを参考にし、効率的かつ効果的な技術継承の仕組みを築いていくことが重要です。
今後もDX技術の進歩に伴い、新しい技術継承の方法は進化し続けます。現場の未来を見据え、デジタルツールを上手に活用していくことが、持続可能な建設業界を支える基盤となるでしょう。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
