建設DXでペーパーレス化は可能?メリットや成功のステップを解説
建設

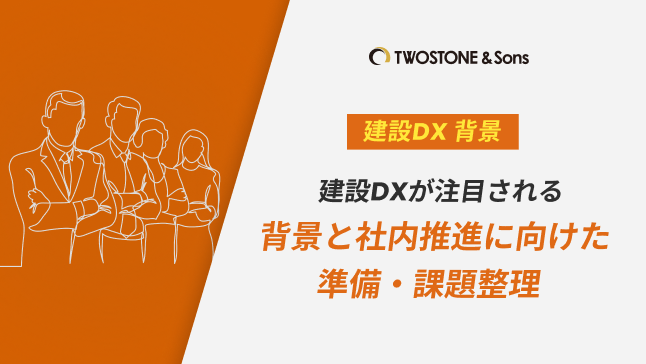
建設業界は今、深刻な人手不足や働き方改革の必要性、老朽化したインフラへの対応、そして生産性の低さと脱炭素社会の実現といった多くの課題に直面しています。これらの問題は現場の負担を増やし、業界全体の持続可能な発展に影響を及ぼすようになりました。こうした状況を背景に建設DXの推進が注目され、技術やデジタルツールの活用によって業務効率化や安全性の向上が期待されています。
本記事では、建設DXがなぜ今注目されているのか、その背景にある課題を明確にした上で社内での推進に向けた準備と課題整理について詳しく解説します。最後まで読むことで読者は自社の現状を見つめ直し、効果的なDX推進のために必要なポイントを理解しましょう。

建設DXが注目される理由は、建設業界が直面している人手不足や高齢化、長時間労働などの構造的課題を解決し、将来の持続可能な業界運営を可能にする手段として期待されているからです。これまでアナログ中心だった建設現場において、デジタル技術を活用することで情報共有の迅速化や業務の効率化が進み、品質管理や安全性の向上にもつながると評価されています。
ここでは、注目の背景を具体的に見ていきましょう。
建設業界では、長年にわたって人手不足が深刻な課題となっています。高齢化により熟練技術者の引退が相次ぐ一方で、若年層の新規参入は少なく、技能継承や人材確保が困難な状況です。現場では限られた人員で複数の工程をこなす必要があり、無理な作業負担が事故や品質低下のリスクを高める要因となっています。
こうした中で注目されているのが、建設DXの推進です。ドローン測量や自動化建機、AIによる工程最適化などを導入することで、省人化と作業の効率化が実現します。また、遠隔支援やクラウド型管理システムの活用により、熟練者の知見を複数の現場に共有できる体制づくりも可能です。これらの取り組みにより、人手不足の中でも安全かつ高品質な施工体制を維持できる道筋が見えてきています。
建設業界は、長時間労働や休日の少なさといった働き方に関する課題を長く抱えてきました。特に若年層の離職理由の多くは労働環境への不満であり、人材確保や定着率の向上には抜本的な改革が求められます。国の政策としても、建設業における時間外労働の上限規制や週休2日制の導入が進められており、企業側には早急な対応が迫られています。そこで有効となるのが建設DXの推進です。
例えば、モバイル端末を活用することで現場と事務所の連携が円滑になり、無駄な移動や待機時間も減少します。加えて、遠隔監督ツールにより本社から現場の進捗確認が可能となり、柔軟な働き方の実現にもつながります。結果として、労働環境が改善され、従業員のモチベーション向上や定着促進が期待できるでしょう。
日本全国に存在する道路・橋・トンネル・ダムなどの社会インフラは、その多くが1960年代から1970年代にかけて整備されたものであり、現在では老朽化が進行しています。
これらの構造物の多くは、設計耐用年数を迎えつつあり、今後一層の維持管理と更新が必要とされています。定期的な点検と的確な補修は安全性を保つ上で欠かせませんが、従来の目視や手作業による点検は労力がかかり、見落としのリスクもあるため、効率的な代替手段が求められています。
そこで注目されているのが、建設DXによるインフラメンテナンスの革新です。ドローンによる高所撮影、3Dスキャンによる構造把握、IoTセンサーによる振動やひび割れのリアルタイム監視などが導入されつつあります。これにより、劣化の兆候を早期に検知し、対策を講じることが可能になります。
建設業は他産業に比べて生産性の低さが指摘されてきました。手作業やアナログな管理方法が多いため、効率化の余地が大きいといえるでしょう。こうした課題が明確になるにつれて、生産性向上に向けた対策が急務となっています。
建設DX推進により、工程管理や設計、施工の各段階でデジタル技術を取り入れられます。BIM(ビルディング・インフォメーション・モデリング)やCIM(コンストラクション・インフォメーション・モデリング)を活用することで、設計情報と施工現場の連携が可能です。また、AIを活用した最適化や自動化技術で無駄な作業や手戻りを減らせます。これにより、工期短縮やコスト削減が見込まれるため、生産性の改善に直結します。
地球温暖化対策として、脱炭素社会の実現は社会全体の喫緊の課題です。建設業界でもCO2排出量削減に向けた取り組みが必要とされていますが、従来の工法や資材の使用では環境負荷を抑えられません。
建設DXは環境負荷の見える化や省エネルギー施工、再生資材の利用促進に活用されています。施工計画段階からCO2排出量をシミュレーションし、最適な工法を選択できるようになるほか、現場の資材管理をデジタル化して無駄を減らすことも可能です。こうした取り組みは環境負荷軽減とコスト効率化を同時に実現し、持続可能な建設業の推進に役立ちます。
建設業界が抱える人材不足や長時間労働などの課題に対応するため、政府は関係省庁と連携しながら建設DXを支援する政策を進めています。これらの政策は、現場の業務負荷軽減だけでなく、生産性の向上やデジタル人材の育成といった中長期的な視点に基づいて構築された政策です。
また、地域間格差の是正や環境負荷低減など、社会全体への波及効果も意識された施策として展開されています。現場が抱える具体的なニーズに即した制度設計により、DX推進のハードルを下げることを目指しています。
国土交通省は、2016年に「i-Construction」という政策を打ち出しました。これはICT(情報通信技術)やロボット技術を活用して建設現場の生産性を向上させることを目的としています。i-Constructionの特徴は、測量・設計・施工・検査の各工程においてデジタル技術を積極的に導入し、省人化や品質向上を実現しようとしている点です。
さらに2023年度には、進化版となる「i-Construction 2.0」が発表され、AIやデジタルツイン、BIM/CIMのさらなる活用により、建設プロセス全体の高度化とリアルタイムな意思決定支援を目指しています。
国土交通省はi-Constructionの推進にあたり、標準仕様の整備や技術研修の支援も行っているため、各企業が導入しやすい環境を模索できるのがポイントです。こうした政策支援は、DX推進の実践を後押しし、建設業の生産性向上に欠かせない柱となっています。
出典参照:i-Construction|国土交通省
出典参照:「i-Construction 2.0」の2025年度の取組予定をまとめました|国土交通省
法務省は2020年に「世界最先端デジタル国家創造宣言」を発表し、日本のデジタル社会の基盤強化に取り組んでいます。これは行政手続きのデジタル化やデータ利活用の促進を目的とした政策であり、建設DXにも深い影響を与えています。
建設業界においても、デジタル文書の活用や電子契約の導入が広がりました。これにより契約業務の効率化が進み、現場でのペーパーレス化も推進されています。また、行政との連携もデジタル化され、許認可申請や検査報告がオンラインで完結するケースが増加しています。
こうした動きは建設現場の業務負担軽減に直結し、現場と事務のスムーズな連携を可能にしました。法務省の取り組みは建設DXの推進を加速させ、業界全体のデジタル化基盤の強化に寄与しています。
出典参照:令和2年7月17日閣議決定「世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」|法務省
経済産業省は2018年に「DXレポート」として知られる報告書を公表しました。その中で、「2025年の崖」という表現でレガシーシステムの老朽化による経済的損失のリスクを警告しています。これは、既存のITシステムの更新遅れが企業の競争力低下や経済の停滞を引き起こす恐れがあるという指摘です。
建設業界も例外ではなく、これまでのアナログ的な業務運用や古い情報システムの維持に多くのコストとリスクを抱えています。経済産業省はDX推進を急ぐよう強調し、IT投資の見直しや最新技術の導入を促しています。これにより業務効率化だけでなく、データを活用した新たなビジネスモデル構築の可能性も広がりました。
出典参照:DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」克服とDXの本格的な展開|経済産業省
中小企業の多い建設業界において、DXの推進には初期投資への不安や社内リソースの不足といった現実的な障壁が存在します。こうした背景を受けて、国や自治体、業界団体などが中心となって、多様な支援制度を整備しました。
具体的には、補助金や税制優遇措置、技術面でのコンサルティング支援などが用意されており、単なる資金援助だけでなく、DX推進に必要な知識・ノウハウの提供も行われています。
これは、中小企業や小規模事業者がITツールを導入する際の費用を補助する支援事業です。建設業におけるDX推進の一環として、施工管理システム・設計ソフト・現場報告アプリなどのIT導入に活用できます。
申請対象となるITツールはあらかじめ登録されており、補助率は導入費用の1/2以内です。IT導入支援事業者のサポートを受けながら進められるため、導入後のフォロー体制も充実しています。
この制度を利用すれば初期投資の負担を抑えられ、建設現場のデジタル化を着実に進める足掛かりを作れます。特に小規模な施工会社や個人事業主が利用しやすく、最新のITツールにアクセスできる点が大きなメリットです。
出典参照:IT導入補助金 |独立行政法人中小企業基盤整備機構
国土交通省は建築分野におけるGX(グリーントランスフォーメーション)およびDX推進事業を展開し、持続可能な社会実現と産業革新を目指しています。この事業の一環として、建設業界に特化した補助金制度が設けられました。
補助金の対象は、環境負荷の低減やエネルギー効率の改善、さらにはDX関連の技術導入など多岐にわたります。施工現場の自動化機器導入やBIM/CIMの活用、現場管理のIT化に使うことが可能です。
補助金の申請には計画書の作成や経費明細の提示が必要ですが、国土交通省主導の制度であるため信頼性が高く、資金面での後押しが強力です。これにより、DX推進のための新技術導入がより現実的になります。
日本政策金融公庫は中小企業の成長支援を目的に、IT関連投資向けの融資制度を設けています。建設業でもICT活用やデジタル技術導入を計画している企業に対し、低利かつ長期の融資が受けられます。
この資金はソフトウェアやハードウェアの購入費用、システム開発費、さらには従業員の研修費用にも充てられるため、幅広いDX推進活動に対応しているのがポイントです。融資条件や返済計画も現場の状況に応じて柔軟に設計されており、無理のない資金計画が立てられます。
融資を活用することで、自己資金だけでは難しい大規模なIT投資も実行可能です。また、金融機関との信頼関係構築にも役立つため、長期的な経営安定にもつながります。
出典参照:IT活用促進資金|日本政策金融公庫

DX推進を着実に進めるためには、まず自社の現状を正確に把握する必要があります。現場と本社、各部門間での業務の進め方や情報の流れを明確にし、どこに課題やボトルネックがあるかを客観的に分析することが求められます。
そのためには、業務プロセスの見直しやITツールの活用状況の棚卸し、社員へのアンケート調査などが効果的です。また、業界全体の動向や他社の取り組みを参照することも有効です。正しい現状認識は、実効性のあるDX戦略の出発点となります。
DX推進の第一歩は、社内のDXに対する認知度を確認することです。現場の作業者や管理者、経営層それぞれがDXの意義や必要性をどの程度理解しているかを調査しましょう。アンケートやインタビューを活用して、DXの概念や具体的な施策に対する理解度や関心度を可視化します。
認知度が低ければ、啓発活動や研修の計画を優先的に行う必要があります。一方で、認知度は高くても実際の施策が進んでいないケースも多いため、実施済みのDX施策や導入済み技術の有無も同時に把握しましょう。
推進状況を把握する際には、どの部門でどのようなITツールやデジタル技術が活用されているか、具体的な利用頻度や効果測定結果も確認します。これにより、DXの推進に成功している分野と遅れている分野を明確にし、重点的な支援が必要な領域を特定できます。
建設業界では、現場の作業者と経営層のDXに対する認識の違いが推進の障害になることが少なくありません。経営層は経営戦略の観点からDXを推進しようとする一方で、現場ではデジタル化による作業負荷や慣れないツールの導入に対する強い抵抗感が生まれるかもしれません。
この温度差を客観的に把握するためには、定期的なヒアリングやワークショップを開催し、双方の意見や要望を聞き取る場を設けることが効果的です。相互理解を深めることで導入計画の現実性を高め、現場の声を反映したDX施策を立案できます。
また、現場と経営層の意識ギャップが大きい場合、コミュニケーションの円滑化や教育体制の整備が必要となります。双方の認識がすり合わないまま進めるとDXツールの定着や活用に支障が生じるため、温度差の可視化は重要なステップです。
DX推進における課題の1つが、建設業界におけるIT人材の不足です。伝統的に手作業や現場経験を重視する文化が強く、IT技術に精通した人材の採用や育成が十分に進んでいない現状があります。
そこで、まず社内にどの程度のITに強い人材がいるかを正確に把握する必要があります。具体的には、その人数やスキルレベル、業務上の配置状況まで詳細に調査しましょう。これらの専門知識を持つ人材が不足していると、DXの企画や運用、さらにはトラブル対応にまで大きな支障が生じる可能性があります。
IT人材の確保が難しい場合は、外部のITコンサルタントや専門ベンダーの活用を検討すべきです。また、社内の既存社員に対してIT教育や資格取得支援を積極的に進めることで、内部リソースの底上げを図れます。こうした調査と対策が、DX推進の成功に直結します。
多くの建設会社には、長期間にわたり使用されてきたレガシーシステムが存在します。これらは特定の業務に特化している反面、拡張性に乏しく、他の最新システムとの連携に支障をきたす恐れがあります。
まずは現状使用しているシステムを洗い出し、機能面や運用面での問題点を詳細に整理することが重要です。具体的な課題としては、データの二重入力や手作業による情報転記、リアルタイムでの情報共有ができない点などが挙げられます。
さらに、これらのシステムの維持にかかるコストや、故障や障害が発生する頻度も把握しましょう。これらの情報を基に、システムの更新や刷新の優先順位を適切に設定する必要があります。建設DXを推進するためには、柔軟かつ効率的に対応できるIT基盤の構築が欠かせません。レガシーシステムの課題を明確にすることが、成功するDX計画の土台になります。
建設DXの推進に伴ってITシステムの利用範囲が拡大し、クラウドサービスやモバイル端末の活用も増加しています。情報漏えいリスクやサイバー攻撃のリスクも高まるため、セキュリティ体制の見直しが必須です。
まずは既存の情報管理ルールやアクセス権限の設定、データバックアップ体制を確認しましょう。加えて、社員のセキュリティ意識や教育状況も把握し、不足している場合は強化策を講じます。
システム面では、最新のセキュリティ対策ソフトの導入やネットワーク監視の実施、脆弱性診断の定期的な実施が求められます。また、セキュリティ事故発生時の対応フローや報告体制の整備も重要なポイントです。
セキュリティ体制が脆弱だとDX推進が妨げられるだけでなく、顧客や取引先からの信用低下にもつながるため、早期の見直しと強化が不可欠です。
建設DXを成功に導いた企業には、自社の現状と課題を客観的に捉え、分析に基づいた戦略を策定した共通点があります。表面的なツール導入にとどまらず、現場の声や運用実態を反映したDX施策を構築したことで、スムーズな定着と業務改善が実現されました。また、導入前後での効果測定を継続的に行い、PDCAを回す体制を整えている点も重要な要素です。
ここでは、背景を深く分析し、効果的にDXを推進した代表的な建設企業の事例を紹介します。
鹿島建設株式会社は、施工管理のデジタル化を積極的に推進し、作業効率の改善を図っています。具体的には、施工現場での人員配置や作業進捗をITシステムで一元管理し、リアルタイムに状況を把握できる仕組みを構築しました。
この取り組みにより現場作業のムダや重複を削減し、作業員の適切な配置を実現しています。結果として、工期の短縮やコスト削減につながっています。また、デジタル化されたデータを活用することで、次回以降のプロジェクトでも同様の効率的な運用が可能となりました。
鹿島建設の事例は、背景分析を丁寧に行い、具体的な課題に応じたシステム導入が成功のカギとなったことを示しています。施工管理のデジタル化は、従来の属人的な管理から脱却し、作業効率と品質を両立させる重要なポイントです。
出典参照:人、モノ、建設機械、環境等の現場情報を一元管理し、建設現場の高度な「見える化」を実現|鹿島建設株式会社
前田建設工業株式会社は、ICT技術を活用した現場運用の標準化を進めています。個々の現場で効果的なDX施策を実施した後、それらの成功事例を横展開する仕組みを整備しました。
この取り組みでは、現場ごとの課題や状況に応じたICTツールや運用ルールを柔軟に適用しながら全社的に再現性の高い運用体制を構築しています。これにより、現場ごとのバラツキを減らし、品質や効率の安定化を図りました。
また、現場担当者が新しい技術やツールをスムーズに取り入れやすい環境作りにも注力し、教育やサポート体制の強化を実施しています。ICT活用を全社レベルで体系的に進めることで、DX推進の持続可能性を高めた点が特徴です。
出典参照:ICT活用による効率・品質向上|前田建設工業株式会社
西松建設株式会社は、リモート技術支援の導入により現場に足を運ばずにサポートを行う体制を構築しました。これは遠隔地にある複数の現場を効率的に管理するための施策で、現場技術者が直面する課題に迅速に対応できるようになりました。
遠隔地からの技術指導や問題解決は、移動時間やコストの削減につながります。さらに、複数の現場を同時にサポートできるため、企業全体の対応力が向上しました。
この仕組みは、高度な通信環境や専用のITツールを駆使し、技術支援の質を保ちながら効率を追求しています。西松建設の事例は、DXを推進して現場運営の効率化を図り、人的リソースの最適配分に成功した例として注目されています。
出典参照:ホイールローダ遠隔操作システムを山岳トンネル工事の実施工へ試験導入 |西松建設株式会社
建設DXには多くの期待が寄せられていますが、その導入・運用には現場特有の制約や人材不足、経営層と現場の温度差といった複数の課題が存在します。また、ITに不慣れな職人や従業員が多い現場では、導入当初から新しいツールを定着させることが難しいという側面も見逃せません。
こうした問題に対応するには、段階的な導入や現場向けの研修の実施、専門家のサポート活用などが有効です。現実に即した対策を講じることで、建設DXの成果を安定して発揮する基盤が整っていきます。
ここでは、建設DX推進を阻む代表的な課題とそれらに対処する具体的な方法について解説します。
建設DXの推進において多く挙げられる課題の1つが、推進コストに関する不安です。新しいシステムや機器の購入、社員の教育、運用体制の整備には一定の初期投資が求められます。これにより、小規模事業者や予算が限られている企業では推進に踏み切れないケースが多いです。
しかし、長期的に見れば、DXによる業務効率化や品質向上がコスト削減に結びつきます。まずは必要最小限の機能から導入し、段階的にシステムを拡充する戦略が効果的です。補助金や助成金制度の活用もコスト面の負担を軽減する手段となります。これにより初期投資を抑え、リスクを分散しながらDXを推進できるでしょう。
費用対効果の見える化により、経営層や現場担当者の理解と協力を得やすくなります。透明性の高いコスト管理は、推進の後押しにつながるでしょう。
建設DX推進は経営層だけの問題ではなく、社内全体で理解と協力を得ることが不可欠です。特に現場の作業者や管理者がDXの目的や利点を理解していないと、現場導入時に抵抗が生まれやすくなります。
そこで、社内に対してDX推進の意義や目標を明確に伝える活動が必要です。説明会やワークショップ、インターネット上での情報発信など多様な手段を活用しましょう。具体的な成功事例や効果を共有すると、実感を持って受け入れやすくなります。
また、DXによる業務の変化や役割の変動についても早期に説明し、不安を和らげる工夫も重要です。これにより、社員のモチベーションを保ちつつ新たなシステムの導入にスムーズに対応できる環境を整備できます。
建設DXの推進は、一度に大規模に取り組もうとすると失敗リスクが高まります。特に技術導入に不慣れな企業では、全社導入前に小規模なプロジェクトで試行することが効果的です。
まずは一部の現場や部門でDXツールを導入し、運用方法や問題点を検証しましょう。成功体験を積み重ねることで社内の信頼感が高まり、次の段階へ円滑に進められます。また、現場からのフィードバックを反映し、システムや運用ルールを改善できるメリットも大きいです。
こうした段階的な取り組みは、DX推進の成功率を高めるだけでなく、社員のITリテラシー向上や新たな働き方の定着にも寄与します。結果として、組織全体でDXが自然に浸透しやすくなります。
建設DX推進の障壁の1つは、社員のITリテラシー不足です。特に以前から紙や手作業中心の業務に慣れている現場作業員や管理者にとって、新しいデジタルツールの操作は大きな負担となることがあります。
そのため、社員が安心してデジタル技術を扱えるように、社内で教育体制を整備することが不可欠です。具体的には、現場で役立つ内容に特化した研修や操作マニュアルの配布、さらにいつでも学習できるeラーニングの導入など、多様な学習支援を用意します。
特に実際の業務を想定したハンズオン形式のトレーニングは、理解度を高める効果が高いです。加えて、一度の教育で終わらせず、定期的なフォローアップ研修や相談窓口を設置することも重要です。こうした継続的なサポートにより、社員は安心してDXツールを活用しやすくなり、現場全体のデジタル化が促進されるでしょう。
建設DXを推進して成果を出すためには、現場の運用改善と経営層の戦略的意思決定を効果的に連携させる仕組みが不可欠です。現場での実態や課題を経営層がリアルタイムで把握できなければ、適切な投資や対策の検討は困難になります。
そのため、現場からのデータや報告を即座に共有できるダッシュボードの導入が効果的です。このような仕組みを活用すれば、経営層はプロジェクトの進捗やリスクを常に把握し、迅速かつ的確な意思決定が可能になります。
さらに、現場担当者が経営戦略の議論に参加する機会を設けることも重要です。これにより現場のニーズや課題が直接反映され、経営と現場のギャップを減らせます。組織全体で目標を共有し意識統一を図ることで、建設DXの推進方向にズレが生じず、一体感のある改革が進むでしょう。

建設DXの推進は容易ではありませんが、課題を正しく認識し、1つずつ着実に対策を講じることで成功に近づきます。コスト不安の軽減や社内周知、小規模推進の積み重ね、IT教育の充実、そして現場と経営の連携体制の構築はいずれも効果的な対応策です。
こうした対策を基に建設DXの背景を理解し戦略的に推進すれば、業務効率や品質の改善だけでなく、持続可能な組織体制の実現にもつながります。記事の内容を参考にしながら、各社の状況に応じた具体的な取り組みを検討してみてください。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
