建設DXでペーパーレス化は可能?メリットや成功のステップを解説
建設

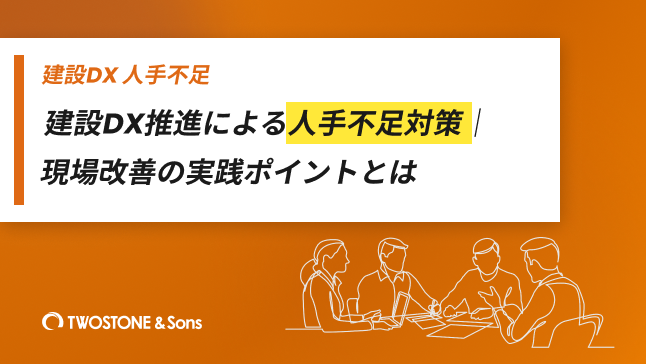
建設業界は長年にわたり、人手不足という深刻な問題に直面しています。高齢化の進行や若年層の就業意欲の低下など複合的な要因が絡み合い、現場の労働力確保が困難になっています。
このような状況に対応するために、建設DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進が注目されるようになりました。デジタル技術の活用で作業の効率化や省力化が進み、現場改善につながる具体的なポイントを理解すれば、限られた人材を効率よく活用できます。
本記事では、建設業界の人手不足の原因を詳しく解説し、DX推進による現場改善の実践ポイントを紹介します。これにより、持続可能な労働環境の構築や業務の効率化を図りましょう。

建設業界で人手不足が続いている背景には、単なる人員減少だけでなく、労働環境や社会構造の変化、高齢化、若年層の建設離れといった複合的な要因が重なっています。特に今の時代、長時間労働や休日の少なさ、危険を伴う作業が多いといったイメージは若年層の就業意欲を低下させる可能性があり、新規採用が難しい状況です。
実際に、国土交通省の「建設労働需給調査結果(令和7年5月)」では8職種の不足率が0.5%で前年同月(0.4%)より拡大しており、特に東北など地域格差が顕著です。
これらの問題を構造的に理解することが、根本的な対策を講じる上での出発点となります。
出典参照:建設労働需給調査結果(令和7年5月調査)|国土交通省
建設業界では熟練労働者の高齢化が進み、引退が相次いでいます。熟練者の技術やノウハウは現場の質を保つために不可欠ですが、その継承が十分に進んでいません。高齢者が退職し、経験豊富な人材が減ることで作業の効率や安全性が低下するかもしれません。
この問題に対しては、技術のデジタル化や自動化を進めることが有効です。建設DXの推進により、熟練技術のデータ化や作業手順の標準化が可能です。これによって熟練者が不在でも一定の品質を保つ体制が構築できます。
若年層が建設業界以外の選択肢を多く持つようになり、現代のライフスタイルにあった会社を選ぶようになってきていることも人手不足の要因の1つです。そのため、新規就業者の確保が難しくなりました。
ここでも建設DXの推進が役立ちます。デジタル技術によって現場作業の負担を軽減し、働きやすい環境を整えることが可能です。スマート機器や遠隔作業の導入で作業効率が上がり、残業削減や安全性の向上に結びつきます。これにより若年層の関心を引き、就業意欲を高めることが期待されます。
日本の建設業界では技能実習制度に依存する傾向があります。外国人実習生が労働力として一定の役割を果たしていますが、この制度は人材の定着や長期的なスキル向上には限界があります。技能実習生の入れ替わりが激しく、現場の安定した人材確保にはつながりにくい状況です。
この問題を解消するには、DXを活用して効率的な現場管理や教育体制を整備することが重要です。デジタルツールを使った作業管理や教育コンテンツの共有により、新人や外国人労働者も早期に戦力化できます。AIやIoTを活用した作業の自動化が進めば、人的依存度を下げてより安定した生産体制を築けます。
建設現場では、慢性的な人手不足に直面しており、従来の人海戦術だけでは対応しきれない状況が続いています。この問題を打開するために、現場の作業負担を軽減し、限られた人員でも対応可能な体制を整備する必要が出てきました。この体制整備によって、少人数でも高い生産性を維持できる柔軟な現場体制が実現可能となります。
ここでは、具体的な現場の人手不足対応策として作業自動化やデジタルツール導入、ICT連携などのポイントを詳しく解説しているのでチェックしてみましょう。
建設現場では重労働や繰り返し作業が多く、体力的な負担が離職の大きな要因となっています。これに対し作業の自動化は、作業負担を減らし労働環境を改善する有効な手段です。
自動化技術の1つに、ロボットやドローンの活用があります。ロボットは高所作業や危険を伴う作業を代替し、ドローンは現場の測量や点検作業を迅速にできるのがポイントです。人手がかかる作業を減らせば、熟練者の負担が軽減し離職を防げます。
また、機械化された重機の操作支援システムや自動運転技術も広がりました。作業効率を保ちながら身体的な負担を抑制でき、若年層や女性、高齢者を含む多様な人材が働きやすい環境を実現できるでしょう。
現場での作業環境を改善するためには、デジタルツールの導入が欠かせません。従来の手書きや口頭指示中心の作業から脱却し、情報共有や管理をデジタル化することで、働きやすさが向上します。
具体的には、スマートフォンやタブレットを使った作業指示や報告のデジタル化などです。作業の進捗や問題点をリアルタイムで共有でき、現場の効率化を促進します。スマートフォンやタブレットは若者にとって日常生活で扱い慣れているため、スムーズに導入することができるでしょう。さらに、デジタルツールはコミュニケーションの円滑化にも活用可能です。遠隔地にいる管理者との連携が容易になって質問や相談もしやすくなるため、若手社員のスムーズな現場適応が期待できます。
建設現場だけでなく、オフィス側の業務効率化も人手不足解消に欠かせません。ICT(情報通信技術)を活用した連携により、現場とオフィスの情報共有や業務フローを円滑にします。
現場で収集したデータや報告書をクラウド上で一元管理し、オフィスの関係者が即座にアクセスできる環境は、意思決定の迅速化になるのがポイントです。現場の問題点を早期に把握し対策を講じられるため、作業の停滞や手戻りを減らせます。
また、ICT連携により請求書作成や労務管理などのバックオフィス業務も自動化・効率化が可能です。これらの業務にかかる負担が減れば現場により多くの人材を配置できるため、全体の生産性向上に寄与します。
従来の建設現場では、書類作成や情報共有に多くの手書き作業や現場間の移動が発生していました。これらは時間的なロスやヒューマンエラーの原因となり、効率低下やストレス増加につながっています。
電子化を進めることで、書類の作成・管理・共有がデジタル上で完結します。ペーパーレス化により書類の紛失や情報の遅延を防ぎ、スムーズな業務推進が可能です。また、タブレット端末を活用すれば現場で即時に情報入力や確認ができ、手戻りを減らせます。
これにより迅速な問題解決ができ、作業効率の向上につながるでしょう。移動時間の削減は作業員の負担軽減にもつながり、現場全体の働きやすさを向上させます。
現代の働き方に適応するためには、柔軟な勤務体制の整備が不可欠です。建設DXの推進によりクラウドサービスとモバイル端末の活用が進み、場所や時間にとらわれない働き方になります。
クラウド上に情報やシステムを集約すればどこからでもアクセスでき、現場だけでなく自宅や出先からも業務が可能です。これにより、勤務時間の調整や在宅勤務の導入も検討しやすくなります。モバイル端末を使えば、現場でのデータ入力やコミュニケーションもスムーズに行え、リアルタイムの情報共有が促進されます。
こうした環境整備により子育てや介護などの事情を抱える社員の働きやすさを高め、多様な人材を活用できる点もポイントです。

建設業界の人手不足は長期化しており、現場の効率化と労働環境の改善は待ったなしの課題です。その解決策として建設DXの推進が期待されています。しかし、ただデジタル化や自動化を導入すれば良いわけではなく、現場の実情を踏まえた段階的で戦略的な進め方が重要です。
ここでは人手不足時代における建設DX推進の手順を具体的に解説し、実践しやすい方法を示します。
DX推進の出発点は、現場で働く人々の生の声を把握することです。現場の状況や課題は机上の空論では見えてきません。作業員・管理者・設計担当者など職種や立場によって感じる問題点は異なるため、多面的に意見を集める必要があります。
ヒアリングでは、日々の作業で何に時間や労力がかかっているか、デジタル化で改善したい点は何かを具体的に聞き取りましょう。こうした情報収集により、課題の優先順位や解決すべきポイントが明確になります。加えて、現場の意見を尊重することで推進への理解や協力も得やすくなります。
現場からの声を集めたら、次に改善すべき項目を職種や工程別に分類しつつ優先順位をつけて整理します。建設現場は多様な作業が複雑に絡み合っているため、すべてを同時に改善するのは現実的でないでしょう。
まずは人手不足や作業効率に影響が大きい部分から着手するのが効果的です。例えば、重労働で離職率が高い工程や手作業が多く非効率な管理作業などが挙げられます。こうした重点領域を明確にすることで、限られたリソースを効率よく使えます。
DX推進には初期投資や運用コストがかかります。これに対して経営層が費用対効果を明確に理解し納得することが成功のカギです。費用対効果の見える化は、導入前におこなうべき重要な工程です。
効果としては、作業時間の短縮、人手不足の緩和、品質向上などを数値化して示します。例えば、作業自動化によって1日あたりの作業時間が何時間削減されるか、これによりどれほどの人件費削減が見込まれるかを算出しましょう。
こうした数字をわかりやすくまとめ、具体的な投資回収期間やROI(投資利益率)を提示することで経営層の意思決定を後押しします。
DX推進は、全社一斉に大規模に展開すると失敗リスクが高くなります。初期段階では小規模なプロジェクトや特定の現場に限定し、成功体験を積み重ねる方法が望ましいです。
小さな成功は推進効果を見える化しやすく、関係者のモチベーション向上につながります。成功事例が社内に広がれば推進の勢いが増し、抵抗感を和らげられます。
段階的に範囲を広げながら運用ノウハウを蓄積すれば、最終的には全社的なDX推進にスムーズにつなげられます。無理なく着実に進める戦略が、長期的な成功には欠かせません。
建設DXは技術的な専門知識や最新のITツールの活用を伴うため、社内だけで完結するのは難しい場合があります。そこで外部パートナーと連携し、体制を強化することが推進の効果を高めるポイントです。
ITベンダーやコンサルティング会社、システムインテグレーターなどの専門企業は、導入計画の策定・システム開発・運用支援を担います。専門的な知見を活用することで、導入リスクの軽減や効率的なプロジェクト運営が可能になります。
人材の確保が困難な中でも、建設DXを推進することで業務の効率化や省力化に成功している企業が多数存在します。
実際に、デジタル化された情報共有によって現場と本社の連携がスムーズになり、意思決定の迅速化や業務負担の平準化が可能になったケースもあります。これらの事例は、人手不足が避けられない現代において、DX推進による改革がいかに実効性を持つかを示しているといえるでしょう。
大林組株式会社では、現場管理の効率化を目的としてMR(Mixed Reality)技術を活用した施工管理アプリ「holonica™」を自社開発しました。このアプリは現実空間に3次元データを重ねて表示できるため、設計図と実際の施工状態を重ねて確認できます。
この取り組みのポイントは、単なるツールの導入にとどまらず施工管理という業務の根幹にDXを組み込んだ点です。情報の見える化により若手でも精度の高い管理が可能となり、人手不足の中でも安定した施工体制を維持できる仕組みが構築されました。
出典参照:施工場所にBIMデータを重ね合わせるMR施工管理アプリ「holonica™」を開発 | ニュース | 大林組株式会社
清水建設株式会社では、人材育成の効率化を目的として現場に行かずに施工技術を学べるVRコンテンツや映像教材を整備しました。これにより、ベテランからの属人的なOJTに頼らず、誰でも一定水準の技術を短期間で習得できる環境を実現しています。
この仕組みにより若手の即戦力化が進み、現場での人手不足の緩和も実現しました。また、教材の質を標準化できるため、教える人によってばらつきが出ることも防げます。教育体制のデジタル化は、長期的な人材確保に向けた基盤強化にも直結しています。
出典参照:デジタル人財育成プログラム「シミズ・デジタル・アカデミー」を開講 | 清水建設株式会社
鹿島建設株式会社では、全社的にデジタル基盤の整備を進め、現場業務の可視化と一元管理を実現しました。具体的には、各現場からの情報をリアルタイムで共有できるシステムを整え、オフィス側との連携強化によって少人数でも対応可能な体制を築いています。
以前は、現場の報告や進捗管理が紙ベースや個別ツールで運用されていたため、情報が分散し、対応に時間がかかっていました。現在は、クラウド上でデータを一括管理し、関係者が同じ情報を共有できるようになったため、判断の迅速化と対応力の向上が図れています。
この結果、現場での人員数を抑えつつも品質管理や安全対策の水準を維持することが可能になりました。
出典参照:鹿島グループ 中期経営計画(2024~2026)|鹿島建設株式会社
建設DXは人手不足への対策として有効ですが、その推進と活用には慎重な検討と段階的な展開が求められます。新しい技術を導入する際に現場の理解や習熟度が不十分であると、かえって業務全体の流れが滞る恐れもあるでしょう。また、ツールやシステムが現場の実情と合っていなければ、運用自体が形骸化してしまう可能性もあるため、推進前にしっかりとフィット感を確認する必要があります。
ここでは、建設DXによる人手不足対策を実現するために押さえておくべき注意点を3つの視点から紹介します。
建設DXを推進する際、多くの企業が最初に直面するのがコストの課題です。新たなシステムや機器の導入、外部パートナーとの契約、従業員への研修費用など初期段階ではさまざまな費用が発生します。このコストがネックとなり、DXに踏み切れない企業も少なくありません。
そこで重要なのが、段階的な推進という視点です。いきなり全社的な推進を目指すのではなく、まずは特定の現場や工程に限定して試験的に推進し、その効果を数値で検証しましょう。推進効果が確認できれば社内の理解も得やすくなり、次のステップへ進みやすくなります。
DXの推進には、システムやデータに関する知識を持つ人材が不可欠です。しかし、建設業界では従来からの職人気質が強く、ITに関する専門人材が社内に少ないという現状があります。このような状況で外部に頼りきりになると、コスト増やノウハウの蓄積不足といった新たな問題が生じます。
そのため、DX人材の採用と育成は中長期的な視点で計画することが必要です。特に、現場の管理職や中堅社員にDXの基礎を理解してもらうことが重要です。計画的な人材戦略によって、自社内にDX推進を担う核となる人材を確保できるようにしていきましょう。
新たなツールや仕組みを導入する際には、それを使いこなすための教育とマニュアルの整備が欠かせません。せっかく優れたシステムを導入しても使い方が浸透しなければ意味がありませんし、現場の混乱を招くリスクも高まります。
ここで大切なのは、ツールの提供と同時に業務フローに沿った教育と操作手順を明文化することです。教育とマニュアルの整備は一度で完結するものではなく、ツールの更新や業務の変化に応じて継続的に見直す必要があります。現場のフィードバックを受け取りながら柔軟に改善し、実用性の高い教育体制を構築していきましょう。

建設業界では人手不足が長期的な課題として深刻化しています。そのような中で、建設DXは単なる一時的な効率化策ではなく、持続可能な業務体制を築くための根本的な変革手段といえます。
ただし、DXの推進には初期費用の負担、IT人材の不足、現場での混乱といった課題も存在する点に注意しましょう。これらの課題を乗り越えるには、段階的な推進、計画的な人材育成、実務に即した教育とマニュアル整備が不可欠です。
現場の声を取り入れながら実用性と再現性の高い形でDXを進めていくことで、確実に人手不足の課題に対処する道が開けてきます。業務の属人化を解消し、誰でも一定のパフォーマンスを発揮できる体制が整えば、これまで取りこぼしていた人材の活用も実現できるでしょう。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
