建設DXでペーパーレス化は可能?メリットや成功のステップを解説
建設

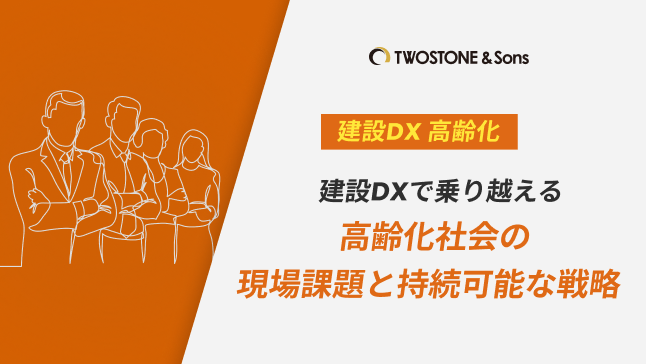
建設業界では、急速に進む高齢化が現場運営に大きな影響を与えています。熟練作業員の引退が進んで若手の担い手不足が深刻化する中、これまでのやり方だけでは持続的な現場維持が困難になってきました。
このような課題に対し、注目されているのが建設DXです。建設DXは単なるデジタル化を超えて、人材不足・作業負担の軽減・ナレッジの継承といった課題を解決する可能性を秘めています。
本記事では、高齢化がもたらす現場課題の実情を明らかにした上で、それを乗り越えるために必要な建設DXの視点と実践的な戦略を解説します。課題の本質を理解し、持続可能な建設体制を目指すためのヒントをつかむ一助となれば幸いです。

建設業界では従事者の高齢化が年々進んでおり、労働力構成に深刻な歪みが生じています。国土交通省の調査によると、建設業従事者のうち60歳以上の比率は年々増加しており、今後さらにその割合が高まると予測されています。
この高齢化の進行は単に人手不足を招くだけでなく、技術力・安全性・若手育成の面にも影響を及ぼすようになりました。ここでは、現場で直面している具体的な課題を項目別に整理し、それぞれにどのようなリスクが潜んでいるのかを明らかにします。
高齢作業員の増加により、現場の作業継続に支障が出てきています。長時間の立ち仕事や高所での作業など、建設現場は体力を要する工程が多いため、年齢とともに身体的負担が大きくなるでしょう。
実際に、60歳を超える作業員の多くがフルタイムでの就業や夜間作業に限界を感じており、継続的な稼働が難しくなっています。このような状況が続くと、作業日数の減少や突発的な人員不足を招き、工期の遅延や工程の見直しといった影響を避けられません。
企業としては、こうした体力的制約を前提に業務配分や就業時間を見直す必要があります。また、物理的な負荷を軽減する機器やアシスト装置の導入を検討し、高齢者が無理なく働けるように環境を整える必要があります。
熟練作業員の退職に伴い、長年蓄積された技術や経験が失われつつあります。特に施工上のコツや安全管理の判断、現場対応の柔軟さといった「暗黙知」はマニュアルではカバーしきれない重要な知識です。
このようなノウハウが共有されないまま失われると若手作業員の育成が遅れ、現場の対応力が低下します。結果として、施工品質のばらつきや安全性の確保が難しくなり、組織全体の力が弱まる要因となります。
こうしたリスクを防ぐには、ナレッジを形式知として記録・蓄積する仕組みが不可欠です。建設DXの推進により、映像・音声・3Dデータを活用したノウハウのデジタル化が実現しつつあります。現場に依存しない継承体制の構築が、持続的な組織力の維持に直結します。
高齢作業員と若手従業員との間で、意思疎通の機会が減っている現場も少なくありません。その背景には、年齢や価値観のギャップに加えて現場業務の分業化や繁忙によって雑談や相談の時間が確保しづらくなっている現状があります。
意思疎通の不足は、コミュニケーションの断絶だけでなく作業ミスや事故のリスク増加にもつながります。また、若手側が不安や疑問を抱えたまま業務にあたることで、離職率の上昇にもつながる点に注意が必要です。
このような問題に対し、建設DXではチャットツールやオンライン会議、現場支援アプリの活用などコミュニケーション環境の整備が進められています。距離や年齢の壁を越えて、情報を双方向でやり取りできる仕組みを整えることが、組織全体の連携強化に寄与します。
高齢化に伴って作業の正確性や判断力の低下が見られるケースも増えており、安全性の確保と品質の維持が両立しにくくなっています。特に高所作業や機械操作など注意力と体力が求められる作業では、ヒューマンエラーのリスクが高まっています。
安全性を確保するためには、現場管理体制の見直しが不可欠です。加えて、建設DXの活用によりIoTセンサーによる危険検知やリアルタイムのモニタリング、遠隔支援といった技術的な補完が可能になります。
品質についても、BIM(Building Information Modeling)を用いた設計・施工の一元管理が有効です。デジタルによって設計と現場のズレを最小化し、施工精度の向上と安全性の確保を両立する体制を築けます。
高齢従業員の退職により、慢性的な人手不足が発生しています。この影響で、計画どおりに現場が進まず、工期の遅延や顧客への対応の遅れといったリスクがあるので注意しましょう。
特に地方や中小規模の建設会社では新たな人材確保が難しく、既存人員に業務が集中してしまう状況が続いています。これでは、働き方改革の流れに逆行するばかりか従業員の疲弊と離職の連鎖を生む原因にもなります。
こうした課題に対し、建設DXは人材に依存しすぎない仕組みづくりの根幹となるのが特徴です。作業の自動化や業務の平準化、クラウドを活用したリソース管理などにより少人数でも現場を維持できる体制が整えられます。
建設業界では高齢化が深刻な課題となっており、特に技能労働者の平均年齢が年々上昇しています。この現状においては、安全性の確保、作業効率の維持、そして技術継承の仕組みづくりが求められます。そこで有効な対策となるのが建設DXの推進です。DXは高齢作業員の身体的負担を軽減し、情報共有の効率を高め、世代を超えたナレッジの移行をスムーズにするでしょう。
ここでは、DXの観点から高齢化に起因する主要課題へのアプローチを具体的に確認していきましょう。
高齢作業員の身体的な負担は、安全性や労働継続に直結する重要な問題です。特に重量物の持ち運びや長時間にわたる立ち仕事や反復的な動作は、高齢者の体力では対応が難しくなるかもしれません。そのため、作業支援ロボットや自動運搬機器の導入が注目されました。
現場では運搬や積み下ろしの一部を自動化することで体力の消耗を抑え、作業者の安全を確保できます。また、ウェアラブル端末によって作業者の動きをリアルタイムで把握し、負荷のかかりすぎを警告するシステムも導入可能です。こうしたDX技術は現場での労働環境を改善するだけでなく、労災リスクの低下にもつながります。
高齢者の退職により、技術やノウハウが継承されずに消えていく課題が深刻化しています。暗黙知と呼ばれる言語化されていない技術的判断や工夫は、従来のOJTでは十分に伝えきれない場面が多く存在します。
この問題に対し、建設DXでは動画や3Dモデルを活用したノウハウの可視化・蓄積が注目されるようになりました。施工手順や判断基準を記録し、クラウド上に蓄積して社内共有することで、経験が浅い若手でも現場で判断しやすい環境が整います。また、AR技術を使った遠隔指導やMRによる作業支援も、現場での技術習得を効率化する手段として有効です。
世代間の価値観やITスキルの差は、現場における連携の障壁となることがあります。高齢作業員は経験に基づく判断に長けている一方、若手は新しいツールへの適応力に優れる傾向があります。この違いを互いに補完し合う仕組みを構築することで、チーム全体の生産性を向上できるのがメリットです。
建設DXを推進し、作業の進捗や状況をリアルタイムで共有するプラットフォームを整備すれば、口頭や紙ベースのやり取りが不要になります。その結果、双方のコミュニケーションの負担が軽減され、誤解や伝達ミスも減少します。
高齢作業員にとって、現場状況の把握や判断には精神的な負担がかかります。特に視認性の低い図面や複雑な情報整理は対応に時間を要し、ミスの温床になりかねません。こうした課題には、BIMやCIMによる3D可視化技術が有効です。
3Dモデルを使えば、構造物の完成イメージや配管ルート、障害物の位置などを直感的に把握できます。作業前の段取りや現場での判断が容易になり、高齢者の経験とデジタルの力を融合させた新たな作業スタイルが実現できます。
高齢化が進む中で、一律の働き方を押し付けるのではなく年齢やスキルに応じた業務設計が必要です。作業負荷を平準化し、現場作業と管理業務、教育業務などを適切に振り分ける仕組みづくりが必要です。
例えば、体力的に現場作業が難しい高齢従業員に対しては、遠隔支援や資料作成、若手育成といった役割を中心に据えることで、組織全体の生産性を維持することも可能です。柔軟な勤務設計により退職を避けつつ経験の活用が可能となり、持続可能な労働環境の実現に近づきます。

高齢化が進む建設現場において、DX技術は生産性向上だけでなく、高齢作業員の就業継続を支える視点でも重要性を増しています。活用のポイントとしては、作業支援ロボットやウェアラブル端末による身体的サポート、ICT建機による操作自動化、さらには遠隔モニタリングによる安全管理の高度化などが挙げられます。
ここでは、実際に現場での高齢化対策として有効性が認められている建設DX技術の活用ポイントを紹介します。
高齢作業員の退職によって蓄積された技術が現場から消えることは、施工品質と業務の安定性に大きな影響を及ぼします。この課題に対しては、BIM(Building Information Modeling)を活用することで、熟練者の暗黙知や手順、工夫をデジタル上に定着させるアプローチが有効です。
BIMでは、建物や構造物の情報を3Dデータとして構築し、工程・材料・作業順などを一元的に管理できます。経験に基づく細かな調整や判断ポイントを3Dモデル上に記録しておくことで、他の作業員も容易に参照でき、属人化の解消につながるでしょう。
また、若手作業員が現場に入る前にBIMモデルで事前に確認することで、手戻りや理解不足を防ぎやすくなり、教育にかかる工数削減も期待できます。
作業現場での実地教育には、事故リスクやコスト面の問題がつきまといます。これに対応する手段として、VR(仮想現実)やAR(拡張現実)を使った訓練や業務支援の活用が広まっています。
VRを利用すれば、仮想空間内で実際の現場と同等の作業のシミュレーションが可能です。高所作業や重機の操作、災害時対応といった危険を伴う訓練でも、現場を使わずに安全に学習できます。高齢作業員が後進指導に従事する場合も、自らが対応した事例をVRコンテンツとして記録することで他の従業員への教育資源として機能します。
一方、ARでは現場に実物の構造物や作業図面を重ねて表示することで、作業手順を視覚的にガイドできるのもポイントです。こうした再現性の高い教育・支援環境は、人材の定着率向上にも寄与します。
高齢化対策としてのDX推進では、知識の属人化を防ぎ、情報を組織全体で共有する体制づくりが欠かせません。そのためには、クラウド技術を用いた情報基盤の整備が効果的です。
クラウドストレージを活用すれば、技術マニュアル・施工事例・作業手順書などを一元的に保管・管理できます。高齢作業員が退職する前に自身が担当した業務を写真や動画で記録しておけば、それがそのまま後進の教育教材として活用できます。また、現場で撮影した状況報告やトラブルの記録もクラウド上で共有できるため、拠点をまたぐ連携もスムーズです。
加えて、最新のBIMや図面データもクラウドで管理すれば、現場と本部間の情報格差を縮小できます。移動やコピー作業の手間も省け、業務負担の軽減につながります。
高齢作業員の中には、タブレットやPCなどの操作に不慣れな人も少なくありません。そのため、システム導入が現場で活用されないまま定着しないケースも見られます。
こうした状況に対応するため、音声UI(ユーザーインターフェース)を取り入れる方法が注目されています。音声UIとは、話しかけるだけでシステムを操作できる機能であり、スマートフォンの音声アシスタントに近い感覚で利用可能です。
例えば、進捗報告・勤怠入力・作業チェックリストの呼び出しなど、基本的な業務を音声だけで完結できれば操作に対する心理的ハードルが下がります。視覚や手先の動作に頼らずに情報登録や参照が行えるため、年齢を問わず継続利用しやすい仕組みとして導入が進んでいます。
体力の低下による作業制限は、高齢者の業務継続における大きな障壁です。特に腰や膝への負担が大きい作業では、無理を重ねることでケガや離職につながる恐れがあります。
そこで注目されるのが、装着型ロボット(アシストスーツ)の活用です。これは作業者の身体に装着して動作を補助する機器であり、特定部位の負担を機械的に分散する仕組みになっています。
荷物の持ち上げや移動、長時間の姿勢保持など日常的に行う作業を補助することで、作業効率と安全性を維持したまま継続的な労働が可能になります。軽量化が進んだ現在では屋外現場にも導入され始めており、特に腰部アシストや膝関節支援モデルなどが実用段階に入りました。
急速に高齢化が進行する建設業界では、年齢に左右されない現場体制の構築が求められています。これに対応するための建設DX推進方法としては、以下のような多面的アプローチが有効です。
これらを戦略的に組み合わせることが、継続的な現場力の維持につながります。
ここでは、高齢化に対応しながら持続可能な建設現場を築くための、5つの実践的なDX推進方法を紹介します。
建設現場における高齢作業員は、豊富な経験と知見を持っています。一方で、加齢に伴う体力や認知面での変化が業務に影響を及ぼす場面も増えています。こうした課題に対応するには、年齢にとらわれない働き方を支える環境整備が必要です。
具体的には、装着型ロボットやICT機器の活用によって身体的な負担を軽減し、作業効率を維持したまま長期間の勤務を可能にします。また、業務内容を細分化し、作業の割り当てを柔軟に調整する仕組みも重要です。負荷の高い作業は若手に、判断や管理が求められる工程はベテランに担当させるなど、年齢や適性に応じた役割分担が現場力の向上につながります。
世代間の断絶は、知識伝承や業務連携の障壁となります。その解消には、日常業務の中で自然な形での協働体制を構築することが重要です。
DXを推進すれば、ベテランが若手を指導する場面でも効率よく情報を共有できます。例えば、BIMで作成された施工モデルを見ながら図面だけでは伝わりづらい意図や背景を解説する場面では、年齢に関係なく同じ情報を共有できます。また、クラウドベースのチャットツールや作業報告アプリの導入により、現場での細かな気づきをリアルタイムで共有することが可能です。
さらに、VRを活用した合同研修やOJT支援ツールを導入することで、世代を超えて同じ環境下で学び合う機会が生まれます。協働体制の構築は単なる業務効率化にとどまらず、チーム内の信頼関係や職場の一体感を高めることにもつながります。
高齢者と若年層がそれぞれの特性を活かして協力し合う環境をつくるには、業務内外の多世代交流を意識的に促す必要があります。その一環として、DXを用いたコミュニケーション設計が有効です。
例えば、現場の進捗管理やスケジュール調整に関する情報を1つのプラットフォームで共有すれば、誰がどのように動いているかを全員が把握しやすくなります。ここで重要なのは、情報の形式が誰にとってもアクセスしやすいものであることです。図解や音声解説、動画による説明など多様なメディア形式を用いることで、世代に関係なく理解が深まります。
これにより、現場の活性化と共にエンゲージメントの向上にもつながります。
高齢化により人手不足が進行する中で、既存人材の流出を防ぐ取り組みが不可欠です。そのためには、働きやすさや成長実感を提供できるDX環境の整備が有効です。
勤怠管理や健康状態の記録をクラウドで一元管理し、過重労働の抑制や勤務時間の適正化を図れば、現場での心理的・身体的負担を減らせます。さらに、進捗管理や報告業務の自動化により、事務作業に割かれる時間が短縮され、本来の業務に集中できる環境が整います。
また、スキルアップ支援の一環としてオンライン研修や業務マニュアルを動画で整備することで、職種に応じた能力向上が期待できるでしょう。作業者は自らのキャリアパスを描きやすくなり、離職防止につながります。
建設業界が抱える高齢化問題を根本的に解決するには、短期的な対症療法ではなく、中長期を見据えた人材戦略の再設計が必要です。その軸となるのが、建設DXの活用による構造改革です。
まずは、業務全体をプロセス単位で可視化し、どの工程にどのスキルが必要かを明確にすることで、職種ごとの人材要件を整理できます。次に、個人単位でスキルや経験をデータ化し、適材適所の配置が可能になる仕組みを構築することで、属人性を排除した戦略的な人事配置が可能です。
このように、建設DXは単なるツール導入にとどまらず、組織の人材活用の在り方を根本から見直すきっかけとなります。
建設DXを推進する上で、現場に多く在籍する高齢者への配慮は欠かせません。先進的な企業では、技術面だけでなく使いやすさや受け入れやすさに重点を置いたDX施策が進められています。
実際に推進した企業では、作業効率が向上するだけでなく、高齢者が自身の経験や知識を若手に伝えやすくなる環境が整い、職場の一体感とモチベーションの向上につながっている事例も見られます。ここでは、高齢者にも扱いやすい建設DXを推進し、現場力の向上を実現した企業の先進事例を紹介します。
鹿島建設株式会社では、建設ロボットや自動化機器を活用した現場改革を推進しています。とくに注目すべきは、高齢作業員の視野や動作範囲に合わせた作業支援システムの導入です。
同社は、ICT建機や自動溶接装置といった建設自動化機器を実際の現場に投入し、作業者の身体的負荷を軽減できるよう工夫してきました。導入されたシステムは直感的な操作が可能で、視認性や反応速度に優れています。
また、同社は現場推進時に作業員への事前ヒアリングを行い、使用感や操作性を細かく調整しました。このプロセスを経ることで年齢に応じた使いやすさと現場環境への適応が両立され、全世代に開かれたDX推進が可能となっています。
出典参照:建設機械の自動運転を核とした自動化施工システム|鹿島建設株式会社
大成建設株式会社は、施工現場のDX推進においてタブレット端末を活用した作業支援に力を入れています。従来の紙図面や口頭指示に代わってタブレット上で操作できる施工管理アプリを現場全体に導入し、情報共有の迅速化を図っています。
この取り組みで特徴的なのが、音声案内や動画チュートリアルによる高齢者支援機能です。
特定の作業指示や確認事項をタブレットが音声で読み上げたり、操作方法を短時間の動画で説明したりする設計が採用されています。
このような補助機能により、画面上の細かな操作が苦手な高齢作業員でも安心して機器を使いこなせるようになりました。
出典参照:タブレット-CAFM連携システム|大成建設株式会社
株式会社竹中工務店では、現場の業務効率化と人材支援を目的としてERP(統合業務管理)システムの導入を進めています。この中で特に重視されているのが、インターフェースの視認性です。
作業記録の入力やスケジュールの確認、勤怠管理などを一括で行えるクラウド型のシステムは、シンプルなレイアウトと大きなアイコン表示で設計されています。高齢者にとって視認性の高さは操作ストレスの軽減につながり、実際に導入後はミスの減少や操作時間の短縮が報告されています。
このような環境整備により、高齢作業員でも管理業務に関与しやすくなり、多様な働き方を実現する土壌が整えられました。
出典参照:ワークフロー電子化でスマートワークに適した基盤を構築 業務効率化・簡略化に成功し、内部統制強化も実現| 株式会社竹中工務店

建設業界では高齢化の進行により、人材の確保や現場対応力の維持が喫緊の課題となっています。これに対し、建設DXは現場の課題を技術によって緩和し、すべての世代が能力を発揮できる環境を整えるための有効な手段です。
DXを単なる技術導入に終わらせず、年齢や世代を超えた連携を可能にする手段として捉えることで、建設業界全体の持続可能性が高まっていきます。高齢化への対応を現場の進化と捉え、全世代が共に成長できる建設DXの推進が、今後の業界の基盤を支えるカギとなるでしょう。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
