建設DXでペーパーレス化は可能?メリットや成功のステップを解説
建設

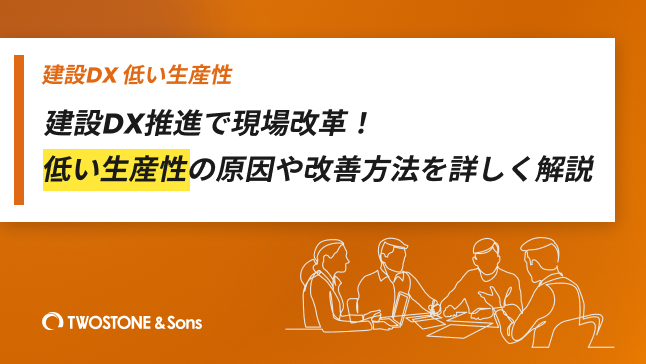
現場の高齢化が進む建設業界では、人材の確保や技術継承にとどまらず、生産性の確保自体が喫緊の課題になっています。熟練作業員の引退が相次ぐ中、若手人材の確保が進まない現場では作業の質とスピードを同時に維持することが困難になりつつあります。
そこで注目されているのが、建設DXの推進です。単に業務をデジタル化するだけでなく、作業の標準化や情報の一元管理、さらには人材の活用方法そのものを見直す手段として多くの建設企業が導入を進めています。
本記事では、生産性が低下しやすい建設現場の背景を掘り下げた上で、建設DXによる具体的な解決アプローチを解説します。現場の負担を軽減し、持続可能な戦略を実現したいと考える企業担当者にとって、今後の指針となる内容です。

建設業界における生産性の低下は、単なる人手不足や高齢化だけで説明できるものではありません。実際には、現場作業と事務処理の分断、アナログ管理の継続、作業の属人化、さらにはIT導入の遅れといった、さまざまな要因が複合的に影響しています。
こうした構造的な課題は、現場ごとに異なる業務フローや情報管理のバラつきを引き起こし、工程全体の非効率を生み出しています。
ここでは、主な原因について具体的にみていきましょう。
建設現場では、建機や一部工程の自動化は進んでいるものの、依然として多くの作業が人力に依存しています。資材の搬入から現場での検査・確認、日報の記入や報告業務まで、細かい作業の多くが手書きや口頭で行われており、非効率な状況が日常的に発生しています。
こうした手作業中心の業務体制では、ヒューマンエラーや伝達ミスが起こりやすくなり、手戻り作業やダブルチェックの増加といった課題が生まれかねません。その結果、工期が延びたり、関係者間の信頼に影響が出たりと、生産性だけでなく現場全体の運営にも悪影響が及びます。
今後、持続可能な現場運営を目指すためには、人手作業からの脱却を視野に入れた改善が欠かせません。
建設現場では、業務の多くがベテラン作業員の経験や技術に依存しており、属人化の傾向が強くなっています。同じ作業であっても担当者によって所要時間や品質にばらつきが出やすく、結果として現場全体の効率を下げる要因になります。
属人化が進行すると、標準的な手順や判断基準が共有されにくくなり、新人や若手への指導や引き継ぎも場当たり的な対応にとどまりがちです。さらに、熟練者が退職するとそのノウハウが失われ、同じ品質の業務を再現することが困難になります。
こうした状況が長く続けば、現場の技術や管理の属人性が強まり、組織としての生産性向上が実現しにくくなります。業務を標準化し、誰もが再現可能な体制を整えることは、技術継承の観点からも重要な取り組みです。
建設現場と事務部門の間に情報の断絶があると、業務全体のスピードと正確性が損なわれます。現場での作業進捗やトラブルがリアルタイムで事務側に共有されない状況では、適切な判断や支援が後手に回り、現場対応が遅れやすくなるでしょう。
特に、日々の報告や工程変更などに関する情報が紙や電話でやり取りされている現場では、情報の共有ミスや行き違いが頻発します。こうした分断がもたらすのは、調整ミスや不要な手配、さらに二重作業などの非効率です。
現場と事務が別々のツールや管理方法を使っている場合には、そもそも情報を統一して扱うことが難しくなります。そのため、ツールの整備や連携の仕組みづくりが生産性向上の出発点となります。
帳票の手書きや紙の台帳による管理がいまだに多くの現場で行われています。こうしたアナログ管理のままでは、同じ情報を何度も記入したり、後からデータを手入力で転記したりする必要があるため、作業が重複しやすくなるでしょう。
また、手書きによる記録は読み取りミスや記入漏れが発生しやすく、集計にも時間がかかるため、迅速な意思決定が難しくなります。管理者が必要なデータをその場で確認できず、判断に時間がかかるケースも少なくありません。
さらに、現場ごとに記録方法が異なっていると、データを比較・分析する際にも手間がかかります。情報の信頼性や透明性を高めるためには、アナログ管理からの脱却とデジタル化による標準化が急務です。
建設業では長年にわたり人手不足が深刻化しています。高齢化が進行する一方で若年層の就業者が増えておらず、多くの現場で作業員の確保に苦慮しているのが現状です。このような中では、限られた人材で現場を回す必要があり、一人ひとりの負担が大きくなっています。
人手不足の状態が続くと、残っている作業員に過重な労働が集中しやすく、結果として心身の疲労が蓄積され、離職リスクが高まります。特に若手にとっては働きにくい環境に映る可能性があり、定着率にも悪影響を及ぼしかねません。
人材不足の改善には、働きやすい環境と効率的な業務体制を両立させる視点が不可欠です。
建設DXを推進する上で欠かせないのが、現場の実態に即したデジタルツールの導入です。業務の一部だけをデジタル化しても全体の生産性は上がりにくく、むしろ情報の分断が新たな課題を生む可能性もあります。そのため、設計から施工・管理・報告に至るまで一貫して支援できるツールを組み合わせて活用することが重要です。
ここでは、建設現場での実務を効率化し、生産性の向上に寄与している代表的なツールを5つ紹介します。設計支援から遠隔操作までそれぞれの特徴と効果を把握し、自社に合った活用方法を検討する際の参考にしてください。
Rebroは建築設備設計に特化した3Dモデリングツールであり、BIM(Building Information Modeling)の導入と活用を強力に支援します。従来の2D図面による設計では、配管・ダクトの干渉や配置ミスのリスクが高く、実際に施工に入ってから手戻りが発生するケースも少なくありませんでした。Rebroを導入することで、設計の初期段階で3Dモデルを活用して視覚的に干渉箇所を確認でき、事前の修正作業でトラブルを未然に防ぐ体制が整います。
Rebroは施工段階での設計変更にも迅速に対応できるため、工期の安定化にも貢献します。Rebroの活用は、業務の効率化だけでなく、品質確保やコスト削減の観点からも注目されているツールです。
出典参照:Rebro|株式会社 NYKシステムズ
Box for Constructionは、建設業向けにカスタマイズされたクラウドストレージで、ファイル共有と文書管理の両立を実現します。設計図面や工事仕様書などの重要な書類をクラウド上で管理することで、どの端末からでもリアルタイムに最新の情報を確認でき、現場とオフィス間の情報共有を効率化します。
従来の紙ベース運用では、古い図面を使用したことによる施工ミスや、関係者への情報伝達遅れが業務に支障を与えていました。Boxを導入すれば、図面や資料のバージョン管理が自動で行われ、変更履歴も明確に残ります。そのため、設計変更が発生しても、誰がどこを修正したのかを迅速に確認できます。
また、アクセス権限の細かい設定が可能で、特定のユーザーや部署にのみ閲覧や編集を許可することもでき、情報漏えい対策にも対応しているツールです。
SiteBoxは、建設現場での報告業務や写真管理をデジタル化し、タブレット端末での運用を可能にするアプリケーションです。現場担当者が日々の作業や進捗を写真付きで記録し、報告書としてそのまま出力できるため、PCへの取り込みや後処理の手間が不要になります。これにより、報告業務の時間が大きく短縮され、現場作業に集中しやすくなります。
また、現場から即時に報告内容を共有できるため、管理者は進捗状況をリアルタイムに把握でき、迅速な判断と対応が可能です。帳票のテンプレートはカスタマイズ性が高く、自治体や元請けごとの書式にも柔軟に対応できるため、外部提出書類の作成もスムーズに行えます。
ペーパーレス化によって資料の持ち運びも不要になり、現場の業務効率化だけでなく、管理精度の向上にも寄与する実用性の高いツールです。
出典参照:SiteBox|株式会社建設システム
Reviztoは、建築・土木分野における3Dモデルの共有を円滑にするコラボレーションプラットフォームです。設計担当、施工管理者、現場作業員など、複数の職種が同じモデル空間を共有することで、業務の認識差や伝達ミスを最小限に抑えることができます。
特に複雑な構造物を扱う現場では、干渉チェックや工程調整の正確さが求められます。Reviztoは、モデル上に直接コメントやマークアップを残すことができ、具体的な指示や意見交換を即時に行うことが可能です。タスクごとに責任者を割り当てる機能も備えており、プロジェクト全体の進行状況を可視化できます。
また、クラウドベースでの運用により、現場・本社・協力会社が地理的制約なく同じモデルを閲覧・操作できるため、多拠点連携の強化やリモートワークの推進にもつながります。
出典参照:Revizto|Revizto SA
SynQ Remoteは、現場とオフィスを双方向でつなぐ遠隔支援用のコミュニケーションツールで、スマートグラスやスマートフォンを活用してリアルタイムの映像共有と音声通話を実現します。現場の若手作業員が装着したデバイスから映像を送信し、本社にいる熟練技術者がそれを見ながら適切な指示を出すことで、現場支援を遠隔で行えます。
これにより、ベテラン技術者が物理的に現場へ出向く必要がなくなり、時間や移動の負担を軽減できるでしょう。さらに、緊急時のトラブル対応や技術確認にも即応できるため、対応力の強化にも効果があります。
人材不足が深刻化する中、限られた熟練者リソースを最大限に活用しながら、若手への技術伝承を現場ベースで進められる点が大きな強みです。チームの生産性と組織全体の柔軟性を向上させる重要な支援ツールと言えるでしょう。
出典参照:SynQ Remote|株式会社クアンド

建設業界でDXを推進する際には、単にデジタルツールを導入するだけでは生産性向上に直結しません。現場の特性や人材の年齢構成、業務フローを丁寧に分析し、それに適したテクノロジーを段階的に組み込む必要があります。
特に効果が期待されているのは、操作性の高いスマート建機、遠隔支援技術、音声入力システム、自動記録による情報蓄積、そして関係者全体でのモデル共有といった領域です。
ここでは、それぞれの推進方法について具体的に解説します。
スマート建機とは、GPSやセンサー、ICT技術を組み込んだ建設機械のことです。これらの建機はオペレーターの経験や技量に左右されず、安定した施工品質を確保しやすくなるのが特長です。
特に高齢オペレーターにとって体力的な負担が軽減される上、誤操作のリスクも抑えられます。また、掘削深さや傾斜の角度を自動で制御できるため、作業時間の短縮や資材ロスの防止にもつながります。
ベテランと若手の技術格差を補う手段としても有効であり、技能継承の面でも意義のある取り組みといえるでしょう。
建設現場では、急なトラブルや不具合への即時対応が工程全体の進捗に大きく影響します。しかし、技術者や熟練作業員の数が限られている現場では、複数のプロジェクトを同時に管理するのが困難であり、対応が後手に回る場面も多く見られます。こうした課題に対して有効なのが、スマートグラスやモバイル端末を活用した遠隔支援技術です。
現場で撮影された映像や音声をリアルタイムで本社や別の拠点に伝送することで、専門技術者がその場にいなくても的確な指示や判断を下せる体制が整います。これにより、トラブル対応までの時間が短縮され、工事の中断や再作業といったリスクを抑えることができます。
結果として、働き方改革にもつながり、長時間労働の抑制や生産性向上にもつながるでしょう。高齢化が進む中で、限られた人材を有効に活用する手段として、遠隔支援の導入は極めて有効な選択肢です。
建設現場では日々多くの情報を記録・報告する必要がありますが、その手間が業務の負担となっています。作業終了後に紙で報告書を記入したり、帰社後にパソコンでデータを打ち込んだりする工程は時間を奪い、特に繁忙期にはミスや入力漏れが起きやすくなります。
このような課題を軽減する方法として注目されているのが、音声入力の活用です。スマートフォンやタブレット端末に話しかけるだけで、作業記録や点検内容などをリアルタイムで文字情報として保存できる機能を導入することで、記録作業を効率化できます。
現場での活用範囲も広く、報告書の自動生成や作業記録の保管などに対応できるため、事務作業の負担を全体的に減らすことが可能です。IT導入に不安を抱える現場でも導入しやすい技術として、多くの中小建設業に適しています。
建設現場では、日々膨大な量のデータが発生します。作業内容、使用機材の稼働状況、品質検査の記録、気象条件の変化など、それぞれが業務の安全性や効率性に直結する重要な情報です。これらをすべて人手で管理しようとすると、管理工数が膨らみ、担当者の負担が増えるばかりか、入力ミスや記録漏れのリスクも高まります。
そこで有効なのが、IoTデバイスやセンサーを活用したデータの自動記録です。例えば、建機に搭載されたセンサーが稼働時間や燃料使用量を自動で取得し、それをクラウド上で管理できるようにすれば、現場での記録作業が不要になります。
人手に依存しないデータ管理の体制を構築することは、属人化の排除にもつながり、業務の標準化や再現性の向上にも効果的です。管理工数の削減と品質の安定を両立する手段として、今後さらに導入が進むと考えられます。
建設プロジェクトでは多数の関係者が関与するため、情報の共有と意思疎通の精度がプロジェクト全体の生産性を左右します。そのため、1つのモデルを軸に関係者が同じ情報にアクセスできる環境の整備が欠かせません。
BIMやCIMといったモデル共有技術を活用すれば、設計図面や施工計画、進捗状況を視覚的に把握できるようになります。現場と事務所、設計者と施工管理者といった部門間のギャップを埋め、認識のズレや二重作業を回避できる効果が期待されます。
また、モデル上にタスクや指示を記録する機能を活用すればメールや口頭による曖昧な指示が減り、責任範囲も明確にできるのがポイントです。これによりチーム全体の連携が高まり、プロジェクト全体の進行がスムーズになります。
建設DXの推進は現場の省力化や業務効率化だけでなく、企業の競争力を高める戦略のひとつとしても注目されています。特に先進的な企業では、独自のDX導入によって人材育成や業務標準化も実現しました。
ここでは、実際にDXによる取り組みを進め、生産性向上を実感している建設会社の具体的な事例を紹介します。それぞれの企業がどのようにDXを現場に落とし込んでいるのか、導入の視点や効果に注目してください。
金杉建設株式会社では、現場の生産性向上と作業負担の軽減を目的に、3DスキャナーとICT建機を活用した取り組みを進めています。これまで複数名で数日かけて行っていた測量作業は、3Dスキャナーの導入により、少人数かつ短時間で正確に完了するようになりました。従来のようにオペレーターの熟練度に作業品質が左右されなくなり、安定的かつ効率的な施工が実現しています。
さらに、作業時間が短縮されたことで作業員の拘束時間も減り、現場全体の安全性向上にも寄与しています。工程管理の精度が上がり、他の作業とのスケジュール調整もしやすくなった点も見逃せません。このように、ICTを活用した作業の自動化は、少ない人員で精度の高い仕事を可能にする代表的な事例となっています。
出典参照:i-Constructionへの取組み |金杉建設株式会社
西松建設株式会社では、ICTと通信技術を組み合わせた建機の遠隔操作を導入し、建設現場の生産性と安全性の両立を図っています。従来の建設現場では、作業者が建機に直接乗り込む必要があり、暑さや粉じん、振動といった過酷な環境に長時間さらされることが問題でした。遠隔操作を導入することで作業現場から離れた快適な環境で建機を操作できるようになり、身体的・精神的な負担が軽減されました。
加えて、映像とセンサー情報をリアルタイムで組み合わせた操作支援システムを用いることで、画面越しでも高度な微調整が可能となり、精密な作業にも対応しています。これにより、熟練技術者の技術を複数の現場で同時に活用でき、限られた人的リソースを最大限に活かせる体制が整いました。
このように、西松建設の取り組みは、建設業界全体が抱える人材不足や技術継承の課題を解決する一手としても注目されています。
出典参照:ホイールローダ遠隔操作システムを山岳トンネル工事の実施工へ試験導入 |西松建設株式会社
清水建設株式会社は、建設DXを人材育成の分野にも活用しています。特に注目すべきは、独自に開発したeラーニングシステムの運用です。現場の基本動作や安全管理、専門技術に関するコンテンツを標準化し、時間や場所にとらわれず学習できる環境を整備しました。
これにより新入社員や経験の浅い作業員が短期間で業務に慣れ、早期に現場で活躍できる体制が整っています。動画やクイズ形式の教材が用意されており、理解度を可視化する仕組みも導入されているため、指導の質も一定に保たれているのもメリットです。
このような取り組みは単に知識を習得するだけでなく、現場での判断力や連携力を高める効果も期待されています。結果として現場全体の生産性が向上し、クオリティの高い施工が実現しています。
出典参照:デジタル人財育成プログラム「シミズ・デジタル・アカデミー」を開講|清水建設株式会社
建設DXは生産性の低さを克服するための有効な手段ですが、導入や活用の過程でいくつかの注意点を見落としてしまうと、かえって現場の混乱や業務負荷の増加を招く可能性があります。単に技術を導入するのではなく、現場の特性や従業員のスキル、業務フローとの適合性を十分に考慮することが大切です。
ここでは、建設DXを推進する上で押さえておくべき重要な3つの視点について解説します。
建設DXを有効に進めるには、最初に現場の実情を丁寧に把握する必要があります。業務のどこにムリ・ムダ・ムラがあるのかを明確にせず、闇雲にツールを導入しても効果は限定的です。DXはあくまで手段であり、対象とする課題を的確に見極めることが前提です。
例えば、図面確認に時間がかかっている場合には、図面共有システムの導入が優先されます。一方で、作業員の配置や調整に時間を取られている現場では、工程管理やスケジューリングを支援するツールの活用が求められるでしょう。
現場ごとの課題を把握するには、ヒアリングや業務日報の分析、作業時間の可視化など多角的な手法が効果的です。
建設現場におけるデジタルツールの導入では、操作性と現場との相性が良いかそうでないかが重要な評価ポイントになります。どれだけ高機能なツールであっても、現場作業者が扱いづらければ業務改善どころか混乱を招く結果になりかねません。
特に建設業では、ベテラン作業員や高齢者の割合が多く、ICTリテラシーに差があるため、導入ツールのUI(ユーザーインターフェース)や視認性、操作手順の簡便さは慎重にチェックする必要があります。
導入前に小規模なトライアルを実施し、現場の意見を取り入れることも有効です。あわせて、サポート体制の充実やマニュアルの整備、導入時の研修プログラムの充実も重要です。運用フェーズを見越して準備を進めることで、DXが現場に定着し、実効性のある改善へとつながります。
DXによって情報をデジタル化しても、そのデータが部署間やツール間でつながっていなければ、期待される業務効率化にはつながりません。むしろ、部分的なデジタル化によってシステムが乱立し、業務が複雑化してしまうケースも散見されます。
建設業では現場・設計・管理部門などが別々に情報を持っている場合が多く、こうした分断を放置すると、ミスの増加や重複作業の温床になり得ます。そこで重要になるのが、データ基盤の統一とリアルタイムでの情報共有の仕組みです。
クラウドの活用やAPIによるシステム連携を通じて、現場から本社まで一貫した情報フローを構築することが求められます。

建設業界が抱える低い生産性の背景には、人手作業への依存、属人化、分断的な業務構造など、長年積み重なってきた構造的な課題があります。しかし、建設DXを通じてこれらの要因に着目し、テクノロジーと業務設計を結びつけることで持続可能な働き方と現場改善を同時に実現することが可能です。
本記事で紹介した事例やツール、推進方法は、DXの推進を検討する上で具体的なヒントになるはずです。変化の早い社会情勢の中で、DXの推進は生き残りの戦略でもあります。現場の声に耳を傾けながら、デジタルの力を活かして建設業界の未来を支えていきましょう。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
