建設DXでペーパーレス化は可能?メリットや成功のステップを解説
建設

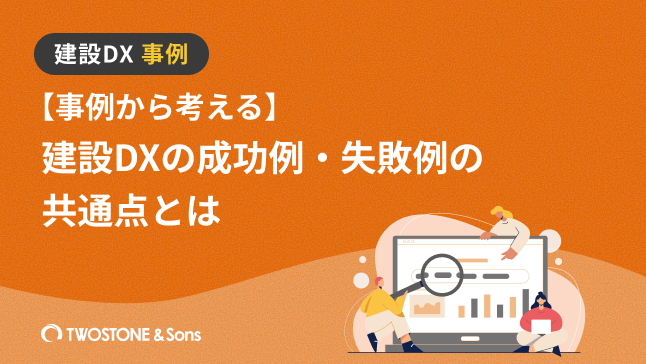
建設業界では人手不足や高齢化、工期の長期化など、現場が抱える課題は多岐にわたっています。こうした課題を乗り越えるための手段として注目されているのが建設DXの推進です。デジタル技術を活用することで、業務効率の向上や品質管理の強化、コスト削減などの実現が期待されています。しかしながら、すべての企業がDXに成功しているわけではなく、推進したものの現場に定着しなかったという失敗例も見受けられるのが現状です。
本記事では、建設DXに関する成功例と失敗例を比較しながら、なぜうまくいく企業とそうでない企業があるのか、その共通点を詳しく解説します。さらに、BIMやクラウド、AI、5G、ドローンといった技術を導入する際のポイントや注意点も紹介します。自社にとって最適なDXの方向性を見つけたい方にとって、実践的なヒントが得られる内容です。

建設DXの推進は、単なるシステム導入ではなく、業務フロー全体の改革を伴う戦略的な取り組みです。現場と本社の連携を強化し、限られた人材で最大の成果を引き出すためには、目的に応じてデジタル技術を適切に活用することが不可欠です。
特に近年は、さまざまな技術が現場に導入されています。
ここでは、それぞれの技術の具体的な活用方法とそのメリットについて詳しく見ていきます。
BIM(Building Information Modeling)やCIM(Construction Information Modeling)は、建築物やインフラの構造を3次元で設計・可視化する技術であり、建設業界のデジタル化を支える基盤です。2次元の図面では見落とされがちだった構造の干渉や複雑な接合部などを、視覚的にわかりやすく確認できるため、設計段階でのリスクの洗い出しが可能になります。
さらに、BIM/CIMを活用すると、施工工程や資材の流れ、人員配置などの施工プロセスまで連携させられ、業務全体の統一管理が進むでしょう。
一方で、失敗事例ではツールの使い方に不慣れな担当者が多く、導入したものの有効活用できなかったケースがあります。BIM/CIMは、単なるソフトの導入ではなく、教育体制や業務フロー全体を見直す取り組みとセットで進めるべきです。
建設業では、現場・設計・本社といった複数の関係者が常に連携を求められます。クラウド型施工管理システムを導入することで、図面やスケジュール、原価、帳票類などの情報をリアルタイムに共有でき、部署間や協力会社との意思疎通がスムーズになります。
成功事例では、クラウド技術によって全関係者が同一の最新データを閲覧できる環境を整備し、誤解や手戻りの削減につながりました。また、作業の進捗やトラブルの報告も即時に共有できるため、対応スピードが向上し、品質管理と工程管理の両立が可能になっています。
一方で、導入前に既存の業務フローを整理しないまま複数のツールを併用してしまい、情報の重複や分散が起きた失敗例もあります。クラウド導入は、システム選定だけでなく、業務プロセスの最適化や利用ルールの整備も重要です。誰が・いつ・どのように使うかを具体的に定めることが成功のカギを握ります。
AIやIoTの技術は、建設現場における業務の可視化・自動化を支援し、効率と安全の両立を実現します。IoT機器によって現場の作業員の位置情報や建機の稼働状況をリアルタイムで収集し、AIがその情報を分析することで、最適な作業工程やリスクの兆候を事前に検知できます。
成功例では、作業環境の変化をAIが即座に判断し、熱中症リスクの高い作業員に対する注意喚起や、資材置場の最適化などが行われました。このように、人的ミスを減らす支援ができる点で、安全性の向上に直結しています。
しかし、導入した機器の管理や運用方法が明確でなかったために、収集したデータが活かされなかった失敗例もあります。特に、データを分析・活用する体制が整っていない企業では、導入だけで終わってしまうリスクがあるでしょう。AI・IoTを導入する場合は、技術の活用を前提とした人材育成とPDCA体制の整備が求められます。
5Gの通信技術は、建設現場におけるリアルタイムの遠隔管理や監視を可能にします。特に、建機の遠隔操作や高精細な映像伝送においてその性能が発揮され、現場とオフィスの距離を感じさせない業務遂行が可能となります。建設業のように広範囲かつ複雑な現場において、5Gは業務効率化の要となる技術です。
成功例では、現場の映像を本社で確認しながら指示を出すことで、現地への出張回数を削減でき、移動コストと時間の節約につながっています。また、現場の状況を逐一モニタリングできるため、トラブルが発生した際の初動対応が迅速になりました。
一方で、通信環境の整備を軽視したことで、5Gの電波が安定せず、操作が中断されるトラブルに見舞われた失敗例もあります。5Gを導入する際は、事前の環境調査とバックアップ体制の構築が不可欠です。
ドローンとレーザースキャナーは、高所や危険箇所での作業を効率化する技術として、建設現場での活用が進んでいます。空撮や自動飛行によって広範囲の測量や出来形確認を短時間で実施できるため、作業効率の向上だけでなく、作業員の安全確保にも寄与しています。
成功事例では、施工前の地形情報をドローンとスキャナーで取得し、BIMに連携することで正確な計画が立てられ、工程の遅延防止につながりました。また、点検業務においても、足場を組む必要がなくなるためコスト削減と事故リスクの低減が実現されています。
ただし、失敗事例では、操縦スキルやデータ解析の専門知識が不足していたため、機器はあっても使いこなせず、結果的に従来手法に戻るケースもありました。ドローンやスキャナーの活用を成功させるためには、運用スキルの標準化と明確な業務フローの構築が求められます。
建設業界では、業務の効率化や人手不足への対応を目的として、デジタル技術を活用する取り組みが広がっています。中でも、大手ゼネコンは社内に専門部署を設けたり、基幹システムを刷新したりするなど、組織全体でDXを推進する企業が出てきました。
ここでは、実際にDXに取り組み、一定の成果を上げている3つの企業の事例を紹介します。各社の取り組み内容や進め方の違いを比較することで、自社のDX推進に役立つヒントが得られるでしょう。
株式会社大林組は、グループ全体のデジタル変革をけん引するために、2022年にDX本部を設立しました。DX本部は、全社的なデジタル戦略の策定と推進を担い、IT部門や各事業部と密に連携しながら、業務フローの見直しや新技術の導入を加速しています。
同社のDX推進の特徴は、単なるIT導入にとどまらず、デジタル人材の育成や組織文化の改革にも力を入れている点です。実際に、施工現場へのICT建機の導入や、現場映像のリアルタイム配信による遠隔支援体制の構築が進められています。
こうした取り組みにより、情報共有や意思決定のスピードが向上し、安全性と生産性の両立を実現しました。DX本部の存在が、社内の意識改革とスムーズなデジタル導入の中核となっており、持続可能な成長を支える土台を築いています。
出典参照:DX本部の新設について | ニュース | 株式会社大林組
鹿島建設では、早くから建設分野におけるデジタル化に注力しており、BIMやCIMの導入、AI・IoT活用、そして現場の遠隔支援体制の構築など、多面的なDX推進を進めています。特に、全社レベルでの共通基盤整備と現場への展開を両輪で進める体制が特徴的です。
同社は、デジタル技術の導入を部分的な改善に留めるのではなく、業務そのものの変革につなげることを重視しています。実際に、クラウド上での工程共有システムやモバイル端末による現場報告などが現場で実装され、属人化を排除しつつ、作業の質を保ちながら効率化を図りました。
また、デジタルに関する社内教育も積極的に行い、現場と本社が一体となってDXを推進する風土づくりが進んでいます。これにより、テクノロジーの導入が一過性の取り組みで終わらず、企業価値の向上につながる基盤として定着しています。
出典参照:DXの戦略的推進 | 鹿島建設株式会社
株式会社熊谷組では、建設DXを段階的に推進するため、2021年よりDX戦略を策定し、年度ごとに具体的なテーマを設定して取り組んでいます。まずは基幹システムの刷新から着手し、全社の業務基盤を整えることで、データの一元管理と業務の可視化を実現しました。
その後は、現場業務と連携したモバイルアプリの導入やAIを活用した工程予測など、新技術の実証実験も行いながら、順を追って取り組み範囲を広げています。これにより、現場からのデータ取得が容易になり、業務改善や意思決定の迅速化につながっています。
熊谷組のDXの特徴は、初めからすべてを変えようとせず、現場の理解と納得を重視して段階的に推進している点です。これにより、現場の負担が最小限に抑えられ、システムが定着しやすい環境をつくることに成功しています。地に足のついたDX戦略が、安定的な成果を生んでいます。
出典参照:DXの取り組み|株式会社熊谷組

建設DXを推進する中で、多くの企業が共通して直面する課題があります。技術の導入自体は進んでいても、現場での運用が根付かないケースや、成果が明確に見えにくい状況も少なくありません。特に、現場ニーズとのミスマッチ、社内理解の不足、インフラや人材面での準備不足などが障壁となっています。
ここでは、DX推進の効果を最大化するために意識すべき代表的な5つの課題を取り上げ、それぞれの問題点と改善への視点を解説します。
DXを推進する上で多い失敗のひとつが、現場の実情と合わないツールを選定してしまうケースです。選定段階で現場の声が反映されず、経営陣やIT部門の意図だけでツールを導入すると、操作が複雑だったり、実際の業務フローに適合しなかったりといった問題が生じます。
結果として、現場担当者の業務負荷がむしろ増え、ツール自体が使われなくなることもあります。これは時間と費用をかけたにも関わらず成果が得られない典型的なパターンです。
ツール選定では、現場の課題や使用環境を丁寧にヒアリングし、実際に使用する従業員の視点からも評価することが重要です。操作性や導入後の運用まで見据えた選定を行うことで、現場への定着がスムーズになります。
建設DXを進める際、経営層が主導して方針を示すことは重要ですが、トップダウンのみで現場の理解を得ようとすると失敗に陥る危険性があります。現場の実務を担う人々が、自分たちにとってのメリットを感じられないままシステム導入が進むと、形だけの運用になってしまいます。
現場では「なぜこれを導入するのか」「自分の業務がどう変わるのか」が明確に伝わっていなければ、積極的な協力は得られません。これでは、本来の目的である業務効率化や品質向上が達成されず、形骸化してしまいます。
そのため、DXの目的や推進理由を現場目線で説明し、双方向のコミュニケーションを通じて合意形成を図る必要があります。現場の納得感を得ることが、継続的なDX推進の土台となるでしょう。
DXの取り組みを始める際に、推進目的や評価指標(KPI)を明確にしていないと、後から成果を正しく測定できず、継続的な改善が難しくなります。特に建設業界では、工期・品質・安全性など評価軸が多様であるため、KPIの設定には慎重な検討が求められます。
推進目的が漠然としていると、社内での認識のズレが生まれ、プロジェクトの方向性もぶれてしまうでしょう。また現場担当者にとっては、目指すべき成果が見えず、モチベーションが下がる要因にもなります。
KPIは、導入したツールやシステムがもたらす具体的な効果(作業時間の短縮、報告の迅速化、ミスの減少など)に基づいて設定し、数値で進捗を把握できるようにしておくことが重要です。定期的な評価と見直しを行う体制を整えることで、DXは持続的に改善・発展していきます。
新しいシステムやツールを導入しても、利用者が使いこなせなければ意味がありません。実際、研修時間が十分に確保されず、マニュアルのみの対応にとどまっている企業では、ツールの活用が進まず形だけの導入に終わることが少なくありません。
また、現場では多忙な日々の中で新たな操作方法を学ぶ余裕がなく、戸惑いや抵抗感が生じやすい環境です。このような状況下では、導入直後の初期教育だけでなく、定期的なフォローアップやヘルプデスクの設置といった運用サポートも不可欠でしょう。
成功につなげるには、教育を単なる説明会に終わらせず、実践形式で体験できる研修を取り入れたり、社内に問い合わせ対応ができる担当者を配置したりすることが有効です。教育とサポートは、現場の自信と安心感を生み、DXの定着を後押しします。
建設業界では、オフィスに比べて現場のITインフラ整備が遅れていることが多く、これがDX推進の妨げになるケースが見受けられます。クラウドシステムやモバイルアプリを導入しても、通信環境が不安定だったり、端末が不足していたりすると、活用の幅が限られてしまいます。
特に仮設事務所や山間部・地下などでは、Wi-Fiやモバイル通信が届きにくい状況も多く、リアルタイムでのデータ連携ができない場合もあるでしょう。こうした物理的な制約は、ツールの導入効果を低減させてしまいます。
そのため、システム導入に先立って、現場ごとの通信状況や電源設備を把握し、必要な整備を計画的に実施することが求められます。安定したインフラがなければ、いかに優れたシステムでも活用されません。現場環境に応じたインフラ整備がDX推進の第一歩です。
建設DXを推進する上では、ただツールを導入すれば良いというわけではありません。現場に根づき、継続的に成果を生み出すには、いくつかの視点を押さえた取り組みが必要です。
ここでは、実際の成功事例にも共通して見られる5つのポイントを紹介します。どの企業にもあてはまる基本でありながら、意外と見落とされやすい点でもあります。一つずつ丁寧に取り組むことで、DXの定着と業務改善が現実のものとなるでしょう。
建設DXの成果を高めるためには、まず現場の課題を正確に捉えることが出発点になります。現場の実務を知らないまま、本社やIT部門だけで判断してシステムを導入してしまうと、期待した効果が得られないばかりか、かえって業務の混乱を招く恐れもあるでしょう。
成功事例では、現場の声を取り入れて課題を明確化し、実際に使う人たちが導入プロセスに関わることで、定着しやすい運用体制を築いているといえます。現場の担当者が自分たちの業務改善に参加しているという実感を持つことで、システムへの抵抗感も軽減されるでしょう。
さらに、現場主導の姿勢は、日々の運用改善やフィードバックの循環を生み出す原動力にもなります。トップダウンとボトムアップのバランスを意識し、現場が主体となるDXの設計こそが、継続的な活用と成功につながります。
建設DXを単なるシステム導入で終わらせないためには、その目的と期待する効果を社内で共有し、明確にしておく必要があります。何を改善したいのか、どういった成果を出したいのかが曖昧なまま進めてしまうと、途中で方針がぶれ、取り組み自体が停滞する原因になります。
成功している企業では、DXの目的を業務ごとに細かく設定し、それに基づいてKPIを設計している傾向です。進捗や効果を数値で評価できる体制が整っていれば、改善点の発見や戦略の修正もスムーズです。
一方、目的が明確でない状態で推進を急ぐと、現場は「なぜこれをやるのか」が分からず、ただの負担として受け止められてしまいます。社内全体で納得できるDX戦略を立て、共通認識を持つことが推進成功の第一歩です。
いきなり全社で一斉に建設DXを推進しようとすると、現場ごとの課題や差異に対応しきれず、システムが浸透しない可能性が出てきます。そのため、最初は一部の現場や業務範囲に限定して推進し、実績や課題を検証した上で拡大していく「スモールスタート」が効果的です。
この方法の利点は、現場の反応や運用上のトラブルを早期に把握できることです。小規模な段階であれば、推進効果を確かめながら柔軟に修正できるため、現場の理解も進みやすくなります。
実際の成功例では、1現場での試験運用を経て操作の慣れや評価の共有を行い、段階的に他部署や全社に展開することで、推進効果の最大化と安定運用を両立しています。計画的な拡張がDX成功のカギです。
建設業界では、現場作業者と本社従業員でITリテラシーの差が大きいことは珍しくありません。そのため、どんなに優れたシステムを導入しても、操作方法が理解されていなければ活用されずに終わってしまうリスクがあります。
成功している企業では、導入前の研修だけでなく、実践的なトレーニングや定期的なフォローアップを行っています。社内にサポート担当者を配置することで、現場からの問い合わせにも即時対応できる体制を整えることが成功のカギです。
また、教育は一度きりではなく、機能の追加や業務フローの変化に応じて継続的な実施が求められます。現場の不安を払拭し、安心してDXツールを使ってもらうためにも、教育とサポートは運用初期から仕組みとして組み込む必要があります。
建設DXの推進においては、ただ新しい技術を導入するだけでは、効果は限定的です。既存の業務プロセスがそのまま残っている状態では、ツールの持つ機能を活かしきれないだけでなく、逆に業務が複雑化することもあります。
成功事例に共通しているのは、システムの導入と同時に業務そのものを見直し、無駄や属人化を解消している点です。例えば、紙での伝票処理をデジタル化しつつ承認フローを簡素化するなど、全体の業務効率を高めるための改革が行われています。
一方で、従来のフローにツールを無理やり組み込んだケースでは、現場の混乱や二重作業が発生し、定着に失敗しています。DXの推進を機に、業務全体を俯瞰し、合理的なプロセスへの転換を図ることが成功への近道となるでしょう。
建設DXの推進には、国の支援施策や制度を活用する視点も欠かせません。国土交通省や経済産業省は、建設業界の生産性向上やデジタル技術の普及を目的に、複数の取り組みを展開しています。
これらの制度を把握することで、戦略的なDX計画の立案や、推進時のコスト負担を軽減するヒントが得られるでしょう。
ここでは、以下の3つの具体的な施策や支援制度の概要を紹介します。
国土交通省が推進するi-Constructionは、建設現場の生産性向上を目的とした総合施策です。ICT技術の全面的な活用により、測量・設計・施工・管理までの各工程でデジタル化を進め、業務の効率化と省人化を図ることを目指しています。
特に、3次元データを活用した設計・施工プロセスの標準化や、ICT建機の導入支援が注目されています。i-Constructionの導入により、現場の視認性や作業精度が向上し、工期短縮や品質安定にもつながるでしょう。
加えて、実証実験の支援やガイドラインの整備なども行われており、初めてDXを検討する企業にも有用な情報が提供されています。制度内容を踏まえ、自社の現場に合ったデジタル化の第一歩を検討することが重要です。
BIMやCIMの活用を促進するため、国土交通省は普及促進プログラムを実施しています。これらは、設計から施工、維持管理までを3次元データで一貫して管理することで、業務の透明性と精度を高める取り組みです。
国は発注業務へのBIM/CIM活用を段階的に義務化しつつ、業界全体のスキル底上げに向けた研修や支援制度も整えています。これにより、民間企業においても導入のハードルが下がり、具体的な成果に結びつけやすくなっています。
また、公共工事での活用が進むことで、民間プロジェクトへの波及効果にもつながるでしょう。BIM/CIMを導入する際は、制度の方向性と技術動向を踏まえて計画的に進めることがポイントです。
建設DXを進めるにあたり、経済産業省や国土交通省が提供する補助金・助成金制度を活用することで、推進コストの負担を軽減できます。特に中小企業を対象とした支援が充実しており、ICT機器の導入費用や人材育成に関する経費が対象となることもあります。
代表的な制度には、ものづくり補助金、IT導入補助金、事業再構築補助金などがあり、いずれも建設業の現場改革を後押しする制度です。制度によっては専門家の支援や申請サポートも受けられるため、情報収集と計画的な活用が求められます。
これらの支援制度を上手に組み合わせることで、DX推進のスピードと安定性を高めることが可能です。自社の事業内容に応じて適切な制度を選び、戦略的な推進を図りましょう。
出典参照:建設産業・不動産業:建設市場整備推進事業費補助金 ~「地域の守り手」となる建設業のICT活用促進~ |国土交通省

建設DXの成功に向けては、技術だけでなく人材・組織・制度の視点も含めた総合的な取り組みが不可欠です。今回紹介した事例や施策からは、現場の課題に即した対応、明確な戦略、段階的な推進、継続的な教育の重要性が見えてきます。
それぞれの事例が示すように、建設DXの成果は一過性の取り組みでは得られません。長期的な視点で戦略を見直し、制度や支援を活用しながら、自社に最適なDXの形を構築するためのヒントとして本記事を活用してください。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
