建設DXでペーパーレス化は可能?メリットや成功のステップを解説
建設

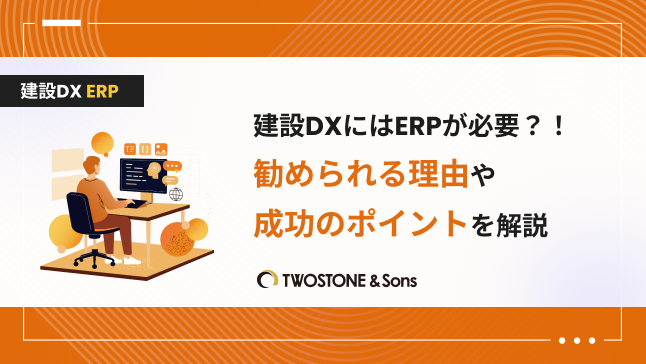
建設業界では長年にわたってアナログな管理体制が主流でしたが、近年、労働力不足や工期短縮の要請が高まる中、現場の効率化と情報共有を加速させる建設DXの重要性が急速に高まっています。しかし、多くの企業では現場と本社で情報が分断されており、全体最適な意思決定が困難な状況に陥っているケースも少なくありません。
そのような中で注目されているのがERP(統合基幹業務システム)です。ERPは、DXを効果的に進めるための中核ツールとして、業務の可視化、情報の一元管理、経営判断の迅速化に役立ちます。
本記事では、建設DXの中でなぜERPが求められるのか、その仕組みや種類、導入における成功のポイントを解説します。業務効率を本質的に改善したいと考える担当者にとって、有益なヒントが得られる内容です。

建設業におけるDXの目的は、業務の属人化や情報の分断を解消し、業務プロセスの効率化とデータに基づく意思決定を実現することにあります。この目的を実現するためには、現場情報・会計・工程・在庫・人員・労務など、企業活動のあらゆる情報を一元管理できる仕組みが必要です。
ERPは、複数の業務システムを統合し、リアルタイムでデータを可視化する統合型の基幹システムとして確立しました。建設業特有の課題、例えば各現場ごとの原価管理や工程管理、協力会社との契約管理にも対応できる柔軟性を持ち、DX推進の基盤となる存在です。
ERPの仕組みはシンプルながらも効果的です。各業務プロセスで発生するデータを、共通のデータベースに集約し、それぞれの部署や担当者が同じ情報をもとに業務を進められる状態をつくり出します。これにより、情報の重複入力や伝達ミス、管理工数の増加といった非効率を解消できます。
現場で入力された進捗データは即座に管理部門や経理部門でも確認できるようになり、予算管理や資材発注のタイミングを正確に判断できるようになるでしょう。また、システムによってはダッシュボード機能を活用することで、リアルタイムで各現場の状態を俯瞰的に把握でき、経営層が迅速な意思決定を下すための基盤にもなります。
参考:SaaS型ERPとは?クラウドを用いた業務の標準化について、メリットやデメリット、効果的な導入戦略を解説|株式会社NTTデータ グローバルソリューションズ
ERPには、導入形態や運用方法に応じていくつかのタイプが存在します。自社のサーバーにインストールして運用するオンプレミス型、インターネット経由で手軽に利用できるクラウド型など、内容も多彩です。
中には「製造業特化型ERP」「医療業特化型ERP」など業種ごとの分類もあるため、自社に合うERPを探してみましょう。企業規模や業務内容、ITインフラの整備状況によって最適な形式を選択することが成功のカギとなります。
オンプレミス型ERPは、自社のサーバーにシステムを構築し、社内ネットワークで運用する形式です。セキュリティ面での安心感やカスタマイズの自由度が高い反面、初期費用が高額になりやすく、運用・保守に専門人材が必要です。
建設業界の中でも、情報漏えいやデータ統制に対して厳格な管理が求められる大手企業では、依然としてオンプレミス型を採用するケースがあります。独自仕様のプロジェクト管理機能や会計連携など、自社に合わせた柔軟な運用が求められる場合に適しています。
パッケージ型ERPは、すでに開発済みのテンプレートを導入し、自社に必要な設定のみを行って利用する形式です。初期費用を抑えられ、導入までの期間も比較的短く済むという利点があります。
中小規模の建設会社では、必要最小限の機能から導入できるパッケージ型ERPが多く選ばれています。段階的に業務範囲を広げながら運用できる点が魅力といえるでしょう。ただし、自由度や拡張性には限界があるため、将来的な業務拡張の方針と整合を取る必要があります。
オンプレミス型とクラウド型(SaaS)を組み合わせたハイブリッド型ERPは、近年注目されている選択肢です。基幹部分は社内で運用し、日報や現場記録など頻度の高い作業はクラウドで共有するといった使い分けが可能です。
この形式は、建設業界特有の現場と本社の物理的距離やインターネット環境の差異に対応しやすく、特に複数の現場を同時に抱える企業にとっては、情報連携の利便性が高まります。安全性と利便性を両立させながら、柔軟なDX推進を目指す際に有効な選択肢です。
近年、建設DXの推進においてクラウド型ERPの導入が注目されるようになりました。その理由は、インフラ構築の手間を省きながら柔軟に機能を拡張できる利便性にあります。
クラウド型ERPは大きく分けてSaaS型、PaaS型、IaaS型の3種類があります。それぞれの特性を理解した上で、自社の業務環境や目的に合った形式を選択することが、導入後の効果を最大化するカギです。
SaaS型ERPは、クラウド上で提供されるアプリケーションを、インターネット経由でそのまま利用する形式です。ユーザーは自社でサーバーを構築する必要がなく、ベンダーが用意したERPシステムを契約・設定するだけで利用を開始できます。
導入までのスピードが速く、月額または年額の利用料でコストが明確になるため、初期投資を抑えたい企業に適しています。また、定期的なアップデートが自動で適用されるため、常に最新の機能やセキュリティ対策が担保される点も強みです。
PaaS型ERPは、クラウド上に提供された開発プラットフォーム上で、自社に最適化したERPアプリケーションを構築する形式です。基本的な開発環境と運用基盤がベンダーによって提供されるため、ゼロから開発するよりも効率的でありながら、業務に合わせた柔軟な設計が可能です。
建設業では、プロジェクトごとに業務の流れや重視する指標が異なるため、汎用的なERPでは対応しきれない場合があります。PaaS型であれば、特定の業務に特化したダッシュボードやワークフローを構築でき、必要に応じて追加開発も行えるため、業務現場に最適な仕組みを構築できます。
IaaS型ERPは、クラウド上でサーバーやストレージなどのインフラを仮想的に利用し、そこに自社のERPシステムを構築する方式です。オンプレミスと同様に、ハードウェアを所有する必要はありませんが、自由度が高いため、システム構築の全工程を自社で管理する必要があります。
そのため、IaaS型はIT部門を持ち、社内にインフラの設計や運用スキルがある企業に向いています。自社専用のセキュリティポリシーやシステム構成を適用できるため、厳格な情報統制が求められるプロジェクトや、長期にわたる業務改革を進めたい場合には有効な選択肢です。
建設DXを推進する中でERPの導入が注目されている理由は、その機能が単なる情報管理にとどまらず、業務全体の再構築と持続可能な成長戦略に直結するからです。
特に建設業界では、現場ごとに異なる条件で進行するプロジェクトの管理、煩雑な労務管理や資材調達の調整、さらには安全対策や法令遵守など、多岐にわたる業務を横断的に見渡す視点が求められます。
ここでは、建設業においてERPを導入することで実現できる6つの効果について解説します。
建設業では、見積作成から契約、設計、施工、引き渡しまで一連の流れが複数の部署や協力会社を跨いで進行します。そのため、業務が断片的になりやすく、ミスや情報の抜け漏れが発生する原因になるので注意しましょう。
ERPを導入することで、これらのプロセスを1つのシステム内でつなぎ、リアルタイムで全体を把握する環境を構築できます。発注から請求までの手続きがスムーズになることで、関係部署間での確認作業や書類のやりとりが減り、業務全体の流れを整えやすくなる点は注目すべきポイントでしょう。
業務が一本化されることにより、人的ミスの削減や属人的な判断の抑制にもつながり、安定した運用ができます。
建設業界では、現場・本社・経理・購買など、それぞれの部門が独立したシステムを使用しているケースが少なくありません。情報の二重入力や更新ミスが起きやすく、エクセルや紙ベースでの管理が混在している場合は、さらに共有や集計に時間がかかるでしょう。その結果、意思決定の遅れや誤判断が発生し、業務全体の非効率につながります。
ERPを導入することで、データを1カ所に集約・管理できる環境が整い、情報はリアルタイムで各部署に共有されます。工程の進捗状況、原価の変動、在庫情報、人員配置など、必要な情報に即座にアクセスできるため、経営判断のスピードと正確性が高まるでしょう。
建設プロジェクトでは、予算内での工事完了が重要な目標となりますが、実際にはさまざまな要因で見積もりと実績に差が出やすくなります。材料費の急騰や天候の影響、追加工事の発生、人的リソースの偏りなどがその要因の1つです。これらの変動をリアルタイムで把握できなければ、赤字案件の発生リスクが高まります。
ERPは、予定原価と実際原価を逐次比較する機能を備えており、原価管理を強力に支援します。どの工程や項目で予算を超過しているのかを即座に特定できるため、早期の是正措置が可能です。プロジェクト全体の財務的健全性を維持するために、ERPによる可視化は有効です。
建設業界では、現場経験の豊富なベテラン社員の暗黙知に業務が依存しているケースが多いです。そのため、担当者が異動・退職した際に引き継ぎがうまくいかず、現場の停滞や品質低下を招く危険性があります。
ERPは、業務プロセスを統一化・標準化する仕組みを提供します。作業内容や帳票の入力項目、承認フローなどがシステム内で定義されているため、誰が業務を担当しても、同じ手順で進めることが可能になります。これにより、業務の品質を均一に保つと同時に、教育の手間やコストも軽減されるでしょう。
建設業界は、労働基準法、建設業法、安全衛生法など、複数の法令への対応が求められます。特に、就労時間の上限管理や契約形態の適正化は、コンプライアンス上の重要なポイントです。法令違反が発覚すれば、行政処分や社会的信用の失墜といった深刻なリスクに直結します。
ERPは、労務情報、契約内容、経費処理、作業実績などを一元的に管理する仕組みを持ち、法令に基づく運用の土台を整えます。例えば、法定点検や申請期限に対して自動アラートを出すことで、人的ミスを未然に防ぐことが可能です。
建設業では、図面管理、労務管理、施工進捗の可視化など、現場ごとに様々なシステムやアプリケーションが導入されています。それぞれのツールが連携していなければ、情報は分断され、再入力の手間が発生し、作業効率が低下するでしょう。ERPは、そのような分散したシステムを束ねる中核としての役割を果たします。
特にクラウド型ERPは、API連携などを通じて、他のITツールとのデータ共有が容易です。現場の状況変化に柔軟に対応するためには、拡張性と連携性を兼ね備えたERPが必要です。

建設業界では、プロジェクトごとの収支管理や原価計算、複数拠点間の人員配置、安全管理など、横断的かつ動的な業務が日々発生します。
こうした業務の特性上、単なる帳票出力や会計処理といった部分的な支援では限界があるため、現場と本社をシームレスにつなぎ、情報共有と管理を一元化できるERP導入の検討が求められます。
ここでは、実際に建設業界で導入が進んでいる代表的なERPシステムを紹介します。
バレーナは建設業に特化したクラウド型ERPで、現場と本社間のリアルタイムな情報連携を可能にするのが特長です。現場で作成される日報や写真、勤怠情報などをタブレットやスマートフォンから直接入力でき、そのデータは即座に本社の管理画面にも反映されます。これにより、現場の状況把握や経費処理の遅れを最小限に抑え、業務全体の判断スピードを高められるでしょう。
さらに、原価管理や請求書処理といった本社業務との連携がスムーズに行えるため、プロジェクトごとの業績管理も一元化されます。現場と本社の間で情報の行き来が多く発生する建設業界において、バレーナはその煩雑さを解消するための有力な選択肢となるでしょう。建設業特有の進捗管理や現場確認の煩雑さにも対応し、全体最適化を実現する基盤として導入が進んでいます。
出典参照:建設業専用業務統合システム|株式会社Office Concierge
Obic7は、建設業務に必要な工程を1つのシステムで統合管理できるERPです。見積書の作成から発注、工事進行中の原価管理、納品後の請求処理に至るまでを一元化することで、業務の整合性と透明性を確保します。特に、複数現場が同時に稼働する建設業では、資材や人材の配置が複雑化しやすく、情報の分断や作業の重複が生じがちです。
Obic7を活用すれば、こうした煩雑な工程を可視化し、部門間の連携ミスや資材発注のタイミングのずれなどを予防できます。さらに、豊富なレポート機能が標準搭載されており、各プロジェクトごとの採算や工期、コスト状況をリアルタイムで確認できる点も魅力です。これにより、経営層の意思決定を迅速化し、経営管理の精度を高める役割も果たしています。
出典参照:建設工事業向けソリューション| 株式会社 オービック
SuperStream-NXは、会計・人事・給与の領域に特化しつつも、建設業に適した設計がなされたERPシステムです。複数の現場を担当する作業員の勤務体系や、プロジェクトごとに異なる手当ルール、労務時間の集計といった業務に柔軟に対応できます。その結果、勤怠情報の正確な把握が可能になり、給与計算における手作業のミスや管理負担の軽減が実現するでしょう。
また、法令遵守が強く求められる現代の労務管理において、勤怠記録の正確性や休暇取得状況の把握は信頼性確保の要となります。SuperStream-NXはこれらの要件に応える機能を搭載しており、労務コンプライアンスの強化にもつながります。加えて、会計システムとの連携により、給与や人件費のデータを即座に経理に反映できるため、コスト管理の精度も向上するでしょう。
出典参照:SuperStream-NX|キヤノンITソリューションズ株式会社
HUE C2は、建設業における工事原価・会計・予実管理を一体的に行うためのERPであり、利益確保のための基盤を構築するのに適しています。工事ごとの仕掛品や未成工事の支出処理、外注費の管理など、建設業独自の経理業務を自動化することで、担当者の作業負担を軽減できるでしょう。また、入力ミスや漏れといったリスクも軽減され、業務の正確性が向上します。
HUE C2では、予算と実績の差異を日次・週次などの短いスパンで把握できるため、コストオーバーやスケジュールの遅延といった問題にも即座に対応できます。このようなスピーディーな予実管理体制は、全社的なPDCAサイクルの高速化にも寄与し、経営の機動力向上につながるでしょう。複雑な工事管理と経理業務をシームレスにつなぐERPとして、高い評価を得ています。
出典参照:HUE C2|株式会社ワークスアプリケーションズ・フロンティア
AnyONEは、現場で日々行われる業務と本社の管理業務をリアルタイムで連携させる建設業向けERPです。スマートフォンやタブレットから、作業報告や資材使用、進捗状況を即時に入力できる設計になっており、現場作業員の負担を抑えながら、情報の正確性と即時性を両立させます。こうして蓄積されたデータは、自動的にクラウドを介して本社に共有され、管理部門は現場の状況を常に把握可能です。
また、現場ごとの状況に応じたリアルタイムな原価分析や納期管理が実施できるため、経営判断のスピードと精度が向上します。工程の進捗に応じて柔軟に対応を取ることで、無駄なコストの削減やトラブルの回避にもつながるでしょう。AnyONEは、現場と経営を結ぶ情報基盤としての役割を果たし、業務全体の質とスピードを向上させるツールとして導入が進んでいます。
出典参照:AnyONE|エニワン株式会社
ERP導入による建設DX推進を成功させるには、システムそのものではなく、それを支える体制や導入プロセスが肝要です。以下の要素がそろって初めてERPは現場の日常業務に自然に組み込まれ、建設DX推進において真の効果を発揮します。
これらを意識して取り組むことで、システム導入が現場に根付きやすくなります。
ERPは終了すればおしまいのプロジェクトではなく、組織全体の運用と体質を変えていく長期的な投資です。経営層が導入の背景、目的、効果について明確に示し、末端まで理解と実行の姿勢を示す必要があります。
その姿勢があると、現場では「自分たちだけ頑張ればいいのか」といった抵抗感が緩和され、主体的な参画や改善提案へとつながりやすくなります。経営層の継続したコミットメントがあれば困難が出た際も調整ができ、現場の信頼が維持され、結果的にDXを推進する文化が醸成されるでしょう。
ERPを使いやすくするためには、現場の作業員が日常的に使い続けたくなる設計が重要です。そこで、現場で何が不便なのか、どこに時間がかかっているのかをこまかくヒアリングし、対して経営層が何を可視化したいか、どのようにコストや品質を管理したいかを整理します。
この両者のギャップをより均衡にするための要件定義を行うことで、システムは現場業務を支えると同時に、経営判断にも資する仕組みとなります。例えば、現場での入力項目と帳票記入の重複を避けるなど、実際の作業負担を減らす工夫が不可欠です。
ERPは一度にすべての機能を導入するのではなく、まずは主要な業務や特定の工程でパイロット運用を行いましょう。ここからフィードバックを得て、使い勝手を改善し、システムに反映させます。
初期導入に失敗しても修正は可能ですが、現場に適合しないまま拡大してしまうと、後からの調整コストが跳ね上がります。段階導入は失敗リスクを抑えるためにも、現場への教育や定着に有効な手法です。まず使いやすい機能を浸透させ、「使える」実績を出すことが重要です。
建設業界でERPを導入し、DXを推進する動きが広がりつつあります。特に、経営層による明確なリーダーシップと現場への配慮、段階的な導入という3つのポイントを押さえた企業では、システムが現場に定着しやすくなっています。現場の負担を最小限に抑えつつ、業務効率と情報共有の改善が可能となるERPは、今後の建設業界において中核的な役割を担う存在です。
ここでは、建設業界におけるERP導入の成功事例を紹介します。
工場設備の建設やプラント整備を手がける中部プラントサービスでは、会計処理と現場での建設仮勘定が分断されていました。そのため、月末になると現場からの経費情報を集約・照合する作業に時間がかかり、決算業務の負担が大きくなっていました。伝票の手入力やデータの突き合せによる人為的なミスも発生し、会計データの整合性に不安が残る状態でした。
この課題に対し、同社はSuperStream‑NXを導入しました。建設仮勘定の処理まで含めて会計システムと統合できる点に着目し、現場で発生した経費や資材費を即座に会計情報として反映できる仕組みを整備しました。リアルタイムの入力とデータ連携により、月末の調整作業が自動化され、業務の正確性とスピードが向上しました。
出典参照:長年の利用で培った高い信頼感を背景にSuperStream-NX へと移行アドオン開発を最小限に抑えて低コストでの移行と業務標準化を実現|株式会社中部プラントサービス
鹿島建設では、現場管理を担う担当者が工事現場と本社の間を頻繁に行き来しており、移動にかかる時間や体力的な負担が深刻な課題となっていました。進捗確認や資料提出のために長距離移動を繰り返すことで、実務にかけられる時間が制限され、業務効率の低下が避けられない状況でした。さらに、突発的な対応が求められる場面では連絡や指示が滞り、プロジェクト全体の進行に影響を及ぼすケースも見られていました。
この状況を改善するため、同社はクラウド型ERPであるHUE PJMシリーズを導入しました。これは、工程表、予算実績、進捗報告などの情報をクラウド上で一元管理し、リアルタイムで共有できるツールです。その結果、担当者は現場や移動中、自宅からでも業務の把握と対応が可能となり、テレワークの実現につながりました。
出典参照:鹿島、ワークスアプリケーションズ・フロンティアのERPパッケージソフトウェア「HUE PJMシリーズ」を導入|鹿島建設株式会社
澤頭建設では、工事担当者が現場で入力した経費伝票や作業日報が、経理部門に届くまでに時間がかかり、何度も確認作業が必要になるなど、情報伝達に多くの手間がかかっていました。手書きの記録や二重入力の負担が大きく、月末の集計作業が滞ったり。部門間での情報の食い違いによる修正作業も頻発しており、業務全体の効率に課題を抱えていました。
このような課題を解消するために導入したのが、建設業専用ERP「AnyONE」です。モバイル端末を用いたリアルタイム入力と、クラウドでの情報共有機能を活用することで、現場の記録が即座に経理部門にも反映される仕組みを構築しました。これにより、現場と本社間の情報共有がスムーズになり、確認作業の手間や誤入力のリスクが低下しました。
出典参照:エクセル管理から脱却。AnyONEで業務効率が飛躍的に改善|株式会社澤頭建設

ERPはシステムを導入すればおしまいではなく、業務や文化に変化をもたらす大規模プロジェクトです。成功のためには、経営層の強いリーダーシップと現場の協力が不可欠です。さらに、現場ニーズを反映した要件定義と段階的な導入が、現場への定着に不可欠です。
建設業界において長期的に持続可能な生産体制を目指すなら、ERPの導入は最適な手段の1つといえるでしょう。ERP導入の有無で将来への差が生まれる時代に突入しています。今こそ戦略的にERPによる建設DX推進を検討し、自社の生産性を底上げしましょう。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
