建設DXでペーパーレス化は可能?メリットや成功のステップを解説
建設

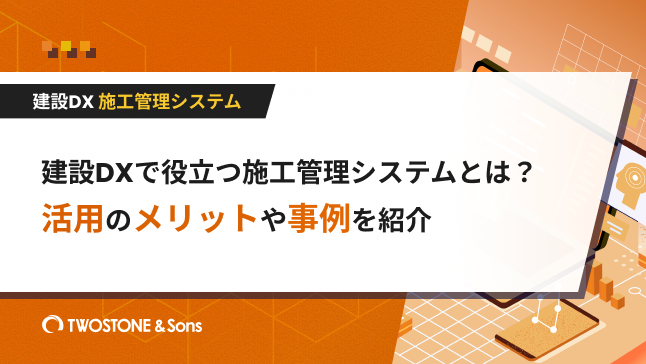
人手不足や業務の属人化、紙ベースの非効率な管理や作業員の高齢化など建設業界が抱える課題は年々深刻さを増しています。特に2024年問題を契機に、現場ではより効率的な業務運営と生産性向上が求められています。
そうした中、注目を集めているのが「施工管理システム」です。施工に関わる情報を一元化し、現場とオフィスをつなぐこの仕組みは建設DX推進の中核を担います。導入によって得られるメリットは、単なる業務効率化にとどまりません。
この記事では以下についてわかりやすく解説します。
最後まで読むと、自社における導入のイメージを具体化できるようになるでしょう。

施工管理システムとは建設工事の進捗・原価・予算・安全・品質など、複数の工程を一元的に可視化・管理できるソフトウェアの総称です。紙やExcelベースで行われていた管理業務が、クラウドやモバイルを活用したリアルタイム化により現場と本社間の連携をスムーズにして無駄やミスを削減します。
建設DXを推進する上ではまず、日々のオペレーションをデジタルでつなぐ環境が必要です。その起点となるのが、この施工管理システムです。
施工管理システムには、建設現場で求められるさまざまな管理機能が搭載されています。特に重要なのが工事の進捗をリアルタイムで把握する機能や原価・予算の管理機能、そして現場資料や写真などをクラウドで共有する機能です。
これらの機能が一体となることで情報の属人化を防ぎ、工程の遅延やコストの逸脱を早期に察知できます。全社的な連携と業務の透明性を高める役割を果たします。
施工現場では、工程の進捗状況を正確に把握し、関係者間でタイムリーに共有することが極めて重要です。しかし従来の運用では、口頭報告や紙ベースの工程表に頼るケースが多く、現場と本社、あるいは協力会社との間で情報のズレが生じやすくなっていました。このタイムラグは工期の遅延や作業の手戻りを引き起こす要因になります。
施工管理システムを導入することで、現場からの進捗報告をデジタル化し、リアルタイムで本社側と共有できます。クラウド上にアップデートされた情報は、遠隔地からでも即座に確認可能であり、現場での判断と本社のサポートがスムーズにつながるでしょう。
建設現場では人件費、資材費、外注費など、日々多様なコストが発生します。従来は、現場で発生した支出の情報を紙の伝票や手入力で集計し、後から経理部門が確認するという流れが一般的でした。このプロセスには時間がかかり、リアルタイムな予算管理が難しい状況にありました。
施工管理システムの導入により、現場で入力した費用情報が即時に本社のシステムに反映されるようになります。そのため、予算と実績の差異をすぐに確認でき、適切な対応判断が早期に可能になります。特に複数の現場を同時に進行している企業にとっては、現場ごとのコスト構造を俯瞰しながら全体の収支管理を行える点は魅力といえるでしょう。
建設現場では日報や作業計画、検査記録、写真、契約書など、多岐にわたる情報が発生します。従来は紙媒体や個々のパソコンでの管理が一般的で、情報が属人的に扱われることも少なくありませんでした。このような管理体制では、必要な情報を探し出すのに時間がかかり、関係者間での共有も非効率になりがちです。
施工管理システムでは、こうした情報をクラウドに集約して保管することで、社内の誰もが同じデータにアクセスできる環境を整備できます。モバイル端末からも閲覧・編集が可能なため、現場と本社、あるいは他部門間での連携が強化されるでしょう。担当者が不在でも、別のメンバーが即座に情報確認や対応が可能となり、業務の継続性が確保されます。
施工管理システムの導入は単なる業務効率化にとどまらず、建設DXを実現する上での基盤です。従来の属人的でアナログな管理スタイルから脱却し、誰でも同じ情報にアクセスできる仕組みをつくることが組織全体のデジタル化の第一歩です。
またクラウドベースのシステム導入により、データが部門を越えて流通して経営層も現場の実態を迅速に把握できるようになります。経営戦略と現場オペレーションをシームレスにつなげるには、こうしたデジタル基盤の整備が不可欠です。
現場改善を積み重ねながらデータ活用による意思決定力を高めるには、施工管理システムの導入が最適な手段となります。
施工管理システムの導入は建設業界が抱える、慢性的な課題を解決する上で有効です。業務の属人化や情報伝達の遅れ、工期のズレ、安全性の確保といった問題をデジタルの力で効率的に対応できます。
これまで手作業や口頭で行っていた業務のシステムでの一元化により、現場の可視化や判断の迅速化が可能になるでしょう。
ここでは施工管理システムによって得られる、5つの主要な利点について具体的に解説します。
施工管理システムの効果は、現場業務のデジタル化です。これまで紙ベースで運用していた日報や工程表、写真管理、作業指示などをすべて電子化して一元管理できます。
現場ではスマートフォンやタブレットから簡単に記録や報告ができるようになり、記入漏れや報告忘れを防ぐことが可能です。また過去のデータもシステム内に蓄積されるため、再確認や分析がしやすくなります。
作業の標準化や省力化が進み業務全体の生産性を高められるだけでなく、経験の浅い従業員でも扱いやすい環境が整います。属人化のリスクも減り、組織としての安定運営に貢献可能です。
施工管理システムでは現場とオフィス、本社など離れた場所にいる関係者間での情報共有がリアルタイムで行えるようになります。これにより、連絡の行き違いや確認の遅れによる手戻りを防止可能です。
現場で記録した内容はクラウドを介してすぐに共有され、状況把握や意思決定の精度が向上します。写真や図面の変更などもその場でアップロード・確認でき、現場の変化に即応可能な体制が整います。
特に複数の現場を同時に管理している場合、このような情報の即時共有は全体最適を実現する上で不可欠です。物理的な距離による業務ロスをなくし、業務のスピードと質を両立できます。
施工管理システムの導入により、判断に必要な情報がリアルタイムで手に入るようになるため、現場や管理者の意思決定が迅速になります。従来は、現場から本社に報告が届くまでに時間がかかり、対応が後手に回る場面も少なくありませんでした。
しかしシステム上で進捗や原価、労務情報などを即時確認できれば現状に応じた判断をその場で下せます。これによって工期の調整やコスト抑制、突発的なトラブルへの初期対応が的確に行えます。
意思決定のスピードが上がることで結果的に顧客対応も早くなり、信頼性の高い施工体制の構築が可能です。
施工管理システムの活用によって、品質管理の精度が向上します。工事の記録や進捗の確認がリアルタイムで行えるようになるため、ミスや仕様のズレを事前に防止できる環境が整います。
さらに過去のデータを分析しやすくなることで類似工事における問題点の傾向を把握し、事前の対策にも役立てることが可能です。品質に関するチェックリストや写真記録などもクラウドで一元管理されるため、抜けや漏れを防げます。
こうした取り組みは現場ごとのばらつきを減らし、安定した施工品質を保つ上で重要です。高品質の維持により、施主からの信頼獲得にもつながります。
建設現場で重要なのが安全管理です。施工管理システムの導入によって危険箇所の情報や点検結果、安全対策の実施状況などを関係者間で共有しやすくなります。
各作業員の配置状況や体調管理もシステム上で管理できるため、労災の予防にもつながります。また災害発生時には位置情報や緊急連絡先も即時に把握できるため、迅速な対応が可能です。
過去の災害事例やヒヤリ・ハットのデータを活用すれば、リスクアセスメントの精度も高まります。安全意識の高い職場づくりには、こうしたデジタルツールの力が必要不可欠です。

建設業界における業務の複雑化と人手不足が深刻化する中、現場の業務効率化を実現するためには現場と本社の連携を高める施工管理システムの導入が重要です。
ただし現場の規模や用途に応じて適したシステムを選ばなければ、その効果は半減します。ここでは工事の進捗管理から品質管理、コスト把握、さらには生コンの状態管理や360度映像の活用まで多様なニーズに対応できる施工管理システムを5つ紹介します。それぞれの特徴を理解し、最適な導入を検討する参考にしてください。
ANDPADは建設現場の多様な情報を一元管理できる、クラウド型施工管理システムです。特に現場と本社の間で、リアルタイムな情報共有を可能にする点が評価されています。
写真や工程表、図面、チャットなどの機能を備えており現場での状況報告や資料の確認がスマートフォンからでも簡単に行えます。すべてのプロジェクト情報がクラウド上に保存されるため、資料のやり取りにかかる時間と手間を削減可能です。
さらに協力業者や職人ともアカウントを共有できるため、チーム全体のコミュニケーションの質が向上します。報告の属人化を防ぎ、トラブルの未然防止にもつながります。
ダンドリワークは住宅・リフォーム業を中心とした、現場に適したクラウド型施工管理システムです。工程表や日報、写真の共有を1つのプラットフォームで完結できる設計となっており、スムーズな情報伝達を実現します。
操作が直感的でわかりやすく、現場の担当者や職人が導入後すぐに利用しやすい設計が特徴です。業務ごとの情報整理が容易になり、必要なデータを迅速に取り出せます。
特に写真の撮影・保存・共有機能は使い勝手がよく、現場の進捗確認や品質チェックに最適です。コミュニケーションと管理の両面で日々の業務を効率化できるツールとして、重宝されています。
出典参照:ダンドリワーク|株式会社ダンドリワーク
現場Plusはスマートフォンだけで工事の進捗状況や工程表を確認・更新できる、施工管理システムです。現場作業で忙しい担当者でも、手軽に最新情報を共有できることから支持を集めています。
特に注目されているのが、施工写真や日報のアップロード機能です。紙の記録を用意する手間がなくなり、報告作業が短時間で済みます。工程の変更や作業指示もリアルタイムで通知できるため、情報の伝達ミスを防ぐことが可能です。
またインターネットに接続していればどこからでも利用可能なため、複数の現場を抱える場合にも柔軟に対応できます。モバイル活用によって現場のスピード感を維持しながら、正確な情報管理を実現します。
出典参照:現場Plus|株式会社ダイテック
it‑Concreteはコンクリートの品質管理に特化した、IoT連携型の施工管理システムです。センサーを用いて生コンの温度やスランプ値、打設時刻などのデータをリアルタイムで取得・可視化する機能が備わっています。
コンクリートは温度や湿度によって品質が変化するため、施工中の状態管理が重要です。it‑Concreteの導入で打設現場での作業品質を定量的に把握でき、必要に応じて迅速な対応を行うことが可能です。
また、クラウドにデータが蓄積されるため、後日の分析や報告書の作成も効率化されます。品質の裏付けができるため、発注者との信頼構築にもつながります。
OPENSPACEは360度カメラを活用して現場の状況を自動的に記録し、進捗管理や空間の可視化を実現する次世代型の施工管理ツールです。現場を歩きながら撮影するだけで、全体の画像データがクラウドにアップロードされます。
記録されたデータは図面と連動して閲覧可能で、オフィスにいながらにして現場の状況を把握できます。遠隔地でも確認できるため現場巡回の頻度を減らし、移動時間とコストの削減につながるでしょう。
また過去の画像と比較できる機能もあり、工程ごとの進捗や変化を定量的に把握可能です。安全管理やトラブル発生時の状況証拠としても有効で、現場全体のマネジメントレベルを引き上げます。
出典参照:OPENSPACE|Open Space Labs, Inc.
建設DXを推進するにあたって施工管理システムの導入は重要なステップですが、システムをただ導入するだけでは効果を発揮しません。
現場に根差した運用ができなければ、むしろ混乱や作業負担の増加につながるおそれもあります。そのためには現場の業務内容やITリテラシーに合ったシステムを選び、運用を定着させる工夫が求められます。
ここで解説するのは施工管理システムを導入する際に重視すべき、5つのポイントです。
施工管理システムの導入で失敗しやすい原因の1つが、現場の実情を把握しないまま選定を進めてしまうことです。業種や現場の規模、作業の流れ、携わる従業員のITスキルなどに応じて必要な機能は異なります。
そのためにはまず、現場の課題や業務フローの丁寧なヒアリングが大切です。例えば写真報告に時間がかかっているのか、工程変更が頻繁なのか、紙の書類整理に負荷がかかっているのかなどを具体的に確認しましょう。
このようにニーズを明確にし、導入後に想定外の使いにくさを感じるリスクを減らすことでスムーズな現場適用が可能になります。
施工管理システムを導入しても、現場の従業員が使いこなせなければ意味がありません。特にITツールに不慣れな作業員も多い建設現場では、直感的に使える操作性とシンプルなUIが求められます。
ボタンの配置や入力方法が複雑だと誤操作や記録ミスが発生しやすくなり、導入そのものが敬遠される可能性もあります。したがって実際に現場で利用するユーザーの声を基に、操作感を重視したシステムを選ぶことが重要です。
可能であればデモ版を活用し、現場での試用を経て評価するのが効果的です。導入後の定着率を高めるためには、習熟しやすさを最優先に考えるべきでしょう。
建設DXの推進では単一のツールだけで全業務のカバーは難しい場合が多く、複数のシステムやIoT機器を併用するケースが一般的です。そのため施工管理システムは他の業務システム、現場デバイスなどと連携しやすい設計である必要があります。
例えば工程管理システムや原価管理システム、生コン温度センサーや安全管理デバイスとのデータ統合がスムーズにできるかどうかは業務全体の効率性に直結します。API連携の有無やファイル形式の互換性、リアルタイムでのデータ同期が可能かも確認すべきポイントです。
連携性の高いシステムであれば現場と本社の情報が分断されず、迅速かつ正確な意思決定ができるようになります。
建設現場ではインターネット接続が不安定なエリアや、通信が制限される地下・山間部での作業も少なくありません。こうした環境下でも施工管理システムを活用するためには、モバイル対応とオフライン利用の可否が重要な判断材料になります。
スマートフォンやタブレットで操作できるモバイル対応システムであれば現場作業員が手軽にデータを入力・確認でき、報告の即時性が高まります。また通信が不安定な場合でも、オフラインで記録した情報を後ほど自動で同期できる機能があれば業務が途切れません。
現場のリアルな使用環境を想定した上で、ストレスなく使えるシステムかどうかを事前に見極めておくことが求められます。
施工管理システムには進捗データや契約情報、原価情報など企業の重要な機密データが多く含まれます。つまりセキュリティ対策が不十分なままという状況は、情報漏えいやシステム障害のリスクが高い状態です。
まず確認すべきは通信時の暗号化やユーザーごとのアクセス制限、ログ管理といった基本的なセキュリティ機能が備わっているかどうかでしょう。加えてサーバートラブルや誤操作によるデータ消失に備えた、自動バックアップの仕組みにも注目です。
クラウド型システムを選ぶ際は提供会社のセキュリティ体制や対応実績を確認し、自社の情報を安全に扱える環境が整っているかを判断しましょう。
建設DXの推進に向け、多くの建設企業が施工管理システムの導入を進めています。これにより、業務効率の向上や品質の安定化、情報共有の円滑化といった成果が得られています。
ここで紹介するのは、施工管理システムを先進的に活用し、建設DXの実現に成功している大手企業の事例です。各社の取り組み内容を通じて、導入効果や運用の工夫、成功に至るまでのポイントが見えてきます。
大成建設株式会社はコンクリートの品質管理を高度化するためにit‑Concreteを導入しました。このシステムはIoT技術を活用して生コンの温度やスランプ値、打設時間などをリアルタイムで計測・記録します。
コンクリートの品質は施工の安全性や耐久性に直結するため、施工現場での正確な状態把握が不可欠です。it‑Concreteによってこれまで経験や勘に頼っていた管理作業をデータ化でき、問題発生時の迅速な対応が可能となりました。
さらに取得したデータはクラウドで一元管理され、社内の関係者がどこからでも閲覧できるため品質管理の透明性が高まり、信頼性の向上にも寄与しています。これにより施工ミスのリスクを減らし、顧客満足度の向上も実現しています。
出典参照:it-Concrete コンクリート品質管理システム|大成建設株式会社
清水建設株式会社はOPENSPACEを活用して360度カメラによる現場の自動撮影と遠隔監視を行い、施工管理の効率化を図りました。現場を歩き回りながら撮影された映像はクラウドに即時アップロードされ、オフィスや遠隔地からでも360度の現場状況を把握できます。
これによって現場巡回の回数を減らし、移動時間やコストの削減が実現されました。また映像の記録は進捗管理や安全管理、トラブル時の証拠資料としても活用され施工品質の安定化に貢献しています。
さらに施工状況の共有がスムーズになることで関係者間のコミュニケーションも活性化し、意思決定のスピードアップと情報の透明化を促進しています。清水建設の取り組みは、建設DX推進のモデルケースとして注目されている代表的な例といえるでしょう。
出典参照:建設現場管理ソフト開発「OpenSpace社」と販売代理店契約を締結|清水建設株式会社
白石建設株式会社はANDPADを導入し、施工現場の写真管理や工程管理、原価管理を一元化しました。これまで手作業で行われていた情報の集約や報告が効率化され、現場担当者と本社間の情報共有がスムーズになりました。
ANDPADはスマートフォンやタブレットでの操作に優れており、現場の従業員が撮影した写真や工程の変更、コスト状況などの情報をリアルタイムに共有可能です。これによって現場での意思決定が迅速化し、施工ミスの防止にもつながっています。
また原価管理がリアルタイムで行えるため、プロジェクト全体のコスト意識が高まり不必要な支出を抑制できます。白石建設の活用事例が示すのは施工管理システム導入が生産性と品質向上の両面で効果的である、ということです。
出典参照:ブラックボックスの現場をクラウドで見える化し、スマートな現場へ| 白石建設株式会社
施工管理システムの導入は建設DXを推進する上で効果的ですが、無計画に導入するとかえって業務の混乱や負担増加を招くリスクがあります。そこで注意すべき点を押さえ、導入効果を最大化しましょう。
システムのカスタマイズや導入範囲の決定は慎重に行い、段階的な展開で運用定着を図ることが推奨されます。ここで解説するのは施工管理システム導入時に避けるべき過剰なカスタマイズと、導入範囲の広げすぎに関する注意点です。
施工管理システムを導入する際には業務に合わせて細かくカスタマイズしたい、というのは当然の欲求でしょう。しかし過剰なカスタマイズはシステムの保守性、運用の安定性などを損なう原因となります。
カスタマイズが複雑化するとシステムのアップデート時にトラブルが発生しやすくなり、結果的に運用コストが増加します。また担当者が変更になるたびに管理が難しくなり、属人化のリスクも高まる点も無視できません。
まずは標準機能を最大限活用し、どうしても必要な部分だけを最小限に調整する方針が望ましいです。これにより導入時の負荷を軽減し、将来的な拡張や他システムとの連携もスムーズになります。
施工管理システムの導入範囲を一度に広げすぎることは、社内の混乱や運用の失敗につながりやすいため注意が必要です。広範囲に導入した場合は操作方法の習熟やシステムトラブルへの対応が追いつかず、現場の抵抗感も強まります。
そのためまずは一部のプロジェクトや部署で試験的に導入し、課題を洗い出しながら段階的に展開するアプローチが効果的です。この方法は運用面の問題を早期に発見でき、教育やサポート体制の強化にもつながります。
段階的な拡大によって現場の従業員からの理解と協力が得やすくなり、全社的なDX推進の成功確率を高めます。焦らず慎重に進めることが重要です。

建設DXの推進において、施工管理システムの導入は業務の効率化や品質の安定化に寄与する有力な手段です。現場作業の進捗管理や原価管理、資料の共有といった複雑な業務をシステム化することで、従来の手作業によるミスや作業の重複を回避しやすくなります。
一方で、過度なカスタマイズや一気に全機能を展開する導入方法は、現場の混乱を招く恐れがあります。
今回紹介した施工管理システムの機能や実際の導入事例を踏まえ、自社の業務内容や組織体制に最適なシステムを検討し、無理のない形で導入を進めることが建設DX成功への第一歩となるでしょう。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
