『n8n×Apify』記事リサーチの工数を大幅削減|上位記事のHタグ構成を瞬時に抽出してスプレッドシートにまとめる方法
全般


調達DXのセキュリティ対策でお悩みですか?サプライチェーン攻撃などのリスクから自社を守る方法を解説します。安全なツールの選び方からサプライヤーの評価手順、先進企業の成功事例まで、担当者が知りたい情報を網羅します。

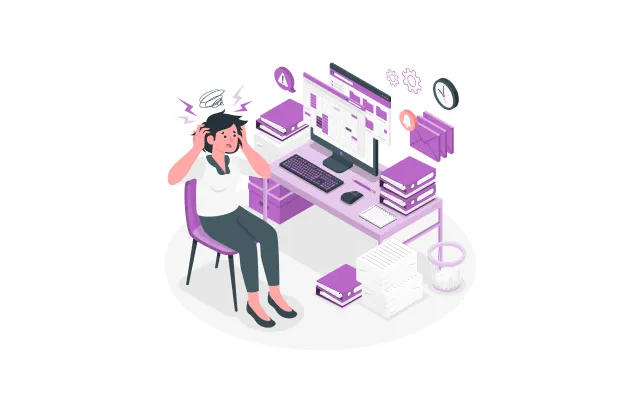
・6万名以上のエンジニアネットワークを活用して課題を解決※
・貴社のDX戦略立案から実行・開発までワンストップで支援可能
※エンジニア数は2026年8月期 第1四半期決算説明資料に基づきます。
調達業務のDX(デジタルトランスフォーメーション)は、コスト削減や業務効率化に大きく貢献します。その一方で、取引先の機密情報などをクラウドで扱うことへのセキュリティ不安は、多くの担当者が抱える課題ではないでしょうか。
この記事では、調達DXを進める上で知っておくべきセキュリティリスクを解説します。安全なツール選びのポイントからサプライヤーの評価方法、さらには先進企業の成功事例まで、分かりやすくご紹介します。

調達DXを推進する上で、効率化の恩恵と引き換えに発生するセキュリティリスクを正しく理解することが第一歩です。これらのリスクは自社だけでなく取引先にも影響を及ぼすため、事前の対策が欠かせません。
ここでは、特に注意すべき5つの代表的なセキュリティリスクについて解説していきます。
サプライチェーン攻撃とは、セキュリティ対策が比較的脆弱な取引先や子会社を踏み台にして、本来の標的である大企業へ侵入するサイバー攻撃のことです。調達業務では多くのサプライヤーとシステム連携を行うため、1社のセキュリティ不備がサプライチェーン全体の脅威になり得ます。
攻撃者は取引先との信頼関係を悪用し、正規の通信を装って侵入してくるため、検知が非常に困難です。自社のセキュリティを固めるだけでなく、取引先全体のセキュリティレベルを把握し、向上させることが非常に重要になるでしょう。
ランサムウェアは、企業のシステムやデータを暗号化して使えなくしてしまい、元に戻すことと引き換えに身代金を要求する不正なプログラムです。もし調達管理システムが被害に遭うと、発注データやサプライヤー情報にアクセスできなくなり、調達業務が完全に止まってしまう恐れがあります。
「情報セキュリティ白書2024」によると、2023年7月に名古屋港運協会に対し侵入型ランサムウェア攻撃が発生し、名古屋港の全コンテナターミナルで利用中の統一ターミナルシステムが全面停止した例などがあります。
近年では、データを暗号化するだけでなく、盗んだ情報を公開すると脅す「二重恐喝」の手口も増えています。これにより、生産ラインの停止や納期遅延など、事業全体に深刻な影響が及ぶ可能性も考えられます。
出典参照:情報セキュリティ白書2024(p.6-18)|IPA
調達部門は、価格情報、契約内容、取引先リストといった、企業の競争力に直結する大切な情報を多く扱っています。そのため、サイバー攻撃者にとって魅力的な標的となりやすいのです。
標的型攻撃は、業務に関連するメールを装ってウイルスを送り込むなど、巧妙な手口で侵入を試みます。攻撃者は事前にターゲット企業を詳しく調査しているため、従業員が見破るのは非常に困難です。一度侵入を許してしまうと、長期間気づかないうちに、継続的に機密情報を盗み出される危険性があります。
クラウド型の調達管理ツールは非常に便利ですが、クラウドサービス特有のセキュリティリスクも理解しておく必要があります。例えば、サービス提供事業者側のシステムに脆弱性があった場合、それがそのまま自社のセキュリティリスクに繋がってしまいます。
また、利用者側の設定ミスが原因で、意図せず情報が外部に公開されてしまうケースも少なくありません。特に、アクセス権限の管理は重要で、「誰でもアクセス可能」といった安易な設定が、重大な情報漏洩事故を引き起こすことがあります。
クラウドサービスを利用する際は、提供者と利用者の責任範囲を正しく理解することが大切です。
セキュリティリスクは、外部からの攻撃だけではありません。従業員や元従業員など、組織の内部関係者が意図的に情報を持ち出したり、不注意で情報を漏らしたりすることも深刻なリスクです。
特に、退職者が取引先リストや価格情報といった機密情報を不正に持ち出し、競合他社へ渡してしまうといったケースが考えられます。悪意のある持ち出しだけでなく、USBメモリの紛失やメールの誤送信といった、ヒューマンエラーが原因となることもあります。
誰がどの情報にアクセスできるのかを適切に管理し、操作の記録を監視することで、不正を早く見つけたり、防いだりする体制を整えることが求められます。
調達DXを安全に進めるためには、導入するツールのセキュリティレベルが非常に重要です。機能やコストだけでなく、企業の機密情報を安心して預けられるかどうかを厳しく評価する必要があります。
ここでは、ツールを選ぶ際に必ず確認したい、4つの重要なセキュリティポイントを解説します。
ツール提供事業者が、客観的な基準でセキュリティレベルを保っているかを確認する分かりやすい指標として、国際的なセキュリティ認証の取得状況があります。例えば、情報セキュリティ管理の国際規格である「ISO/IEC 27001」や、クラウドサービスの信頼性を評価する「SOC 2報告書」などが挙げられます。
これらの認証は、定期的な厳しい審査を経て維持されるため、継続的に高いセキュリティレベルを保っている証拠となります。ツール選定の初期段階で、これらの認証の有無をウェブサイトなどで確認することが効率的です。
内部不正や設定ミスによる情報漏洩を防ぐためには、細かいアクセス権限の管理機能が欠かせません。「誰が」「どの情報に」「どこまでアクセスできるか」を役職や担当業務に応じて厳密に設定できるかを確認しましょう。
例えば、担当者ごとに閲覧・編集できるサプライヤー情報を制限する機能などが考えられます。また、保存されているデータと通信中のデータの両方が、強力な方式で暗号化されていることも必須の要件です。
これにより、万が一データが外部に流出しても、内容を読み取られるリスクを最小限にできます。
ソフトウェアに存在するセキュリティ上の欠陥を「脆弱性」と呼びます。ツール提供事業者が、自社サービスの脆弱性を発見し、修正するためにどのような取り組みを行っているかを確認することが大切です。
具体的には、第三者の専門家による定期的な脆弱性診断や侵入テストを実施しているか、その結果を公開しているかなどを確認しましょう。新たな攻撃手法は日々生まれているため、こうした定期的な診断は不可欠です。
発見された脆弱性に対して、どのくらいの期間で修正対応が行われるのかという点も確認すると、より安心材料になるでしょう。
セキュリティに関する問題は、いつ発生するか予測ができません。そのため、万が一の事態に備えたサポート体制や、障害発生時の対応フローが明確に定められているかを確認することが不可欠です。24時間365日対応のサポート窓口があるか、問題発生時の連絡体制や復旧までの目標時間が定められているかなどを事前に確かめましょう。
特に海外のサプライヤーと取引がある場合は、時差を考慮したグローバルなサポート体制が整っていると、より安心です。信頼できるパートナーを選ぶことが、安定した運用に繋がります。

市場には数多くの調達DXツールがありますが、特に世界的に豊富な導入実績があり、セキュリティ機能に定評のあるツールを選ぶことが成功への近道です。
ここでは、代表的な3つのツールを取り上げ、それぞれのセキュリティに関する特徴を解説します。
SAP Aribaは、世界最大級のビジネスネットワークを持つ、調達・購買管理のソリューションです。導入事例では、株式会社日立ハイテクや株式会社 NTT データなど、多くの導入実績が掲載されています。
SAP社の非常に堅牢なセキュリティ基盤の上でサービスが提供されており、データセンターの物理的な安全対策からアプリケーションの保護まで、何重もの防御策が施されています。
特に、サプライヤーのリスク評価やコンプライアンス管理の機能が充実しており、グローバルなサプライチェーンにおけるセキュリティ管理を強化するのに役立ちます。
出典参照:導入事例|SAP ジャパン株式会社
Coupaは、調達から支払いまで、ビジネスでのお金の流れをまとめて管理できます。全世界3,100社以上が利用するAIネイティブ総支出管理クラウドプラットフォームです。
すべての業務が一つのプラットフォームで完結するため、システムを連携させる際に生じるセキュリティリスクを減らせる点が大きな特徴です。また、「Coupa Risk Assess」という機能を通じて、サプライヤーのセキュリティリスクを継続的に評価・監視することもできます。
Amazon Web Services(AWS)という信頼性の高いインフラ上で動いており、安定したサービスと高い安全性を実現しています。
出典参照:Coupa|Coupa株式会社
出典参照:会社概要|Coupa株式会社
Oracle Fusion Cloud Procurementは、Oracle社が提供する総合的な調達管理ソリューションです。
このツールの最大の強みは、セキュリティを最優先に設計された「Oracle Cloud Infrastructure (OCI)」という基盤上でサービスが提供されている点にあります。
脅威を自動で検知・修復するデータベース機能や、高度なアクセス管理機能により、企業の重要な調達データをサイバー攻撃からしっかりと保護してくれます。
出典参照:Oracle Fusion Cloud Procurement|日本オラクル株式会社
安全な調達DXを実現するためには、自社で導入するツールだけでなく、サプライチェーンを構成する取引先全体のセキュリティレベルを把握し、管理することが欠かせません。
ここでは、サプライヤーのセキュリティ体制を評価するための具体的な4つのステップを紹介します。
まず、サプライヤーに求めるセキュリティレベルを決め、それを評価するための基準と具体的なチェックリストを作ります。評価基準は、経済産業省が公開している「サイバーセキュリティ経営ガイドライン」などを参考にすると良いでしょう。
チェックリストには、「情報セキュリティに関する社内ルールはありますか」「従業員へのセキュリティ教育を定期的に行っていますか」といった、具体的な質問項目を盛り込みます。このチェックリストは、自社の事業内容や取引の重要度に応じてカスタマイズすることが大切です。
情報システム部門など関連部署と連携し、網羅性の高いリストを作成することをおすすめします。
作成したチェックリストをもとに、各サプライヤーへアンケート形式で回答をお願いします。これにより、多くのサプライヤーのセキュリティ状況を効率的に把握することができます。アンケートを送る際は、評価の目的を丁寧に説明し、サプライヤーの理解と協力を求めることが円滑な進行の鍵となります。
ただし、自己申告だけでは本当の状況が分からない可能性もあるため、特に重要な取引先には、担当者と直接話すヒアリングの機会を設けることが望ましいです。ヒアリングでは、「具体的にどのように対策していますか?」といった深掘りの質問をすることで、実態をより正確に把握できるでしょう。
集めたアンケートやヒアリングの結果から、各サプライヤーのセキュリティリスクを分析・評価します。リスクの大きさを「高・中・低」などで判定し、特にリスクが高いと判断されたサプライヤーには、具体的な改善策を盛り込んだ是正計画の提出をお願いしましょう。
その際、どの項目に課題があるのかを具体的にフィードバックすることが重要です。一方的に取引を停止するのではなく、改善の期限を明確に設定し、サプライヤーと協力してセキュリティレベルの向上を目指す姿勢が、サプライチェーン全体の強化に繋がります。
自社が持つノウハウを提供するなど、改善活動を支援することも有効な手段です。
一度評価して終わりにするのではなく、サプライヤーのセキュリティ状況を継続的に見守り、少なくとも年に1回は定期的な再評価を行うことが重要です。ビジネスの環境やサイバー攻撃の手口は常に変化するため、評価基準やチェックリストも定期的に見直す必要があります。
サプライヤー側で重大なセキュリティ事故が発生した場合や、組織体制に大きな変更があった場合に、速やかに報告してもらうルールを契約書などに盛り込んでおくことも有効です。新しい取引を始める際の必須プロセスとして、このセキュリティ評価を定着させることが、安全なサプライチェーンを維持する鍵となるでしょう。

理論だけでなく、実際に企業がどのようにして調達DXとセキュリティ強化を両立させているのかを知ることは、自社の取り組みを進める上で非常に参考になります。
ここでは、先進的な取り組みで成果を上げている国内企業の事例を2つ紹介します。
自動車部品メーカーの株式会社杉浦製作所は、自動車業界のサプライチェーンの一員として、取引先から高いレベルのセキュリティ対策を求められていました。
従来のウイルス対策ソフトだけでは防ぎきれない未知の脅威への懸念から、同社はEDR(Endpoint Detection and Response)という仕組みを導入しました。これは、パソコンやサーバーの不審な動きを検知して、迅速に対応するためのものです。
専門家による24時間の監視サービスも併せて利用することで、セキュリティ担当者の負担を増やすことなく、サイバー攻撃への対応力を大幅に向上させました。この取り組みにより、同社は取引先からの信頼を獲得し、安心して調達DXを推進できる体制を整えることができました。
出典参照:中堅企業のEDR、決め手は総合的なコストパフォーマンス|株式会社杉浦製作所
大手総合商社の住友商事株式会社は全社的なDX推進の中で、クラウドサービスの利用を拡大していました。しかし、社外からのアクセスや多様な働き方が増える中で、従来の「社内は安全」という考え方に基づくセキュリティ対策では不十分だと判断しました。
そこで同社は、「すべてのアクセスを信用しない」ことを前提とするゼロトラストという新しい考え方を導入しました。具体的には、場所や端末を問わずにすべての通信を検査し、厳格な認証を経なければ社内システムやクラウドサービスにアクセスできない仕組みを構築したのです。
これにより、利便性を損なうことなくセキュリティを大幅に強化し、社員がどこからでも安全に業務を行える環境を実現しました。
出典参照:現場主導で生まれた、業務のデジタライゼーションへの動き 国内からグローバルへと展開し、事業のバリューアップを促進する|住友商事株式会社
安全な調達DXの実現は、一度きりの対策では終わりません。継続的なアクションが不可欠です。まずは自社に潜むリスクを正確に把握し、セキュリティ要件を盛り込んだツール選定基準を確立しましょう。
さらに、サプライヤーのセキュリティ評価を業務プロセスに定着させ、万が一の事態に備えて情報システム部門との連携体制を整えることが重要です。セキュリティを単なるコストとしてではなく、事業を守り成長させるための未来への投資と捉える視点が、成功への道を拓きます。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。
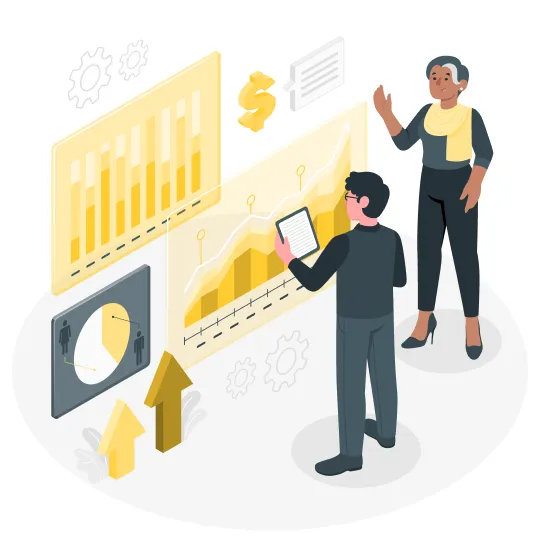
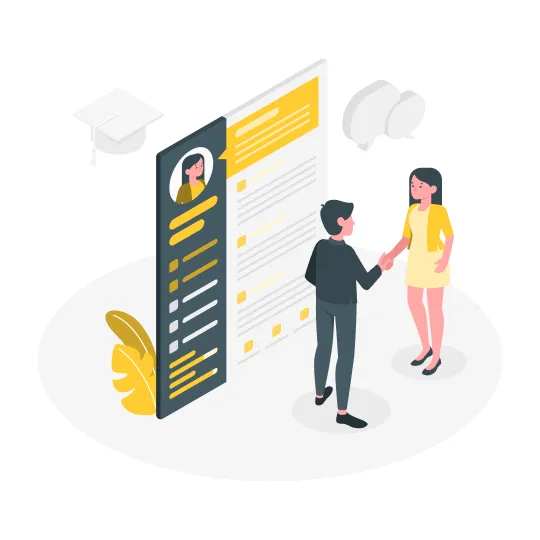
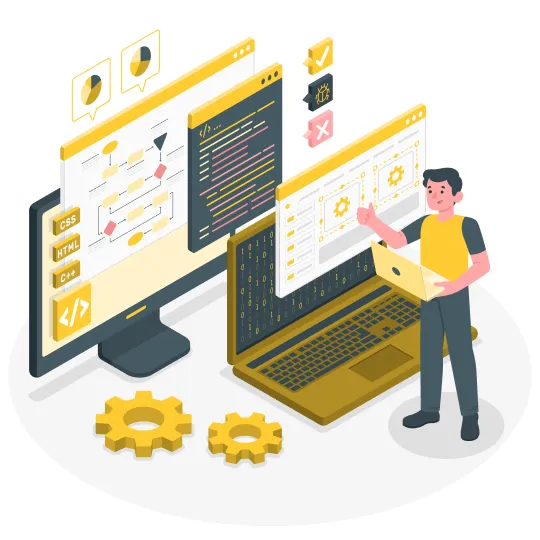
幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
