金融DXの推進によって叶う勘定系システムの刷新|4つの取り組み例を紹介
金融

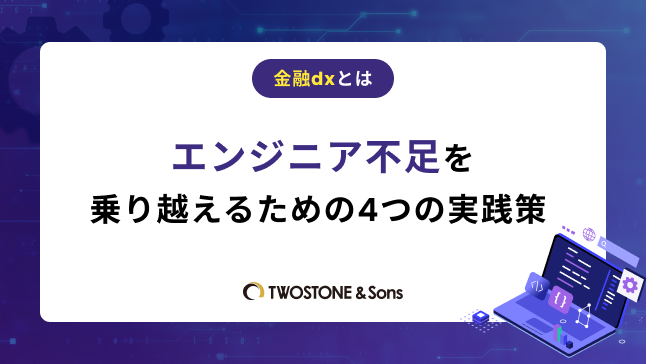
近年、金融業界でもデジタルトランスフォーメーション(DX)の波が加速しています。しかし、多くの金融機関では「エンジニア不足」という課題に直面しており、DXを進めたくても進められない現実に悩んでいるのではないでしょうか。
この記事では、そんな悩みを抱える方に向けて金融DXとは何か解説するとともに、エンジニア不足を乗り越えるための実践策を詳しく紹介します。この記事を読むことで、金融DXを推進するメリットを理解して具体的な解決策を知ることができ、自社の未来に向けた確かな一歩を踏み出せるようになります。

金融業界においてDXが推進される今、その本質を正しく理解することが的確な戦略を立てる第一歩となります。
ここでは、金融DXとは何かを明確にし、さらに金融業界でDXが求められる背景について解説していきます。
金融DXとは、銀行・証券・保険などの金融機関がデジタル技術を活用して、業務プロセスやビジネスモデル・顧客体験を根本から変革する取り組みを指します。単なる業務のデジタル化ではなく、AI(人工知能)・ビッグデータ・クラウド・ブロックチェーンといった先端技術を駆使し、競争優位性を高めることが目標です。
例えば、融資審査をAIで自動化したり顧客行動データをもとにニーズに合わせたサービスを提供したりすることなどが含まれます。つまり金融DXは、デジタルを手段としてビジネス全体を変革する戦略的取り組みといえるでしょう。
では、なぜ今金融業界でDXが急務とされているのでしょうか。その理由は大きく分けて以下の3つです。
スマートフォンの普及により、顧客はいつでもどこでもサービスを受けたいと望むようになりました。フィンテック企業が業績を伸ばしてきているためもあり、金融機関にはスピーディーな対応が求められます。また、低金利環境が続く中、従来の収益モデルでは限界があり、業務効率化やコスト削減に向けた抜本的な改革を進める必要があると考えられています。
このような状況を踏まえると、金融DXはもはや選択肢ではなく必須の取り組みだといえるでしょう。
金融DXを推進することには、単なるシステム更新以上のメリットがあります。
ここでは、顧客体験の向上、業務効率とコスト削減、新規ビジネス創出という3つの観点からDX推進の意義を掘り下げていきます。
金融DXの恩恵の一つは、顧客体験(CX)の質を高められる点です。従来、融資手続きや口座開設には多くの書類提出や対面手続きが必要でしたが、DXによってこれらをオンライン化すれば顧客の負担を軽減できます。
例えば、スマートフォンアプリを通じて数分でローン申請が完了する仕組みを整えることで顧客満足度を向上させることができるでしょう。また、データ活用によって個々のニーズに合わせた商品提案ができるようになり、より深い顧客エンゲージメントを実現できます。
金融機関にとっては、顧客ロイヤルティの向上にも直結する重要なポイントといえるでしょう。
金融DXは、内部業務の効率化とコスト削減にも直結します。例えば、融資審査や取引モニタリングにAIを取り入れることで人手に頼っていた作業を自動化でき、ミスの削減と処理速度の向上が実現します。さらに、クラウドシステムを活用することで、従来のオンプレミス型インフラに比べて運用・保守コストを抑えることも可能です。
このように、DXによる業務効率化は、限られたリソースでより高い生産性を追求する上で非常に効果的なアプローチといえるでしょう。また、リモートワークの普及を見据えた柔軟な働き方改革にも貢献します。
DXを推進することで、これまでになかった新たなビジネスモデルを生み出すチャンスも広がります。例えば、オープンバンキングの仕組みを活用して外部企業と連携して新たな金融サービスを提供する事例が増えています。また、サブスクリプション型の保険商品やAIによる資産運用アドバイザリーサービスなど、顧客のライフスタイルに密着した新しい収益モデルの開発も可能です。
このように、金融DXは単なる効率化に留まらず、競争力そのものを高めるための重要な戦略であるといえます。従来型の業務モデルに固執するだけでは、今後の激しい市場環境に生き残ることは難しいでしょう。
DX推進において慢性的なエンジニア不足は深刻な課題となっています。この問題に対して、単なる採用強化だけでなく根本的な業務設計や社内体制の見直しが不可欠です。
ここでは、エンジニア不足を本質的に解消するための具体策を紹介します。
エンジニア不足を採用活動だけで解消しようとすると、限界に直面するのが現実です。むしろ、職務設計と業務分担の最適化によって既存リソースで効率的に業務を遂行できる体制を築くことが重要です。
具体的には、プロジェクトごとに必要なスキルセットを明確化し専門領域ごとに役割分担を細分化します。例えば、要件定義や設計フェーズは業務アナリストが担い、開発工程はエンジニアに集中させるといった方法です。これによってエンジニア1人当たりの負担を減らし、成果の最大化を目指しましょう。
また、ノーコード・ローコードツールを導入して非エンジニアでも対応可能な業務領域を広げることも効果的です。
エンジニアの採用競争は激化しており、優秀な人材を確保しても流出リスクは常に存在します。そのため、社内での定着率向上こそが持続可能な組織運営には不可欠です。
定着率向上にはキャリアパスの明確化と適切な評価制度の整備が効果を発揮します。例えば、技術力に応じた昇進ルート(エキスパート職とマネジメント職の両立)を提示し、自身の成長ビジョンを描きやすくする環境を整えることが重要です。
さらに、柔軟な働き方の推進も欠かせません。リモートワーク制度の整備やフレックスタイム制の導入によって、エンジニアが働きやすい環境を提供しましょう。環境を提供することで企業へのロイヤルティ向上と離職防止が期待できます。
人員リソースが十分でない状況でも高い成果を出すためには、チーム運営に工夫を凝らす必要があります。単なる作業分担ではなく、チームの生産性を最大化するための戦略的マネジメントが求められます。
具体策としては、アジャイル開発手法の導入が効果的です。スプリント単位でタスクを細かく区切り短期間で成果を積み上げることで、限られたリソースでもプロジェクト全体の推進力を高めることができます。
また、情報共有を促進するために、進捗状況の確認や振り返りを定期的に実施しましょう。振り返りを定期的に行うことでチーム内の課題を早期に発見し、スムーズな軌道修正が可能となります。
金融業界のDX推進には、即戦力となるエンジニアや技術者だけでなく、現場の社員全体にDXリテラシーを浸透させることが鍵となります。
ここでは、金融業界特有の事情を踏まえた人材育成策を紹介します。
DX人材の育成において、即戦力のみを求めるのは現実的ではありません。特に金融業界では業務知識とテクノロジー両方を理解する人材の育成が重要となるため、初心者から段階的に育成する体制づくりが必要です。
効果的な方法として、OJT(On the Job Training)とメンター制度を組み合わせた育成体制が推奨されます。実務経験を積みながら経験豊富な社員が1対1で指導する仕組みを整えるのです。これにより、学びながら現場適応力を高めることができ、現場力の底上げが期待できます。
また、失敗を許容してチャレンジを促す文化を醸成することも成長を加速させる要素となるでしょう。
金融DX人材の育成では、全員に同じ内容を教えるだけでは十分ではありません。スキルレベルや職種に応じた最適化された研修プログラムの設計が不可欠です。
例えば、エンジニア向けには最新のクラウド技術やセキュリティ知識を深堀りする講座を、データアナリスト向けには機械学習やデータモデリングに特化したトレーニングを提供します。さらに、マネジメント層にはDX戦略策定やデジタル組織マネジメントに関する講義を実施しましょう。
研修内容は実践型を中心に構成し、ケーススタディやワークショップ形式を多用することで受講者の実務応用力を引き上げる工夫が必要です。
金融機関全体でDXを推進するためには、一部の専門人材だけでなく全社員に対してDXリテラシーを浸透させる取り組みが求められます。リテラシーとは、単にIT知識を持つことではなくテクノロジーを活用して業務変革を推進できる力のことです。
まずは、全社員に向けた基礎研修を実施し、DXの基本概念やデータ活用の重要性について理解を促します。次に、職種や役割ごとに応じた応用編へと段階的にレベルアップしていく設計が理想です。
eラーニングと対面研修を組み合わせることで、個々の理解度に応じた学びを促進しましょう。最終的には、社員一人ひとりが自らデジタル技術を活用して業務改善に取り組む「自走型組織」への進化を目指します。

金融DXを成功させるためには、単にシステムやツールを導入するだけでは不十分です。企業文化そのものを変革し、デジタルに適応できる柔軟な組織をつくり上げることが大切です。
ここでは、カルチャー変革を実現するための具体的なアプローチを紹介します。
従来の金融機関では、年功序列や対面主義といった伝統的な慣習が根強く残っています。しかしDX推進においては、これらの古い価値観を見直し新しい働き方を支援する制度設計が求められます。
まずはリモートワークやフレックスタイム制の導入を進め、業務の柔軟性を高めることが重要です。さらに、プロジェクトベースでの働き方や社内副業制度などを取り入れ、多様なキャリアパスを許容する文化を醸成するべきでしょう。このような制度変更により、社員一人ひとりがイノベーションに主体的に関与しやすい環境を整えることが可能になります。
金融DXの実現には、現場を巻き込んで変革を推進するリーダーの存在が不可欠です。ただし、単なる管理職ではなくデジタルリテラシーを備え、変化を恐れずチャレンジする姿勢を持つリーダーが求められます。
そのためには次世代リーダー育成プログラムを策定し、デジタル戦略・アジャイルマネジメント・デザイン思考などを体系的に学べる機会を提供しましょう。また、経営層自らが変革の旗振り役となり現場の声を尊重する姿勢を示すことで、組織全体の意識改革を促進することができます。
単にトップダウンで指示を出すだけではカルチャー変革は定着しません。社員一人ひとりが変革の意味を理解した上で納得感を持って取り組めるようにするためには、オープンな対話の場を設けることが欠かせません。
具体的には、定期的な管理職と社員のミーティングや社内ワークショップを通じて、経営ビジョンと個々の業務がどう結びつくのかを共有する場を設計します。そして、評価制度も「チャレンジ精神」や「デジタル活用への貢献度」を正当に評価する仕組みに見直し、社員が安心して新たな取り組みに挑戦できる土壌を整えましょう。
短期的な人材獲得競争にばかり注力していては、金融DXを本質的に推進することはできません。持続可能な人材戦略を描き、社員一人ひとりのキャリア成長を支援する仕組み作りが必要です。
ここでは、その具体策を紹介するので参考にしてください。
即戦力人材を中途採用で獲得することも重要ですが、それだけに頼るのはリスクが高いです。金融DXでは、企業独自のビジネス理解と高度なデジタルスキルを兼ね備えた人材の内製化が求められます。
そのためには、新卒採用から育成を見据えた計画を立案し、入社後数年単位でのリスキリングプログラムやローテーション制度を設けることが効果的です。また、外部研修やビジネススクールへの派遣など体系的なスキル強化策を盛り込んだ人材育成ロードマップを策定し、組織的に人材力を底上げしていきましょう。
育成を進める上では、社員自身が自分の成長や習得スキルを可視化できることが重要です。このため、キャリアパス制度とスキルマップを整備して職種ごとに必要なスキルセットやキャリアの到達目標を明示する必要があります。
例えば、「データサイエンティスト」「プロダクトマネージャー」などの職種に対して、求められる知識・経験・能力をリスト化し、社員が自らの成長に向けて具体的な行動計画を立てられるよう支援します。さらに、定期的なキャリア面談を通じて上司と目標設定や進捗確認を行うことで、成長実感を高めることができるでしょう。
金融DXの領域ではテクノロジーの進化スピードが極めて速いため、社員が常に最新知識を習得し続ける必要があります。そのためには、全社的にリスキリング・アップスキリングの機会を提供して学び直しを文化として根付かせることが重要です。
具体的には、eラーニング・社内オンライン講座・デジタルバッジ制度などを導入し、多様な学習スタイルに対応できるプログラムを整備します。また、学習成果を昇進・昇格条件に組み込むことで学びに対する動機付けを強化し、社員一人ひとりが主体的にスキルアップに取り組める環境を整えるのも1つの方法です。
金融DXを成功させるためには、技術導入だけでなく組織文化や業務プロセスへの影響も十分に考慮する必要があります。
ここでは、推進時に特に意識すべきポイントを解説します。
金融機関における既存システム(レガシーシステム)は、長年にわたり構築され、膨大なデータや複雑な取引を支えてきました。このため、DXを推進する際には一度にすべてを刷新するのではなく、段階的な移行を意識することが重要です。
理由は、既存システムには依存する業務プロセスや取引先システムが多く存在し、急な変更が業務停止リスクを高めるからです。
例えばクラウドサービスの導入にあたっては、まず一部業務からクラウド移行を開始し、安定運用を確認しながら徐々に対象範囲を拡大していく方法が取られています。このアプローチにより、業務への影響を最小限に抑えながら新しい技術を取り入れることが可能です。
したがって、金融DXでは「全体最適」を見据えた段階的な移行戦略が不可欠となります。
金融業界は特に、個人情報保護法や金融商品取引法など厳格な規制下にあります。このため、DX推進にあたっては法令遵守と高度なセキュリティ対策が前提となります。
なぜなら、デジタル化が進むほどサイバー攻撃のリスクが高まり、万一の情報漏洩は企業の信用失墜に直結するためです。
実際、クラウドサービス利用時には「ゼロトラストセキュリティモデル」を導入し、すべてのアクセスを前提とせずに常に認証・監視を行うことができる体制を整える事例が増えています。このような対策により、脅威に柔軟かつ迅速に対応できる環境を構築できるでしょう。
DX推進には経営層のリーダーシップが不可欠ですが、実際に変革を支えるのは現場の社員です。そのため、現場の理解と主体的な参加を促す施策が必要です。
例えばある地方銀行では、全社員向けにデジタルリテラシー研修を実施し、AIツールの活用方法を体験型で学ぶプログラムを導入しました。その結果、現場から自発的な改善提案が増え、DX施策が加速したという成功例もあります。
このように、金融DXを本質的に進めるためには、現場の声を尊重しながら双方向のコミュニケーションを重視することが求められます。
参考:京都信用銀行
金融DXは一朝一夕で完結するものではなく、中長期的な視点で取り組むべきテーマです。短期的な成果だけに固執すると、真に必要な変革を犠牲にしかねません。
例えば海外の大手銀行では、DXプロジェクトを5年スパンで設計し、初年度はデータ基盤の整備に集中するなど段階的に成果を積み上げる戦略を採用しています。このような長期的なロードマップに基づく取り組みが持続可能なDX成功へと繋がります。
したがって、金融DXは「短期成果」と「長期成長」の両立を意識した柔軟な推進体制がカギとなるでしょう。
金融業界では、さまざまな企業が先進的なDX施策に取り組んでいます。
ここからは、代表的な事例を紹介し、それぞれの取り組みから学べるポイントを考察します。
住信SBIネット銀行は、「BaaS(Banking as a Service)」を提供し、他業種企業が自社サービス内で金融機能を実装できる仕組みを支援しています。
背景には、金融サービスが多様化するなかで銀行が直接顧客にサービスを届けるだけでなく、他社と連携して間接的にサービスを提供するニーズが高まっていることがあります。
具体的には、SBIのBaaSプラットフォームを通じて、決済機能や融資機能をAPI経由で提供し、企業のサービス内で金融機能を自然に組み込める仕組みを構築しました。この柔軟性を取り入れたことによって金融サービスの利便性向上と新たな収益機会の創出を実現しています。
住信SBIネット銀行の取り組みは、従来型の銀行業務から一歩進んだ「サービスのプラットフォーム化」が金融DXの重要な方向性であることを示しています。
参考:住信SBIネット銀行
りそなホールディングスは、顧客データ分析を通じて個々のニーズに最適化された金融サービスを提供する取り組みを強化しています。
金融機関が保有する膨大なデータを、従来の「保管」から「活用」へと転換することが狙いです。
実際には、AIを活用したデータマイニングによって顧客ごとのライフステージや資産状況に応じたローン・保険・資産運用商品の提案を行っています。AI活用によって顧客満足度を高めるとともに、クロスセル機会の創出にも成功しました。
この事例は、金融DXにおける「データドリブン経営」の重要性を強く示しています。
参考:りそなホールディングス
大和証券グループは、リアルタイムで米国株式の取引が可能なシステムを構築して投資家ニーズへの迅速な対応を実現しました。
背景には、個人投資家のグローバル投資志向の高まりと即時性のある取引環境への期待があります。
大和証券グループでは、システム基盤を刷新して取引データの即時処理やリスク管理体制の強化を進めたことで、夜間や祝日でも米国株式取引をスムーズに行える環境を整えました。この結果、顧客満足度と取引量の向上を同時に達成しています。
この事例からは、ユーザー体験(UX)向上が金融DXの成否を分ける重要な要素であることが読み取れます。
参考:大和証券グループ本社

金融DXを成功させるには、IT部門だけに任せるのではなく、「人」を中心に考えた総合的な取り組みが大切です。人材育成や組織づくり、業務プロセスの見直しをバランスよく進めることで、持続可能なデジタル化が目指せます。
まずは、本記事で紹介したポイントを参考にしながら、社内に「人事主導」のDX推進体制を整えるところから始めてみてはいかがでしょうか。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
