金融DXの推進によって叶う勘定系システムの刷新|4つの取り組み例を紹介
金融

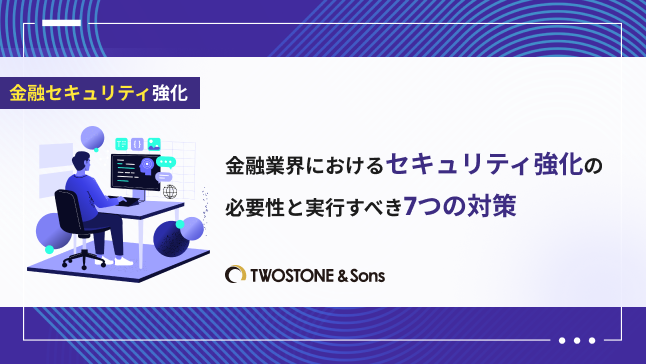
近年、金融業界を取り巻く環境は急速にデジタル化が進み、それに伴いサイバーセキュリティへの関心も高まっています。
しかし、実際には「うちは大丈夫だろう」とリスクを過小評価し、十分な対策を講じられていない金融機関も少なくありません。金融情報は金銭的価値が非常に高く犯罪者にとって魅力的な標的となっているため、対策を怠れば甚大な被害を招く危険性があります。
この記事では、金融業界が直面する4つの主なセキュリティ課題とそれにどのように向き合うべきかを解説します。
記事を読むことで、今後求められる具体的なセキュリティ対策が明確になり、自社のリスクマネジメント力を高めるための実践的なヒントを得ることができるでしょう。

金融業界では、かつてないスピードでデジタル化が進展する一方でセキュリティリスクも複雑化・高度化しています。その結果、単純な防御策だけでは十分な対応ができない時代に突入しました。
まずは金融機関が現在直面している代表的な4つの課題を整理していきましょう。
サイバー攻撃の脅威は年々増加し、特にフィッシング詐欺やランサムウェアといった手法が巧妙化しています。金融業界にとって、個人情報や取引データは高い市場価値を持つため常に狙われるリスクに晒されています。一度侵入を許してしまえば多大な金銭的損害だけでなく、社会的信用の失墜にもつながりかねません。
こうした現状を踏まえると、もはや「侵入を防ぐ」だけではなく「侵入後の早期発見と迅速対応」までを見据えた体制整備が求められています。
高度なサイバー攻撃に対抗するためには、最新のセキュリティ技術とそれを扱う専門人材の存在が不可欠です。しかし、多くの金融機関ではセキュリティ対策が後手に回りがちであり、必要な人材の確保も追いついていないのが現状です。特に中小規模の機関ではセキュリティ対策に割ける予算が限られているため、脆弱な環境が温存されてしまう傾向にあります。
このような人材不足と予算制約という課題を解決するためには内製化にこだわるのではなく、外部パートナーとの連携を積極的に活用するという発想が重要となります。
金融業界におけるサイバーセキュリティ関連の規制は年々厳格化しています。例えば、金融庁の「金融機関等におけるサイバーセキュリティ管理態勢に関するガイドライン」では、リスク管理体制の整備と定期的な見直しが求められています。
しかし現場レベルでは、これら規制を形式的に捉え実効性ある対策に落とし込めていないケースも散見されるのが現状です。
コンプライアンス意識が希薄なままでは、インシデント発生時に行政処分や顧客離れという深刻な影響を受けるリスクが高まります。規制に適応するだけでなく、それを超えるレベルで内部統制を強化しリスクを最小限に抑える努力が求められるのです。
参照:金融分野におけるサイバーセキュリティに関するガイドライン
顧客データは金融機関の最重要資産であり、その適切な管理は企業の存続に直結します。しかし、ひとたび個人情報が流出すれば顧客からの信頼は急速に失われ、その回復には長い時間と多大なコストが必要となります。加えて、近年はSNSなどを通じた情報拡散が加速しており、悪評が一瞬で広がるリスクも無視できません。
このためデータの暗号化、アクセス権限管理、内部監査体制の強化といった技術的・組織的対策を徹底することが不可欠です。さらに、社員一人ひとりのセキュリティリテラシー向上にも力を入れることで組織全体の信頼性を高めていく必要があるのです。
現在金融業界全体でエンジニア不足が深刻化しており、特にサイバーセキュリティ分野では、高度な専門知識と実践的なスキルを持つ人材の獲得がさらに困難になっています。このような状況下でも金融機関がセキュリティ体制を強化し続けるためには、従来のやり方にとらわれない新たなアプローチが求められます。
ここからは、エンジニア不足の時代に対応するために有効な7つの具体的戦略について見ていきましょう。
まず、根本的な解決策として、適切な人材採用戦略の構築が重要です。従来型の中途採用だけに頼るのではなく、ポテンシャル採用やインターンシップを活用した若手育成型の採用にシフトする必要があります。特に、セキュリティエンジニアに必要なスキルセットを明確に定義し実務能力を重視した評価基準を設けることで、即戦力となる人材を確保しやすくなります。
また、リモートワークや柔軟な働き方を許容することも優秀なエンジニアを引きつける重要な要素です。地方在住者や副業希望者など、多様な人材プールにアクセスできると、採用競争を有利に進められるでしょう。
採用だけで全てを解決するのは現実的ではありません。そこで不可欠となるのが、既存社員に対するスキルアップ支援とリスキリングです。特に、IT部門以外の社員に対しても基礎的なサイバーセキュリティ知識を浸透させることが重要です。
社内トレーニングプログラムを定期的に実施し、最新の攻撃手法や防御技術について学び続けられる環境の整備が求められます。また、資格取得支援制度やeラーニングの導入など、多様な学習機会を用意することで社員のモチベーション向上にもつながります。
しかし、全てを自社で賄うのは難しい場面もあるため、次に外部リソースの活用がカギとなるのです。
外部の専門企業と連携し、サイバーセキュリティ体制を補完する取り組みも非常に有効です。特に、SOC(Security Operation Center)サービスやMSSP(Managed Security Service Provider)の活用により、24時間体制での監視や迅速なインシデント対応が可能となります。
外部パートナーを選定する際は、コストだけでなく、技術力、インシデント対応の実績、レポーティング精度といった要素を総合的に評価することが肝心です。アウトソーシングする場合でも、自社側で一定の監視・統制機能を維持し外部任せにしすぎないバランス感覚を大切にしましょう。
人手不足を補うためには、セキュリティ運用の自動化が不可欠です。SIEM(Security Information and Event Management)やSOAR(Security Orchestration, Automation and Response)といった自動化ツールを活用すればで、膨大なログ分析やアラート対応業務を効率化し、人的リソースの負担を大幅に軽減できます。
特に脅威検知や初動対応といったプロセスの自動化で、限られたエンジニアがより高度な分析や意思決定に集中できる体制を構築することが可能になります。自動化は、単なる効率化策ではなく、セキュリティレベル全体の底上げにもつながる重要な施策です。
オンプレミス環境に依存する従来型の運用では、セキュリティ対策が煩雑化しやすく人的リソースを圧迫しがちです。これに対し、クラウドサービスを積極的に活用すれば、セキュリティ強化と運用効率化を同時に実現できます。
クラウドベンダーは、高度なセキュリティ機能(WAF、DDoS防御、データ暗号化など)を標準装備しており、専門的な運用負担を軽減できます。特に、ゼロトラストモデルに基づくクラウドセキュリティ設計を導入することでより柔軟で堅牢な防御体制を築くことができるでしょう。
こうした技術的対策を支える基盤として重要なのが、次に紹介する組織文化の醸成です。
いかに技術や体制を整えても、現場の意識が低ければサイバーリスクは排除できません。そのため、組織全体にセキュリティ文化を根付かせる取り組みが必要です。
トップマネジメントが率先してセキュリティ重視の姿勢を示し、定期的な啓発活動や情報共有を行うことが求められます。また、社員一人ひとりが「自分ごと」としてリスク意識を持てるよう、インシデント発生時の影響を具体的に示したワークショップや訓練を取り入れると効果的です。
高度なサイバー攻撃に対応するためには、一般的な社内研修だけでは不十分です。そこで、外部の専門機関によるセキュリティトレーニングの積極的な活用をおすすめします。
例えば、実際の攻撃シナリオを模擬したペネトレーションテスト形式の演習や、インシデント対応訓練(Tabletop Exercise)など、実践的なプログラムに参加することで社員の対応力を飛躍的に向上させることができます。外部委託により、最新の脅威動向に即した訓練を受けられる点も大きなメリットです。
こうした多層的な取り組みを積み重ねることで、エンジニア不足時代においても堅牢なセキュリティ体制の維持が可能となるでしょう。

近年、金融DX(金融業界におけるデジタル・トランスフォーメーション)が加速しています。これに伴い従来のセキュリティ対策だけでは不十分な場面が増え、より高度で柔軟な防御体制が求められるようになりました。金融DXの進展は、単なる業務効率化にとどまらずセキュリティレベルの大幅な向上をもたらす可能性を秘めています。
ここでは、金融DXによって実現できる具体的なセキュリティ強化策について見ていきましょう。
金融機関にとってクラウド技術の導入は単なるコスト削減手段ではなく、セキュリティ強化の重要な柱となっています。クラウドサービスプロバイダーは、ファイアウォール、侵入検知システム(IDS)、データ暗号化といった高度なセキュリティ機能を標準装備しており、オンプレミス環境よりも迅速かつ柔軟に対策を講じることが可能です。
例えば、クラウドサービスの中には「ゼロトラストセキュリティ」モデルを標準搭載しているものもあります。ゼロトラストとは、全てのアクセスリクエストを信頼せず検証を経てアクセスを許可するセキュリティモデルです。これにより内部犯行リスクやアカウント乗っ取りリスクを大幅に軽減できます。
さらに、クラウド基盤の定期的なセキュリティパッチ適用や脆弱性管理も金融機関自らが行うより効率的に実施できる点も大きなメリットです。今後もクラウド技術の活用は、金融機関のセキュリティレベル向上に不可欠な選択肢となるでしょう。
デジタル化が進む中で、個人情報や金融取引データの保護はますます重要なテーマになっています。金融DXにより、データ保護の手法も高度化しプライバシー管理が飛躍的に容易になりました。
近年は特に、データ分類とアクセス制御を自動化する「データガバナンスプラットフォーム」の導入が進んでいます。この仕組みにより、重要データと一般データを自動的に識別して適切なセキュリティレベルで管理できるようになり、「同態暗号」と呼ばれる新しい方式では暗号化されたままデータ処理を行えるため、従来以上に安全なデータ活用が可能です。
これらの技術を駆使することで、金融機関は国内外の厳格なプライバシー法規制(例:GDPR、改正個人情報保護法)にも柔軟に対応できる体制を整えることができます。プライバシー対策の強化は、顧客との信頼関係を深めるうえでも不可欠です。
金融DXの推進により、脅威検出・対応のスピードも劇的に向上しています。AI(人工知能)と機械学習を活用した「リアルタイム脅威インテリジェンス」は、これまで人手では追いきれなかったサイバー攻撃を即座に察知し、迅速な対処を可能にします。
例えば、金融機関向けに設計された「SOAR(Security Orchestration, Automation and Response)」プラットフォームでは、異常なアクセスパターンや取引ログをリアルタイムで分析し、自動でインシデント対応フローを開始することができます。これにより、攻撃拡大を最小限に食い止めるだけでなくセキュリティ担当者の負担軽減にもつながるのです。
また、リアルタイム対応の実現には、ネットワークトラフィック監視(NDR)やエンドポイント検知対応(EDR)といった先進的なソリューションも非常に便利です。これらを組み合わせることで、金融機関は未知の脅威に対しても機動的に防御体制を構築できるようになるでしょう。
金融DXによるセキュリティ強化は、単なるリスク管理を超えて企業の競争力を左右する要素にもなっています。セキュリティ対策が強固な金融機関は、顧客からの信頼を獲得しやすく長期的な関係構築にも成功しやすいからです。
例えば、取引先企業や個人顧客が金融機関を選定する際、「サイバーリスクへの対応力」や「プライバシー保護体制」を重視するケースが増えています。この流れに対応できる金融機関は、競合他社よりも一歩リードできる可能性が高まります。
さらに、金融庁や各種監督機関が求めるサイバーセキュリティガイドラインへの適合状況も、今後ますます金融機関の評価指標として重視される見込みです。こうした観点からも、金融DXを通じたセキュリティ強化は自社のブランド価値向上と市場での優位性確保に直結すると言えるでしょう。

金融DXが加速する現代において、サイバー攻撃の脅威は日々巧妙化しています。従来型の防御策だけに頼るのではなく、クラウド活用やリアルタイム脅威検知、組織全体でのセキュリティ意識改革など多面的な対策を講じることが不可欠です。
また、エンジニア不足という現実にも正面から向き合い、採用戦略の見直しや社内人材のリスキリング、外部パートナーとの連携強化など即効性のあるアクションを起こすことが求められています。金融機関としての信頼性を高めることは、単なるリスク回避だけでなくビジネス競争力を左右する重大な要素になりつつあります。今こそ、金融機関にとって本当に必要なセキュリティ対策を見極め、迅速に実行へと移すべきタイミングです。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
