金融DXの推進によって叶う勘定系システムの刷新|4つの取り組み例を紹介
金融

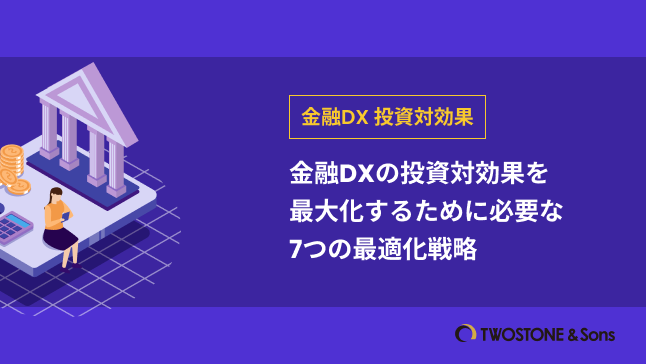
「金融DXに取り組んでいるが、なかなか成果が見えない」「コストばかりかさんでしまい、投資効果が感じられない」といった悩みを抱えていませんか。
金融業界におけるデジタルトランスフォーメーション(DX)は近年推進が求められていますが、単なるシステム導入やツールの活用だけでは本当の効果は得られません。重要なのは、正しい「投資対効果(ROI)」の視点を持ち、戦略的に最適化を図ることです。
この記事では、金融DXにおけるROIの基本から効果的に投資対効果を最大化するための7つの戦略について詳しく解説していきます。読み進めることで、DX投資を成功に導くために必要な考え方とすぐに実践できるポイントを参考にしてください。
金融DXを推進するにあたり、最も意識すべき指標の1つが投資対効果(ROI)です。
ここでは、DXやROIの基本概念について整理していきます。
 DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、デジタル技術を活用してビジネスモデルや組織文化、業務プロセスを抜本的に変革し、競争優位性を確立する取り組みを指します。
DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、デジタル技術を活用してビジネスモデルや組織文化、業務プロセスを抜本的に変革し、競争優位性を確立する取り組みを指します。
金融業界においては、オンラインバンキング・AIによる審査業務の自動化・データドリブンなサービス開発など顧客体験と業務効率の両面での変革が求められています。
単なるIT化と混同されがちですが、DXは単なるシステム導入では終わりません。組織全体の在り方を再定義することが本質であり、ここに投資の正当性を見出すためにもROIの観点が欠かせません。
ROI(Return on Investment)とは、投資に対して得られた成果の割合を示す指標です。金融DXにおいては、システム導入費用や人件費といった投資額に対してどれだけ業務効率化・売上拡大・顧客満足度向上などの成果が得られたかを定量的に測る必要があります。
ROIの高さは、プロジェクトの成功度合いを示す重要な尺度です。したがって、DXの各施策について事前に投資とリターンを見積もり、実施後に効果検証を行う体制を整えることが求められます。
ROI(投資対効果)は、投資がどの程度利益を生んだかを測る指標で、一般的に次の計算式で求められます。
ROI(%)=(投資による利益÷投資額)×100
「利益」には、金銭的なコスト削減や売上増加といった直接的な財務的効果に加え、顧客満足度の向上によるリテンション率向上、解約率の低下など、間接的な効果も含まれます。これにより、単に金銭的な利益だけでなく、ブランドの強化や顧客関係の向上といった定性的な効果も含めて評価することが重要です。したがって、投資のROIを算定する際は、定量的なデータと定性的な成果の両方を総合的に捉えることが求められます。
金融DXでは、業務プロセスの効率化による人件費削減やシステム自動化による運用コスト削減がメリットです。
コスト削減効果を測定する際は、以下の2点を明確にしておきましょう。
例えば、年間1,000時間かかっていた手作業を自動化により500時間削減できた場合、その時間単価に応じた金額を算出します。
この具体的な数値がROI計算の精度を高める指標となります。
ROI(投資対効果)を算定する際には、いくつかの重要なポイントに注意が必要です。まず、短期的な成果だけを評価するのではなく、中長期的な影響も考慮することが求められます。特に、顧客ロイヤルティの向上や社員満足度の増加といった定性的な効果は、数値化が難しいものの、長期的な企業成長に影響を与える可能性があります。これらの影響を無視せず、包括的に振り返ることが重要です。
さらに、ROIを最大化するためには、導入後に定期的な効果測定を行い、仮説と実際の結果との差異の分析が欠かせません。フィードバックをもとに改善策を講じ、継続的な見直しを行うことで、投資の効果をさらに高めることができます。
金融DXにおける投資対効果(ROI)の高さは、単なるコスト削減だけでなく顧客満足度の向上や業務品質の向上にも繋がります。
ここでは、実際に高いROIを実現した国内大手金融機関の成功事例を紹介し、具体的な取り組み内容とその成果を分析していきます。
三菱UFJ銀行は、業務効率化を目的に生成AIであるChatGPTの活用を進めた結果、月間22万時間に相当する労働時間の削減に成功しました。この取り組みは、単なる人件費の圧縮にとどまらず、社員がより付加価値の高い業務に専念できる環境整備にも良い影響を与えたのです。
まず背景として、金融機関では大量の書類作成・問い合わせ対応・資料作成などルーティンワークが多く存在していました。この非効率性が業務改革のボトルネックとなっていたのです。
そこで、ChatGPTをベースとした社内向けツールを導入し、定型的な業務を自動化するプロジェクトを開始しました。導入初期から部門横断的に展開し、現場のフィードバックを取り入れながらブラッシュアップを繰り返した結果、わずか半年で効果を可視化できるまでに至りました。
この事例からわかるポイントは、単なるシステム導入ではなく、現場ニーズを踏まえた運用設計とスピーディな改善サイクルの重要性です。効率化の成果を最大化するためには、テクノロジーと組織文化の変革をセットで推進する必要があるといえるでしょう。
参考:日本経済新聞
SMBCフィナンシャルグループは、2023年にモバイル総合金融サービス「Olive」を開始し、利用者層の拡大と顧客接点の強化に成功しました。30代では196%、40代では199%、50代では195%と提供開始前に比べて利用増加を実現しています。
背景には、金融サービスのモバイル化、ワンストップ化への顧客ニーズの高まりがありました。従来のバンキングアプリでは、口座管理・クレジットカード管理・資産運用などが別々に存在し、ユーザーにとって煩雑さが課題となっていたのです。
「Olive」はこれらを一元化し、スマートフォン一つで完結できるUX(ユーザー体験)を設計しました。また、アプリ上でパーソナライズされた金融アドバイスを提供するなどデータ活用型サービスにも注力しています。
この事例から得られる示唆は単なる利便性向上だけでなく、顧客とのエンゲージメントを深めるためにサービス全体をデザインし直す重要性です。結果として、顧客基盤の拡大と長期的なロイヤルティ向上に繋がる好循環を生み出しています。
金融DXにより投資対効果(ROI)が向上すると、組織全体にさまざまなメリットがもたらされます。
ここでは、代表的な5つのメリットについてそれぞれ具体的な効果と実現方法を解説していきます。
金融業界におけるDXは、業務プロセスを効率化して無駄なリソースや工数の削減により、直接的なコスト削減効果を生み出します。AIを活用した与信審査の自動化やRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)による事務作業の効率化など、技術の進化により作業の迅速化が進んでいます。これにより、従来の手作業や人的ミスを減らし、業務の質と生産性を向上させることができるのです。
ただし、業務効率化を単なる部分的な最適化に留めず、全体的な業務フローを見直すことが重要です。BPR(ビジネスプロセス・リエンジニアリング)によって業務全体の再設計を行うことで、根本的な業務改革が可能となり、さらに長期的に高いコスト削減効果が期待できます。段階的に進めることが成功のカギであり、全社的な協力と徹底的な分析が求められるのです。
金融DXの進展により、企業はビッグデータやAI分析を駆使してより精緻な意思決定が可能となります。これまでの経営判断は経験則や直感にもとづく部分が多かったのですが、現在では顧客データや取引履歴、信用情報などをリアルタイムで統合・分析することで、より正確でリスクを最小限に抑えた戦略的判断が可能になります。リアルタイムの分析によって、金融機関は市場変動に迅速に対応し、競争力を保つことができるのです。
データドリブン文化を組織に浸透させるためには、まずデータガバナンス体制の構築が不可欠です。適切なデータ管理や分析のプロセスを整備し、社員全体のデータリテラシーを向上させることが組織全体の意思決定精度を向上させるカギとなります。データにもとづいた経営判断は、将来的な成長に繋がる重要な要素です。
金融DXが進む中で、顧客体験(CX:カスタマーエクスペリエンス)の向上は企業にとって重要な競争要素となります。例えば、チャットボットやAIを活用した24時間対応サービス、パーソナライズドオファーの提供は顧客満足度を大きく向上させているという事例があります。金融DXを推進することで顧客はより便利で快適なサービスを受けることができ、その結果、企業の信頼度や満足度が高まるのです。
また、顧客体験の改善は短期的な売上向上にとどまらず、長期的な顧客ロイヤルティの強化に繋がります。結果として、リテンション率(顧客維持率)の向上やLTV(ライフタイムバリュー)の最大化が実現し、企業全体の成長が促進されます。顧客のニーズに合わせたサービス提供は今後さらに重要となり、企業の競争優位性を確立するために欠かせない要素となるでしょう。
金融市場は日々変化しており、その中でDXに成功した企業は確固たる競争優位を手に入れることができます。フィンテック企業との協力や新しいビジネスモデルの開発を通じて、競争力を高めることが可能になっているのです。
例えば、APIエコノミーを活用して自社のサービスを拡張したり、他業種との連携を深めたりすることで新たな価値を提供できます。競争力を高めるためには、スピード感を持ったイノベーションを推進し、レガシーシステムの改善・移行が重要になってきます。
守りに徹するだけでなく攻めの姿勢を持ち続けることで、迅速に市場シェアを拡大できるでしょう。このように、金融業界における競争力強化は単なる生き残りの手段ではなく、成長を加速させるための重要な要素です。
金融業界のDX推進は、従業員の生産性を飛躍的に向上させる要素ともなり得ます。例えば、手作業によるデータ入力や反復的な業務の自動化により、従業員はもっと創造的で戦略的な業務に集中できるようになります。これにより業務効率が向上するだけでなく、従業員満足度(ES)も高まり優秀な人材の定着に繋がるのです。
加えて、DXは働き方改革にも良い影響をもたらします。業務負担を軽減した上での柔軟な働き方の実現で社員のストレスや過労を減らし、健康的で生産的な職場環境を提供することができます。このように、DX導入は組織全体のエンゲージメント向上にも直結し、企業文化の向上にも繋がるのです。

金融業界におけるデジタルトランスフォーメーション(DX)の投資対効果を最大化するためには、計画的かつ段階的なアプローチが求められます。
ここで紹介する7つの戦略を実行し、効率的に投資対効果を高めていきましょう。
DXの投資対効果を最大化するためには、まず何を達成したいのかという目的を明確に定めることが不可欠です。例えば、業務効率化や顧客体験の向上、リスク管理の強化など目的によって必要な施策が異なります。明確な目標設定は、投資額の最適化や進捗状況の測定基準を定めるためにも重要です。
さらに、目的の明確化は、DXが企業全体にどのように利益をもたらすかを理解する上での指針にもなります。目標を明確にした上で社員に共有することで関係者全員が一丸となって共通の目標に向かって進むことができ、プロジェクトの成功率が高まります。
大規模なDXプロジェクトをいきなり実施するのではなく、小規模なPoC(概念実証)を通じて実際の効果を確認しながら投資判断を行うことが効果的です。PoCは、新しいテクノロジーや手法を実際に試すことでその有効性やリスクを見極めるための重要なステップです。
段階的に実施することで無駄な投資を防ぎ、期待されるROI(投資収益率)の見込みが立った段階で本格的な導入に進めます。このプロセスを繰り返すことで、投資のリスクを最小限に抑えることができるでしょう。
投資対効果を最大化するためには、DX施策の成果を定量的に振り返ることが重要です。そのためには、施策開始前から必要なデータを収集する体制を整えることが不可欠です。例えば業務効率化を目指す場合、事前に作業時間やコストをデータとして記録しておき、施策後の変化を比較する体制を整える必要があります。
データ収集体制が整えば、施策がどの程度成功したのか、どの領域に改善の余地があるのかを具体的に把握することができます。このようにして得られたインサイトをもとに、次のステップに進むための意思決定を行いましょう。
DXの導入において、すべての業務を一度に改革しようとするのは無理があるでしょう。そのため、投資対効果を短期間で回収できる領域から順に始めることが重要です。例えば、顧客対応の自動化や社内の業務プロセスの簡素化などは、比較的短期間で効果が現れる分野です。
短期的に効果を見込める分野に投資を集中することでプロジェクトへの信頼感が高まり、さらなる投資を引き出しやすくなります。これにより、DX施策を段階的に広げていくことができるのです。
DX施策を実施する際には、内製化と外部パートナーの利用をどのようなバランスにするかが重要なポイントです。内製化で自社の特性に合ったシステムを構築しやすくなりますが、そのためには専門的な知識や人材が必要です。一方で、外部パートナーを活用すれば最新の技術やノウハウを迅速に取り入れることができますが、コストがかかる場合もあるため注意が必要です。
このバランスをうまく取ることで、効率的なDX推進が可能になります。例えば、基幹システムの開発は内製化し、AIやクラウドサービスの導入は外部パートナーを活用するなど、適材適所で活用することが求められるのです。
DXを成功させるためには、テクノロジーの進化に対応できる人材の育成が不可欠です。そのためには、社員のスキルアップやリスキリングに継続的に投資する必要があります。新しい技術を導入しても、それを使いこなす人材が不足していてはDXの効果を十分に発揮できません。
具体的には、データ分析やAI、クラウドサービスに関する研修を定期的に実施し、社員の能力を高めることが求められます。また、外部の専門家とのコラボレーションや企業内のDX推進担当者を育成することも効果的でしょう。
DX施策は一度導入したら終わりではなく、定期的な評価と見直しを行いながら進化させていくことが大切です。市場環境や技術の進化に合わせて戦略を見直し、新たな課題に対応できるように改善していく必要があります。
定期的な評価を通じて、目標が達成されているか投資が無駄になっていないかを検証し、その結果をもとに次のステップを決定しましょう。定期的に振り返りを行うことで、投資対効果を最大化して企業の競争力を高めることができるのです。
金融業界におけるデジタルトランスフォーメーション(DX)を成功させるためには、組織の一体感と戦略的なアプローチが欠かせません。
金融DXを成功させるための3つのポイントを紹介するので、投資対効果の最大化に向けて参考にしてください。
DXを推進するためには、企業全体が一丸となって取り組む必要があります。単独の部署やチームだけで進めるのではなく、経営層をはじめ各部門が協力して目標を共有し、連携を強化することが大切です。DXの成果を上げるためにはシステムの導入や業務フローの改革が必須ですが、それに伴う組織文化の変革も欠かせません。
例えば、金融業務のデジタル化は単にIT部門だけの仕事ではなく、営業やカスタマーサポート部門の協力も求められます。こうした部門間の協力体制を整えることで、組織全体でDXの効果を最大化できるのです。
DXを成功させるためには、企業の目的や環境に応じた独自の戦略を策定することが必要です。金融業界のDXは、単なるIT化や業務のデジタル化にとどまらず、顧客サービスやリスク管理、さらには業務効率化に至るまで多岐にわたります。そのため、業界の動向や競争環境を踏まえた明確で実行可能な戦略を立てることが求められます。
具体的には、顧客のニーズを理解し、どの領域で競争優位を確立するかを考えることが重要です。また、DX戦略は柔軟でなければならず、テクノロジーの進化や市場の変化に応じて適宜見直しを行うことも必要です。
DX推進の成功には、適切なスキルを持つ人材が必要です。しかし、技術的な知識を持つ人材だけでは不十分で、企業の文化や方針にマッチした人材が求められます。企業の方針を明確にした上でDX人材を選ぶことで、DX施策がスムーズに進行し、企業全体に浸透させられます。
そのためには、社内でのリスキリングや外部からの専門人材の採用など、柔軟な人材戦略を取ることが重要です。DXに必要なスキルセットは、データ分析・AI・クラウドコンピューティングなど多岐にわたりますが、企業の長期的なビジョンに沿った人材を確保することがDXの成功を支えるカギとなります。
金融業界におけるDX投資対効果の最適化には、高度な専門知識と豊富な経験が必要です。
『株式会社 TWOSTONE&Sons』では、金融機関に対して、効率的かつ効果的なDX戦略の導入を支援してきました。業界特有のニーズや課題に精通しており、貴社のビジネス環境に最適なデジタルトランスフォーメーションをご提案することが可能です。
また、データ活用、業務効率化、そして投資対効果の最大化を実現するための具体的な方法を提供し、持続的な成長を支援します。貴社のDX戦略を成功へと導くために、ぜひ一度ご相談ください。

金融業界でのDX投資は、競争力の向上と成長を実現するためのカギです。成功には戦略的な投資判断と継続的な改善が求められます。
『株式会社 TWOSTONE&Sons』では、最適なDXソリューションを提供して投資効果の最大化をサポートします。今後の業界の進化をリードするためにDXを活用し、確実に成果を上げるための第一歩を踏み出しましょう。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
