金融DXの推進によって叶う勘定系システムの刷新|4つの取り組み例を紹介
金融

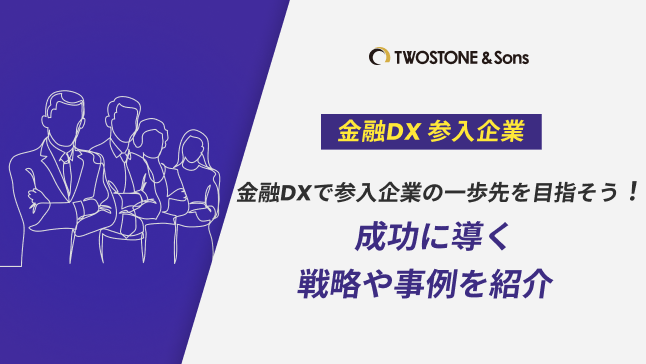
金融業界は長年にわたり、既存のシステムや定型的な手順をもとに、安定した運営を続けてきました。しかし近年では、近年では、テクノロジーの進化や市場の多様化により、さまざまな企業が新たに参入しています。そこで企業の将来に役立つ取り組みがDXです。
本記事では金融業界に参入企業が増えた理由や金融業界におけるDXについて具体的に解説します。企業の将来のためにも、ぜひ本記事を参考にしてください。

金融業界に参入企業が増えた理由として考えられるのは、以下の3つです。
まずは、それぞれの理由について、詳しく解説します。
各金融機関が自社のAPIを外部に公開し始めたことにより、決済や口座管理といった機能を自社サービスとして展開しやすくなりました。たとえば、フィンテック企業が個人資産を可視化できるアプリを開発したり、会計ソフトに口座連携を組み込んだりする例が増えています。これまでのように金融機能の開発に高い技術やコストが必要とされないため、参入を検討する企業が増えています。
国の後押しによって、金融業界はよりオープンで柔軟な環境へと進化しています。特にスタートアップ企業や異業種からの参入を促すため、さまざまな規制緩和や制度整備が進められてきました。
「金融庁のFinTech実証実験ハブ」は、最新の技術を活用した新しい金融サービスの実証実験を後押しするため、法律や規制の適用を一時的に緩和し、イノベーションが生まれやすい環境を整備しています。
こうした取り組みにより参入のハードルが高かった金融業界に対し、新たなビジネスチャンスを見出す企業が増えてきたことも理由として考えられるでしょう。
参考:金融庁|「FinTech実証実験ハブ」支援決定案件について
スマートフォンひとつで買い物が完了する時代になり、決済のスタイルが変わりました。こうした変化に対応するため、IT企業や小売業などが独自の決済サービスを導入しています。たとえば、コンビニが自社アプリにQRコード決済機能を追加したり、ECサイトが独自の電子マネーを展開したりするケースも見られます。
このようなキャッシュレスの進展にあわせて、利益を見込んで参入する企業が増えているのです。
金融業界では今、デジタル技術を活用してビジネスモデルを根本から見直す「デジタルトランスフォーメーション(DX)」の必要性が急速に高まっています。その背景には、業界を取り巻く環境の急激な変化と顧客の価値観や期待の多様化、そして既存の業務プロセスの限界といった複合的な要因があるのです。
ここでは、金融DXの必要性を後押しする4つの視点から、その背景を詳しく解説していきます。
金融業界におけるDX化は、テクノロジーの進化によってさらに加速しています。クラウドコンピューティングやAI・ビッグデータ・ブロックチェーンなど最新のテクノロジーが業務に導入され、効率性や精度が向上しています。
例えば、AIによるリスク管理や顧客分析は業務の自動化を進め、より迅速で的確な意思決定を可能にするでしょう。また、データ解析によって顧客の行動を予測し、個別のニーズに合ったサービスの提供ができるようになるのです。これらの技術を駆使することで、金融業界は今後さらに競争力を増していくでしょう。
近年、金融業界における顧客のニーズは多様化しています。個人投資家や企業はより迅速かつパーソナライズされたサービスを求めており、従来の手続きやシステムではこれに対応しきれないケースが出てきているのです。具体的には、スマートフォンを通じたオンラインバンキングやAIによる金融アドバイスなど、利便性や顧客体験が重視されています。
このような事態に金融DXを推進すると、顧客との接点を増やせるため、より柔軟に対応でき、顧客満足度を向上させることができます。
金融機関は、競争激化とともに利益率の圧迫に直面しています。そのため、業務効率を高めてコストを減らすことが重要な課題となっています。
そこで、従来の手動で行われていた処理や重複した業務をDXによって自動化すれば、コスト削減ができるのです。また、クラウドやAIなどのテクノロジーを活用することで業務プロセスを最適化し、経営資源を効率的に活用できるようになります。
金融DXを推進すると、これまで手動で行われていた業務を半自動的に処理できるため、競争に打ち勝つための経営・運営に力を入れることができ、より収益性の高い事業運営が実現できるでしょう。
多くの金融機関では、長年にわたって使われてきたレガシーシステムが存在しています。これらのシステムは現在のテクノロジーに対応しておらず、業務の効率化やデータ活用を妨げる要因となっています。また、システムの老朽化によって運用コストが高くなり、柔軟性が欠如していることも問題です。
このようなシステムを維持し続けることは、長期的な競争力を失うリスクを伴いかねません。そのため、DXによるシステムの刷新や業務プロセスの改善が必要です。既存のシステムを見直して最新の技術を取り入れることで、業務効率の向上だけでなく顧客ニーズに即応できる柔軟な体制を構築することができます。
金融業界におけるDX推進は、単なるデジタル化を超えて、業務効率やサービス品質の向上・リスク管理の強化・経営基盤の強化にまで広がる可能性を秘めています。顧客のニーズや市場環境が急速に変化する中で、DXはもはや「取り組むべきかどうか」という段階ではなく、企業の生存戦略として必須といえるでしょう。
ここでは、金融業界がDX推進によって得られる5つの具体的なメリットについて順を追って解説していきます。
まず、金融業界においてDX推進がもたらす大きなメリットの1つが、業務の効率化とコスト削減です。
金融機関では、長年にわたり紙ベースの申請・対面での審査手続き・手入力によるデータ管理といったプロセスが主流となっていました。しかし、これらのアナログな業務は人件費や時間的コストを過大に消費し、ミスや遅延の温床にもなりやすいという課題を抱えてきました。
そこで金融DXを推進して業務プロセスを自動化・最適化することで、作業時間を短縮し、コスト削減を実現できるでしょう。
例えば、RPA(Robotic Process Automation)を活用すれば、定型業務を自動化し、社員がより付加価値の高い業務に集中できる環境を整えることが可能となります。三井住友銀行では、融資審査にかかる業務をAIとRPAを組み合わせることで処理時間を従来の半分以下に削減した事例もあります。
このように、DXによる業務効率化は単なるコスト削減にとどまらず、組織全体の生産性向上へとつながっていくでしょう。
参考:三井住友銀行
次に、DX推進が顧客体験(CX:Customer Experience)を向上させる点も重要なメリットといえます。
現代の消費者は、サービスのスピード・利便性・パーソナライズ化された対応を当然のように求める傾向があります。金融サービスにおいても、24時間対応のオンライン手続きや個別ニーズに応じた商品提案などが期待されているのです。
しかし金融業界における人員には限りがあります。そこで金融DX化を進めれば、これらの期待に応えることができるでしょう。
具体的には、スマートフォンアプリを通じた口座開設・ローン申し込みの即時審査・AIチャットボットによるカスタマーサポートなどが挙げられます。足利銀行では、顧客の行動データを分析し、最適なタイミングで住宅ローンのキャンペーン案内を行ったところ、契約率が向上したという結果も報告されています。
顧客とのタッチポイントをデジタル化することで、スムーズかつ満足度の高い体験を提供し、顧客ロイヤルティを高められるでしょう。
参考:足利銀行
リスク管理の高度化も、金融DX推進によって得られる大きな効果の1つです。
金融機関にとってリスク管理は、経営の根幹を成す重要な機能です。しかし、従来のリスク評価手法では、大量かつ多様なデータをリアルタイムで把握して予兆を察知することは容易ではありませんでした。大量の人材を割く必要のあるこの業務に対して、AIやビッグデータ解析といったデジタル技術を取り入れることでリスク管理の精度向上が期待できるかもしれません。
例えば、不正取引の検知をAIに任せることで、従来のルールベース検知よりも迅速かつ柔軟に異常を察知できるようになります。実際に三越伊勢丹ホールディングスでは、AIによる不正検知システム導入後、不正利用検出率が飛躍的に向上したと報告されています。
リスク管理の高度化は、損失リスクを抑えるだけでなく、金融機関全体の信頼性向上にも直結するといえるでしょう。
さらに、DXはスピード感と柔軟性の向上にも大きく寄与します。
市場環境や顧客ニーズが目まぐるしく変化する現代において金融機関に求められるのは、迅速な意思決定とサービス提供です。従来型の縦割り組織では情報共有に時間がかかり、変化への対応が遅れがちでした。
しかし、DXを推進することで、組織内の情報フローを円滑化しアジリティ(機敏性)を高めることができるのです。
例えば、クラウド基盤の活用によって各拠点からリアルタイムでデータを参照し、迅速な判断を下す体制を整えることが可能です。また、アジャイル開発手法を取り入れたサービス開発により、顧客フィードバックをスピーディーに反映して機能改修を繰り返す取り組みも進められています。
こうした変革によって、時代の変化に柔軟に対応できる強靭な組織づくりが実現されるでしょう。
データ活用による競争力強化という点も見逃せないメリットです。
金融業界は、顧客情報や取引データといった膨大なデータ資産を有している点で他業界と比べてもポテンシャルが高い領域といえます。しかし、これまで多くの金融機関では、データの収集は行っていても分析や活用にまでは十分に至っていないケースが目立ちました。
この問題を解決するためにDXを推進することで、こうしたデータを有効活用し、新たなビジネスチャンスを創出できるでしょう。
例えば、AIを活用した個人のニーズに合わせたマーケティングによって個々の顧客のライフステージや行動パターンに応じた商品提案が可能になります。また、ビッグデータ分析によって潜在的な需要や市場の変動兆候を把握し、先手を打った戦略策定が可能となります。
このように、データ分析に基づいた経営へのシフトが、金融機関にとっての持続的な競争力確保のカギになるでしょう。

金融業界において、デジタルトランスフォーメーション(DX)は単なるトレンドではなく、事業の成長と持続性を左右する重要な戦略となりつつあります。
ここでは、日本を代表する金融機関がどのようにDXに取り組んでいるか、具体的な事例を紹介します。各社の取り組みから学べるポイントを整理し、自社での応用のヒントを探っていきましょう。
MUFGは、グループ全体でDXを推進するために「Digital Transformation戦略」を策定し、組織的に取り組みを進めています。特に注目されるのは、デジタルチャネルの強化と新サービスの創出に力を入れている点です。
例えば、スマートフォン専用アプリ「MUFG Wallet」では、銀行取引・クレジットカード利用・資産運用の管理を一元化しています。このアプリにより、顧客は場所や時間を問わず自分の資産状況をリアルタイムで把握できるようになりました。また、MUFGはAI(人工知能)やRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)を活用し、事務処理業務の効率化を進めています。これにより、従来よりもスピーディーかつ正確なサービス提供が実現されつつあります。
さらに、MUFGはスタートアップ企業との連携にも積極的です。オープンイノベーションを推進する「MUFG Digitalアクセラレータープログラム」を通じて、最新技術を取り入れた金融サービス開発を加速しています。これらの取り組みにより、MUFGは顧客満足度の向上と業務の効率化を両立させることを目指しているのです。
みずほフィナンシャルグループは、DX推進のために「みずほDX推進部」を設置し、全社的なデジタル改革を進めています。特に、クラウド化とデータ利活用の分野において先進的な取り組みが見られます。
具体的には、基幹システムの一部をクラウド上に移行し、柔軟かつ迅速なシステム運用を実現しました。これにより、システム障害時のリスクを低減しつつ新たなサービス展開をスムーズに行えるようになりました。加えて、ビッグデータ分析を通じて顧客のニーズや市場動向を高精度で把握し、パーソナライズされた商品提案を行っています。
また、みずほフィナンシャルグループはデジタル人材の育成にも注力しています。社内で「デジタルアカデミー」を開設し、AI・データサイエンス・クラウド技術に関する教育プログラムを提供しています。このような取り組みにより、組織全体のデジタルリテラシーが底上げされ、DX推進力が強化されているのです。
SBIホールディングスは、設立当初からデジタル技術を積極的に取り入れてきたことで知られています。近年では、ブロックチェーンやAI技術を活用した新たな金融サービス開発に注力しています。
代表的な取り組みの1つが、SBIグループが主導する「SBI VCトレード」における暗号資産取引プラットフォームの構築です。このプラットフォームでは、最新のセキュリティ技術と高速な取引処理能力を組み合わせ、安心して取引できる環境を整えています。また、AIを活用した個人向け資産運用アドバイスサービス「WealthNavi for SBI証券」も導入し、ロボアドバイザーによる投資サポートを強化しています。
さらに、SBIホールディングスは地方銀行との連携を深め、地方金融機関のDX支援にも取り組んでいるのです。自社のノウハウを活かして、地方銀行のインターネットバンキング化やキャッシュレス決済導入をサポートし、地域経済の活性化にも貢献しています。このような多角的なDX戦略により、SBIホールディングスは独自のポジションを築きつつあるのです。
参考:SBIホールディングス
金融業界においてDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進するためには、テクノロジーだけではなく、それを支える人材戦略が不可欠です。最新のシステムやツールを導入しても、それを活用し運用できる人材がいなければ、DXの真の価値を引き出すことは難しいでしょう。
ここでは、金融業界でDX化を成功させるために押さえておきたい7つの人材戦略について、具体的に紹介します。
まず重要なのは、自社の事業戦略や文化に適したデジタル人材を確保することです。単にスキルが高い人材を採用するだけでは、DXの推進は期待通りに進まないでしょう。
例えば、データサイエンティストやシステムアーキテクトといった高度な技術者を採用する場合でも、自社の金融商品やサービスへの理解度、チームとの協働力なども重視する必要があります。採用段階では、専門スキルに加えて金融業界特有の規制やリスク管理への適応力を持つかどうかを見極めるのもポイントの1つです。
これらを踏まえた上で、人材紹介会社との連携やダイレクトリクルーティングなど、複数の採用チャネルを柔軟に活用する姿勢が求められます。
次に重要となるのは、既存社員に対するDX特化型の教育です。新たな技術を導入するだけでは現場の混乱を招きやすく、長期的な成果には結びつきにくいでしょう。
そこで有効となるのが、実務に直結したスキル教育プログラムの導入です。例えば、RPAツールの活用方法やデータ分析基礎やクラウド環境の基礎知識など、実践に即した内容を段階的に学べるカリキュラムを用意します。さらに、座学だけで終わらず、演習やケーススタディを通じて実際に手を動かす機会を設けると学びが定着しやすくなるでしょう。
加えて、部門ごとに異なる業務内容に合わせた専門コースを設計することも有効です。これにより、社員一人ひとりが自分事としてDXに向き合えるような土壌が形成されていくでしょう。
DXを単なる技術導入プロジェクトに終わらせないためには、組織全体にデジタルカルチャーを根付かせる必要があります。技術だけが進化しても、文化がそれに追いつかなければ、イノベーションは生まれにくいでしょう。
具体的には、社員の挑戦を歓迎する姿勢を組織全体で明確に打ち出し、失敗を許容する風土を育むことが重要です。また、社内コミュニケーションにデジタルツールを積極的に取り入れることも有効でしょう。例えば、社内SNSやチャットツール、ナレッジ共有プラットフォームを活用することで、情報共有と意思決定のスピードが向上し、デジタル思考が自然と浸透していきます。
このような取り組みを継続的に行うことで、社員のデジタルリテラシーが底上げされ、DX推進力が高まることが期待できるでしょう。
変化の激しい時代においては、現有戦力のリスキリング(新たなスキルの習得)がより一層重要になっています。単なる教育プログラムの提供だけでは不十分であり、キャリアパスと連動したリスキリング戦略が求められるでしょう。
例えば、システム運用担当者に対しては、クラウド環境に対応するインフラ技術やセキュリティ知識を身につけさせる施策が考えられます。また、営業担当者にはデータドリブン営業手法やCRMツール活用法の習得を促すと効果的です。
リスキリングを推進するためには、個別のスキルマップを作成して習得すべきスキルを明確に可視化することも大切です。これにより、社員自身が成長ビジョンを持ちやすくなり、自律的な学習意欲を引き出すことにつながるでしょう。
すべてのリソースを自社内だけで賄おうとすると、時間もコストも大きな負担となりかねません。そこで重要になるのが、外部パートナーとの協力と人材シェアリングの活用です。
例えば、ITベンダーやコンサルティングファームと提携し、最新技術の知見やプロジェクト推進ノウハウを柔軟に取り入れる方法が考えられます。短期間だけ専門人材を招き入れる「業務委託」や「プロジェクトベースの人材活用」も有効でしょう。
また、地方銀行間でのデジタル人材シェアリングのように、複数企業が連携して人材資源を有効活用する取り組みも注目されています。これにより、コスト負担を抑えながら必要なタイミングで専門性の高い人材を確保することが可能となるでしょう。
金融業界では、長年にわたる伝統や慣習が根強く残っているケースが少なくありません。しかし、これがDX推進の大きな障壁となる場合もあります。
組織文化を改革するためには、トップ層の強いリーダーシップと現場レベルでの意識変革の両方が求められるでしょう。まずは経営層自らがデジタルシフトの必要性を明確に発信し、具体的な行動指針を示すことが第一歩となります。
次に、現場で働く社員に対しても、変化を受け入れることの重要性を啓発する活動を継続的に行います。例えば、変革に成功した部署やプロジェクトを積極的に社内表彰するなど、成功事例の可視化を通じてポジティブな意識改革を促進できるでしょう。
最後に、DX推進において軽視できないのが柔軟な働き方の推進です。テレワークやフレックスタイム制度の導入は、単なる福利厚生ではなくDX時代にふさわしい働き方改革の一環として位置づけられます。
働き方改革を行うことで地理的制約を超えて優秀な人材を確保しやすくなるとともに、多様な働き方への対応力が高まるでしょう。特に、デジタルネイティブ世代やITエンジニア層にとっては柔軟な勤務体系が大きな魅力となるため、採用競争力の強化にもつながります。
具体的には、テレワーク環境下での生産性向上施策やオンラインでのチームビルディング支援ツールの導入など、ハイブリッドワークを前提とした制度設計が不可欠です。こうした取り組みを通じて、社員一人ひとりが最大限に能力を発揮できる環境を整えていくことが求められるでしょう。
金融業界におけるDX(デジタルトランスフォーメーション)推進は、単なる技術導入にとどまりません。変革を成功に導くためには、適切な人材の確保と育成が重要なカギを握っています。しかし、DX人材の採用にはさまざまな課題が潜んでいるのです。
ここでは、金融DXに向けて人材確保を進める際に押さえておきたい4つの注意点について、具体的に解説します。
DX推進においては、単に技術的なスキルを持っているだけでは不十分です。これからの金融業界には、専門性と柔軟性の両方を持ち合わせた人材が求められるでしょう。
例えば、クラウドコンピューティングやAI(人工知能)、ブロックチェーンといった最新技術に関する知識や経験は大切です。しかしそれ以上に、ビジネスモデルの変化に応じて柔軟に役割を変えたり、新しい業務領域に挑戦したりできる適応力が重要となります。
そのため、採用活動においては、応募者のこれまでの専門分野だけでなく変化に対する適応実績や異なるプロジェクトでの貢献度にも注目することが重要です。過去の職務経験における「変化対応力」や「クロスファンクショナルな業務経験」が確認できるかどうかを意識しながら、選考を進めましょう。
DX人材を採用する際には、即戦力を重視するあまり短期的な成果ばかりに目を向けがちですが、本質的なDX推進には時間がかかり、継続的な人材育成が欠かせません。
特に金融業界では、法規制やリスク管理といった独自の要件を理解した上でのデジタル施策が求められます。外部から即戦力として採用した人材であっても、業界特有の知識や文化に慣れるには一定の時間が必要となるでしょう。
そのため、採用時点で期待しすぎるのではなく、中長期的に育成する前提で採用計画を立てることが重要です。入社後6か月〜1年をかけて業界知識や社内システムに関する研修を段階的に実施し、段階的に責任範囲を広げていくような育成プランを設けると効果的です。
金融DXの推進においては、SIer(システムインテグレーター)やコンサルティング会社など外部リソースの活用が一般的になっています。しかし、外部に頼りきりになるとノウハウが社内に蓄積されず、持続的なDX推進が困難になるリスクが生じます。
そこで重要なのが、内製化とのバランスを取る戦略です。最初は外部パートナーの支援を受けながらプロジェクトを進めつつ、並行して社内メンバーに技術移転を行い、徐々に自走できる体制を構築することが求められます。
例えば、外部ベンダーとの契約には「ナレッジトランスファー(知識移転)」を義務付ける条項を盛り込み、成果物だけでなくプロセスや考え方まで伝授してもらう必要があります。また、社内に専任のプロジェクトマネージャーやエンジニアを配置し、外部との協働を通じてスキルアップを図る体制を整えることも重要でしょう。
優秀なDX人材は、金融業界だけでなく、IT業界やコンサルティング業界、スタートアップなど多様な選択肢を持っています。したがって、採用市場において競争力を高めるためには自社の魅力を積極的に発信する必要があります。
金融機関の採用活動では、どうしても堅いイメージや保守的な印象を持たれがちです。そのため、単なる業務内容や待遇面の説明だけではなく、DX推進に向けたビジョンや社内の挑戦文化、柔軟な働き方支援など働く魅力を具体的に伝えることが求められます。
例えば、実際のDXプロジェクト成功事例を紹介したり、現場で活躍している社員インタビューを掲載したりというように、応募者に具体的なイメージを持ってもらう工夫が効果的です。また、リモートワーク制度や副業制度の導入など現代的な働き方を積極的にアピールすることも、優秀な人材の関心を引きやすくなるでしょう。
金融業界でDX推進に悩んでいるなら、『株式会社 TWOSTONE&Sons』にご相談ください。
豊富な実績を持つ当社は、ITコンサルティングからシステム開発、運用支援までワンストップで対応しています。業界特有の規制やセキュリティ要件を踏まえた、最適なデジタル戦略をご提案可能です。また、プロジェクト推進だけでなく、社内にノウハウを根付かせるための内製化支援にも力を入れています。
DXを単なる施策に終わらせず、企業価値向上へとつなげるためのパートナーとして、ぜひお役立てください。

金融業界におけるDX推進は、単なるシステム導入ではなく、組織そのものの変革を伴う大きな挑戦です。その成否を左右するのは、人材戦略にあるでしょう。
専門性と柔軟性を備えた人材の確保・中長期的な育成・内製化への取り組みそして企業魅力の発信まで、今すぐ着手すべき課題は多岐にわたります。未来を切り拓くためには、待つのではなく動くことが重要です。今こそ、自社に合った方法で金融DXを進めて、自社の成長を加速させましょう。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
