金融DXの推進によって叶う勘定系システムの刷新|4つの取り組み例を紹介
金融

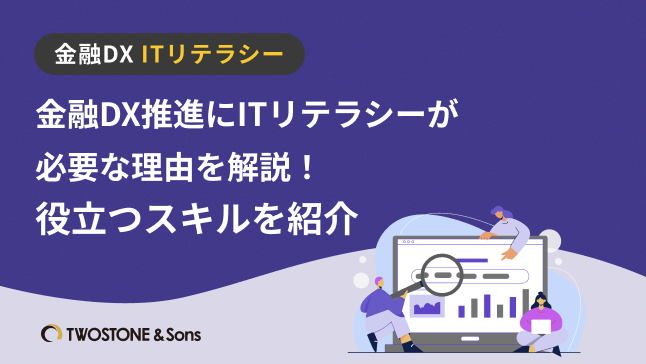
近年、金融業界でもデジタル技術の活用が急速に進み、業務の効率化や顧客満足度の向上が期待されるようになってきました。一方で、デジタルトランスフォーメーション(DX)を推進しようとすると、多くの企業が思わぬ壁に直面します。その1つが「ITリテラシーの課題」です。
しかし、「現場と経営層でデジタル化に対する理解度が異なる」「ITに不慣れなスタッフが多く、DX化が進まない」悩みを抱える企業は少なくありません。しかし、ITリテラシーを強化することで、こうした壁を乗り越えるヒントが見えてくるでしょう。
本記事では、金融DXの概要から推進において生じる課題、そして解決におけるITリテラシーの重要性までを解説します。これを読むと、DX推進に向けた具体的なアクションのヒントや今後の戦略に役立つ視点を得られるでしょう。
 金融DXとは、金融業界における業務やサービスの在り方をデジタル技術の活用で変革させる取り組みです。具体的には、クラウドコンピューティングの導入やデータ分析による顧客理解の深化、AIによる業務効率化、そしてオンラインチャネルを活用した非対面型サービスの強化などが挙げられます。
金融DXとは、金融業界における業務やサービスの在り方をデジタル技術の活用で変革させる取り組みです。具体的には、クラウドコンピューティングの導入やデータ分析による顧客理解の深化、AIによる業務効率化、そしてオンラインチャネルを活用した非対面型サービスの強化などが挙げられます。
金融DXが推進されている背景には、社会全体のデジタル化と消費者ニーズの変化があります。スマートフォンやネットバンキングの普及により、顧客が金融サービスに求める価値観も大きく変化してきました。その結果、迅速で直感的な操作性や、個々のニーズに応じたパーソナライズされた提案、安全で信頼性の高い取引環境への期待が高まっています。企業は、こうした顧客の要望にしっかりと応えていくことが求められるでしょう。
また、金融DXは単なるIT化ではなく、組織の文化や業務プロセスの見直しも含まれるため、表面的なデジタル導入だけでは本質的な変革にはつながりにくいといえます。だからこそ、社内の理解と技術的な素地が重要になるのです。
金融DXの必要性が高まる中、現場ではさまざまな障壁が浮かび上がっており、特に中堅・中小規模の金融機関では、人的資源や技術面においてさまざまな課題があります。
ここでは、金融DXを推進する上で生じる主要な5つの課題を解説します。
最初に挙げられるのが、従業員のITリテラシーに関するばらつきです。金融業界は伝統的に文系出身の人材が多く、業務におけるITの活用に苦手意識を持つ社員も少なくありません。
一方で、クラウドの操作・AIツールの活用・データの読み解きといったスキルが求められる場面は増え続けています。これに対応できるよう全社的にIT知識の底上げを行わなければ、プロジェクトが一部の人材だけに依存し、組織全体としての推進力に欠けてしまうリスクがあります。
この課題を乗り越えるには、段階的な教育と、ITリテラシーの可視化を通じた現状把握が必要とされるでしょう。
次に多くの金融機関が抱えるのが、保有する膨大な顧客データや取引データを十分に活用できていないという問題です。
例えば、口座の利用履歴・ローン申請状況・相談履歴などを分析すれば、個々の顧客ニーズに応じたサービス提供が可能となります。しかし、分析基盤が整っていなかったりデータが各部署に分散していたりする場合、活用にはつながりにくいのが現状です。
このような状況では、データ統合や分析ツールの導入以前に、社員が「データをどう読み解き、業務に活かすか」といった基本的なスキルを身につけることが不可欠になります。
3つ目の課題は、長年使い続けてきた基幹システムの老朽化です。メインフレームを利用している金融機関では、運用保守に多大なコストがかかる上に新たなデジタル施策と統合しにくいという悩みがあります。
また、古いシステムはブラックボックス化していることも多く、担当者が退職することでノウハウが失われるケースも見られます。その結果、新しいツールやアプリケーションの導入が後回しになり、全体のDX推進を阻む原因となってしまうのです。
この問題を解消するには、段階的なシステムの現行化と並行して、現場のIT知識を高める必要があるでしょう。
DXが進む一方で、サイバー攻撃へのリスクも高まっています。金融業界は、個人情報や取引情報を大量に扱うため、セキュリティ対策はDX推進と同等かそれ以上に重要な要素です。
しかし、現場では「何がセキュリティリスクなのかを理解していない」「最新の脅威情報を知らない」といった声も多く、対策が後手に回るケースが見られます。セキュリティは専門部署だけの責任ではなく、全従業員が意識し、適切に行動することが求められるでしょう。
ITリテラシー向上により、従業員が危機感を持ち、日常業務の中でリスクを最小限に抑える行動を取れるようになることが期待されます。
最後に、DXを支える人材の確保という課題があります。システム開発やデータサイエンス、クラウド運用などを担う高度な専門人材は、他業界からの引き合いも強く、慢性的な人材不足が続いています。
そのため、多くの金融機関では「外部パートナーに頼らざるを得ない」「内製化を目指しても教育が追いつかない」といった声があがっているのです。こうした状況を打破するには、即戦力を採用するだけでなく、既存社員のリスキリング(学び直し)を計画的に進めることが必要となるでしょう。
このように、金融DXを推進する上では、複数の課題が密接に絡み合っています。それらの根底には「ITに対する理解不足」が共通要因として存在しており、ITリテラシーの強化が今後のカギを握るといえるかもしれません。
金融DXの実現には、単にシステムを最新化するだけでなく、従業員一人ひとりのITリテラシーの底上げが欠かせません。というのも、デジタル技術を導入しても使いこなせなければ本来の価値を引き出すことは難しいからです。特に金融業界では、正確性やスピードが重視される場面が多く、ITリテラシーが業務の質を左右するといっても過言ではありません。
また、金融DXは一部のシステム担当者だけで完結するものではなく、現場の担当者・営業・マネジメント層といった全体の連携が求められる取り組みです。誰もが一定レベルのITリテラシーを持っていれば、社内での情報共有やツールの活用がスムーズになり、組織全体でデジタル化の成果を実感できるようになるでしょう。
このように、ITリテラシーの強化は金融DXの土台を支える存在となり、ゆくゆくは業務効率化や競争力強化にもつながっていくのです。
ITリテラシーの向上は金融DXの推進においてさまざまなメリットを生み出します。
ここでは、具体的にどのようなメリットがあるのか、5つご紹介します。
ITリテラシーが高まることで、データに基づく業務運営が現実味を帯びてきます。金融業界では日々膨大な量のデータが生成されていますが、これを正しく読み解くには一定の知識が必要です。
データ分析ツールの使い方を理解し基礎的な統計知識や可視化技術を習得していれば、現場での意思決定がスピーディかつ合理的になるでしょう。例えば、顧客の行動履歴からニーズを把握したり市場の変動を予測したりすることが可能になり、これまで感覚や経験に頼っていた判断にも客観的な裏付けを加えられます。
結果としてマネジメント層が迅速かつ正確に戦略を立案できるようになり、変化の激しい金融市場において競争優位を築けるようになるでしょう。
ITリテラシーの強化は、顧客と社員の両方にとっての利便性向上にも直結します。例えば、社内でITスキルが浸透すれば、問い合わせ対応の自動化やオンライン手続きの導入が円滑に進みます。これにより、顧客は待ち時間の短縮やサービス利用の簡便さを感じられるようになるでしょう。
一方で、社員にとっても業務フローのデジタル化によってルーティン作業から解放され、より付加価値の高い業務に集中できる環境が整います。また、新しいツールやシステムの導入に対する心理的な抵抗感も少なくなり、変化に柔軟に対応できる企業文化が育っていくと考えられます。
このように、ITリテラシーの向上は、業務効率化だけでなく顧客満足度や社員満足度の向上にもつながる多面的な効果をもたらすのです。
金融業界においては、リスクの見極めと対応力が企業の信用を左右します。ITリテラシーが高ければ、リスクマネジメントの精度も向上すると考えられるでしょう。
例えば、不正アクセスやサイバー攻撃に対する初動対応においても、システムのログを読解する力や、セキュリティポリシーの意味を正しく理解する力があるかどうかが問われます。こうした知識が社内に浸透していれば、異常の早期発見と迅速な対策が可能となり被害の拡大を防げるでしょう。
また、情報管理の意識が高まることで、日常業務においても不用意な情報漏えいのリスクを減らせるようになります。これにより、企業全体としてリスク耐性を強化することが可能となります。
金融機関には、常に複雑な法規制への対応が求められます。マネーロンダリング防止や個人情報保護法への対応など、法律に準拠したシステム運用が必要不可欠です。
ITリテラシーが高ければ法規制に関するシステム的な要件を理解しやすくなり、コンプライアンスを遵守した運用体制の構築がスムーズに行えるでしょう。例えば、定期的なアクセスログの監視やデータ暗号化の実装など、具体的な技術対応を社内で検討・実行できるようになります。
こうした取り組みが社内に根付くことで、外部監査や規制当局からの信頼を得やすくなり、結果として企業のレピュテーションを高めることにつながるでしょう。
ITリテラシーの高い組織では、既存業務の改善だけでなく、新しいサービスの創出にも前向きに取り組めるようになります。デジタル技術の知識と実務理解が結びつくことで、顧客ニーズを的確に捉えた柔軟なサービス設計が可能になります。
例えば、AIを活用した与信スコアリングやブロックチェーン技術を取り入れた取引の可視化など、従来では考えられなかった革新的な仕組みを社内から生み出すことができるでしょう。
こうした変革は、単に目新しいことをするという意味ではなく、企業の持続的な成長と他社との差別化を生み出す重要な戦略となります。ITリテラシーの高さは、イノベーションの起点となり、DXを加速させるための原動力となるのです。

金融DXを推進する上で、ITリテラシーの向上は欠かせません。しかし、「ITリテラシー」とは単なるパソコン操作やインターネットの使用にとどまるものではなく、最新のデジタル技術に対する知識や業務に応用するスキルを含む、より広範な能力を指します。
ここからは、金融業界の変化に柔軟に対応して競争力を高めていくために必要な7つのスキルを紹介します。
金融DXにおいては、膨大なデータをいかに有効活用するかが重要なカギとなります。業務改善や顧客ニーズの把握には、定量データを適切に分析して意味のあるインサイトを導き出す力が必要です。
例えば、顧客の取引履歴や問い合わせ内容を分析することで、個別に最適化されたサービス提案ができるようになります。その結果、顧客満足度の向上や離脱防止につながっていくでしょう。
また、分析にはExcelやBIツール(例:TableauやPower BI)などのツールを扱う技術も求められます。初歩的な統計学の知識も持ち合わせておくことで、より深い分析ができるようになり、組織全体の意思決定の質も高まると考えられます。
クラウドコンピューティングは、金融機関における業務効率化と柔軟なシステム運用を支える重要な基盤技術です。従来のオンプレミス(自社内設置型)に比べて初期費用を抑えつつ、スピーディなシステム導入が可能になることから、多くの企業がクラウド環境への移行を進めています。
クラウドサービス(例:AWS、Microsoft Azure、Google Cloud)を正しく理解していれば、自社の業務に適したシステム選定や運用設計に貢献できるでしょう。特にSaaS(Software as a Service)やPaaS(Platform as a Service)などの仕組みを理解しておくと、DX戦略を効果的に構築する上で大いに役立ちます。
金融業界にとって、情報セキュリティは最重要課題の1つです。デジタル化が進むほど外部からのサイバー攻撃や内部不正のリスクは増加し、顧客情報の漏えいやサービス停止といった重大な事態を引き起こす可能性があります。
そのため、情報を守るための基本的な考え方や最新のセキュリティ対策について知識を持っていることが求められます。例えば、ファイアウォール(外部攻撃の防止)やエンドポイントセキュリティ(不正アクセス端末の特定)、ゼロトラストアーキテクチャ(網羅的な調査)などの概念は理解しておくと良いでしょう。
さらに、組織全体でセキュリティ意識を共有することも重要であり、従業員向けの啓発活動や定期的なセキュリティトレーニングを推進する役割も担うことができるようになります。
AI(人工知能)や機械学習(Machine Learning)は、業務の自動化や予測精度の向上を実現する強力なツールです。与信審査や不正取引検知などの分野では、すでにAIを活用した仕組みが導入されています。
この分野では、プログラミング技術や数学的素養があればより実践的な運用が可能になりますが、まずは基本的な用語や仕組みを理解することが第一歩です。「教師あり学習」「クラスタリング」「ニューラルネットワーク」といった言葉の意味を押さえておくだけでも、技術者とスムーズにコミュニケーションが取れるようになるでしょう。
技術そのものの実装が難しいと感じる場合でも、AI活用の企画や導入の意思決定に携わる立場では、基礎的な知識が必須となります。
近年注目を集めているブロックチェーンは、分散型台帳と呼ばれる仕組みで取引記録を改ざんされにくい形で管理する技術です。仮想通貨の基盤技術として知られていますが、実際には送金・決済の効率化、契約の自動化(スマートコントラクト)など幅広い用途が期待されています。
この技術を活用することで、仲介コストの削減や透明性の向上が進むため、従来の金融サービスに革新をもたらすでしょう。
導入には法規制や技術面の課題もあるため、実際の運用には慎重な検討が必要です。将来的な可能性を理解して今後の変化に備えるために、技術の基礎的な仕組みと活用事例について知識を深めておきましょう。
ITエンジニアに依存せずに業務アプリケーションを構築できるノーコード・ローコード開発ツールは、業務部門主体のDX推進を可能にするツールとして注目されています。このツールを活用すると、社内の申請フローやデータ集計の自動化ツールをプログラミングなしで短期間に開発できるようになります。
具体的には、「Power Apps」や「OutSystems」「Bubble」といったプラットフォームが知られており、操作方法を習得すれば現場の課題を自ら解決する能力が高まっていくでしょう。
これにより、システム開発にかかる時間とコストを削減しながら業務プロセスの最適化を図ることができるでしょう。
金融サービスの提供においても、ユーザー視点での情報発信や顧客体験の設計が重要になっています。SNS・ウェブ広告・SEO対策などを駆使したデジタルマーケティングの知識は、顧客接点の強化に直結する要素です。
また、UX(ユーザー体験)とUI(ユーザーインターフェース)に関する理解があれば、顧客にとって使いやすくわかりやすいサービスの設計がしやすくなります。金融機関にありがちな「使いづらい」「操作が複雑」といった印象を払拭し、利用者満足度の向上に貢献できるはずです。
さらに、ユーザビリティテストやペルソナ設計といった実務的な手法も活用することで、より精度の高いサービス設計が可能になるでしょう。
これまでに挙げたような専門スキルを習得することは、個人にとっても企業にとっても金融DX推進の大きな原動力になります。しかし、知識の習得だけでは真のITリテラシー強化とはいえません。継続的に学び続ける環境づくりや、企業全体での取り組みが欠かせないからです。
ここでは、ITリテラシーをさらに高めるための実践的なコツについて解説します。
ITリテラシーの強化は、個人任せにしていては継続が難しくなるでしょう。特に金融業界におけるDX推進には、組織全体での戦略的な取り組みが求められます。そこでカギとなるのが「DX人材の確保と育成」です。
まずは、経営層がDXの必要性を正しく理解し、自社にどのようなデジタル人材が必要なのかを明確にすることが出発点となります。その上で、現場と連携しながら中長期的な人材育成計画を立てていく姿勢が重要です。
例えば、社内研修制度を見直し、社員一人ひとりのITスキルに応じたカリキュラムを提供すると、無理なくステップアップできる環境を整えられます。また、外部セミナーやeラーニングの活用、資格取得支援制度の導入も有効な施策といえるでしょう。
こうした取り組みを通じて、社員がDXの担い手として自律的に学び、成長できる土壌を築いていくことが大切です。それによって、企業としての競争力も着実に向上していくでしょう。
ITリテラシーを強化する上でテクノロジーやツールの活用に偏重しがちですが、忘れてはならないのが「コンプライアンスの遵守」です。特に金融業界では、法規制やガイドラインに基づいた情報の管理が求められるため、情報リテラシーと倫理観の両立が不可欠です。
具体的には、個人情報保護法やマイナンバー制度や金融商品取引法など、業界特有の法令についての理解が必要です。また、サイバー攻撃への備えとして社員一人ひとりがセキュリティリスクを認識し、日々の業務において適切な対応が取れるようにしておくことが重要です。
例えば、不審なメールへの対処方法やクラウドサービスの安全な利用方法、社内データの取り扱いルールなど、基本的な行動規範を社内での統一などがリスクの軽減につながります。
企業が全体として高いITリテラシーを維持し続けるためには、法令遵守を徹底しつつ、現場でも実践できる教育体制の整備が必要になるでしょう。
金融業界におけるDX化を加速するには、単なる技術導入だけでなく、業務の本質的な変革が求められます。そこで強い味方となるのが、ITとビジネスの両面から課題解決を支援する『株式会社TWOSTONE&Sons』です。
『株式会社TWOSTONE&Sons』では、IT戦略の立案からシステム開発、さらには運用支援まで一貫してサポートする体制が整っています。また、サービスを通じて、単なる外注ではなく「パートナー」として企業のDX実現に伴走してくれるのも強みです。
公式サイトでは、実際の導入事例やサービス内容を詳しく紹介しているので、ぜひチェックしてみてください。

この記事では、金融DXを推進する上で求められるITリテラシーの基礎から応用、そして企業としての取り組みまで幅広く紹介しました。急速に進化するデジタル社会の中で、変化に対応できる柔軟なスキルと知識を身につけることは、もはや選択肢ではなく必須事項といえるでしょう。
まずは、今の自社や自身のITリテラシーの現状を見つめ直し、小さな一歩を踏み出すことから始めてみることが大切です。未来の競争力を手に入れるために、今日から行動してみましょう。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
