金融DXの推進によって叶う勘定系システムの刷新|4つの取り組み例を紹介
金融

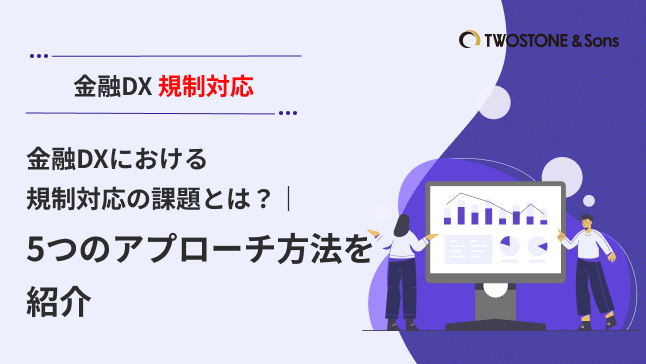
金融業界では今、「DX(デジタルトランスフォーメーション)」の推進が急務とされています。しかし、単にデジタル技術を導入するだけでは、目まぐるしく変化する規制や法律に対応するには不十分です。多くの金融機関が規制への対応に苦慮しており、業務負担や人材不足、技術面での課題に直面しています。
この記事では、金融DXを推進する際に立ちはだかる規制対応の課題とそれに対して取り得る5つの具体的なアプローチ方法を紹介します。これを読むことで、自社のDX戦略において何を見直すべきか、どのような準備が必要なのかを明確にできるでしょう。
 金融DXとは、デジタル技術を活用して、業務の効率化やサービスの高度化、さらにはビジネスモデルの転換を実現する取り組みを指します。単なるシステムの入れ替えではなく、組織全体の価値提供の方法を見直すことが求められます。
金融DXとは、デジタル技術を活用して、業務の効率化やサービスの高度化、さらにはビジネスモデルの転換を実現する取り組みを指します。単なるシステムの入れ替えではなく、組織全体の価値提供の方法を見直すことが求められます。
例えば、AIによる与信判断や不正検知システムの導入、チャットボットを活用した顧客対応の自動化などは、金融DXの一例です。こうした技術の導入は、業務のスピードと精度を高めるだけでなく、顧客満足度の向上にもつながるでしょう。
一方で、これらの技術革新は金融業界特有の厳格な法規制と密接に関わっており、新たなリスク管理やコンプライアンス体制の構築も不可欠です。金融DXを進めるうえでは技術と規制のバランスを取ることがカギとなるでしょう。
金融DXを推進する際、技術の導入だけでなく、法規制にどのように対応するかが重要なポイントとなります。
ここでは、金融機関が直面する主な規制対応の課題について解説します。
金融業界では近年、マネーロンダリング対策や個人情報保護法の強化などさまざまな規制が追加・改定されています。これにより、日々の業務において求められる文書作成や報告、審査業務が増加し、担当部署への負荷が大きくなっている状況です。
規制への対応は正確性とスピードが同時に求められるため、人力だけでは対応しきれないケースも多く見られます。そのため、業務効率化とコンプライアンスの両立を実現するにはデジタル技術の活用がカギとなるでしょう。
金融規制は国や地域によって異なるうえに、内容が専門的かつ流動的です。特に暗号資産やフィンテック分野では、規制の枠組みがまだ整っていない部分も多く、最新の情報を正確に把握し続けることが困難となっています。
こうした状況では、内部の法務部門やリスク管理部門だけで全てに対応するのは難しく、誤解や見落としが業務リスクを高める可能性もあるでしょう。外部専門家の活用やリアルタイムで情報を収集できる体制の構築が求められます。
金融DXと規制対応の両立には、テクノロジーと法規制の両方に精通した人材が不可欠です。しかし、現在の金融業界ではこうしたスキルを持つ人材の確保が難しくなっています。特に中小規模の金融機関では、専門人材の採用や育成に十分なリソースを割けない状況が続いているのです。
その結果、システム導入後にうまく活用できなかったり誤った運用により法令違反に至ったりするリスクもあります。教育体制の見直しや外部リソースの導入も1つの解決策となるでしょう。
規制対応を効率的に行うためには、AIやRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)といったテクノロジーの活用が有効です。しかし、現場では「どの技術をどう導入すればよいかわからない」「既存の業務フローに合わない」といった声が多く、導入が進んでいないケースもあります。
ツールの選定や設計段階でのサポートを得ることがスムーズな導入と運用のために重要なステップになるでしょう。また、業務プロセスの可視化も適切な技術導入に欠かせない要素です。
金融関連の法改正は頻繁に行われ、その都度業務の見直しやシステムの改修が必要になります。ところが、実務担当者が情報をキャッチアップしきれなかったり社内の意思決定に時間がかかったりすることで、対応が遅れることも少なくありません。
こうした遅延は、結果として法令違反につながる可能性があります。法改正への迅速な対応を実現するためには、事前の予測と備え、そして柔軟なシステム構成が重要になります。予測可能な変化に備えるためには社外パートナーのサポートも有効です。
金融機関がDXを進めるにあたり、法令遵守は避けて通れない重要な要素です。テクノロジーを活用した業務効率化やサービスの高度化が進む一方で、法的・制度的な整備も厳格化しており、従来以上に高度なコンプライアンス体制が求められています。
ここでは、金融機関が意識すべき主要な法令や規制を取り上げ、それぞれのポイントをわかりやすく解説します。
金融商品取引法は投資家保護を目的として制定された法律であり、証券会社や資産運用会社にとっては根幹ともいえる法令です。この法律では、不公正取引の禁止・情報開示の義務・適合性の原則などが定められています。
特に近年では、顧客本位の業務運営(フィデューシャリー・デューティ)の観点から、透明性の高い情報開示や顧客に適した商品提供が強く求められるようになってきました。DXによって収集・分析できるデータが増加している今、FIEAとの整合性を保つためにはアルゴリズムの透明性や自動化された判断プロセスの監査体制が重要となるでしょう。
参考:金融商品取引法
法令そのものだけでなく、金融庁が発出する各種ガイドラインも、実務においては重要な指針となります。例えば「金融機関向け総合的な監督指針」や「金融検査マニュアル」などは、日常業務のあらゆる局面に影響を与える内容です。
これらのガイドラインは必ずしも法律のように強制力を持つものではありませんが、金融庁による監督や検査の基準として活用されるため、実質的には遵守が求められる文書といえます。DXを進める際には、システム変更や業務フローの改修がガイドラインに準拠しているかを都度確認し、監査対応にも備える必要があるでしょう。
マネーロンダリング防止の観点からは、金融機関に対して顧客確認義務や取引記録の保存、異常な取引の報告といった義務が課されています。これは国内法に限らず、FATF(金融活動作業部会)による国際的なガイドラインも含めて対応が必要です。
金融DXにおいては、オンライン口座開設やスマートフォンを使った金融取引が普及しているため、従来の対面確認に代わる高度な本人確認(eKYC)が求められます。顔認証技術やAIによる取引モニタリングなど、テクノロジーを活用したAML対策の強化がカギとなります。
金融機関が扱う個人情報はセンシティブであり、個人情報保護法やEUの一般データ保護規則(GDPR)など、厳格なルールが適用されます。GDPRはEU圏に限られた法令ですが、国際展開を行う金融機関やグローバルな顧客データを保有する企業にとっては無視できない存在です。
GDPRでは、取得目的の明示・データ最小化・本人の同意取得・データ削除の権利などが規定されており、これらの対応をシステムレベルで実現する必要があります。DXによってデータの取り扱いが効率化される一方で、万が一の漏洩や誤用が重大な法的リスクに発展することもあるため、セキュリティ強化やアクセス管理が重要な対策となるでしょう。
日本版SOX法とも呼ばれるJ-SOXは、金融商品取引法に基づく内部統制報告制度の一部です。企業の財務報告の信頼性を確保するために、業務プロセスの統制・監査・文書化が求められます。
金融DXが進むなかで業務の自動化が加速すると、J-SOXの要件に適合する形でのシステム統制が求められます。具体的には、業務プロセスの変更点が適切に記録されているか、システムアクセスの権限が適正か、ログの保管が十分かといった点が監査対象です。これに対応するには、ITガバナンス体制の整備が欠かせません。
バーゼル規制は、銀行の自己資本比率やリスク管理の枠組みを国際的に統一するための基準です。バーゼルIIIでは、信用リスク・市場リスク・オペレーショナルリスクの計測や管理がさらに厳格化されており、資本の質や流動性にも新たな要件が加わっています。
この規制に対応するためには、複雑なリスク評価モデルやシナリオ分析が必要となります。DXによって高度なデータ分析が可能となった今、バーゼル規制に即したリスク管理体制の構築が可能となる一方で、それに見合ったシステム投資と専門人材の確保も欠かせない課題なのです。

金融機関が直面している多くの課題は、デジタル技術の活用によって新たな解決の道を見出すことができるでしょう。特に規制遵守に関する業務は、煩雑かつ高い正確性が求められる領域であるため、DX(デジタルトランスフォーメーション)の導入が効果的とされています。
ここからは、金融DXの推進によって期待される具体的な解決策について解説します。
金融DXの導入によって、これまで人手に依存していた規制対応のプロセスを効率化し、迅速に対応できるようになると考えられています。
まず、金融機関は法改正や新しい規制に対応する際、従来は各部門で手作業による確認や報告が行われてきました。しかし、デジタルツールを活用することで関連文書の管理や業務フローの自動化、コンプライアンスチェックの一元化が可能になります。
例えば、レグテック(RegTech:Regulatory Technology)と呼ばれる分野のソリューションには、法令情報の自動収集や社内ルールとの整合性チェックを行う機能を備えています。こうしたツールの導入により対応スピードが向上するだけでなく、業務負担の軽減にもつながるでしょう。
結果として、担当者が本来注力すべき判断業務やリスク評価に時間を使えるようになり、より戦略的な業務運営が可能となるのです。
金融業界では規制の変更が頻繁に行われ、それに伴いシステムや業務フローの見直しが必要になります。このような環境下では、柔軟性の高いシステムが求められます。
デジタル基盤を整えることで既存の業務システムを柔軟に拡張・修正できるようになり、規制変更に対しても迅速に対応できる体制を作れるでしょう。クラウドベースのインフラやAPI連携を活用することで、外部ベンダーや他の業務システムとの統合もスムーズに行えます。
例えば、金融庁から新たな報告義務が課された場合にも、データの収集から報告までのフローの迅速な設計・実装が可能になります。こうした柔軟性は、将来的な業界変化への適応力を高めるうえでも重要といえるでしょう。
このように、DXの推進は単なる業務改善にとどまらず、変化に強い組織づくりに貢献すると考えられています。
コンプライアンス業務は多くの書類や数値を扱うため、人的ミスの発生リスクが常に存在します。金融DXによってこれらのプロセスを自動化することで、ヒューマンエラーを減らせるでしょう。
自動化が効果を発揮する領域としては、顧客情報のKYC(Know Your Customer)チェックや取引監視、帳票作成などが挙げられます。AIやRPA(Robotic Process Automation)を取り入れることで、これらの処理を正確かつ一貫して行うことが可能になるのです。
具体的には、AIが過去の取引パターンを分析し、不正や異常な動きを検出する仕組みを構築できます。また、RPAにより、複数のシステム間で情報を転記する作業を自動化すると、入力ミスを未然に防げるでしょう。
人的ミスの削減は金融機関の信用維持にとって極めて重要であり、規制違反によるリスクの軽減にもつながるため、積極的な自動化の推進が望まれています。
膨大な業務データを蓄積している金融機関では、データ分析の活用がリスクマネジメントの高度化に寄与すると期待されています。特に、規制リスクの兆候を早期に発見するためには、データドリブンなアプローチが効果的です。
例えば、過去の違反事例や内部監査レポートを統合的に分析することで、特定の部署や取引にリスク傾向が偏っていることが明らかになります。さらに、自然言語処理(NLP)を活用すれば監査コメントや報告書のテキストから潜在的な問題点を見つけることもできます。
このように定量データと定性データの両面から規制リスクを調べることで、従来のチェックリスト型の監視では見逃されていたリスクを補足できるでしょう。結果として、問題が顕在化する前の段階で対処でき、健全な業務運営につながります。
近年、クラウドコンピューティングの進化により、金融業界でもクラウド導入が加速しています。規制対応においてもクラウドの活用は高い柔軟性と拡張性を提供してくれるでしょう。
クラウド基盤ではシステムのスケーラビリティが確保されており、必要に応じて処理能力やストレージの拡張が可能です。また、サービスプロバイダーが提供するセキュリティ対策や監査機能を活用することで、法令遵守をサポートする環境が整えられています。
さらに、災害時やシステム障害時のバックアップや復旧体制も強化されているため、業務継続計画(BCP)にも対応しやすくなります。
このようにクラウドを活用すると、金融機関はよりスピーディで安定した規制対応を実現できるだけでなく、長期的な運用コストの最適化にもつながるでしょう。
金融業界においては、複雑化する規制や顧客ニーズの多様化に対応するために、デジタル技術の導入が不可欠です。特に規制対応においては、DX(デジタルトランスフォーメーション)の活用が業務の効率化やリスク低減につながるとして注目されています。
ここでは、実際に多くの金融機関が進めているDXの具体的な取り組み事例を紹介します。
業務効率の改善を目的として、規制対応に特化したデジタルツールを導入する動きが活発化しています。
例えば、三菱UFJ国際東進株式会社では複雑な金融商品ごとの報告義務を正確に履行するために、レグテック(RegTech:規制対応技術)ツールを導入しました。このツールは、法令データベースと業務システムを連携することで、最新の法改正に自動で追従できるよう設計されています。これにより、担当者が逐一手作業で確認する手間を削減でき、ヒューマンエラーのリスクも抑えられたのです。
このようなツールの活用は、人手不足や法規制の頻繁な変更に悩まされる現場において有効な手段の1つです。
人工知能(AI)と機械学習の技術は、リスク検知や不正取引の兆候を見逃さない仕組みを構築するうえで有効です。
具体的には、取引データや顧客データをAIで分析することで通常と異なる取引パターンをリアルタイムで検出できる体制が整えられつつあります。例えば楽天証券では、AML(マネーロンダリング対策)業務にAIを導入し、従来よりも迅速に疑わしい取引を検出できるようになりました。
機械学習アルゴリズムを取り入れることで、過去の不正事例から学習し、新たな手口に対しても柔軟に対応できるのです。
クラウド技術の導入は、柔軟かつスピーディな規制対応を可能にする手段として注目されています。この技術を使って規制当局への報告業務をクラウドベースのシステムで自動化することで、報告ミスの削減や作業の簡略化が実現できるでしょう。
三井住友フィナンシャルグループでは、レポーティングツールとクラウド環境を組み合わせることで、毎月数百件に及ぶ報告書作成業務を自動化しました。この仕組みでは、社内の取引データをリアルタイムで収集・分析し、必要な形式に変換して当局に提出するまでの流れをシステムで一貫して処理できます。
こうした取り組みは、運用コストの削減にもつながると評価されています。
ブロックチェーンは、その改ざん困難な構造により、取引履歴の真正性を担保する技術として注目されています。この特性を規制対応に取り入れることで、透明性と信頼性の高い業務運用が実現できる可能性が広がります。
例えば、三菱UFJ信託銀行のKYC(顧客確認)の手続きにブロックチェーンを活用した例では、複数の金融機関が同一の顧客情報をブロックチェーン上で共有することにより、本人確認の重複作業を省略できる仕組みが整えられました。これにより、手続きの簡素化だけでなく顧客の利便性向上にもつながっています。
また、トレーサビリティが確保されることで、規制当局からの監査にも迅速に対応できるようになるでしょう。
参考:三菱UFJ信託銀行
従来のシステム開発には時間とコストがかかることが課題でしたが、ノーコード・ローコード開発の普及により、専門的なプログラミング知識を持たない部門でも柔軟に業務システムを構築できるようになっています。
金融業界でも、例えば規制変更に伴う申請フォームの改訂や新たなリスク管理プロセスの導入に対し、ローコードツールで簡易的なアプリケーションを内製する事例が増えています。ある地方銀行では、Excelで行っていた規制監査のチェックリストをローコードプラットフォームでウェブアプリ化することで、作業効率を高めました。
このような技術の導入によって現場レベルでの素早い対応が可能になり、全体の業務スピードが上がることが期待されています。
参考:足利銀行
規制対応を含む金融DXの推進において、専門的な知見と実績を持つパートナーをお探しなら、『株式会社TWOSTONE&Sons』にご相談ください。金融機関を中心に、複雑なレギュレーション対応、AML対策、KYCプロセスの効率化など現場の課題に即したソリューションを提供しています。
また、レグテック導入支援からデータ基盤の構築、クラウド移行まで幅広いサービスで金融業界のDXを力強くサポートしています。DXを進める上でお悩みの企業は公式HPで導入事例やサービスの詳細をご覧ください。

金融業界における規制対応は、業務効率とリスク管理の両面で重要性が高まっています。デジタル技術を活用することで、複雑な業務プロセスを簡素化し、透明性と正確性を確保できるでしょう。
今回紹介したAI・クラウド・ブロックチェーン・ノーコードといった技術は、今後より一層求められる対応力の強化に直結します。まずは自社に適したDXの第一歩を見極め、信頼できるパートナーとともに実行に移していくことがカギとなります。今こそ、持続可能な体制づくりに向けて行動を起こしましょう
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
