金融DXの推進によって叶う勘定系システムの刷新|4つの取り組み例を紹介
金融

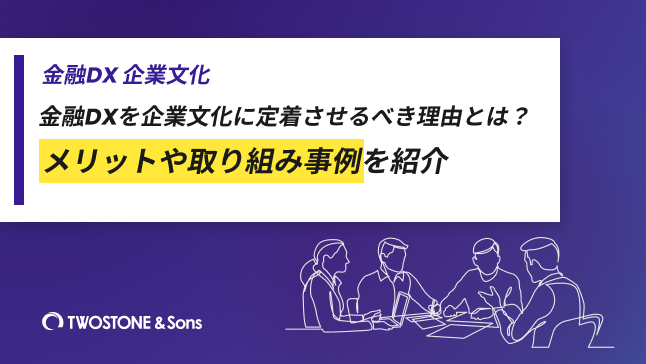
近年、金融業界においてデジタルトランスフォーメーション(DX)化が重要な企業戦略になっています。DX化によって、コストを抑えられ売り上げや利益の向上を目指せるでしょう。
しかし、DXの推進は新しい企業文化に切り替えることになり、これまでに積み上げた文化を捨てるのは、抵抗があるものです。
この記事では、金融業界においてどのようにDXを企業文化に定着させていくか解説します。DX化に取り組む過程でどのような課題があるか、またどのようにDX化を進めるかが分かれば、コスト削減や売り上げを高められるでしょう。

金融DXとは、金融機関がデジタル技術を利用して、業務内容やサービス、さらには組織のあり方そのものを変革することです。DXは単にITツールを導入するだけでなく、データやデジタル技術を使ってビジネスモデルや顧客体験を根本から変える取り組みを指します。
スマートフォンアプリを利用しての銀行取引、AIを活用した顧客対応や投資アドバイス、オンラインでの保険相談などが、金融業界におけるDX事例です。これらは、顧客の利便性を高めるだけでなく、金融機関内部の業務効率化にもつながります。
重要なのは、こうした変化を一過性のものとせず、継続的に新しい技術を取り入れて、企業文化として定着させることです。技術の導入と同時に、社員の意識改革や組織体制の見直しも進めることが、金融業界におけるDX化といえるでしょう。
金融業界では、以下5つの理由から金融DXを企業文化として定着させていくべきと考えています。
順番に解説していきます。
経済産業省が提唱する「2025年の崖」とは、老朽化した基幹システムの維持が困難となり、事業継続や競争力に深刻な影響を及ぼす可能性がある問題です。金融業界では、レガシーシステムが複雑化・ブラックボックス化しており、DX推進が遅れれば対応が難しくなります。金融DXを企業文化として根付かせることで、こうしたリスクに柔軟に対応し、将来のビジネス基盤を強固にできるでしょう。
参考:経済産業省|DXレポート
現在使用しているシステムをメンテナンスできるIT技術者が減少傾向で、メンテナンス不足による老朽化が始まろうとしています。推測では老朽化が始まるのは今年2025年です。
老朽化の背景には、システムの複雑さが関係しており、中にはあまりにも入り組んだ構造のシステムもあるため、全体像を把握できるIT技術者が限られて属人化も進んでいます。このままDXに取り組まずにいると、老朽化によるシステムトラブルや保守の限界が顕在化し、業務効率が低下してしまう可能性もあります。そのため、DXを前向きに進めていくことが重要なのです。
金融業界は深刻な人材不足の問題に直面しています。経済産業省の発表によると、2030年には40〜80万人ものIT技術者が不足する見込みです。おもな原因は日本の少子高齢化で、現役のIT技術者が第一線を退いた後の後継者が減少しています。
とくに金融業界では、レガシーシステムに対応できる技術者の高齢化と退職が進み、システム保守に必要な人材確保が難しい状況です。さらに、超低金利の継続や競争激化により利益が圧迫される中、業務の効率化やコスト削減が重要な課題です。DX化による業務の効率化を図らなければ、人手不足への対応が難しくなるでしょう。
金融サービスの提供方法は、従来の支店での対面コミュニケーションから、ネットバンキングやスマホアプリを活用したオンラインサービスへと変化しています。現在では多くの人がインターネットを利用しており、消費者の中にはインターネット上で手続きを完結したいと考える人が増加しました。
また、コロナ禍をきっかけに非対面取引の需要が急増し、通帳レスやネット振り込み、非現金決済などの普及が加速しています。証券業界でもインターネット取引口座数は年々増加しており、対面で営業する従来のビジネスモデルでは、オンラインを積極的に活用する企業との競争において不利になる可能性もあると考えられます。
金融業界では規制緩和により支店を持たないネット銀行やネット証券が台頭し、モバイル決済業者など異業種からも参入してきました。さらに、株式会社NTTドコモや第一生命株式会社など大手企業がネット銀行サービスへ進出する動きもあります。
これらの新規参入者は、既存顧客の流出を招くリスクがあります。金融業界もDXを企業文化として定着させなければ、ビッグデータやAIを駆使した競合他社との競争に遅れをとる可能性が高いでしょう。
参考:dスマートバンク
参考:第一生命NEOBANK
金融業界でDXを企業文化として取り入れることで、以下のメリットがあります。
いずれも、今抱えている課題や今後出てくる問題を解消できるメリットです。
DX化を進めることで、従来の業務を自動化でき、効率を高めることが可能です。AIやRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)の導入により、データ入力や確認作業といったルーティーン作業を自動化できるため、時間短縮が目指せます。
たとえば、融資審査や保険金支払い査定などの業務では、AIによるデータ分析と判断支援によって処理時間を短縮できる上に、人的ミスも少なくなります。また、クラウド技術の活用によってシステム間の連携が強化され、データの二重入力や連携ミスなど業務の解消につながるでしょう。
DX化により、スタッフは単純なルーティーン作業による負担が軽減され、より重要な業務に集中できるため、組織全体の生産性が向上します。金融DXが企業文化として定着すれば、つねに業務プロセスを見直し、継続的に効率化を図る文化が定着するでしょう。
企業文化としてDX化を進めれば、業務でのさまざまなコストを削減可能です。まず、DXによって業務の自動化による人件費の削減や、書類のデジタル化によってペーパーレス化が進み、され紙資源や保管スペースのコスト削減が期待できます。
また、従来のシステムからクラウドベースのシステムへ移行することで、ハードウェアへの投資や維持管理費用の削減も期待できるでしょう。さらに、データ分析によって不正取引の早期発見や与信管理の精度向上が実現し、損失リスクの低減にもつながります。
DX化によって、サーバーやソフトウェアなどへの初期投資を抑えつつ、必要に応じて人員や予算を調整できるようになり、さまざまな面でコスト削減につながるでしょう。
DXによる恩恵は、企業側だけでなく顧客側にも広くもたらされます。たとえばDX化によって24時間365日いつでもアクセス可能なオンラインバンキングやモバイルアプリが提供されることで、顧客はいつでもどこでも金融サービスにアクセスできます。
また、AIによるチャットボットの導入によって、簡単な問い合わせにすぐ対応できるようになるため、顧客の待ち時間を短縮できるでしょう。加えて、ビッグデータ分析を活用すれば、顧客一人ひとりの行動パターンや嗜好を把握し、それぞれに最適な商品やサービスを提案することも可能になります。顧客の資産状況や投資傾向に合わせた金融商品の提案や、ライフイベントに応じたタイムリーな情報提供を行うのも1つの方法です。
このように金融DXの企業文化への浸透は顧客満足度の向上につながり、結果として企業の利益にもつながるでしょう。
金融DXを一時的なプロジェクトではなく企業文化として定着させるためには、以下4つの施策が効果的です。
ここでは、金融機関がDX化を企業文化として定着させるために実施すべき4つの具体的な施策を紹介します。
書類のペーパーレス化、つまり紙ではなくデジタルで書類を保管します。紙ベースの業務をデジタルに変換することで、書類の保管や管理にかかるコストの削減だけでなく、業務効率も期待できます。
たとえば、口座開設やサービス申込などの各種手続きを電子化すれば、顧客は来店不要でスマートフォンから手続きできるため、スタッフは顧客情報の入力作業が不要です。また、手入力が少なくなるので、処理の正確性が向上して業務の効率が向上します。
コスト削減やスタッフのミスを減らせるので、まずはペーパーレス化から取り組むのがおすすめです。
システムを、従来の自社運用型(オンプレミス)からクラウドへ移行させます。自社運用型システムは拡張性に乏しく、回収や改善が難しいです。一方、クラウドならシステムを拡張させやすくビジネス環境の変化に対して対応しやすくなるでしょう。
たとえば、ユーザー数やデータ容量の増加に合わせて柔軟に規模を調整できるため、素早くシステムを開発でき、新しいサービスを迅速に市場へ投入可能です。また、クラウドなら初期投資を抑えつつ、最新技術の導入も簡単になります。
セキュリティ面でも、クラウド事業者による最新の対策が適用されるため、より安全なセキュリティ環境を整えられるでしょう。
オープンAPI(Application Programming Interface)とは、あるアプリの機能や情報をほかのアプリと共有する仕組みのことです。たとえば、地図アプリで店舗の情報が出る、天気予報アプリで最新の天気予報が見られるなどが、オープンAPIです。
金融機関の例なら、資産管理アプリと銀行口座を連携させてすべての資産をまとめて見られるようにしたり、ECサイトと決済システムをシームレスに接続したりすることで、ユーザーの利便性を高められます。
顧客体験の向上によって顧客離れを抑えられ、DX化の重要性を浸透させていけば企業文化に定着するでしょう。
RPA(Robotic Process Automation)とは、定型的なPC作業をソフトウェアロボットが代行する技術のことです。RPAを活用すれば、金融機関の日常業務に多い反復的なルーティーン作業を自動化できます。
たとえば、データ入力や照合作業、レポート作成などの定型業務をRPA化させることで、作業時間の削減とともにヒューマンエラーの防止も可能です。15人で行っていた作業を4人でこなし、7,000件以上の処理を2か月で終わらせたRPAの導入事例もあります。
RPAによってルーティーン作業が簡略化されるだけでなく、「ここをRPAに任せられないか」と考えるようになり、組織全体にDX化が定着していくでしょう。

金融DXを企業文化として定着させるには、4つの課題があります。
これらの課題を克服していけば、企業にDXが文化として定着するでしょう。
ITに関する専門知識とスキルを持つ人材の確保と育成が重要です。現在の金融業界では、金融業務に精通しつつデジタル技術にも詳しい人材が不足しています。AIやクラウド、データ分析などの先端技術に関する知識を持ち、それらを金融ビジネスに活かせる人材はどの企業も欲しがる人材です。
また、デジタルに強い人材は市場で高いニーズを持っており、なかなか確保できません。そのため、人材の確保だけでなく育成も重要で、企業全体でスキルアップ研修や意識改革が必要となります。
DXを企業文化として定着させる第一歩として、人材の確保と育成が急務です。
金融業界に根付いた企業文化を変えていかなければなりません。多くの金融機関では、今までのやり方を変えて新しい方法を取り入れることに抵抗感があります。とくに、長年同じ業務プロセスに慣れた中堅以上の社員からは、デジタル化への移行に対して「今までのやり方で十分」という反発が生じがちです。
古い企業文化を改革するには、トップマネジメントが明確なビジョンを示し、強いリーダーシップを発揮することが欠かせません。また、小さな成功体験を積み重ね、その効果を見える形で共有すれば、組織全体の理解と協力を得やすくなります。「失敗から学ぶ」姿勢や、変化を恐れずに挑戦できる雰囲気を社内に根付かせてください。環境が整えば、DXも企業文化として、自然に定着していくでしょう。
予算の確保も、金融DXを企業文化として定着させるために必要です。DXの推進には、システムの刷新や新技術の導入などの初期投資に加え、人材の育成や組織の変革にかかる継続的な資金が必要となります。
しかし、多くの金融機関では投資に対して効果や成果が見えにくいと、予算を確保しにくい傾向があります。とくに中小規模の金融機関では、「予算の確保が難しい」という声が多く、DX推進の障壁となっているのが現状です。
予算の課題を解決するには、短期的な投資回収だけでなく、中長期的に見てDX投資によってどのくらい成果が出るか評価することが大切です。初期段階では小規模なプロジェクトから始めてください。その中で得られた成果を可視化して、効果を実績として示すことで、経営層に対して予算拡大の必要性を訴えられます。このような積み重ねがあれば、DX推進への予算も確保しやすくなるでしょう。
データセキュリティとプライバシー保護の強化は、DX化における重要な課題です。金融機関は顧客の個人情報や資産情報など機密性の高いデータを大量に扱うため、デジタル化の進化に伴ってセキュリティ体制の強化が不可欠です。
クラウド移行やオープンAPI連携などでデータアクセスポイントが増えることで、サイバー攻撃の対象面が広がりデータの流出リスクが高まります。また、テレワークなど働き方の多様化に伴い、社内からの情報漏洩リスクにも十分注意を払う必要があります。
こうした課題に対処するためには、最新のセキュリティ技術の導入だけでなく、全社員を対象とした継続的な教育や意識改革を実施してください。セキュリティ対策が万全であることを社内外に示すことができなければ、DXを企業文化として定着させることは難しいでしょう。
金融DXの推進は、以下の手順で計画的かつ段階的に進めていくことが重要です。
ここでは、金融DXを効果的に進めるための5つのステップを順番に解説します。
まずは、自社が直面している課題を正確に把握することが重要です。現状の業務を分析し、非効率な部分や顧客側が不便さを感じるなど、改善が必要なポイントを特定します。
たとえば、窓口での長い待ち時間、手順が多い申込手続き、管理や保管のコストがかかる紙ベースの契約など、デジタル化によって改善できないか現場の声を聞きながら検証しましょう。実際に業務を担当している社員や顧客と直接接している部門からの意見は、リアルな課題を発見する貴重な情報源です。
また、顧客アンケートやフィードバックも分析し、顧客視点での不満や改善要望も把握します。課題の洗い出しは、DXの範囲や方向性を決める重要な基盤となるため、十分に時間をかけて丁寧に進めてください。
解決すべき課題を洗い出した後は、それぞれの課題に対して対応の優先順位を設定しましょう。課題と一口にいっても、早急に解決すべきものから、現時点では対応を急がなくてもよいものまで、その性質はさまざまです。
優先順位を決める際には、「ユーザーにどれだけ良い影響をもたらすか」という観点を重視すると効果的でしょう。とくに初期段階では、申込書のデジタル化を始めとした、ユーザーの使いやすさに直結する課題から始めるのがおすすめです。
企業都合ではなく、あくまでユーザーファーストの姿勢で課題解決に取り組んでください。既存顧客の離脱を防ぐだけでなく、新規顧客の獲得も期待できます。
優先順位を決めた課題に対して、どのように解決するか慎重に決めていきます。自社開発か外部ツールの導入か、サーバーかクラウドか、など複数を比較検討しましょう。
解決方法だけでなく、導入や管理、維持にかかる費用も十分に考慮すべきです。自社でツールを開発する場合、初期の導入コストは抑えられますが、開発から実際に社員が使用できるようになるまでには時間がかかる可能性があります。金銭的なコストだけでなく、時間的なコストも含めて、最適なツールと導入方法を選定しましょう。
導入するツールが決まったら、予算を組みます。しかし、ツールを導入したからといってすぐに効果が出るわけではありません。長期的な視点で投資した予算を回収できるかどうかを慎重に考えましょう。
たとえば、これまで窓口で対応していた手続きをインターネットで完結できるようにすれば、窓口業務にかかる人件費を抑えられます。抑えられた人件費が、ツールの導入や維持にかかる費用がどれくらいで回収できるかしっかり試算しましょう。試算結果が企業として問題ない範囲であれば予算を組み、ツールの導入を進めましょう。
予算が組めたら、いよいよDX化への取り組みです。業務をデジタル化させたら、積極的にツールを利用して業務を効率化していきましょう。
ツールを導入したら終わりではなく、ここからが始まりです。実際に利用したユーザーや社員からのフィードバックをもとに、使用方法を改善していきます。導入によって発生する課題もあるので、社内で情報を共有しつつ課題を洗い出し、改善していきましょう。短期間で目に見える成果が出にくい場合もありますが、中長期的には効果が現れやすくなります。
金融業界でDX化を進めて企業文化に定着させた3社を紹介します。
それぞれの企業で、お客様との接客やサービス提供において、積極的にDXに取り組んでいます。
三菱UFJフィナンシャル・グループでは、来店客が減少してネット決済を利用する人が増えたことに合わせて、手続きをデジタルで完結できるようにしました。店舗は残しつつ形態を変えていき、セルフ端末を設置した店舗や対面で接客する店舗など、お客様の需要に合わせて複数の形態を提供しています。
外部事業者との連携も進めており、2021年に株式会社NTTドコモと業務提携契約を締結しました。これにより、取引状況に応じて株式会社NTTドコモが提供するdポイントが付与されるデジタル口座の運営が始まっています。
みんなの銀行は、ふくおかファイナンシャルグループの傘下として設立された、国内初のデジタルバンクです。みんなの銀行は店舗を持たないため、全国どこからでも利用可能です。
口座開設だけでなく、入出金や決済などお金に関することサービスがスマートフォン1台で完結します。みんなの銀行は、今後増えてくるデジタルネイティブ世代に向けたサービスを提供しており、今後さらに需要が高まると予想されます。
参考:みんなの銀行
アフラック生命では、デジタル技術を採用した接客が行われています。AIによるデータ分析をもとに、お客様のニーズや属性を把握し、提供するサービスを最適化するシステムが導入されました。
また、オンライン面談により、お客様は場所や時間に縛られることなく、どこからでも面談を受けられます。これにより、DXを活用した新たな接客モデルとして成功を収めた事例といえるでしょう。
参考:アフラック生命保険
金融業界でDX化を進めるためには、古い方法論や考えを見直し、企業文化として定着させる必要があります。しかし、これまでのやり方を変えることは簡単ではなく、とくに結果が不透明な場合、第一歩を踏み出すには勇気が必要でしょう。
そのような企業に有益なのが、『株式会社 TWOSTONE&Sons』のサービスです。当社は、金融業界に特化したDX戦略の支援を行っており、コストの管理やリソースの配分に関する具体的なアドバイスを提供します。さらに社内戦略だけでなく、外部事業者との提携を含む社外戦略に関してもサポートが可能です。
金融DXを継続的に推進し、企業文化として根付かせたいとお考えの企業は、ぜひ『株式会社 TWOSTONE&Sons』にご相談ください。

コストの削減や顧客のニーズといった観点から、金融業界におけるDX化の推進は重要な企業戦略といえます。短期的な結果ではなく、中長期的な視点でDXを企業の文化に定着させましょう。
もし、DX化にお悩みであれば、『株式会社 TWOSTONE&Sons』が提供する専門的なサービスやサポートをご活用ください。企業に合わせて最適化されたDX戦略を提供し、サポートします。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
