金融DXの推進によって叶う勘定系システムの刷新|4つの取り組み例を紹介
金融

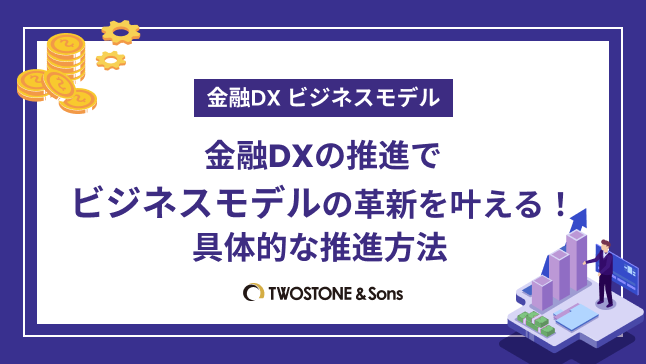
金融DXでビジネスモデルを革新する方法と、その後に取るべき5つのステップを専門的に解説します。顧客対応、業績指標、組織体制、パートナー戦略、データ活用まで網羅し、『株式会社 TWOSTONE&Sons』によるご支援もご紹介します。
金融業界では、急速なテクノロジーの進化や顧客ニーズの多様化により、これまでの常識が通用しにくくなっています。「デジタル化の波に乗り遅れてはいけない」と感じてはいるものの、「どこから手をつけるべきかわからない」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。従来のビジネスモデルに限界を感じている金融機関にとって、今こそビジネス変革を図る絶好のタイミングです。
本記事では、金融DXの基本から従来型のビジネスモデルの課題、そしてビジネスを根本から変革するための第一歩として何をすべきかを具体的に解説していきます。読み進めることで、金融機関が今後どのように変わるべきか、その道筋が明確になるでしょう。変化に対応しながら競争力を高めたいと考えている方は、ぜひ最後までご覧ください。

金融DXとは「Digital Transformation(デジタルトランスフォーメーション)」の略で、テクノロジーを活用して金融機関の業務、サービス、ビジネスモデルそのものを革新する取り組みを指します。単なる業務のIT化にとどまらず、企業文化や顧客対応の在り方までを含めて変えていくことが特徴です。
例えば、AIやビッグデータ、クラウドといった先進的な技術を導入すると、業務の効率化や精度の高いマーケティングができるようになります。従来は人の判断や手作業に依存していたプロセスも、デジタルの力で改善できるのです。
金融DXを推進することで変化する顧客ニーズに柔軟に対応し、より高付加価値なサービスを提供できます。また持続的な競争優位性を築く上でも、金融DXは避けて通れない重要な取り組みといえるでしょう。
金融DXが求められる背景には、既存のビジネスモデルの限界があります。ここでは、特に課題となりやすい3つの要素について掘り下げていきます。
従来の金融機関は、店舗を構えて対面での営業活動を行うスタイルを主軸としてきました。預金や融資、保険の案内なども主に窓口や訪問営業を通じて提供していたのが実情です。
このような対面営業は信頼関係を築きやすいというメリットがある一方で、人件費や店舗運営費などコスト負担が大きく、収益を圧迫する要因にもなっています。さらに少子高齢化や地方の過疎化が進む中で、物理的な店舗網だけでは市場をカバーしきれない場面も増えているのが現状です。
また、近年はインターネットバンキングやモバイルアプリを利用する顧客が急増しており、「店舗に行く時間がない」「非対面のサービスを求めている」といったニーズが高まっています。こうした変化に対応できないままでは顧客離れが進むリスクも無視できません。
これまでの金融機関は、自社で開発した商品を一方的に提供する「プロダクトアウト」型のサービスが主流でした。決まった金利や返済条件の商品を画一的に案内し、顧客側がそれを受け入れる形が一般的だったのです。
しかし、現代の消費者はより多様な価値観を持ち、自分に合ったサービスを求めています。「同じ住宅ローンでも、働き方やライフステージに応じて条件を柔軟に変えてほしい」といった声も増えています。そのため、画一的な商品ではこうした期待に応えるのが難しくなってきました。
その結果、フィンテック企業や外資系の金融プレイヤーなどより柔軟なサービスを提供する新興勢力に顧客が流れる現象も起きています。商品一辺倒のアプローチでは、今後の競争に勝ち残るのは困難になってきているのです。
金融機関は顧客情報を豊富に保有していますが、その多くが部門ごとに分断されており、統合的に活用されていないケースも少なくありません。たとえば、営業部門とマーケティング部門がそれぞれ別の顧客データを管理していることで、効果的な提案ができないという課題が生じています。
本来であれば、顧客の属性や取引履歴、相談履歴などの情報を連携させて分析することで、より的確なタイミングで最適なサービスを提案できるはずです。しかし、データが活用されずに眠っている状態では、それを実現することはできません。これは大きな機会損失であると同時に、顧客体験の質を低下させる要因にもなります。
さらに、こうした非効率なマーケティング活動は、結果的にコストの増加にもつながってしまいます。限られたリソースを有効に活用するためにも、顧客データの一元管理と戦略的な活用が求められるでしょう。その実現に向けては、デジタル技術の導入が急務となっています。
金融DXの推進により、従来の制約から解放された新たなビジネスモデルが次々に誕生しています。単なるIT化に留まらず業務構造や収益構造そのものに変革をもたらし、顧客視点での最適化が実現されつつあります。
ここでは、金融DXの導入によってどのようなビジネス変革が進んでいるのか具体的な側面から解説します。
かつての金融業界において営業といえば、対面での信頼構築が必須とされていました。しかしコロナ禍を契機に非対面チャネルの活用が加速し、今やそれは主力の営業手段となりつつあります。スマートフォンアプリやウェブポータルを通じて、顧客は自宅にいながら金融商品の申し込みや契約、資産運用の相談まで完結できるようになりました。
特に、ビデオ通話によるオンライン面談やAIチャットボットを活用した24時間対応の顧客サポートが注目を集めています。これによって店舗や営業時間に縛られない柔軟な営業活動が可能になり、遠隔地の顧客にもスムーズにアプローチできる体制が整いつつあります。営業効率の向上に加え人件費や施設維持費の削減にもつながるため、経営的なメリットも大きいといえるでしょう。
金融DXの中核を担うのが、顧客一人ひとりに最適化されたサービスの提供です。従来のような画一的な商品販売から脱却し、顧客属性やライフステージ、行動履歴に基づいた「パーソナライズド・バンキング」が広がっています。
例えば、ライフプランに応じて住宅ローンや教育資金、老後資金のアドバイスを自動的に提案する機能や、個別の消費傾向に合わせた資産運用プランの提示などが挙げられます。こうしたサービスは単に利便性を高めるだけでなく、顧客との長期的な関係構築にもつながるのです。
また、UX(ユーザーエクスペリエンス)を重視したアプリ設計や顧客の声を迅速にサービスに反映させるアジャイル開発の導入など、金融業界においても「顧客中心」の文化が根づきつつある点は見逃せません。
AIとビッグデータは、金融DXの推進において極めて重要な役割を果たしています。膨大な取引履歴やウェブ閲覧データ、問い合わせ内容などを基に顧客ニーズを高精度で予測し、適切なタイミングで最適な提案を行う「予測型マーケティング」が可能となりました。
例えば、ある顧客が特定の保険商品に関心を持っている兆候があれば、その行動をAIが即座に分析して営業担当者に通知、もしくは自動で関連情報を送付することで商機を逃さずアプローチできます。また、リスクスコアリングや信用スコアの算出にもAIが活用されており、融資判断のスピードと精度が向上しています。
これにより、従来の経験則に頼る営業手法からデータドリブンで科学的なマーケティング施策へと進化し、収益性の向上や無駄なコストの削減が実現されているのです。
金融DXにおいて、オープンAPIの導入は業界の垣根を越えた連携を可能にしました。API(アプリケーション・プログラミング・インターフェース)とは異なるシステム同士をつなぐ仕組みであり、これにより金融機関は外部の企業やサービスと柔軟に連携できるようになります。
例えば家計簿アプリと連携すると、利用者は金融口座を一元管理できるようになります。またECサイトと連携して決済機能を統合することで、ユーザー体験の向上も実現するでしょう。フィンテック企業との提携も活発化しており、既存の金融商品に新たな付加価値を加える動きが加速しています。
こうしたオープンな連携の仕組みはサービスの多様化を促進し、利用者にとってより利便性の高い選択肢を提供する土台となるのです。
金融業界でも、収益構造に対する再定義が進んでいます。つまり、これまでの手数料依存型モデルからサブスクリプション型や成果報酬型への転換が注目されているのです。これにより、単発の取引ではなく継続的な価値提供を重視する方向へとシフトしています。
実際に、月額制で資産運用のアドバイスを受けられるロボアドバイザーサービスや、実際に得られた利益に応じて報酬を支払う成果報酬型の保険商品などが実用化されています。このようなモデルは顧客にとっても費用対効果が明確であるため、利用のハードルが下がるのです。
また、金融機関にとっても顧客との継続的な接点が生まれるため、アップセルやクロスセルの機会が増えて中長期的な収益拡大につながるため。短期的な販売に依存せず持続可能なビジネスモデルを構築する動きは、DXの本質に近い変革といえるでしょう。

金融DXの推進により生まれた新たなビジネスモデルは、企業の在り方そのものを変えつつあります。従来の枠組みにとらわれない発想とテクノロジーの活用により、企業はより柔軟で持続可能な成長を目指せるようになっているのです。
ここでは、ビジネスモデルの変革が企業にもたらす具体的な影響について掘り下げていきます。
ビジネスモデルの革新により、従来の金融商品販売中心の収益構造から脱却して幅広い収益源の確保が可能になります。フィンテック企業との連携によって生まれたサブスクリプション型サービスや、成果報酬型のフィナンシャルアドバイザリーなどがその代表例です。
このような取り組みにより、企業は単一の商材に依存せず複数の収益チャネルを持てるようになります。収益構造が多様化することで市場の変動や顧客ニーズの変化にも柔軟に対応しやすくなり、長期的な事業安定につながるのです。
変化の激しい市場において、他社と明確な違いを打ち出すことは顧客から選ばれるために重要です。革新的なビジネスモデルを導入すると企業は独自の価値提供ができ、競争優位性を確保できます。
例えば、顧客のライフスタイルや金融リテラシーに応じて最適化されたパーソナライズド金融商品は他社が模倣しづらく、高い付加価値を持ちます。さらに、AIを活用したレコメンド機能やブロックチェーンを用いた透明性の高い取引記録なども、顧客からの信頼を獲得する上で有効な差別化要素となるでしょう。
ビジネスモデルの革新は、顧客との関係性の質を高めるきっかけにもなります。特に、デジタルツールによって実現するパーソナライズドなコミュニケーションや顧客の行動履歴に基づく最適な提案は、利用者の満足度を向上させるカギとなります。
AIチャットボットによる24時間対応のカスタマーサポートやデータドリブンな金融アドバイスによって、ユーザーは自分だけの専属サービスを受けているような体験を得られます。このような体験は顧客の企業に対する信頼や愛着を育み、ロイヤルティの向上へとつながるのです。
変化のスピードが速い現代において事業の柔軟性を保つことは、存続のための必須条件といえます。そこでビジネスモデルをデジタル基盤にシフトすると、企業はスピーディかつ柔軟に外部環境の変化に対応できるようになります。
例えば、クラウドを活用した業務体制やノーコード・ローコードを導入すると、短期間での新サービス開発が可能になります。また、オープンAPIを通じて他業種やスタートアップと連携すると、従来の枠を超えた協業によるイノベーションも促進できるでしょう。
ビジネスモデルの革新は、単に仕組みやプロセスを変えるだけではありません。企業文化そのものに変革をもたらし、従業員一人ひとりの意識や行動に変化を起こせます。
デジタル技術を積極的に取り入れる風土が定着すれば、社内にはチャレンジ精神や柔軟な思考が育ちやすくなります。さらに、データに基づいた意思決定や失敗を許容する文化の醸成は、現場からのイノベーションを生み出す重要な要素になるでしょう。
金融業界においてビジネスモデルの革新を成功させるためには、単にテクノロジーを導入するだけでなく経営戦略と密接に連動した「金融DX(デジタルトランスフォーメーション)」の推進が不可欠です。顧客のニーズや市場環境が刻々と変化する中、デジタル技術を活用しながら柔軟かつ持続可能なビジネスモデルへと移行することが求められています。
ここでは、金融DXを推進するための7つの具体的なステップについて解説していきます。
最初に行うべきは、自社の現行ビジネスモデルの構造を多角的に見直すことです。例えば、収益の主要源がどこにあり、どのような顧客層に対してどのような提供価値を持っているのかを可視化しましょう。同時に、外部環境としての市場トレンド、競合の動向、規制の変化なども整理する必要があります。
ここで活用すべきフレームワークが「ビジネスモデルキャンバス」や「SWOT分析」です。ビジネスモデルキャンバスを用いれば、自社の価値提案・チャネル・顧客関係・収益構造などを構造的に把握できます。また、SWOT分析によって自社の強み・弱み、外部機会・脅威を明確にし、DXの優先順位付けがしやすくなるでしょう。
次に取り組むべきは、顧客のニーズや行動変化の把握です。近年、金融サービスの利用形態はオンラインへと急速にシフトしています。モバイルバンキング・キャッシュレス決済・個別最適化された投資アドバイスなど、顧客は利便性と即時性を求めるようになっています。
顧客インタビューやアンケート調査、SNS分析、Web行動データの活用を通じて、具体的なニーズやペインポイントを浮き彫りにしましょう。その上で、「どのような価値を、どの顧客に、どのチャネルで届けるか」という問いに明確な答えを出すことが大切です。
明確な目標設定と進捗を測定する指標(KPI:重要業績評価指標)の定義は、DXを推進する上での羅針盤です。例えば「口座開設のオンライン完結率を半年で80%に引き上げる」「投資信託のクロスセル率を1年で1.5倍にする」など、具体的かつ測定可能なKPIを設定しましょう。
加えて、これらの目標を全社的に共有して部門間で整合性をとることが重要です。目標が不明瞭なまま進めると、現場の混乱や施策の断片化を招きやすくなります。経営層から現場の担当者まで共通のビジョンを持つことで初めて、組織全体が一丸となってDXに取り組む体制が整います。
DXを実行に移す際には、目的に応じた最適なデジタルツールやシステムの選定が不可欠です。デジタルツールは、CRM(顧客関係管理)・AIチャットボット・データ分析プラットフォーム・RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)など選択肢は多岐にわたります。
ここで重要なのは、ツール導入が目的化しないようにすることです。「業務効率の向上」「顧客体験の質的向上」といった明確な目的に沿って、必要最小限の技術を選びましょう。
デジタル技術を導入するだけでは真のDXとはいえません。業務フローや組織構造も、それに合わせて根本から見直す必要があります。紙ベースの手続きが残っている場合、どれだけシステムを導入しても業務は効率化されません。
また、従来の縦割り組織ではDXの横断的な推進は困難です。クロスファンクショナルなチーム編成やアジャイル開発手法の導入によって、部門を超えた協業体制を構築しましょう。
DXは一気に完了するものではなく、段階的に進めることでリスクを抑えつつ、確実に成果を上げるアプローチが有効です。いわゆる「PoC(概念実証)」や「パイロット導入」を活用し、小さく始めてからスケールアップしていくことが推奨されます。
このフェーズでは、仮説と検証を繰り返すアジャイル的な思考が不可欠となります。たとえば、ある業務にRPAを導入した場合、どれだけの工数削減ができたかを定量的に測定し、その効果をもとに他部門への展開可否を判断することが重要です。
また、段階的な導入は組織内部での抵抗感を抑える効果も期待できます。小さな成功体験を積み重ねていくことで、従業員の意識改革やモチベーションの向上につながるでしょう。
DXは始めて終わりではなく、そこからがスタートです。運用後も社内外からのフィードバックを収集し、継続的な改善を加える姿勢が不可欠です。ユーザーの使い勝手、業務の実効性、想定外のトラブルなど現場のリアルな声に耳を傾けましょう。
定期的なレビュー会議を設け、KPIの達成度とギャップ分析を実施します。その結果を基にシステムの改修や業務フローの微調整を行いながら、DXの成熟度を高めていきましょう。
近年、金融業界ではデジタルトランスフォーメーション(DX)が急速に進展しており、業務効率の向上だけでなく、顧客体験の刷新や新たな収益モデルの構築にまで影響を及ぼしています。特に、デジタルチャネルの整備やキャッシュレス決済の普及、AIの導入などを通じて、金融機関はこれまでにない価値を提供するようになりました。
ここでは、実際に金融DXを推進し、ビジネスモデルの革新に成功した企業の事例を紹介します。
三菱UFJ銀行は、従来の店舗型サービス中心の体制から、デジタルチャネルを主軸に据えた戦略へと大きく舵を切りました。具体的には「MUFGデジタルチャネル戦略」として、スマートフォンアプリやインターネットバンキングの機能を大幅に拡充し、顧客が来店しなくても幅広い取引を完結できる仕組みを整備しています。
この取り組みの背景には、顧客ニーズの多様化と来店頻度の減少がありました。そこで同行は、利便性の高いアプリ設計やAIチャットボットの導入により、顧客がいつでもどこでも安心して取引できる環境を整えたのです。また、個人向けだけでなく法人向けのデジタルサービスも強化し、事務手続きの効率化とペーパーレス化を推進しています。
非対面サービスの充実により、同行はサービス提供の柔軟性を高めただけでなく、人的リソースの最適配置を可能にしました。今後は、デジタルと対面を連携させたハイブリッド型の顧客対応が主流となると見込まれています。
参考:株式会社三菱UFJ銀行
みずほフィナンシャルグループは日本国内におけるキャッシュレス社会の実現を目指し、独自のQRコード決済アプリ「J-Coin Pay」を展開しています。このサービスは、銀行口座と連携して直接入出金ができる点が特徴であり、利用者はアプリ上で即時に送金や決済が可能です。
J-Coin Payの導入によってグループ全体は現金管理業務の負担軽減を実現し、コスト削減にも成功しました。また、地方銀行との提携も積極的に進めており、地域経済の活性化にも寄与しています。
このように、単なる決済ツールとしてではなく金融エコシステムの中核としてJ-Coin Payを位置付けた点が革新的でした。利用者の利便性を追求しつつ、銀行間の連携を強化することで、持続可能なキャッシュレス社会の実現に貢献しています。
地方銀行でありながら、北國銀行は大胆なDX推進により業界の注目を集めています。同行は「フルバンキングサービスの完全デジタル化」を掲げ、預金・融資・資産運用などのあらゆるサービスをオンラインで提供できるようにしました。
特筆すべきは、対面チャネルを縮小する一方で、デジタルチャネルの品質向上に注力した点です。例えば、オンラインでの口座開設や資産相談の機能を強化し、地域の顧客にもストレスなく利用してもらえるように設計しています。
さらに、社内業務においてもペーパーレス化と業務プロセスの自動化を進め、バックオフィスの生産性向上を図りました。これにより、限られた人的資源をより付加価値の高い業務に振り分けることが可能となり、競争力の強化につながっています。
参考:株式会社北國銀行
楽天銀行は、金融テクノロジーを最大限に活用することで、従来の銀行の枠を超えたサービスを提供しています。特に注目されるのは、AIを活用したリスク管理とパーソナライズドサービスの自動化です。
同行はAIモデルを用いて不正取引の兆候をリアルタイムで検知し、リスクの早期対応を実現しています。また、顧客の取引履歴や行動パターンをもとに、適切なタイミングで最適な金融商品を提案するシステムも導入しました。
この仕組みにより、顧客満足度の向上と業務の効率化を同時に実現しています。さらにデータドリブンな経営判断を可能にする基盤を整えることで、急速に変化する市場環境にも柔軟に対応できる体制を構築しています。
参考:楽天銀行株式会社
ビジネスモデルの変革には、専門的な知見と戦略的な設計力が不可欠です。『株式会社 TWOSTONE&Sons』は、金融業界における豊富な実績と深い業界理解を活かし、貴社のDX推進を全面的にサポートいたします。
単なるシステム導入にとどまらず、ビジネスプロセスの再設計・KPIの設定・社内教育・パートナー戦略まで一貫したコンサルティングを提供しています。実務に即した現実的な施策の提案と、成果創出に向けた伴走支援を行っておりますので、安心してご相談ください。

金融DXは単なるIT導入ではなく、顧客価値の再定義と持続的な競争優位を生み出すための経営改革です。ビジネスモデルを革新することで企業は新たな収益機会を得るとともに、変化する市場環境にも柔軟に対応できるようになります。
本記事でご紹介したように、DX後の継続的な取り組みとして、顧客志向のサービス提供・指標の再設計・組織の柔軟化・外部連携の強化、そしてデータ活用による成長戦略が重要です。こうした流れを確実に実践すると真の意味での「変革」を実現できるのです。
未来志向のビジネスモデルを築き、持続的な成長を目指す企業様は、ぜひ『株式会社 TWOSTONE&Sons』へご相談ください。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
