金融DXでビジネスモデルを変革!三菱UFJ等の成功事例と7つの推進手順
金融
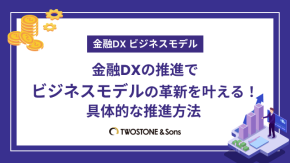
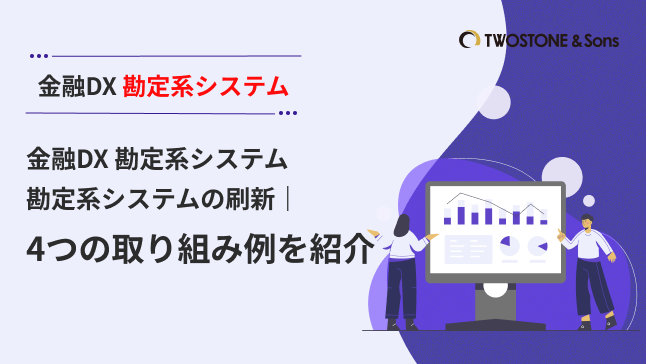
金融DXに注目が集まる今、各金融機関が導入を進める勘定系システムの刷新についてクラウド技術やAPI連携を活用した最新事例を交えて詳しく解説します。金融DXを成功させるための勘定系システム構築のポイントを丁寧にご紹介しています。
金融業界では今、「DX(デジタルトランスフォーメーション)」の推進が急務となっています。急速に進化するテクノロジーや顧客ニーズに対応するためには、従来のシステムに依存し続けるのではなく柔軟かつ効率的な仕組みに刷新する必要があります。特に、その中核を担う勘定系システムは業務全体の基盤であるため、改革の遅れが企業競争力の低下を招くリスクがあるのです。
多くの金融機関が抱える「システムの老朽化」や「専門人材の不足」といった課題は、現場の業務に直接的な悪影響を与えています。
本記事では、金融DXと勘定系システムの関係を明らかにした上で、勘定系システムの刷新に向けた具体的な課題やその影響について解説します。読み進めていただくことで、今なぜ勘定系システムの見直しが求められているのか、その背景や取り組むべき方向性を理解できるでしょう。
金融業界の未来を左右する勘定系システムの改革。その第一歩を踏み出すためのヒントを、ぜひこの記事から見つけてください。

金融業界においてDXを推進する際、影響が大きいシステムの1つが勘定系システムです。
ここではまず「金融DXとは何か」を確認し、その上で勘定系システムとの関係性について掘り下げていきます。
金融DXとは、金融機関がデジタル技術を活用して業務の効率化や顧客体験の向上、新たなビジネスモデルの構築を図る取り組みのことです。単なるIT化ではなく、組織文化や業務プロセス全体を見直す大規模な変革が求められます。
このDX推進の背景には、スマートフォンやオンラインバンキングの普及による顧客の行動変容、そしてFintech企業の台頭による競争激化があります。従来型の金融サービスでは顧客の多様化するニーズに対応しきれず、取り残されてしまうリスクが高まっているのです。
そのため、金融機関が今後も選ばれ続ける存在であるためには柔軟性とスピードを備えたデジタル体制の構築が不可欠です。
金融DXを本格的に推進するには、基幹業務の中枢である勘定系システムの刷新が欠かせません。勘定系システムは、顧客の預金管理や取引履歴、入出金処理などを担うシステムであり、その安定性と正確性が求められます。
しかし、古くから運用されてきた勘定系システムは多くの場合でレガシーシステム化しており、新しいテクノロジーとの統合や改修が困難です。結果として、DXの足かせとなっているケースが少なくありません。
金融DXを進める上では、まずこの勘定系システムの構造的な課題を理解し、段階的に改善していくことが成功のカギを握ります。
現在の勘定系システムが抱える問題点は多岐にわたりますが、特に深刻なのが「老朽化」「人材不足」「柔軟性の欠如」の3点です。ここから詳しく見ていきましょう。
多くの金融機関では、1990年代や2000年代初頭に導入された勘定系システムを今も運用しています。これらのシステムは設計思想が古く、最新技術との互換性に乏しいという問題を抱えているのです。
またベンダー依存度が高いケースが多く、改修や保守に多大なコストと時間がかかる構造になっています。これでは新たなサービスを迅速に提供することが難しくなり、結果として顧客離れを引き起こしかねません。
加えて古いプログラミング言語やOSに依存しているため、対応できる技術者が限られてきている点も懸念材料です。
勘定系システムの維持には高度な専門知識が必要ですが、対応可能なエンジニアの多くはすでに高齢化しており、後継者が育っていないという課題があります。
特にCOBOLや汎用機(メインフレーム)に関する知見を持つ技術者は市場でも希少で、採用や育成に多くの時間とコストがかかります。このような状況では、障害発生時の対応や機能改修が遅れ、業務全体のリスクが高まりかねません。
人材不足は単なる技術的な問題ではなく、企業の競争力や信頼性にも直結する深刻な経営課題といえます。
古い勘定系システムは、構造が複雑かつブラックボックス化していることが多いため、新たなサービスや機能の追加は容易ではありません。
例えば、新しいキャッシュレス決済手段やデジタル通貨への対応、外部システムとのAPI連携など現代のニーズに応じた改修には多大な労力がかかります。これは、Fintech企業との競争で後れを取る原因になります。
将来の変化に柔軟に対応するためにも、勘定系システムの柔軟性確保は不可欠です。
勘定系システムの老朽化は、単なる技術的な問題にとどまりません。日常業務の効率性や社内体制、さらに顧客との信頼関係にまで影響を及ぼします。現場での実務に直接関係する課題として、ここでは3つの観点から具体的に見ていきます。
古い勘定系システムは、インターフェースや操作性が現代のシステムに比べて直感的ではなく、作業の大半を熟練担当者の経験に頼るケースが多く見られます。そのため、業務プロセスが一部の人にしか理解されていない状態、いわゆる「属人化」が進みやすくなります。
この属人化は担当者の不在や退職などの際に業務の停滞を招くリスクが高く、結果として部門全体の生産性を低下させる原因となるでしょう。また、新たに採用された人材が古いシステムの操作を習得するには長期間の研修と実務経験が必要であり、教育コストの増大にもつながります。
さらに、属人化が進む環境ではナレッジの共有が不十分になり、イレギュラーな対応やトラブル処理にも時間がかかります。こうした負の連鎖を断ち切るには、標準化された操作性とドキュメント化された業務フローが不可欠です。システム刷新によって作業の平準化が進むことで、チーム全体の柔軟性と対応力が向上するでしょう。
金融業界では顧客の資産や個人情報を取り扱うため、常に高度なセキュリティ対策が求められます。しかし、古い勘定系システムは設計段階で現代の脅威を想定しておらず、最新のセキュリティ技術に対応しにくい構造になっています。
例えば暗号化方式が旧式である、または多要素認証などの新しいセキュリティプロトコルに未対応である場合、外部からの不正アクセスに対して脆弱です。特にOSやミドルウェアのサポート終了によりセキュリティパッチが提供されなくなることで、サイバー攻撃の標的にされやすくなります。
近年では、金融機関を狙ったフィッシング詐欺やランサムウェア攻撃が増加しており、攻撃手法もより巧妙化しています。古いシステムを使い続けることは、これらの攻撃に対抗する術を持たないまま運用を続けるという意味です。結果として、顧客情報の漏えいやサービス停止などの被害につながる危険性が高まります。
金融サービスにおいて、システムの安定稼働は事業継続に直結する課題の1つです。特に、勘定系システムは顧客の口座管理や取引処理などの中核業務を担っており、少しの障害でも顧客体験に悪影響を及ぼします。
古いシステムはソフトウェアやハードウェアの保守部品の入手が困難になるほか、障害発生時のログ管理やエラー分析が複雑化しており、復旧までに長時間を要するケースが多く見られます。また、複雑に組まれた既存の業務フローや処理手順の可視化が進んでいない場合、問題の根本原因にたどり着くまでに時間がかかる傾向があるのです。
このようなシステム障害は、例え一時的であっても顧客からの信頼を損なう原因となりかねません。口座残高の誤表示や送金エラーが発生した場合、ユーザーは企業に対する不信感を抱き、場合によっては他の金融機関に移行する選択をする可能性もあります。安定性の高いシステム基盤へと移行し、障害の発生を未然に防ぐことが顧客との信頼関係を維持するカギとなります。
近年、金融業界では「金融DX(デジタルトランスフォーメーション)」の推進が急務とされています。この背景には、顧客ニーズの多様化、規制対応の複雑化、そして新たな競争環境への適応といった課題が挙げられます。これらに応えるためには、業務全体のデジタル最適化が不可欠であり、その中核をなすのが勘定系システムの刷新です。
勘定系は金融機関の根幹業務を担う存在であり、ここを見直さずにDXを進めても成果は限定的になります。ここでは、金融DXの実現がどのように勘定系システムの再構築と結びつくのかを3つの観点から解説します。
DXの取り組みによって、従来の枠組みを超えた業務設計が可能になります。特に、業務プロセスの自動化やデータ活用の高度化を実現するには、柔軟かつモジュール化されたシステムアーキテクチャが求められます。
現行の古い勘定系では業務ロジックがシステム内に深く組み込まれており、機能単位での変更や拡張が困難です。デジタル化を進める中でこうした「閉じた設計」は障壁となりうるでしょう。そこでシステム全体を再設計すると、業務ごとの処理を柔軟に分離し変更にも迅速に対応できる構造へと進化させられるのです。
また再設計により、UI/UXの改善・リアルタイム処理の導入・データの一元管理といった多くの付加価値を創出できます。これにより、顧客サービスの質を高めつつ社内オペレーションの効率も向上します。
金融業界におけるクラウド利用はかつて慎重に進められてきましたが、セキュリティ技術の進歩とともに急速に普及が進んでいます。こうした背景には、金融庁が公表する「クラウド利用ガイドライン」や、総務省が策定した「サイバーセキュリティ戦略」といった政府の指針があり、安全かつ適切なクラウド活用を促進する環境が整えられていることが大きな要因です。
クラウドの最大の利点は、必要なリソースを柔軟に確保できる点です。従来のオンプレミス環境では予測に基づいた大規模な設備投資が不可欠でしたが、クラウドではスモールスタートが可能で、事業成長に応じてシステムを段階的に拡張できます。
また、クラウド環境では、自動スケーリングや障害時の冗長化が標準化されており、高可用性と復旧力に優れています。これにより、災害対策や業務継続性の観点からも優位性が高く、安定したサービス提供が実現できるのです。
さらにクラウドを活用することで、新しい技術やサービスの導入スピードが向上します。例えばAIによる不正検知やデータ分析基盤の構築も容易になり、競争力の強化につながるのです。
参考:金融庁
参考:総務省
API(アプリケーション・プログラミング・インターフェース)は異なるシステム同士を連携させるための仕組みであり、現代の金融DXにおいて欠かせない技術要素です。これにより、勘定系と周辺システムの間でのデータ連携や処理の自動化がスムーズになります。
例えば、APIを用いてCRM(顧客管理システム)やチャットボット、外部決済サービスとリアルタイムに連携すれば顧客対応の迅速化と正確性の向上が図れます。これにより、フロント業務とバックエンドの垣根を超えた統合的なサービス提供が可能になるのです。
またAPIベースの設計は、将来的なシステム変更や他サービスとの連携においても拡張性が高く、新たなビジネスモデルへの対応を容易にします。これにより、金融機関は変化に強い柔軟な業務基盤を構築できるのです。

勘定系システムの刷新は、金融機関にとって大規模かつ重要なプロジェクトです。そのため、計画的に段階を踏んで進めることが求められます。ここでは、刷新を成功に導くための6つのステップを順に解説します。
最初のステップでは、現在運用しているシステムの全体像を明らかにします。機能の一覧・データフロー・依存関係などを洗い出し、どこにボトルネックやリスクが存在しているかを把握しましょう。
この可視化は、将来の設計や移行時の課題抽出にも直結します。また、属人化されている業務や暗黙知となっている操作手順もここで明文化し、後のステップでの標準化の基盤としましょう。
次に、なぜ刷新するのか、何を実現したいのかを明確にします。これは単なるシステムの置き換えではなく、業務効率の改善・顧客満足度の向上・新規サービスの創出といったビジネス視点からの目的が中心になります。
業務要件についても、現行業務をそのまま再現するのではなく「あるべき姿」を描く視点が必要です。ユーザー部門との対話を重ね、業務の抜本的な見直しと再構築を視野に入れて進めましょう。
勘定系刷新には、高度な技術と豊富な実績を持つベンダーの力が不可欠です。クラウド・API設計・セキュリティ対応など、技術的な選定と同時に信頼できるパートナー企業の選定も重要です。
この段階ではRFI(情報提供依頼)やRFP(提案依頼書)を活用し、複数ベンダーからの提案を比較検討しましょう。コストだけでなく、プロジェクト管理能力やサポート体制も評価軸とすると良いです。
一括移行はシステム停止やトラブル時のリスクが大きいため、段階的な移行が推奨されます。まずは新システムをサブシステムとして導入し、一部業務から順に切り替えていく方法が有効です。
段階的移行によりトライアルを通じて問題点を早期に発見・修正できるため、結果として全体の移行成功率が高まります。並行稼働期間を設けることで、既存業務への影響も最小限に抑えられるでしょう。
新システムの運用を定着させるためには、運用マニュアルの整備と業務担当者への教育が不可欠です。新たなインターフェースや運用フローに対応できるよう、ロール別のトレーニングを実施しましょう。
またベンダーや社内のIT部門との連携を強化し、問題発生時のエスカレーションルートを明確にすることで、迅速な対応が可能になります。運用管理の平準化とナレッジ共有もあわせて推進しましょう。
刷新はゴールではなく、スタートです。移行後は、定期的にシステムの稼働状況や業務への効果を評価して改善を重ねることで、持続的な成長を支えるインフラとして機能させていく必要があります。
PDCAサイクルを回しながら、運用負荷や障害発生率、顧客満足度などの指標をモニタリングし、必要に応じて機能追加や設定変更を行っていきましょう。こうした継続的改善こそが真のDX実現につながります。
金融DXは、勘定系システムの刷新を通じて持続可能で柔軟な業務基盤の構築を後押ししています。実際に各金融機関では、最新技術を活用しながら業務効率や顧客満足度の向上を図る取り組みが進められているのです。
ここでは、金融DXを具体的に推進している国内の代表的な事例をご紹介します。
住宅金融支援機構では、「総合オンラインシステム」の構築を通じて勘定系業務のデジタル化を実現しています。この取り組みでは、顧客との接点となるフロント業務と融資審査や管理を行うバックオフィス業務を一体化した統合的なシステム設計が特徴です。
さらに基幹システムにおいてもAPI連携を活用することで、地方公共団体や住宅事業者との情報連携を円滑に行えるよう工夫されています。これにより申請から融資実行までの業務フローが効率化され、ユーザー利便性と事務処理精度の双方を高めています。
このような取り組みはレガシーシステムに依存しない柔軟なサービス提供の基盤として、他の金融機関にも示唆を与えているといえるでしょう。
農林中央金庫ではJAバンク全体をカバーする「統合勘定系システム」を構築し、全国のJAとの連携強化と業務の標準化を推進しています。この大規模な再構築プロジェクトでは、共通基盤を導入することでスケーラビリティを確保し、将来的な制度改正や業務変化にも柔軟に対応できる体制を整えました。
このシステムはクラウド技術と仮想化基盤を活用し、物理サーバーに依存しない高可用性構成となっており、障害時のバックアップ体制も強化されています。結果として、業務継続性(BCP)を重視した堅牢なインフラが構築されました。
また地方ごとのニーズに合わせたカスタマイズも可能で、JA各支店の多様な業務形態に適応できる点も評価されています。
参考:農林中央金庫
福島銀行ではSBIグループと提携し、「クラウド型勘定系システム」の導入を進めています。このプロジェクトの最大の特徴は、従来型のオンプレミス環境から完全に脱却してフルクラウドベースで勘定系を運用している点です。
クラウド環境への移行で初期投資の抑制や柔軟なリソース管理が可能となり、新サービスの立ち上げや法制度対応にもスピーディに対応できるようになりました。また、最新のセキュリティ機能を随時適用することでサイバーリスクへの備えも強化されています。
システムの可用性・拡張性に優れている点から、今後は他地方銀行への横展開も期待されるモデルケースとして注目されています。
ほくほくフィナンシャルグループは、「BeSTA(ベスタ)」と呼ばれる勘定系パッケージとオープンAPI連携基盤「ピトン」の導入により金融DXを実現しています。BeSTAは複数の地方銀行で共同利用されており、運用コストの削減と機能強化を両立する共通基盤です。
一方のピトンは他のシステムとのデータ連携をリアルタイムで実現するAPI基盤であり、FinTech企業との連携や新たなデジタルサービス提供において大きな役割を果たしています。
このような二層構造のシステム構築により、安定運用とサービス革新の両立を図りながら利用者体験の向上に貢献しています。
勘定系システムの刷新は単なるシステム更改に留まらず、金融機関全体の業務改革と顧客満足度向上に直結する重要な施策です。しかしその一方で、システムの複雑性・業務依存度の高さ・リスク対策など乗り越えるべき課題も少なくありません。
『株式会社 TWOSTONE&Sons』では、クラウド移行・API連携・基幹系刷新といった先進的な取り組みに精通しており、各組織に最適なシステム構築と導入後の運用支援までを一貫してご提供いたします。
プロジェクト初期の構想段階から、要件整理・技術選定・移行計画の策定・社内教育に至るまで幅広い分野でのサポート体制を整えております。複雑な勘定系業務だからこそ、専門性の高いパートナーと進めることが成功への近道です。
DXの第一歩として、ぜひ一度ご相談ください。

金融業界におけるDXの加速は単なる技術導入ではなく、業務プロセスや顧客対応の変革を意味しています。中でも勘定系システムの刷新はその中核を担う施策であり、組織の柔軟性・持続可能性・成長性を左右するのです。
今回ご紹介したように、多くの金融機関がクラウド技術・API活用・共通基盤の導入などを通じて、勘定系の最適化に取り組んでいます。これにより、業務の効率化と同時にサービス品質や顧客満足度の向上が期待されています。
もし貴社が今後のDX推進や勘定系刷新について検討されているのであれば、専門的な知見を持つパートナーのサポートが重要です。未来志向の金融インフラを構築し、競争力ある業務基盤を共に作り上げていきましょう。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
