金融DXの推進によって叶う勘定系システムの刷新|4つの取り組み例を紹介
金融

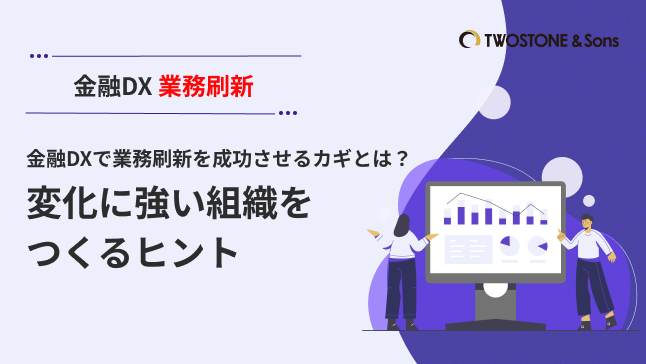
「この働き方を進めて、本当にこのままで良いのだろうか」。そう感じたことがある方は少なくないでしょう。
金融業界では、長年の慣習や紙ベースの業務が残る中で時代の変化に追いつけずにいる組織も多く存在します。しかし、デジタル技術の進化が著しい今、旧来のやり方にこだわっていては競争力を保つことが難しくなるでしょう。
そこで注目されているのが「金融DX(デジタルトランスフォーメーション)」です。単にツールを導入するだけではなく、業務の在り方そのものを見直して刷新していく動きが加速しています。
この記事では、金融DXがどのように業務刷新を促し、組織の柔軟性や競争力向上に寄与するのかを詳しく解説します。業務を効率化したい方、社内体制を見直したい方、将来的に強い組織を目指す方にとって実践的なヒントが得られる内容となっているでしょう。

デジタル技術を取り入れるだけでは真の変革にはつながりません。重要なのは、それをどのように業務の中に落とし込み、成果につなげていくかという点です。
金融DXとは、「デジタル技術を活用して、金融業界のサービス・業務・組織全体の在り方を変革していく取り組み」です。具体的には、オンラインバンキングの強化やAIによる審査業務の効率化、クラウドの導入などが挙げられます。
しかし、こうした表面的なツール導入にとどまらず、組織文化や業務フローそのものの再設計が求められる点が特徴です。単純な紙の帳票をデジタル化するだけでなく、その帳票がなぜ必要なのかを見直すことが真のDXへの第一歩となるでしょう。
金融業界は、顧客の信頼を土台としながら膨大な情報を扱い、正確な対応が求められる業種です。ところが、紙ベースの業務や属人化した作業が多い現状では人的ミスや非効率が避けられません。
さらに、FinTechの台頭や顧客ニーズの多様化により、従来のやり方ではスピードや柔軟性が不足しているという声も増えています。このような背景から、業務の構造そのものを見直し、より柔軟で対応力のある体制へと移行する必要があるのです。
業務刷新とは、既存の業務プロセスや仕組みを見直し、より効率的かつ柔軟に対応できるように再構築することを指します。そして、金融DXはその業務刷新を実現するための手段ともいえるでしょう。
例えばRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)を導入すれば、定型的な入力作業を自動化し、人的リソースを他の業務に振り向けることができます。また、クラウドシステムの活用によってリモートでも業務が進められる体制を整えることで、働き方改革にもつながります。
このように、金融DXの推進は業務刷新と密接に関わっており、両者を並行して進めていくことで組織全体の柔軟性と競争力が高められるでしょう。
金融DXによって業務刷新を進めるとさまざまな形で組織に好影響をもたらします。
ここでは、具体的な5つのメリットを紹介します。
属人化とは、特定の業務が一部の社員の経験や知識に依存している状態です。属人化が進むと、担当者が不在の際に業務が滞ったり引き継ぎが困難になったりするといった問題が生じます。
金融DXでは、業務の手順を明確化してITツールを用いて一貫性のあるフローを構築することが可能です。こうすると誰が担当しても一定の品質が保てるようになり、効率的に業務を進める体制が整っていくでしょう。
従来の業務では、日常的な入力作業や確認作業に多くの時間が割かれ、人材が本来の能力を発揮しづらい場面も少なくありませんでした。そこで業務刷新を進めると、ルーティンワークを自動化できるため、社員がより創造的な業務に集中できる環境をつくれるのです。
この環境を整えることで、人材配置の柔軟性が出てきて適材適所の運用が可能になるため、組織全体のパフォーマンスが高まるでしょう。
顧客満足度を高めるには、迅速かつ的確な対応が欠かせません。業務刷新を通じて情報の一元管理やリアルタイムでの共有が可能になることで、問い合わせ対応のスピードが上がるでしょう。
例えばCRM(顧客関係管理)ツールを導入すれば、過去の対応履歴を即座に参照できるため顧客のニーズに対して的確な対応ができるようになります。結果として、顧客の信頼を築きやすくなり、長期的な関係を構築できるでしょう。
部門ごとの情報が分断されていると意思決定の遅れや誤解が生じやすくなります。そこで金融DXを活用して業務の見える化を図ると、部門間で情報がスムーズに共有されるようになり、連携の強化につながるのです。
例えば全社で統一されたデジタルプラットフォームを導入すれば、営業と事務、経営層が同じ情報をもとに判断を下すことが可能になります。情報を一元化することで組織内の連携が強まり、戦略の実行力も高まるでしょう。
業務刷新が進んだ組織では、業務プロセスが整理され、必要な情報も整備されているため、新しい取り組みも始めやすくなります。新規事業やキャンペーンを立ち上げる際にも、フローやデータを活用することで準備期間を短縮できるでしょう。
また、既存の業務フレームを柔軟に応用できる環境が整っていれば変化の速い市場にも対応しやすくなり、企業としての競争力維持にもつながっていきます。
業務刷新を実現するためには、単にデジタルツールを導入するだけでは不十分です。金融業界が真に変化に対応できる組織へと進化するためには、現場の課題を正確に把握し、戦略的に取り組みを進めることが求められます。
ここでは、業務刷新の土台を築くために取り組むべきポイントを5つ紹介します。
まず必要なのは、業務プロセス全体の可視化と現状分析です。現在の業務フローがどのように構成され、どこに無駄や非効率が潜んでいるのかを洗い出すことで改善すべき領域が明確になるでしょう。
例えば、日々のルーティン作業にどれだけの時間がかかっているのか、担当者の経験や属人性に依存している業務がどの程度あるのかを把握することで、DXによってどの業務を効率化すべきかの優先順位が見えてきます。分析には業務プロセスマッピングや業務時間の計測ツールなどを活用すると良いでしょう。
DXを進めるうえで、すべてを外部に任せるのではなく、内製化可能な領域を見極めて組織内部で対応力を育てていくことが重要です。特に、継続的な改善が求められる業務については、内製化することで柔軟に対応できる体制が整います。
例えば、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)や業務用チャットボットの設計・運用は、ある程度内製化しやすい領域といえるでしょう。社内に知見を積み上げることで将来的にさらなる業務効率化にもつながります。
一方で、最新の技術や専門的なノウハウが必要な領域に関しては、信頼できる外部パートナーと連携することが効果的です。自社だけで変革を推進するのは限界がありますが、外部の知見を取り入れることでより実現性の高いDX戦略が立案できるようになります。
例えば、『株式会社TWOSTONE&Sons』のようなDX支援に特化した企業との連携によって、自社の課題に合った最適な手段を提案してもらえるだけでなく、変革を成功に導くための伴走支援も受けられるでしょう。
業務刷新の成功には従業員のスキルアップも不可欠です。これまでの業務スタイルと異なるデジタル環境に対応できるように、リスキリング(再教育)を積極的に進める必要があります。
例えば、データ分析の基礎や業務自動化ツールの操作方法、クラウドサービスの利用方法など実務に直結するスキルを学ぶ機会を設けることで、社員の意識と行動が変化していきます。若手だけでなく経営層もこの教育を受けることで、組織全体で変化に強い体制を築けるでしょう。
いきなり大規模なDXプロジェクトを始めるのではなく、小さな成功体験を積み重ねるアプローチが効果的です。PoC(Proof of Concept:概念実証)として小規模な範囲で新しい取り組みをテストしてその成果を検証することで、リスクを抑えながら導入の可能性を探ることができます。
例えば、一部の業務部門だけでRPAを導入し成果を測定すると、その後の全社展開に向けた説得力あるデータが得られるでしょう。このように段階的に取り組むことで、社内の理解と協力も得やすくなります。

金融DXが業務刷新において効果を発揮するのは、単なるデジタル化にとどまらず業務構造そのものの見直しや最適化を可能にするからです。
ここでは、その具体的な理由を5つ紹介します。
RPAやAIを活用した定型業務の自動化で、人材をより価値の高い業務にシフトさせることが可能ですこれにより、これまで手作業で対応していた処理業務の時間が削減され、戦略立案や顧客提案といった創造的な業務に注力できるようになります。
例えば、定期的に発生するレポート作成やデータ入力作業を自動化すれば、営業担当者がより多くの顧客に向き合える時間を確保できるようになるでしょう。結果として、組織全体の生産性が向上できるでしょう。
クラウドサービスを取り入れることで業務データをリアルタイムで共有しやすくなり、部門間の連携もスムーズになります。特に在宅勤務やハイブリッドワークが進んでいる今、クラウド化による業務基盤の強化が求められているのです。
例えば顧客データベースや取引履歴をクラウド上で管理することで、営業部門とコンプライアンス部門が同じ情報に基づいて迅速な意思決定を行えるようになります。このような仕組みは、情報の一元管理と業務の透明性向上にも寄与するでしょう。
DXを推進すると、組織内に蓄積されたデータを活用しやすくなります。適切な分析基盤を整えることで経営判断における根拠を数値で把握できるようになり、感覚や経験に頼らない合理的な意思決定が可能になるでしょう。
例えば顧客の行動履歴や取引傾向を分析することで、新商品の導入時期やキャンペーン施策のタイミングを適切に判断できるようになります。このような取り組みは、競争力のあるサービス提供にもつながります。
契約書のやり取りや承認フローに紙を使っていると、郵送や押印の手間が発生して業務スピードが低下する要因になります。電子契約や文書管理システムを導入すると、こうした手続きをスムーズに進められるでしょう。
また、ペーパーレス化により保管スペースの削減や情報検索の迅速化も図れます。業務担当者の負担軽減だけでなく、環境への配慮という観点からも有効な施策といえるでしょう。
顧客からの問い合わせ対応に時間がかかっている場合、チャットボットやFAQシステムを取り入れることでよくある質問に自動で対応し、業務負荷を軽減できます。これにより、対応品質を維持しながら担当者がより複雑な案件に集中できる環境が整います。
例えば、口座開設やローン申込のステータス確認など、定型的な質問に対してはAIが自動で案内することで、顧客満足度の向上も期待できるでしょう。人的リソースを有効に使うための有力な手段といえます。
金融DXは業務刷新や競争力の強化につながる可能性がある一方で、進め方を誤ると期待した成果が得られにくくなる恐れがあります。
ここでは、金融業界がDXを推進する際に気をつけたいポイントについて、具体的にご紹介します。
デジタル化施策の多くは成果が短期的に現れるとは限りません。例えば、業務システムのクラウド移行や人材育成にかかるコストは初期投資が必要であり、数カ月単位での費用対効果だけを評価してしまうと重要な取り組みが中断される可能性があります。
そのため、ROI(投資利益率)を判断する際には中長期的な視点を持ち、成長戦略や組織の柔軟性の向上といった非財務的な効果にも着目していきましょう。DXによって業務がどれだけ効率化され、従業員の生産性や顧客満足度がどう変化したのかを測定する視点が求められます。
経営層が描く理想と、現場での実務との間にはしばしばギャップがあります。トップダウンで施策を導入しても現場に適応しなければ形骸化してしまう可能性があるため、プロジェクトの設計段階から現場担当者の意見を反映する体制が必要です。
新しい業務ツールを導入する場合は、実際に使用するオペレーターや営業担当が操作しやすいと感じるかどうかを検証する時間を取りましょう。現場との対話を重ねることが、DX推進の成功率を高めるカギとなります。
外部のITベンダーやコンサルティング会社と連携することは、専門的な知見を活用するうえで有効です。ただし、すべてを丸投げしてしまうと自社内にノウハウが蓄積されず、将来的に自立したDX推進が難しくなる可能性があります。
そのため、内製化可能な領域については自社メンバーで対応し、必要に応じて外部と協業するハイブリッドな体制を目指すことが現実的です。プロジェクトの初期段階からどこまで自社で担えるのかを明確にし、段階的に内製化比率を高めていく戦略を検討するとよいでしょう。
「DX」という言葉は広く使われていますが、その意味が社内で共有されていなければ、部門間で温度差が生まれたり施策の目的が不明瞭になったりする可能性があります。
したがって、まずは社内で「自社にとってのDXとは何か」を言語化し、それを経営層から一般社員まで共有するプロセスが重要になります。定義づけを行うことでプロジェクトの方向性が明確になり、関係者が一体となって取り組みやすくなるでしょう。
DXという言葉に引きずられ、ツールの導入自体が目的になってしまうケースも少なくありません。チャットボットを導入したにもかかわらず、活用されないまま終わってしまうといった事態も起こり得るでしょう。
本来、DXの目的は「業務の効率化」や「顧客体験の向上」であるため、ツール導入はあくまで手段に過ぎません。導入前に業務プロセスの見直しや運用フローの最適化を行い、「なぜこのツールが必要なのか」を明確にしてから取り組むことが重要です。
金融業界におけるDX推進は、単なるシステムの刷新にとどまらず、業務そのものの見直しや人材育成、組織文化の変革を含む包括的な取り組みです。これらをバランス良く実行していくには、専門的な知見を持つパートナーの存在が欠かせません。
『株式会社 TWOSTONE&Sons』では、以下のような支援サービスを提供しています。
これらのサービスは、単なる技術提供にとどまらず、金融機関の業務フローや文化に合わせたカスタマイズが可能である点が特徴です。もし、金融DXの進め方に不安を感じている場合や自社の課題にマッチする解決策を探している企業は、ぜひ一度ご相談ください。

本記事では、金融業界がDXを通じて業務を刷新していくための具体的なアプローチについて解説しました。まず、現状の業務プロセスを分析し、内製化できる領域を明確にしながら外部の知見を取り入れていくステップが有効です。加えて、デジタルツールの活用やデータ分析基盤の構築、クラウド化による業務の可視化は、競争優位性の強化に直結するでしょう。
未来に向けて持続可能な組織を築いていくために、今こそ業務刷新の一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。『株式会社 TWOSTONE&Sons』では、その歩みを伴走型で支援しています。金融DXに取り組むことで、変化の激しい社会の中でも柔軟に対応できる組織基盤を構築できるでしょう。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
