金融DXの推進によって叶う勘定系システムの刷新|4つの取り組み例を紹介
金融

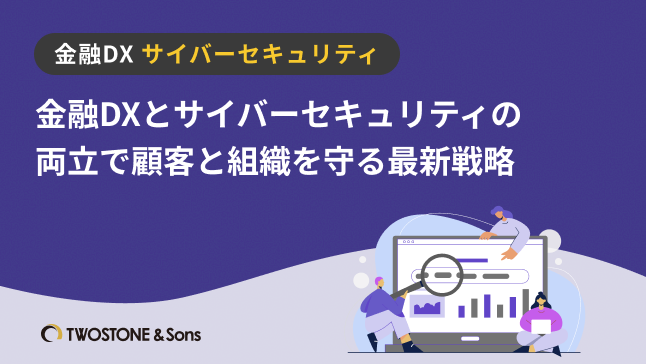
近年、デジタル化の波が金融業界にも押し寄せ、業務効率化やサービスの高度化が進む一方で、サイバー攻撃による情報漏えいやシステム障害のリスクが増大しています。
「業務をデジタル化したいけれど、セキュリティが心配」
「どのように守りと攻めのバランスを取ればよいのかわからない」
と悩んでいる担当者も多いのではないでしょうか。
この記事では、金融DXの基本からサイバーセキュリティとの関係性までを解説し、金融機関が直面する課題にどう向き合うべきかを解説します。本記事を読めば、デジタル化を推進しながらも安全性を確保するための考え方や戦略を整理でき、組織として何に注力すべきかを見極められるでしょう。

デジタル化を進めると、利便性の向上と同時に情報セキュリティのリスクも高まる傾向にあります。そのため、金融DXとサイバーセキュリティは表裏一体の関係にあるといえるでしょう。ここでは、まず金融DXの概要を再確認し、そのうえでサイバーセキュリティの役割や課題を具体的に見ていきます。
金融DX(デジタルトランスフォーメーション)は、単なるITの導入を超えて組織の構造や業務プロセス、さらには顧客体験までも変革する取り組みです。多くの金融機関が時代のニーズに応じたサービス提供を目指し、既存のアナログな業務を見直しています。こうした動きは、利便性の向上だけでなくコスト削減や競争力強化にもつながるでしょう。
とはいえ、金融DXを推進するうえでは、単に最新のシステムを導入するだけでは不十分です。顧客の情報を預かるという業界特有の責任がある以上、セキュリティとの両立を考えることが欠かせません。
サイバーセキュリティとは、ネットワークやシステム、データを不正アクセスや攻撃から守るための総合的な取り組みのことです。これは単に技術的な対策を講じるだけでなく、組織全体で情報リテラシーを高めて継続的な監視や教育を行うことが求められます。
ここからは、サーバーセキュリティの基本的な概念と、金融業界における課題について説明します。
サイバーセキュリティにおいては、「機密性」「完全性」「可用性」の3要素が基本的な考え方とされています。機密性は情報が第三者に漏れないこと、完全性は情報が改ざんされないように保つこと、そして可用性は必要なときに必要な情報にアクセスできることです。この3つの要素をバランス良く保つことが、安定したシステム運用に不可欠です。
加えて、ゼロトラストと呼ばれる新しいセキュリティモデルも注目されています。これは「すべてを信頼しないこと」を前提に、ユーザーやデバイスの認証を強化するアプローチであり、クラウドベースのサービスが増える中で重要性を増しています。
金融業界は顧客の資産や個人情報を扱うため、他業界と比較しても高いレベルのセキュリティ対策が求められます。しかし現実には、古い基幹システムが足かせとなり最新のセキュリティ技術を導入しづらいという課題も残っています。また、外部委託先とのデータ連携や、クラウド利用による新たなリスクも無視できません。
さらに、人的リスクも見逃せないポイントです。社員の不注意による情報漏えいや不正アクセスへの対応遅れなど、技術面だけでなく運用面の見直しも重要です。こうした複合的なリスクに対応するには、専門的な知識を持つ外部パートナーと連携することが現実的な解決策の1つとして考えられるでしょう。
金融業界には、金融DXの推進と並行してサイバーセキュリティへの対策強化が求められています。その中で、金融庁は具体的な方針を打ち出し、金融機関が組織として適切な防御体制を整えるための枠組みを明示しています。これらの方針は単なるリスク回避のためではなく、顧客と組織の信頼関係を守るための基盤です。
ここからは、金融庁が重視する4つの柱について詳しく紹介します。
参考:金融庁|金融分野におけるサイバーセキュリティ強化に向けた取組方針(概要)
金融庁は、金融機関のサイバーセキュリティ対策の実態を把握するため、建設的な対話と情報の一斉把握を実施しています。この取り組みは、単なる監督ではなく現場の実情を理解しながら支援する姿勢に基づいているのです。
例えば、金融庁は年に一度、金融機関全体に対してサイバーセキュリティに関するアンケート調査を行い、その結果をもとに改善の方向性を共に検討しています。こうしたプロセスにより金融庁と金融機関との間で透明性の高い対話が実現され、現場の課題が可視化されやすくなります。
このような連携体制を維持することで、サイバー攻撃への対策がより実効性のあるものとなり、組織全体での対応力を高められるでしょう。
サイバー攻撃は単独の企業にとどまらず、業界全体へ波及するリスクがあります。そのため、金融庁は金融機関同士の情報共有の枠組み強化を推奨しています。情報共有はインシデントの早期発見や対応の迅速化に寄与する手段として重要視されているのです。
例えば、ISAC(Information Sharing and Analysis Center)のような組織を通じて、攻撃の兆候や被害状況、対応策などがリアルタイムで共有されるようになってきました。このような枠組みは各機関の孤立を防ぎ、被害の最小化に役立っています。
情報の共有を円滑に進めるためには、セキュリティポリシーの統一や技術基盤の整備も必要となるでしょう。その実効性を高めることで金融業界全体のセキュリティレベルを底上げすることが可能になります。
実際のサイバー攻撃は予期せぬタイミングで発生します。そのため、事前の訓練が重要です。金融庁は、業界全体での横断的なサイバーセキュリティ演習の実施を奨励し実務レベルでの対応力強化を行うよう提示しています。
演習では、実際の攻撃シナリオを想定した対応プロセスの検証・改善が求められ、こうした訓練により、各部署の連携体制や判断スピードが向上し、有事の際の混乱を最小限に抑えられるでしょう。
また、演習の内容を定期的にアップデートすることで、新たな攻撃手法に対する知識と対応力も蓄積されていきます。継続的な取り組みが長期的な安全性の確保につながるでしょう。
テクノロジーの進化とともにサイバー攻撃の手口も日々複雑化しています。そのため、金融庁は人材育成を柱の1つに掲げ、専門的な知見を持つ人材の確保と育成に注力しています。
現場で求められるのは単なるITスキルにとどまらず、金融特有の業務知識を理解したうえでリスクを評価・対処できる能力です。そのため、金融庁では、大学や専門機関と連携した教育プログラムの充実化を図り、実務に活かせる研修機会の提供を促しています。
さらに、社内でのローテーション制度やOJTを通じて若手人材が継続的にスキルを高められる仕組みづくりも推進されています。人材の質を高めることが、結果として組織全体のサイバーセキュリティ耐性を強化することにつながるでしょう。
サイバー攻撃が日々巧妙化する中で、金融機関が主体的にセキュリティ水準を高めていく姿勢が求められています。金融庁の方針に基づいた取り組みを進める一方で、各機関が自らの役割と責任を認識し現実に即した施策を講じていく必要があります。
ここでは、金融機関が実行可能な対策を5つの視点から整理していきましょう。
まず、効果的な対策を実施するには現状を正しく捉えることが重要です。多くの金融機関では、既に何らかのセキュリティ対策が講じられているものの、攻撃の手法や脅威の性質が変化する中で過去の対策だけでは不十分になる可能性があります。こうした背景から、自社のセキュリティ体制を定期的に点検し、強化すべきポイントを明確にする取り組みが必要でしょう。
自己点検にあたっては、ISO/IEC 27001などの国際的な情報セキュリティ管理基準を活用し、自社の取り組みを客観的に評価することが推奨されます。また、第三者機関によるアセスメントを受けることで、自社では気づきにくい脆弱性を可視化しやすくなると考えられます。
セキュリティ対策は、単独での対応に限界があります。近年では、サイバー攻撃の被害を受けた企業が他機関と情報を共有することにより、被害の拡大を防いだ事例も増えてきました。このような実績を踏まえ、同業他社との情報連携体制を構築する必要があるのです。
具体的には、ISAC(Information Sharing and Analysis Center)と呼ばれる枠組みの活用が考えられます。これは、同一業界内の企業がサイバー脅威に関する情報を安全に共有するための仕組みであり、攻撃の兆候や発生後の対応策についてスピーディに把握できる環境を整えることが目的です。
こうした情報共有は単なる防御力の強化にとどまらず、業界全体のリスクマネジメント力を底上げする役割も果たすことになるでしょう。
技術的な対策を講じてもそれを運用する人材が不足していれば十分な効果は期待できません。特に金融業界では、サイバーセキュリティに精通した専門人材の確保が課題となっています。このような状況を打破するには、外部からの人材採用だけでなく社員に対して継続的な教育を行い、セキュリティ意識を高めることが必要になるでしょう。
育成の手段としては、実践型の研修プログラムの導入やサイバー攻撃を模した訓練の実施が効果的です。加えて、経営層を含む全社員がセキュリティの重要性を理解し、日常業務において意識を持てるような社内風土の形成が求められます。
このように多層的な人材戦略を講じることで、組織としてのセキュリティ耐性を高めていくことが現実的なアプローチといえるでしょう。
業務の一部を外部のITベンダーやクラウドサービスに委託している場合、委託先のセキュリティ対策もまた重要な検討事項となります。実際に、外部ベンダーの管理体制が甘く、そこを起点にサイバー攻撃を受けたという事例も報告されています。このため、ベンダーとの契約を見直し、情報セキュリティに関する管理基準の明確化やモニタリング体制の強化が求められるでしょう。
また、定期的な監査やチェックリストに基づく評価を行うことで外部委託先のリスクを早期に把握しやすくなります。加えて、委託契約の段階で情報漏えいや事故発生時の責任分担を明確に定めておくことも、リスク管理の観点から有効です。
こうした対応を通じて、金融機関とベンダーの間に明確な役割分担と責任範囲を確保することが重要になるでしょう。
最後に、金融システム自体の設計・開発段階からセキュリティを意識した対応を組み込むことが必要です。これを「セキュリティ・バイ・デザイン(Security by Design)」と呼び、近年では国際的にも重要視されています。この考え方に基づき開発初期から脆弱性対策を意識することで、後の対応コストを抑えられるでしょう。
例えば、アクセス制御の厳格化・通信の暗号化・ログの記録と監視体制の整備などを開発段階から組み込むことが求められます。また、開発後にも継続的に脆弱性診断やペネトレーションテスト(侵入試験)を実施し、問題の早期発見と対応に努めることが重要です。
こうしたセキュリティ設計は、システムの可用性や信頼性を支える基盤となるものであり、結果として利用者の安心感にもつながっていくでしょう。

デジタル技術の進展とともに、金融業界におけるDX(デジタルトランスフォーメーション)の重要性は急速に高まっています。業務の効率化や新たな顧客体験の創出だけでなく、サイバーセキュリティの強化にも大きく寄与している点が注目されているからです。
ここでは、金融DXを推進することで実現可能となる5つの具体的なサイバーセキュリティ対策について詳しく見ていきましょう。
DXの進展によりセキュリティ監視体制のリアルタイム化が実現しつつあります。これは、攻撃の兆候を迅速に検知し、対応までの時間を短縮するうえで有効です。
従来の金融システムでは、インシデント発生から対応までに時間差が生じることが少なくありませんでした。これに対し、AIによるログ解析やSIEM(セキュリティ情報イベント管理)ツールを導入すると、異常なトラフィックやアクセスをリアルタイムで分析できる体制が整うのです。具体的に、ネットワーク内で発生するデータ通信を常時モニタリングし、不審な動きがあれば即座にアラートを出す仕組みを整えます。
このようなリアルタイムの対応力を強化することは、被害の拡大を未然に防ぐうえで欠かせない取り組みだといえるでしょう。
金融DXによってID管理やアクセス制御の仕組みを高度化できる点も大きな利点の1つです。特に、クラウドサービスの利用が進む中で境界の曖昧なネットワーク環境におけるアクセス管理の重要性が増しています。
社員だけでなく業務委託先や外部ベンダーのアクセス権限も含めて厳格に管理するためには、IDaaS(Identity as a Service)の導入が効果的です。これは、個人ごとにアクセスできるシステムやデータを細かく制御し、不正アクセスを防止する仕組みとなっています。
加えて、認証手段として多要素認証(MFA)を採用することでなりすましなどのリスクを低減する効果も期待できるでしょう。
組織内においてセキュリティポリシーを統一し、かつ運用の自動化を図ることは人的ミスや運用のばらつきを抑えるために重要です。DXを推進すると、こうした統一的なセキュリティ管理が可能になります。
例えば、クラウドベースのポリシー管理ツールを活用すると、ネットワーク設定やアクセス制限の方針を一元的に適用することができます。また、一定の条件下で自動的にルールを更新したり、違反が検知された際に即座に修正が入ったりするような設計も可能です。
このように組織全体で共通のセキュリティポリシーを徹底できる環境を整えることで、内部統制の強化にもつながっていくと考えられます。
近年注目されている「ゼロトラスト」は、あらゆるアクセスを信頼しないという前提に基づき、継続的に検証・監視を行うセキュリティアーキテクチャです。金融DXの一環としてこのモデルを導入することで、境界型セキュリティでは防ぎきれない脅威にも対応できる体制が築かれます。
ゼロトラストでは、ユーザーの身元や端末の状態やアクセス先のデータの機密性などを総合的に判断し、アクセス可否を動的に制御します。加えて、マイクロセグメンテーションと呼ばれる手法により、ネットワーク内の通信経路を細かく分離し侵入後の横展開を抑制する効果も見込めるでしょう。
これにより、仮に不正アクセスが発生しても、被害の範囲を限定的にとどめられるのです。
AI(人工知能)の活用は、サイバーセキュリティの分野でもその効果を発揮し始めています。金融DXによってAIを取り入れることで、従来のパターンマッチングでは検知が難しかった未知の脅威に対しても柔軟かつ先回りした対処ができるのです。
具体的には、機械学習を活用して大量の通信ログや操作履歴を分析し、通常とは異なる挙動を自動で検出します。深夜帯に発生した通常業務では考えられないデータ送信や、複数の端末からの不自然なログインなどが該当します。
こうした異常を早期に察知し、システム担当者へ通知したり自動的にアクセス制限をかけたりすることで、被害発生の前段階で対処できるようになるでしょう。
金融DXの導入は、外部からの脅威だけでなく、内部不正の防止にも有効です。特に注目されているのが、業務ログの可視化によって社員の操作履歴を監視し不正行為を未然に防ぐ取り組みです。
従来のシステムでは、誰がいつどの業務を実行したのかを正確に把握することが難しいケースもありました。しかし、DXの進展により、業務システムやクラウドサービス上の操作履歴を詳細にログとして記録・管理する仕組みが整ってきています。この仕組みが整うと、特定の顧客データへのアクセス履歴やシステム管理者による設定変更の履歴などを時系列で把握できるようになります。
業務の透明性が高まることで、「いつでも見られている」という意識が社員に浸透し、不正行為を思いとどまらせる心理的な抑止効果が出てくるでしょう。さらに、万が一不正が発生した場合でもログから証拠をたどることで迅速な原因追及と対処ができるのです。
金融機関がサイバーセキュリティ対策を強化するためには、信頼性の高いツールの導入が効果的です。ここでは、Microsoft社の「Microsoft Defender for Endpoint」とPalo Alto Networks社の「Prisma Cloud」について解説します。
Microsoft Defender for Endpointは、エンドポイントのセキュリティを強化するための包括的なソリューションです。Windows・macOS・Linux・Android・iOSなどさまざまなプラットフォームに対応しており、企業の多様なデバイス環境を保護します。
主な特徴として、以下の点が挙げられます。
これらの機能により、企業はサイバー攻撃に対する防御力を高め、迅速な対応が可能となるでしょう。
Prisma Cloudは、クラウド環境におけるセキュリティを包括的に提供するプラットフォームです。AWS・Azure・Google Cloud・Alibaba Cloudなど主要なクラウドサービスに対応しており、企業のクラウドセキュリティを強化します。
主な機能として、以下が挙げられます。
Prisma Cloudの導入により、企業はクラウド環境全体のセキュリティを可視化しリスクを最小限に抑えられるでしょう。
金融DXとサイバーセキュリティの両立に課題を感じている企業にとって、専門的な支援を受けることは効果的です。『株式会社 TWOSTONE&Sons』は、金融業界に特化したDX推進とサイバーセキュリティ対策の豊富な実績を持ち、企業の課題に対して多角的なソリューションを提供しています。
同社では、企業の現状を丁寧に分析しそれぞれに最適化されたDX戦略の立案と実行を支援するほか、最新のセキュリティツールの導入支援やセキュリティポリシーの策定を通じてセキュリティ体制の強化を図ります。
これらの支援を受けることで、企業は金融DXとセキュリティ対策を同時に推進し、競争力と持続的な成長を両立できるのです。
専門的な知見と実績に裏打ちされた『株式会社 TWOSTONE&Sons』のサービスを活用し、貴社のサイバーセキュリティ対策と金融DX推進を同時に進めましょう。

金融業界におけるサイバーセキュリティ対策は、企業の信頼性を高めて競争力を維持するために不可欠です。
Microsoft Defender for EndpointやPrisma Cloudなどの先進的なツールを活用することで、セキュリティ体制を強化できます。また、『株式会社 TWOSTONE&Sons』のような専門企業の支援を受けることで、金融DXとサイバーセキュリティの両立を効果的に進めることが可能です。
これらの取り組みにより、企業は変化の激しい金融業界において持続的な成長と顧客の信頼を確保できます。顧客の信用を得るためにも、サイバーセキュリティ対策を見直しましょう。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
