金融DXの推進によって叶う勘定系システムの刷新|4つの取り組み例を紹介
金融

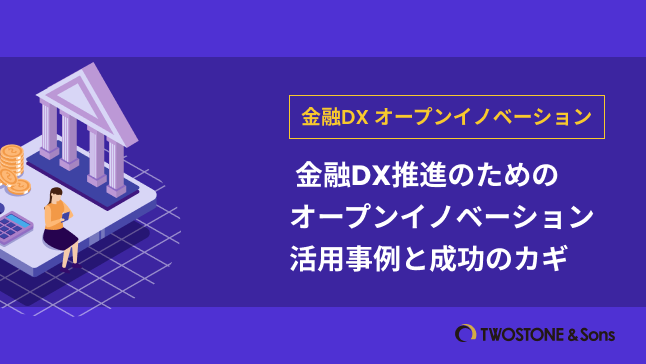
近年、金融業界では「デジタルトランスフォーメーション(DX)」という言葉を目にする機会が増えてきました。紙ベースの業務から脱却し顧客体験の向上や業務の効率化を図る動きは、多くの金融機関にとって避けられないテーマとなりつつあります。しかし、DXを進めようとしても、自社だけのリソースでは限界を感じる場面もあるのではないでしょうか。
そんなときに注目されているのが「オープンイノベーション」の活用です。これは、社外の技術やノウハウを取り入れることでスピーディかつ柔軟にDXを進める手法です。
この記事では、金融DXとオープンイノベーションの関係をわかりやすく整理しながら、なぜ今この組み合わせが必要とされているのかを明らかにします。読み進めることで、金融業界でDXを成功させるための考え方や具体的な進め方、さらには有効な外部支援の活用法まで理解できるでしょう。

金融DXを単独で推進しようとすると、既存のシステムや文化が壁となり思うように前進できないケースがあります。こうした課題に対して、オープンイノベーションは突破口になりうるでしょう。
ここでは、金融DXについて解説した後、金融DXとオープンイノベーションがどのように関係しているのかを説明します。
金融DXとは、金融業界においてデジタル技術を活用し業務やビジネスモデルを根本から変革する取り組みのことです。これには、単なる業務のデジタル化を超えて、顧客との関係構築やサービスの再設計、データ利活用による経営判断の高度化などが含まれます。
特に近年では、スマートフォンやクラウドサービス・AI・ロックチェーンなどの技術進展により、これまで不可能だったサービスが実現できるようになりました。これに伴い、顧客の期待値も変化しています。金融機関には、これまで以上にスピード感と柔軟性が求められるようになってきました。
このような環境の中で、いかにして変革を進めるかが問われています。そこで有効な手段の1つが、外部との連携を通じて新しい価値を生み出す「オープンイノベーション」です。
オープンイノベーションとは、自社だけでなく、他社やスタートアップ・学術機関・行政など外部の組織と連携して新たな価値を創出する取り組みです。新しい技術やアイデアをスピーディに取り込める点が特徴です。
特に金融業界では、テクノロジーの進化が速く内製にこだわっていては時代の変化に追いつけないリスクがあります。だからこそ、外部との協働を前提としたイノベーションがカギとなるのです。
理由の1つは、急速なテクノロジーの進展により競争環境が劇的に変化していることです。フィンテック企業の台頭や異業種からの参入が進む中、既存の金融機関も俊敏に対応する必要があります。
さらに、顧客ニーズが多様化・高度化していることもオープンイノベーションを求められる理由です。これまでの画一的なサービスでは満足されにくくなっており、個別ニーズに応じた柔軟なサービス提供が求められています。このような環境では自社リソースだけでは対応が難しい場面が多くなるため、外部の知見や技術力を取り入れるオープンイノベーションが有効とされるのです。
また、法規制やセキュリティ要件が厳しい金融業界においては専門知識を持つ外部パートナーの存在がプロジェクトの成否を左右することも少なくありません。そのため、信頼性のあるパートナー選びも成功への重要な要素となるでしょう。
金融DXを加速させるには、自社の枠を越えた発想と仕組みが必要です。そこで注目されるのが「オープンイノベーション」という考え方です。
金融業界では、顧客ニーズが多様化しテクノロジーの進化も速いため、スピーディな対応が求められています。ここでは、オープンイノベーションによって金融機関が実現できる5つのことについて具体的に紹介していきます。
1つ目は、スタートアップとの協業によって既存にはない新しいサービスを創出できる点です。スタートアップ企業は最新のテクノロジーや斬新なビジネスモデルを持っていますが、実証の場や信頼性を必要としています。一方、金融機関は信頼やインフラを持っていますが革新のスピードには限界があります。この両者が連携すれば、それぞれの強みを活かしながら短期間で価値あるサービスを形にできるでしょう。
例えば、スマートフォンから口座開設やローン申請が完結するモバイルバンキングサービスは、こうした協業の成果として知られています。スタートアップが持つUI/UX設計力と金融機関のノウハウを組み合わせることで、顧客にとって直感的で使いやすいサービスを提供できているのです。
次に、企業外の技術や発想を取り入れる「アクセラレーションプログラム」や「オープンコール」などの仕組みを活用する方法があります。これらは、広く社会に向けて課題やテーマを提示し解決策を募集する形式で進められます。
金融機関が抱える課題は、システムの老朽化からカスタマーサポートの効率化まで多岐にわたるでしょう。こうした課題に対し、外部の技術者や企業が独自の視点からソリューションを提案することで従来では考えられなかった選択肢が見えてくるのです。
プログラムの運営には一定の準備が必要ですが、社内にない視点を取り入れることで革新的なプロジェクトの種が生まれやすくなります。また、参加する外部パートナーにとっても金融業界の知見に触れる機会となり、双方にとってのメリットが期待できるでしょう。
フィンテック(FinTech)企業との連携もオープンイノベーションの代表的な形の1つです。フィンテックは、「金融(Finance)」と「技術(Technology)」を組み合わせた言葉で、デジタル技術を用いて新しい金融サービスを提供する企業を指します。
近年では、AIによる資産運用支援やチャットボットを使ったカスタマー対応、ブロックチェーンを活用した送金システムなどフィンテックによる進化が目覚ましい状況です。これらを自社単独で実現しようとすると時間もコストも膨大にかかる可能性があります。
そこでフィンテック企業と協業することによって、スピード感を持って新機能を取り入れられるようになるでしょう。特に顧客接点の改善やアプリの使いやすさを向上させる領域では、フィンテックの知見が大いに役立ちます。
金融業界に限らず、異業種と連携することで新たな市場を切り開く取り組みも進んでいます。これにより、金融サービスの提供方法自体が変わりつつあるのです。
例えば、自動車メーカーと金融機関が連携して車両購入時のローンや保険をワンストップで提供する仕組みを構築したり、不動産業界と連携して住宅ローンだけでなく物件選定から契約までを一括サポートしたりするサービスを開発した例も見られます。
こうした異業種連携は単なる業務提携ではなく、利用者視点での利便性向上や新たなライフスタイルの創出につながるのです。業界の枠を超えた発想が、従来型の金融サービスに変化をもたらすきっかけとなるでしょう。
最後に挙げるのは、「ハッカソン」や「アイデアソン」といったイベントの開催です。これらは、特定の課題やテーマに対して多様な背景を持つ人材が短期間でアイデアを出し合う場のことです。
これらのイベントでは、社内の若手社員だけでなく外部のクリエイターや開発者、ユーザーも参加することができます。その結果、従来の業務プロセスでは生まれにくいアイデアや視点が出てくる可能性が高まります。
また、イベントを通じて優秀な人材と出会う機会が増えることも利点です。人材確保が課題となっている金融業界にとって、こうしたオープンな場づくりは、次世代のサービス開発に向けた重要なステップとなるでしょう。
オープンイノベーションは、金融業界でも注目されている取り組みの1つです。多くの金融機関がスタートアップや異業種と協力しながら新たな価値創造に挑んでいます。
ここでは、オープンイノベーションを積極的に導入している日本の主要な金融グループの事例を紹介します。
三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)は、オープンイノベーションを通じて新規事業の創出を目指す取り組みに力を入れています。その一環として「MUFG INNOVATION PARTNER」プログラムを展開しています。
このプログラムの特徴は、スタートアップとの共創によって新たな価値を見出そうとしている点です。企業が抱える課題を明確にし、それに対して最適な外部パートナーを募る仕組みが整えられています。金融業界に限らず幅広い業種のスタートアップと協業することで、従来の枠組みにとらわれないアイデアが生まれやすくなるのです。
例えば、ブロックチェーンやAI技術を活用した新サービスの開発を行うなど先端テクノロジーを積極的に取り入れています。このような取り組みから、MUFGは「共創型」の姿勢を明確に打ち出し、柔軟な発想を重視する企業文化の構築を進めているのです。
三井住友フィナンシャルグループ(SMFG)もオープンイノベーションに注力している代表的な金融機関の1つです。特に「SMBCグループ×スタートアップ共創プログラム」では、金融サービスの枠を超えた新しいビジネスの可能性を模索しています。
このプログラムは課題解決型のアプローチが特徴です。例えばキャッシュレス化の加速やサステナブルファイナンスへの対応など、社会的な課題を念頭に置きながら共創テーマが設定されています。SMFGは、これらのテーマに対して社内外の知見を融合し、新しいサービスのプロトタイプ作成や実証実験に取り組んでいるのです。
また、社内の新規事業創出支援プラットフォームも整備されており、社内のイノベーションを支える体制も強化されています。このように、SMFGはオープンイノベーションを単なる外部連携にとどめず、企業全体の競争力向上に結びつけているのです。
住信SBIネット銀行は、デジタルバンクとしての強みを活かしてオープンイノベーションを推進しています。
「NEOBANK」ブランドを中心に展開される銀行サービスでは、他業種との連携が盛んに行われています。異業種の企業とAPIを通じて連携しそれぞれの顧客基盤やサービスを活用することで、これまでにない金融サービスの提供ができるのです。
また、住信SBIネット銀行は「Service Innovation Lab」を通じて、FinTech企業や学術機関との共同研究にも取り組んでいます。こうした研究開発活動では、単なる新機能の追加にとどまらずユーザー体験全体を最適化するようなアイデアが生まれやすくなっています。
このように、技術と実行力の両面からオープンイノベーションを進める住信SBIネット銀行は、従来の銀行像を塗り替える存在として注目されているのです。
参考:住信SBIネット銀行
みずほフィナンシャルグループもまた、オープンイノベーションを通じた変革に取り組んでいます。同社は「Mizuho Innovation Lab」や「Mizuho Innovation Award」など、複数の施策を通じて社外との協業を積極的に展開しています。
特に注目されるのが、スタートアップ企業の技術力とみずほグループが持つ金融知見の融合を目指す姿勢です。例えば、ブロックチェーンを活用した取引の効率化やESG投資に関する新しい指標の開発など、社会的意義のあるテーマに重点を置いた協業が進んでいます。
また、同社では社員のイノベーション意識を高める社内教育やアイデアコンテストも開催されています。こうした取り組みによって、オープンイノベーションが一部の部門に限らず、全社的な活動として定着しつつあるのです。
みずほフィナンシャルグループは、オープンイノベーションを通じて顧客ニーズの変化に柔軟に対応しつつ、社会課題の解決にも貢献することを目指しているのです。
オープンイノベーションを効果的に導入するには単に外部と連携すればよいというわけではありません。社内外のリソースを活用しながら、継続的に新しい価値を生み出せる仕組みが求められます。
ここでは、オープンイノベーションを進める上で注目されている5つの実践的な取り組みについて紹介します。
新たな技術や発想を取り入れるためには、外部との連携が大切です。その中でもスタートアップ企業や専門家との協力は、スピード感と柔軟性のあるプロジェクトを生み出す上で欠かせません。
例えば、AIやブロックチェーンのような先端技術を活用した新サービスを開発する際には、自社だけで技術を獲得・育成するよりも既にノウハウを持つ外部と連携した方が効率的です。こうした連携は、双方にとっての価値創造につながる関係となるでしょう。
特に金融業界では厳しい規制と高度な専門性が求められるため、特定分野に強みを持つスタートアップの技術と知見は貴重な資産となります。
オープンイノベーションを社内で推進するには、社員からのアイデアを吸い上げる仕組みの整備が欠かせません。これは、イノベーションの芽を見逃さないために重要なアプローチといえるでしょう。
社内コンテストやアイデア投稿制度などの導入は効果的です。社員が日々の業務の中で感じた課題や改善点を共有できる環境が整えば、思いがけない発見やヒントが集まるようになるでしょう。
さらに、投稿されたアイデアを評価・検証するプロセスを設け、実行可能性のあるものについては試験的に実施する仕組みも必要です。このように、社内からの提案を組織的に活用することで、内発的なイノベーションの流れを作り出せるでしょう。
若手社員の柔軟な発想や新しい価値観はオープンイノベーションの重要な資源となるでしょう。変化に敏感な世代の意見を取り入れることで、今の時代に即したサービス設計や改善が行いやすくなります。
例えば、Z世代のライフスタイルや価値観を取り入れた金融サービスの開発においては、同世代の意見が不可欠です。社員の視点からは既存の仕組みがどのように見えているのか、どのような点が改善されるべきかといった実感に基づいた意見が得られるでしょう。
そのためには、発言しやすい風土づくりや年齢や立場に関係なく意見を尊重する企業文化の醸成が重要です。単に意見を聞くだけでなく実際にプロジェクトに参画させることで、より実効性のある取り組みに発展させやすくなります。
オープンイノベーションを導入する際には、まず小規模なプロジェクトから試しましょう。いきなり全社レベルでの展開を目指すよりも、限られたリソースで素早く試行錯誤できる環境を整える方がリスクも抑えられます。
例えば、特定の顧客層向けに新しいサービスモデルを試験的に導入し、その反応を測定するなどの取り組みが挙げられます。ここで得られたデータやフィードバックは今後の本格的な展開に向けた貴重な判断材料となるでしょう。
また、こうした小規模プロジェクトは失敗に対する心理的ハードルも下がるため、チャレンジ精神を育てやすいという利点もあります。成功事例が積み重なれば、社内の信頼も高まり、次第に規模の大きなプロジェクトへと移行しやすくなります。
他の業界との交流は、自社にはない視点や手法を学ぶ上で有益です。金融業界にとっては、IT・医療・小売など他の分野の課題に対するアプローチから多くの示唆が得られるでしょう。
例えば、小売業界では顧客体験(CX)を重視したデジタル施策が進んでおり、金融業にも応用可能な要素が含まれています。こうした業界横断的な学びは新たなサービス設計や業務効率化のヒントになるでしょう。
実際に、業界を超えた共創イベントやセミナーや連携プログラムなどを通じて知見を深める企業が増えています。情報共有を通じて得られた気づきは今後のイノベーション活動の土台となることでしょう。

金融業界では、DX(デジタルトランスフォーメーション)を進める上で、オープンイノベーションの考え方が有効だと注目されています。
ここでは、その理由を5つの視点から解説していきます。
金融DXの要となるのは、AI・ブロックチェーン・クラウドコンピューティングなどの先端技術です。これらを自社内だけで開発・導入するには膨大な時間とリソースが必要になります。その点、オープンイノベーションを活用すれば既に専門技術を持つスタートアップ企業や研究機関と連携でき、効率的に最先端技術を取り入れやすくなるでしょう。
例えば、フィンテック企業との協業により、既存の銀行システムにAIによる審査機能をスムーズに統合できた事例もあります。外部との連携を通じて技術導入のスピードを高めることが、金融DXの推進に直結するでしょう。
社内だけの視点ではどうしても固定概念にとらわれがちです。しかし、オープンイノベーションの導入によって業界外や異なる分野の専門家の知見を取り入れることができれば、柔軟な思考と新しい視点がもたらされるでしょう。
例えば、ユーザー体験に精通したデザインファームと協力し金融アプリのUI/UXを刷新した結果、若年層の利用者が増えたケースもあります。外部の知見を加えることでこれまで見過ごされていた課題にも気づきやすくなり、継続的なサービス改善につながるでしょう。
オープンイノベーションは、単なる技術導入にとどまらず企業文化や組織体制の見直しにもつながります。これにより、今後長くイノベーションを生み出す土壌が整い、中長期的には企業の競争力強化に寄与する可能性が高まるでしょう。
社内にアイデア提案制度を設け、外部のパートナーと連携した実証実験を積極的に行うようになれば、社員の主体性が育まれます。結果として、スピード感ある意思決定や柔軟な組織運営が可能になり、他社との差別化を図れるのです。
金融業界は、これまで堅いシステムと規制環境の中で発展してきましたが、近年はライフスタイルの多様化に伴い、金融の枠を超えたサービス展開が求められるようになっています。オープンイノベーションによって異業種との連携が進めば、金融サービスのあり方そのものが変わる可能性も見えてくるでしょう。
例えば、小売業と提携してポイントサービスを金融口座と連携させる、健康管理アプリと保険サービスを組み合わせるなどこれまでにないサービス設計が可能になります。このように他の業界との協働によって、生活全体に密着した新たな金融の価値が生まれるのです。
金融DXの推進には、セキュリティや規制対応といった複雑な課題が伴います。それらの問題に対処するためにもオープンイノベーションが有効です。なぜなら、複数の視点を取り入れることで潜在的なリスクや盲点に早期に気づき、対処しやすくなるからです。
また、外部の専門企業と協働すれば、リスクマネジメント体制の強化や法令遵守の仕組みづくりがよりスムーズに進むでしょう。問題発生時の対応も迅速に行えるようになり、結果として金融DX全体の推進力が高まるのです。
金融DX(デジタルトランスフォーメーション)を本格的に推進するためには、単に最新技術を導入するだけでなく、それらを業務にどう組み込むかを考える必要があります。特に、クラウド技術やAI、API、モバイルアプリなどの活用は業務の効率化と顧客満足度の向上の両面で効果を発揮するでしょう。
ここでは、金融機関がDXを推進するための具体的な手法と、それによって得られるメリットを紹介します。
DXの基盤を支える技術としてクラウドコンピューティングは欠かせない存在です。従来のオンプレミス型システムでは、システムの拡張や保守に多くの時間とコストがかかっていました。クラウドを活用すれば業務の拡張性や柔軟性が向上し、変化に迅速に対応しやすくなるでしょう。
例えば、繁忙期にはサーバー容量を一時的に拡張し、閑散期には縮小するようなリソースの調整が容易になります。また、クラウド上で業務データを管理すれば在宅勤務や出張先からでも安全に業務を遂行しやすくなるため、柔軟な働き方も促進されるでしょう。
金融業界では、口座の開設やローンの申し込みやサービス内容に関する質問など、顧客からの問い合わせが日常的に発生しています。これに対してAIチャットボットを導入することで、24時間対応が可能な自動応答システムを構築できるでしょう。
実際に、よくある質問に対して即座に回答できるチャットボットを設置した結果、オペレーターの負担を軽減しつつ顧客満足度を維持できたという事例もあります。さらに、AIによる自然言語処理の精度向上により、顧客とのコミュニケーションの質も向上するでしょう。
現代の消費者は、銀行窓口に足を運ぶよりもスマートフォンを使って手続きを済ませる傾向が強くなっています。そのため、モバイルアプリの開発と活用は顧客接点を増やす有力な手段といえるでしょう。
例えば、残高照会や振込操作をアプリで簡単に行えるようにしたりAIによる家計簿機能を付け加えたりすることで、顧客の日常生活に密着したサービスを提供しやすくなります。こうしたアプリの利便性は継続的な利用につながり、結果的に顧客ロイヤルティの向上にも貢献するでしょう。
API(アプリケーション・プログラミング・インターフェース)は、異なるシステム同士を接続するための仕組みであり、オープンバンキングを支える基盤でもあります。APIを活用することで、金融機関は外部のサービスと柔軟に連携し、新たな付加価値を生み出しやすくなるでしょう。
例えば、フィンテック企業の家計管理ツールと連携すれば、顧客は自身の金融情報を一元管理できるようになり利便性が大きく高まります。またローン審査や与信判断においても、複数の外部データと合わせることで精度の高いサービス提供が可能になると考えられます。
これまで金融商品の申し込みや契約には、紙の書類を用いた手続きが一般的でした。しかし、電子契約やデジタル署名を取り入れることでオンライン上で完結する手続きが実現し、顧客にとっての利便性が向上しやすくなるでしょう。
今では、証券口座の開設手続きをオンライン上で行えるようにして数分で完了させるサービスを提供する企業も増えています。こうした仕組みによって時間や場所に縛られず契約が行えるようになり、利用のハードルが下がることで新規顧客の獲得にもつながるのです。
金融機関においては、事務処理やチェック業務など定型的なタスクが多く存在します。これらの業務を自動化するためにRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)などの技術を活用すれば、人材不足の解消に向けた有効な手段となるでしょう。
例えば、口座開設後の顧客情報の登録作業や定期的な与信データのチェックといった業務をRPAで処理することで、ミスの軽減や処理時間の短縮が可能になります。これにより、社員はより高度な判断や顧客対応に集中できるようになり、業務全体の効率と質が向上するでしょう。
金融DXを効果的に推進していくためには、単にテクノロジーを導入するだけでは十分とはいえません。組織全体のシステム構造や法規制、外部との連携、そして顧客との信頼関係を見据えた慎重な設計と運用が求められます。
ここでは、金融DXを進める際に注意すべきポイントを紹介します。
新たなデジタル技術を導入する際、既存の基幹システムとの連携を無視してしまうとデータの分断や業務の停滞を引き起こしかねません。特に金融業界では、長年にわたって使われてきたオンプレミス型のシステムが多く存在しており、その資産を無理に捨て去るのは難しいでしょう。
このため、クラウドサービスやAPI連携を導入する際には、既存システムの仕様やデータ構造を正確に把握した上で段階的な移行計画を立てる必要があります。システム間の橋渡しを担う「ミドルウェア」の活用も、スムーズな連携を図る手段の1つといえるでしょう。
金融サービスは常に高いレベルのセキュリティと法令遵守が求められる分野です。DXの推進においても、これらの要件を満たすことが前提となります。特に、個人情報や取引データを扱う際は情報漏えいのリスクを最小限に抑える設計が不可欠です。
クラウドサービスを利用する場合、データ暗号化やアクセス制御の設定が適切に施されているか、第三者認証を受けたサービスかどうかを確認することが重要です。また、金融庁のガイドラインやFISC安全対策基準など業界特有のルールを理解し、それに則った運用体制を構築しておく必要があるでしょう。
DXを内製だけで完結させるのは困難なケースが多く、SIerやクラウドベンダー、デザイン会社など外部の専門企業と連携する場面が増えてきます。しかし、関係者が増えるほど責任の所在が曖昧になりやすく、トラブルの元になりかねません。
こうした事態を防ぐためには、プロジェクト開始段階で明確な役割分担を文書化し、合意を取ることが重要です。誰が要件定義を行うのか、セキュリティ設計はどこまで担保されるのか、運用開始後の保守は誰が担当するのかといった点を明確にしておくことで、スムーズな連携とトラブルの回避ができるでしょう。
データ分析による経営は、金融サービスを目指す上で蓄積された顧客データを活用することは有効な戦略といえます。しかし、顧客からの信頼を損なわないためにはデータの扱い方に関する透明性が極めて重要です。
例えば、個別のニーズに対応したレコメンド機能を導入する場合、どのような情報をもとに提案がされているのか、ユーザー自身が理解しやすい説明が求められます。また、プライバシーポリシーの明確化やデータ提供の同意取得プロセスを整えることも、信頼構築には欠かせません。データの収集・解析・活用という一連の流れを倫理的かつ公正に運用していく姿勢が今後さらに求められていくでしょう。
『株式会社TWOSTONE&Sons』では、企業のDX推進を支援する幅広いサービスを展開しています。金融機関に求められる高いセキュリティ基準に対応した開発体制を整え、クラウド導入から業務設計、プロダクト開発、内製化支援までを一貫してサポートします。
システム開発とデザインの両輪で貴社の金融DXを着実に推進するための最適なパートナーとなるでしょう。金融DXの推進やオープンイノベーションの活用でお悩みの方は、一度ご相談ください。

金融DXを成功に導くには、最新技術の導入と同時に柔軟で戦略的な体制構築が求められます。そのためには、自社単独での取り組みにこだわらず、外部パートナーと連携する「オープンイノベーション」の考え方が不可欠です。
今こそ業界の常識を打ち破り、顧客視点での価値提供を強化していく一歩を踏み出しましょう。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
